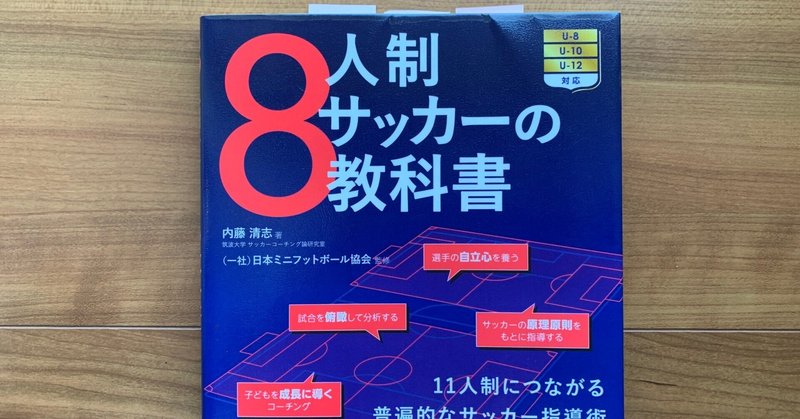
固定観念から自由になることの大切さを教えてくれる『8人制サッカーの教科書』
この本はプロジェクトに取り組む人にとって、プロジェクトの設計力を鍛えるための良い気づきや視点を与えてくれる――。
本書を読み始めてすぐ、このように直感しました。
私はルーティンワークではない、新しい仕事に他者と協力して取り組むための考え方や方法を身につけるための企業研修を行っています。新しい仕事には新規事業、新製品開発といったものの他、新制度やツールの導入などもあります。また、既存の製品や体制を変革・改善するといった仕事もあります(ここでは、これらの仕事をひっくるめて「プロジェクト」と言います)。
研修内容を考えるにあたり、受講者が楽しんで取り組める「仕事の練習メニュー(トレーニング)」を考案する参考になるかもしれないと思い、本書を手に取りました。申し遅れましたが、私はサッカーの指導者でも趣味でサッカーをすることもない、ただのサラリーマンおじさんです。
チームづくりにもトレーニング計画づくりにも共通する「設計」のテンプレート
プロジェクトに取り組むには、与えられている条件のもと、プロジェクトを構成する要素を見つけてあれこれ組み合わせ、姿かたちのない未来の目標を実現するための「設計」を行う必要があります。
このように書けば、自分が指導するチームを上のカテゴリーに昇格させるということや、プレーモデルをチームに落とし込むための練習メニューを計画するということや、選手一人一人を上達させるということも、設計の対象といえるのではないでしょうか。
研修では設計を行いやすくするためのフレームワーク「プロジェクト譜(略して「プ譜」)」を提供しています。

自分のプロジェクトの設計図をプ譜で書くのが研修のゴールなのですが、その過程でプ譜を用いたプロジェクトの原理原則を知り、プロジェクトを進めていくうえで必要な思考を鍛えるドリル(机上演習)をいくつか出します。
サッカーでいえば、ピッチ上に選手やボールやゴールを配置した図を描き、「このようなシチュエーションのときどう動く?」「どこにパスする?」という問題のようなものです。
8人制サッカーの教科書を題材にしたプロジェクトドリル
本書に書かれていた8人制サッカーの生まれた背景や目的が、まさにプロジェクトの原理原則を知り、設計に必要な考え方を練習する題材になると感じ、つくってみたのが下記のドリルです。(※サッカー指導者や経験者の方にとっては簡単・自明のドリルですが、このドリルはサッカー指導者ではない人向けにつくっています)

シチュエーション:
あなたは日本全国の小学生世代を指導するサッカー組織の責任者に抜擢されました。子どもたちが上の世代にあがって最終的には世界でも通用するための、サッカーの「本質」を子どもたちに身につけさせる指導者向けのプログラムを考えたり、サッカーをする環境を整備したりするのが任された仕事です。
サッカーの本質には、「相手との駆け引き」や「味方との意思疎通」、「ピッチ上の自分と味方、相手の位置関係の把握」や「局面局面での意思決定」、「責任感」や「リスクを冒す勇気」といったものがあります。これらを身につけるには、子どもたちができるだけ多く試合に出場し、一試合の中でできるだけ多くボールに触り、攻守にわたってプレーに関与する回数を増やすことが必要です。
しかし、実際のところ試合に出られるのはうまい子どもに限られていて、チームに所属する子ども全員が出場できていないのが実情です。
このような状況を創り出すために、どのようなことをすればいいでしょうか?
回答:
思いつく方法を施策欄に書き込んで下さい。
書いた施策がどの中間目的に影響を与えるのかがわかるように、関係する施策と中間目的間に矢印線を引いて下さい。
1つの施策からつなげる中間目的は複数あってもかまいません。

問題が難しい場合は、下図に書き込まれた施策から必要と思われるものを選び、その施策が影響を与える中間目的に矢印線をつないでください。

ドリルの解説
以上がこのドリルの出題文と図です。これを私が研修で出題するときには、事前に3つのことを伝えます。
施策は実行する数だけ労力・お金・時間がかかるので、少ないに越したことはないということ。
廟算八要素の「外敵」にはプロジェクトの障害になりそうな人や組織だけでなく、思い込みや固定観念もあるということ。
プロジェクトの原理原則として、「プロジェクトを構成する要素のすべてが絶対不変ではない」ということ。
この3点を伝えることで、自分が抱いている「サッカーとはこういうものだ」という思い込みから自由になり、「どの要素なら変えられるか?」ということを考えるよう促していきます。
そうすると他のスポーツを参考にしたアイデアが出てきます。バスケットボールの選手が何度でも交代していいルールやバレーボールの1プレーごとに選手の立ち位置(ポジション)を変える(選手が移動しなければならない)取り入れることで、ボールに触れる回数を増やすという要素に影響を与えられそうです。
ボールを2個使うというアイデアはどちらのボールを追えばいいかわからなくなるのと、審判を増やさないと危ないプレーを止めることができません。審判が増えれば人件費がかさんでしまいます。プロジェクトでは経済性を考慮する必要があります。この点ではコートをたくさん用意するというアイデアも建造費が増えてしまって不経済です。
ではどの施策が最も経済的に各要素に良い影響を与えるかというと、本書のテーマである8人制サッカーの基本ルールである「コートのサイズを狭くする」になります。

そして、施策を例示したプ譜では記載しなかった「一度に出場する選手の人数を11人から8人に減らす」を加えます。

8人制サッカーの利点
「コートのサイズを狭くする(半分にする)」と「一度に出場する選手の人数を11人から8人に減らす」。これが8人制サッカーの基本フォーマットです。
8人制サッカーのコートサイズは68m x 50m で大人のちょうど半分のサイズです。サイズが狭くなることでこれまでの倍のコートを労せずして確保できます。これにより、まず試合に出られる子どもの数が増えます。人数を減らすことで「ボールに触れる回数」と「プレーに関わる回数」も増えます。
この2つの要素の数が増えることで、意思決定を行う回数も増えていきます。プ譜の世界では施策が直接的にプロジェクトの構成要素(中間目的)に影響を与えるものもあれば、施策は直接的に影響を与えられないものの、ある構成要素が別の構成要素に影響を与えるケースを、中間目的間に赤い点線を引いて表現します。
コートサイズを狭くする施策と人数を減らす施策は、「然るべきときにリスクを冒せている」や「責任感が身についている」という要素に直接的には影響を与えられないと考え、これらの間には線を引いていません。その代わり、 「ボールに触れる回数」と「プレーに関わる回数」から赤い矢印点線を引いてこの理屈を表現しています。以上が本書の説く8人制サッカーの利点です。
8人制サッカーが導入された背景とその効果を読んで、この一手は高額の設備投資をすることなく、コートを半分にしてプレーヤーの人数を減らすだけで問題を解決できている素晴らしい事例だと感じ入りました。
認知心理学の権威、佐伯胖先生の著書『「わかる」ということの意味』に、このような記述があります。
「わかっている」人というのは、与えられた問題の中のいくつかの項目を、自分で動かしてみている。問題の中で与えられた事態を、問題の制約の範囲内で変化させてみている。当面の事態の中で、自分なりに新しい探求目標を設定してみて、それを達成するためにはどうしたらよいかと考えている。
「わかっていない」人というのは、与えられた課題の中では何もかも与えられているとし、何も変えてはならず、問題として直接求められていること以外は何も求めてはいけないと思い込んでしまう。
したがって、答えを出すというのは、そういう世界の中での「正しい求め方」というものに正しくしたがって出すということ以外にありえないと思っている、
図らずも私はこの一節を本書を読んで思い出しました。
本書の巻末に収録されている著者の内藤氏と小野剛氏の対談では、日本サッカー協会が8人制サッカーを導入しようとしたとき、「サッカーは11人でやるものだ。人数を減らしてどうやってサッカーをやるんだ」「11人制になったときに戸惑うだろう」ということを指導者から言われたことが話されています。ここでも固定観念が外敵になっていたことがわかります。長年11人のサッカーに親しんできた指導者からすれば戸惑いも大きく、抵抗も強かったのではないかと思います。
しかし真の目的は8人制サッカーの上手な指導者を作りたいのではなく、子どもたちがサッカーの本質を理解し、より身につけ、体で理解できるようにするためです。
この本質を理解し、柔軟に対応できる人こそが「わかっている」人です。真の目的、勝利条件実現のために、固定観念や与えられている条件から意識的に自由になる。これは何もサッカー指導者に限った話ではありません。
一般企業の仕事の中にも、固定観念にとらわれて変化を起こせないという事例はくさるほどあります。
本書は8人制サッカーを指導する際のトレーニングメニューの解説などが多くを占めます(そりゃそうです)。しかし、8人制サッカーの導入背景や目的、効果を読むことは、サッカーとはまったく関係ない仕事であっても、固定観念から自由になることの力や重要さを教えてくれます。
直接的に仕事の問題を解決する方法を教えてくれる本ではありませんが
(そりゃそうです)、「固定観念から自由になれ!」と人から言われたり自分に言い聞かせたりするより、読むことでその大切さを実感できるのではないかと思います。
未知なる目標に向かっていくプロジェクトを、興して、進めて、振り返っていく力を、子どもと大人に養うべく活動しています。プ譜を使ったワークショップ情報やプロジェクトについてのよもやま話を書いていきます。よろしくお願いします。
