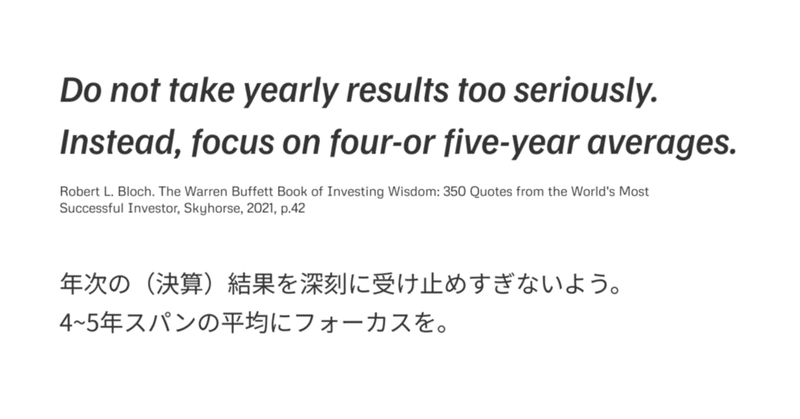
バフェット氏の言葉たち 4言目。
長期投資のスパンとは?
私たち株取引をしている人間は、短期、中期、長期という言葉を使っていますが、実は人によってその期間はまちまちです。
バフェット言う長期とは、どれくらいの期間なのでしょうか?
バフェット的な「長期」とは少なくとも10年は覚悟。
私たちが長期投資という場合「年単位でしょ!」となりがち。
それはまだまだ短いです。
1年で短期、5年で中期、10年でようやく長期です。それを念頭にもう一度今日の言葉を考察します。
年次はブレがある
企業が経済活動をするとき、商品が大ヒットすれば収入は増加しますし、保有する土地を売ったりしてもやっぱり収入は増えるわけです。
年次決算だとそういった「一時的な現象」が反映されやすいのです。
期間を延ばすとブレは小さくなる
一方4~5年程度のスパンですと「中期」くらいの感覚になります。臨時的な要素が全体に与える影響は小さくなります。
これは株価の移動平均線を想像するとわかりやすいでしょう。
日足と週足、週足と年足とスパンを広げていくに従って線の動きがなだらかになり、全体的な方向感が出てきますよね。そういうことです。
もう一つの意味
この言葉の前提には「目先の動向に惑わされるような投資はするな」という考えが裏にあります。
そのような考えが出てくる時点で銘柄選定が適切でない可能性が高いです。
では適切な銘柄選定とは?
銘柄選定は慎重に慎重を期すべし
よく「自分が応援したいと思う株を長期保有しなさい」と言われたりします。
私はその意見には反対です。
「自分が応援したいと思う株」という観点で取引するのは、初めて少額資金で株式を買って、試しにしばらく運用しつつ株取引を学んでいく、そのようなシチュエーションが適切です。
長期保有とは少なくとも10年は持つことを意味します。
そういったシチュエーションでは主観をなるべく排除し、客観的な要素で銘柄選定をする必要があります。
例えばその銘柄を買った理由について説明する際、
「応援したいと思ったから!」
という感情ではなく、
「過去10年間の決算を確認し、事業内容は目立たないが堅実で、毎年配当を出せていて、増配傾向。市場におけるシェアも大きい。」
というように説明できるのがベストです。
このようなレベルに達していれば、年次決算がちょっと悪かったくらいで動じることは、ありません。
銘柄選定では少なくとも4~5年間の決算を確認。
さてもう一つの意味とはまさに見出しの通りです。
運用中には4~5年の平均を吟味しろという意味ですが、それは銘柄選定の時も同じです。むしろその銘柄についての知識量は運用開始前の方が少ないはずですので、なおさらです。
まとめ
銘柄選定は感情ではなく、客観性を。目先に惑わされず、きちんとした考えを持って運用を。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
