
すさましや今日時雨行く鷹の面 夏目漱石の俳句をどう読むか75

すさましや釣鐘撲つて飛ぶ霰
— حملة الأسهم في الشرك (@mokuhyokabuka) March 27, 2024
岩波は「撲」に「う」とルビを振っている。「ぶ」でもいいかと思ったところ、まあ、「桐油を撲(う)つ雨の音と」と『思い出すことなど』にあるから、ここは「うつ」でよいか。一人ネットで「なぐつて」と読んでいた人がいた。それはさすがになかろう。しかし『それから』では「撲(どや)される」なので要注意だ。
この句は少し解釈を迷ったが「霰が斜めに降ってきて釣鐘に当たる様子」をすさまじいと詠んでいると解釈してよいだろうか。鐘楼、鐘撞堂には屋根があるので普通は霰が当たることはない。そうとうの風が吹いていなければ「霰が斜めに降ってきて釣鐘に当たる様子」などというものはあり得ないわけだ。
しかしあくまで雹ではなく霰なので、鐘を撞くまではいかないわけだ。それでもパチパチと弾けるような音はしていたのであろうか。まあ、珍しい様子を詠んだ句ではあると思うが、特に申し上げることのない句である。
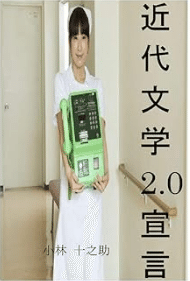
昨日しぐれ今日又しぐれ行く木曽路
しゃぶしゃぶでも食べに行ったのかという句である。いやしぐれ煮か。
木曽路など実際に歩いて旅をしていたわけでは無かろう。これもまた何か元ネタとというか、講談本か何かに因縁がありそうな句ながら、岩波の解説は「ふーん」している。
いずれにせよ古色をつけた分だけ緞帳芝居じみた狭さを感じさせる句である。木曽が時雨れれば路は狭かろうということか。
岩波は「昨日」にルビをつけないが「きぞしぐれけふまたしぐれてきそのみち」で「きぞ」と「きそ」の洒落になっていない?
使う機会少ない漢字集
— ぷて (@_imperial_navy_) March 25, 2024
奸 尊皇討奸でしか使わない
璧 完璧でしか使わない
嬬 嬬恋村でしか使わない
虔 敬虔でしか使わない
睛 画竜点睛でしか使わない
冪 昇冪・降冪でしか使わない
煕 細川護煕でしか使わない
洒(≠酒) 洒落でしか使わない
熾 熾烈でしか使わない

鷹狩りや時雨にあひし鷹のつら
これも実景では無かろう。そうなると霰もあやくしなり、あれが実景ではないとすると全く面白くもなんともない感じがしてくる。どうも私は俳句は私小説でないと気に入らないようだ。
この句も漱石が鷹を飼っていた、鷹狩りをしていた、という話を聞かないことから想像の句と見做してみると、鳥はたいていびっくりしたような顔をしているものだから、月並みに落ちている感じがしてしまう。
(魚はたいてい「やられた」という顔をしている。)
一体どのような手段で他人の口座から何回にも分けて高額なお金を振り込ませることができるのか解らないように、一体どのような状況であれば「時雨にあひし鷹のつら」というものが出来上がるのかどうか、私にはまったくわからない。鷹は落ち着かせるために頭に袋をかぶせられて移動させられていた筈であり、時雨が降る日に鷹狩りはやらないだろうし、仮に鷹狩りの最中に急に時雨が降ってきたとしても鷹の表情はそう変わらない筈だ。
この句の場合、創作で言えば設定ミスということにならないだろうか。

辻の月座頭を照らす寒さ哉
無理やり寒さに持って行った感じの句である。「辻の月座頭を照らす」ではストレートに「寒さ」には結びつかない。月が座頭を照らす時期は決まっていない。年がら年中照らす。
そこは漱石も解っていて、かなり開いたところを寒さに持って行って、このつき過ぎないところが上手いだろと言いたげだ。
寒聲や木辻の月を袖の上


この「辻の月」という表現がちょいと面白いかなと思ったが、それほど斬新というわけでもなかった。
残念。

[余談]
店の前ではなく全然離れた「歩道」にずっと看板を置いているインド料理の店があるんだけど、こういうのはOKなんだっけ?
結構邪魔なんだけど。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
