
芥川龍之介の『素戔嗚尊』が解らない⑤ 君は何を言っているんだ
そんな日本語があるか
「おれは腹が減っているのだ。食事の仕度をしれい。」

覚悟をしろいとは言うが、覚悟をしれいとは言わないのではないか。つまり面白いを「おもしれい」とは言うが、それは「白い」の「しろ」であり、命令の「しろ」は「しれ」にはならないのではなかろうか。
ここも「そんな言い方をすることもあるんだ」と漫然と読んでいてはいけない。
「さあ、これで腹は出来た。今度は着る物を一枚くれい。」
この「くれい」は正しい。
ほたりは瓶ではない
その内に食事の仕度が出来た。野獣の肉、谷川の魚、森の木の実み、干した貝、――そう云う物が盤(さら)や坏(つき)に堆く盛られたまま、彼の前に並べられた。若い女は瓶(ほたり)を執って、彼に酒を勧むべく、炉のほとりへ坐りに来た。目近かに坐っているのを見れば、色の白い、髪の豊な、愛嬌のある女であった。
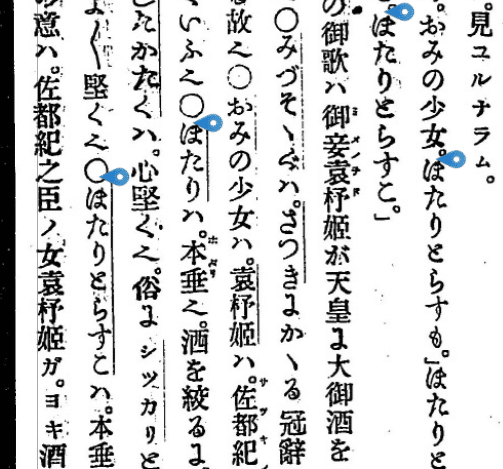
ほん‐だれ【本垂】 祭事に用いる古風な幣(しで)の一種。掻垂(かいだれ)。
全くの推測ながら芥川自身が「ほたりとらすも」の歌の解釈として「ほたり」を酒と解釈して「瓶」と当て字をしたものと考えられる。ここは「かめ」で良かったのではなかろうか。
そこは濁る
素戔嗚は膝を抱えたまま、洞外をどよもす風雨の音にぼんやり耳を傾けていた。すると女は炉の中へ、新に焚き木を加えながら、
「あの――御名前は何とおっしゃいますか。私は大気都姫(おおけつひめ)と申しますが。」と云った。
「おれは素戔嗚だ。」
大気都姫はオオゲツヒメで濁る。
国学院がŌgetsuhimenokamiと書いているので間違いなかろう。それは別人だと白を切るわけにもいくまい。鼻口・尻から食物を取り出して奉ったと『古事記』には書かれている。
しかしまあ、昔の書き方だと濁点を省略したものもある。
『平治物語』では信西に「シンサイ」と読み仮名が降られている。古い書物では濁点が抜けることは珍しくないが「シンゼイ」と「シンザイ」では流石に違いすぎる。これほどまで信西とは曖昧な存在なのである。
こんなこともあるからまあ良しとしよう。
紅おしろいはなかろうて
その内に夜になった。老婆は炉に焚き木を加えると共に、幾つも油火の燈台をともした。その昼のような光の中に、彼は泥のように酔い痴れながら、前後左右に周旋する女たちの自由になっていた。十六人の女たちは、時々彼を奪い合って、互に嬌嗔を帯びた声を立てた。が、大抵は大気都姫が、妹たちの怒には頓着なく、酒に中った彼を壟断していた。彼は風雨も、山々も、あるいはまた高天原の国も忘れて、洞穴を罩めた脂粉の気の中に、全く沈湎しているようであった。ただその大騒ぎの最中にも、あの猿のような老婆だけは、静に片隅に蹲って、十六人の女たちの、人目を憚らない酔態に皮肉な流し目を送っていた。
元ネタでは大気都姫は鼻口や尻から食べ物を出して、素戔嗚が「気持ち悪」となり殺されてしまうのだが、ここでは酒盛りになる。それにしてもこの時代に「脂粉の気の中」はいかがなものであろうか。と思えば、
赤い顔料のようなものを顔に塗る習慣はあったようなのでまあこれはいいか。
二回同じ比喩を使う馬鹿が……
彼等は互に競い合って、同じ河の流れにしても、幅の広い所を飛び越えようとした。時によると不運な若者は、焼太刀のように日を照り返した河の中へ転げ落ちて、眩い水煙を揚げる事もあった。が、大抵は向うの汀へ、ちょうど谷を渡る鹿のように、ひらりひらりと飛び移って行った。そうして今まで立っていたこちらの汀を振返っては声々に笑ったり話したりしていた。
うん。「焼太刀のように日を照り返した河の中」か。まあ、水面がギラギラしたと読めということだな。
しかしある夜夢の中に、彼は山上の岩むらに立って、再び高天原の国を眺めやった。高天原の国には日が当って、天の安河の大きな水が焼太刀のごとく光っていた。
うむ。「天の安河の大きな水が焼太刀のごとく光っていた」か。水面がギラギラしていたと読めということだな。
あれ?
おかしいぞ。
なんだこれ。
同じ比喩を二回使う馬鹿が同じ比喩をまた二回使っている。しかも「天の安河の大きな水」とは何だ? 「大きな水」って何なんだ?
私の頭がおかしいのか?
それとも芥川龍之介の『素戔嗚尊』がおかしいのか?
同じ比喩を二回使うことに何か隠された意味があるのだろうか。これは確かに解らない。解ったような顔をしている自称読書好きとか、芥川の写真のアイコンを平然と使っているような人に真剣に質問してみたい。
あなた芥川龍之介の『素戔嗚尊』が解るんですかと。
今日のところ私にはさっぱり解らない。明日解るかもしれないけれど。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
