
達磨忌や茶の花折つて石蕗の花 夏目漱石の俳句をどう読むか71
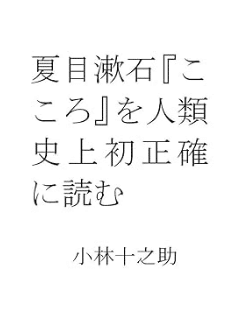
達磨忌や達磨に似たる顔は誰
最初この句を
達磨忌や達磨に似たる人は誰
と読み違えて、意味のない句だなあと勘違いしかけた。この句は中身のない質問ではなくて、「達磨忌だなあ、あの達磨に似た顔の人は誰なんだろう」という感想だ。子規の評点は「◎」。
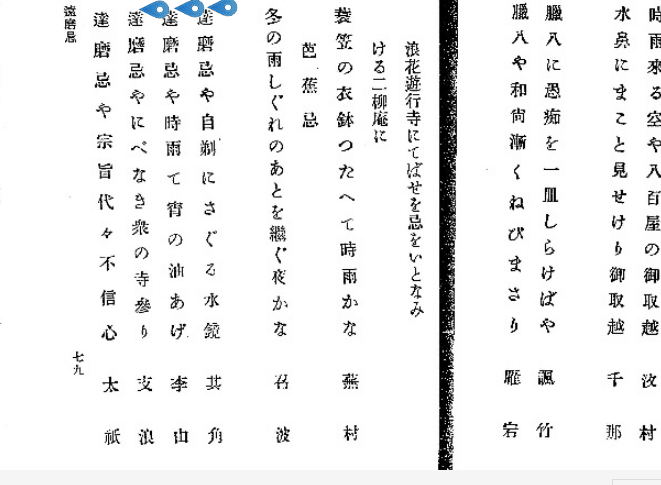
達磨忌の句にもう一つ達磨を入れた果敢さを評価したのだろうか。

実際達磨みたいな顔の人が現れたら驚くだろうが、おそらくここは「顔」がポイントだろう。
達磨だから「顔」だけしか似るわけにはいかない。「達磨に似たる足」「達磨に似たる手」というわけにはいかないし「達磨に似たる姿」もおかしい。その達磨の顔に手足が生えているから「にゃんこ大戦争」みたいにグロテスクになる。
そこまでの画が出てくると「◎」かなという句である。
達磨忌や達磨に似たる顔は誰
達磨というものの特徴を「達磨に似たる顔」と捉えたところにこの句の面白みがある。
芭蕉忌や茶の花折って奉る

子規はこの句にも「◎」と評点をつける。

小宮達お弟子さんたちは「ふーん」している。仔細はないと言われているが、これは『猿蓑』の、
みのむしの茶の花ゆへに折れける 伊賀猿雖
と、芭蕉の
みの虫の音を聞きにこよ草の庵
あたりのイメージが重ねられていまいか。
いないな。
ハイ、次。
本堂へ橋をかけたり石蕗の花
いずれかの寺院の門から本堂までの間に橋を架けたようにつわぶきが咲いていたという句意であろうか。
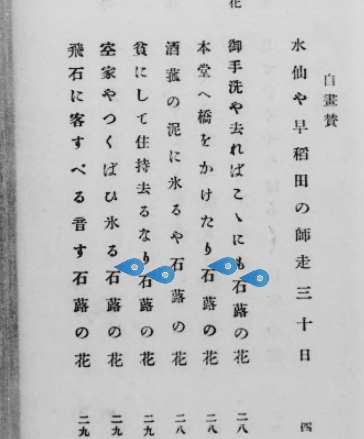
漱石はこの石蕗の花を何度か詠んでいる。この石蕗には毒性があり増えやすいので植えてはいけないという注意喚起がされている。

漱石の句もまたこのよく増えるという性質を繰り返し詠んでいるように思える。そこはかとなく可憐な花に見えるが嫌われたものだ。
その中でこの句は、比較的肯定的な石蕗の花の繁茂を詠んでいるように思える。
日にあてゝ着かへる衣や石蕗の宿 蔵六

ちまちまとした海もちぬ石蕗の花 一茶

そこまで剛情やないやろ。
本堂へ橋をかけたり石蕗の花
この句の面白みはごくありきたりにその季節であることよというところにあるのではないか。夏にこの同じ場所を訪ねれば花はない。毎年この季節になると思うのだが桜の花はわっと咲いて二週間ほどで散ってしまい、残りの十一か月と半月の間はただ何の木だかわからないくらいただぼうっと立っている。何もそんなに極端でなくてもいいのではないかと思うのだが、この二週間だけ大はしゃぎだ。全く馬鹿馬鹿しいようなことながら、それが季節というもので目出度いことなのだ。
雑草であれ、毒であれ、桜ほど目出度いとは言われなくても、ああ、花が咲いたなと思われることは良いことであろう。
この時期はどこでもいろんな花が咲いている。桜の圧倒的な派手さに比べるべくもないが、地べたに咲いている花を見るにつけ、そのつつましやかなところもよいなと思う。漱石の見た石蕗の花もそんな程度のものだろう。しかしまあ橋というくらいだからみんなどしどしそこを踏んづけて本堂に向かうのだろう。そう思えば取り澄まして風流ぶっていない、なんともリアリズムの句だ。
踏まれても気にしない石蕗の花が見えるようだ。

[余談]
なんだか大きなすばらしいものが、小さなどうでもいいものによって台無しにされているような気がする。そんなに簡単に崩れてしまうのかと呆れてしまう。
まあ「夏目漱石論」なんていうものがたいていそういうものなんだけど。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
