
オオストラリアの猿? 芥川龍之介の『猿』をどう読むか④
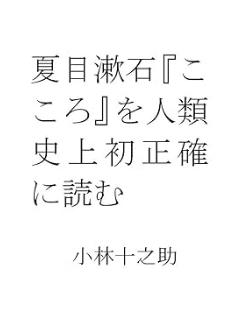
昨日は語り手が危険な優越感に充ちていて、奈良島を「猿」と呼び、狩ろうとしているというあたりの感覚の斬新さと気味悪さについて書いた。なんだかとても気持ちが悪い。それは自分の中にもそういう恐ろしいものが潜んでいるのではないかという不安があるからであろう。その不安は間違いなくこの若い書き手が操っているものだ。そしてそのような意匠は何度考えても芥川以前には見いだせない……。
いや、そこまでは言い過ぎだろうと思いつつも、やはりこの恐るべき若者たちの原型はなかなか思いつかない。官製の優越感に限れば、その程度のものは『聖書』にでも見つけられそうな気もするが、仲間を猿と見做して狩ることを面白くってたまらないというような恐るべき若者の姿は……やはり見当たらないのである。
あるいは芥川が「仲間を猿と見做して狩ることを面白くってたまらないというような恐るべき若者」を書いていたことすら、殆ど議論されてこなかったのではなかろうか。例えば三島由紀夫の『午後の曳航』に描かれた恐るべき少年たちについて語られる際に、芥川の『猿』が引き合いに出されたことがあるだろうか。
この猿と云ふのは、遠洋航海で、オオストラリアへ行つた時に、ブリスベインで、砲術長が、誰かから貰つて来た猿の事です。それが、航海中、ウイルヘルムス、ハフエンへ入港する二日前に、艦長の時計を持つたなり、どこかへ行つてしまつたので、軍艦中大騒ぎになりました。一つは、永の航海で、無聊に苦んでゐたと云ふ事もあるのですが、当の砲術長はもとより、私たち総出で、事業服のまま、下は機関室から上は砲塔まで、さがして歩く――一通りの混雑ではありません。それに、外の連中の貰つたり、買つたりした動物が沢山あるので、私たちが駈けて歩くと、犬が足にからまるやら、ペリカンが啼き出すやら、ロオプに吊つてある籠の中で、鸚哥が、気のちがつたやうに、羽搏きをするやら、まるで、曲馬小屋で、火事でも始まつたやうな体裁です。その中に、猿の奴め、どこをどうしたか、急に上甲板へ出て来て、時計を持つたまま、いきなりマストへ、駈け上らうとしました。丁度そこには、水兵が二三人仕事をしてゐたので勿論、逃がしつこはありません。すぐに、一人が、頸すぢをつかまへて、難なく、手捕りにしてしまひました。時計も、硝子がこはれた丈で、大した損害もなくてすんだのです。あとで猿は、砲術長の発案で、満二日、絶食の懲罰をうけたのですが、滑稽ではありませんか、その期限が切れない中に、砲術長自身、罰則を破つて、猿に、人参や芋を、やつてしまひました。さうして、「しよげてゐるのを見ると、猿にしても、可哀さうだからな」と、かう云ふのです。――これは、余事ですが、実際奈良島をさがして歩く私たちの心もちは、この猿を追ひかけた時の心もちと、可成よく似てゐました。
話がもう一つ過去に戻ってしまった。しかしオオストラリアへ寄って猿を貰うだの「外の連中の貰つたり、買つたりした動物が沢山ある」だのまるで軍艦ではないかのようだ。そしてなによりも「猿」が気になる。オオストラリアにはニホンザルはいまい。
オーストラリアは猿のいない国である。
え?
オーストラリアは猿のいない国である。
つまり?
つまり「オオストラリアへ行つた時に、ブリスベインで、砲術長が、誰かから貰つて来た猿」というのははなはだおかしな話なのである。後にこの若い書き手は様々な無茶な設定を放り込んでくる。それは『羅生門』の二階の死体、一度きりのことではない。
そしてこのオオストラリアの猿の大人しいこと。その猿がどんな大きさなのかはわからないが、人間が素手で猿を掴まえることは極めて困難であろう。飼い犬や飼い猫はたやすく飼い主に掴まえられてしまうが、あれは掴まえられたふりをしているだけのことで、本気で逃げた動物はなかなか捕まるものではない。
つまりこのオオストラリアの猿は演技しているのだ。
何のために?
結果的にはこのオオストラリアの猿は「私」に間違った成功体験を与えてしまい、当てにならない自信を与えてしまっていることになる。相手をたかが猿と見下しながら、実はこの恐るべき若者たちは偽物の優越感に酔っていることにはならないだろうか。
つまり彼らが「猿」と見下した奈良島は実は……と続きを書きたいが、おしっこがしたいので今日はここまで。

[余談]
おしっこで思い出したが、ショーン・Kって今何をしているんだろう。
ショーンKって、話し方が上手いよな。
— 晴考雨読🫡🇺🇦(Seikou Udoku) (@SherryErkko) March 24, 2024
人を納得させられる話し方。
経歴詐称云々は置いといて、これは有能。
pic.twitter.com/BdbKcJ5YmC
やっていることは「芸」で芥川と変わらないのに。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
