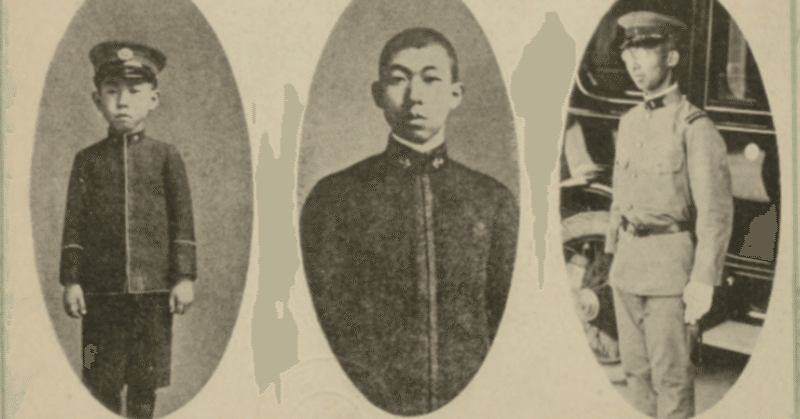
菱川の正体 平野啓一郎の『三島由紀夫論』を読む63
菱川の正体
しかし菱川には、一体過去にどんな作品を書いたかは知れぬが、癒しがたい芸術家気どりがあつた。
平野が菱川を三島の「自己戯画化」と見做している点に関しては既に述べた。しかしその醜さが何ゆえのものなのか、『鏡子の家』ではお互いが干渉しないように平和に棲み分けられていた三島由紀夫の分身が何故衝突せねばならないのか、突き止めてはいないように見える。「贋物の芸術家」「実作をせぬ芸術家崩れ」と罵られているのが三島由紀夫自身であるとするならば、杉本清一郎と山形夏雄は何故罵り合わなかったのか。
深井峻吉は飯沼勲となって散ったように見える。敢えて言えば舟木収はまた松枝清顕となって散ったと見做してよいだろうか。
それにしても五井物産の芸術家崩れとは珍妙なキャラクターである。言ってみれば杉本清一郎と山形夏雄を最悪の形で融合させたような、そんな造形である。
平野啓一郎は「Ⅱ 『金閣寺』論 22 『鏡子の家』」から「Ⅱ 『金閣寺』論 24 存在と無 」において丁寧に『鏡子の家』を読み、三島が夏雄に希望を見出す様子を確認していた筈だ。
存在論以上の政治的共同体の構想としては、楽観的すぎるであろうが、三島が『潮騒』や『金閣寺』に代表されるこの時期の「古典主義」を強調するのは、スタイル上の問題に留まらず、こうした世界認識の可能性を信じようとしていたからだった。その挫折のきっかけが、『鏡子の家』であり、夏雄という登場人物への愛着は、芸術家としての生の可能性というに留まらず、こうした思想への期待もあったのであろう。
この夏雄への愛着が世間に認められなかった、つまり『鏡子の家』という渾身の力作が不評であったが為に、三島が落胆したのは事実である。しかしもっと落胆しなければならないのは平野啓一郎が夏雄の「なにもなかった」という樹海体験を『天人五衰』の何もない庭と結び付けながら「樹海の分節化不可能な全体というイメージ」とあらゆるシンメトリーに対する侮蔑である夕焼けというものを決して結びつけようとしない欺瞞に対してではないか。
夏雄はどこへ行ったのか?
そう素朴に問い直してもいい。
無意味な色彩の濫費としての夕焼けは、オルギエ(らんきち騒ぎ)によってあらゆる体系を無効化して終わる。夏雄が愕然とした樹海体験は菱川によって杜撰にリフレームされ夕焼け理論に置き換えられている。つまり夏雄は変節し、芸術家崩れの菱川になってしまっていたのである。
そういってみるともう一人の三島由紀夫、杉本清一郎の「世界崩壊の予兆によって現実を虚無化し、仮象としての生を欺瞞的に受け容れている」というキャラクターの末路も気になる。杉本清一郎は細かいところまでよく気の付く、卑屈で、怠け者の、単に人にぶら下がって生きている案内人になっていたのではないか。
世界崩壊の予兆はもうどこかへ行ってしまった。それは昭和三十七年の『美しい星』まではリアルなものだった。しかしいつの間にかなくなっていた。それは三島が生き続けることを確信していた年でもあった。昭和三十八年の『午後の曳航』に平野は三島の死への意識を見るが、むしろそこには栄光もなく漫然と生き続けることへの畏れの方が強く出てはいまいか。仮に世界崩壊がないとしたら「世界崩壊の予兆によって現実を虚無化し、仮象としての生を欺瞞的に受け容れている」などという態度は途端に胡散臭い現実主義に堕ち、偶然を装い高級ホテルの朝ご飯の御相伴にあずかろうとしてしまうものではないか。
問いの立て方
何か「論」を書こうとした経験のある人間なら誰しも、問いの立て方が適切であるかという問題を繰り返し考えてきたはずである。
平野は「Ⅲ『英霊の声』論 14 天皇との神秘主義的合一」において、神風が吹かなかったことに対する霊の、「何故、神風が吹かなかったのだろう」という疑問に対して、『海と夕焼』の中の次のような一文が想起される、としてこう引いている。
「おそらく安里の一生にとって、海がもし二つに分れるならば、それはあの一瞬を措いてはなかったのだ。そうした一瞬にあってさえ、海が夕焼に燃えたまま黙々とひろがっていたあの不思議……。」
三島の公式見解通りのストーリーを知りながら「想起」と言ってみる欺瞞はさておくとして、既に述べている通り、これがキリスト教的唯一神の奇蹟のことだと平野は確認しない。作品としての『海と夕焼』と本気で向き合う姿勢がまるで感じられない。
そしてさらには特攻隊員たちと安里の、つまり三島由紀夫の根本的な問いの立て方のおかしさに言及しない。「何故、神風が吹かなかったのだろう」と真剣に問うためには、呼ばれればすぐに飛んで来るロデムかハクション大魔王みたいな便利な神の存在が前提になる。そういう便利な神が存在しないことを知っている人は、「何故、神風が吹かなかったのだろう」とは問わない。
仮に「何故、神風が吹かなかったのだろう」と真剣に問うとしたら、その人は相手側の神が神風を妨害する力のない神であると信じていることになり、そういう人は同時に海が二つに割れないことを知っている本当の無神論者であるべきであろう。安里と特攻隊員たちは同型の問いの立て方をする決して相容れない存在なのだ。仮にそうしたものを二つ並べた人間がいたとしたら、その人は最初から神風が吹くわけがないと知っている当たり前の人間だ。
そういう人間が改めて、「何故、神風が吹かなかったのだろう」と真剣に問うとしたら、「科学的理性を媒介して辛うじて認識し得る」地球の自転のような、日常の感覚や知性だけでは捕まえられず、きわめて正確で体系的でもあり直感的でもあるような、そういう超理性的な確信が認識させているものが神風なのではないかという畏れがどこかにあるからではないだろうか。
つまり人間には理性と科学的知識と、それに相反する未知なる領域に対する畏怖がありうる。
全く「例えば」という話ではあるが、どういうわけか三島由紀夫は成功した弁護士である本多をインドに連れて行き、輪廻転生は信じられているだけではなく自然の現象に過ぎなかったと言わせてみる。
この馬鹿馬鹿しい程のオカルト感覚がなければ「何故、神風が吹かなかったのだろう」と真剣に問うことはなかっただろう。
狂信者本多
ジン・ジャンに会いに行く本多を、三島由紀夫は何故かオカルトの狂信者のように描いていく。
芝生のなかの迂路を近づくあひだ、どこにも人影が見られなかつた。形而上的な喜びに向かつてがつがつと牙を鳴らし涎を垂らしてゆくこの接近に、本多は自分の趾に密林を潜行する獣の爪を感じた。さうだ、彼はこの喜びのためにだけ生まれたのだ。
これが筆のすさびでもなく、ただ盛り上げ過ぎたわけでもないのだとしたら、本多は異常者である。平野は誤解の可能性も含めて本多を「認識者」という役割に押しとどめるが、ここで本多は無理にも転生者を生み出しかねない能動的な態度にある。ここで三島が「獣」と書いているからには、ジン・ジャンは獲物に過ぎない。
つまり特攻隊員や安里が「獣」ならば、天皇もキリスト教的唯一神も獲物に過ぎないことになる。
何故三島は本多を「獣」にしてしまったのであろうか?
この個所は44ページにあり、平野はここを読み飛ばしている。それはやはり「認識者」としての本多を守るためではなかったか。
そして三島の意図の中では本多を「認識者」に留めることなど到底考えていなかったからこそ、三島は本多を獣にしてしまったのではないか。
奇妙な質問
これも平野が単に無視しているように見えなくもない個所ではあるが、ネジが一本抜けても決定版とはならないという程度の意味で指摘しておきたい。
平野はジン・ジャンに対して「勲の生まれ変わりであることを主張し」と書いている。確かにそう主張している。しかし本多はそのジン・ジャンに対して奇妙な質問を投げかけるのだ。
「松枝清顕が私と、松枝邸の中ノ島にゐて、月修寺門跡の御出でを知つたのは、何年何月のことか、おたづねしたい」
これは松枝清顕にしか答えられない問いである。
問いの立て方が適切ではない。
二番目の問いの立て方も適切ではない。
「飯沼勲が逮捕された年月日は?」
裁判官としても弁護士としても適当な質問ではない。これは飯沼勲しか答えられない問いではない。従ってこの問いに正確に答えられたところで、それが飯沼勲の転生者であることの証明にはならない。
三島由紀夫は何故本多にこのような順番で、このような問いを立てさせたのであろうか。法学部出身の三島由紀夫がここに創り出したのは、恐らく問いの立て方の不自然さである。
思い出しても見れば、本多は勲に松枝清顕の記憶を問うことをしなかった。明示的な部分では、飯沼勲には松枝清顕の明確な記憶は移し替えられてはおらず、ただ清顕と聡子が情交した軍人下宿の記憶がうっすら残っているだけである。本多は勲が松枝清顕の生まれ変わりではないかと疑いながら、勲が松枝清顕の記憶をそっくり持っていることまでは期待していなかった。
それなのに本多は、「獣」となった本多は、いきなりジン・ジャンに対して松枝清顕の正確な記憶を求めたのである。あたかも松枝清顕の記憶がなければ飯沼勲ではないと言わんばかりである。
この本多のちぐはぐな質問の意味はなんなのだろうか?
これは、三島が仕掛けた菓子パンなのか?
奇妙な認識
やはり本多は少しおかしくなっている。
……本多にはそのとき、幼ない姫の見てゐるものが何ものか即座に分かつた。
姫は時間と空間を同時に見てゐた。すなはち、彼方の驟雨の下の空間は、本来ここから見える由もない未来化過去に属してゐた。身を現在の晴れた空間に置きながら、雨の世界を明瞭に見てゐることは、異なる時間の共在でもあり、異なる空間の共在でもあつて、雨雲が時間のずれを、はるかな距離が空間のずれを垣間見せてゐた。いはば姫はこの世界の裂け目を凝視してゐた。
この説明からは、本多もやはり姫の見ているもの、世界の裂け目が見えていることになる。これは如何に認識者とはいえ、認識者過ぎるもののいいではなかろうか。
この本多の過剰な認識に関して平野は「48 自殺しなかった本多」において第二部の「二つの富士」に関して指摘するまでは、特に注目することなく泳がせているように見える。
しかし三島由紀夫はこの時の本多の怪しさを、こう表現してもいたのだ。
そのときの姫の小さな桃いろの潤んだ舌は、(もし女官が見咎めたら忽ち叱つたであらうが)、本多が献上した指輪の真珠を一心に舐めてゐた。舐めてゐることによつて、こんな奇蹟の顕現を、小さな姫自身が保障してゐるかのやうに。……
この三島の、いや本多の言い分は「果物は怠惰に美しく熟れるべきで、勤勉な果物などといふものがあつてはなりません」という菱川の言い分にもいや増して鬱陶しい。
七歳にもなれば指輪は舐めないもので、指輪を舐めることで保障されるのは姫の幼稚な口さみしさだけだ。あるいは姫は世界の裂け目を見ているのではなく、ただぼうっとしていただけだ。そこに注ぎ込まれた本多の過剰解釈は、ただ奇妙であるというよりは、何か焦りすぎている感じさえする。
この焦りの意味もまだ誰も知らない。何故ならまだ書いていないからだ。
[附記]
どうしても平野啓一郎が指摘していないことを論うと一人旅の感じがしてしまうが、漏れ、抜けの指摘は避けるわけにはいかないだろう。
何故三島由紀夫は金閣寺を天皇として描いたのか?
この問いからは何も生まれない。
夏雄の「何もない」を本多が見た「何もない庭」と結び付けてしまうと、夏雄は本多になってしまい、
何故夏雄は本多になったのか?
という無意味な問いが生まれかねない。
だから菱川の半分は夏雄だ、と平野が書いていないことも書かねばならぬ。それが決定版三島由紀夫論を読む者の最低限の義務である。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
