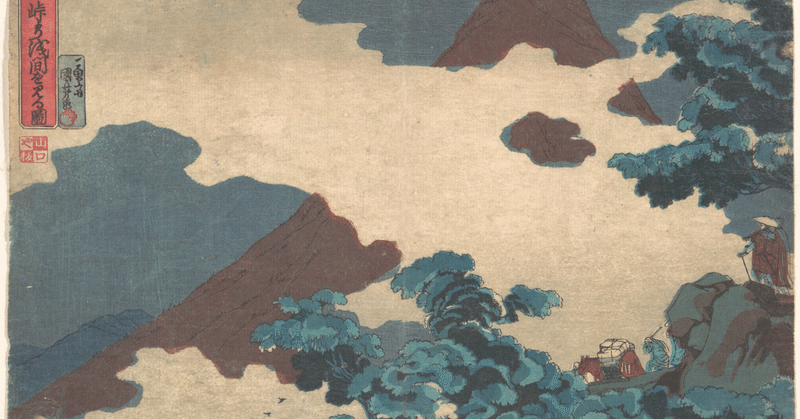
三島由紀夫の書簡を読む② 遅れてきた軍国少年
遅れてきた軍国青年?
私も亦、順応主義をもつとも憎みますが、日本人の中にあるあのどうしやうもない順応主義は、一体どこから来たものなのでせう。
昭和四十一年九月三日
昔の小生だけ知つてゐる人は、かういふ変貌を理解してくれないばかりか、オポチュニストのやうに言ひますが、小生としては、休火山が爆発しただけだと申したいのです。
昭和四十三年八月十七日
「蓮田善明とその死」感激と興奮を以て読み了へました。毎月、これを拝読するたびに魂を振起されるやうな気がいたしました。この御作品のおかげで、戦後二十数年を隔てて、蓮田氏と小生との結縁が確かめられ固められた気がいたしました。御文章を通じて蓮田氏の声が小生に語りかけてきました。蓮田氏と同年にいたり、なほべんべんと生きてゐるのが恥ずかしくなりました。一体、少年の忘恩は、数十年後に我身に罪を報いて来るやうであります。今では小生は、嘘もかくしもなく、蓮田氏の立派な最期を羨むほかに、なす術を知りません。しかし蓮田氏も現在の小生と同じ、苦いものを胸中に蓄へて生きてゐたとは思ひたくありません。時代に憤つてゐても氏にはもう一つ、信ずべき時代の像があつたのでした。その信ずべき像のはうへ行けたのでした。
昭和四十三年十一月八日
さてわれわれには、いつ戦ひの日が来るのでせうか。
昭和四十四年六月十八日
何やら、このごろ、現在の日本が明治維新直前のやうな気がしてなりません。
昭和四十二年三月二十三日
三島由紀夫は昭和二十一年十一月十七日、蓮田善明を偲ぶ会に参加して詩をささげているが、蓮田善明から精神的薫育を受けていた、あるいは思想的な支配を受けていたという様子はない。むしろ『憂国』以降次第に湧き上がってきた謎の怒りが昭和四十年代になってさらにその勢いを加速し、「蓮田善明とその死」によってその方向性は明確になってしまったという風に見える。ある意味一貫しているのは保田與重郎の国学、あるいはもっともらしさへの信頼で、やはり蓮田善明への傾倒は突然現れたと言っていいくらい唐突なものである。
しかし蓮田善明が自殺の期限を切ったわけでもないことは「戦後二十数年」「数十年後に」という表現の微妙さに現れている。ともかく昭和四十四年の帝国ホテルでの自殺未遂の前に「自決」というゴールだけは定まってしまったように思える。
ところがさて、「休火山が爆発しただけだ」という言い訳は、やはり何か確証バイアス、後知恵バイアスや想起バイアスなどが組み合わさった訂正不可能な信仰のようなものに思える。
こう言っては何だが昭和二十一年十一月十七日、平岡公威は自決しても良かったのだ。だがそうしなかった。そこに生じるちぐはぐさを三島由紀夫の脳みそが正当化・合理化するために「休火山」というストーリーが後付けされたのだ。
堀氏は現在の青年作家のうちで、時局を語らない唯一の人ともいへませうか、なんといつたつてお先走りの文報連中、大東亜会などで大獅子吼を買つて出る白痴連中より、数千倍の詩人、したがつて数千倍の日本人と思います。
昭和十八年九月十四日
この時の平岡公威は「何も知らない子ども」というより、お調子者の卑しい者たちの姿がはっきり見えていた素直な青年だった。この堀辰雄に対しても後に「軽井沢しか書けない」と訳の分からない文句をつけることになる三島由紀夫、或いは市ヶ谷の自衛隊駐屯地のバルコニーで大獅子吼を買って出る三島由紀夫の方が世間的には白痴じみてはいまいか。
あるいは蓮田善明が置かれた環境に於いて、その当時の状況の中で、蓮田の上官射殺と自決という行動は「已むに已まれぬもの」と見做すことができないわけではない。
問題は戦後二十数年という時間と、その間に「近代文学ではなく源氏物語を書きたい」言っていた青年が中年の成功した文学者となっていたことだ。とことん反時代的であれば『仮面の告白』も『金閣寺』も必要なかった。『散木男妖しの懺悔』『北山鹿苑禅寺物語』でよかった。ひたすら古典の世界に遊んでいればよかった。しかし三島由紀夫は戦後日本の生活水準の向上とともに、何でも書く作家となった。ただ藤原定家は書けなかった。
選択肢はあったと思う。もう一度自分本来の古典の世界に戻り藤原定家を書き、老成すること。
ただその選択肢はまるで最初から存在しなかったかのように「蓮田善明とその死」によってかき消されてしまったように私には思える。勿論それが三島由紀夫事件の原因の全てではあり得ない。しかし大きな要因の一つであり、手紙を見る限り三島自身が「戦後二十数年を隔てて、蓮田氏と小生との結縁が確かめられ固められた気がいたしました」として自らにストーリーを与えていることは確かだ。
この三島由紀夫を「遅れてきた軍国少年」と呼ぶのは何か言葉が足りない気もするが、「戦後二十数年」という遅延の理由の曖昧さも含めて、あるいは軽率なからかいの意味も込めてここでは一旦「遅れてきた軍国少年」と呼んでおきたい。
また別の三島が見つかるという期待も込めて。
[余談]
昭和三十三年十二月二十九日、三島由紀夫は遠藤周作に澁澤龍彦の自宅を教える手紙を書いている。遠藤周作と澁澤龍彦? どんな用事があったのだろう?
日経平均は10万円に上がる https://t.co/LGIj4nnidf pic.twitter.com/NnqxPfdakS
— Dan Takahashi (@Dan_Takahashi_) September 6, 2023
すばらしい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
