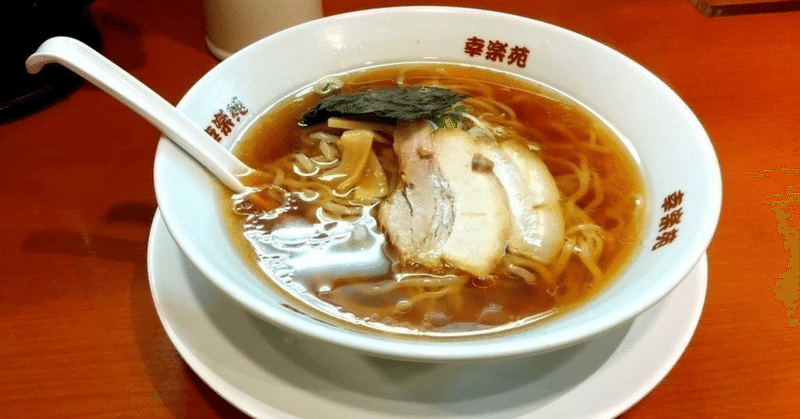
芥川龍之介の『偸盗』をどう読むか③ 想像のつかない生き物
そう言えば兄弟の話だ
村上龍と村上春樹の対談集『ウォーク・ドント・ラン 村上龍VS村上春樹』は大人の事情で文庫本化されず、一時期は単行本がネットで高値で取引されていたようだ。
この本は二人が本当に素直に語り合う珍しい内容で、『ミミズクは黄昏に飛び立つ』や『職業としての小説家』と様々な点で記憶が食い違うという意味では貴重な資料と言えよう。
その『ウォーク・ドント・ラン 村上龍VS村上春樹』の中で確認されたことに二人とも一人っ子で、自分たちの小説は一人っ子小説だということがある。この事実は何でもないようなことであるも、実はかなり面白い指摘ではないかと思う。
実際村上春樹作品の主人公と兄弟との葛藤が描かれた作品と云うものは思い当たらない。何かの冗談のようにクレタとマルタが並べられるくらいで、それでさえ「姉妹」という人間関係が描かれたとは言えないように思える。
そう言われてみれば夏目漱石作品の多くでは「兄(姉)弟(妹)」という人間関係が盛んに取り上げられてきた。『坊っちゃん』『虞美人草』『それから』『門』『行人』『こころ』『道草』『明暗』、これらの作品において「兄(姉)弟(妹)」という人間関係が様々に組み合わされてきた。
そう言われてみれば芥川龍之介は実質的に一人っ子で、その作品にはどこか一人っ子らしさというものがあるような気がして来る。今主要な作品の主人公たちを思い返してみると、確かに兄弟というような人間関係の中にいない者たちばかりが浮かんでくる。『雛』『お律と子等と』『歯車』に兄弟関係のようなものがあるにはあるが、その程度である。つまり太郎と次郎を主人公に仕立ててみれば、『偸盗』は一人っ子の芥川龍之介作品の中には珍しく、兄弟という人間関係を軸としたほぼ唯一の作品だといって良いだろう。
ところがそう言われてみれば、その「兄弟」というものがまるでクレタとマルタのように薄っぺらいのだ。
が、次郎は、それをうつくしい夢のように、うっとりした目でながめていた。彼の目には、天も見えなければ、地も見えない。ただ、彼をいだいている兄の顔が、――半面に月の光をあびて、じっと行く手を見つめている兄の顔が、やさしく、おごそかに映っている。彼は、限りない安息が、おもむろに心を満たして来るのを感じた。母のひざを離れてから、何年にも感じた事のない、静かな、しかも力強い安息である。――
「にいさん。」
馬上にある事も忘れたように、次郎はその時、しかと兄をいだくと、うれしそうに微笑しながら、頬を紺の水干の胸にあてて、はらはらと涙を落としたのである。
兄の額に将棋の駒を叩きつけたり、勝気な妹に手を焼いたり、知恵を使って交渉して見たり、当てにならないと見下げられたり、無理難題を押し付けられたり、母親の世話を押し付け合ったり、小遣いをやったり、大いに口げんかしてみたりと、年齢や関係性によって兄弟間にはさまざまな出来事が起こる。当たり前だが兄は母に置き換えられるものではない。
兄弟は友人ではない。家族の中の役割のようなもので、序列があり、地位がある。情愛に似た絆がある。しかし父や母とに対する絆とはまるで違う。兄弟がいない人間からすると兄や弟はおそらく想像のつかない生き物なのだ。
芥川は『偸盗』で一応は兄弟を書いてみた。けれど得心には至らなかった。これが本音ではなかろうか。
兄弟は二人がかりで沙金を殺す。
翌日、猪熊のある家で、むごたらしく殺された女の死骸が発見された。年の若い、肥った、うつくしい女で、傷の様子では、よほどはげしく抵抗したものらしい。証拠ともなるべきものは、その死骸が口にくわえていた、朽ち葉色の水干の袖ばかりである。
また、不思議な事には、その家の婢女をしていた阿濃という女は、同じ所にいながら、薄手一つ負わなかった。この女が、検非違使庁で、調べられたところによると、だいたいこんな事があったらしい。だいたいと言うのは、阿濃が天性白痴に近いところから、それ以上要領を得うる事が、むずかしかったからである。――
いやいやいや。
これはおかしい。朽ち葉色の水干の袖は次郎のものであろう。
別して、老婆の目をひいたのは、その小屋の前に、腕を組んでたたずんだ、十七八の若侍で、これは、朽ち葉色の水干に黒鞘の太刀を横たえたのが、どういうわけか、しさいらしく、小屋の中をのぞいている。そのういういしい眉のあたりから、まだ子供らしさのぬけない頬のやつれが、一目で老婆に、そのたれという事を知らせてくれた。
「何をしているのだえ。次郎さん。」
しかし阿濃の言うような状況ならば、朽ち葉色の水干の袖が咥えられる余地はない。
その夜、阿濃は、夜ふけて、ふと目をさますと、太郎次郎という兄弟のものと、沙金とが、何か声高に争っている。どうしたのかと思っているうちに、次郎が、いきなり太刀たちをぬいて、沙金を切った。沙金は助けを呼びながら、逃げようとすると、今度は太郎が、刃を加えたらしい。それからしばらくは、ただ、二人のののしる声と、沙金の苦しむ声とがつづいたが、やがて女の息がとまると、兄弟は、急にいだきあって、長い間黙って、泣いていた。阿濃は、これを遣り戸どのすきまから、のぞいていたが、主人を救わなかったのは、全く抱いて寝ている子供に、けがをさすまいと思ったからである。――
この説明と状況は微妙に食い違う。沙金には、朽ち葉色の水干の袖を咥える余裕などなかったはずだ。二人が仮で刃物で襲われて、袖を食いちぎる余裕などあるわけもない。何が起こったのかは定かではない。これは殆ど『藪の中』だ。「天性白痴に近い」から嘘はないというわけではなかろう。ここには自分の憧れである次郎が、元々惚れていた沙金を切り殺すという、阿濃にしてみればキュンキュンするような理想の物語があるに過ぎないのではなかろうか。
また私は阿濃が嘘をついたとも思わない。それは飽くまで彼女にとってのものの見え方なのだ。物証としての朽ち葉色の水干の袖は何も証明しない。それは阿濃のはげしい願望が現実化したものかもしれないのだ。
仮に朽ち葉色の水干の袖が食いちぎられたとして、太郎も次郎もそれを取り返さないことは無かろう。朽ち葉色の水干は阿濃にとって次郎が沙金を見限る証拠として意味があるだけで、それ以外の何の事実も示さない。
太郎と次郎の兄弟は阿濃という腐女子の描いたBL小説のキャラクターのようだ。
そんなものを芥川は書こうとしていたのだろうか?
[付記]
どこかに書いていたような気がしていたが、書いていなかったかもしれないので念のため。
この『偸盗』という話は「年の若い、肥った、うつくしい女で」というところで軽く落ちている。「え、沙金ってデブだったの?」と読者に言わせようとしている。
芥川龍之介の奥さんは芥川龍之介の晩年ころころと太っていたけれど、「肥った」は誉め言葉ではない。芥川の美観として、この「年の若い、肥った、うつくしい女で」というところはやはり皮肉なのだ。
これを「もしや沙金も妊娠していた?」と読むとミステリーにはなる。なるけれども、今一つ「ふり」が足りていない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
