
寒き夜や泥に凍るや火鉢かな 夏目漱石の俳句をどう読むか74

寒き夜や馬は頻りに羽目を蹴る
そういう音が聞こえてきた、という句であろうか。
ボコ、ボコっと。
寒いからといってなんで羽目を蹴るのか馬に訊いてみたいような気がするけれども私は馬語が話せないし、明治二十八年には行けない。そこは想像するしかない。
何かを不安に感じているのかな。
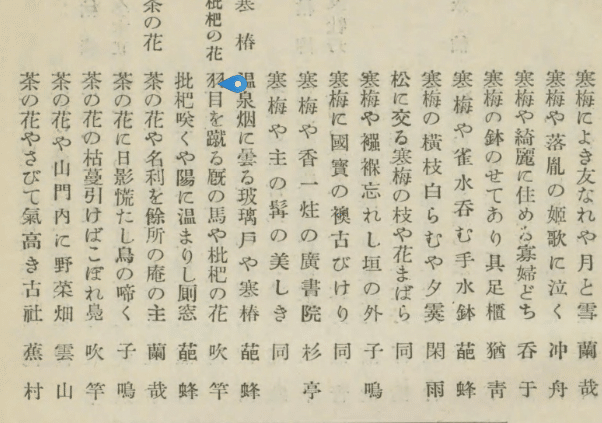
まあ馬は何かと羽目を蹴るもののようだが、
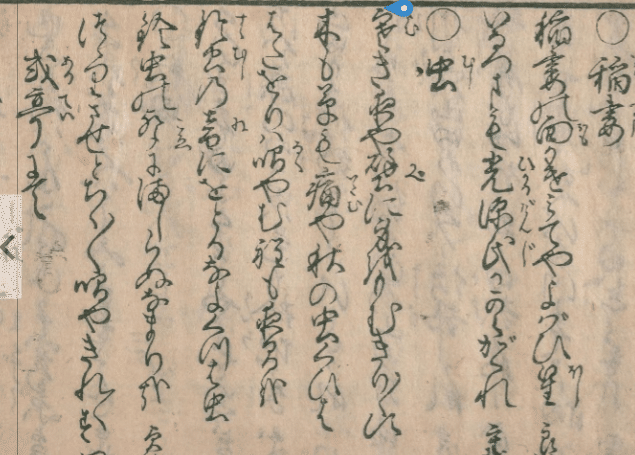
寒き夜や壁に身を揉むきりぎりす
きりぎりすも寒かったからもぞもぞしてたわけではないかもしれないが、そう見えた、という人間の側の感情が出てくるように、本当は馬は別の理由で羽目を蹴っていたのかもしれないが、ここでは大方寒いから蹴っているのだろうというように聞こえたという句と解釈しておこう。
さして含みのない句だと判断する。
馬というのは図体は大きいけれどそんなに賢くはないように思える。あまり複雑なことは考えていないだろう。深く考えてもしょうがない。

来ぬ殿に寐覚物うき火燵哉
例の「ついているついていないで自分の立場を入れてくる読み方はセクハラだ」式の話はまあ置いておくとして、女性身をやつして俳句を詠むというのはどんな感覚なのかなと考えてしまう。そう思えば紀貫之にしてみれば、今でいうところの「ネカマ」の元祖であり、そもそもそういうことは別に珍しくもなく、とくに変態的とかそういうことではなかったのかなと一旦は考えてみる。しかし詠まれている事柄が性そのものである場合少し事情が変わってくるようにも思える。
なんというか変態性が出てくる。
正直に言えば少し気持ちか悪い。
漱石はそこの感性に柔軟性があり、容易女性の気持ちにもなれるようだ。三島由紀夫にもそういうところがある。しかしそういうのはかなり例外的であって、書き手としての「ついているついていない問題」というのはなかなか深刻なもののように思える。
いずれにせよこの句は江戸の殿様なのか何なのか知らないが、通い婚らしい。火燵で寝ると風邪をひくので布団で寝た方がいい。そう思わせる句だ。

腰かけて待つのか?

酒菰の泥に氷るや石蕗の花
散々な扱いである。
いや、石蕗の花ではなくて、酒樽が。
この酒樽は空樽が樽拾いに転がされてきたものであろう。そうではなくては泥が付かない。それに押しつぶされた石蕗の花か張り付いて氷っていたと。
菰樽というものがおそらく日本ぐらいにしかなかろうから、日本ならではの俳句だ。外国人にはとても理解できまい。


最近は樽拾いも見なくなったけど、鏡開きとかした後はどうしているんだろうと考えさせる句である。

古綿衣虱の多き小春哉
うん。不潔。しかし蚤ならともかく、虱ならはたくか何かして一掃できそうなものだがどうなのだろう。日干しするとか。
この句も何か含みがあるようで捉えきれない句だ。衣虱に刺されて発疹が出来たよということなのか、頭虱も床虱もいないのに、衣に虱かと呆れているのか。
なんにしてもいろんな小春があるものだ。
[余談]
これ凄い話だよね。異国に自国の風習を持ち込んで通用させているってことだから。侵略行為だよね。燃やしていいんじゃない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
