
べつやうに眼置いたりみの蒲団 芥川龍之介の俳句をどう読むか92
森さんの歌は下手ですね僕の方がうまいでせうすなはち
秋ふくる昼ほのぼのと朝顔は花ひらき居り呉竹のうらに
[大正十一年十二月二十九日 香取秀真宛]
御一笑下さい、とある。これを笑ってあげなくてどうする。
なんと誰も笑っていない。季節外れの寝坊助の朝顔を皆無視する。
山々を枕にしきぬみの蒲団
[大正十二年一月六日 小穴隆一宛]
不二山を枕になしてねころべは足は堅田のうちにこそあれ
細川幽斎あるいは片桐且元あるいは前田利家の歌とされるものがある。
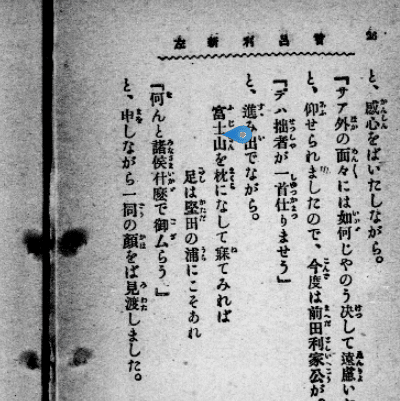


片桐には別バージョンもあり、
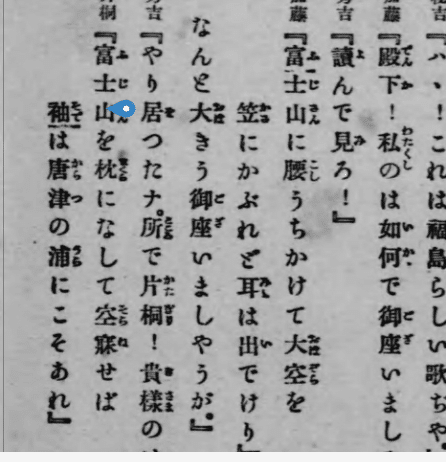
福島正則のバージョンもある。

こうなると加藤清正が黙ってはいない。もう何が何だかわからない。わからないが、にぎやかなことだ。

芥川の句はそういう狂歌的なものではなく、また
やうやくに恋にわたらぬ歌おほし寒き山をも枕とぞする
こんな詩情でもなく、かつまた西郷さんのように城山を枕に死なん、という覚悟でもない。
木曾山を枕にしたり蝸牛 一茶
遠景と近景の取り合わせの中で三枚敷いた布団で高くなった頭に遠くの山々が枕のように重なっているよ、というあり得ない句である。まるでぬいぐるみの要塞からもっさりと立ち上がる元少年Aを元少年Aが描いているような描写法である。ぬいぐるみの要塞からもっさりとした動作で起き上がるという表現は父親の手記をそっくり真似たかのようだ。
幽体離脱しないと詠めない句である。酒鬼薔薇くんの幽体離脱にも誰も気が付いてやらない。
酒鬼薔薇くんは「記憶の中で周囲を見回す」などという普通はできないことをさらりと書いている。やってみればいい。できないから。ストリートビューじゃないんだから、普通は一方向、顔面の前しか見えていない。
そんなことにも気が付いてあげないと、作者がかわいそうだ。
いや、芥川がね。
9一一. 1200500755305 142-Sh91ウ12 14.142 6 8 L 9 9ヤ3 2レml 20 6 8 L 9 (
911.142 SH91失西戶儀著法師道統社版
まへがき西行が人麿·芭蕉と並んで日本詩歌史のうへの三絕をなすことは誰しも異存のないところであらうが、その詩人としての業績に觸れたものとしては、わづかに故藤岡東圃の小論あるのみであるのは、何故であらうか。るのは、蓋し、蓋し、彼の文學は、今もなほあらゆる國民の胸奥に漂渺として遍滿する一つの名狀しがたい感情であり、しかも造形性を融解したそこはかとない表現を取つてゐて、このため古來彼ほど國民に愛せられた詩人がないにもかかはらず、彼の文學は、情であり、このため古來彼ほど國民に愛せられた詩人がないにもかかはらず、これを明晰に分解することを困難ならしめたのであら50この困難を知りつつ、故東圃博士の試みを承けて、私はここに敢へて最初の一鍬を下ろさうとする。したがつて、多くの昏迷や藪睨みや送巡を避け得たとは云へないにちがひない。しかし、西行を通らずして中世の精神史に一步も入れないことが明らかであるとすれば、西行論の成長の50この困難を知りつつ、とする。したがつて、しかし、1西行論の成長の
ための最初の足場となり得ることを私はひそかに光榮とする。西行寂して七百五十年、その遠忌は昨年三月河内弘川寺に營まれ、續いて十月に「佛には櫻の花をたてまつれ」の歌を彫つた碑の建立式があつた。地下の西行果して何を今日の精神史に投じようとするか。傳記は、尾山篤二郎氏の『西行法師傳』(昭和九年改造社版)、『西行法師の生涯』(昭和十三年富山房文庫本『西行法師全歌集』附錄)、ならびに、川田順氏の『西行』(昭和十四年創元社版)、『西行〓究錄』(昭和十六年同社版)によつてほぼ完璧に近く、殊に川田氏の著書に私は負ふところが多かつた。ここに多謝する。なほ、歌集は佐々木信綱氏監修の『西行全集』(昭和十六年文明社版)に據り、併せて尾山氏の富山房文庫本を參照した。但し、歌詞のいろいろな異同は私のよいと思はれるものによつて統一し、卷末の秀歌抄もその流儀に從つた。文献學が私の目的でないからである。昭和十六年十一月中旬東京市外、狛江村、泉のほとりにて宍戶儀- 2戶-目次西行法師論-一人麿影供三=新古今前後二五三庶民の歌と西行四九四自然と感傷七七五出離の日を繞つて戀旅とと一〇一3 *とと〓
西行秀歌抄西行略年譜八七西行後鳥羽院その他生涯とその完成法師論三三二三一七九三4
神風にこころやすくぞまかせつる櫻の宮の花のさかりを西行·-麿影供鳥羽帝の元永元年六月、六條家の歌學の基礎を築いたといはれる顯季の六條東洞院の邸で、人麿影供が行はれた。雨を冐して會したのは、長實、俊賴、顯仲、敦光、宗兼、道經、爲忠等の人たちで、すこし後れて行盛がこれに加はつた。『柿本影供記』の傳へるところによると、手に筆と紙とを持つた烏帽子·直垂の人麿像を正面に掛け、道の長者として推された源俊賴がまづ初献を奠めてから、各々歌を讀み上げてそれを講じた。「その起りといふは、白河天皇の御時、藤原の兼房といふ人、歌道に志深く、貫之、忠岑等の詞につきて、朝臣〔人麿〕を仰慕せられしに、夢中の感得によりて眞影を寫しとどめらる。最後にこれを帝に献る。これを島羽の寶庫に藏められしを、顯季奏請して寫し取り、これをもつて影供の大饗を設けられしこと、『古今著聞集』『十訓抄』等に見えたり」と『歌聖傳』はこの時のこと人3
を記してゐる。この催しが例となつて、後に土御門通親の三條坊門の亭で影供が行はれ、續いて和歌所で行はれたことは、『家長日記』に見えてゐる。また、鎌倉で同じ催しがあつたことは、『東鑑』の記すところによつて知られる。そして、この人麿影供が後世の歌會の會式の初めとなつたのである。六條家はいつたいに、平安朝末期の歌論史に寄與するところ少くなかつた有力な家柄で、殊に萬葉學の必要を唱へ、後には御子左家の古今派に對立して、萬葉〓究の中心勢力となつた。云ふまでもなくこの道統は六條〓輔の『奥儀抄』『袋草紙』、また同じく六條家から出た顯昭法師の『顯昭陳狀』『萬葉集時代難事』等に現はれ、その波紋がやうやく擴がつて、僧仙覺の大著『萬葉集註釋』が起稿せられ、賴朝が鎌倉幕府の基礎を置いた元曆元年には、有名な『元曆校本萬葉集』が成るに至つた。『類聚古集』『古葉略類聚鈔』等の部類分けした萬葉集も編まれ、『萬葉集抄』のごとき註釋書も出來た。かういつた氣運は、對立者である藤原俊成やその子定家をしてなんらかの萬葉管見を語らしめずにおかないくらゐであつた。源實朝の出現は、したがつて偶然ではない。定家が祕藏の『萬葉集』を實朝に贈つたのはよく知られてゐる話であるが、實朝はそれによつて4萬葉調を學んだわけでなく、當時に於ける萬葉〓究の風潮はすでにいち早くこの俊敏な靑年詩人26 183を捉へてゐたのである。事實、『金槐集』が出來たのは、定家の祕藏本寄贈にまだ接しない頃であ9つた。ところで、何故にこの頃に至つて萬葉〓究が起つたのであらうか。その理由は、ひとくちに云つて、三代集以後の歌界の著しい沈滯に求められる。『古今』の反芻が『後撰』『拾遺』と續き、さらに『後拾遺』と繰り返されるに至つて、王朝人の詩情はまさに涸れ盡さうとし、「世降り人のこころ劣りて、たけも及ばず、詞も卑しくなりゆく。況んや近き世の人は、ただ思ひ得たる風情を三十字に云ひ續けむことを先として、さらに姿、詞のおもむきを知らず」(近代秀歌)と語られるやうな狀態に立ち至つた。すなはち、「むかしはただ、花を雲に擬へ、月を氷に似せ、紅葉を錦に思ひよするを、おかしきことにせしかど、今はそのここち云ひ盡して雲のなかにさまざまの雲をたづね、水にとりて珍らしきを云ひそへ、···かやうに嗜みて思ひうれば、珍らしきふしは難くなりゆく。まれまれ得たれども、昔を詔らへる心どもなれば、賤しく碎けたる樣なり。況んや言葉に至りては、云ひ盡してければ珍らしき詞もなく、目とまるふしもなし。殊なる秀逸ならぬは、五
七五を讀むに、七八の句はそらに推し量らるるやうなり。」(無名秘抄)和歌支學のこの危機に際して、たとへば本歌取りなどによつて辛ふじて歌に縋りつく人たちの間に、とにもかくにも『古今』の限界外にある表現と考へられた『萬葉』への模索が行はれたのはすこしもふしぎでない。當時、保守派の人々を驚かした曾根好忠のごときは、まさしくさういつた模索の一例であつた。また俊賴も明らかにその一人であつた。紫陽花の花のよひらに洩る月を影もさながら折ることともがな。掃く人もなきふるさとの庭の面は、花散りてこそ見るべかりけれ。白河の春の梢を見わたせば、松こそ花の絕え間なりけり。この里も夕立しけり、淺茅生に露のすがらぬ草の葉もなし。なごリなく時雨の空は晴れぬれど、また降るものは木の葉なりけり。鶉なく眞野の入江の濱風に尾夜波よる秋の夕暮。あはれにも、操に燃ゆる螢かな、聲たてつべきこの世と思ふに。繊銳な感覺を通じてかういつた妖艶·幽暗の美を描いた俊賴の歌は、時代の危機を蔽ふかのやに强い光を放つてゐるが、考へてみれば、このやうに感覺的に銳く對象に切り込むことは、知らずしらずのうちに理智的な角度で物を捉へてゐることであつて、そのかたはらで抒情の分解が行はれつつあることを示してゐる。抒情としての内的震蕩が停つて疎らな感覺的反射、それをつなぐ理智的な奇趣がこれに代るのである。事實、『詞花集』になると、子の日すと春の野ごとに尋ぬれば、松にひかるるここちこそすれ。」取りつなぐ人もなき野の春駒は、霞にのみやたな引かるらむ。いかなれば氷ほとくる、春風にむすぼほるらむ、靑柳の絲。のやうな、俊成の謂はゆる「ざれ歌」が少くない。歌も、ここまで來ればおしまひであらう。の危機に際して、『古今』の道統に還るべく必死の力を傾けながら前代のあらゆる遺產を綜合して『新古今』の新風を樹立したのが藤原俊成であるが、『萬葉』、に新趣を見出さうとして焦つた源俊賴をそれとは意識せずに彼が宗としたのは興味ふかい。好忠や俊賴にしても、また六條家の萬葉7
學者たちにしても、行きづまつた歌界から何とか逃げ出さうとして純りつきはしたものの、彼等と『萬葉』との間には、仰ぎ見ることすら至難な斷崖が聳え立つてゐた。大伴家持の時代からわづか二世紀と隔つてゐるわけではなかつたけれども、その間の失墜のすさまじさに比べることのできる他の時期を私は知らない。王朝人の痳痺しきつた人工心理には、『萬葉』はあまりにも懸け離れた世界であり、もしも求められるものがあるとすれば、それは表現の變つた趣好のためである。前代に於ける失墜の深さを知るには、東人の荒ぶる魂をなかばその血統に示け繼いだ右大臣實朝まで待たなければならなかつた。中世的重壓を身みづからの試錬に代へて神典に於けるますらをの道をこの地上に再確立するに至るその久しい道程の初めの日に、「愚かに用心なくて文の方」に溺れ「大臣の大將汚し」たのみでなく「また跡もなく失せぬるなり」(愚管抄)と罵られた實朝のまだ深い憂愁を堪へた働哭の歌がまづ流れはじめたのである。8今日の人たちはよく、『萬葉』のヘレネ風を讃へ、それが古代日本人の內生活の理想的な型であつたとする。世界文學のうへから見てその壯觀はまことに蓊欝たるにちがひないが、民族の精神史のうへでむしろそこに頽廢の進行を讀むところに我々の新しい出發があることもたしかであら50我々はそれを一つの大きな傾斜面に於いて捉へる。この斜面につづくのは、無限にずり墜ちる者の自意識喪失である。白鳳から天平に至る時代は、文化文物の爛漫たる開花によつて飾られた未曾有の隆盛期として知られてゐる。我々の國が文化國として浮び上つてきたのは、たしかこの時代である。しかし、空間的に固定せしめられたいはば可視的な文化文物の高さは、「精神史のうへから見て必ずしも高い指標を得るとは云ひがたい。むしろ、文物·制度の華やかな布置のうしろには、巨いなるものの失墜の軋みが聞かれたのである。私はその軋みの一つを天武紀に於ける大津皇子の變に聞く。その年六月、草薙の御劍が熱田の社に納められた。そしてその翌月に朱鳥と建元された。白鳥ではない、朱鳥である。思へばそのことすら一つの悲劇的な豫感となつた氣がする。九月に帝の崩御があり、その翌月、皇子に死を賜はつたのである。皇子はいはば、後世欝結の日の小確命であられた。持統紀に詩賦は大津皇子を始まりとしてゐるくらゐで、その御作は『懷風藻』の詩人た
ちの先登を切つてゐるが、この詩賦といふ異國の樣式を取られた點にも、典笑に包まれた皇子の風流の豪奢なイロニーが拜せられるやうにすらおもはれる。「遊獵」と題して、10朝に三能士を擇び、暮に萬騎の筵を開く、鬱を喫ひて倶に豁笑し、盡を傾けて共に陶然たり。月の弓、谷裏を暉かし、雲の旌、嶺前に張る、曦光巳に山に隱るれど、壯士且らく留連せむ。豪華な饗宴の日に臨んだこの堂々たる帝王調を見よ。「壯に及んで武を愛し、多力にしてよく劍を擊つ。性すこぶる放蕩、法度に拘はらず、節を降して士を禮す。ここによつて人多く附託すといふ『懷風藻』の批評はおそらく皮相であるが、しかも皇子の御風貌を或る程度まで傳へてゐる。天文、ト筮を解する新羅の僧行心が「太子の骨法これ人臣の相ならず」として蹶起をお奬めした、といふ記事の信じがたいことは勿論であるとしても、運命的な悲劇の影は御身邊に深く漾つてゐたのかもしれない。御臨終に際しての御作-る。金鳥西舍に臨みて、鼓聲短命を催す。泉路實主なし、この夕家を離れて向ふ。悲愴深沈、まさに有馬皇子の結松の詠に比せらるべきであらうが、これと同時に歌はれた「百傳ふ磐余の池に鳴く鴨を今日のみ見てや雲隱りなむ」の御作にその莞葡たる御微笑を仰ぐとき、この悲劇の深さが初めて我々の眼にありありと浮き上つてくる。身をもつて購はれたこの微笑が一瞬にして消え去つたとき、皇子の踏まれた土のひとくれまでが搖らぎはじめた。上昇と失墜。丹11
靑のいろいろな甍や壁が天に麗はしく浮び上るにつれて、神々のうめきと嗚咽とがどこかで入り亂れた。そしてその嗚咽のなかには、皇子の御陵のある二上山の麓に立たれた姉君·大伯皇女の純白眼に泌みるやうな美しい哀唱が幽かに搖らめいた。12うつそみの人なるわれや明日よりは二上山を兄弟とわが見む。磯のうへに生ふる馬醉木を手折らあど、見すべき君が在りといはなくに。壬申の亂が鎭まつてからも、次々といろいろな移り變りがあつた。飛鳥淨見原への遷都に次いで人材登庸の詔が發せられたのも、前代から引き續いて高まつてきた抗しがたい文化への激情であつた。一切經が河原寺で寫され、僧侶の服制が定まり、宮中や諸寺院に於いて初めて金光明經が說かれた。藥師寺が建てられ、家每に佛舍を造つて禮拜供養せしめられることになつた。文武官の考續進階の制が定められた。禁式九十二條が立てられた。諸姓八等、爵位六十階を定めた外に、新制は儀禮、言語、結髮のはてにまで及んだ。龍田、大江の二關が築かれ、難波の築城が成り、諸國の邊彊が定められた。諸道政道の巡察も行はれた。占星臺が興され、帝紀の撰修が命じり、られた。大陸文化との接觸がいよいよ繁くなつた。しかも、すべてこれらの變化は、波濤にも似た汪洋たる勢ひを伴つてゐた。この趨勢はやがて和銅三年の平城遷都からさらに倍加して天平の盛を招くのであるが、その天平と白鳳との間にすらすでに深い間隙があつた。たとへば藥師寺金堂の藥師三尊を仰ぐとき、端嚴雄偉なその深沈たる無言の觀想のうちに、さういつた失墜の底知れぬ空間を暗示してゐるかのやうにおもはれる。失墜-無限の憤ろしい失墜その深淵を覗いた者の知的眩暈と慟哭こそ、白鳳期の大詩人·柿本人麿の世界であつたのである。人はよく人麿の慟哭といふことを云ふ。たしかにその歌は慟哭にほかならない。しかも、それは、皇運の無窮を祈り奉らうとする草莽の民の鳴咽でもあらう。とはいへ、かういつた嗚咽がつねに危機の日にのみ現はれることを省みなくてはならぬ。交化國家への〓情が激流となつて高まり、社會的變化が次々と慌だしく傳へられたとき、國風の〓養のなかに育つた曇りない人麿の感受性には、失墜の危機が、否その進行が、大寫しとなつて迫つたのであつた。大津皇子が御年二十四で薨ぜられたことなども、年少多感の彼にはおそらく强い衝撃であつたにちがひない。なほ、それにもまして人麿の心を烈しく搖すぶつたのは、氏族共同體の崩壊に伴ふ過渡期の測13
り知れぬ不安であつた。その一つの現はれは、盜賊と浮浪の續出であり、早くも天智帝九年にそのため戶籍を造つた記事が書紀に見えてゐるが、『續日本紀』の時代になるとやうやくそれが頻繁化して大きな社會問題になつてゐる。「街衝に零疊して妄りに罪福を說き、朋黨を合構し、指臂を焚剝して歷門假說、强ひて餘物を乞ふ」(靈龜元年五月條)として罰せられた僧行墓が出現したのも、「率土の百姓四方に浮漫して課役を規避しつひに王臣に仕へ、或ひは資人を望み、或ひは得度を求む」(養老元年五月)といふ狀態に於いてであつた。人麿と同時代であつた役小角が伊豆に流されたのも、文武帝三年のことであつた。そしてその前年に藥師寺の落成式が華やかに行はれるかたはら、答法を制して博戲遊手が禁じられた。私はひそかに、崇神紀に初めて見える疾疫蔓延の記事をもつて、古代崩壞の最初の徴表であつたと考へてゐるが、禁令を布くまでに至つたこの頃の博戲流行こそは、大陸の文化に接して蒙つた民族精神の頽廢を示すものであらう。祖神たちの内部に湧いてゐた自然の〓冽な泉はやうやく濁りはじめた。すでに大化以前、「この神を祭る者は富と壽とを致さむ」として常世神の信仰が流布したのも、各自の血統のなかに息づく祖神たちのかはりに抽象神が漠然と求められるに至つたことであり、それみづから神々の失墜を示してゐ14これに加へて、民間の神祗崇拜を廢して國〓としての佛〓を强ひようとした上からの壓迫を通じて、民間信仰が漸次に佛〓に腐飾せられ、神道と佛〓との混淆が行はれた。かうして、役小角、行基等の佛說が神道的色彩を帶びてゐるのは當然のことで、この傾向がやがて本地垂跡へと定決的に推し進められる。白鳳から天平の初めにかけての謂はゆる「公地公民」の時代は、氏族社會の大崩壞と莊園の發生との暫時的聯鎖のうへに立つた一つの均衡期であつで、史上に稀れな活氣橫溢が見られるとともにその足下には、直ちに涯しない失墜の眩暈が渦卷いてゐた。壬申の亂に於ける大津政府の敗北は、土地私有制への滔々たる步みを進めつつあつた大和の新興貴族を中心とする一派の指導精神に破れたためであつた。さざなみの志賀の大わた淀むとも昔の人にまたも逢はめやも。廢墟に立つてかう歌つた人麿の心のうちには、壬申の亂が强く閃めいてゐたにちがひない。さざなみの志賀津の子らが罷リ道の川瀨の道を見ればさぶしも。もののふの八十氏河の網代木のいさよふ波の行方知らずも。15
近江のうみ夕浪千鳥汝が鳴けば、心もしぬにいにしへ思ほゆ。16大友皇子の妃が天武帝と額田姫王とのあひだにお生れになつた十市皇女であつたことなどに對して、この多感な詩人はいかになまなましい感慨を抱いたことか。結局、殘るものは、生けるものへの働哭に充ちた深い憫れみと過ぎ去る時劫の涯しなさ、そしてまた失墜へのやりどころない憤ろしさであつたらう。かうして彼の挽歌には、ほとんど絕叫にも近い魂の哀哭と憤怒とが漾つてゐる。「しきたへの袖交へし君」の歌を評して「悲しみの心が自然に深くひそむのでありまして、その潜む力が、單なる悲しみを通り越しで、人生の究極に想ひ至らせるほどの力をもつてをります」(『歌道小見』參照)と云ひ、また「あしびきの山川の瀨」を評して「この歌は、人麿の雄渾な性格に徹しておのづから人生の寂寥所に入つてをります」(同)と述べた、島木赤彥の會つての批評は、人麿の心臟部をいきなり直指してこの間の消息を傳へてゐる。賀茂眞淵も、「勢ひは雲風にの云りて空ゆく龍のごとく、言は大海の原に八百潮の湧くがごとし」とその英雄的悲劇精神の雄大さを歎じてゐる。混沌の重みに抗するかのやうなこの憤ろしい號哭には、祖神たちの會つて知らなかつた「死」なるものへの絕望的格闘が現はれてゐる。すなはち、人麿に於いては失墜のすさまじさは、まづ死への意識を通じて訪れたもののやうにおもはれる。宗不旱氏はその新釋『柿本人麿歌集』のなかで、人麿の眼に映ずる事象はことごとく神なる自然であつた、と論じてをられ、たしかにそのとほりであるが、その「自然」にすでに蔽ひがたく浪曼的龜裂が現はれてゐたことも事實であら50神人分離の日のいはば殘燭の乏しい光と化した、しかしそれなしには全くの闇に鎖される、最後の一點こそ、この詩人の悲劇的運命ではなかつたか。ともあれ彼は、異國の文化や疫癘とともに入つて來た死の現象をしばしば嚴肅に覗き込む。「見香具山屍悲慟作歌一首」と題して、くきまくら旅の宿りに誰が夫か、國わすれたる家待たなくに。また「讃岐狹岑島視石中死人」として長歌を詠じ、これに反歌二首を添へてゐる。17要もあらば採みて食げまし、佐美の山、野の上の蒐萩過ぎにけらずや。
TA沖つ浪來よる荒礦もしきたへの枕と經きて寢せる君はも。18わけても人麿が深い感慨に打たれたのは、文武帝三年に入寂した僧道照から始つた火葬の式であつたらしい。「土形娘子火葬泊瀨山時」と題して、こもりくの泊瀬の山の山の際にいさよふ雲は妹にかもあらむ。また、溺死した出雲のうら若い女性が吉野山で火葬に附された時の歌にも、諦觀のなかに佇ましめる影ふかい哀感が漾つてゐる。人をして言ひ知れぬ山の際ゆいづもの兒らは霧なれや、吉野の山の嶺にたなびく。:八雲さす出雲の子らが黑髪は、吉野の川の奥になづさふ。かういつた死への意識を通じて、現世の限界が初めて大きく浮び上つてくる。「讃酒歌」等の萬葉人をもつて古代日本人の素朴な人生論だなどと考へてはならぬ。それは我々の祖先たちに初めて訪れた魂の荒廢を反映してをり、それが、やがて御堂關白時代の現世的榮華へ、したがつてそれをさらに裏返ししたときに出てきた中世の宗〓的不安へとつながつてゆくのである。人鷹は、しかし、現世主義に逃避することなく、深淵に面して知的眩暈によろめき渾身の力をこめて生への激しい働哭を歌つた。しかし、「いさよふ波の行方知らず」滔々と流れ去るものの聲々がたちまち騷然と彼の耳朶を打つたとき、現人神の知ろしめすこの國土の姿がただ一つ流れに抗する無窮の磐石として立ち現はれたのである。それはむしろ悲願であり、それゆゑに慟哭のひそかな吸り上げに充ちてゐる。それは、危機の日に際會した歷史の烈しい霧笛であり、したがつて民族としての輪廓ある〓念のうちに總括されなければならなかつた。すなはち、すめらみくにの無窮の步みを體視することだまの幸は、それみづからの失墜に面して、ここでは明らさまな抽象の形を取らなければならなかつた。人麿の歌はいはば、言靈失墜を痛む聲であつたとも考へられる。周知言靈ののとほり、山上憶良に、「······そらみつ倭の國は、皇神のいつくしき國、幸はふ國と」云々と續けられた「好去好來の歌」がある。しかし、これは、言靈へのすでにダンディーと化した空しい追想にすぎなかつた。そこには、破れた胡弓をまさぐる知識人·憶良のなさけない自已分裂19
が見られる。「貧窮間答」をなんらかの社會的な情熱と見たがるのは現代のおそろしい藪睨みで、おそらくこの歌には、作者のさういつたなさけない困惑と窮迫の姿勢の外には何もないのである。現世さへ樂しかつたらと歌つて大伴旅人が酒を讃へたとき、その逃避的ディレッタントの心情は、まもなく家持のサロンを形づくらうとしつつあつたのであらう。そして、それはまさしく『古今集』への道であつた。個々の生活の內壁をいろいろにかき變へて細かに映し出す心理主義-竹の葉を吹きそよがす幽かな風の音に思ひをひそめ、麗かな春の日の雲雀の聲にかへつてひとり寂寥を感ずるといふ、その纎細な感情裝飾は、それみづから囘顧的、遊離的であつて。生活がもはや主體としての質的深淺を失つたことを意味する。天平の三月堂を照してかの寶冠の繊細な飾りが初めて眩ゆく搖らめいた日、大伴家持のサロンは、もはや決定的に次代への方向を語つてゐた。ここに始まる道をもつて、生活を豐かにしその端々を浪曼化する藝術と讃へ、それ以前を單なる生活の〓奮の叫び、本能だけを歌つたものとする者があれば、さういふ人たちと私との間にはまさに越えがたい國境が存する。前代からの失墜の深さを速力とを肯じない人たちと共に、歷史を語ることを私は拒絕したい。家持にすら「劍太刀」を按ずる夜半の激越な流涕があつたことを20私は考へるのである。奈良朝に於ける文化運動の中核となつた現人神證歎の聲は、盛唐の文物を移した「咲く花の匂ふがごとき」都大路から擴がつてゆき、この神としてのすめらみことの尊貴神聖が、儒〓の君德觀や天人感應思想によつて修飾せられ、さらにまた佛〓の示す王法の理想に彩られた。宣命に祝はれたやうなもろもろの瑞祥が現はれるとともに、大小の黄金佛が次々と鑄られ、國家慶福の祈りのために「諸國の華」國分寺が建立せられた。しかし、熱情のこのやうな抽象的放散には、何かしら只ならぬ無氣味な影が感じられる。果して、黄金の大佛のうしろには僧侶の墮落が動き、政界にも多くの陰謀や虚僞が絡まり合つてゐるのであつた。そして、さういつた暗黑面を曝け出してかの道鏡事件が持ち上つたのである。しかし、ここまで來れば人麿からあまりに離れてしまふ。私はただ、白鳳期を最後の抵抗とした崩壞と失墜の激しさを語りたいのである。とはいへ、人麿の詩そのものがすでに、失墜を傷む21
聲であつた。言靈の痛ましい抽象であつた。したがつて、彼以前の神人のおほらかな歌のひびきに比するとき、そこに蔽ひがたい彼の限界が見られる。あれほど絕讃の辭を惜しまなかつた眞淵が「上つ代の歌を味ひみれば、人麿の歌も巧みを用ゐたるところなほ後につく方なり」と評してゐるのも、單に技巧に就いてだけのことではなからう。しかるに、人麿から家持までになると距離はさらに著しくなり、『古今』の時代に至ると、人麿の姿ははるか視野の外に沒してしまふ。それは歌聖としてだけ傳へられるやうになる。しかも、それが家持歿してわづかに百二十年の後であつたと知るとき、我々はその埋沒と荒廢のすさまじさにただ茫然とせずにゐられない。玉炭、にあつては、忘却したといふよりは時の距離感がむしろ失はれたのである。ましてそれ以後の人たちには、『萬葉』も『古今』も古典といふ點でなんら變りはなかつた。釋阿が『古來風體抄』に論じてゐるところであるが、『萬葉』の歌はやさしいことを難かしく言ひ表はしたなどと考へる(後後遺』序その他)ほど、當時の人たちは歷史的感覺を喪失してゐたのである。このとき雨季の陰翳ふかい顯季邸で催された人麿影供は、果していかなる意義を含んでゐたか。ただ我々が知るのは次のことである。22示寂のすこし前、後鳥羽院の御下問にしばしば奉答した時のこととして、西行が「貧道は歌は知らず待れど、ただ雅意に任せて申さば、『萬葉集』ぞ神妙の限りにて侍れ。さて人丸こそ歌の善を盡し妙を極めたる開闢にて侍れ。赤人、家持相次げり。すべてこの集の歌は、これはいかがあらむと思ひ候歌までも、みな神代の氣ありて妙なり。その後業平が詠める、また神代の氣に長出して妙なり。『古今集』の頃、貫之、躬恒に至りて、詞、美を好み、體、艶を樂しみければ、神代の氣長く廢れてみな人代の氣となれり。これよりこのかたの歌、上を離れて下に趣けり。惡くなれるの端なめり。しかはあれど、この集は、これはこともなきかなと見えぬる歌までもみな君子の氣あり。『後撰集』に至りて、美も失せ艶も廢りてことごとく惡き地に落ち着きたり。『後拾遺』君子の氣みな盡きて、げに凡俗の限りにて侍れ」と述べたことが『水無瀨の玉藻』に載つてゐる。この文献の眞疑の程は知らないが、論旨だけはおそらく眞に近いと見てさしつかへなく、若い頃から彼は『萬葉』に深く學ぶところがあつたもののやうにおもはれる。今はほぼ眞書と認められてゐる『西公談抄』のなかでも、「梅の花の歌〔梅の花それとも見えずひさかたの天霧る雪のなべて降れれば〕は、凡夫のこころ思ふべきにあらず、大なる歌とはこれを云ふなり。叶ふべきこと23
にはあらねども、歌はかやうに詠まむと思ふべし」として人麿を絕讃してゐるのを見ても、『萬葉』に對する秀拔な見解がうかがはれる。ともあれ、この書に述べようとする後の西行·佐藤義清は、永元年に胍々の聲をあげたのである。彼の24初めて前述の人麿忌の營まれた元二新古今前後平安朝の文化を彩る華やかな宮廷文學の發生が藤原氏の後宮政策によるところ大であつたことは、更めて說くまでもない。後宮のいろいろな局に、多くの美しい女性がそれぞれ一門の浮沈を荷つて對立し、それらにまた數々の上薦女房が繞つて互ひに綺羅を爭ひ才藝を競つた。これらの才女たちは、絕えず對立を意識して〓養を怠らず、博識、機智、心ばへに於いて、いささかも他に選色を見せないやうに努めなければならなかつた。このやうにして、頽唐の日の文化が著しく女性化するのに照應して、前後に比を見ぬ鬱然たる女性文學が花咲くのであるが、裏面には、もちろん、その女性を政略の具とする者たちの陰險な策謀、醜い嫉妬、卑屈な中傷などが入り亂れた。そしてまた、それがそのまま女性たちの運命に暗く投影した。『源氏物語』の女性のうち、藤壺、空蟬、朧月夜内侍、女三の宮、浮舟のごとき、會つて最も華やかに描かれた美しい人たちが25
やがてみな尼僧としてみほとけに仕へるに至るのも、明らかにこの間の消息を傳へてゐる。最後に逃れる所はやはり穢土からの出離の外になかつたのであらう。一京の貴族は、すべて、莊園から離れてゐてしかもその莊園からの貢納だけで生活する奢侈的浪費者であり、初めから國民の生活と遊離して無氣力を極めてゐた。かうして、骨肉間にさへ見られた日常の險しい暗圖、これに伴ふ露骨な後宮政策、爲すところない女性的な室內遊〓の數々等が生れた。京からごく近い播磨を指して發ち去る時ですらほとんど生けりともなかつたくらゐ、彼等の萎縮は甚だしかつたのである。牛車に御して都大路を往き交ふ時ですら、夜などはふと百鬼夜行の恐怖に襲はれることがあつた(大鏡)。事實、『今昔物語』を初めこの頃の文献に見えるやうに、驛路制の壞頽とともに賊が到るところに猖獗を極め、それが京にまで出沒して內裏の女官を襲ふたこともあつた。袴垂保輔、茨本童兒などの名もこの頃のものとして傳へられてゐる。とにかく、沈滯と萎縮とによつて著しく消極化した貴族たちの心意は、何か思ひがけないこと、たとへば水鳥が門前の木にとまつたとか、寺に參詣に行くと蛇が堂上に落ちて死んだとか、狐が殿上に昇つた最後26とか、人魂が飛んだとか、異雲が出たとか、さういつたことすべてに肝を冷し、それを怪異の象として陰陽師に占はせるのであつた(小右記)。.まして天象の異變のごときは、國家大變の徵として恐れられた。かうして、陰陽、曆天文等の迷信が生活を制限し拘束すること非常なもので、火災防止のために女房の衣に緋色を禁じ年號などに火に關係ある文字を避けるまでに至つた。冷泉院はもと冷然院であつたのが、然の字が火に關係あるためさう改められたといふ。そのやうに萎縮しきつた貴族たちが生きたここちを取り戾したのは、自身の心の世界に於いてだけであつた。世界は心の外にないといふ『方丈記』の著者の世界觀こそ、すでに一般にこの人たちのものであつた。『榮華物語』によれば、地獄も極樂もつまりは人のこころのなかに存する。彼等はこの生活をおもむろに几帳の蔭の幽暗な「こころ」に溶解した。生活はことごとく心情の澱みに浸され、その中でいろいろな綾を織り翳をつくるところに「あはれ」「おかし」「いみじき」等の味ひが生れる。そしてそれらは、女性的心理のもつ迂曲した纎細な線と相俟つて、特殊た耽美的世界をつくり出した。對象としての自然はすつかり影をひそめ、その朧ろな反映を繞るいろいろな心の屈折だけが捉へられる。云つてみれば、水面に投影する物の姿や色彩が魚眼に映つて27
妖しく伸び縮みするやうに、外界の朧ろな反射を集める「こころ」の密室に閉ぢこもつたのであzoo胸の奥にこそ世界があるとすれば、そのことはまた、そこに棲むものがひとりでに遊離して彷ふのを防ぐすべがないことであつた。すなはち、夢と現實との間になんら境界を認めないことであつた。否、夢こそは魂の行爲そのものであつた。怒りや嫉妬に燃える魂は、夢となつて實際に相手に打つてかかることもできる。たとへば『源氏』の六條御息所は、葵の上に對する嫉妬と屈辱の念によつてむらむらと起る「うかれた心」をどうしやうもなく、ふとまどろむ夢にも葵の上のもとに到つてなぶりかなぐると見ることがたびかさなる。夢さめては「あなこころ憂や」と自分のあさましさを嘆くのであるが、夢はしかも現實に作用して葵の上を苦しめ、夕霧出產と聞いたときつひに葵の上を殺してしまふのである。夢かうつつ、うつつか夢、その定かならぬ魂の彷徨は、ひとり『更科日記』の著者ばかりではなかつた。この日記の著者は、夢の〓へにいくたびか背いて、曾つての夢の鏡に見えた「ふしまろび泣く」運命に陷つたのを知り、思へば一生こそは夢であつたと嘆く。そして、殘されてゐるたつた一つの夢に心身のすべてを託さうとする。すると、或る夜の夢に、蓮花の座に立つ金色眩28とい阿彌陀佛が現はれ、「このたびは歸りて後に迎へに來む」と約されたのであつた。この最後の夢のさとしをただ一つの賴みとしてそれから暮すことになるのであるが、思へばこれとても夢のなかの夢のうき世の人生である。平安朝の心理主義は、一四、このやうな擬浪曼的夢想となつて優婉さを增すのである。うつつとて誰ちぎりけむ、さだめなき夢路に迷ふわれはわれかは。(後撰集)しかし、夢とうつつとのかういつた相卽には、たとひその底に求法のこころを秘めたとしても、現世主義をまだまだ否定してゐるわけでなかつた。たとへば丹後國の一聖人が每年大晦の夜、童をして戶を叩かせ、「極樂世界より阿彌陀佛の御使なり、こ、の御文奉らむ」と云はせ、みづからその文をおし頂いて「臥しまろび淚を流して泣」いた(今昔物語)といふ話のごとき、夢とうつつの境に淨土を觀ずるはかない遊樂として、御堂關白の法成寺供養などと本質的に差別があるわけでない。源〓蔭ほか四人の男女が集つて「世の中のはかなきこと、世間のあはれなること」を語り合つたとき、「云ひつつも世は儚きをかたみにはあはれといかで君にみえまし」と〓蔭が詠んだ29
ので皆がよよと泣いたといふ(大和物語)。愛欲への耽溺に日もこれ足りなかつた人たちにこそ、このやうな嘆きは深かつたであらう。しかし、嘆きが同時にそこはかとない歡びであり、その歡びが哀れな嘆きをひそめてゐるところに王朝人の纎細な心情があつた。歡びにしてもまた悲しみにしても、その本然の姿に接するには彼等の心はあまりに脆く且つ弱かつた。哀歡の交叉する姿をさらに間接化しそぞろに哀しく美しく彩つてこれを味ふところに、「もののあはれ」が生じたのである。この際に於ける間接化の作用が風流と呼ばれる。風寒い越中國に客死したとき、臨終の說〓者に向つて「中有の旅の空には嵐に類ふ紅葉、風に隨ふ尾花などの本に松蟲などの音などは聞えぬにや」(今昔物語)と息もたえだえに問ふたといふ藤原惟規のごときは、死に至るまで風流に執してつひにこれとともに終つたものと云ふべきであるが、「夢と現實の間に架したこの耽美的な現世主義こそ王朝人の心理的核心であつたのである。30しかるに夢とうつつとの定かならぬ連續は、末期に至るに從つて悲劇的な相貌を呈し、凝然と虚空を見つめる不吉な表情と化してくる。そしてそれが「つかのまの闇のうつつもまだ知らぬ夢より夢に迷ひぬるかな」と歌はれた式子内親王に於いて極まり、『新古今』の詠風を側面から特徴づけるのであるが、西行法師はこの内親王と世代をほぼ同じくしてゐた。現世主義の日が終つて堪へがたい痛恨が訪れてきたのである。院政の開始によつて貴族政權の崩壞が表面化しはじめた頃には、すでに京の衢は、何かしらけたたましく喚いて右往左往するものの影に騒然としてゐた。思へば、永長元年夏の祇園祭に於ける田樂のごときは正氣の沙汰でなかつた。その十日も前からの催しに下人、靑侍が群がり騷いで往反を妨げ、『中右記』の著者をして「時の妖言の致すところか」と嘆ぜしめてゐるのはまだしもとして、當日に至ればすでに禁中に人なく、その騷ぎが一と月も續いてつひに天覧に及んでゐるとあつては、そこには何か只ならぬものが感じられる。針が狂つてゐて、ちよつと觸つてもたちまち極端と狂態とに陷る、時代の異常な心理が考へられる。騒然と踊り狂ふ興奮とともに、放心狀態の心の弛緩があつたのである。そのかたはら、外からは京を包圍して自己を形成しつつある武門の壓力が瀧口、北面の武士としてやうやく宮中にまで現はれ、武力と冥罰とに訴へながら迫31
つて嗷訴する諸山の僧兵を退けるためだけでも、武士の影は彼等のうへに急激に擴がりつつあつた。のみならず市中の治安はますます紊れてゐた。人の心はどこか氣違ひじみて殺伐となる。「佛法は火をもつて滅ぶべし、王位は軍をもつて止むべし、その期十月十七、廿五、十一月五日な0) (中右記)といふ無氣味な落書が院のなかに現はれる世の中となつた。かういつた情勢は、自己の沒落を感じた貴族たちの間に深い絕望感を擴げずにはおかなかつた。たとへば、事ごとに「佛法、王法の破滅する時か」といふやうな嘆聲を繰り返した『中右記』の著者·藤原宗忠のごときは、「天下の大亂」の近いことをしばしば豫感したやうなことを述べてゐるが、このときはすでに保元·平治の亂の後であつて、果してやがて、平氏滅亡が「天下の滅亡」と見えるほどの「大亂となつて勃發するのである。奢れる者も久しからず、ただ春の夜の夢のごとし。猛き人もつひには滅びぬ、ひとへに風の前の塵に同じ。」まことに平曲の語るやうに、藤氏もかくやと思はれた平家一門の榮華も一代のうちにはかなく消え、威望飛ぶ鳥を落した强氣の〓盛が遠い流人の幻影に脅えながら奇病に斃れる。平家の軍を粉碎して京洛に入つた豪勇の若武者·木曾義仲も、やがて粟津の原の露と消32える。平家は西國に據つて頽勢の挽回を求めるが、運命すでに決して壇の浦の合戰に一門ことごとく減び去り、「分段の荒き浪玉體を沈の奉る」に及んで轉變無常の悲痛はここに極まる。後白河法皇の嘆ぜられたやうに、これをまのあたり體驗しては、「夢の裏の果報、幻の間の樂しみ、すでに流轉無窮なり、車輪の廻るがごとし、天人五衰の悲しみは人間にも候ひけるかな」と云はなければならないであらう。「盛衰昇沈の習ひ、有爲無常の哀しみ、みづから想ふて心に記ずに、淚を漉ぎ腸を斷たざるはなし」(覺法親王左記)。或ひはまた、「壽永、元曆の頃の世の騷ぎは、夢とも幻とも哀しみとも何ともすべて云ふべききはにもなかりしかば、よろづいかなりしとだに思ひわかれず。·····ただ云はんかたなき夢とのみぞ、近くも遠くも見聞く人みな迷はれし」(建禮門院右京大夫集)。前代の人たちは、そぞろな哀感が漾つて何となく心細い生活であつたとはいへ、その生活を「あはれ」とも「おかし」とも嘆じて眺め且つ樂しみ、それを夢ふかい「こころ」に涵して、そこからすべてを發想しまた評價した。今はしかし、現實の過度の激しさと目まぐるしさとに氣も顕倒し、腸を斷つ思ひでああこれがうつつのことかと嘆いてゐるのである。この悲嘆が諦觀となつて鎭靜し、虛ろな眼で樂しかつた過去をきれぎれに回想するとき、先にも述べた式子内親王33
のうら悲しい靜かな詠歎が漂ふのである。34花は散りその色となく眺むれば、むなしき空に春雨ぞ降る。花ならでまた慰むるかたもがな、つれなく散るをつれなくて見む。はかなくて過ぎにしかたをかぞふれば、花にもの思ふ春ぞ經にける。桐の葉も踏み分けがたくなりにけり、かならず人を待つとならねど。君をまだ見ず知らざDしいにしへの戀しきをさへ嘆きつるかな。忘れてはうち嘆かる夕かな、われのみ知りて過ぐる月日は。秋はきぬ、ゆくへも知らぬ嘆きかな、たのめしことは木の葉ふりつつ。時代の激しい動亂と痛恨のなかにあつて、この靜かな抒情に浸り得るには、よほどの優れた天質を必要とする。しかし、心奥に徹するこの歌のひびきを解するにしては、『新古今』の多くの歌人たちは現實の受け取り方の點であまりに弱かつた。彼等は內親王が切り拓かれた靜謐の境地だけをただ表面的に攝り入れ、現實に眼を塞いでただ回想のなかに幻影を描き出さうとしつつあつた。この人工的な制作によつてたまたま生ずるどこか自然らしい餘韻こそ、「幽玄」たとみてさしつかへない。の正體であつ鴨長明などによつて幽玄論の提唱者とせられた俊成卿を中心に、その當時の美學をもつと突き進めて考へてみよう。御裳濯河歌合の判詞の初めに、若い頃からよく知り合つて盟友となつた旨が記されてをり、西行と俊成とはすくなくとも年少の日から歌のことを語り合つて互ひに提携を約したのであらう。「昔天承、長承の頃ほひより、或る時は雲居の月の前に見馴れし友も昔の夢にのみなりぬるに、人の數にもあらず桑の門の棄て人となりながら、今まで世に永らへて、かやうのすずろことを書きつけ侍る」とあるから、西行が初めて北面に侍した十五歲前後のことで、俊成は十八九であつた。しかし、温厚な世間人であつたらしい俊成に對して、西行がどれだけ胸襟を開いたかは、かなその當時の美學をもつと突き35温厚な世間人であつたらしい俊成に對して、西行がどれだけ胸襟を開いたかは、かな
り疑はしいと去はれてゐる。ただ俊成の理論と學殖とには-さういふ點に至つて無邪氣な彼は-心から長敬して兄事したもののごとく、晩年もなほ御裳濯河歌合の判を乞ひ、その道統を繼ぐ子の定家にまでも宮河歌合の判を求めてゐる。ただ、天成の繊銳な感受性をもつてゐた西行は、俊成が抽象的な希求の念として描き得なかつた幽玄の道をたちまち具體的に感得し、それが出家の間接的な原因となつたとさへ見られぬこともない。歌界の危機が强く感じられるにつれて、數年前に世を去つた藤原俊賴のかの幽玄と評せられた歌風が、俊成と西行の間でしばしば語られたであらうことは想像に難くない。かうして保延四年、二十五歲のとき、俊成は、俊賴や顯季が亡くなつてからの歌壇に幽玄を唱へて最も聲望のあつた藤原基俊の門に入つた。西行の俊成との交友は、最も親しかつた大原の三寂の場合と同じく、崇德院を御中心としてのものであつたらしいが、西行在俗の頃の主家に當る德大寺家と俊成は緣戚關係にあつた。西行の莫逆の友なる三寂の姉妹が俊成の妻の一人であつた。さらに考證によると、保延五年、俊成が母の喪で嵯峨の法輪寺に籠つたが、その頃この寺には空仁といふ西行の友人がゐたから、そこでもしぜん落ち合ふことが一再でなかつたらう、といはれてゐる。かうして、特に年少の頃は、西行の俊成との往復はか36なり頻繁であつたにちがひなく、基俊の傳へた歌論を繞つて俊成といろいろ議論したりその示唆を受けたりしたと想像してさしつかへない。基俊の歌論は、「餘りの心」と「おかしき心」とを說いた『新撰髓腦』の藤原公任からの發展として現はれ、鴨長明などによつてその提唱者として祖述せられた俊成の幽玄論の直接の先蹤をなしてゐる。『悅目抄』が僞書であるといふから、基俊の歌論はいろいろな歌合の判詞によつて知るほかはないが、それらを綜合してみると、彼の內容論は、幽玄なる心、妖艶なる心、長高き心の三つにおよそ要約せられ、中世歌論の理念として用ひられた言葉がこれにほぼ盡されることは注目してよい。また、幽玄の思想は俊成卿に承け繼がれて完成するが、定家が最も重んじた妖艶の美がすでにここに說かれてゐることも見逃しできない。もつとも、妖艶は俊賴の謂はゆる「優なる心」の實質であり、すでにこの歌人によつて實現せられたものである。「······おほかた歌のよしあしといふは、心を先とし、珍らしきふしを求め、詞を飾り詠むべし。心あれど詞飾らざれば、歌おもてめでたしともおぼえず。詞飾りたれどもさせるふしなければ、よしともきこえず。めでたきふしあれども、優なる心、詞なければまたわろし」(俊祕抄)。これが俊賴の見解であつて、37
妖艶を生むべき新感覺がおのづから表現の角度の目新しさを求めつつその詞を飾ることを語つてゐる。彼が判詞に多く用ひてゐる「優なる」と「心ある」とはほとんど同一であつて前代の美學につながるものであるが、ただ彼は、妖艶といふ感覺に重みのかかる一つの情緒をこれに含めて考へてゐるのである。かうして、それはすなはち、俊成卿を通つて妖艶論者·定家の「有心」に展開する。對象以前にすでに湛へられてあるべきこの有心こそ、歌界の新しい目標となつたもので、當代の危機の解決如何は多くこれに懸つてゐた。そしてまた、それゆゑにこそ西行は、歌壇からの「出離」の手續きを、彼が類型として總括した有心からの一應の脫却に置かなければならなかつたのである。俊成は俊賴の歌風を慕つたといはれてゐるが、基俊の博識や保守性をも受け變いだことはたしかである。俊賴の革新的な歌風に魅惑を感ずるところひとかたではなかつたものの、聰明で氣の弱い彼は、直ちにこれに做ふやうなことをせず一應これを『古今』以來の和歌史のなかに還してそこから再出發しようとした。古今的正統への復歸を標準として『千載集』を撰した晩年に至つてからでも、この立場は變らなかつた。期せずして歌壇の指導者となり幽玄論の祖と仰がれはし38たが、決して獨創的な型の人でなく、むしろ、解釋者としての綜合に彼の役割はあつたのであら50鬼才俊賴の新感覺を歎美しながらも、「歌のよさは必ずしも錦繡のごとくなら」ずといひ(古來風體抄)、「繪所の者のいろいろの丹の數を盡し、作物司の工のさまざまの木の道をえりすゑたる樣にのみ詠むにはあらざることなり」(民部〓家歌合)と論じてゐるのを見ても、彼の見解の穩當さがうかがはれる。したがつて、西行に對して或る程度まで理解が深く、西行自身が意識しない點まで時には指摘してくれるといふふうで、歌に關してはやはり、西行が心から兄事するところがあつたのであらう。俊成の歌論の立場は、ひとくちに云へば、前述のやうに感覺に溺れた奇〓な表現を排してゐる外に、「艶」とか「あはれ」とかの抽象的な美感を有してゐること、その抒情の內容に韻律が美しく協和してゐること等である。彼の批評はすべて繊銳を極め、たとへば住吉社歌合の武庫の海を風ぎたる朝に見わたせば、眉も亂れぬ阿波の島山39を評して、「詞を幼はらずしてまた寂びたる姿、一つの體に侍るめり。眉も亂れぬ阿波の島山と云
へいる、龍門翠黛眉相對など云へる詩おもひ出でられて幽玄にこそ」と述べてゐるごとき、この歌から詞を勧はらないでしかも一つの風趣を見出したとしてゐるのは、煙のごとくひそやかに漾つて釀し出す詞と詞との深い韻き合ひを捉へ得る人にして初めて可能なことである。また、慈鎭和尙自歌合に彼は「よき歌になりぬればその詞姿の外に景氣の添ひたるにや」と述べてゐるが、の「景氣」とは、心の外にはみ出た得も云はれぬ情調と、姿から漾つてくるやはり言ひがたいものすなはち韻律との、不可分の統一であつて、互ひに深く聯關する。この統一によつて、公任このかた〓念的に分けて考へられた「心」と「姿」との問題を解決するとともに、兩者にわたる纎銳な分解の意識を有し得たのである。しかし、「歌はただ、よみあげもし詠じもしたるに何となく艶にもあはれにもきこゆることあるなるべし」(古來風體抄)と說いてゐるのは、「何となく艶にもあはれにも」なるのは一にその歌の韻律の美しさに依存するといふ意味で、「きこゆる」といふところに重點が見られる。このことは繰り返して「もとより詠歌と云ひて、聲につきてよくもあしくもきこゆるものなり」(前)と論じてゐるのを見ても明らかである。姿を越えた「景氣」としての韻律は、それみづから內容を誘40ひ出し浮き立たせて心を越えた「景氣」としてのかるに韻律と協和するこの情趣は、たとへば、「何となき」情趣を漾はせなければならぬ。し夕されば、野邊の秋風身に泌みて、鶉なくなり、深草の里に現はれてゐるやうな性質のもので、この作に作者の生活や個性や深草の里の情景を捜しても失望しなければならぬ。ただ、ここにあるのは、漠とした寂しさやあはれさであり、深草の里によつて抽象される秋の野の夕一般のもつ情趣、一つの抽象的な美感であつて、彼が「何となく艶にもあはれにも」云々と述べてゐる世界に相當する。そしてこの世界は、詞の巧みな取り合せと韻律の應和とによつて成立する。これは、生活に卽したなんらかの感動があつて形式が呼び寄せられるのでなく、抽象的な美感とこれを融一した形式の美しさとによつて逆に人の感動を誘はうといふのであるから、もはや人工美學と云ふよりはむしろ人工的方法論に屬する。しかも、生田お現實に卽しないで抽象的な美の世界を喚起することは、題を軸としてその周邊にさまざまな情景や情趣を描き出すこととほとんど同じである。つまり、題詠と本質的に異つてゐないのである。41
かういふ世界は必然に心の一廓に大きな空白を擴げるのであるが、この空白をたまたま覗き込んだ孤獨な佇まひこそ「幽か」「心細し」「さびたる」「遠百し」「心深し」等の綜合として用ひられたらしい幽玄であつた。もつとも、ここでの幽玄は、人工美學に對立するものでなく、これを抒情的に淡く陰翳づける特徵的な色彩であつた。そしてそこに『千載集』の歌史的位置があるのである。42しかし、『千載集』勅撰とちやうど時期を同じくして源賴朝に政權が移り、幕府の基礎が着々と固まるにつれて、『千載集』を幽暗に彩つた社會的不安がそれなりにとにかく薄らいでいつた。そして、貴族たちの間には、見えない何かに挑みでもするやうな一種の虚無的熱情をもつて幻影を空中に描き出さうとする氣運が生じた。定家卿は十九歲の時の日記に、「世上の亂逆追討は耳に滿ちたりといへども、これを注せず、紅旗征我わが事にあらず」と書いたが、憑かれた者のやうに「藝道」に沒頭した彼の面目がすでにここに現はれてゐる。『大日本史』の歌人列傳に、定家卿は性狂燥にして進取に急であつたと書いてあり、それがおそらく事實に近いものであらうことは御鳥羽院の御批評(御口傳)によつても想像される。とはいへ、定家らの世代を切り拓いた動力は、數奇や風流ではなかつた。御子左家の幽玄論と云はれてはゐるが、定家に至ると、幽玄の陰翳が剝落してふたたび『金葉』『詞花』時代の危機がさらに露骨に現はれてくる。『新古今』は解決でなく單に回顧的整理であつたから、それは當然のことであらう。しかも、『千載』には曾つての生活に纒綿する抒情がまだ漾つてゐたが、今はそれも失はれ、過去の榮華を材料として幻影をいかに彫り上げようかといふ努力に、創作のすべてが託せられる。かうして、後鳥羽院が「定家卿が庶幾するすがた」(御口傳)は俊賴のそれだと仰せられたやうに、抒情的な幽玄に代つて感覺または官能の妖艶が求められ、漢とした夢想だけからなんらかの情景や情趣を作り出すための彫心鏤骨が必要とされる。人工美學といふ點ではすこしも變りはなかつたが、その題詠性がさらに進められて積極的な一つの樣式的性格を有するやうになる、たとへば、43なごの海の霞の間よリ眺むれば、入日を洗ふ沖つ白浪
霞立つ末の松山、ほのぼのと、みよし野の高根の櫻散りにけり、ほのぼのと、波に離るる橫雲の空嵐も白き春の曙44といふふうに、大和繪のそれにも似た樣式の意識が强くなつてゐる。しかし、この優雅な錦繡の蔭には、虚空の一點に眼を放つて凝立する者の弛緩した表情があつた。このことにみづから氣づいたとき、象牙の塔はたちまち崩れ落ちる。四十歲の定家の眼にはすでに幻影が消えてゐた。その幻滅の日、末法濁惡の世の常なさに「すべて世の中のありにくく、わが身とすみかとのはかなくあだなるさま、またかくのごとし」(方丈記)と嘆き、「世に順へば身苦し、順はねば狂せるに似たり。いづれの所をしめて、いかなるわざをしてか、しばしはこの身を宿し、たまゆらも心を休むべき」(同)と悶へた、日野山の隱者の、嗚咽を混へた悲しい讀經の聲が、厭世と求法とに深く傾かうとしつつある人々の胸に擴つていつた。しかし、ここまで來れば我々は中世に足を踏み入れることになる。要するに、新古今人の努力は、現實に眼を蔽つた抽象的な幻影の世界をいろいろに微分し細化現實に眼を蔽つた抽象的な幻影の世界をいろいろに微分し細化して應用するところにあつたと云へる。しかし、現實にあり得ぬ世界を過去の世の回想に求めてその幻影に生きようとした彼等の熱情には、何かしら固形表情の美しい虛無と云つたやうな姿しか感じられず、現實の哀感をまじめに掘り下げた形跡はすこしも見られない。かうして、回想に耽つて凝立する自分だけを殘してすべては薄需のかなたに遠のき、意欲の影をひそめたしづかな詠歎をよそに、鴨川だけが流れの音をかすかにひびかせてくる。すべては逝く、この流れのやうに曾つての榮華はどこへ消えたか。彼等の歌の優艶、華麗は、この過去の日の回想から來てゐた。しかし、それは幻影でしかなかつた。春日山、谷の藤浪たち歸り、花咲く春に逢ふよしもがなさう、定家は歌つた。回想は何よりも過去の書をしるべとする。釋阿あたりから『源氏』『狹衣』の類を歌人に必讀の書と〓へたことは、決して偶然ではない。『新古今』に物語的な特色をもつた歌が多いことは人のよく指摘するところであるが、彼等が住んでゐた回想の世界そのものがいはば物語であつたと云へよう。「梅の花、あかぬ色香もむかしにて、同じかたみの春の夜の月」と詠45
じ、また「橘の匂ふあたりのうたたねは、夢もむかしの袖の香ぞする」と歌つたとき、それらの花の香に物語の艶かましい衣ずれを思ひ描いてゐるのであるが、もとよりすべては寂として廢墟のやうに思ひ出のうちに眠り、月のみがひとりその上に蒼ざめた光をひろげてゐる。物語と歌との結びつきは、すでに平安朝盛期の文學にも見られた。そこでは、先にも述べたやうに、抒情が直ちに表現を求めず、耽美的な「こころ」に浸され且つ搖すられて纎細な曲線を形づくるとともに、その周邊にいろいろな聯想や雰圍氣を喚び起しつつ、一首にまとられる。したがつて、その周邊の波紋が擴がる時は、一首にどうしても收まらぬ廣い世界がその背面に生ずる。ここに歌を中心とした物語の出現がおのづと考へられてくる。とはいへ、その成り立ちから見てもわかるやうに、歌物語からの物語の獨立がたとひそのかたはらにあつたとしても、物語は歌の震幅から擴つたものであつたことはたしかであらう。しかるに『新古今』に至つては、物語的な-必ずしも物語とは云はないまでも-世界をまづ豫想し、そこから想を引き出してきて一首としての浮彫をこころみてゐるのであつて、方向を全く逆にしてゐる。抒情の波紋を固定化した物語に作因を搜らうといふのであるから、抒情の泉に浴することはもはや望むべくもない。泉がふたたび湧46き出すのは、行きづまつた自己を分解しこれを客觀化してみてそのみづからの姿におもはず洩らす歎聲を見出すところの俳諧の精神によつてであり、しかもその實現のためには中世連歌の鍛鍊を俟たなければならなかつた。事實、和歌の歷史は、藤原定家に於ける作歌のゆきづまりとともにほぼ終つてゐた。父釋阿がいかに身を削つて苦吟したかは『さざめごと』の記述などによつてよく知られてゐるが、定家の藝熱心はこれよりももつと烈しく、時には變質的と見えるくらゐ自說に執したりするところもあつて、つひに御寛厚な御島羽院の逆鱗にすら觸れてゐる。それが、壯年を越えるとまもなく創作を續ける力に疲勞を感じ、『明月記』などにもしばしばそのことを訴へてゐる。源實賴へ送つた例の『近代秀歌』にも「言葉の花色を忘れ、心の泉源涸れて」と云つてゐるが、これはおそらく僞らぬ告白であつたらう。このことは、單に定家の才能の問題と云ふよりは、和歌史のうへに全體のゆきづまりが訪れた結果にほかならない。『新古今』はいはば、『金葉集』『詞花集』に示された危機の最後の打開策として求められたものであり、或る程度まで成功し得たかのやうな活氣を呈してゐるので、ずつと中世和歌の燈臺となるのであるが、初めからその根底は彫身鏤骨を作者に要47
讀したやうな不自然さを含んでゐた。それはいはば、人工的な培養によつて咲き出した妖艶な花々であつて、みづから生成する力を失つてゐたのである。48三庶民の歌と西行中世人が聖代として顧みた延喜·天曆の時代に、平將門を中心とする東國の叛があつたことは、一つのささやかな投石にはすぎなかつたとしても、やはり見逃すことのできない現象のやうにおもはれる。それは、空也の唱へる念佛とともに、大宮人の心のどこかへ哀しい鈴の音をひびかせて消えていつた。このとき將門を誅した俵藤太秀〓の名がいくらか京で噂されたが、この秀〓の曾つての流謫などを人々はもう忘れてゐた。秀〓にどれだけ東國の血が通つてゐたか、私は知ら병しかし、のたがの叛えものあな京の偏同交化しずする品の借放であつたえはへないこともなからう。賴朝を柱とする後の東國土豪政權の樹立に通ずる一つの警笛がここに聞かれたのである。もつとも、叛亂前の延長三年に諸國からふたたび風土記が徴せられてゐるが、地下の泉の〓冽49地下の泉の〓冽
な流れに京の人々が觸れ得たとは考へられない。彼等は、前にも述べた時間的距離の喪失とともに、この世界の廣さや距たりを見失つてしまつた。彼等の住んだ世界は、京に限られ、しかもそのまた宮延と家庭の簾や几帳の蔭、燭下のほのかな圓光のなかに限られた。かうしてたとへば官命によつて地方へ赴く時でもおほかた生きここちもなく、「多年風月の遊びを忘るることなき」期してわづかにみづからを慰めるといふありさまであつた。光源氏が京から須磨へ立ち去る時にさへ、「知らぬ世界へまかる」ことを嘆き悲しみ、歸京への一縷の望みを「命ありてこの世にまた歸るやもあらむを」と稱して京の生活を「この世」といふ語で表はしてゐる。といつて、京にあつてもこれぞといふ積極的な生活の歡びがあるわけでなかつた。まづ朝廷に出仕しては煩瑣な年中行事と化した政事をただ繰り返してそれを形式的に記錄するだけで日が暮れる。緩漫な官位の昇進が唯一の希望であり、おぼほしい心を展く樂しみといへば詩歌管絃の遊びぐらゐであつた。かういふ心細い哀れさをなかば目醒めてみづから「あはれ」と眺めることはあつても、その「あはれ」すらも偏向した人工的心情の綾に吸收せられたものにすぎなかつた。今日、私たちはこの時代の局部的に偏結した文化を殊に痛切に考へる。それは、現代の私たちの文化もさうであるや50うに民族の聲ではない。民族の心の消息が地上に現はれるには、後鳥羽院の謂はゆる「おどろの下」の道をさらに久しく潜りぬけなければならなかつた。將門の血を亂した怒りも、その日にはまだ、逆賊としての形を取らざるを得なかつた。とはいへ、彼と俵藤太とではそれほど異るところがあつたわけでない。いづれも、その血のどこかに東人の鬱結した歎きをひそめてゐたのである。ところで、よく知られてゐるやうに西行法師は俵藤太九代の裔に當つてゐる。俵藤太の母は、もともと下野採鹿島女であつて、藤太以後に至れば東國の血はますます濃くなつていつたと見なければならぬ。在俗のころ鳥羽院北面の武士として西行が仕へたのも、關東以來の「家風を傳」へたその弓馬の道によつてである。しかも武士としても非凡な練達の士であつたことは、『台記』などの記事によるまでもなく、晩年賴朝の前で和歌を講せずに弓馬の道を語つたことでもうかがはれる。彼が京の雰圍氣に堪へられずにいち早く草茅のなかに隱れたのも、彼に東人の血がつながつてゐたためのやうにおもはれる。西行出自の佐藤氏は、俵藤太五代の裔、左衞門尉公〓を祖とし、その子孫が各地に榮え、川田51左衞門尉公〓を祖とし、その子孫が各地に榮え、川田
順氏の考證によれば、「山內、首藤、鎌田、後藤、尾藤、池田、伊藤、波多野の庶流を生ずるに至り、地理的に云へば、平安末、鎌倉初めにはすでに、相模、伊豆、武藏、下總、常陸、奧州、出羽、越後、下野、甲斐、三河、尾張、伊勢、伊賀、紀伊、山城、但馬、安藝、阿波、讃岐、土佐等に繁殖した」(『西行〓究錄』一八-九頁)。かうして代々所領の莊園による地方的地盤は古くから源平兩氏を凌ぐものがあり、とりわけ藤太秀〓の昔から關東、奥羽にかけての勢力は鬱然として拔きがたいかたちであつた。まことに、西行がもつと後まで俗籍にあつたとすれば、或ひは關東に據つて一門同族を東西に糾合し、緣のつながる平泉とも連絡を取つて、源平二氏の間に實力を行使し得る立場に立つてゐたかもしれない。さうすれば、もちろん、保元·平治の亂を初め、鎌倉幕府の存否さへどうなつてゐたかわからない。島羽上皇が西行に遯世の志あるのを覽はしてこれを諭して檢非違使に補せむと仰せられたと傳へられてゐるが、源平兩氏の目に餘る所爲に對して上皇が佐藤一門を起用あそばされようとしたと考へることは、不自然ではない。尾山篤二郞氏も觸れてをられるが(『西行法師全歌集』附錄)、北畠親房が結城親朝に援軍を乞ふた有名を關城書に、結城氏はもともと秀〓を祖とする大豪族の一門でその家柄は〓盛や賴朝の及ぶところでないと書い52てゐるが、後世の結城氏にさへそれぐらゐの聲望があつたのであるから、秀〓直系の佐藤氏に至ればなほさらのことである。西行が諸國を巡り步いてすこしも衣食に事缺かなかつた理由も、こにあるのである。また、西行が在俗の日に出仕した院そのものの周邊には、白河院が北面武士を置かれた頃から東國との眼に見えないつながりが生じてゐた。なぜなら、武士はほとんど東人であつたからである。この院に始まる院政がすでに藤氏の專橫を抑へて天皇親政に還されようとした御決意の現はれであつたが、源平がやがて第二の藤氏となり、しかも武力を擁してゐるため始末わるくなつたとき、上と蒼生との直接の暖かな交流をこの東人を介して夢みられたのかもしれぬ。上下の疏通を妨げる中間勢力を退けて民族一體に還すことがつねに維新の原則であるとすれば、院政の開始はすなはち庶民の自覽に卽應したものと云つてさしつかへない。承久の變に院方惣大將として河內の佐良で壯烈な自害を遂げた藤原秀康とその兄弟は西行の一族であつたが、東國系の武者を中心としてかういつた殉忠の士を多く出した承久の役こそ、『承久の役と源有雅卿』の著者·萩原賴平氏も詳しく論じてゐられるやうに、「實にこの國に於ける王政復古運動の先驅をなしたものであ53
つて、雨來、明治維新に至るまで」(十頁)彼等の非願と決意とが續いてゐるのである。54白河院の御宇に寛平このかた久しく絕えてゐた高野御物詣が再興せられたことに就いても、私は、一つの假說を立ててみたい。それは熊野と東國との關係で、この時代に至つてふたたび太古からの隱密な交流が熊野參りの形で復活せられてきたもののやうに見える。また南都、北嶺の天台諸寺院が、紊亂と墮落の底に蠢いてゐるとき、高野の法燈がこれに伴つて耀きを取り戾してきたのは當然であり、白河院の皇子が仁和寺門跡として法親王の稱を受けさせれるに及んで宮廷の信仰はふたたび密乘に傾いたのである。そして、かういつた氣運に應へて立ち現はれた眞言の新しい指導者が正覺坊覺鏤であつた。宗〓政革の先蹤としては、空也を始め慧心僧都源信、融通念佛の良忍等が前にあつたが、眞言から始めて出て改革の運動に決定的な活を吹き込んだのはこの覺鑁であつて、原勝郞博士のごときは、その著『日本中世史研究』Lift,て、もしこの覺錢が世に出なかつたなら「法然上人の活動も或ひはもう少し後れたかもしれない」(三六八頁)と論じてゐる。その著述にかかる『孝養集』に徵してもわかるやうに、覺鏤はまづ庶民や子女の啓蒙に目を注ぎ、それらの大衆を地盤として改革を行はうとしたらしい。そして、そのために高野山の衆徒から迫害された時のこととして「きりもみ不動」の奇蹟が傳へられてゐるくらゐであるが、彼が庶民の最も汚れない姿を東國に見出してその布〓をこころみたらしいのは興味ふかい。原博士の說によれば、「東國の傳道といふことは、おそらく上人の念頭に置いた重大事件の一つであるに相違ない。上人瀉瓶の弟子たる兼海が鎌倉に行つてゐたために上人の臨終に居合はさなかつたと傳へられてゐる。もし兼海が上人の命によつて鎌倉に行つたのだとすると、上人の東國傳道を念とした一つの證據になる。(中略)上人が鎌倉を中心として東國の傳道に意を留めたと想像するのは、あながち架空の說とのみ云へまい」(三六六頁)。さうしてみると覺錢は、天曆のころ奧羽の下層庶民を對象として念佛を說いた空也上人のあとを承けてゐることになる。西行が最も崇敬したこの覺鑁の示疲は彼の出家後三年、すなはち康治二年であつて、この時はまだ高野に入つてゐなかつたから、西行は、同じく武門の出で歌人なるこの一代の傑僧から直接に〓へを聽いたことはなからうといはれてゐる。ただ『續千載集』釋〓歌に、55
鳥羽院の御時御撫で物の鏡を賜ひて奏しける(覺錢上人)ます鏡うつしおこする姿をば、まことに三世の佛とぞ見る御返おしなべで誰も佛になリぬとは、鏡の影に今日こそは見れとあつて、この上人が鳥羽院の御寵遇を忝うしたことは明らかで、仙洞にもしばしば參候したらしく、その關係で「北面の佐藤義〓も、よそながらこの傑僧の面貌を覗き、或ひはもしかすると說〓を聽聞し」(川田氏『西行〓究錄』五三頁)たかもしれず、「後年の高野入りはこのやうなことにも遠因の一つをもつてゐたか」(同)とさへ考へられぬこともない。西行が台密から東密へ轉じた點に就いて、川田順氏は、「眞言宗の象徴的思想が詩歌の精神と一致する」(川田氏前揭書五〇頁)ところにも理由があると論じてをられる。傾聽すべき一說であるが、それとともに私は、高野から三熊野にかけての幽邃な山間に、末期文化の酸敗に冐されぬ〓新な雰圍氣が深く漾つてゐたことを考へたい。白河院の御宇に於ける興〓の御志のさかんな現はれに就いては、ここに說くまでもない。院のこの御志の存するところを窺ふのも畏れ多いが、厩戶皇56鏡の影に今日こそは見れしく、子のそれのやうな御決意をやはり佛〓を通じて持ちたまふたと拜せられないこともなからう。白河院の御幸は、高野·熊野を合せて十二回にわたつてをり、鳥羽院ならびに後白河院がこの御意志を承け繼がれて驚くほど頻繁にそれらの地へ御幸を重ねられてゐる。白河院が法勝寺を建てさせられたとき、禪林寺の永觀律師に「いかほどの功德ならむ」とお尋ねあそばされると、律師はしばらく默つて考へてから、やがて「罪にはよも候はじ」とお答へしたと傳へられてをり(續古事談)、時世から云つても、心の眞の安住を託すべき塵外の道場の求められる機運が迫つてゐた。まして、院宣の政を初めて布かれた英邁豪毅の白河院には、單なる求道を超えた大御心を東人の遠く杖ひく奥紀の山々に通はせられたと拜察することも不可能ではない。もちろん、さういふ御意識が明白に存したとは云へないかもしれないが、時代の趨勢として一つの漠然とした雰圍氣がそれらの山々を繞つてゐたことはたしかであらう。落花の歌あまた詠みけるに、勅とかや下す御門のいませかし、さらば畏れて花や散らぬと。57
波もなく風を治めし白河の君のをりもや花は散りけむ。53いづれも西行作のこの二首は白河院の御宇を讃へて回顧したもので、「勅とかや下すみかど」云々といふのは、御佛事の日の雨に逆鱗あそばした白河院がこれを器に取つて獄に下したまふた謂はゆる雨禁獄の挿話を指すのであるが、雨神をさへ叱咤されたその激情の凛乎たる御指向は、院の傳統として後白河院、後鳥羽院の繼承したまふところとなるのである。鳥羽院が佐藤義〓一門を起用せられようとしたこと、覺鑁上人を寵遇あそばしたことは、先に述へた。また、熊野三山への難澁な御幸を二十一度も行はせられたことも、この院の上を偲び奉るよすがとなるやうにおもはれる。また、長講堂に奉安せられる御尊像のかの眉字に漲るものを拜してもわかるやうに、後白河院の豪壯英邁の御氣象はここに記すまでもない。しかし、我々今、何よりもこの院に感謝を捧げるのは、『梁塵秘抄』の御撰に對してである。かういつた雜藝の歌謠に於いて無双の御權威であらせられたことを人はとかくおろそかにしがちであるが、このやうに庶民居の生活の底を流れる〓冽な泉に掬されたことは、この時代の精神史を願みるうへに一つの決定的な指標をなしてゐると云つてさしつかへない。そしてこの院の御自覺は、御孫·後鳥羽院に承け繼がれてさらに鮮明な組織を伴ひ、つひに承久の役となつて發動するのである。不輸·不入の特權を擁する莊園の領有のうへに貴族制社會が出現し、その文化が京に集中して地方から遊離するに及んで、京の貴族たちは、民族的共感に足なみを揃へる力を失ひ、生活感情をますます局部的、人工的に抽象し、繊細な美學をつくり出した。しかし、たとへば、後宮の女人がさういふなかで生活するために「和魂」の才智を互ひに織銳に〓いでゐたとき、下層の官吏や庶民の家庭の女たちの間では、「和魂」は別の形で受け取られたもののやうにおもはれる。「めのとせむとてまうで來りける女の乳〔智に通ず〕」が細かつたので、大江匡衡が戯れて「はかなくも思ひけるかな、ちもなくて、博士の家の乳母せむとは」と詠んだとき、59
さもあらばあれ、大和心し賢くば、ほそちにつけてあらすばかりぞ60とこれにその女が和したことが『後拾遺集』卷末に赤染衞門作として見えてゐるが、「さねさし相模の小野に」と歌はれた弟橘媛に見られるやうな女心の深い傳統が、ここにもなほ幽かに音して流れてゐることを我々は知るのである。庶民はそのまま民族を代表するものではない。それはむしろ民族のカオスである。しかし貴族たちの遮斷によつて頭部を見失つた時でも、庶民たちの間には、民族の聲が絕えたことは曾つてなかつた。しかも、今は杏として知るよしもないこの草莽の民の唄こそ、民族の傳統をつなぐただひとすぢの流れであつたのである。彼等の營みは、傳承のなかから起り、そして傳承のなかに消えていつた。しかし平安朝末期に至つて堂上文化がすつかり行きづまつたとき、民間のいろいろな雜藝が新しく上層の人たちの間に浮び上り、特に今樣その他の歌謠に注意が向けられた。そして、そのおかげで、そのころの歌謠の一端が今に傳へられてゐるのはありがたい。わが子は十餘になりぬらむ、巫してこそして步くなれ。田子の浦に汐ふむといかに海人集ふらむ。正しとて、問いみ問はずみ〓るらむ。いとをしや。難澁して育てた子もやうやく大きくなりかかつたかとおもふと、主から徴用されるのはまだしもとしても、多くは働くのを嫌つて法師になつたり浮浪の徒に加はつたりするといふ狀態で、子を持つた母親の苦勞がひとかたならぬ時代であつたのであらう。法師といつても名ばかりで、「夜行を好む」はあたりまへのことであつたし、博打の巢窟がもともと寺であつたらしい。この歌では巫古をしつつ流離の日を重ねるまだいとけない子への母の哀切な嘆きが歌はれてゐる。春の野に小屋かいたる樣にてつい立てる鉤蕨。61
忍びて立てれ、下司に採らるな。62初めの行の形容も美しいが、さらに「忍びて立てれ」と呼びかけたこの〓らかな秘唱の發想を見よ。淀河の底の深きに、鮎の子の、鵜といふ鳥に背中食はれてきりきりめく、可憐しや。淀河の深い流れの底に、や」と結んでゐる。鵜に追はれた銀鱗の美しい関めきを鮮かに思ひ浮べ、そして「いとをし舞へ舞へ、舞はぬものならば、馬の子や牛の子に蹴させてむ、まごとに美しく舞うたらば、花の圍まで遊ばせむ。踏み割らせてむ。いはば童話であるが、「舞へ舞へ蝸牛」と呼びかけ「花の園まで遊ばせむ」と結んだこの抒情の〓明な優しい美しさは、世界のどこの童話にもその比を見ないと云つてさしつかへない。さうかとおもふと、次のやうな、幽玄な象徴的發想もある。おもふと、御厩の〓なる飼ひ猿は、絆離れてきぞ遊ぶ、木に撃り。當盤の山なる檜柴は、風の吹くにぞ、ちうとろ搖らぎて裏返る。63
猿の無心の動作と、風くれば葉裏をかへす楢の木のそよぎとが自然のおのづからなリズムに融一して透きとほつた象徴的沈默のなかにはるかに消え去つてゐる。後に世阿彌などによつて大成された高度の象徴主義も、おそらくかういふところに胚芽を持つてゐるのであらう。€4遊びをせむとや生れけむ、〓れせむと生れけむ、遊ぶ子どもの聲きけば、わが身さへこそ搖るがるれ。ここに至れば、影ひとつなく晴れわたる天の安の河原に會した祖神たちの麗らかな哄笑が想はれるくらゐで、中世的重壓の始まりつつあつた日にこの無邪氣な明るさを保ち得た庶民たちの姿に私は感動する。そしてなほ、これらの歌謠の一端が-たとひいかに貴族化したものであつたとしても-主として後白河院の救慮によつて今に傳へられたところに、民族の大きな誇りを感ず300當時の知識人たちがこれらの歌謠を好奇的にしか眺めなかつたとき、現人神にあらせられる院には、300御みづからの御氣息と蒼生の爽かな息吹との根源的融一を直ちに感得したまふたのであところで、歌界のどうにもならぬ人工美學に對して强い反撥を感じたとき、西行はおそらく、右に述べたやうな庶民たちの歌にひそかに胸を搖すぶられてゐたにちがひない。特に、血の通つた眞實のひびき、その率直な隱すところない歌ひぶり、その世界の歡ばしい明るさなどには、〓へられるところがあつたのではなからうか。『梁塵秘抄』卷二の終りに、「右一册、以寂蓮手跡徹書記」云々書き込みあり、寂蓮は曾つて後成の猶子であつた人で、西行に私淑した慈圓が師の示寂の時もこの人へ最先に挽歌を送つてゐるくらゐで、殊に和歌のうへでは親交があり、いろいろ〓へを乞ふところもあつたにちがひなく、詩人としての感受性に惠まれた西行が當時の歌謠に目を着けなかつたとは考へられない。後鳥羽院は寂蓮を評して「長などぞかへりていたく高くはなかりしかど」(御口傳)云々と仰せられてゐるが、續けて「機につけて、きと歌よみ、連歌師の狂歌に至るまでも俄かのことも故あるさまにありしかたは、しんじつ堪能と見えたりき」とあり、ういふ自由な俳諧的態度はやはり西行のそれをさらに碎いて祖述したものであつたやうにおもは65
れる。出家前と推定せられる西行の作のうちに、66ささがにの絲につらぬく露の玉をかけて飾れる世にこそありけれ(「百首」のうち)とあり、彼のその頃の時代批評の一端がうかがはれる。人工的、形式的に流れて自然の美しさをすなほに認め得ぬ人たちの間に一線を劃して、やや誇らかに「人はみな吉野の山に入りぬめり、都の花にわれはとまらむ」(同)と歌つた日の北面の士、佐藤義〓であつた。それにしても、その當時、ほととぎす、ほととぎす、なべて聞くには似ざりけり、深き山邊の曉の聲(同)といつたやうな〓新な抒情が現だれたのは、歌界だけに凹して見れば驚くべき現象と云つてよかつくれb平安朝このかた相聞にはなほ在原業平を初め幾多の詩人が輩出してゐるが、そのすべてを通じて云へることは、affectationともいふべき一つの身ぶりがまづ抒情を規定してこれを抑へてしまふために人間性の素朴な眞實さが失はれてしまつたことである。「汀ちかく引き寄せらるる大なべて聞くには似ざりけり、網に、いくせのものの命こもれる」(同)といつたやうな、實感のこもつた熱切な歌ひぶりは、掌上文壇には絕えて見られなかつたものである。しかも、むしろ放縱ですらあるその自由無礙な作歌は、定家等とは反對に內部がありあまるくらゐ豐かでおつたためでもあらうが、一つには、窒息するほど窮屈な周圍の歌の雰圍氣に反撥しすぎたせゐであつだと云へる。西行はつまり、不自然に偏結して造花と化しつつあつた末期王朝文化の息苦しさに堪へられずに、ひとり別天地を切り展いたのであつて、噴出の日を待つ東人の血がそのうしろに波うつてゐたとするのは、果して私だけの獨斷であらうか。京の貴族から蟲けらとしか見られなかつた庶民たち-もちろん武士を含めて-が東人を先登として莊園の蔭から起ち上りつつあつたことは、たとへば今樣を初め田樂、白拍子等の雜藝の勃興にすら感じられる。すなはち、貴族たちが漸次に自己喪失してゆくのに反比例して、庶民の自意識はおもむろに高まつてきてゐた。そしてそのかたはら、藤氏擅權の淵叢をなす莊園の整理をまづ企てられた後三條天皇の御遺志が、さらに院政の堂臭に深く根を下ろし、庶民の擡頭に應へようとしつつあつた。白河院以來の興〓策に對すス新興佛〓の進出も、一面に於いて、形成せられつつあつたこの庶民の隱密の力に乘じたものと掌€7
云へる。もちろん、彼等の意欲を明白に知るにはなほかなり後まで待たなければならないが、白鳳このかた失墜の一途を辿つてつひに動きのとれない頽廢の沼に沈んだ民族の活力は、ここにやうやく息づき得る〓新な一角を見出したのである。白68ただここで考へなければならないのは、庶民とは、貴族といふ存在の反措定であつて、その限りに於いて上との間に介在するその遮斷者のために頭部を失つた族である、といふことであらう。したがつて、そのやうな狀態に於いて自己を意識するといふことは、人間としての存在の客體性を恢復することにほかならぬ。上層に居てしかもひとり目醒めた實朝を別とすれば、かういふ場所では、人は英雄として自己を捉へ得ないばかりでなく、悲劇に身をさらすこともできない。民族的主體性が彼の背すぢを貫いてゐないからである。西行の生涯を見てもわかるやうに、彼にはすべて抵抗らしい抵抗がなく、遁走だけがあつた。彼に英雄的氣魂があつたとしたら、もちろん世を捨てなかつたらうし、したがつて保元の變の時も大軍を擁して起ち上つたことであらう。ししかるに、「この君はとて」と献身すべき君があるにもかかはらず、「吳竹の節しげからぬ世なりせば」などと云つて逃げてしまふのである。彼の出離を鳥羽院が惜しませたまふたとき、惜しむとて惜しまれぬべきこの世かは、身をすててこそ身をも助けめと歌を奉つてゐるが、「身を捨ててこそ身を助けめ」といふのがたしかに彼の哲學である。ここで身を捨てると云つてゐるのは捨て身になることではない、負けることである。このことを知つて初めて我々は、川田氏の次の論評を首肯することができる、「山來、戀愛をしても捨て身になり得ず、佛者の修行しても顯密の一方に專念することできず、新院に親しみ奉りながら美福門院關係の御殿にも出入し、平家に同情しながら源氏を捨てず、西行の性向は、不卽不離の妙諦はあつても,一徹といふことがなかつた」(『西行』二五頁)。かういふ西行には悲劇的精神がなかつた。その精神はただ、今や、現人神にまします列聖の保たせたまふのみであつたのである。1ところで、自然に深く照應する素朴な眼を回復するには、類型化した擬態に陷る自己を一應分解してその姿を客體化するといふ過程を必要とするが、このことはまた、自己の或ひは自己等の69
孤立を捨てて身を民衆の間に置くことにほかならぬ。かうして、俳諧の精神が次の時代の架橋となり、「筑波の道」なる連歌が庶民たちの間に行はれるに至つたのは興味ふかい。連歌の始まりを求めるとすれば、すでにその前にもあつたものを、連歌師たちがそれを日本武尊と燈ともしの翁との問答に求めたのは、やはり尊と庶民との間の暖かな交流を感じたからであらうか。百韻、千句、一萬句等の謂はゆる長連歌が發生して、これが中世の中期以後を通じてさかんに行はれ、さらに後の時代の俳諧まで續いてゆくのであるが、建武元年、二條河原の落書に「京鎌倉をこきまぜて、一座そろはぬえせ連歌、(中略)點者にならぬ人ぞなき」と諷せられたくらゐなこの隆盛は、そこに庶民がみづからの息吹きを見出したためであつた。歌人たちが派閥爭ひに腐心していろいろ煩項な因襲や規則に因はれてゐるとき、二條良基の『筑波間答』などが次のやうに〓へてゐるとほり、舊來の殻を破つた自然人の素朴な眼が輝きはじめる。「歌の道は秘事口傳もあらむ。連歌はもとより、いにしへのもやう定まれることなければ、ただ當座をもよはさむぞ興はあるべき。上手といひて煩はしく硬ばり聞きにくからむことゆめゆめ用ひたまふべからず。」西行が緇衣を纏うたのは、この姿に於いてのみ自由人の境涯が得られたからであるが、70さ彼の歌風もまた「煩はしく硬ばり聞きにくき」堂上歌壇からの出離を意味してゐたと云へる。いはば、身を「無心」の側に置いてみづからの「有心」を救つたのである。この間の逆說がわからなければ、身を捨てて歌を生かすことを考へた彼の欲求-必ずしも意識的と云へない-の在りどころが判明しないであらう。山櫻咲きぬと聞きて見にゆかむ、ひとを爭ふ心とどめて。かういつた歌をもつてよく人は、西行出離の因となつた「雲井のよそに見し月」への今は及ばぬ戀の孤獨が現はれてゐると考へる。のみならず、「袂に宿し」たその月の影が美福門院であつたなどとする(尾山氏說)。或ひは事實であつたかもしれない。しかし、有心·無心と呼ばれたものの具體的な意味を考へるとき、この「月影」からすすんで離れ去らうといふ、破戀の日の自虐的とも見える捨身の激情をその一方に假定してもよささうにもおもはれる。かう假定し初めて、花にそむ心のいかで殘りけむ、捨て果ててきとおもふわが身に71
の眞の意味がわかつてくる。「花にそむ心」も「ひとを爭ふ心」も一つのものの異つた現はれにすぎぬ。72何とかく、あだなる花の色をしも、心に深く染めはじめけむ。そして、この一つのものの變革こそ、出離の決意を齎らしたものの漠然とした目的である。彼の或る種の歌を見ると、對象が果してそのままの風月なのか、それとも風月に託された戀人なのかがわからないが、彼自身にとつてもそれは初めから一つのものであつた。「あはれあはれ、この世はよしやさもあらばあれ、來む世もかくや苦しかるべき」といふやうな相聞の歌が口を衝いて流れたのは、身を無心の衆の間に置くつらい試練の月をどうやら過ぎ、三十歲前後に高野山に入つてからであつたらしい。庶民のうちに生きつづけた素朴の眼はその時やうやく彼に輝きはじめ、それまで避けた相聞や風流に惧れなく對し得るやうになつたのである。しかし、晩年「心なき身」にも「あはれ」は知られると歌つたとき、芭蕉の「この道や」に似た-しかし方向の異つた-感慨がそこになかつたと云へるであらうか。後鳥羽院や實朝の閃光は別として、平安末期の氷結した歌界の一角を破つたこの滾々たる〓冽な流れを承け繼ぐためには、一應それを連歌の形に分裂してふたたびその綜合の成る日をおもむろに俟たざるを得なかつたからである。すなはち、後鳥羽院の謂はゆる「おどろの下」の道をくぐり拔けなければならなかつた。そして、その流れがはるか後世の芭蕉に注いで同時に消滅するのである。「ただ釋阿、西行の詞のみかりそめに言ひ散らされしあだなるたはぶれごとも、あはれなるとこる多し。後鳥羽上皇の書かせたまひしものにも、これらは歌に實ありてしかも悲しびをそふると宣ひ待りしとかや。されば、この御言葉を力として細きひとすぢを辿り、失ふことなけれ」(柴門辭)。松尾芭蕉がみづからの系譜を西行から起したことは云ふまでもないが、「かりそめに言ひ散らされしあだなるたはぶれごと」こそ、俳諧に負はされた悲しい運命ではなかつたのか。もちろん、釋阿はただこの運命を訴へる幽玄論の祖として取り上げられたのであらう。しかし、後鳥羽院に於かれては、西行解釋はこれとかなり緯と規模とを異にしてゐた。「西行はおもしろくてしかもこころ73
に殊にふかくあばれなるありがたく、出來しがたきかたもともに相兼ねて見ゆ。生得の歌人とおぼゆ。これによりておぼろげの人のまねびなどすべき歌にあらず。不可說の上手なり」(御口傳ここでもこのやうに絕讃せられてゐるが、その撰出に院の御心が決定的に作用してゐる『新古今集には九十四首も收められ、院がいかに西行を重んじたまふたかがわかる。これに反して、定家に對しては、ちよつと氣の毒と思ふくらゐ痛烈な批判を下してゐられる。定家が「ものにすきるところ」(同)なく風流の豪奢な精神を解しないのはここで觸れないとしても、「惣じて彼卿が存知のおもむき、いささかも事により機によるといふことなし」(同)として彼の歌の室虛な抽象性をみごとに剔抉せられるとともに、この「有心」の提唱者がかへつて「心ある樣なるをば庶幾せず、ただ調、姿の艶に優しきを本位とす」(同)る點を衝かせられてゐる。院の大批評家としての御面目は、かうしてこの御著の後半に集中せられた定家論にうかがふことができるのであるが、終りに院の歎賞せられる歌人として「釋阿、西行などが最上の秀歌は詞も優にやさしきうへ、心ことに深くいはれもあるゆゑに」(同)云々と仰せられてゐる。芭蕉が基準として據つてゐるのはこの點であるが、しかし院の西行理解は、はるかに悲劇的な相貌を呈してゐたもののやうにおもは74れる。院はおそらく、この西行といふ小さな水鏡に、民族の大鳳のおほどかな羽搏きをさへ夢みられたのである。規模あまりに壯大であり、これに應和すべき蒼生の動きはまだまだ地下に深く眠つてゐた。そのとき、最へて「奧山のおどろの下も踏みわけて道ある世ぞと人に知らせむ」て運命に挑ませられた院の龍顏には、後白河院のお膝にあられた日からすでに悲劇的な羽搏きが影を落してゐたのであらう。當時、院の切迫した激情に對してただひとり働哭をもつて烈しく應和し奉つたのは、鎌倉の將軍·實朝であつた。悲劇はかうして同時に實朝をも捉へたのである。しかし、右に述べたやうな、雷はたためき雲噴く山上のすさまじい光景は、西行のなんら知るところでなかつた。彼は野の子であつた。といつて、西行が庶民になりきれたか否かなどと傳記を漁るのでない。ただ、彼の繊銳な詩感が庶民たちの夢や歌にのびのび浸り得る場を摑んだと云ふのである。そこに〓冽な泉を見出したとするのである。この泉はごくささやかであつたが、それがなければ人はみづからの像を知ることができなかつた。後鳥羽院が西行を直接の契機として立たれた所以はここにある。しかし、一面、中世人がその民族的主體性を回復するためには、自己を庶民の間に投げ出してこれを入間性としてひとまづ客觀しなければならなかつた。彫刻などで75
素剛なリ、アリズムが勃興したのはこのためである。西行の歌は、客體なる自然に投入することによつて自己を捉へたもので、言ひ換へれば有心の放棄によつてかへつて眞のごを回復したものであつて、ウーズウォースを自然主義者と云ふやうな意味でならやはり自然主義者と呼んでさしつかへない。しかも、自然に向つて放散し且つそのなかに溶解した視覺の自由さによつて俳諧への道につながるのである。76四自然と感傷現世的榮華の限りを盡した人としてみづから「望月の缺けたることもなし」と謳つた御堂關白道長がよく擧げられる。しかし、道長がそのやうに歌つたことにすら、榮華や快樂のはかなさを知りつつこれを歎美したやうなひびきが漾つてゐるではないか。事實、法華經信者としての彼の數々の佛事·供養はよく知られてゐるとほりであるが、諸靈の菩提を祈つて彼が香爐の火を打つと、一度で點火したので、感淚にむせび、人々もまた流涕雨のごとくであつたといふ(御堂關白記)。また、鳴らない新調の法螺をみづから「三寳に奉らむ」とて吹いてみると、高く鳴つたので、これにも一同は感悅して泣いたと傳へられてゐる(同)。有名な法成寺の御堂供養にしても、彼岸の幻影を夢みるためのはかない演劇にすぎなかつた。かうして、晩年の彼には、榮華への滿足はもはやどこにも見られなかつたのである。記)。77
平安後期の多くの佛像に見られる腫れぼつたい顏やけだるい手足には、厭世をさへ耽美の對象に化して辛ふじて支へる心の或る姿勢がうかがはれる。しかも、この脆い均衡はたちまち崩れかかる。我々はもともと、いくら快樂に浸つてもそのなかにすつかり耽溺しきれるやうな民族ではない。まして、その現世意識をひとたび失したとなると、脆くも堰を切つたやうに無常感へ流れ込んでいつたのは當然である。といつて、それは、他の民族に見るやうな荒凉たる思想的懊惱のはてにではない。無常感はいはば、一つのみづみづしく稚ない感傷でしかなかつた。このときただひとり『今昔物語』(卷十九)の參河守·大江定基は、感傷に抗して現實の刻薄さを見究めようと身構へる。腐爛してゆく愛妻の死體を視つめながら現世の愛執の醜さやうとましさに烈しく身を搖すぶられ、厭離の念に驅られるが、彼はなほも執拗に人生の姿を視つめようとする。それから參河の國の風俗なる風祭に猪を屠るのを見た彼は、人の心の無慙さをさらにみづから突きとめるべく、下人に命じて雉子を捕へ、生きたままに羽をむしつて調理するのをぢつと見てゐた。しかし、鳥がばたばたして痛々しく叫び聲を立てるのやだくだく血の流れるのを默つて見てゐた彼も、最後に心ない下人たちがそれを賞味するのを見た時、つひに大聲を立てて泣き伏してしまつ78た。彼が直ちに參河を去つて出家したのはもちろんである。しかし、このことを單に佛〓史の資料として强ひて陰鬱に塗り潰して考へてはならぬ。佛〓が示す怖ろしい觀念の舞臺に身も魂も奪ひ去られたことは事實であつたとしても、衝動はむしろ、人の血を腐濁せしめる文化の偏結や衰頽に堪へられない素朴な心のをののきにあつた。たとへば、人を殺傷しない日が少いくらゐに猛惡無道であつた讃岐國多度郡の五位源某が、ひとたび彌陀の救ひのことを〓へられるや、阿彌陀佛を聲高く叫び求めて西に向つて走りつづけ、お答へがないかぎり山があらうと海があらうと決して歸るまいと云つて、つひに海岸の樹に上つて唱名しながら往生を遂げた(今昔物語)、といふ話は、芥川龍之介の小說に書かれたりしてよく知られてゐる。このことから人は多く、ひとたび罪業に醒めた者がいかに烈しく救濟を求めたかをしか見ないやうであるが、私はかへつてそこに深い荒廢に堪へ得ない素朴で〓純な魂のをののきを感得する。そして、そのをののきは、思想と云ふよりは存在の浪曼的解體としての感傷であつて、榮華の重みに堪へ得ない道長の感傷とすこしも變らないのである。煩瑣な形式の呪縛にかかつてゐる無氣力の時代にあつては、そこから遁れ出すためには、與へ79そこから遁れ出すためには、與へ
られたその現實を浪曼的にひとまづ解體しなければならぬ。「苦學寒夜紅淚露袖、除目春朝倉天在目の一句が一條帝をして「敢へて御膳を差めず、夜御帳に入りて涕泣して臥さ」せたまひ、それによつて藤原爲時は立身の途をひらいたのであるが、さういつた感傷はすでに平安後期を通じて一つの底流をなしてゐたのである。後一條帝の寵臣であつた源顯基は、榮華に誇り得る身ながらつねに世のはかなさ常なさを思ひ、琵琶を朝夕に彈じては、あはれ罪なくして配所の月を見ばやと歎じたと傳へられてゐる。やがて帝が崩御あられてからは、梓宮には主殿司すら居らず、夜に入つても燈を奉る者もないのを見たとき、彼は、人の心のはかなさに泣いて直ちに出家してしまつた。しかし、求法の心からと云ふよりは、やはり感傷の形としての出離なので、その後もなほ「世を捨てて宿を出でにし身なれどもなほ戀しきは昔なりけり」(後拾遺集)と歌つたのである。また、花山院の御出家は、愛せられた女御の薨去を動機としてゐるのであるが、「世の中の人いみじう道心起して尼法師になりはてぬときこゆ」榮華)る例の數多い當時の世相を覽はして、世のはかなさを嘆かせられ、「いかで罪をほろぼさばや」と思ひ亂れたまふ御心が深かつたといはれ、萬乘の御尊身をつひに頭陀抖撒の境涯に任せられたのは申すも畏い極みであらう。80平安朝も末期に及んで出家遁世する人々が眼に見えて激增し、到るところの山蔭や野の果てに形ばかりの庵を結んで法華を誦し彌陀を唱へる人々が見られ、また破笠蓬衣で諸國を行脚する念佛者も多くなつた。しかも、「罪なくして配所の月を見」るこれら僧形の隱者たちを慰めるものが白然の風光のみであつたことは、自然感の解放のために寄與するところ少くなかつたやうにおもはれる。西行以前に於ける寒納の抖撤詩人として增基、能因、行尊などが學げられてゐるが、「都をば霞とともにの能因法師にはここで觸れないとしても、あらためて見直してよいのは增基法師であらう。この法師は、延喜あたりの人らしく、紀行に『いぬほし』あり、熊野や東路に杖を引いて西行の先蹤をなしてゐる。ともすれば四方の山邊にあくがれし心に身をも任せつるかな。神無月、時雨ばかりを身にそへて、知らぬ山路に入るぞ悲しき。いとどしく嘆かしき世を神無月、旅の空にも降る時雨かな。81いとどしく嘆かしき世を神無月、
冬の夜にいくたびばかリ寢ざめして物思ふ宿のひましらむらむ。山鶏、かしらも白くなりにけり、わが歸るべき時や來ぬらむ。82僧正行尊は、台密の高僧であつて、保安四年天台の座主に任ぜられ、西行十八歲の保延元年に示寂したが、白河院や鳥羽院の熊野御幸の導師であつたこの僧正こそ、西行の境涯にとつて直接の先蹤をなしてゐると云ふことができる。この僧正が年少の頃から山野に交はつて行脚を重ねたのも、哀傷と鬱悒の心を幽かにひらくためであつたらしいことは次の代表作によつて明かであり、しかもその詠風と歌はれた內容とは西行に著しく接近してゐる。Sentimenさ1〓ourneyは、日本では早くも西曆十一世紀の頃に行はれてゐたのである。もろともに哀れとおもへ山櫻、花より外に知る人もなし。草の庵をなに露けしと思ひけむ、波らめ窟も袖は満れけれ早き瀨に堪へぬば第、われも憂き世にめぐるとを知れ。見し人はひとりわが身に添はねども、遲れぬものは淚なりけり。數ならぬ身を何故に恨みけむ、いきざよき空のけしきも恃むかな、とてもかくても過しける世を。われ惑はする秋の夜の月。自然のふところに佗しく甘えるやうにして流離の日を續けてゐるうちに、西行もまた、さういつたやうな出家にしばしば出會つて、同じ運命を語り合つてゐる。永曆といふから保元の變のあつた翌年のことになるが、その年八月、西行が信濃の佐野の渡を通り過ぎたとき、蟲の音そぞろた野末に、薄、刈萱、萩、女郞花等を手折つてそれらでもつて庵を結んでゐる一人の僧があり、見るとそのなかには硯だけが置いてあつた。そして、それらの草々には、和歌が書いて結びつけられてあつた。薄の戶に「薄しげる秋の野風のいかならむ、よなよな蟲の聲の寒けき」とあるのを初めとして、刈萱の都、蘭の襖、萩の戶などにもそれぞれ歌が書いてあつた。西行は殊のほか優しさを感じてその僧に話しかけたところ、「この春より」と答へたきり、僧はつひに物も言はなかつた。彼は尊さに淚を拭きあへずそこを立ち去つて進むと、繪のやうに美しい山川の水上に一人の年老いた出家が居るのに出會つた。「ここにもまたかかる人をはしけり」と思つて近寄つてみ83
るに、端坐したまま眠るやうに往生を遂げたところであつた。そして、木の枝には和歌が結びつけられて、「紫の雲立つ身にしあらざれば、澄める月をばいつまでも見る」と書いてある。これ前の出家と同行であらうと思ひ引き返してこのことを告げると、その僧はただ、哀れにこそ」といつて硯を引き寄せ、「迷ひつる心の闇を照らしこし月もあやなく雲隱れけり」と書き終るや、筆を持つたまましづかに膜目して果ててしまつた。西行は、悲しともあさましとも云へぬ思ひに泣く泣く野邊の送りを濟ませるのであつた。「あはれ貴かりけることかな。生死心に任せたまへるぞありがたく侍る。(中略)人里も待らずまた持ち蓄へるものも見えず、何として暫くの程の命をも支へたまへりけるぞや。われ世を背いて廣く國々を經めぐりしに、貴き人あまた見しかどもかかる人にいまだ會はず侍りき」と『撰集抄』(廣本卷六)には記してある。これを西行自身が書いたか否かは問ふところではない。ただ、ここでは、時代の感傷が西行に託して語り傳へたことを願みればよいのである。感傷は時として激越な形を取つた。たとへば、願西は、飛鳥寺のほとりに草廬を結んでから、小豆をもつて念珠に代へてひたすら彌陀を唱へること十數年、天承元年に、小豆はつひに七百石84に達した。また翌長承元年には、かねて法華の行者であつた楞嚴院の信敬は、自分の左脚の骨に釋尊の像を刻し、脛骨やうやく癒えてから手の皮を剝いで彌陀三尊の像を描き、さらに手の指でもつて觀自在、大勢至の二像を供養し、願滿ちて安らかに往生した。さうかと思ふと、「佛僧を敬はず、經〓を信ぜず」(後拾遺往生傳)にただ武勇の人としてのみ知られた攝州渡邊郡の武士·源傳は、人に知らしめぬ日夕千遍の念佛を怠らず、長承三年、三十六億唱名の願成つて來迎の紫雲に包まれたと傳へられてゐる。西行出離の前後には、特に、これらに似た例が數限りなく語られてゐる。熊野詣でもいはば、この時代を浸したさういふ感傷の大なる出水を示す一つの徴表であつた。しかし、そこで最も注目すべき事實は、出家した人々が寺院に於いて佛に仕へず、流離や沈默の行のなかに自己の姿を消し去つてゐることである。思ふに、當時の寺院は、權門に媚びて官榮に眼も眩むのでなければ、忍辱の手にあるまじき刄を砥いで爭鬪常なく、累をしばしば朝家にまで及ぼしてゐる狀態で、衆生濟度の實をすでに失つてゐたのである。增賀法師が內憤の發するままに公家や山門の徒を驚かしたのも、かうして當然のことと云へる。また、慈惠僧正良源のごときは、天台座生たるべしといふ夢〓があつたとき願てゐたのである。のことと云へる。85
はくはわれ現世の榮進を思はず、何ぞこの告あらんや」と云ひ、その願文にも老母あるために隱樓の志を抑へて塵巷にとどまると記してゐる(日本高僧傳要文抄)。とにかく流離を求めるこれらの人たは、虚僞や東縛に充ちた煩雜な社會生活に堪えがたい苦痛を感じ、その痛みやすい胸を眞如の宿る自然のみに歸して、形影ひとり相弔しつつ靜かに來世を待つのであつた。そして臨終のとき彼等はしばしば來迎を見た。來迎に接して紫雲たなびくうちに示寂することこそ、生涯の二つとない本願であり、詩的憧憬の最大の對象であつたのである。このころ多くの往生傳が書かれたのも、かういつた要求からであつた。「後のこの記を見む者、疑惑々生ずるなかれ。願はくはわれ一切衆生とともに安樂國に往生せむ」と『日本往生極樂記』は序に記してゐる。臨終に際して來迎の相を見ようとする願ひは、そのために觀相といつて佛の姿を心のなかにありありと描き出すための練習をすら招くに至つてゐる。また、來迎のこのやうな現實化または可視化への努力によつて多くの來迎圖が描かれたこと、しかもその來迎圖に於いて地上の山水が大きな役割を持ちはじたことは、注目に價ひする。源信作と傳へられる高野山の有名な來迎圖には地上の山河と花紅葉が一隅に小さく描かれるにとどまつてゐたが、この頃からそれが繪の前面に大きく浮び上り、謂86ふところの山越彌陀の構圖を取りはじめる。知恩院の山越彌陀圖を見ると、綠の山々がはるかにたたなはつて畫面いつぱいに波うつ上を、斜めに橫ぎつて紫雲ひるがへり、金色端嚴の彌陀佛が聖家とともに天降らうとしてゐる。東京の靈雲寺に藏せられる吉野曼荼羅圖では、遠く俯瞰せられた吉野の山々に薄紫の霞がそことなく漾ひ、金色にまどろむもろもろの佛たちがここの山蔭、かしこの溪間に點々と美しく散在してゐる。西行も時には、花吹雪する吉野の山の嶺に立つて、このやうな曼茶羅の幻想に浸る時がなかつたであらうか。ともあれ、解氷してゐこここから水が溢れるやうな感傷の出水に映つて、今や自然が、その花や綠や雲や鳥が、人々の眼にいきいきと迫りはじめた。西行は歌つてゐる、花ゆゑに身をうき草となりにけり、散るを惜しめば誘ふ山水。-季節のいろいろな移り變りを通じて、花につけ紅葉につけて歌の姿や詞も變へ、その情趣をさながら感ずるやうにすべきである。たとへば、早春の雪のなかから咲きはじめた軒近い紅梅とか民家の垣根の梅は、色はそれぞれ異つてゐても、匂ひに變りなく手折る袖にも移り、香り身87
に泌むここちするのに、花のさかりになると、吉野山の櫻は消え殘つた雪にまがひ、まして禁裡の奥ふかく咲いた爛漫たる花は、[白雲がかさなつてゐるのかと怪しまれる。春が深くなつてゆくにつれ、井出の山吹に蛙が鳴き、岸の藤浪に夕の鶯が行く春を惜しむかのやうに歌つて、いろいろと身に泌むここちするとき、岩に圍まれた沼の社若とか山の麓を明るく染める岩躑躅などに至るまで、そのそれぞれに感懷を催さないものはない。卯月にもなると、垣根の卯の花蔭に時鳥が來て鳴いたり、籬の撫子が朝露を含んで咲いたりするのも、まことに印象の深いものであるが、それほどでもない路傍の樗の花が風に香つたり、庭の紫陽花に夜ごく置く露に宵の月がほのかに宿つたりするのも、やはり風情があつて棄てがたい。(古來風體抄)右は俊成卿が季感に就いて論じた章の一端であるが、彼のやうな堂上派にあつても、今や『古今』以來の風景感をこのやうに綜合的に整理して、移り變る季節の細かな陰翳を觀察せよと〓へなければならなかつたのである。したがつて、出離して山野に交はることは、それほど暗鬱な出來事でなく、考へられるよりもずつと明るい現象であつた。『台記』によれば、北面の佐藤義〓は家富み年若くして心に愁ひなかりきといふ。心に愁ひがなかつたとは云へないかもしれないが、88しかしその愁ひはすくなくとも沈鬱な哀哭を含むやうな性質のものでなく、何ものかに甘へかかつて遠くを憬憧するそぞろな感傷的憂愁にすぎなかつた。さういふ魂が社會の煩はしい日々に堪え得ないで隱者の生活を求めるのは當然であらう。ウオーズウォースがその晩年を捧げて完成に努めた詩篇がThe Rocluse" (隱者)であつたことは、この詩人の志がどこにあつたかを示してゐて興味ふかい。この詩篇に於いては、とペイタアは曾つて論じた、彼は、みづからそのやうな世界に退隱してゐる、승しかも、ウォーズウォースは、この隱者の心をもつてかへつて、滿滿する自然感の解放を行つたのである。この點は西行にあつても同樣である。藤岡作太郞博士はその西行論(同氏本『異本山家集』附錄)に述べてゐる、「平安朝の末に至りて天下の風雲穩かならず、源平二氏權を爭ひて洛中つひに合戰の巷となりたれど、堂上人の遊情は元のごとく、空しく從來の乾燥なる生活を送れり。かくして文學社會の境遇と思想との共に依然たるとき、ひとり歌道に眞の革新あるべけんや。新樣を試みるものも、内容は舊のごとくただ辭句のうへに刻苦するにすぎず、彼等は感ぜずして作り、これを聞く者も人工あつて天工あるを知らざりき。かかるとき西行ひとり群を離れて毅然として立てり。すでに繁縟なる社會の束縛を受89
くるを屑しとせずして身を雲水の行くに任する境界に入れる者、歌壇にありてもまたその道の法則と稱するものに掣肘せらるるに堪へんや。彼は、詩歌管絃にうきみをやつす上達部にあらず、六條二條の門に雌伏する歌人輩にあらず、敢へて和歌を學ばず、辭章を練らず、天禀の才をもつて興來ればすなはち詠あり」(七五、六頁)。かうして「その作歌は堂上に坐して强ひて構成するものにあらずして、自然によつて動かされたる感興を文字のうへに現はせるなり。されば西行の歌がひとり群衆を拔き、後人をして感に堪へざらしむるも、決して偶然にあらざるなり。」(八〇頁)かうして、王朝四百年の詩歌史を通じて曾つて見られなかつた自然の〓新な聲がひびきはじめなそれは、ブランデスの謂はゆる「イギリス自然主義」に通じたところをもち、早くも近代詩の胚芽をそのなかに含んでゐる。なぜなら、自然を親しく意識してそのささやかな動きにも耳を傾け目を瞠るのは、近代詩の樣相の大きな特質となつてゐるからである。-山里に住んでゐると、空がうつすらと霞みわたつたのでどうやら春らしいと知るばかりであるが、やがて霞は、藻鹽やく浦のあたりに停まつたまま、煙を爭つてゐるかに見えるやうになる。さういふとき、野邊に出て若葉をつむのも、この霞が昔を遠く隔ててしまつてゐるのだと考90る。へると、へると、感傷をそそることではないか。まもなく鶯が鳴きはじめる。霞に咽ぶやうな鶯の曙の聲ほど淨らかなすがすがしいものはないが、しかしまた、春雨蕭々たる竹林に爲が鳴き濡れてゐるのも捨てがたい風情がある。それはそれとして、待ちきれないのは櫻である。まさか春を忘れる花でもあるまいからと考へる。それなのにどうもそはそはしてくる。世を捨ててもこればかりは昔に變らない。まだ花は咲く筈もないのに、花信を尋ねてまだうら寒い山路を辿つたりする。或るとき、山人に花が咲いたのかと尋ねると、さあ、白雲らしいよと答へて行つたこともある。どうして花と云へばこんなに心が浮き浮きするやうになつたのか。ともあれ、吉野山で梢の花を見た日から、すつかり心を奪はれてしまつたらしい。いくら分身してもよいからあらゆる山々の爛漫たる花を見盡したいとさへ考へる。山路を分けて花を尋ねてゐると、いつのまにか日が暮れかかり、宿權島の聲も霞んで聞える。と、そのうち、曉と思はれるやうな明るい音が響く、花に暮れる入相の鐘が。かうしてのどかに歩いてゐると、むかし白河の關を越えた時の、東から來る人の影とてもほとんどないあの山中の花が憶ひ出される。雲のやうな花の下で月を眺める、月は朧ろに煙つてゐる。春の曙は鶯の鳴かり、と、91
くのさへ何か異なつて聞えるのは、花の色が聲に染るからでもあらうか。さてその花もたちまち送ふやうにして散りはじめる。そんな時は梢の鶯に花のことばを聞くここちがする。風に誘はれた花のゆくへは知るよしもないが、惜しむ心だけが身に殘つてゐる。花は散つた。訪れる人ももうなくなる。さうして山峽はふたたび閑寂に包まれるであらう。やがて夏······。西行の歌のなかから以下すこし拾つてみよう。92ほととぎす偲ぶ卯月も過ぎにしを、なほ聲をしむさみだれの空。ほととぎす、深き嶺より出でにけり、外山のすそに聲のおちくる。さみだれの頃にしなれば、荒小田に、人にまかせぬ水たたへけり。さみだれは、いささ小川の橋もなし、いづくともなく水脈に流れて。旅人の分くる夏野の草しげみ、葉末に菅の小笠はづれて。雲雀あがる大野の野原、夏くれば、涼む木蔭をねがひてぞ行く。うなゐ兒がすさみに鳴らす麥笛の聲におどろく夏の晝臥し。播磨瀉、灘のみ沖に漕ぎ出でて、あたり思はぬ月を眺めむ。月澄みて夙ぎたる海の面かな、雲の波さへたちもかからで。雲晴るる嵐の音は松にあれや、月も綠のいろに映えつつ。波にやどる月を汀にゆりよせて鏡にかくる住吉の岸。打ち具する人なき道の夕されば、聲たて送る轡蟲かな。難波江の入江の蘆に霜冴えて浦風寒きあさぼらけかな。雪ふれば、野路も山路もうづもれて、をちこち知らぬ旅の空かな。つらなりて風に亂れて鳴く雁の聲のしどろにきこゆなるかな。古畑のそばの立つ木にゐる鳩の友よぶ聲の凄き夕暮。月澄めば、谷こそ雲はしづむめる、嶺吹きはらふ風にしかれて。とはいへ、後世の南畫家などが竹林の榻にみづから畫中の人として風月を怡しんだやうに自然に怡しみ浸ることは、西行の望み得ないところであつたらしい。高根政次郞氏はこのことを評して述べてゐる、さあれ、ここに悲しきは、さばかり親しめるその自然のふところにだに彼はなほ心ゆくばかり抱かるるを得ざりき、そは、厭離を人生の第一義とせる彼の傳統的信念が、この種93そは、
の觀照をだになほ且つ去りがたき執着の一端としてこれを覊絆視せざるを得ざりければなり、と(『歌人西行』第一篇、一頁)。すなはち、自然のふところに抱擁せられる筈の詩人が、詩を容れぬ小乘的理想にゆくりなくも投じてみづから運命の絲を縺れしめ、それとは知らずにその縺れる絲の〓のつらさに泣いたといふのである。たしかにそのとほりであらう。ただ流離の悲しみのなかに求めてみづから浸るところがあつたことも事實である。すなはち、「罪なくして配所の月を」といふ感傷のグンディーがそこに見られるのである。しかも、それは、このやうに自然に甘えかかる氣もちから云つても當然のことであつた。自然は裏切らない、私もない。いついかなるところでも抱擁してくれる。そのやうに夢みて鳴咽しつつ自然に歸する人たちは、もともと安定を失して溢れる心情すなはち感傷をみづから持てあましてゐると云へる。何といふことなしに、ただ感情が傷み、あてもなく漂泊しようとするのである。鴨長明の『無名抄』によると、幽玄とは「たとへば秋の夕暮の空の景色は、色もなく聲もなし。いづくにいかなる故あるべしともおぼえねど、すずろに淚こぼるるごとし」と說かれてゐるが、さういふ意味ではしたがつて幽玄の典型的形態が西行の作に見られると云つてさしつかへない。と94何となくおぼつかなきは、天の原、霞に消えて歸る雁群吉野山、花をのどかに見ましやは、憂きがうれしきわが身なりけり。佗び人の淚に似たる櫻かな、かぜ身に泌めばまづこぼれつつ。花も散り、淚も脆き春なれや、またやはとおもふ夕暮の空。行く春をとどめかねぬる夕暮は、曙よりも哀れなりけり。つくづくと物思ひをれば、ほととぎす、心に餘る聲きこゆなり。何となく物哀しくぞ見えわたる鳥羽田の面の秋の夕暮。くまもなき月の光にさそはれていく雲井まで行く心ぞも。眺むるにまことしからぬここちして世に餘りたる月の影かな。風になびく富士の煙の空に消えてゆくへも知らぬわが思ひかな。95私は先に、西行と庶民の關係を述べた。しかし、このことをもつて直ちに西行文學が庶民的だ
などと考へてはならぬ。變革に力を點じたその情〓が庶民層の擡頭に沿ふてゐることはたしかであるが、西行自身は何よりも藤原時代の人であつて、堂上的〓養を母の乳とともに深く吸ひ込み、その現實から隱遁はしたもの、別にそれと對立したわけではなかつた。庶民の歌の律動に動かされるところはあつても、そこにある少しの曇りもない無邪氣さ、屈托なさには達し得なかつた。彼は、自分の歌ふ聲のすばらしい〓新さをみづから知ることなく、歌論のうへなどでも〓してその頃の常識を深く疑はうとはしなかつたらしい。二見浦に於いて談した彼の歌論を抄錄したといふ『西公談抄』が傳へられてをり、眞疑の程はわからないが、ただそのなかで、和歌は美しくよむべく、『古今』の風體を本としわけても雜の歌をつねに見るべし、心につきて優に覺えんその風體を詠むべし、と〓へてゐるのは、おそらくそのまま彼の見解であつたのであらう。遁世はしても都戀しさからなかなか脫けきれなかつた西行である。すくなくとも意識的には、彼は、堂上文化に對してほとんど批判的でなかつたやうにおもはれる。西行のこのやうな歷史的限界は、彼をして無縫の羽搏きを天に描くことを得ざらしめ、縹渺たるうちにもつねに咽び泣くやうな鬱悒の翳りを漾はしてゐる。彼に歌はれた自然にしてさういふ96ふ翳りを含んでゐないものはほとんどない。彼の境涯は客觀的にはあまり暗影に包まれてゐるとは見えないが、崩壞しつつある公卿社會の蔽ひがたい悲愁と厭世の浪に彼が泛べられたことはたしかである。その浪からしてもともと深刻でなかつたのは、堂上人にあつてもなほ、この民族の特徴としてどうにもならぬ爛熟や頽廢を伴ふまで舊に執することなく、若々しい熱情をまだどこかに保有してゐたからであらう。彼等は、榮華のさなかでわれからそのその儚さを說き、その解體を暗示した。所與の境涯のうちにその反措定を見る一つのゆとりある觀照態度を風流と呼ぶとしたら、それはまだ風流としての意識を缺き、またそれだけに所與の現實に堪へ得ない哀歡のそぞろな交流に浮かされてゐる。かうして、いかなる生活ももはや彼等に滿足を與へない。彼等はすべて、時代を横ぎる感傷の出水に浮びはじめる。公卿社會が崩壞したことは事實であるとしても、その事實から來る苦痛よりも、その日になつてもなほみづから投影した夢への哀歡に浸るのである。しかも宗〓界の動向は、かういつた感傷の濤を吸收するのにあまりあつた。人々は智力と抑制とを通じて三昧に達しようとする久しい苦鬪に疲れて、自己を無遍の慈悲の大洋のなかに溶け込97
ませる念佛の思想を狂喜しはじめた。この信條の組織者なる源信や源空は、聖道門のかたはらに新しく淨土門による救濟の道を樹ててゐる。これによると、人が救はれるのはむしろ阿彌陀佛とその發現としての觀音の愛によるのであり、ほとんど母性と覺しいこの佛に向つてなされる念佛だけで淨土に赴くことができる。要するに、無限の愛と易行との宗〓が、浪曼的な碧一色の濤となつてこの國を横ぎつたのである。人々は愛の無遍の廣がりに咽び泣き、阿彌陀の名を唱へながら群をなして都や村を棄て去つた。蓮の莖から拔き取れる絲で曼茶羅を織つたり縫ひ取りをしたりして生涯を送る婦人たちも多くなつた。そして、嗚咽に充ちたこの熱狂と捨離を防げる現實との矛盾は、それみづから人をして思ひ餘らしめるものを持ち、涯しなく憧憬してしかも何にも浸りきれぬ多感な澱み多い心情を作つてゐる。幽玄といふ名稱で俊成が言ひたかつたものも、おそらくさういふ心情に近いのであらう。この道に心を入れむ人は、よろづの春、ちとせの秋の後は、みなこのやまと歌のふかき義によりて、法文の無盡なるをさとり、往生極樂の緣と結び」云々(古來風體抄)といふのは、彼の僞らない宿願であつたにちがひない。しかし、「世の中は道こそなけれ」と歌つた常識人の俊成には、身98をもつて幽玄の新風をひらくことができなかつた。解釋はいろいろに變つても中世の藝術論の理想として久しく受け繼がれた幽玄體を-俊成に代つて-樹立したのはまさしく西行法師である。『撰集抄』の僞作を始め、いろいろの繪卷、物語、謠曲、江戶時代の夥しい俳諧等にうかがはれる彼のたいへんな人氣は、その國民詩人的要素によるところも多いにちがひないが、もう一つの理由は、近代にまでも根を引く中世藝術の理念を覆ふものとして解釋せられ得る包括性を彼が持つてゐることである。ただ、中世的重壓のもとにあつた藝術家たちが次のやうに論じたとき、西行に體現せられた俊成卿の所論などとはかなり異つてしまつてゐる。たとへば、心敬の『さざめごと』は記してゐる、「もとより歌道はわが國の陀羅尼なり。(中略)西上人も歌道はひとへに禪定修行の道とのみ申したまひしとなん。まことの境に至り侍らば頓語直語の修行なりと云へり。」中世に入るとこのやうに意志的な錬成がふたたび始つてくるが、西行の時代は解體が當然の成り行きでありむしろ使命でもあつた。彼は、社會を浸した感傷の出水に浮んで、堂上の凍結した99
歌人たちの歌ひ得なかつた生活のあらゆる現象を內的衝動の赴くままに自由に歌つた。したがつて、辭句のごときは深く注意するところでなく、新派に與みしてことさらに新奇にしたりはしないが、新しい技巧を取り入れるにすこしも吝かでなかつた。御子左派のやうに三代集に範を限らないとはいへ、その流麗と雅馴とは、彼の最も學ぶところであつた。ただ、謂はゆる「平懐體」(定家)として「ふつふつ云ひ」(八雲御抄)て用辭を重視しない結果、時に蕪雜、粗笨にわたり、修辭の當を失するものが見られるばかりでなく、佳什に入り混つて駄作もずゐぶん殘されてゐる。ペイタアはウォーズウォースを論じて、彼の詩に於いてほど「深い個性的な力をもつた作と、ほとんどなんらの個性をも有しない作との、亂雜な混合物」はないと論じてゐるが、これは西行の場合かなり當てはまつてゐる。西行もまた、「あらゆる創造的制作では、詩想の多くは、受働的に靈感をそのまま忠實に享ける人に與へられると信じて、みづから忠實にこれを待ち、そして事實、ときどき大きなものを賦與された彼には、また、心の空虛と弛緩との時もあつた」のである。我々は今日、すべてが融解し、分裂し、剩すところなく崩壞して、その有機的生成が止み、ただどうにか機械的にまた恣意的に組み立てられ、〓念によつてだけ秩序立てられるやうな、う100の無形式の時代に住んでゐる。このやうな時に西行の革新の意義を正しく評價することは困難かもしれない。西行出現の意義は、歌論として隈なく意識づけられるまでになつた形式の美しい痳醉力から脫出するところに懸つてゐたからである。したがつて、濫作と認められるくらゐ緊密さを缺いた歌が多く、散漫な月並みの作が少からず見られるとしても、これは已むを得ない。歌界の現狀に對しても、批判的主張をはつきり持つてゐたわけではない。齡から云つて孫のやうな定家卿に歌合の判を乞ふてゐるくらゐで、論や批評に〓して疎かつたことすら、彼に於ける無形式の力の奔流を示してゐると云へる。そしてここに、この時代に於ける浪曼的解體の意義があるのである。101
102五出離の日を繞つて西行法師が俵藤太から九代の裔に當ることは前に述べた。右大臣魚名の末なる藤太秀〓は下野掾鹿島女を母として生れたが、爾來その家系に東國の血がかなり濃厚に入り混つてゐることは想像に難くない。西行·佐藤義〓(或ひは憲〓、則〓、範〓)は、元永元年、平〓盛と前後して生れた。『尊卑分脈』によれば、父は左衞門尉康〓、母は監物〓經女。仲〓といふ兄があつたことになつてゐる。しかし、西行に觸れた『台記』の記事に、「家富み年若くして心に愁ひなし、つひにもつて遁世す、人これを歎美す」とあり、彼が佐藤氏の惣領でなかつたら、出家したからと云つて世人がことさら「歎美」する筈もないから、川田氏も論じてゐられるやうに(『西行〓究錄』一六七頁)これを次男とするのは信じられない。しかも、結城系圖の一本には、西行の方を兄としてゐる。ただ、ここの系圖の仲〓の註に「內舍人、一說康〓弟」とあり、むしろこの一說のはうが眞實かもしれない。また、西行の子に隆聖僧都があることになつてゐるが、これも甚だ疑はしく、いま引用した系圖には「一說弟」と註してあつてこのはうに信が置けさうである。或ひは小山系圖が記してゐるやうに甥であつたのかもしれない。また、奥州御館系圖には、子として隆聖の外に一女を記してゐる。右兵衞尉義〓が出家して西行と號したのは、『台記』および『百練抄』によれば、崇德帝の保延六年十月十五日である。法名は圓位、別に大寶房とも號した。蓋し圓位とは性相圓融の位を謂ふのであらう。『台記』に「俗時より心佛道に入る」と記してあるやうに、出離の志は少年の頃から深く兆してゐたもののやうである。これは、出家前の作と考へられる『山家集』卷末の「百首」中にある次のやうな歌によつても知られる。103
山ふかく心はかねて送りてき、身こそ浮世を出でやらねども。104また東山の或る僧菴を訪ねたとき詠んだ次の歌は謂はゆる柴の菴を初めた覗いたもつと年少い日の印象がよくうかがはれる。柴の菴と聞くは賤しき名なれども、世にこのもしき住居なリけり。北面の義〓をして出離に至らしめた決定的な動機は何であつたか。彼の評傳を草するに當つてまづ困惑するのはこの點であるが、動機らしいものはあつたにちがひないとしても、それが必ずしも決定的に作用したとは云へないやうに考へられる。彼をして決意せしめたものは、主として時代の現實や思潮とこれに對する彼の曇りない感受性とであつたと云つてさしつかへない。わけ、ここの溪間、かしこの岩間から流れはじめた感傷の出水は、すべての多感な少年をその渦に卷き込むのに充分であつた。やつと物心のつきはじめた義〓九歲の春、すなはち大治元年三月、同族に屬する陸奥の藤原〓すなはち大治元年三月、同族に屬する陸奥の藤原〓衡が中尊寺を建立した。八十餘字の堂塔、八百餘の禪房、金碧燦爛たるありさまは、誇らしさを交へて彼の耳に傳へられたにちがひない。しかしこの建立を一代の榮華として〓衡はまもなくその年の七月に他界した。前年の冬、殺生禁斷の令が發せられたが、さらにこの年の六月、諸國の魚網八千八百餘張の回收と燒却、鷹犬、鶴鵞などの放生が行はれた。十月には、法皇の勅によつて市中の籠の鳥が放たれた。翌年、十歲の二月には、白河院、島羽院および待賢門院のお揃ひでの熊野御幸があつた。院新院に於かれては、この年しばしば法勝寺に御幸あり、一月には五重塔、三月には愛染像百餘軀、七寶塔および小塔一萬基、四月には觀世音像百餘軀をそれぞれ慶したまふた。七月にはまた、東殿に御して不動尊像一百軀、畫像一千鋪を慶したまふと傳へられてゐる。「波もなく風を治めし白河の君」と西行が後に讃へ奉つた白河院が寶算七十七で崩御あらせられたのは、彼が十二歲の大治四年七月七日であるが、その數日前に院は二條東洞院第に御幸あり、佛像三十軀を慶せられてゐる。翌五年十月、勅によつて狩獵の禁が嚴にせられた。さらに翌長承元年三月、得長壽院(三十三間堂)の建立成り、觀音像一千軀が置かれた。また十月の傳法院密嚴院の落慶供養には島羽院の臨幸を仰いでゐるが、「時に十五歲の義〓も、北面武士になつ105
たばかりで、或ひは供奉したかもしれない」(川田氏『西行〓究錄』五三頁)。長承三年の正月にも、島羽院と待賢門院の熊野御幸があつた。翌保延元年、義〓十八歲の二月、白河院、鳥羽院の熊野御幸をいつも先導し奉つた僧行尊が七十九歲で示寂した。哀愁に充ちた詩的抖撒のダンディーのなかにその生涯を送つたすぐれた歌人であるこの大僧正の姿が、彼の意識に强く投影しなかつたとは考へられない。私はひそかに、西行といふ號は、行尊の行から取られたものでないかとすら疑つてゐる。ところで、先に述べたやうな殺生禁斷の令や落慶供養の數々の營みは、上に於ける宗〓的危機の克服の努力であつたとともに、下に於ける寺院からの離脫に對應するものであつた。延曆寺や興福寺の騒擾が烈しくなつてゆくかたはら、無限の愛を夢みる宗〓的情熱の形で、存在に關するあらゆる舊〓念の浪漫的解體が行はれつつあつたのである。106うらうらと死なむずるなと思ひとけば、心のやがてさぞと答ふる。うつつをもうつつとさらに思はねば、夢をも夢と何か思はむ。燈火のかかげ力もなくなりて止る光を待つわが身かな。水乾たる池にうるほふ滴リを命に特む魚鱗や誰。世の中になくなる人を聞くたびに、思ひは知るを愚かなる身に。(以上「百首」より)少年にして義〓はすでに「うらうらと死なむずる」ことに思ひを致してみづから感傷の淚にひたつてゐる。「燈火のかかげ力」もなくなつたと云ひ、「水乾たる」池の魚に自分を譬へてゐるのももちろん感傷的誇張である。また、戀の對象に强く迫らうとせず、今までのことを月だけに語らせて「影に沿ひつつ」立ち離れようと歌つてゐるところにも、少年の日の甘へるやうなまた拗ねるやうな感傷の身のくねりが感じられる。月にいかで昔のことを語らせて影に沿ひつつ立ちも離れむ。山櫻咲きぬと聞きて見にゆかむ、ひとを爭ふこころとどめて。(前町北面に出仕しては院の御覺えめでたく、眉目衆にすぐれ、弓馬の道に於いても重代の名譽に背かず、まことに「家富み年若くして心に愁ひなし」と見られながら、多感な義〓は、櫻咲く頃にもなると、われともなく感傷に浮き立つて洛外の山々をひとりあてもなくさまよひ、塵外流離の夢にみづから淚ぐんでゐたのであらう。そんなとき、心を打ち明けて語り合つたのは、おそらく107
彼の部下で東國をふるさととする鎌倉源次兵衞季政、すなはち影の形に添ふごとく西行の近邊から離れないでその生涯を送つた後の西住上人であつた。彼等よりもすこし先に出家したらしい友の空仁を法輪寺に共に訪れて語り合つたこともあつた。或る日、その歸りを空仁が大堰川の渡りまで送つて來たとき、筏が流れてきたのを見て、「······早く筏はここにきにけり」と詠んで別れを惜しんだ。「薄らかなる柿の衣着てかく申して立ちたりける。いと優に覺えけり」とその時の空仁の姿を傳へてゐる西行の詞書のうちに、我々は、彼自身の憧憬の美しいダンディーを汲みとることができる。かうして早い頃から法心にそぞろ傾いてゐた義〓の眼には、世俗の機構があまりに荒々しく無殘に映つたにちがひない。行尊入寂の年八月、海賊を平定して父忠盛とともに凱旋した平〓盛が從四位下に叙せられたとき、〓盛と同じく十八歲であつた義〓は果してどう考へたであらうか。云ふまでもなく、〓盛とは北面の同僚で、その家庭にも出入りして北面の上役なる忠盛とも親しかつたのである。しかし、西行にとつてはおそらく、その頃の天災地禍のはうがもつと痛烈に胸を搖すぶるもの108その頃の天災地禍のはうがもつと痛烈に胸を搖すぶるものであつたらしく考へられる。白河院崩御の翌年の災旱のために天承と改元せられたのであるが、飢渴はさらに續いて巷に餓李の影が絕えず、これに加へて疫病の猖獗が甚しかつた。そのため、〓盛凱旋の年には、官稟が開かれて窮民の賑恤があつたくらゐで、翌年正月の齊會には公卿饗無飯とすら記されてゐる。その年の大飢饉で、記錄にこそ殘つてゐないが、餓死者の數はおそらく養和のそれを凌いだもののやうである。しかも、かういふ情勢は莊園の獨立とその國有地蠶食に拍車をかけ、社會的基礎をやうやく危殆に瀕せしめるに至つた。たとへば、大治二年の淡路の國司の奏文に、神社、佛寺、權門、勢家の莊園みな膏肥の地を占め官物を致さず國役を勤めざるがゆゑに、在々所々の調丁等、これを利とし、爭ひてその地に入り、莊家薨を連ね棟を比し、郡〓の戶口日々に減少し地ありて人なし、と記されてゐる。したがつて領主間に土地の爭奪が起り、わけても大莊園を領有した寺院間に紛爭が頻發し、それぞれ私兵を擁して嗷訴のために事ごとに京へ亂入した。また、さういつた殺伐な世相を反映して火災が續出し、內裏、仙洞を初めとして名だたる社寺殿宇の炎上はほとんど數知れなかつた。末法到來の豫言は、かうして今や人々の眼に抗しがたい現實となつて迫りはじめたのである。109
といつて、もともと感性の人である西行がそのため深刻な思想的苦悶に陷つたとは考へられない。彼は、たぶん、さういつた現實の醸し出す雰圍氣を厭ふべき「憂き世」として感じ取り、いよいよ厭離の念を强めたのにちがひない。そこへたまたま「申すも恐れある上薦女房」(源平盛衰記への悲戀の問題が起り、尾山氏の美福門院說を假に信じるとすれば、上皇の彼への御寵遇が深ければ深いほど苦しい思ひをしなければならなかつたし、主筋の德大寺家を通じてその御周邊に關係の深かつた待賢門院の御腹なる崇德院に最も微衷を捧げまつらうとしたために、立場はいつそう複雜になつた。詳しくは述べてゐられないが、美福門院の御腹の近衞院が春宮に立たれるに及んで、君臣の契りをひとしほ深く感じてゐる義〓は、崇德院の御心中を察しまゐらせて人知れぬ苦境に陷つたこととおもはれる。彼の出家はその翌年のことであつた。次の歌はたぶんその時の心境であらう。110善惡を思ひ分くこと苦しけれ、ただあらるればあられける身に。吳竹の節しげからぬ世なりせば、この君はとてさし出でなまし。ただ繰り返しておくが、かういつた事情が必ずしも出離の根本動機になつたのではない。て『源平盛衰記』(卷八)のやうに「源は戀ゆゑ」とだけする說には與みしがたい。まし眺めきて月いかばかリ偲ばれむ、この世し雲の外になりせばと歌つた頃には、まだまだ切迫した息づかひは感じられない。この時代のあらゆる純眞な魂を洗ひつつあつた無限の愛への溺沒的な憧憬は、滿されない心のままに、ともすると人をしてその對象に拗ねさせたり、それからわざと離れ去つてわれとわが身の悲愴さに鳴咽せしめたりする。さういふところには、眞の悲劇は決して起らない。西行も、悲劇解體の時代の詩人として、月にひとり昔を偲びながら「影に沿ひつつ立ちも離れ」ることに、感傷的な舞臺上の悲劇を思ひ描いたのではなかつたか。この意味で、精神史のうへに古典的と近代的との二つの型があるとすれば、まさしく西行こそは、近代的な型を代表する最初の人であつたと云へる。彼が戀の切實を初めてみづから知つたのは、むしろ出家してからのことであつたらしい。111
112右兵衞尉義〓が出離して緇衣を纏つたのは保延六年十月十五日。鳥獸戯〓の有名な鳥羽僧正覺猷が示寂したのは九月十五日であるから、ちやうどその一と月あとのことである。剃りたての頭も見るからに寒々として山里の冬を迎へた靑道心は、豫期にまさる荒涼と蕭條に驚いてゐる。遁世ののち山家にてよみ待りける山里は庭の梢の音までも世をすさみたる景色なるかな。世を遁れて鞍馬の奥に待りけるに、筧の氷まで來ざりけるに、春になるまではかく待るなりと申しけるを聞きてわりなしや、氷る筧の水ゆゑに、思ひ捨ててし春の待たるる。これによつてみると、その年の冬は鞍馬に居たらしい。『山家集』の題は「山里は」の歌に由來するといふ說もあるやうであるが、それがもし本當だとすると、この歌を第一聲として自然に包まれた新しい生活に入つたのであらう。「わりなしや」の歌も、悲鳴と云ふよりはむしろ好奇心が輝いてゐる。翌永治元年には、東山に移つて雙林寺や長樂寺の坊の近くに性んだらしい。次の歌にはまた、自然への新鮮な驚異と解放された輕やかた歡びが現はれてゐる。夜もすがら、惜しげなく吹く嵐かな、木の葉の落つるたびごとに、わざとしぐれの染むる紅葉を。心浮かるるみ山べの里。神無月、しかし、そこで二十五歲の春を迎へた西行は、人に誘はれて白河の櫻を見に行つた歸りに、散るを見て歸るこころや櫻花、昔に變るしるしなるらむと、ひとりうなづいて、二年ほどになる寒納生活を振り返つてゐる。今や、好奇心が消えて自然への平靜な凝視が加はつてくる。同時に、自然の爽かな呼氣に觸れて初めて、彼の歌は、獨自なひびきを帶びはじめる。川田氏の說に從へばこの年の秋から嵯峨小倉山の麓に轉じ、さらに大堰川を渡つて法輪寺にも籠つたらしいが、このあたりから次のやうな秀吟が作られるに至つた。113
人に具して修學院にこもりたりけるに、小野殿見に人々まかりけるに具してまかりて見けり。そのをりまでは釣殿かたばかり破れのこりて、池の橋わたされたりける事柄繪に畫きたるやうに見ゆ。祈誓が石立て瀧落したる所ぞかしと思ひて、瀧落したるところ目立てて見れば、みな埋れたるやうになりて見わかれず。木高くなりたる松の音のみぞ身に泌みける。瀧落ちし水の流れもあと絕えて、昔かたるは松の風のみ。この里は人すだきけむ、昔もや、寂びたることは變はらざりけむ。小倉の麓に住みけるに、鹿の鳴けるを聞きて牡鹿鳴く小倉の山の裾近み、ただひとりすむわが心かな。廣澤にて人々月を翫づること待りしに池に澄む月にかかれる浮雲は、拂ひのこせる水錆なりけり。嵯峨野の見し世にも變りてあらぬやうになりて、人去なむとしたりけるを見てこの里や、嵯峨の御狩の跡ならむ、野山もはては褪せ變りけり。秋の末に、法輪にこもりて詠める114て見けり。大井川、井堰に淀む水のいろに、秋深くなるほどぞ知らるる。山里は秋の末にぞ思ひ知る、哀しかりけり木枯の風。秋暮るる月なみわかぬ山賤の心美む今日の夕暮。ここには、自然の前に佇む自己を視つめる彼の沈痛な息づきが感じられる。思ふに、齡から云つても、靑春の日がやうやく去らうとしつつあつたのである。しかし、このころの歌がすべて秋風落莫の情景にのみ充されてゐるのは、かへつてその裏面の弛んだ生活の一面を豫期せしめる。これは私だけの創作的な假定であるが、近衞帝の御卽位は彼の豫期したところであつたとしても、待賢門院の御落錺があつてからは、捨離の身にも何か安からぬ思ひを抱いて御周邊に出入してゐるうちに、おのづから脂粉の匂ひに包まれるに至つたらしい。康治二年(川田氏說)の暮春のころ、東國行脚を思ひ立つたのも、たぶん、かういふところに理由があつたのであらう。「鈴鹿山うき世をよそにふり捨てて」といふ歌の句も、さう考へると何か納得がゆくやうにおもはれる。仁和寺菩提院の女房たちに暇乞ひして歌を詠み交はしてゐるのも、この時のことらしいといはれる。115
菩提院の統子內親王は崇德院の御同母妹であらせられた關係から、その御所にしばしば伺候してゐたのであつた。粹人の源三位賴政ともここで落ち合つたことは或る歌の詞書に見えてゐる。さて、鈴鹿の峠を越えて伊勢の大神宮に額づき、二見の浦から鳥羽灣に出、船で伊良湖崎に渡つて海邊づたひに天龍の渡、箱根の峠を越えて東國に入り、白河の關へとかかつてゐる。平泉に基衡父子を訪ねたらしいと云はれてゐるが、白河以北のことは杏として知るよしもない。しかし、この大旅行によつて心境が著しく變化したと考へられない。むしろ、出家前には考へたこともなかつた心の迷ひがしきりに信念を曇らせたかにさへ見える。116世を捨つる人はまことは捨つるかは、捨てぬ人こそ捨つるなりけり。捨てたれど隠れて住まぬ人なれば、なほ世にあるに似たるなりけり。世の中を捨てて捨て得ぬここちして、都離れぬわが身なりけり。捨てしをりの心をさらに改めて、見る世の人に別れはてなむ。これらの歌には、自責の思ひが深く罩つてゐる。「惜しからぬ身を捨てやらでふるほどに、長き闇にはまた迷ひなむ」と言ひ送つてきた人に對して、世を捨てぬこころのうちに闇こめて迷はむことは君ひとりかはと返してゐる。久安元年八月、たまたま待賢門院の崩御があつて、を感じたが、彼にはまだ、行くべき方途すら定まつてゐなかつた。して、ともし火の消えたやうな寂寞闇のしるべせよと乞ふ人に返思ふとも、いかにしてかはしるべせむ、〓ふる道に入らばこそあらめと詠んでゐる。待賢門院にお仕へした中納言局が世を背いて小倉山に隱棲したとき、さういつた自分の身に比べて愍れさに堪へがたく、「事柄まことに幽に哀れなりけり、風のけしきさへ殊に悲しかりければ」と云つて次の歌を送つてゐる。山おろすあらしの風の烈しきをいつ習ひたる君が住家ぞ。17
女院崩御ののち世を儚んで隱棲した堀川局、兵衞局、中納言局、師局などと西行がこのころしきりに往復したのは、迷執の闇のなかで相憐れむここちからであつたもののやうにおもはれる。戀の古疵が疼きはじめたのもこのころであらうし、捨て去つた妻子の身を考へると何か居たたまれなくなる歲にもなつてゐた。しかも、女院御尙祥の法金剛院の庭は夏草の茂るに任せ、新陵に詣でる人とてもない、人情浮薄な時代であつた。あれを想ひこれを偲ぶとき、悒懷うたた堪へがたいものがあつたのであらう。118もちろん、世を捨てたと云つても、いはば隱者になるだけのことで、當時の風習として、俗緣とも交渉を失はず、中には子を儲ける者も少くなかつたくらゐで、西行だけが山林に韜晦して妻子を顧みなかつたとは考へられない。まして、すぐれて熱誠な情愛の人であつた西行は、をりにつけて妻子の身を思ひ按じたにちがひない。覺雅僧都の六條房にて、心ざしふかきことに寄せて、花を惜しむ心の色の匂ひをば、子を思ふ親の袖に重ねむ。花の歌よみ侍りけるにたとへば、この歌にも肉親の眞情が暖かく流れてゐる。彼に子があつたことはたぶん事實なのであらう。妻にあてたらしくおもはれる歌に次の數首がある-世を遁れけるをり、ゆかりなりける人のもとへ云ひ送りける世の中を背きはてぬと云ひおかむ、思ひ知るべき人はなくとも。月月見れば契りおきてしふるさとの人もやこよひ月を見るらむ。はるかなる所にこもリて、都なりける人のもとへ月のころつかはしけるうはの空なるかたみにて、思ひも出でば心通はむ。歲暮に、人のもとにつかはしけるおのづから言はぬを慕ふ人やあると、安らふほどに年の暮れぬる。月のみや、119
修行して遠くまかリけるをり、人の思ひ隔てたるやうなることの侍りければよしさらば、幾重ともなく山越えて、やがても人に隔てられなむ。國々めぐりまはりて、春歸りて吉野の方へまからむとしけるに、づくにか跡とむべきと申しければ花を見し昔の心あらためて吉野の里に住まむぞとおもふ。題しらず吉野山、やがて出でじと思ふ身を、花散リなばと人や待つらむ。年の暮、縣より都なる人のもとへ申しつかはしけるおしなべて同じ月日の過ぎゆけば、都もかくや年は暮れぬる。120人のこのほどはい吉野山、これによつて見ると、歲末とか遠くへ旅立つ時などはそのをりをりに消息を傳へたり會つたりしたらしい。「おのづから」は、便りをくれないのは無事で忙はしさに取り紛れてゐるのであらうから、まづまづ安心して暮れを迎へる、といふ意味。「おしなべて」は、謂はゆる只事歌のやうであるが、家開かはやじじ意意感がともてゐる。不を見亡に」的にさな洗いを「よしさらば」の詞書にある「人の思ひ隔てたるやうなこと」が何であつたかはわからないが、「やがても人に隔てられなむ」といふ感情は、西行の性向の一端を示してゐるやうにおもはれる。「思ひ知るべき人はなくとも」も、同じやうなところから發してゐるものであらう。西行の妻は、俗說によると、後に尼となつて長谷寺で彼と邂逅した。また娘も尼となつて母子共に天野別所に住んだと語られてゐる。しかし、『十訓抄』では、娘はあつたが死んだことになつてゐる。すなはち「西行法師男なりけるとき、愛しくしける女の三、四ばかりなりけるが、重く煩ひて限りなりける頃、院の北面の者ども、弓射て遊びあへりけるに、いざなはれて心ならずののしり暮しけるに、郞等男の走り來て、耳に物囁きければ心知らぬ人は何とも思ひ入れず、西住法師いまだ男にて源次兵衞尉とありけるに、目を見合せて、このことすでにと打ち言ひて、人にも知らせず、さりげなく、いささかの氣色も變らでゐたりし、ありがたき心なりとぞ西住のちの人々に語りける」(下卷第八)。いかにも尤もらしいこの記事がもし本當であるとしたら、西行出離の動機はむしろこのはうにありさうであるが、今のところ信じられない。「儚くなりて年經にける人の文を物のなかより見出て、娘に侍りける人のもとへ見せにつかはすとて」121
淚をやしのばむ人はながすべき、あはれに見ゆる水莖の跡122と詠んでゐるが、「娘に侍りける人」とは誰のことであらうか。それを彼の娘とするか否かは、今はただ人々の想像に任せるよりほかない。妻なる人ではないらしいが、次の連作の「淺からず契りありける人」もまた、おそらく最も親しい者の一人にちがひなからう。淺からず契りありける人のみまかりける。あとの男、心のいろ變りて、るやうにきこえけり。古里にまかりたりけるに、庭の霜を見てをりに會へば、人の心ぞ變りける、枯るるは庭の葎のみかは。あはれみし袖の露をば結ひかへて、霜に泌みゆく冬枯れの野邊。亡き跡を誰訪ふべしとおもひてか、人の心の變りゆくらむ。慕にまかりて思ひ出でし尾上の塚の路絕えて、松風悲し、秋の夕闇。淺茅深くなりゆく跡を分け入れば、袂こそまづ露は散りける。昔にも遠退るやうにきこえけり。歸り詣で來て、男のもとへ、なきかげにもかくやと覺え侍りつると、申しつかはしける思ひ出でてみ山おろしの悲しさをときどきだにも訪ふ人もがな。友人として最も交渉が深かつたのは、在俗のころ彼の郞黨として同じく北面にあつたらしい元の鎌倉次郞源季政、すなはち西住であつた(八代集抄その他)。歲は西行とほぼ同じくらゐ、出離もどうやら同じ頃に行はれたらしい。西住は鎌倉の出で、東人の血を承け、剛勇の士であつたと傳へられてゐる。出が東國であつたため、西行初度の東國巡遊の時に案內をしたのであらう。そして、この時のこととして、次のやうな話が巷間に傳へられてゐる。二人で天龍川にさしかかつて渡船に乘つたとき、ふとしたことで船頭が西行を打つてその額を傷つけたのを見て、默つてゐる法がないと云つて西住が慍ると、そんなことでは佛弟子たることはもちろん自分の同行にも價ひしないと叱つて、袂を拂つて、ひとり飄然と立ち去つたといふ。この話はどうかと思ふが、この旅にどこまでか西住が属從したこと、驛路の亂れた時代であつたからそれぐらゐの危難があつたにちがひないことだけは、どうやらたしかである。ともあれ、彼等の親交は終始變らなかつたも123
ののごとく旅もたいていは一〓にし、歌會にも揃つて顏を出し、その關係で知己、朋友も共通のものになつたらしい。『傳燈廣錄』傳法嗣祖統派の續八卷に「季正入道、西行とともに一双をなす、西住と曰ふ、理性法脈を得たり」と記してあるやうに、彼等が共に醍醐理性院に參じてその法脈を承けたことは、西行の或る歌の詞書に「醍醐に東安寺と申して理性房の法眼の房にまかりたりけるに」云々とあるに徴しても明らかである。西住の病ひが革まつて今生の別れに人々が枕頭に驅けつけたとき、西行は、月が明るかつたので、124もろともに眺め跳めて秋の月、ひとりにならむことぞ悲しきと悲嘆の聲を洩らしてゐる。西住に次いで親しかつた寂然から、「亂れずと終り聞くこそ嬉しけれさても別れは慰まねども」と慰められて、この世にてまた會ふまじき悲しさに、すすめし人ぞ心亂れしと彼は答へてゐる。また、遺骨を高野に納めに行つてくると、ふたたび寂然から「入るさには拾ふかたみも殘りけり、歸る山路の友は淚か」と言つてきたので、いかでもと思ひわかでぞ過ぎにける、夢に山路を行くここちしてと返してゐる。相慰め相勵ましてこの世の幾山河を踏み越えてきた眞の伴侶を失つては、の〓澄を怡しんだ彼の心もさすがにうたた寂寥に堪へかねるものがあつたのであらう。寂然は藤原爲忠の末子、俗名は賴業、その長兄に寂念·爲業、次兄に寂超·爲隆がある。兄弟いづれも遁世して大原に隱棲し、世に大原三寂と呼ばれた。寂超の出家は康治二年で、西行のそれより四年遅れてゐるが、唯心房·寂然もこれと同じ頃に遁世したものと見える。この寂然の出家はおそらく、近衞帝崩御(久壽二年)以後であらうと考へられてゐる。この兄弟と西行との交遊は、院ならびに母后門院を御中心として行はれたらしく、彼等は世代の味爽の風をさへそこに感じつつあつたのかもしれない。したがつて、保元の變による院の讃岐遷幸は、彼等に少くない打撃を與へたと見え、『山家集』に、老來そ125
讃岐へおはしまして後、云ひつかはしける言の葉のなさけ絕えにしをりふしに有り合ふ身こそ悲しかりけれかへし(寂然)歌といふことの世にいときこえざりければ、寂然がもとへ126敷島や、絕えぬる道に泣く泣くも、君とのみこそ跡を偲ばめとあつて、新風そよぐ藝苑の御主宰が院にあらせられたことは疑ふべくもない。院が讃岐におはします頃、松山にはるばる訪ねて慰めまゐらせたのも、寂然であつた。彼の幽寂な歌風は西行のそれに通じ、性至純で西行とよく話が合つたらしい。『大鏡』の作者とも傳へられる長兄の寂念は、皇太后大夫に累進した後、弟たちよりずつと遲れて出離した。友人に源三位賴政がある。『尊卑分脈』によれば、寂念、寂超の母は待賢門院女房であつたといふ。寂超の妻で美福門院に仕へた加賀は、後に藤原俊成に嫁して定家を生んだが、寂超との間にも子があり、男を隆信と稱した。後白河法皇、平重盛、源賴朝、法然上人等の畫像の作者として有名な畫伯がすなはちこれであり、その隆信の子、信實も畫家として日本美術史のうへに巨大な位置を占めてゐる。隆信は、若い者の好きな西行に可愛がられたらしく、西行の勸めた伊勢百首にも應じてゐる。しかし、それはずつと後のことである。出離前後の交遊のうちで、歌友としては外に俊成があつた。その父の俊忠とも親しかつたことは、「勢賀院の花さかりなりける頃」云々の詞書ある歌の贈答によつて知られる。勢賀院とは、まだ前齋院と申し上げてゐた頃の統子内親王の御所で、西行がしばしばそこに伺候したことは先に述べた。『台記』康治元年八月七日の條に「故俊忠」と見えるから、俊忠はおそらく西行の出離後まもなく亡くなつたものらしい。俊成も崇德院を繞る雅宴に列してそのなかで新風を吸つた一人であつた。しかし、その院の御眷顧を忘れたわけではなかつたとしても、後に院の宸翰を拜しつつ人目を憚つてひそかに女房のもとに返歌したごときは、保身に戀々とした彼の性向をよく示してゐる。またたとへば、平家都落ちのとき、今まで親しくしてゐた忠盛が詠草を懷中して訪ねて來たのに、彼は、門にも入れず勅撰のみぎりはゆめゆめ疎かにすまいと約しながら、『千載集』撰上のとき、貢,しかも讀人知らずとしてこれを採つてゐる。また定家が若いころ御退位あられ127
た高倉院に同情し奉つて御佛名の會に參らうとすると、平家を憚る俊成がこれを烈しく叱りつけた、と定家自身が記してゐる(明月記)。久安百首に添へて崇德院に上つた長歌にもすでに現はれてゐるやうに、その翼々たる小心をひたすら利達に用ひたのである。西行は、かういふ俊成と心から溶け合つたわけではないらしい。ただ、その學識と精緻な理論とには耳を傾けさせるものがあり、やはり兄事はしたのであらう。俊惠法師との交遊も見落しできない。俊惠は源俊賴の子、六條、二條の歌風に對しておのづから一派をなし、父の雋銳さはなかつたかはりに、「五尺のあやめ草に水をかけたるやうに歌はよむべし」(後鳥羽院御口傳)とみづから〓へたやうな、姿に流れと餘韻のある幽婉な作をもつて知られてゐる(鴨長明は彼の晩年の弟子であつた)。永久元年生れ、西行より五つ年上であつたから、早くから交遊はあつたものと見てよく、特に次のやうな歌は西行の好むところであつたらう。128眞菰草つのぐみわたる澤邊には、つながぬ駒も放れざりけり。夜もすがら物思ふ頃は、明けやらぬ閨のすきさへつれなかりけり。ふるさとの板井の〓水、水草ゐて、月さへ澄まずなりにけるかな。주深くも簾のそよぐなるかな。龍田山、梢まばらになるままに、この外では、堀川局等の叔父で歌をよくした仁和寺僧綱·覺雅、西行の遠い親類に當る歌僧·勝命等との間にそのころ來往があつたにちがひないが、これは大して重要でない。また今に鞠聖として崇められる待從大納言·藤原成通、顯仲の兄雅實の次子で舞樂の名手であつた右大臣·源雅定、まもなく落餝して例の信西となつた碩學·藤原通憲父子、行成卿の末で能書家として知られた藤原定信、鵺退治の傳說で有名な源三位賴政などとも交渉あり、特に成通とはごく親しかつたもののごとく、平治元年、亂の直前に二十一も年上の成通に勸めてこれを出家せしめてゐる。待從大納言成通のもとへ後の世のこと驚かし申したりける返しごとに驚かす君によりてぞ永き世の久しき夢は醒むべかりける。返し驚かぬ心なりせば世の中を夢ぞと語るかひなからまし。(成通) 129
落餝して栖蓮と號したこの成通は、藝道の書として貴重なその『成通卿口傳日記』にもうかがはれるやうになかなかの大才であつて、西行に深く影響するところがあつたやうにおもはれる。すくなくとも西行は、在俗のころ、この人に蹴鞠や今樣の手ほどきを受けたのであらう。待賢門院の女房たちでは、中古六歌仙のうちのただ一人の閨秀歌人であつた堀川局と最も親交があつた。源雅定の從姉妹に當るこの堀川は、神祇伯·顯仲の娘で源三位賴政と囁き合つたこともあり、賴政は西行より十四も年上であつたから、堀川の年齡もほぼこれによつて想像できる。門院に仕へる前は、前齋院怜子内親王家の女房であつた。門院の御落餝とともに尼になつたが、まもなくその崩御に會ふや、130夕されば、わきて眺めむ方もなし、煙とだにもならぬ別れはと云つて慟哭し、その後は洛西仁和寺のほとりに隱棲したが、久安百首の御催しの時に長歌を捧げて志を述べ、門院御在世の昔を戀ひ、ひたすら崇德院に縋りまゐらせたもののやうである。かし、讃岐に院が遷幸あらせられてからは、この多感な情熱の女性は、よるべない身の徒らに老けるのを悲しんで、後れゐて涙さへこそとどまらぬ、見しも聞きしも殘Dなき世にと斷腸の思ひを絞り、その晩年を流離のなかに査として消え去つてゐる。兵衞局は堀川の妹で、門院崩御の後は上西門院(菩提院前齋院)に仕へた。西行の家集にしばしばその名が見えるから姉と同じく親密であつたらしい。この外、中納言局、帥局、伏柴の加賀局等とも交際があつた。しかし、右に擧げた女房たちとの間に戀愛的感情の動いた形跡はない。高貴の方々では、崇德院を御中心として、その御母后たる待賢門院、御同母妹なる上西門院、御同母弟たる仁和寺御室·覺性法親王等の御恩寵に浴した。後白河院も同じ門院の御腹に渡らせられる關係から、西行はまた、親近し奉つたにはちがひないが、家集にほとんど御名をとどめてゐないところをみると、保元の變の後に御遠慮申し上ける氣もちが起つたためであらうか。或ひはまた、承安元年初夏、後白河院熊野へお成りの途すがら住吉にお立ち寄りあられたとき、たまたま行き合した西行が洩らした次の感慨、131
絕えたりし君が御幸を待ちつけて神いかばかり嬉しかるらむいにしへの松のしづ枝を洗ひけむ波を心にかけてこそ見れ132を見ても、これは私だけの見解かもしれぬが、よそながら和歌の神なる住吉神に托してその道の復興を祈るおもむきが見えるところから推察して、院の御志の雄大な羽搏きをもともと理解すること少かつたのではないかとも考へられる。そのくせ、西行文學の眞髓は、院の好ませたまふた庶民の歌を措いてはほとんど考へられないのである。六戀と旅と私は先に、西行が戀の切實さを初めて知つたのは、むしろ出家してから後のことであるらしいと書いた。悲劇をみづから作り出して身をくねらせる王朝人の悲しい心理主義は、和泉式部あたりまででほぼ終つたと見てよく、あとにはただ、その悲しさを夢みるもつと涙脆い、もつと腫れて彼感になつた、感傷の物語が殘された。人工のいろいろな心理屈折の遊びのかはりに、それにすら疲れてぼんやりと綠の照明だけを視つめる、人の居ない舞臺だけが眼の前にあつた。そして、この舞臺は、式子內親王や建禮門院右京太夫に於ける焦燥の蛾の明りをめぐる美しい羽搏きによつて終るのであるが、西行は、そのやうに內面に蛾を點じるかはりに、やはり初めは流通する感傷のダンディーに浸つたにすぎない。ただ、それが結果として堂上歌界からの眞の遁走となつたところに、彼が單なる感傷詩人に終らなかつた所以があるのであらう。そ133
俊成が「山の奧にも鹿ぞ鳴くなる」と云ひ、また子の定家が「吉野の山もなき身なりける」と歌つたのも、彼等の卑俗さからばかりでなく、時代の美學をそのなかに映した思ひ入れがあつたためと解してよい。事實、西行が自然のなかに愛の無限の美しさを見出さなかつたら、出離もまた單なる身ぶりの一つでしかなかつたにちがひない。しかし、稀有のみづみづしい感性の所有者であつた彼は、すでに年少の日に、自然の荒い呼氣を蹠に感じ、その綠のなかにみづからの相聞の流れを大きく映し出して捉へ、擴大せられた一つの茫漠たる感傷をもてあましてひとり尙佯しつつあつた。それは、舞臺のあとに浮ぶ殘像の感傷的反芻にとどまらぬ解放の爽かな豫感を包んでゐた。彼の眼にうつすらと漾つた霧は、いくらか夜の體えた吐息であつたとともに、それ以上に、〓愁にも似た味爽のあてどない憧憬であつたのである。そして、その憧憬のなかには、眼醒めた庶民の歎きがひそんでゐた。庶民の歌の調子は、疲れた王朝人の會話にいつか忍び入つてきて、たとへば綜合者たる俊成などにすらそれが現はれてゐる。しかし、彼等にとつてそれは、どことなく地下から響いてくる鬼の酒宴のやうで、まねずにをられず、まねてしかも呻くやうなそのみづからの聲に脅えたのである。しかし、西行を通じて庶民の謠のしらべは、やうやく出口を134見出し、曙のそことない囁きに變つた。霧が流れ、露が光り小鳥たちがさざめいた。西行は、そのなかに身を投影して初めて湧くやうな相聞の悲しみを知つたのである。奈良朝末期の女性たちの相聞歌が家持邸の宴遊に流れ込んだ日、神々の去つた虚ろな自然の背面に、多樣な心理屈折を客體として映寫してみて初めて自己を知る、謂はゆる心理主義が發生した。それは、したがつて、物語の發生でもあつた。人々は、機智や聯想の纎銳な角度で社交のなかにいろいろと反射せしめることによつて自己を捉へた。そして、この傾向はそのまま後宮を中心とする王朝の文學傳統を形づくつた。たとへば、夢幻に託してはかない運命の影に憧れ、せめてもその失意の悲しみをやらうとして、空しく自己の內部を視つめた小野小町は、すでに王朝の初めの日に、「佗びぬれば身を浮草の根を絕えて」の悲しい自己喪失を告白しなければならなかつた。しかも、小町に於けるこの化粧の破綻すらも、人工美學の一つの化粧法であつたと云へる。まして歌合や贈答歌は、王朝に不可缺の風景であつた。詩は今や、無限者に呼びかける無遍の擴がりを捨てて、庭球のやうに人と人の間に互ひに反射し返されるもの、すなはち相聞としてのみ存續する。しかし、式子内親王まで行つてこの相聞も終りを告げる。內親王の御歌は、もはや相西行は、そ135
聞ではなくて獨白であつた。また西行も、內親王より少し先に出て、自然のなかに相聞の悶えを止揚したのである。しかも、山野に交はらむとの歎きは西行だけのものではなかつた。彼の前にも花山院、增基、能因、行尊等があり、同じ頃では後白河院またその望みをお持ちあそばされた。いづれも、旅によつて自然と相聞とを架橋し、鬱結した志をそこに展かうとしたのである。幾山河を放浪する心はすでにそれみづから、身一つに支へかねる自己をそれらの名もない山や水のほとりに埋め去らうとする哀しい感傷に濡れてゐる。かうして、その表白は、やがて封建の世ともなれば、つねに「かりそめに言ひ散らされしたはぶれごと」(芭蕉)として落葉のやうに作者から捨て去られ、またそれゆゑにそのなかに彼の熱い血が單められる。「身を分けて見ぬ梢なく盡さばや」と西行が歌つたやうに、旅はいはば涯しもない分身である。王朝の初めの日に小野小町が「誘ふ水あらば」と相聞の破綻を嘆いたとき、それはすでに、在原業平とともに、無限の分身としての旅を相聞の終りに架橋しようとした增基法師の出現を待つてゐたと云へる。この成り行きはきはめて當然である。しかし、「冬の夜にいくたびばかり寢覺めして物思ふ宿のひましらむらむ」と云つてひとりまた西行も、內親王より少し先に出て、自然のなかに相聞の悶えを136夜の宿に轉輾したこの增基も、また「早き瀨に堪へぬばかりぞ水車、われも憂き世にめぐるとを知れ」と空しくひとところに縛られて廻る身を訴へた行尊も、まだまだ自己を自然に託しきつてゐない。旅をもつて相聞を歌つた初めての人は、やはり西行であらう。西行をもつて王朝短歌の傳統は終りを告げる。そして、放浪の步一步に自己を棄ててそのあだなる「たはぶれごと」に眞實を知る俳諧の悲しい運命が始まる。しかし、西行自身は、ぞのことを決して意識しなかつたし、したがつてもちろん正風の悲劇などはまだまだ知らなかつた。彼に於いては、王朝のもののあはれの相聞が、ほとんど肉感的に旅のうへに蔽ひかぶさつてつねに透明にこれを包んでゐるからである。芭蕉に至ると、肉感と自意識との葛藤が現はれてくるが、その浪曼的心情によつて造形性がかなり融解してゐるとはいへ、西行はまだ肉感的な無縫の把握力を失つてゐない。相聞の抒情がそのまま旅を描いてすこしも間然するところない所以は、ここにある。137
王朝の相聞は、式子内親王等に於ける天上の愛の悲歌によつて終つた。戀愛は今や一つの深い沈默に包まれはじめる。サロンの中性化した虚々しい心理交換が終つて、黑衣に包まれた女たちの手でひそやかに性の純潔が洗ひ出され、丈夫ぶりに纏綿する献身の咽び泣きと化してくる。そして、それを蔽つて雄壯な英雄的ロマンスの時代が茫と浮び上つてくる。息もたえだえな舞のうちにしづやしづと呼びかけたかの白拍子の歌は、もはや王朝風のもののあはれではなかつた。西行もさういふ雰圍氣に早くから接してゐたとすれば、或ひは大丈夫の志を捨てずに刀を撫して起ち上つたかもしれない。しかし、彼の育つた環境がこれを許さなかつた。彼は、その對象と拾身の激情を共にして羽搏きを行爲に示さうとせずに、當時の風習として年上の女たちの喃々に圍まれ、永遠のベアトリーチェに導かれて悲劇の階段を下りるかはりに、戀を捨てるべく空しく旅に遁れてゐる。ところで、西行の戀の對象は誰であつたか。それは目上の人であつたらしいことは若干の歌からも察せられるが、「申すも恐れある上薦女房」說はかなり疑はしい。高貴の女性に想をかけて叶はぬ戀に出家する譚は歌書などに古くから見えるところで、その女性は時によつて女院、京極御138息所、猛者の娘等であり、また男は志賀寺の僧、禁中の掃除人、猛者の下人等になつてゐる。れらの譚が集大成せられてつひにお伽草子の『西行』が書かれ、阿漕の話もいつとなく織り込まれるに至るのであるが、我々は今のところ、さういつた傳說の一つとして以上に西行の戀を描き出すことができない。また、誰に戀したかといふやうなことは、さほど重要でもない。ここではただ戀する人があつたと知るだけで充分である。しかし、光にも述べたやうに、彼がみづから否定した有心のすきごころの核心に戀を發見したのは、出家してからかなり後のことであつたらしい轉身後の修行にいそしんでゐる頃には、「捨てはててき」と思ふ身に殘る「花に染むこころ」を否定する氣もちは强かつたのであらう。嘆かじとつつみし頃は、淚だに、うちまかせたるここちやはせし。しかし、彼の性狀から云つても、この抵抗は長く續かなかつた。惑ひきて悟り得べくもなかりつる心を知るは心なりけり。139
その心を無理に抑へつけてもかへつていつまでも闇に迷はなければならないことが解つたとき、彼は、煩惱を煩惱としてすなほに知らうとしら。煩惱に發する綺語の戯れも、讃佛乘の緣となり得て初めて許される。ひとたびさう悟つたとき、今まで抑へてゐた相聞の歌が口を衝いて流れはじめた。それは、おそらく、高野に入つた後、しかも大峯修業などを經てからのことであたう。140身を知れば、人のとがとも思はぬに、恨み顏にもぬるる袖かな。哀れとて人のこころのなさけあれな、數ならぬにはよらぬなさけを。數ならぬ心のとがになしはてて、知らせでこそは身をも怨みめ。今ぞ知る、思ひ出でよ契りしは、忘れむとてのなさけなりけり。辛からむ人ゆゑ身をば恨みじと、思ひしかどもかなはざりけり。何せむにつれなりしを怨みけむ、逢はずばかかる思ひせしやは。何とては、數まへられぬ身のほどに、人を怨むるこころありけむ。嘆くとも知らばや、人のおのづから、哀れと思ふこともあるべき。何となくさすがに惜しき命かな、あり經ば人や思ひ知るとて。憂きたびに、などなど人を思へども、かなはで年のつもりぬるかな。人を恨み身を恨んでは、結局身ひとりの運命を思うて佗しくもだえてゐる。夏草の繁りのみゆく思ひかな、待たるる秋の哀れ知られて。哀れとてなどとふ人のなかるらむ、もの想ふ宿の荻の上風。身をも厭ひ、人のつらさも嘆かれて、思ひ數ある頃にもあるかな。眺めこそ憂き身のくせとなりはてて、夕暮ならぬをりも分れね。人知れぬ淚にむせぶ夕暮は、引きかつぎてぞうち臥されける。うたたねの夢を厭ひし床のうへの今朝いかばかり起き憂かるらむ。逢ふとみしその夜の夢の醒めであれな、長きねぶりは憂かるべけれど。もの思ひまだ夕暮のままなるに、明けぬと告ぐる柴鳥の聲。わりなしや、いつを思ひのはてにして、月日を送るわが身なるらむ夜もすがら恨みを袖に湛ふれば、枕に波の音ぞきこゆる。141
身の憂さの思ひ知らるることわりに、抑へられぬは淚なりけり。こと問へば、もてはなれたる氣色かな、うららかなれや、人のこころの。142哀傷に最も堪へがたいのは、秋しかも月の冴える頃であつた。哀れとも、見る人あらば思はなむ、月のおもてに宿すこころを。弓張の月にはづれて見し影の、やさしかりしはいつか忘れむ。思ひ出づることはいつもと云ひがら、月には堪へぬこころなりけり。月のおもてに宿すこころを。嘆けとて月やはものを思はする、かこち顔なるわが淚かな。淚ゆゑくまなき月ぞ曇りぬる、あまのはらはらねのみなかれて。もの思ふ心の隈をのごひすてて曇らぬ月を見るよしもがな。戀しさや思ひ弱ると眺むれば、いとど心を碎く月かな。眺むるに慰むことはなけれども、月を友にてあかす頃かな。かうして懊惱は身も世もあらぬ鳴咽に變る。人は憂し、嘆きはつゆも慰まず、こはさはいかにすべきこころぞ。かき亂るこころやすめの言の葉は、あはれあはれと嘆くばかりぞ。おぼつかな、何の報いの歸りきて、心せたむる仇となるらむ。もの想へど、かからぬ人もあるものを、哀れなりける身のちぎりかな。君にわれいかばかりなる契りありて、まなくもものを思ひそめけむ。いとほしやさらに心のをさなびて、たまぎれらるる戀もするかな。はるかなる岩のはざまにひとりゐて人目つつまでもの思はばや。あはれあはれ、この世はよしや、さもあらばあれ、來む世もかくや苦しかるべき。測々として人のこころを打たずにおかぬこれらの歌のひびきは、和泉式部や業平の域を越えてはるかに『萬葉』の相聞詩人たちに迫り、しかも陰翳と曲線の多い〓新な近代風を暗示してゐる。この思ひあまる咏嘆を抱いて自然のなかに入つていつたとき、無限の浪曼的有差に充ちた漂渺たる哀感が奏でられはじめる。斗藪詩人としての西行の面目がいよいよ明白になつてくるのである。143
144久安の中頃から治承四年の春まで、すなはち年から云つて三十歲の頃から六十三歲までの三十餘年といふものを、西行は高野山を中心として生活し、そこから多くの地方行脚をこころみてゐる。そのうちで最初のいちばん大きな旅行は、久安末もしくは仁平初年頃の安藝嚴島參詣であら50この旅は西住も一〓の筈であつたが、近親の者の病氣で同行できなかつた。家集に、「志すことありて、安藝の一の宮へ詣でけるに」とあるから、何か祈願の筋が特にあつたのである。この時は海がたいへん荒れ、船もろとも高飛の浦に吹き寄せられてそこで凪ぎを待つたと見え、50波の音を心にがけて明かすかな、苦もる月の影を友にてと心細がつてゐる。また、詣でてから後、をりからの月明に、次の秀吟を得てゐる。もろともに旅なる空に月も出でてすめばや影のあはれなるらむ。川田氏說によれば、西行は、この參詣に就いてたぶん平〓盛からの添狀で神主に面會し、その厄介になつたのであらうといふ(『西行研究錄』一九九頁)。「むかし見し野中の〓水」云々の歌によco.その時も須磨、明石を過ぎて姫路の西北にある書寫山に詣でてゐることは知られるが、の旅の道順はそれ以上はわからない。書寫山は、花山院の御巡禮があつてから道俗雲集の靈場となつた天台の淨利である。兒島その他の地名の見える歌は、後年四國旅行の際に通過した時の印象らしい。西行の旅の歌を整理してみると、木曾路から北越にかけての旅の道筋が見出されるが、もしこれだけが目的で行はれたとすれば、生涯中での大旅行の一つを形づくることになるが、別にそれらしい形跡が見出されないから、私の推定では、この道筋は東北旅行からの歸途に當ると考へられる。さう假定すると、歌の內容から見て若い時のことにちがひないから、この旅は、嚴島への旅より八、九年も早いことになる。そして、これもまた、私だけの創作的な假定になるが、最初の東北行脚の際に平泉まで足を延ばした形跡がすこしもないから、同行と途中で別れて心細い氣もちもいくらか手傳つて、或ひはこのとき、白河の關まで達して、關屋の柱に白河の關屋を月のもしこ145
もる影は云々と紀念の歌を書きつけてから、引き返して北越に向つたのではなからうかとおもはれる。「關に入りて、信夫と申す渡、あらぬ世のことにおぼえてあはれなり。都出でし日數思ひつづけられて、霞とともに侍ることの跡辿るまで來にける、心ひとつに思ひ知られて」といふ詞書にも、何かさういふ感慨が見える。季節は北國の櫻も散る頃であつた。146白河の關路の櫻さきにけり、東より來る人の稀なる。そして、引き返したとすれば、おそらく、利根を溯つて佐野の渡にかかり(五月雨に佐野の浮橋云々の詠あり)、草津街道から越後に拔けさらに引き返して越の中山を越えたのであらう。この越の中山は、信越の境にそそり立つ妙高山越えに於いて新井から牟禮までを中山と呼んでゐるから、たぶんそこであらうといふ。ら、雁群は歸る途にや感ふらむ、越の中山霞へだてて。嶺わたしにしるしの竿や立てつらむ、こびき待ちつる越の中山。戶隱の蔭を過ぎ犀川を渡ると、『大和物語』明を待つて次の幽思を抒べたのであらう。このかた田每の月で有名な姥捨山がある。おそらく月あまぐもの晴るるみ空の月影に、恨みなぐさむ姥捨の山。顯さぬわがこころをぞ怨むべき、月やはうとき姥捨の山。立ち昇る淺間の煙を眺めてもいつか頰には冷たいものが傳はつてゐる。次の歌の深い嘆きを見よ。いつとなく思ひに燃ゆるわが身かな、淺間の煙しめる夜もなく。今西行と呼ばれた似雲の『窓の曙』によると、千曲河畔の布引山にも滯在してゐたといふが、れはともかくとしてやがて諏訪へ拔けたらしい。そ閉ぢそむる氷をいかに厭ふらむ、あぢむらわたる諏訪の湖。147それから中山道の嶮として名にし負ふ木會にさしかかり、信濃守陳忠の落梯の話(今昔物語)を
憶ひ出したりして膽を冷してまだ雪ふかい棧道を渡つてゐる。浪と見る雪をわけてぞ漕ぎわたる、木曾のかけはし底も見えねば。ひと時は都を捨てゝ出づれども、廻りて花を木曾のかけ橋。駒なづむ木曾のかけ路の呼子鳥、誰ともわかぬ聲きこゆなり。さまざまに木曾のかけ路を傳ひ入りて、奥を知リつつ歸る山人。148戀の枕言葉として知られた謂はゆる箒木の伏屋も見ようとして妻子の驛から飯田への山道にも入つたらしい。會はざらむことをし知らず箒木の伏屋と聞きて尊ねゆくかな。飯田の西にある風越のほとりにも花の待たれるころ行つたと見える。風越の峰のつづきに咲く花は、いつさかりともなくや散るらむ。美濃に入つてからは、山里の春を怡しんで、しばらく滯在したもののごとく、大井の宿の長岡寺に次の歌二首を藏することが『木曾名所圖繪』に見えてゐる。夜もすがらあらしの山に風冴えて、大井の淀に震をぞ開く。待たれつる入相の鐘の聲すなり、あすもやあらば聞かむとすらむ。同書はまた、同書はまた、大井を中心として西行硯石を藏する所、西行幽栖の跡と傳へる竹林庵、夜晝のさかひをここに云々と詠まれた月吉、日吉の里等のことを記してゐる。次の歌も、もし眞作であるとすれば大井附近の作で、春關けてやうやく思〓の思ひに驅られた彼の姿がそこにうかがはれる。ほととぎす都へゆかばことづてむ、こえくらしたる山の哀れを。二十六、七歲頃のこの旅、三十五、六歲頃の嚴島への旅に次ぐ大きな旅行は、仁安二年、五十歲の時の四國行きである。十月十日、出發に先立つて日ごろ信心する賀茂の社にまづお暇乞ひに參じた。家集に、「そのかみ、こころざし仕ふまつりける習ひに、世を遁れて後も、賀茂へ參りけり。年高くなりて、四國の方修行しけるにまた歸り參らぬこともやとて、仁安二年十月十日の夜參りて、幣まゐらせけり。內へも參らぬことなれば、棚尾の社にとりつきてまゐらせたまへとてり。149
こころざしけるに、木の間の月ほのぼのとつねよりも神寂び、あはれにおぼえて·····」とあり、月光寂たる神前に拍手して額づく莊嚴な姿が髣髴としてゐる。云ふまでもなく、四國への旅は、三年前の長寛二年秋に讃岐に崩御あらせられた崇德院の御靈を追善し奉るためであつた。150月冴ゆる明石の瀨戶に風吹けば、氷のうへをたたむ白波何となく都の方と聞くからは、睦まじくてぞ眺められけると詠んだのもこの旅の途上であらうか、ち書寫山に詣らうとしてふたたび野中の〓水のほとりに立むかし見し野中の〓水變らねば、わが影をもや思ひ出づらむ待懷舊の思ひに耽り、やがて備前兒島に渡り、風浪があつたのでしばらく日比といふ港で便船を作つた。「たてそむる糠蝦とる浦の」云々および「下り立ちて浦田に拾ふ」云々の歌は、この時のとである。まもなく對岸に着くと、寒月が冴えて海上一里半のかなたにある日比の津がうつすらと見え、をりからその方を指して水島が飛び去るのもあはれであつた。敷きわたす月の氷を疑ひて日比の戶まはるあぢのむら鳥。一二そこから松山の西藏へ醜けつけて御所跡を尋ねたが、「形もなかりるあさましさ、萬乘の寶座にましました御身の「思ひやれ、都はるかに沖つ波、立ち隔てたる心細さを」と遊ばされた御無念を察しまつつて、松山の浪に流れてこし舟の、やがて空しくなりにけるかな。松山の波のけしきは變らじを、かたなく君はなりましにけり。それからやうやく新院の御墓は白峰といふ山寺と聞いて尋ねて行くと、寺の西北の御陵には草いちめんにうら枯れて御傷はしい極みであつた。額づき伏して法施をたむけまつる西行の胸には、淚よりももはや憤ろしい思ひがつまつてゐたのであらう。「····思思ひきや、今かかるべしとは。かけても測りきや、他國邊土の山中のおどろの下に朽ちさせたまふべしとは。貝鐘の聲もせず、151
法華三昧つとむる僧一人もなき所に、ただ峰の松風の烈しきのみにて、鳥だにも翔けらぬありさまを見奉るに、そぞろに淚を落し侍りき」と『撰集抄』(廣本卷一)は記してゐる。152よしや君、むかしの玉の床とても、かからむ後は何にかはせむ。讃岐へ來たついでに、そこから近い善通寺を訪れた。善通寺は、師の生誕地である。その地に樹が垣をめぐらしてゐるのを見て、生涯渴仰の的であつた弘法大あはれなり、同じ野山に立てる木の、かかるしるしのちぎりありけり。また、岩に堰く関伽非の水のわりなきに、心澄めともやどる月かな。この善通寺では、山に菴を結んでしばらくここに逗留したらしい。同じ國に大師のおはしましける御あたりの山に、菴を結びて住みけるに、月いと明るくて海の方くもりなく見え侍りければ曇リなき山にて海の月見れば、嶋ぞ氷の絕え間なりける。住みけるままに、菴いとあはれにおぼえて今よりは厭はじ、命あればこそ、かかるすまゐのあはれをも知れ。菴の前に松の立てりけるを見て久に經てわが後の世をとへよ松、跡したふべき人もなき身ぞ。土佐の方へや罷らましと思ひ立つこと侍リしにここをまたわが住み憂くてうかれ往なば、松はひとりにならむとすらむ。雪のふりけるに雪つみて木もわかず咲く花なれば、常磐の松も見えぬなりけり。花と見る梢の雪に月冴えて、譬へむ方もなきここちする。をりしもあれ、嬉しく雪のつもるかな、かきこもりなむとおもふ山路を。谷の菴に玉のすだれを掛けましや、縋る垂氷の軒を閉ぢずば。153
さて、そのしばしの菴になごりを惜しんで立ち去つた西行は、どこへ足を向けたか。土佐へ行つてみようと思ひ立つたとあるが、行つたらしい形跡もない。筑紫の大和田崎を通り過ぎる時と、香椎の近くの宇美の宮に參つた時の印象が歌に殘されてあるから、年末には九州の地を踏んだのであらう。もつとも、九州行きは、前の嚴島參詣の際のことのやうな氣もする。ただ、川田氏も推定してをられるやうに(『西行〓究錄』八四頁)、このとき嚴島にふたたび詣でたことはたしかである。當時、密〓渡來が嚴島明神の御願によること、大師入唐に際してこの明神に祈願したことが一般に信じられてゐたから、西行もおそらくこの明神に歸依するところ深かつたのである。それに、この前に來た時に安藝守〓盛が着手してゐた社殿の造營がやうやく成り、この年十月十八日に有名な平家納經が行はれたのであるから、近くにあつた西行がこの機會を見逃す筈もない。もし納經の日にまにあつたとすれば、〓盛は舊知の思ひがけない來訪にすつかり喜んだにちがひない。しかし、新社殿の絢爛たる美々しさも、西行の眼を今さら驚かしもしなかつたであらう。次の旅は、治承四年、(六十三歲)頃、高野を出て、熊野から新宮へ、新宮から伊勢へと赴いた時のそれで、伊勢では二見の邊に菴を構へて文治二年までこの邊に落ち着いた。154「新宮より伊勢の方へ罷りけるに」云々と詞書があるから、次の歌はこの時の旅の印象であらう。年經たる浦のあま人、こと問はむ、浪をかつぎて幾世過ぎにき。黑髪は過ぐると見えし自波をかつぎはてたる身には知る海士。同じく途上の錦浦で、浪にしく紅葉の色を洗ふゆゑに、有馬村の北なる花の窟で、錦の鳥と云ふにやあるらむ。また、三熊野のみ濱に寄する夕浪は、花のいはやのこれぞ白木綿。西行最後の大旅行として、文治二年、六十九歲のとき、東大寺大佛殿再興の沙金勸進のために新秋の氣動くころ發足して東北行脚に出かけた。「流れてはいづれの瀨にか」と曾つて歌つた二川から、ふたたび濱名湖のほとりを過ぎ、憶ひ出のある天龍川を渡つて小夜の中山へとさしかかつな155
年たけてまた越ゆべしと思ひきや、命なりけり小夜の中山。156それから久能山の山寺をも訪ねたかどうか、淚のみかきくらさるる旅なれや、は澄めども、とここで詠んだのは、おそらく前回の旅であらう。〓見潟では、さやかに見よと月〓見潟、沖の岩越す白浪に、光を交す秋の夜の月と、と、をりからの名月を賞し、人麿の歌に有名な田子の浦にたぶん立ち寄り、そこから浮島沼のほとりに出て、低徊顧望、去りがたい思ひで煙を噴く富士山をふたたび仰いだ。風になびく富士の煙の空に消えて、ゆくへも知らぬわが思ひかな。無限の浪曼的有差感に充ちたこの絕唱は、浮島原附近での作であつた。それから三島を過ぎ箱根の嶮を越え八月十五日には、鎌倉の八幡宮に着いた。すると、ちやうどそのとき、賴朝の參拜があつて、鳥居の邊にゐるところを恠まれ、梶原景季に名を聞かれたので西行法師と答へると、賴朝は慇懃に彼を營中に迎へた。世を捨てたとはいへ、それから三島を過ぎ箱根歌人としてあまねく知れわたつてゐるのはともかくとしても、その背後に殊に東國を地盤とする同族一門の勢力を隱然と擔ひ、しかも奧州の秀衡のもとへ赴くとあつては、鎌倉にとつては痛し痒しの存在であつたらう。幕府の日誌『東鑑』に、特に陸奥守秀衡入道は上人の一族なりと附記してゐる點にも、この間の消息がうかがはれるやうにおもはれる。賴朝が辭を低くして和歌と弓馬の道に就いて〓へを乞ふと、西行は、秀〓このかた九代嫡家相承の兵法書を遁世に際して燒き棄ててしまつたし、また罪業の因となると思つてそのことを曾つて心にも留めず、すべて忘れてしまつた、詠歌は花月に對して感興が湧けばこれを綴るだけで別に奥旨といふやうなものは存じ申さぬ、とあつさり斷はつてゐる。しかし、賴朝の强つての所望に、それではと云つて弓馬のことに就いて話し出したので、賴朝は側近の者に命じてこれを書き取らしめてゐる(東鑑)。翌日退下するとき賴朝から贈られた銀製の猫を門の外に遊んでゐた子供に與へて立ち去つたとも傳へられてゐるが、この話は信じられない。しかし、もともと威嚴に充ちた彼の堂々たる態度は、源家に對する快からぬ思ひがどことなく滲み出てゐるのと相俟つて、一種の無氣味さを鎌倉の人々に與へたことはたしかであらう。157
鎌倉以北では、158玉にぬく露はこぼれて武藏野の草の葉むすぶ秋の初風(武藏野)汲みて知る人もあらなむ、おのづからほりかねの井の底のこころを(堀兼の井)知らぐる光を花にかざされて、名を顯はせる埼玉の宮(前玉神社)霧ふかき許我のわたりの渡し守、岸の舟つき思ひ定めよ(古賀の渡)都ちかき小野大原を思ひ出づる柴のけぶりのあはれなるかな(下野)等の歌があり、どれが前回のものか、で勿來の關を通つたのかもしれない。またこの度のものか、區別がつかない。とにかく、今の岩沼の近くに出て、或ひは海道を擇ん枯れにける松なき跡の武隈は、みきといひてもかひなかるべしと、武隈の松の跡を弔ひ、枯薄のなかに藤中將實方の墓を見出して一掬の淚を灑いでゐる。朽ちもせぬその名ばかりをとどめおきて、枯野の薄かたみにぞ見る。實方は西行の知人なる熊野別當湛快の祖父、〓少納言などと交際あつた外は世間的に容れられなかつたらしく、行成と殿上に爭つたりして陸奥守に左遷せられ、歌枕を探つてその數奇の生涯をつひにここに終つたのである。それから名取川を渡つて「なとり川、岸の紅葉の」云々と詠み、やがて秋草の爽かに咲き亂れる名にし負ふ宮城野の木下路へさしかかつた。萩が枝の露ためず吹く秋風に、牡鹿鳴くらむ、宮城野の原。あはれいかに、草葉の露のこぼるらむ、秋風立ちぬ、宮城野の原。鹽竈に近い謂はゆる末の松山では、賴めおきしそのいひごとやあだになりし、波越えぬべき末の松山と感慨を寄せ、松島を右手に見て、一路平泉に向つた。着いたのは十月十二日、北國のこととてもう雪が降りしきり、「嵐はげしくことのほかに荒れた」る日であつた。高館の城に入る前に或ひは後にしたところで直ちに)、「いつしか衣川見まほしくて」と云つてまづ要害の視察をし、「川159
の岸に附きて衣川の城しまはしたる、は何のつもりであつたらう。事柄さま變りてものを見るここちしけり」と呟いてゐるの160とりわけて心も泌みて冴えぞわたる、衣川見に來たる今日しも。衣川、汀によりて立つ波は、岸の松が根洗ふなりけり。かういふところから見て、どうも私には、この時が再度の平泉訪問であつたと考へられない。その後の改修があつたにしろ、いつか見たいと思つてゐたと云つて旅裝も解くか解かないうちに最先に馳けつけてゐるくらゐで、おそらく初めて見る衣川であつたことはたしかのやうである。秀衡の館で、常よりも心細くぞおもほゆる、旅の空にて年の暮れぬると北國での初めての越年を佗しがつたが、れた束稻山の櫻の歌がある。この平泉には翌春まで居たらしく、吉野に亞ぐと謳は聞きもせず、たはしね山のさくら花、吉野の外にかかるべしとは。奥になほ人見ぬ花の散らぬあれや、尋ねて入らむ、山ほととぎす。事實、櫻の咲き初める頃、ふたたび漂然と旅立ち、山ほととぎすの聲を尋ねながら出羽に赴いてゐるが、この旅をもつて裏日本をずつと津輕邊まで究めたとする說は信じられない。「いたけもる」「胡沙ふかば」等の蝦夷の歌を眞作と見做すことは、私にはたいへん疑はしくおもはれる。殊に後者は、『玄同放言』によれば、他人の作であるといふ。まして「壺のいしぶみ、外の濱風」とか「象潟の秋の夜の月」に至つては、眞作と見做しがたい。かうして殘るところは、家集に、前揭衣川の歌にすぐ續けて「またの年の三月に、出羽國に越えて、瀧の山と申す山寺に侍りける。櫻の常より薄紅の色濃き花にて並み立てりけるを、寺の人々も見て興じければ」と詞書のある次の歌、たぐひなき思ひいではの櫻かな、薄紅の花の匂ひは161ならびに「同じ旅にて」と題した、
風荒き柴の菴は、常よりも、寢ざめぞものは哀しかりける162だけになる。さうしてみると出羽といつてもその南端をちよつと掠めただけで、そこから米澤の街道に出、板谷の峠を越して信夫の里に入つたものであらう。瀧の山は藏王山の裏側で、今の山形市のずつと南に當り、行基の草創、慈覺大師の再興にかかる靈山寺を擁してゐる。この寺隆昌の時は全山の坊舍三千に餘つたといはれ、地方きつての靈場であつたから、西行もわざわざ迂回してここへ立ち寄つたものと見える。信夫へ出たとするのは、次の歌がどうやらこの時の作らしいからである。東路のしのぶの里に休らひて、勿來の關を越えぞわづらふ。勿來に「な來そ」の意味をかけたにしても、るのは、歸途のことと見てよささうである。しかし、かは推定しかねる。さて、以上によつて西行の旅行はほぼ盡きるのであるが、通る通らないは別として、信夫でその關を望んでゐしかし、そこからどこをどう通つて上方に歸着したこの外、時期はわからないが、敦賀から北陸への旅を推定して後に芭蕉などがその足跡を追つてゐるが、はすこし疑はしい。敦賀以東へ行つたとするの風吹けば、花咲く波の寄るたびに、櫻貝よる三島江の浦う余吳の湖の君を三島に引く網の目にもかからぬあぢのむら鳥は、余呉湖での印象。それから愛發の關を通り過ぎる。あらち山、さかしく下る谷もなく、かじきの道をつくる白雪。次の歌によつて敦賀灣を抱く立石岬の種の濱まで赴いたことは事實らしい。汐そむるますをの小貝拾ふとて〓いろの濱とは云ふにやあるらむ。加賀にあるといふ竹の泊の歌は信じがたい。まして芭蕉が擧げてゐる汐越(越前と加賀の境にある岬)の松の歌は、たしかに秀吟にはちがひないが、眞作ではない。しかし、事實北越に行つた163
のであるとすると、次の西住の歌はたぶん西行に宛てられたものであらう。164夏のころ越の國にまかりける人の、秋は必ず上りなむ、るまで上りまうで來ざりければ、遣はしける待てと云ひて賴めし秋も過ぎぬれば、歸る山路のなどかひもなき。まどろみてさても止みなばいかがせむ、寢ざめぞあらぬ命なりける。駒のあとは、かつ降る雪に埋もれて、後るる人や道まどふらむ。待てと云ひけるが、冬にななほ、近畿を中心とする小旅行の秀歌をあげておく。東路-わきて今日、逢坂山の霞めるは、立ち遲れたる春や越ゆらむ。(逢坂の關)流れやらで津田の入江に卷く水は、舟をぞもやふ、さみだれの頃。(野州附近)大和路-三笠山、秋篠や、廣瀨川、月さしのぼる影冴えて鹿なきそむる春日野の原。(春日)外山の里やしぐるらむ、生駒の岳に雲のかかれる。(秋篠里)みかき渡りの沖のみをつくし、水嵩そふらし、さみだれの頃。(廣瀨川)熊野路立ちのぼる月のあたりに雲消えて、光かさぬるななこしの峰。(七越)夕ざれや、檜原の峰を越えゆけば、すごくきこゆる山鳩の聲。(1回)波よする白良の濱の鳥貝、拾ひやすくもおもほゆるかも。(白良濱)離れたる白良の濱の沖の石を碎かで洗ふ月の白浪。(同)、月影のしららの濱の白貝は、波も一つに見えわたるかな。(前町雲消ゆる那智の高嶺に月關けて、光をぬける瀧の白絲。(那智) (同)、津の國- 165
水無瀨川、をちの通ひ路水滿ちて、舟わたりするさみだれの頃。庭よりも鷺ゐる松の梢にぞ雪はつもれる夏の夜の月。(天王寺)難波江の入江の蘆に霜冴えて、浦風さむき朝ぼらけかな。(難波)津の國の難波の春は夢なれや、蘆の枯葉に風わたるなり。( 附)住吉の松が根洗ふ浪の音を梢にかくる沖つ汐風。(住吉)波にやどる月を汀に搖リ寄せて鏡にかくる住吉の岸。(1月)播磨瀉、灘のみ沖に漕ぎ出でて、あたり思はぬ月を見るかな。(水無瀨川) 166 ( 附)排七生涯とその完成久壽二年七月、寶算わづか十七をもつて近衞帝が崩御あらせられた。帝は、鳥羽院第八皇子、御母は美福門院、皇后は德大寺多子であつた。時に三十八歲の西行は、御移葬前の知足院の御陵にお參りして、「野邊の景色たぐひなく哀れにて、春宮と申しし昔より今の露けきまで思ひつづけて」と云つて、薄命の御生涯に心から挽歌を奉つてゐる。磨かれし玉のすみかを露ふかき野邊にうつして見るぞ哀しき。その年十月、後白河院の御卽位があり、越えて翌年四月、保元と改元せられた。と、まもなく鳥羽法皇の御不豫が傳へられ、七月二日つひに崩御あらせられた。高野から急いで馳けつけて島羽殿南離宮に伺候した西行は、むかし御增修落成して院がここにお忍びになられるのに主家の德167
大寺實能と自分だけでお供したことなどをいろいろと思ひ出して、168こよひこそ思ひ知らるれ、淺からぬ君にちぎりのある身なりけリと哀傷の歌を詠んでゐる。思へば數ならぬ身にも垂れたまふた深い御仁慈の程を今まで顧みなかつたと嘆いてゐるのである。納めまゐらせける所に渡しまゐらせけるに道かはる御幸かなしき今宵かな、限リの旅と見るにつけても。納めまゐらせて後、御供にさぶらはれし人々譬へむ方なく悲しみながら、限リあることなければ歸られにけり。はじめたることありて明日までさぶらひてよめるとはばやと思ひよりてぞ嘆かまし、昔ながらのわが身なりせば。しかるに、御大葬終つて初七日が過ぎると、たちまち戰が起り、二日の夜、御同母弟覺性法親王御室の仁和寺北院に渡らせられた。新院側の敗北に歸して院は十いつかこのやうなことが起るかもしれぬと豫知して遁世した西行ではあつたが、院の御上を察しまゐらせてはそぞろに心の痛むものがあつたであらう。數日後の月明の夜、仁和寺に行つて阿闍利兼賢を通じて、かかる世に影も變らず澄む月を見るわが身さへ怨めしきかなと申し上げてゐる。それから數日後の二十三日、今は御落餝の崇德院に於かれては、まだ曉闇のうちに仁和寺を御發輦、草津から御船に御して波路はるばる讃岐へ向はせられた。松山の津への御着は八月三日と記されてゐる。その後、西行は、邊土の佗しい御起居を思つて女房のもとに慰めまゐらせる歌を送つてゐる。世の中を背くたよりやなからまし、憂きをりふしに君が會はずば。あさましや、いかなるゆゑの報いにて、かかることしもある世なるらむ。存へてつひに住むべき都かは、この世はよしやとてもかくても。幻の夢をうつつに見る人は、目も合はせでは夜を明かすらむ。169
また、讃岐へ下つて伺候した人(たぶん寂然)に託して、170その日より落つる淚をかたみにて思ひ忘るる時のまぞなきと送り、これに對して女房の名による次のやうな御返歌を戴いてゐる。波の立つ心の水をしづめつつ、咲かむ蓮を今は待つかな。また、便りにつけて女房のもとよりとして、水莖のかき流すべきかたぞなき心のうちは汲みて知らなむと遺はされた御無念を拜し、その御返しに、ほど遠み、通ふ心のゆくばかり、なほかき流せ水莖のあとと憤ろしい思ひを抒べた。しかるに、重ねて、いとどしく憂きにつけても賴むかな、契りし道のしるべ違ふなかかりける淚に沈む身の憂きを君ならでまた誰かうかべむとお示しあり、西行これに、賴むらむしるべもいざや一つ世の別れとだにも迷ふ心はとお答へしてゐる。君臣の契り思ふべし、しかも西行は、深く恃みまゐらせるところがあつたのである。藝苑の新風の御主宰としてのこの院にさて、亂の翌年、すなはち保元二年の九月、主家の德大寺實能が世を去り、まもなく忌服のうちにその妻も亡くなつた。その男公能は、西行からこのとき出離を奬められたが、應じなかつたところ、それから數年の後に、右大臣になつたばかりで父母の後を追つてしまつた。そして、こ171
れで德大寺家に對する西行の緣はほとんど絕えてしまふのである。保元の變があつて三年目に、ふたたび平治の亂が持ち上つた。西行が成通に勸めて出家せしめたのはその直前のことであるが、世のあさましい騒々しさを見て何事か起らずに止みさうもないことを豫知したのであらう。彼の親友の壹岐守賴業も、その頃すでに入道して大原に隱れ、唯心坊寂然と號してゐた。翌永曆元年、源義朝の伏誅に次いで、その子賴朝が伊豆に流され、ひとまづ亂が收まつたが、その年十一月、近衞院、鳥羽院相繼いで神去りましてからこのかた鬱居の日のみ續いた美福門院が崩ぜられた。その御舍利は御遺誠によつて高野に葬られることになり、御弟の入道時通がこれを「首にかけまゐらせ」、それに母がお仕へした關係で幼い頃から御眷顧を得た晝伯隆信と、栖蓮すなばち今は入道の成通とが供奉して、師走の四日に高野に着いた。雪の霏々として散り舞ふなかをお出迎へした西行は、172今日や君、蔽ふ五つの雲晴れて、心の月を磨き出づらむと挽歌を奉つた。しかるに、このとき供奉した栖蓮も、その翌々年(應保二年)に六十六歲をもつて薨じた。「ゆき散らむ今日の別れを」云々と西行はその時これを弔つてゐるが、「或る人」としてその遺族から返しがあるから、おそらく家庭的にも親しかつたのである。長寶二年、西行四十七歲の秋、崇德院崩御の悲報が讃岐から齎らされた。御陵を拜するために四國の地を踏んだのは、それから三年後、〓盛が太政大臣になつた仁安二年十月であつた。前述のとほり、おそらく四國から安藝に渡り、行き合した〓盛の得意な顏を淡々と見過しながら九州の一角まで行つたのであらう。しかし、〓盛のはうでは、今は高僧としてまた歌人として名聲のあるこの舊知の來往をたいへん喜んだと見えて、その翌々年の三月攝州福原での千僧供養のついでに催した和田濱の萬燈會に西行を招いた。次の歌は、そのとき〓盛の好意を謝したものである。消えぬべき法の光のともし火をかかぐる和田の岬なりけり。その前年、すなはち承安元年初夏、またま會して、「絕えたりし君が御幸」熊野御幸の途すがら後白河院の鳳輦の住吉に駐するのにたをふたたび仰いだことをここの歌神とともに喜んでゐる。173
『千載集』撰進宣下の際に伊勢から釋阿に贈つた歌に徴しても、また崇德院の讃岐遷幸によつて歌道の廢れたことを寂然と嘆き合つてゐるのを見ても、和歌に對する西行の執心は驚くほど强かつたのである。174仁安二年の西國旅行は、西行の精神史を辿るうへにきはめて重要な指標をなしてゐるやうにもおもはれる。しかし、それ以前の大きな事件として三十幾歲かの時、野山入りの前後に行はれた大峰行者としての自己試煉も、一應ここで振り返つてみなければならぬ。ところで、西行は初め、台密の寺院を賴つて修行したらしいが、まもなく東密に轉じて、まづ西住とともに醍醐理性院の法脈を受け、それから大本山の高野に入つてゐる。といつて、多くの學僧のやうに區々たる末節に囚はれなかつたから、台密からも攝取するところがあつたにちがひなく、かたはら法華を誦しつつ念佛唱へた雜修念佛の行者として、その名の示すやうに西方淨土の思想をも抱き、十念成就を詠じてゐるのを見れば融通念佛の流れをも汲んでゐたことがわかる。まづ彼が、單に遁世したといふだけでなく、全身を修行に打ち込みはじめたのは、おそらく野山入りの前後の大峰修行からで、『古今著聞集』に語られた大峰二度の行者としての難行苦行はたとひ虚妄の作話であるとしても、ここでの試煉によつて初めて久しきにわたる野山の幽棲に堪へ得たことはたしかである。彼の敬慕したにちがひない行尊の精進をもつて知られた大峰は、熊野と同じ信仰のもとに一括して考へられたが、熊野はもともと神祗を同んじ、大峰は多く東密の修驗道によつて支持されたのであらう。奧院の卒塔婆や小笹の西の笙の窟に、あはれとも花見し嶺に名をとめて、紅葉ぞけふはともに散りける露もらぬ岩屋も袖は濡れけりと、聞かずばいかに怪しからましと行尊の跡を偲ぴ、また、月澄めば、谷にぞ雲は沈むめる、峰吹きはらふ風に敷かれて(神仙)梢もる月もあはれと思ふべし、光に倶して露のこぼるる(幣持の宿)古畑のそばの立つ木にゐる鳩の友よぶ聲の凄き夕暮(古畑) 175
等の凄絕な秀吟を得、峰入りの作法に從つて多くの嶮所難所の行をつひに濟ましたのである。しかも、彼はどうやら謂はゆる順峰の道順を取つてゐるらしいから、大峰の前に那智、新富の修業を經たらしく考へられる。那智での一聯の歌は、たしかにこのときのものであらう。さて、話はまた元へ戾るが、この大峰修業と、それからほぼ二十年の後に行はれた西國行脚とは、西行の內面史に劃期する一一つの決定的な指標をなし、特に後者が重要である。藤岡東圃博士の西行論(『異本山家集』附錄)に從へば、「崇德上皇の一生は西行の半生に苦悶の情を斷たざらしめ、世を棄てたる人をしてつびに全く世を棄つる能はざらしめぬ。渠の歌に悲哀痛苦の辭多きもこれにもとづくこと蓋し鮮少ならざりしなるべし。されど、上皇崩御の後は、悲痛の種ここに去りて過ぎ去りし禍福は今はた得道解脫の因となり、世事とは全く相離れて、ひたすら無我なる自然に接したるならむ。」これはすこし誇張にはちがひないが、西行がこれに近い熱誠の人であつたことはたしかである。今や、しかし、その院の御跡も隈なく弔ひ、心にかかる雲もなくなつた。仁安三年の春に旅から歸つたとすれば、待賢門院御腹として長く親しみまゐらせた仁和寺の覺性法親王が薨去せられ、今や關係の御筋としては、後白河院に親近し奉るところ少かつたやうであ176るから、同じく故門院御腹なる上西門院ならびに五辻齋院の御上と、崇德院の忘れがたみであられるまだ年少の法印元性の御上とが心に殘るだけで、しかも、この御三方には、しばしば伺候して、おのづから經驗の力に溢れた人間性の豐かな法話を申し上げたのであらう。といつて、美福門院側にも御緣がなかつたわけではない。近衞院の御同母姉なる八條院姫宮にも謁してゐることが歌詞によつてうかがはれる。單に宗〓的と云へない、愛憎を超えて愛憎に還る、いはば淨らかで、靜かで、そして自然な觀照が、彼のうちに波うちはじめたのである。また、西行五十八歲の安元元年に法然が吉水の草庵に移つて念佛往生を唱へはじめたり、その七年前の仁安三年に榮西が宋に赴いたりして、宗〓界には新氣運が今や動かうとしつつつあた。道に携はる敏感な西行がかういふ動きをいち早く感じなかつたとは云へない。もちろん、新しい思潮のいづれかを全幅的に支持することはできなかつたにしても、軀のどこかにそれらのものの出現の必然さを感じてゐた彼は、何か油然として心の暖まるものをおぼえたにちがひない。五十歳を過ぎてやうやく宗〓人としての自信を得たのである。見やうによれば、彼の生涯は宗〓改革かうして、さうの到來を詩歌のかたちで豫〓する大きな羽搏きであつたと云へないこともない。177
いつた時代の潮流のなかにおのづから浮べられて、圓位上人と云へば眞言密乘の高僧として、法然の運動がやうやく烈しくなつた安元年間頃には、ますます重きを加へるに至つたらしい。安元元年、五辻齋院頌子内親王が御父帝の菩提を弔はせられるために、高野東別所に蓮華乘院を草創せられようとしたまふや、西行は、命を承はつた大義房賢宗を輔けてそのことに當り、賢宗入寂後はそのことを繼いでゐる。落成供養は治承元年十一月であつたが、越えて翌年九月、內親王はその事業を記念として薨ぜられた。初め御領の紀州南部庄を蓮華乘院に寄せさせられる御寄進書のうちに、「······大本房〔西行〕の聖の御房よくよく計らひおほせられおかせたまふべし」とあり、御信賴がきはめて深かつたのである。同じ治承元年に、高野の領に課せられた紀州日前宮造營の賦役を免除してもらふために、金剛峰寺の檢校房光に代つて出京し、當局に申請してゐるが(高野山寶簡集、西行書狀)、〓盛との舊交をいくら暖めつつあつた際のこととはいへ、このことはやはり彼の社會的信望がかなりに重かつたことを語つてゐると云へる。「高倉院の御時傳へ奏せさすること侍りけるに書き添へて」とて「跡とめて古きを慕ふ世ならなむ」云々の歌を奉つてゐるところを見ると、和歌か何かのことで奏上するところがあつたらしいが、それもたぶんこの頃法178である。川田氏は、勅撰集の御事ありたしと奏上したにちがひないと推測してをられるが(『西行』四六頁)、おそらく肯綮に近いであらう。とにかく年齡から云つてももはや六十に達し、遁世の際に望んだ性相圓融の位にやうやく近づいたのである。といつて、先にも述べたやうに、單なる孤高脫俗ではない。ただ、その「煩惱」は、泉に涵された水草のごとく豐かな觀照のうちにむしろ剩すところなく花ひらき、全人間的均衡のうへに靜かな氣息を保つに至つてゐる。王朝の「もののあはれ」は、彼によつて初めてヒューマニズムの内容を與へられた。『山家集』卷末に近く「戀百十首」が收められてあるが、その大部分は、建春門院少納言局がこれを借覽して返した旨の後記があるから、嘉應から安元にわたる數年間のうち、すなはち彼の五十代の作であつた。後記に「この歌ども、山里なる人の語るにしたがひて書きたるなり。されば、ひがことどもや。昔今のこと取り集めたれば、ときをり節違ひたることどもも」とあるが、彼にとつてはもはや、他の人に於いてであらうと、また自分にあつてであらうと、戀心のその人間的なあはれさだけがいとほしく見えたにちがひない。かうして、煩惱こそ淨土への契機とする思想がおのづから內部に兆してゐた。「戀百十首」の終りに「何事につけてか」云々と詠んでゐるやうに、煩惱によつて出離の179
道が開かれたことを今は感謝してゐる。180一つ根に心のたねの生ひいでて花咲き實をば結ぶなりけり。入り初めて悟りひらくるをりはまた、同じ門より出づるなリけり。花見ればそのいはれとてなけれども、行も、今は、心のうちぞ苦しかりける。曾つてさう告白して苦しんだ西色染むる花の枝にもすすまれて梢まで咲くわが心かなと歌つて明るい歡喜に浸つてゐる。ウォーズウォースをここにふたたび私は連れて來るが、もとその靜謐にして圓滿な西行の個性は、ウォーズウォースにかなり近いところを持つてゐる。近世イギリスのこの自然詩人に關するウォルタア·ペイタアの所論に從へば、「彼の性格には、彼のやうな動きやすい感性となかなか結びつかぬ一つの滿足、さう生れついた一種の宗〓的平靜があつて、そのために靜的な或はやや動的な生活を平穩無事に觀察するのに好都合であつた。彼の八十年の生涯は、特に深く感じた出來事によつて分裂されてゐることがなく、その變化はほとんど內面的で、したがつて彼の生涯は、廣い、平和な、おそらくはやや單調な空間を占めてゐる。かの早い頃のイタリーまたはフランドル派の畫家たちは、その心が或る至福な幻像に充ちてゐたので、その或る者は六十年の大半を靜かなひとすぢの勤勉に費したが、彼の生涯もそれらの一人に似てゐる。かついつた平靜な生涯は、眞に生れつきのそのすぐれた感性を、自然界の樣相や響-岩に落ちる花の影とか、時鳥とその木魂など-に順應せしめた。」この批評はほとんどそのまま西行に當てはまつてゐる。存へむとおもふこころぞつゆもなき、壓ふにだにも足らぬ憂き身ははかなしや、あだに命の露消えて、野べにわが身の送リ置かれむそのをりの蓬がもとの枕にも、かくこそ蟲の音にはむつれめいづくにか眠り眠りてたふれ臥さむとおもふ悲しき道芒の露181と曾つて激越な感傷に浸り、また、
大波にひかれ出でたるここちして、助け舟なき沖にゆらるる182と闇に迷ふ身の悲しさを訴へたこともあつたが、彼の生涯の基調をなすものは、ほのぼのとした圓光に圍まれた平靜な且つひそやかな內的生成の世界であつた。その幽證な透きとほつた夢の營みは、かうして、蓊鬱たる山間の植物に入り交つて、眞言密〓の深い碧天をしづかに指さしたのである。安元二年、西行五十九歲の時、叡山無動寺にあつて千日修業をやつてゐた慈圓に「いとどいかに」云々の歌を贈つてゐるところを見ると、前述の賦役免除請願のためにその年のうちに出京してゐたのかもしれない。翌年三月にはたしかに京に滯在してゐた。『山家集』下上に、中宮大夫すなはち平關白時忠から、京へまた出て來られるのはいつですか、こんな雪のなかを出立するのはお止しになつては、と聞かれて、歌で返事したことが見えてをり、時忠が中宮大夫の職に任じてからのこととすれば、治承二年もやはり京洛に出たらしい。時忠に答へて、雪を踏み分けて深い山路に籠るのであるから、年でも改まつたらまた會へるかもしれぬ、と云つてゐるのに對して、山路の雪はいかに深くとも年とともに早く立ち歸つて來られよ、と時忠が返してゐるところから窺ふと、京にかなり長く滯在して時忠などと交游しつつあつたことが想像される。平家にあらずんばと傲語したといつて京童に誣ひられた時忠は、流謫再度にわたる豪膽な任俠の士で、西行とどこか氣が合つたらしく、彼の請願に對してもいくらか盡力するところがあつたのかもしれぬ。しかし、それはともかくとして、彼が京にわりあひ長く逗留したと想像し得る一つの理由は、すでにこのとき野山退出の快意を有してゐたのではないかと考へられるふしがあるからである。西行が高野を去つたのは、治承四年、六十三歲のとき、六月に福原遷都の噂を伊勢で聞いて雲の上や古き都になりにけり云々と慨歎してゐるから、おそらく前年の初冬ではなかつたかとおもはれる。といふのは、新宮から東浦づたひに伊勢に出る途中にある錦浦で、「磯わの紅葉散りけるを」眺めて卽興の歌を詠んでゐるからである。治承二年十一月、中宮平德子の御腹に言仁親王が出誕あらせられるに及び、西行は、崇德院の御時のことなどを念頭に浮べてすでになんらかの豫183
感に迫られたにちがひない。果して翌年十一月、大地震の混亂のさなかに後白河院が幽せられたまひ、〓盛の暴狀ここに極まるに及んで、高倉院に於かせられては憤怨つひに病を成したまふと聞えた。越えて二月、安德帝の御卽位あり、五月、以仁王を奉じて老三位賴政が兵を擧げ、また福原遷都の直後、人心の動搖に乘じて賴朝の石橋山擧兵があり、木曾義仲またこれに呼應して立ち、十月には平軍の富士河敗走が傳へられた。さらに、翌養和元年正月、憂悶のうちに高倉院崩御あらせたまひ、皮肉にもこれに續いて閨二月、鴟豪〓盛もまた遽だしく御跡を追ひ奉つた。西行は、かういつた動亂の報を、伊勢の二見浦にあつて耳にした。彼が三十年の長いあひだ住み馴れた野山を去つてそこに赴いたのは、何のためか。思ふに、その主たる所以は、世の騷擾の無殘さに何かしら居たたまれない氣もちに驅られたことであらう。寂蓮の百首歌勸進を斷はつて熊野詣でする途すがら「何事も衰へゆけど、この道こそ末の世に變らぬものなれ、なほこの歌詠むべき」旨を別當湛快が釋阿に言つてゐるところを夢に見、驚いて詠草を送るのに添へて、「末の世にこのなさけのみかはらずと、見し夢なくばよそに聞かまし」と寂蓮に傳へたことが、家集の一本に見えてゐるが、これを伊勢行き直前のこと(川田氏說)とすれば、「何事も衰へぬる」世相に愴184惶として立ち去る彼の姿が眼に見えるやうである。それに、覺鑁上人このかた密嚴淨土の大道場として法燈の耀き比びなかつた野山も金剛峰寺と大傳法院この分裂·抗爭が久しく續くに至つて、今は心友の西住をも失つた西行には、決して住みよい所でなくなつてゐた。また、武門の專橫がやうやく目に餘つて衰龍の御裁きをさへ妨げまつるに至つて、神統の逸遠を顧りみる思ひが强く湧き上つてきたものとおもはれる。幸ひに、伊勢には佐藤氏の同族が多かつた。かうして、賦役免除の運動を金剛峰寺への最後の奉公として、たまたま伊勢の祠官(荒木田氏良兄弟等)などから招かれたのを機としてつひに野山を下つた、と見て大過なささうである。崇德院の御製に「道のべの塵に光を和らげて」云々とあり、親近し奉つた西行もまた、早くからこの時代の垂跡說を奉じたことは想察に難くない。慈圓、良經等の同じ思想も、彼からの繼承に屬すると云へる。和光同塵の結緣は、桑門としての彼が生涯を通じて欣求するところであつたが、初めは冥助のたつきとして對立的に考へられた神明も、漸次に渾然たる同體として捉へられ185
るに至つたもののごとくである。『撰集抄』(廣本第九)の次の言葉は、彼の眞實の心を表はしてゐると云つてさしつかへない、「わが朝はこれ神國なり。佛法たるこれ神力、王法の王法たる、擁護の神力なり。一天の主、萬乘の寶位と仰がれたまへる天子は、忝けなくも伊勢大神の御流。藤氏の長者天下の攝政と齋かれたまふは、春日の明神の御斎にいまそかりける。百寮何か神氏を離れたまへるはおはしまさず。」伊勢に赴いた西行は、二見浦溝口の邊にまづ留錫し、そこから西福山その他に居を變へて、最後の一、二年を宇治の西行谷に送つた。その森つづきに菩提山神宮寺が再興されて、そこに藤成通の友人なる良忍上人が住み、その關係で西行が移つていつたのである。また、祠官等に西行の歌弟子もかなりあつた。伊勢滯在中の作では、次の諸作がある。186 a御裳濯の岸の岩根に世をこめて堅め立てたる宮柱かな。深く入りて神路の奥を等ぬれば、また上もなき峰の松風。宮柱、下つ岩根に敷き立てて、露も曇らぬ日の御影かな。何事のおはしますをば知らねども、かたじけなさに淚こぼるる。神路山、月さやかなるかひありて、天の原をば照すなりけり。流れ絕えぬ波にや世をば治むらむ、神風涼し御裳濯の岸。この春は、花を惜しまでよそならむ、心を風の宮にまかせて。岩戸あけしあまつみことのそのかみに、櫻をたれか植ゑはじめけむ。神風に心やすくぞまかせつる、櫻の宮の花のさかりを。よろづ代を山田の原の綾杉に風しき立てて聲呼ばふなり。また、壽永二年四月、時に次の詠があつた。勅使として內府宰相·土御門通親が參向したのを五十鈴のほとりに迎へた夙く行きて神風めぐむみ扉ひらけ、天の御影に世を照しつつ。世の中を天の御影のうちになせ、荒潮あみて八百合の神。今もされな、昔のことを問ひてまし、とよあしはらの岩根、187木立。
これらの諸作を通じて知られるは、當時としてさふいふ入り方しかできなかつたものの、に至れば、和光同塵も何もないといふことである。これらはまさしく、日本の詩歌史のうへに未曾有の鬱然たる壯觀であり、民族悠久の悲願がここに於いてほど明らかに具象化せられた例はほとんどない。これらを缺けば西行の詩人としての位置ははるか下方に〓落しなければならず、これらによつてのみ彼は、白鳳期の人麿に對峙し得るのである。ただ、人麿は神々の失墜を支へるべく渾身の力をもつて格闘した英雄的、悲劇的な詩人であつたが、これに反して西行は、神々がそのなかに眠り休らふ草莽の民の歌ひ手として、無限の明るい信賴のもとに、神代の杏たるむかしから咲きこぼれ咲き繼いできた櫻の花が神風にみづからを託して無心に散り舞ふ姿を眺めてゐる。人麿には決意があり慟哭があつた。しかるに、ここに見られるものは、絕對の曇りない信念と歸一とである。日本人はいつたいに、死ぬことを何となく民族的一體として滿々と明るく湛へられた命の滿ち潮に還ることと考へる。したがつて、死はいはば歡ばしい祝典でしかない。佛〓的解釋のこびりついた頭腦には解しかねるかもしれないが、平安末期に於ける紫雲來迎の幻想さも、おそらくさういつた祝典の頽廢的一變形であつたと云へる。時至ればいつせい喜々として188も、枝を離れる櫻の花が國花とせられた所以は、ここにある。命惜しむ人やこの世になからまし、花に代りて散る身とおもはば。さう歌つた西行は、誰知らぬ者ない櫻の詩人であつた。信念といふよりはむしろ、民族の魂そのものの在り方の源初の鮮かな形、滾々と湧く地下の淨らかな可能が、西行をして國民の詩人たらしめた。無窮に息づく章莽の民の悲願が「かたじけなさに」嗚咽する一人の西行のうちにその主要な表現を見出してゐるのは、かうしてすこしも偶然ではない。西行の名はとにかくとしても、かたじけなさに淚こぼるるの歌は童兒にすらもよく知られてゐる。後鳥羽院は、西行といふ小さな泉のおもてに民族の大鳳のおほらかな羽搏きをすら夢みさせられた、と私は先に述べたが、れは、決して過言ではないのである。殊に晩年の西行は、神統擁護の積極的な思想に近づいたらしく、新進のすぐれた歌人たち、慈圓、寂蓮、隆信、定家、家隆等に勸進して伊勢百首の詠を募つたりしてゐる。齋宮の御所の荒廢を見て、注連の御內の塵がいつ拂はれようと嘆き、倭姫が初めそこに神宮を奉じた瀧原を訪ねて189
ここに滯在中のことであつた。浪とまがふ花の下の岩根が瀧の宮に轟く音に强く感動したのも、慈圓が後に『愚管抄』を著してそのなかに國體の尊嚴を繰り返してゐるのはたいへん有名であるが、その淵叢の西行に發することは明らかであらう。190壽永二年七月、義仲の入京に平族は幼帝を奉じて西國に下り、翌月後鳥羽院が立たせられた。翌年正月に入ると事態はさらに再轉して、義仲が敗死し、またその翌年に平族一黨つひに西海に沈むと傳へられた。西行は伊勢にあつて世のかういつた移り變りを痛ましく見守つてゐたが、源氏はもちろん平氏に對しても、もともと同情のあるわけでなかつた。彼にとつては、舊知〓盛の悶死を悼むよりも、宗盛の幼兒の運命にその母の心を思つてひそかに「夜の鶴の」云々と詠むはうが、いつそう眞實であつたらしい。文治二年、六十九歲の西行は、前述のとほり、東大寺大佛殿再興のための沙金勸進を重源上人から依賴され、老軀を起してはるばる東北行脚に上つた。御裳灌河歌合および宮河歌合の判を俊成と定家とにそれぞれ乞ふたのは、その出立の前であつたと見える。翌年の何月かに奧州から歸つた西行は、死のすこし前まで足かけ三年ほどを京洛のほとりに幽棲した。旅から歸つた年の九月に『千載集』奏覽あり、彼の宿望も叶つた。今や彼の周圍には有爲な若い歌人たちが蝟集し、歌作三味の生活が續いた。文治四年、西行七十一歲の時には、藤原隆信四十七、寂蓮四十有餘、慈圓三十三(一說四十一)、藤原家隆三十一、藤原定家二十七、鴨長明二十五、藤原良經二十であつため.釋阿と彼とを中心に、今や新古今歌界の中樞が形成せられつつあつたのである。文治五年七月、上西門院の崩御があつたとき、西行はさすが意氣沮喪して御葬送に列する足の重みを感じたにちがひない。かうして自分の死期も遠くないことを知つたものか、おそらくはそれからまもなく、河內の葛城山麓にある弘川寺に移り、その霜月に至つて病褥に臥したことが都に聞えた。そして、翌建久元年、願はくは、櫻のもとに春死なむ、そのきさらぎの望月の頃と歌つたのと符節を合したやうに二月十六日の未の刻、この曠世の詩人もつひに大往生を遂げた。191
存生にふるまひ、思はれたり寂蓮に送つた慈圓の挽歌の詞書にも、「臨終などまことにめでたく、しにさらに違はず。末の末にありがたき由なむ申し合ひける」と見え、十念亂れぬみごとなその臨終であつたと傳へられてゐる。生涯にわたる彼の雅兄であつた釋阿のこの時の挽歌の序に、「かの上人、先年、櫻の歌あまた詠けるなかに、花のもとに春死なむと詠みたりしををかしく見たまひしほどに、つひに二月十六日、望の日に終り遂げける」云々とあつて、前年すでに辭世代りに「佛には櫻の花を」その他の櫻の歌を多く作つて、花々の明るく搖らぐ祝典としての死を希つたのであらう。そして、この祝典は、風流の明るい燈として喜々として旅に散る中世の庶民詩人たちの草宴を照した。中世の末端につらなる幻住庵の主が「たよりなき風雲に身をせめ、花鳥に精を勞して」と記したとき、彼もまた横顏になかばその燈を感じたのである。192八後鳥羽院その他室町末期ぐらゐの著述に『水無瀨の玉藻』と題する書があり、水無瀨殿に當代の歌人たちが伺候して歌の話を申し上げたことが詳しく記されてゐるが、おもしろいことにはそのなかに西行も登場してくる。もちろん假托書の類にちがひないとしても、そこに述べられた各人の歌論などになかなか穿つたところがあり、その時の事情を詳しく傳へた記錄によつて潤色して綴つた話とさへ思はしめるところを持つてゐる。水無瀨の院が御幼少にして帝位にましましたとき、當代の歌人たちに和歌のことをお尋ねあつたとしたところで、私には不自然ではないとおもはれる。傳へられるところによると、高倉院は、才藻英發、芳齒わづか十歲にして林間に酒を暖める詩のこころを伴の者に許させたまふたが、後鳥羽院が御父帝の神才を承けさせられ、御同年の頃はすでに和歌を學んでその道の人たちに接したまふたことは明らかである。193
『水無瀨の玉藻』のなかで師範として最も高く仰がれてゐるのは西行、また世代の新しい星として重んじられてゐるのは定家よりもむしろ家隆であつて、さういふところから著者の思想的系統がいくらかわかるやうな氣もする。『古今著聞集』に、晩年-もし事實とすれば河內の弘川寺に赴く直前-西行が家隆を訪れて、もう私は長いことがないから思ふところあつて特にあなたにお預けすると云つて、兩河歌合の祕稿を託した、といふことが見えてをり、この話が眞實でないまでも、家隆が西行の囑望する新人であつたことはたしからしい。『遠島御抄』に於いても「家隆は、若かりしをりはいと聞えざりしかど、建久の頃ほひより殊に名譽も出できたりき。歌になりかへたるさまかひがひしく、秀歌ども詠み集めたる多き、誰にもまさりたり。長もあり心も珍らしく見ゆ」と賞揚せられたくらゐで、院の知遇を蒙ること殊に厚く、彼また晩年まで、院のおはす佗しい孤島の空をひとり變ることなくはるかに慰めまゐらせてゐる。かういふところから見ても、人間的に信賴の置ける人であつたのである。さて、この『玉藻』のなかで西行が奏上してゐるところとして、巧みな釋阿論が記されてゐる。すなはち、釋阿は「稽古八十年、その功あくまで長けつれば、かの天性が利きたる妙所こそなけ194佐れ、その歌、生みあるふし失せ、色めきたる氣絕えて、古き器物の瑕なきがおのづから物深く厚くして捨てがたきがごとし。(中略)天性の口といへども、かく色づき光沈みたるは有りがたくこそ」と論じてゐる。これは賞讃であるが、その裏面には人工美學に對する不同意もあつた。今の世の歌、もはら作爲に耽りて、深く妙處を求めてもはらこの趣きのみより至ることを得たり。かくしもあれば、この道ひたすら人作の僞りにのみなりゆきて、天成自然の妙處は少かるべし。」かうして必然に「題の歌詠まむに、その題の理は世の常の見もし聞きもする事物のうへにあり」と云つて題誅の本質的でない所以を說き、すすんで『萬葉』このかた歌の精神が段一段低落したことに及んでゐる。彼によれば『萬葉』の歌は、いかがはしい作にさへ「神代の氣」を保つてゐる。業平にもまだ神代の匂ひは失せてゐない。『古今集』の貫之、躬恒に至つて、詞を飾り體を華やかにしたので、神代の氣を喪失していはば人代の氣を湛へるやうになつた。これ以來、歌は「上を離れて下に赴」いてきた。頽廢の初めである。ただ、『古今』にはまだ「君子」の風がある。『後撰集』に至つて、「美も失せ艶も廢りてことごとく惡しき地に」〓落した。『後拾遺』はもはや、君子の風をすつかり失つて「凡俗の限り」になつてしまつてゐる。これがここに引かれた西行の歌195
史的展望であるが、實際には誰の見解であつたとしても、當時としては驚くべき達見であつて、これを記した著者も決して凡庸の士でなかつたもののごとくである。『西公談抄』のなかで、人麿の「梅の花それとも見えず」云々の歌に就いて「凡夫の心おもふべきにあらず。大なる歌とはこれを云ふなり」と喝破し、「叶ふべきことはにはあらねども、歌はかやうに詠まむとおもふべし」と〓へてゐるのに徵しても、西行が時代の息苦しい人工と裝飾に反撥して、「神代」の悠々濶步に强く庶幾するところあつたことはたしかであらう。ただ、時代の壓力をあまりに孤獨な双肩に受けたために、その反撥の姿勢がおのづから彼の內的形成を規定して、英雄的抵抗の地盤を築かしめるかはりに、息苦しい反撥の空しい餘力としての庶民的遁走をその性格たらしめた。これは、作品にも反映して、なんらかの造形を結ぶかはりにむしろ造形性を融解して空に放散する傾向になつてゐる。構成でなくて解體である。求心でなくて遠心である。かうして、句間にそことなく遍滿して漾ふかの浪曼的味歎が生れるのであるが、前述『玉藻』は、家隆の言としてそのことを「いかなることも安らかにしてそこもとに神氣あることもなくしかもその間に仙骨あり。平懐にしてここにえも云はぬ匂ひあり」と論じてゐる。水196無瀨の院が西行は「不可說の上手」だとせられたときも、やはりこのことを仰せられてゐるのである。水無瀬の院が御幼少のころ老西行に歌道を問はせられた話は後世の作りごとでしかなかつたとしても、院がいかに彼を御敬慕あそばされたかは、御口傳の一端にもうかがはれる。富詹にして纎銳な感受性に富まれた英明なお若い日の院は、「綾杉に風しき立てて呼ばふ」民族無窮の悲願を歌つたこの西行の神統頌をいかなる御感慨をもつて聞こし召されたであらうか。もともと院政の傳統として根を下ろした一つの決意は、この院に於いてつひに欝勃と動きはじめた。憤惋病ひを成して斃れたまふた御父帝の御息吹きも、時とともにいよいよ鮮かに耳朶に迫るものがあつたのである。承久の役のための決意と組織とがいかなるものであつたかは、院がみづから御所鍛冶の間に立つて鎚を振はせられたと知るだけですでに髣髴としてくる。そしてそれは、すべて文化政策の面にも鮮かに現はれてゐる。延喜天曆の復興への線に沿ふて和歌所を置かせられたのは、式197
子內親王の崩じたまふた(正月)建仁元年の七月、また『新古今』の撰を命じたまふたのはその年の十一月であり、御年二十二にしてすでにこの御計劃があつたのである。それは、まさに、帝王としての遮るものなき堂々の歩武を群臣の前にけざやかに示したまふ雄渾な大精神の現はれにほかならない。この意味で、元久二年三月、春日殿で執り行はれた新古今竟宴は、建仁元年の有名な千五百番歌合とともに、絢爛たる交響のうちにその御雄志の羽搏きを夢みさせたまふた大饗宴として、藝文の史のうへに忘れてならぬ事件であつた。すでに米壽に達した釋阿、七十歲を越した季經、顯昭、師光などがそのとき參加してゐるが、雄大にして旺盛な院の御精神の振幅に沿ひ奉るためには、それらの近臣たちにしてもよほどの緊張が必要であつたこととおもはれる。かうして、すでに定家に至ると、欝結した志をひらくためのこの豪奢な風流のこころを解し得る筈がなかつた。彼は、新歌壇の指導者としてたしかに群を拔く存在であつたものの、行きづまつた時代の壁を突破し得るほどの力を缺き、わづかにその工藝的新趣と賦彩とに成功しただけである。そして、つねにその影を全身に感じた父釋阿が亡くなつた元久元年の頃には、詩的情熱をほとんど出し盡したかの觀があり、仙洞の雅安をすら厭ひはじめた。彼は今や、院と自分との大198きな隔りを感じないでゐられなかつたのであらう。さうなると、院に於かせられても、彼のいらいらした世俗的な眼の配りだけが映り、鎌倉へのひそかな身振りまで見透かされたにちがひない。勅勘の因は、すでに早くから兆してゐたのである。院の御周邊には、慈圓、寂蓮、良經、家隆、雅經、秀能、定家などのすぐれた歌人があつたが、いづれもなんらかの意味で西行の影響を受けてゐると云つてさしつかへなかつた。「おほやうは西行がふりなり」と院の評せられた慈圓はもちろん、寂蓮も若くから西行に親炙するところがあつたし、家隆はまた前述のとほり西行に囑目されたとおもはれるふしがある。また、慈圓の〓の中御門良經も、西行の詠風を慕つた。かうして、萬葉·古今に次いで劃期し得た謂ふところの新古今風は、西行の切り拓いた地盤のうへに院を御中心として形成せられた新風であり、しかもその現象の規定者としての院御自身は、時の歌壇の傾向と必ずしも同じであつたとは云へがたい。さういつた流風よりも、ずつと展望の廣い見地に立ち、西行とともに、その氣宇の濶達さに於いて『萬葉』にさへ出入あそばされた。院が求められたのは、豪奢な風流の精神であり、跼蹐し停滯することなき國風のおほらかな流發であつた。院の好ませられる絢爛たる錦繡に工藝的處理をも199
つて應じようとした定家は、彼の氣鋒が銳かつただけに、たちまち精根を枯らさざるを得なかつた。まことに院の御出現は萬骨を蔽ふて餘りあり、これに伴ふべき蒼生の自覺がまだまだ著しく低かつたために、その雄渾な決意と組織とを抱かせられたまま、承久の失敗をはるかに越えて、人なき曠野へとひとり踏み入りたまふのである。このとき、院に於かせられてのこのけざやかな悲願に人臣としてただひとり應和し奉つたのは、當の鎌倉の將軍實朝であつた。水無瀨の院の雄大な御志は、新古今竟宴の噂を聞いてその年(十四歲)から作歌しはじめた少年實朝にいつか感得されるに至つたにちがひない。千五百番歌合に際して受け持たれた院の御判のうしろに、「治まれり、なほも絕えせじ、しきしまや大和島根も動きなき世ぞ」と御製あらせられたが、國風の歌が國體によつてのみ支へられるとするこの絕對の傳統的信念こそ、文化變革の指導者としての院の御立場であつたのである。雁字がらめに縛られて衰龍の膝下に額づくことも望み得なかつた實朝は、身に落ちかかる萬貫の重みに堪へてひとり雄誥びし働哭した。水無瀨の院の御志の雄渾な羽搏きに呼應するこの實朝の絕叫こそ、人麿のそれが貴族政權の進行に抗する銳い警笛であつたやうに、封建の初めの日のあらゆる眼に見えぬ重200壓に渾身の力をもつて反抗した大丈夫の悲劇であつた。がうして、調高い應和は、いはば龍雷の對應にも比すべき壯大な風景として、り類を見ないところであらう。水無瀨の院とこの實朝との格日本の文學史のうへにもあま大君の勅をかしこみ、ちちわくにこころはわくと人に云はめやも。山は裂け海はあせなむ世なりとも、君にふたごころわれあらめやも。ほ一+ひむがしの國にわが居れば、朝日さす藐姑射の山の陰となりにき。箱根路をわが越えくれば、伊豆の海や、沖の小島に浪の寄る見ゆ。大海の磯もとどろに寄する波、割れて碎けて裂けて散るかも。もののふの矢なみつくろふ小手のうへに霰たばしる那須の篠原。時により過ぐれば民の嘆きなり、八大龍王雨やめたまへ。しかし、その實朝はたちまち斃れ、承久の役あつて院もまた隱岐へ遷らせたまふた。201われこそは新島もりよ、隱岐の海の荒き浪風こころして吹け。
奥山のおどろの下も踏みわけて、道ある世ぞと人に知らせむ。202烈風にはためくその欝勃たる帝王の怒りは、今は幽明を異にするかの實朝の龍神をすら叱咤した捨身の激情とはるかに呼應し、大海をも野として孤島に立たせたまふ御姿を傳へてゐる。昨日の豪奢な饗宴にひきかへ、孤島の暗い茅舍での御日常は推し奉ることすら畏いかぎりであつたらうとおもはれる。しかし、憂愁の深い刻みを伴つて沈痛無比な悲歌と化したといへ、御生來の豪奢な明るさは最後まで失はれてゐない。無限の寂寞に面して昏迷の翳なく、欝悒のなかに無心のおほどかな微笑を保ち、その測々たる哀調のうちに〓明な心の休らひを含み、また、人間心理の複雜な陰翳を映してしかも限りなく暖い愛の圓光に包まれてゐる。神統のなかにまします王者としての莊嚴な御信念は、曠野にひとり立つ者の憤ろしい激情と孤高とにかかはらず、實朝などに於ける世の常の一途な英雄的格闘と異つて、八百潮の湧く月明の海の漾々として烟霧に消えるおもむきにあらしめるのである。したがつて、御製のうちに悲劇的な字句を求める人はあてがはづれるかもしれない。しかし、日本の悲劇精神はかへつて院のはうにあり、日本武尊や大津皇子このかた、悲劇をその莞爾たる明るい唇に浮べるところにこそ我々の傳統は置かれたのである。この傳統を支へるためには、ただ、人間精神としておよそ極北の力を要し、且つ無邊の博大な愛を前提する。それゆゑに、限りあれば、さても堪へける身の憂さよ、民の藁屋に軒を並べてと、と、さりげなく呟きたまふたとき、てなほ、かへつて我々は、孤島十九年のあらゆる艱苦に堪へさせられ眺めばや、神路の山に雲消えて、神風や、とよみてぐらに靡く幣、夕べの空を出でむ月影かけて仰ぐといふも畏しと信念にほほ笑まれる强烈な御精神を拜することができる。院の御歌は、絕極に面してそこから引き返した者ののみもつ博大な心の歎きに充ち、沈痛無限なその悲歌のうちに曙の仄暖かい明るさを映してゐる。放膽にして繊銳を極め複雜にしてしかも簡明なそのふしぎな交錯は、おそらく203
ここから發するのであらう。院に於かせられては、悲歌すなはち愛の獻泣であつた。しかも、自他融一のこの深い愛は、萬乘の至尊にあらせられるところから、草茅はてしない民の旦夕にすら及び、「つらき住まゐの夕霜をおのれ鳴きつつ淚と降」る悲しい雁の思ひあらせたまふたのである。204おのれのみ逢へる春ぞとおもふにも、峰の櫻の色ぞ懶き。美まし、永き日影の春に逢ひて、いせをの海士も袖や干すらむ。春雨も花のとだえぞ、袖にもる櫻つづきの山の下道。よしの川せかばや春の休らはむ、折られぬ水の花の泡沫。櫻咲く遠山鳥のしだり尾の、ながながし日も飽かぬ色かな。櫻山に夕かけて鳴くほととぎす、椎柴がくれしばし語らへ。夏山の繁みに匍へる靑つづら、苦しや憂き世わが身ひとつに。ふるさとを別れ路に生ふる葛の葉の秋はくれども歸る世もなし。ちはやぶる神も知るらむもろかづら、ひとかたならずかくる賴みを。人も愛し、人も怨めし、あぢけなく世を思ふゆゑにものおもふ身は。思ひつつ經にける年のかひやなき、ただあらましの夕暮の空。大空に契る思ひの年も經ぬ、月日もうけよ行くすゑの空。思ひやれ、眞柴のとぼそおしあけてひとリ眺むる秋の夕暮。いかにせむ、葛はふ松のときのまも、怨みて吹かぬ秋風ぞなき。見し世にもあらぬ袂を哀れとて、おのれ萎れて訪ふ時雨かな。とにかくに、人のここるも見えはてぬ、憂きや野守の鏡なるらむ。本枯らしの隱岐の柚山吹きしをり、荒くしをれて物思ふころ。院の御主宰によつて新古今風が生れたことは事實であるが、これらの御製はもはや、西行の作品とともに、單に新古今風といふやうなものではない。それはさういつた流風を高く越えて孤高永遠のひびきを傳へてゐる。『水無瀨の玉藻』のなかの西行があらゆる作爲を排して「神代」の天衣無縫を說いてゐるとき、この書の著者は院の御文學のために忠實であつたと云へる。205
水無瀨の院が隱岐に遷らせられ、草莽の間に御身を沈めたまふた時から、封建の鐵壁ことごとく天日を蔽ひ、國風の眞の詩のこころは久しく「おどろの下」の流離に任せられなければならなかつた。貴族政權の地盤としての莊園はそれみづから封建の端初であつて、藤氏擅權の極に幕府形態をほとんど具へるに至つたとはいへ、その瓦壤に從つてやうやく頭を擡げた庶民たちは、先登に立つた一部の武門のためにもつと嚴しい桎梏をふたたび迎へた。といつて、中世を一〓に暗いとだけ考へてはならぬ。庶民の自意識の高まりがあつたからこそ、より暗く感じられたのである。そして、そのやうに感じた詩人たちは、いづれも院と西行のあとを追ふて山林や塵巻に身を隱した。しかし、遠島の御島羽院の身をもつてあそばされた實證によつて後に正風としての位置を與へられた西行の抒情は、庶民の無意識の力を吸收して立ち現はれたとはいへ、やはりますらをの志に發するものであつた。したがつてそれは、俳諧の源流をなしたとはいへその精神は決して俳諧そのものではない。俳諧人が草茅の旅に描いたものは、狹斜であつて相聞でない。世態であつて魂でない。後に芭蕉が正風への復歸を宣告したとき、浮世派のすきごころを評して「或ひは人情206を云ふとても、今日の騷がしき隈々を探り求め、西鶴があさましく下れる姿あら」(去來抄)と述べたこの變革者にしてもなほ、「さすがに捨てがたき情のあやにくに」食ひ入つた自身の肉體への危ふい拒絕にをののいたのである。西行が一身に融卽して保ち得た人間性への浪曼的〓解は、次代の人たちになると、支點を失つてただ客體としてのみ捉へられ、いきほひ分裂して無心衆と有心衆との對立を示すとともに、その分解した發想も、衆のなかに自己を客體として茶化し抛棄すべき餘裕ある連歌の形を取つた。しかし、いづれにしても、もともと悲劇を知らぬ庶民たちは、あとも先もないいはば肢體だけの戯宴に浮かれ、茶坊主を宗匠として「しどけなき輕口のみ云ひ出でて、月も花も笑ひあかして靜かなること侍らず」(蕉門俳諧語錄)、しかもそのかたはら、職業化して流浪した連歌師などを通じて浮世文學を作り出すに至つてゐる。かうして、曠野と化したこの廢墟を前にして行はれた芭蕉の正風再建は、すでにそれみづから封建下のあらゆる創痍に堪へる悲劇的な血戰として、塚も動けの慟哭を伴はなければならなかつなまづ太刀を捨てて庶民に歸した芭蕉は、武夫の志を擁しつつ國民的廣がりにまで身を遍滿し得た西行と反對に、封建的庶民文化の重圍のなかからふたたび丈夫の道へと血路を開かうとした207
のである。あらゆる意味で、芭蕉の壯烈を極めた戰ひも、歸するところ觀念上のものでしかなかつた。そしてこのことは、誰よりも芭蕉みづからの知るところで、「かりそめに云ひ散らされしあだなるたはぶれごと」を恃んでつひにその細きひとすぢにつながる、と自身の喜劇を見出したとき、彼は二重の悲劇に身を置いたと云へる。彼は西行の旅の終つたころから逆に歩みはじめ、その歩一步を探り出しこれを確めつつ身を支へた。譬へて云へば芭蕉の努力は、茫々たる廢墟を駈けめぐつて徒手もつて榮華のプランを復元しようとするそれにも似てゐた。「血脈」を決定的に重んじた所以もここにあるのであるが、しかも、死が迫つてもなほ「この道や行く人なしに」と嘆き、夢に曠野を駈けめぐらなければならなかつた。芭蕉に於いては、西行とちがつて、遁走そのものがすでに血まぶれな敗恤であつたのである。芭蕉に於ける正風への變革は、無心·有心を問はず、俳諧の悲しい運命を自覺するところから始まつた。彼が「俳諧は世の變相」(葛の松厚と說いて流行說を基礎づけたとき、移り變る世塵のなかに喜々として入り交ることの哀しさを意識することをまづ前提としてゐるのであらう。流行は、畢竟、人それぞれのすきごころによつておのづから釀し出される(去來抄)。それゆゑに208有心衆の色界放浪も、その移り變りの哀しさを覗くことによつてのみ不易の相に入ることができる。その意味で、旅の歩一步にみづからを捨てて、落葉と散り敷く「あだなるたはぶれごと」に永遠のひびきを聞くところにこそ、自身でなかば喜劇化した彼の嚴肅な觀念悲劇が横たはつてゐた。西行が時のない悠遠のなかに融け去らうとしたとすれば、芭蕉はおよそ、刻々の日の翳りを痛いくらゐ剋明に感じ取つてゐる。或るとき彼は、人に招かれていつて、食事が終つてからその蠟燭を消してくれと乞ふた。主人がなぜと聞き返すと、「夜の更くること眼に見えて心せはしきとなり。かくものの見ゆるところ、その自心のおもむき俳諧なり」と答へ、續けて「命もまたかくのごとし」と云ひ添へてゐる(くろさうし)。また、他のところでも〓へてゐる、「飛花落葉の散り亂るも、そのなかにして見とめ聞きとめざれば收まることなし。その活きたるものだに消えて跡なし」(あかさうし)。日本の藝術史のうへでこの芭蕉ほど時間を意識した作家を私は知らない。彼にあつては、時そのものがすでに漂泊の思ひであり、句々ことごとく辭世であつたと云ふことができる。西行が山野をもつて永劫の母性を描き、また隱岐の院が御自身の激情を曠野に化せられたとすれば、芭蕉はひとり、非情の涯しない荒野にみづからを見出して歩々のよろめきに堪へ209
たのである。210西行の遁走の後、御島羽院が承久の決行に敗れて孤島に遷幸あられた日、元祿の芭蕉の敗恤はすでに定まつてゐた。もちろん、隱岐の院は、孤島の茅舍に於かせられてもなほ、敗戰を斷じて肯定しない一つの世界包含的な激情として、その內面に欝紆として濤うつ雄大な展望を失ひたまはなかつた。しかるに、敗戰の否定は、その血管に綠の靑春を失はない者のみの持つ特權であり、しかもそれは今や現人神によつてのみ可能であつたのである。我々が院に捧げる感謝の一つは、まことにこの院によつて靑春の存續を證し得たことであらう。このとき院の點火がなかつたとすれば、民族の精神史に一つの暗翳が漾ふことは明らかである。中世の初めの日に仰がれた院の突々たる神彩は、神話的彷徨者にして政治的變革への指導者、繊銳並ぶ者ないすぐれた詩人にして雄大な組織者、大饗安に臨む帝王にして曠野にただひとり立つ生ける塑像、悒欝にして〓明、弱冠にして老成、陶醉的にして理智的、まさしく永遠の靑年としてのすべてを包括してゐると云つてさしつかへない。しかし、院の出現は、明らかに、西行に於ける靑春の回想に俟つところがあつた。王朝四百年にわたる文化の血の老廢から脫して西行が歌つたかの靑春への美しい憧憬、そのなかに無限の有羞感の漂ひ消える杏かな碧一色の浪曼は、彼以後の中世の空を明るく染め、遠く我々の足もとにまでその波紋の麗かな照り返しを投じてゐる。西行は靑年自體ではないし英雄でもない。ただ彼は靑春の回想を高く點じ、これに向つてその生涯を逆に歩いていつた。すなはち、草莽の大地に己のすべてを惜しみなく投げ出してそこに神々の安らかな寢息を聽き、絕對の信賴に浸りつつ、しかも〓愁に驅られるもののごとく母なるその神々の顏を求めて感傷し放浪した。さうして窮極に尋ねあてた民族の靑春の象徴こそ、無限に咲きこぼれ咲き繼ぐかのうららかな櫻の花であり、山田の杉の森々たる梢をわたつて無窮に呼ばふ神統頌であつた。西行が國民詩人として千古に絕する所以の最大のものは、云ふまでもなくここにある。彼の回想に應じて、身をもつてその靑春を現じた人こそ、畏くも後鳥羽院であらせられる。院の承久の擧は、たとひ敗戰に終つたとはいそれみづから靑春不滅の決意として、元寇後わづか五十年にして正宗、親房、正成の三星を211
つらねる燦爛たるオリオンと化し、爾來、明治に至るまで、民族の悲願の據つてもつて發する遠い淵叢になつてゐる。しかし、藝文の徒の悲しい運命は、これをまともに受け取ることができず、多くは決意以前の西行に歸つて山間や狭斜にその姿を韜晦した。武士たちの錬成的な象徵藝術にすら、もはや靑春は描かれなかつた。芭蕉に至つてふたたび靑春への渴望が見られたが、滿身創痍の彼にとつてそれはすでに幻影でしかなかつた。彼は、西行に於ける靑春の回想をさらに回想したにとどまつてゐる。「予もいづれの年よりか片雲の風に誘はれて漂泊の思ひ止まず」として奥の細道に西行の足跡を辿つたとき、彼の眼に映つたものはもはや、風月の佇まひではなくて曠野の觀念そのものであつたのである。虛に居て實を行ふことの危ふさは、誰よりも芭蕉その人が知つて居た。中世の最後の人として近代を展いたこの元祿の大詩人によつて初めて、現代に至つてもまだ散見される何者にも支へられぬ裸形の痛ましい自意識が發生するのである。爾來、明治に至るまで、民族の悲願の據つてもつて發する遠212西行略年譜
西行の生涯を年譜として揭げるのは甚だ困難であるが、讀者の便を圖つて判明してゐるだけから、拾ひ出してみる。*年號の下の括弧中の數字は年齢。元永元(一)油小路二條南に(〓〓眼抄)生る。○藤璋子中宮となる(正月)、〇六條東洞院の顯季邸に初めて人麿影供を催す(六月)。ニ(二)○中宮璋子顯仁親王(崇德帝)を生む。保安三(五)○白河院法勝寺にて未曾有の法會(四月)。四(六)○崇德天皇卽位(二月)、〇六條顯季薨ず(九月)。天治二(八)○行尊大儈正となる。大治元(九)○中尊寺建立(三月)。二(一〇)○源俊賴『金葉集』撰進。215四(一二)〇白院崩御(七月)。○俊頼歿す(十一月)。
長承元(一五) *この前後に初めて北面に出仕。同じ頃藤原俊成と相知る。○良忍寂す(二月)、〇平忠盛内昇殿(三月)。○この年天下飢饉。 216三(一七)保延元二(一八)○平〓盛、父忠盛に從ひて西海よリ凱旋(八月)。○法金剛院に三重塔および金泥一切經供養(十月)。○俊成、基俊の門に入る。*鳥羽上皇安藥壽院本塔檢覽のお忍びに德大寺實能とともに供奉す。○美福門院體仁親王(近衞帝)を生む(五月)、立てて皇太子となす(八月)。*十月十五日、出家して西行と號す。妻子に關しては本文參照。但し鴨長明『發心集』(卷六)に、このとき家を弟に讓り幼き娘を託すとあり、この方むしろ正しからんか。これによれば、妻また同時に出離して高野山麓天野別所の金剛寺附近に隱棲せるもののごとし。(なほ、このこと事實ならば、待賢門院中納言局が後に隱棲して小倉山より天野に移りたるにもなんらかの關係あるべし。) (一九)四五(二一) (二二)六(二三)○鳥羽僧正覺猷寂す(九月)。○近衞帝卽位(十二月)。*二月、待賢門院落筋のとき御結緣のため法華經廿八品の歌を詠む。筆一品經の供養を勸進して內大臣賴長の門に立つ。○藤原基俊歿す(一月)。*この頃東國旅行。○僧覺錢寂す(十二月)。藤原顯輔、『詞華集』撰上の命あり、就きて崇德院より歌を召さる。原三寂と交渉あり。○橘忠兼『伊呂波字類抄』執筆、○藤原敦光卒す。○待賢門院崩ず八月)花散る頃、堀川局のもとへ故門院哀悼歌を贈る。*この前後に野山に入る。大峰修行もこの頃か。永治元康治元(二四) (二五)三月、自(二六)天養元(二七)このとき大執筆、○藤原敦光卒す。久安元(二八二(二九) 217三(三〇)
六仁平元ニ久壽元ニ三三)崩德院百首歌召したまふ。『詞華集』撰進、その歌讀人不知として一首入選。*この頃西國へ下り安藝嚴島明神に參詣す。源右大臣雅定に出家を勸む。七月近衞帝崩御、その後、船岡知足院の御陵に詣づ。○藤原顯輔歿す(五月)、〇後白河天皇卽位(十月)。*七月、島羽院崩御、高野より出でて御大葬に會す。同月保元の亂起り、崇德院仁和寺北院へ渡らせたまふ。急ぎて伺候し、阿闍利兼賢に會ふ。その數日後院讃岐へ遷幸。*父母を失ひし德大寺公能を野山より弔ひ、出家を勸む。〇二條天皇卽位(十二月)亂以前、待從大納言成通に出家を勸む、成通十月出家す。*十一月、美福門院崩じ、翌月その御舎利を野山に迎ふ。218 (三四(三五)三七) (三八)保元元(三九) *二(四〇) *出家を勸む。三(四一)平治元永曆元(四二) (四三)應保二長寛二永萬元(四五)成通薨じ、これを弔す。○崇德院讃岐に崩御(八月)。二條帝崩御、九月その御陵に詣づ。〇六條天皇卽位(七月)。信西入道の妻紀伊二位局待賢門院出仕)の死を弔し挽歌十首あり。*十月、賀茂社に暇乞ひの參拜の後、西國行脚に出づ。讃岐崇德院の白峰御陵を拜し、弘法大師出誕の善通寺に至り、年末九州の一角まで至れるもののごとLo (四七) (四八)仁安元二(四九) (五〇)○〓盛太政大臣となる(二月)。○高倉天皇卽位(三月)。○後白河院の『梁〓秘抄口傳集』成る(三月)。*六月、後白河院熊野御幸の途次住吉に御駐輦ありしにたまたま會し、○前年『今鏡」成り、またこの頃『水鏡』成る。三(五一)嘉應元承安元(五一) (五四)感あり。219
ニ(五五) *三月攝州福原に〓盛の千僧供養あり、ついでに和田岬にて萬燈會ありしもののごとくこれに會す。五辻齋院、御父帝御追善のため大義房賢宗に高野東別所に蓮華乘院の建立を命ず、輔けてこれに當る。*十一月、內裏近隣出火、西行の生家破却さる。ついでに和田岬にて萬燈會ありしもの220安元元(五八) *○僧源空、專修念佛を唱ふ。叡山無動寺に千日修行の慈鎭のもとへ歌を贈る。○俊成出家、釋阿と號す。三月頃京にあり、紀州日前宮造營の賦役免除を請願して奔走す。五辻齋院の命にて蓮華乘院を壇上に移す。六月上棟、十一月御供養。○京都大火(四月、○藤原〓輔歿す(六月)。たぶんこの年、雪深き頃、高野へ歸るに際して平時忠と歌の贈答あり。○平德子言仁親王(安德帝)、を生む(十一月)、○ 一長秋詠草」(俊成歌集)成る。*この年深秋頃、新宮を經て伊勢に赴くか。なに、熊野詣での途すがら夢の告二(五九)治承元(六〇)五辻齋院二(六一)三(六二)に驚きて寂蓮勸進の百首歌に應じたるも、○大地震、〓盛法皇を圍す(十一月)。伊勢にて六月福原遷都を知り感慨深し。口字豆石山林間、西行舊跡)。この頃なるべし。四(六三)この頃二見浦邊に居住す(現在二見町溝○安德天皇卽位(四月)、○源頼政以仁王を奉じて擧兵仲擧兵(九月)、平軍富士河に敗退(十月)。○高倉天皇崩御(一月)、〇〓盛薨去(閏二月)、〇定家の(五月)、○賴朝擧兵(八月)、〇義養和元壽永元ニ(六四)『初學百首』成る。(六五)○顯昭の○顯昭の『古今集序註』成る。二月『千載集』撰進の院宣釋阿に下り、久我通親の伊勢參拜を迎へ歌あり。(六六)これに歌を送る。*四月、公卿勅使○義仲京に迫り、平氏天皇を奉じて西下、本朝臣人麿勘文』成る。正月義仲栗津に敗死と聞きて歌あり。○後白河院、後鳥羽天皇を立つ(八月)、〇一部221元曆元(六七) *
文治元(六八)良忍宇治橋畔に菩提山神宮寺を再興、依つてその森續きに庵を結ぶ(その跡現在西行谷と稱す)。*六月、平宗盛父子鎌倉より京都に送らるると聞きて同情の歌あり。○平氏一門西海に沈む(三月)、〇『松浦宮物語』この頃成る。*初秋頃、東大寺大佛殿再興の沙金勸進のため東北東海大行脚の途に上る。八月十五日鎌倉にて賴朝に謁し、十月十二日平泉着。この頃義經また平泉の館に隱る。*なほ出發前に當代の新進歌人に伊勢百首の詠を勸進せるもののごとくこの年定家二見浦百首を詠ず。○大原御幸(四月)、〇『保元物語』『平治物語』成れるはこの頃か。櫻の頃平泉出發、三月、出羽國最上〓瀧の山の靈山寺に赴く。御裳濯河歌合一卷に釋阿判す。歸來京洛附近にありしもののごとし。『千載集』成り歌十八首入る。○平泉の秀衡卒す(十月)。222ニ(六九)三(七〇)御裳濯河歌『千載集』成り(十月)。四五(七一) 秋その勸進によつて慈圓御裳濯川百首を詠ず。定家宮河歌合に判す(八月返却)。たぶんこの年の秋頃、麓の弘川寺に移る。○衣川合戰、義經殺さる(閏四月)、○賴朝奥羽を平定(九月)。二月十六日、櫻咲く滿月の日、未の刻に入寂。○賴朝入京(十一月)。(七二)河内石川郡葛城山建久元(七三) 223
西行秀歌抄
春(山家集)海邊の霞といふことを藻鹽やく浦のあたりは立ちのかで、煙あらそふ春霞かな若菜に寄せて古きを思ふといふことを若菜つむ野邊の霞ぞあはれなる、昔を遠くへだつと思へば鶯によせておもひを述べけるに憂き身にて聞くも惜しきは、鶯の、かすみにむせぶ曙の聲閑中鶯といふことをうぐひすの聲ぞ霞にもれてくる、人目ともしき春の山里雨中の鶯227爲の春さめざめと鳴き居たる、竹の雫や淚なるらむ
霞中歸雁といふことを何となくおぼつかなきは、天の原、かりがね霞に消えて歸る雁群228水邊の柳水底にふかきみどりのいろ見えて、花を待心をおぼつかな、いづれの山の嶺よりか、風に波よる川柳かなおぼつかな、待たるる花の咲きはじむらむ花のうたとてよめるおしなべて花の盛りになりにけり、山の端ごとにかかる白雲よしの山、こずゑの花を見し日より、心は身にもそはずなりにき身を分けて見ぬ梢なく盡さばや、よろづの山の花のさかりを白川の春の梢の鶯は、花のことばを聽くここちする願はくは、花の下にて春死なむ、そのきさらぎの望月のころ佛には櫻の花を奉れ、わがのちの世を人とぶらはば何とかや、世にありがたき名を得たる、花よ櫻にまさりしもせしだ花も散り人も來ざらむをりはまた、山の峽にて長閑なるべし花のしたにて月を見て詠みける雲にまがふ花の下にてながむれば、朧ろに月は見ゆるなりけり春の曙花見けるに鶯の鳴きければ花のいろや聲に染むらむ、鶯の鳴く音ことなる春の曙花花ときくは誰もさこそはうれしけれ、思ひしづめぬわが心かな初花のひらけはじむる梢よりそばへて風のわたるなるかな蛙眞菅生ふる山田に水をまかすれば、三月晦日に行く春をとどめかねる夕暮は、嬉し顏にも鳴く蛙かな曙よりも哀れなりけり229
230夏(山家集)郭公を待ちてむなしく明けぬといふことをほととぎす聞かで明けぬる夏の夜の浦島の子はまことなりけり時鳥をほととぎす聞くをりにこそ夏山の靑葉は花に劣らざりけれ時鳥おもひもわかぬ一聲を聞きつといかが人にかたらむ語らひしその夜の聲は時鳥、いかなる世にも忘れむものか鳥を雨の中に郭公を待つといふことをよみけるにほととぎす偲ぶ卯月も過ぎにしを、なほ聲をしむ五月雨の空五月雨の晴間も見えぬ雲路より山ほととぎす鳴きて過ぐなり五月雨水湛ふ入江の眞孤刈りかねて、むなでに捨つる五月雨のころつくづくと軒の雫をながめつつ、日をのみ暮らす五月雨のころ東屋の小萱が軒の絲水に玉ぬきかくる五月雨のころさみだれの頃にしなれば、荒小田に、人にまかせぬ水たたへけりみを五月雨はいささ小川の橋もなし、いづくともなく水脈に流れて川わだの淀みにとまる流木のうき橋わたす五月雨のころ旅行草深といふことを旅人の分くる夏野の草しげみ、葉末に菅の小笠はづれて行路夏といふことを雲雀あがる大野の茅原、夏くれば、凉む木蔭をねがひてぞ行く題しらず夏の夜は篠の小竹の節ちかみ、そよや程なく明くるなりけり雨中夏月凉む木蔭をねがひてぞ行くしらずそよや程なく明くるなりけり231
夕立の晴るれば月ぞ宿りける、玉搖り据うる蓮のうき葉に232秋〓1家集、七タいそぎ起きて庭の小草に露ふまむ、やさしき數に人や思ふと舟よする天の川邊の夕暮は、涼しき風や吹きわたるらむ荻おもふにも過ぎて哀れに聞ゆるは、荻の葉みだる秋の夕風秋の歌よみける中におぼつかな、秋はいかなる故のあれば、すずろに物の悲しかるらむ何となく物哀しくぞ見えわたる鳥羽田の面の秋の夕暮晴れやらぬみ山の霧のたえたえに、ほのかに鹿の聲きこゆなり荻の葉みだる秋の夕風秋の夜の空にいづてふ名のみして影ほのかなる夕月夜かなあまの原月關けのぼる雲路をば分けても風の吹きはらはなむ播磨潟、なだのみ沖にこぎ出でて、あたり思はぬ月をながめむ月澄みて風ぎたる海の面かな、雲の波さへたちもかゝらで閑に月を待つといふことを月ならでさし入る影もなきままに、暮るるうれしき秋の山里名所の月といふことを沖の岩こす白波に、光を交す秋の夜の月〓見潟、月前にとほく望むといふことをくまもなき月の光にさそはれていく雲ゐまで行く心ぞも月のうたあまたよみけるに人も見ぬよしなき山の末までも澄むらむ月の影をこそおもへながむるもまことしからぬここちして世に餘りたる月の影かな239
雲晴るる嵐の音は松にあれや、月も綠のいろに映えつつ雲も見ゆ、風も更くれば荒くなる、のどかなりつる月の光をもろともに影を並ぶる人もあれや、月の漏りくる笹の庵に月瀧をてらすといふことを雲消ゆる那智の高根に月たけて光をぬける瀧の白絲月前蟲露ながらこぼさでをらむ月かげに、小萩が枝の松蟲の聲人々住吉にまゐりて月を翫びけるに波にやどる月を汀にゆりよせて鏡にかくる住吉の岸船の中の初雁沖かけて八重の汐路をゆく舟は、朝に初雁を聞くよこ雲の風に別るるしののめに、山とびこゆる初雁の聲234ほのかにぞ聞く初雁のこゑ山とびこゆる初雁の聲夕暮に鹿をきく篠原や霧にまがひてなく鹿の聲かすかなる秋の夕暮蟲の歌よみ侍りけるにきりぎりす、夜寒になるを〓げ顏に、枕のもとに來つつ鳴くなり秋ふかみ弱るは蟲の聲のみか、聞くわれとてもたのみやはある物思ふねざめとぶらふきりぎりす、人よりもけに露けかるらむ夕の道の蟲といふことを打ち具する人なき道の夕されば、聲たて送る轡蟲かな秋物へまかりける道にて心なき身にもあはれは知られけり、鴫たつ澤の秋の夕暮鴫たつ澤の秋の夕暮冬(山家集) 235
長樂寺にて夜紅葉をおもふといふことを人々よみけるに夜もすがら惜しげなく吹く嵐かな、わざと時雨のそむる紅葉を神無月、木の葉の落つるたびごとに、心うかるるみ山べの里236題しらずねざめする人の心をわびしめてしぐるる音は悲しかりけり冬のうたよみけるに難波江の入江の芦に霜冴えて浦風さむきあさぼらけかな山家冬月月出づる嶺の木の葉も散り果てて、麓の里はうれしかるらむ月かれたる草をてらす花におく露にやどりし影よりも、庭上冬月といふことを冴ゆとみえて冬ふかくなる月かげは、枯野の月は哀れなりけり水なき庭に氷をぞしく加茂の臨時の祭、かへり立つ御神樂、土御門內裏にて侍りけるに、竹のつぼに雪のふりたりけるを見てa裏返す小忌の衣と見ゆるかな竹の裏葉にふれる白雪社頭雪玉垣は朱も綠も埋もれて雪おもしろき松の尾の山雪のうたども詠みけるに何となく暮るる雫の音までも山べは雪ぞ哀れなりける雪ふれば野路も山路もうづもれてをちこちしらぬ旅の空かな靑根山、苔のむしろの上にして、雪はしとねのここちこそすれ千鳥磯わの千鳥聲しげし、瀨戶の夕風さえまさる夜は淡路潟、瀨戶の夕風さえまさる夜は237
238戀(山家集)後朝今朝よりぞ人の心は辛からで明けはなれゆく空をながむる月前戀を哀れとも見る人あらば思はなむ、月のおもてに宿すこころを想ひ出づることはいつもと云ひながら、月には堪へぬ心なりけりを月前の戀といへることをなげけとて月やは物をおもはする、かこちがほなるわが淚かな淚ゆゑくまなき月ぞくもりぬる、あまのはらはらねのみなかれて戀何となくさすがにをしき命かな、有り經ば人や思ひしるとて有り經ば人や思ひしるとて何せむにつれなかりしを怨みけむ、逢はずばかかる思ひせましや物思へどかからぬ人もあるものを、哀れなりける身のちぎりかな搔き亂る心やすめの言草は、あはれあはれとなげくばかりぞ人は憂し、嘆きはつゆもなぐさまず、こはさはいかにすべき心ぞ今ぞ知る、おもひ出でよと契りしは、忘れむとての情なりけりなかなかに思ひ知るてふ言の葉は、とはぬに過ぎて怨めしきかな物思ひはまだ夕暮のままなるに、明けぬと〓ぐる柴鳥の聲哀れとてなどとふ人のなかるらむ、物おもふ宿の荻の上風あはれあはれ、この世はよしや、さもあらばあれ、來む世もかくや苦しかるべき雜(山家集一) 239題しらず
つくづくと物を思ふにうちそへて、をり哀れなる鐘の音かななさけありしの昔みなほ偲ばれて長らへまうき世にもあるかな240花桶によせて懷舊といふことを長らへむと思ふ心ぞつゆもなき、厭ふにだにも足らぬ憂き身は思ひ出づる過ぎにし方を恥かしみ、あるにものうきこの世なりけり花たちばなによせて思ひをのべける世の憂きを昔語になしはてて花橘に思ひいでばや尋ねまかりけるに、月あかかりければ世を捨てて谷ぞこに住む人見よと嶺の木のまをいづる月かげ題しらずさらぬだに世の儚さを思ふ身に、鵺なきわたるしののめの空こととなく今日くれぬめり、明日もまた變らずこそはひま過ぐる影はかなしや、あだに命の露きえて、野べにわが身の送り置かれむ物こころぼそうあはれなるをりしも、の音きこえければそのをりの蓬がもとの枕にも、菴の枕ちかく蟲かくこそ蟲の音にはむつれめ無常のうた、あまたよみける中にいづくにか眠り眠りてたふれ臥さむと思ふ悲しき道芝の露大波にひかれ出でたるここちして、助け舟なき沖にゆらるる題しらず曉の嵐にたぐふ鐘の普を心の底にこたへてぞ聞く松風の音あはれなる山里に、さびしさそふるひぐらしの聲何となく汲むたびにすむ心かな、岩井の水に影うつしつつ鶉ふす刈田のひづち思ひいでてほのかに照らす三日月の影つらなりて風に亂れて鳴く雁のしどろに聲の聞ゆなるかな朝に花を等ぬるといふことを241
すぎてゆく羽風なつかし、鶯の、なづさひけりな梅の立枝を古畑のそばの立つ木にゐる鳩の友よぶ聲の凄き夕暮すがるふすこぐれが下の葛まきを吹き裏返す秋の初風ませに咲く花にむつれて飛ぶ蝶の美しきも儚なかりけり風吹けばあだに破れゆく芭蕉葉のあればと身をも賴むべきかば侘び人の淚に似たる櫻かな、かぜ身にしめばまづこぼれつつ俊惠天王寺にこもりて、ひとびと倶して住吉にまゐりて歌よみけるに倶して住吉の松が根あらふ波の音を梢にかくる沖つ白浪天王寺へまゐりたりけるに、松の鷺の居たりけるを月のひかりに見て庭よりも鷺ゐる松の梢にぞ雪はつもれる夏の夜の月題ら242いかでかは音に心の澄まざらむ、草木も靡く嵐なりけり旅(山家集)大峯のしんせんと申す所にて月を見てよみける月澄めば谷こそ雲はしづむめる、嶺吹き拂ふ風にしかれて題哀れなり、よりよりしらぬ野の末に、哀れなり、鹿を友になるる住家は高野にこもりたる人を、京より何ごとかまたいつかいづべきと申したるよしききて、その人にかはりて山水のいつ出づべしと思はねば、心細くてすむとしらずや松の絕え間より纔かに月のかげろひてみえけるを見て影うすみ松の絕え間を漏りきつつ、心ぼそくや三日月の空243
祝大海の汐干て山になるまでに、君はかはらぬ君にましませ244戀百十首夜もすがら恨みを袖に湛ふれば、枕に波のおとぞきこゆる身をもいとひ人の辛さも歎かれて、思ひ數ある頃にもあるかなこととへばもてはなれたる氣色かな、うららかなれや、人の心のわれのみぞわが心をばいとほしむ、愍れむ人のなきにつけても眺めこそ憂き身のくせとなり果てて夕暮ならぬをりも分れねいとほしや、さらに心のをさなびて、たまぎれらるる戀もするかな人知れぬ淚に噎ぶ夕暮は、引きかつぎてぞ打ち歐されける逢ふとみしその夜の夢の醒めであれな、長きねぶりは憂かるべけれど雪のふりけるに花とみるこずゑの雪に月冴えて譬へん方もなき地する百十をりしもあれ、嬉しく雪のつもるかな、かきこもりなむと思ふ山路を小鳥どものうた、よみけるなかに聲せずと色濃くなると思はまし、柳の芽食む鶸のむらどり桃園の花にまがへる照爲の群立つをりは散るここちする熊野へまゐりけるに、ななこしのみねの月を見てよみ立ちのぼる月のあたりに雲消えて光かさぬる七越の嶺月雲はれて身にうれひなき人の身ぞ、日の入る、つづみのごとし波のうつ音を鼓にまがふれば、入日の影の打ちて搖らるるさやかに月の影はみるべき245
246百首(山家集)郭公なべて聞くには似ざりけり、ほととぎす、深き山べの曉の聲異本山家集梅梅さかりなるわが宿を、尋めこかし、うときも人はをりにこそよれ花山人に花さきぬやと尋ぬれば、いざ白雲とこたへてぞ行く待たれつる吉野の櫻咲きにけり、心を散らせ春の山風吉野山、花をのどかに見ましやは、憂きがうれしきわが身なりけり山路わけ花をたづねて日は暮れぬ、宿橿鳥の聲もかすみて白川の關路の櫻咲きにけり、東より來る人のまれなる那智に籠りし時、花の盛りに出でける人につけて遣し曉とおもはまほしき音なれや、花に暮れぬる入相の鐘鶯の聲に櫻ぞ散りまがふ、花の言葉を聞くここちして花も散り淚も脆き春なれや、またやはとおもふ夕暮の空郭公時鳥、ふかき嶺より出でにけり、秋風あはれいかに草葉の露のこぼるらむ、時鳥、外山のすそに聲のおちくる秋風立ちぬ宮城野の原247月
月見ばと契りおきてしふるさとの人もやこよひ袖ぬらすらむ憂き身こそ厭ひながらも哀れなれ、月をながめて年を經ぬれば248冬月小倉山ふもとの里に木の葉ちれば、梢はなるる月をみるかなあづまの方へ修行しはベリけるにふじの山をよめる風になびく富士の煙の空に消えてゆくへも知らぬわが思ひかな八島内府(宗盛)〓倉に迎へられて、京へまた送られ八島内府(宗盛)〓倉に迎へられて、京へまた送られたまひげり。武士の母のことはさることにて、右衞門督(〓宗)のことを思ふにぞ、とて、哭きたまへると聞きえ夜の鶴の都のうちを出でてあれな、この思ひには惑はざらまし無常の心をかたがたにはかなかるべきこの世かな、あるを思ふもなきを偲ぶも津の國の難波の春は夢なれや、芦の芦葉に風わたるなりあづまのかたへ、あひ知りたる人のもとへまかりけるに、さよの中山見しことの、昔になりたりける、思ひ出でられて年たけてまた越ゆべしと思ひきや、命なりけり小夜の中山昔になりたりける、命なりけり小夜の中山月のうたとてよめる老けにけるわが世の影を思ふまに、高倉院の時そぞろにそれになりぞゆく、はるかに月のかたぶきにける見ればげに、枯野の薄、有明の月大神宮御祭日によめる何事のおはしますをば知らねども、伊勢大神宮にて下つ岩ねにしきたてて、かたじけなさになみだこぼるる249宮柱、露もくもらぬ日の御影かな
神路山にて月さやかなるかひありて、250神路山、天の下をば照らすなりけり御裳濯川のほとりにて岩戶あけしあまつみことのそのかみに、櫻を誰か植ゑはじめけむ櫻の、御まへにちりつもり、風にたはるるを神風に心やすくぞまかせつる櫻の宮の花のさかりを題不知秋篠や外山の里やしぐらむ、生駒のたけに雲のかかれる道のべの〓水ながるる柳影、しばしとてこそ立ちどまりつれよられつる野もせの草のかげろひて、凉しく曇る夕立の空月の歌の中にかくれなく藻にすむ蟲の見ゆれども、戀歌中にわれから曇る秋の夜の月はるかなる岩のはざまにひとりゐて人目つつまで物思はばや有明はおもひであれや、よこ雲の、漾はれつるしののめの空見我人不知戀をわが戀はみしまが澳にこぎ出でてなごろわづらふあまのつり舟身延〔箕面か?〕にて雨しのぐ身延の〓の垣柴に、すだちはじむる鶯のこゑ山ほととぎす橘の匂ふ梢にさみだれて、山ほととぎす聲香るなり聞書集及殘集花のちりけるを見てよみける命惜しむ人やこの世になからまし、花にかはりて散る身とおもはば251
郭公ほととぎす、曇りわたれるひたかたの皐月の空に聲のさやけさ墓にまかりておもひいでし尾上の塚の路絕えて、松風かなし秋の夕闇252ほととぎす、松風かなし秋の夕闇月あはれいかに豐かに月を眺むらむ、八十島めぐる海士の釣舟花歌十首人々よみけるにひとときに遲れさきだつこともなくよごとに花の盛りなるかな八十島めぐる海士の釣舟聖衆倶會樂枝交し翼ならべし契りだに世にありがたく思ひしものを月難波江の岸にそなれて這ふ松を音せで洗ふ月の白波嵯峨に住みけるに、たはぶれ歌とて人々よみけるをうなゐ兒がすさみに鳴らす麥笛のこゑに驚く夏の畫臥し心からせし隱れ遊びになりなばや、片隅ごとに寄り伏せりつつ篠ためて雀弓張る男の童、額鳥帽子のほしげなるかないたきかな、菖蒲かぶりの茅卷馬は、うなゐわらはのしわざとおぼえて戀ひしきを戯れられしそのかみのいわけなかりしをりの心は地獄畫を見て見るも憂し、いかにかすべきわが心、かかる報いの罪やありけるあはれあはれ、かかる憂きめをみるみるは、何とて誰も世にまぎるらむ憂かるべきつひの思ひを置きながら、かりそめの世にまどふ儚さ公卿勅使に通親の宰相のたたれけるを、五十鈴のほとりにてよみけるいかばかり凉しかるらむ、つかへきて御裳濯川を渡る心は夙く行きて神風めぐむみ扉ひらけ、天の御影に世を照しつつ五十鈴のほと253
おなじをりふしの歌に世の中を天の御影のうちになせ、荒潮あみて八百合の神今もされな、昔のことを問ひてまし、豐蘆原の岩根、木立254題なき歌浮世にはほかなかりけり、秋の月、なきながむるままに物ぞ悲しき兩宮歌合御裳濯川歌合色つゝむ野邊の霞のしたもえて、心をそむる鶯の聲つくづくと物思ひをれば、ほととぎすこころにあまる聲きこゆなり宮川歌合萬代を山田の原の綾杉に風しき立てて聲よばふなり諸撰集歌玄玉集波と見えて尾花かたよる瀧原に、松の嵐の音流るなり夫木集駒なづむ木曾のかげぢの呼子島、誰ともわかぬ聲きこゆなり萠え出づる峰の早蕨亡き人の形見に摘みて見るも儚し松の嵐の音流るなり255
西西西詩西行と景樹と守部西行法師傅西西行行行人法法法西行行師師師行西行宗〓倫理叢書佛〓史談叢書〓育偉人叢書日本百傑傳文少年の頃のわが愛讀書なりき。印はこの著述に際して參照せるもの。献献窪梅梅犬松布〓奬學〓究會中獨立の單行本のみを揭ぐ。野田澤澤道井寺龍松空精精廣峯穗一一直兒吉(大正八年、(大正六年、(大正四年、(明治四十三年、(明治四十三年、(明治三十二年、(明治二十九年、(明治二十六年、なほ上野氏の『西行』聽松書院白日社)廣文堂森江書店文明堂·興文館東京帝國史學會)民友社港書房)は257
西行〓究錄西行法師文献目錄西人行間法西師行 歌西創西西西西行法師評傳放たれた西行漂泊の人西行西行の俊成·定家·西行西行と一茶行人行作さ西法西生涯行行ま行師行 *歷代歌人〓究川大窪大橫品蓮木相尾野高上吉上田阪田坪史草山沼村馬山口田篤米政口根司野野史田談空二靑文善御二次次小臥松順會穗郞娥順順範之風郞郎郎劍城峯(昭和十六年、昭和十五年、昭和十五年、(昭和十五年、(昭和十五年、(昭和十四年、(昭和十一年、(昭和十一年、(昭和十年、(昭和九年、(昭和九年、(昭和八年、(昭和八年、(大正十四年、(大正十二年、(大正十年、改造社)春秋社)著者)春秋社)創元社)大阪史談會)厚生關)時代社)文學書房)創元社)人文書院大東出版社)第一書房)實業之日本社)而立社)新光社) 259 258
昭和十七年一月二十日昭和十七年一月十五日發印師法行西圓二價定(行刷(錢十二圓二價定地外)配給元印刷著發行所者發行者者東京市神田區淡路町二ノ九日本出版配給株式會社岩東京市麹町區有樂町一ノ四壁保宍會社株式道東京市麴町區有樂町一ノ四統社會社合資三東京市日本橋區芳町二ノ一福印刷會員番號一二〇五七〇番道指〓東京一六五五六一番電話銀座五四一統一番社道三戶福印統儀ギ刷所一
東洋人の時代生田長江著十數年前既に歐羅巴の行詰りを說き、興亞の今日を豫見してゐたこの著者の達見に驚くこれこそ新東亞建設識見の泉。(定價一圓八十錢送料十二錢)民族的優越感保田與重郞著今我々に必要なのは日本人としての自信を持つことだ。著者はこれまで私達の知らなかつた日本と日本人の偉らさを〓へて吳れる。(定價二圓送料十二錢)大西郷の精神影山正治著著者は昭和に大西〓の精神を生き拔いて來た人、この人に書かれた大西〓こそ讀者をぢかに大西〓に引見せしめる。(定價一圓五十錢送料十二錢)不滅の人吉田松陰武田勘治著著者は文部省推薦となゆた前著吉田松陰に嫌らず、更に沸々たる熱情をこの書に籠めた松陰の全貌を描いて完璧。(定價一圓五十錢送料十二錢)道統社新刊武田勘治著更に沸々たる熱情をこの書に籠(定價一圓五十錢送料十二錢)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
