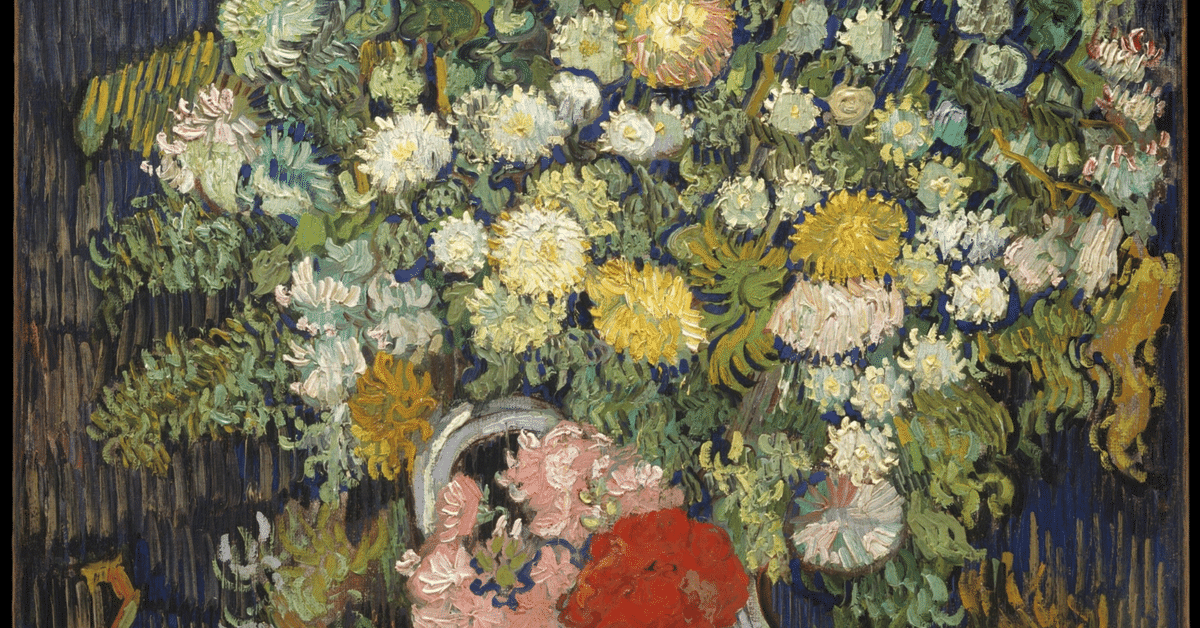
秋の山左右に細き蕃椒 夏目漱石の俳句をどう読むか46
日本全国の近代文学2.0の皆さん、おはようございます。
みなさん、これが近代文学2.0で、皆さんがこれまで寝ていたことを證明します。
秋の山静かに雲の通りけり
子規は「通り」に傍線を引いて「此語生矣」としたそうだ。「矣」の音読みは「イ」。断定・推量・疑問・反問・感嘆の意。~矣で。…である。…だなあ。…だろう。の意味になる。つまり生、そのままでよくないと言っている。俊成なら「ただことばならむ」というところだ。
俳句が何を求めてのふるまいかということを子規は真剣に考え続けてきた筈だ。要するに神来の興とは言ってみても、それは人それぞれで、誰かの神来の興が別の誰かとっても神来の興であるわけもない。漱石は「生」にこそ価値を置いたかもしれないし、子規にはそれが通じなかっただけなのかもしれない。しかし子規は「此語生矣」と指摘した。
流れる、揺蕩う、たなびく、と別の表現がありうるからではない。おそらく子規はこの時「雲の通ひ路」という和歌の言葉を思い、「雲の通路」は雲の行き通ふ路で、本來は空の意であることを思い、「雲の通りけり」に軽いトートロジー、不完全な意味のなさを見たのではないか。それで「此語生矣」でなければ少し厳しい。
天津風雲の通ひ路ふきとぢよ乙女のすがたしばしとどめん
雲めぐる岩の柱や秋の山
秋の山雲一片飛んで去る
雲むらむら秋の山高くあらはるゝ
雲も皆沈み勝ちなる秋の山
ほかに「秋の山寺」との組み合わせが一つあるが子規の句の内「秋の山」と「雲」の取り合わせは、この五句だ。このうち漱石の句と近いのは、
秋の山雲一片飛んで去る
であろうか。「飛んで去る」とは確かに「通り」よりは工夫している。人によっては誇張と感じるかもしれないが、とにもかくにも遼東の豕にはなりたくなかったのであろう。「あたりまえ」ではいけないと尖りに尖っていた時期のことでもあろうし、この時期の漱石のおおらかな句が「生煮え」にも見えていたのかもしれない。
秋の山静かに雲の通りけり
しかし私はむしろ「静かに」に工夫を見る。雲なんてそう音のないものである。たいてい静かである。それを敢えて「静かに」と詠んでみたところに漱石の悪戯があるのではないか。
さらにいえば確かに「通りけり」があっさりしすぎている感じが確かにあるので「静かに雲」に意識が行かない。「静かに雲」に意識が行かないようにするために「通りけり」とわざとあっさり詠んだとまで考える必要はなかろうが、出来上がった句は結果としてそういう構造を持っている。
これだけの短い詩形の中でできることは沢山あるのだなと感心する句だ。
谷川の左右に細き刈田哉
たいていの川は左右に何かを持つものである。片側しかない川はない。しかしこの句の面白いのは谷川こそが細かろうに、その左右の刈田が直細いところだ。そんな刈田はあるまいと突っ込みたくなるところ。
勿論子規はこの句も気に入らぬようで、「細き」に傍線を引いて「狭きの意かそれにしても陳腐」としている。
陳腐と言われてしまうと陳腐。
谷川の細きに左右の刈田かな
では月並みか。
いやいや、そもそも「谷川」の左右に刈田はなかろう。角度が付けば水田ができない。段田を作るなら谷川ではなく用水路を巡らすだろう。
谷川の細きに左右の刈田かな
という光景そのものが、まずないものである。つまり陳腐と言えば陳腐だが、もっとでたらめなのが、
谷川の左右に細き刈田哉
この句も結果として「細き刈田」とうところに意識を持っていかれてしまい、「谷川ってことは山の中や。坂やで。そんなところに何で刈田があんねん。畑ならいいで。田圃は無理やろ」と思わせない構造になっている。
証拠?
子規の評がそのまま証拠である。
私なら「谷川」に傍線を引く。何故ならこれが近代文学2.0だからだ。子規の評は残念ながら近代文学1.0に留まっている。
これはコメの作り方を知らない、というキャラクターを演じる漱石にしか詠めない句なのではないか。
滝の音や渋鮎淵を出で兼る
子規はこの句の「出で兼る」に傍線を引いて「下句渋鮎の形容ならじ」と真面目に指導している。子規という男は本当にまじめな男だ。たしかに「出で兼る」は「渋鮎の形容ならじ」なのであろうが、そもそも回遊魚である鮎は山の清流に戻るためには急流を遡上せざるを得ないのであって、「滝の音」などにいちいち怖気づくこともあるまい。
さらにいえばいくら回遊魚で元気だからと言って、魚が淵を出れば干からびてしまうので「淵を出で兼る」がおかしいと言わねばならないのだ。それなのに子規が「出で兼る」に傍線を引いているところがなんともいえぬ味わいがある。「出で兼る」とは、それこそ一つの選択肢が選べないので現状に留まるという意味であり、川に留まるという意味になる。それこそ魚にとっては当たり前すぎるくらいに当たり前の状態が、「淵を出で兼る」なのである。
漱石はそのそぐわない形容で渋鮎ならぬところを詠んでいて、子規が大真面目で指導している感じがなくもない。
この句も「出で兼る」にひつかかるが、そもそも「なんで淵に出なあかんねん」と近代文学2.0的には読める句である。そういうところから始めないと先には行けない。
赤い哉仁右衛門が脊戸の蕃椒
さあ、この句は解らない。こんな解釈がネットでは見つかった。しかし「脊戸」つまり勝手口と「背戸」裏口を間違えている時点で情報の信頼度は低い。

一茶の「脊戸」はほぼ「瀬戸」である。


また「脊戸」は「脊戸」を出たまわりの意味で詠まれることが多く、ドアそのものの句というものは見つからなかった。勝手口に茄子を吊るしても唐辛子を吊るしても通るのに邪魔であろう。「仁右衛門」が何者なるかは保留しておくとして、「脊戸の前に生えていた唐辛子が赤いよ」という句なのではなかろうか。
[余談]
赤が反抗の色としている時点で「革命家世代」の人の回答なのかなと想像する。赤が反抗の色なら日の丸は何なのだというがする。赤備えなどは強者のイメージ。
……とは言いながら仁右衛門が何者なのかということはやはり解らないし、仁右衛門と唐辛子の因縁も掴めない。瀬戸の唐辛子も解らない。座敷風車も解らない。解らないことだらけだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
