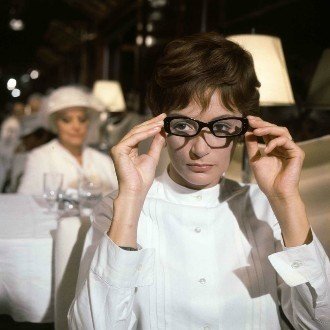東欧映画、ロシア映画以外の未公開映画についてまとめています。最近は公開された作品も掲載しています。全ての記事をどこかに帰属させてあげたいという親心です。見逃してください。
- 運営しているクリエイター
2022年4月の記事一覧

ラヴ・ディアス『Serafin Geronimo: The Criminal of Barrio Concepcion』全てはここから始まった
ラヴ・ディアスの長編デビュー作。エンジェルという名のジャーナリストが暗殺された。彼女の後輩で親友だったエルヴィラは、ジャーナリスト暗殺事件のほとんどが未解決のまま放置されていることについて、葬儀場に来た国会議員を問い詰めるが、大きな成果は得られない。そこで何か物言いたげなセラフィンという男と出会う。彼はエンジェルが死の直前まで担当していた未解決の誘拐事件について、情報提供をしようと田舎からマニラまでやって来たのだ。エルヴィラはエンジェルの後を引き継いで、関係者全員死亡で幕を下