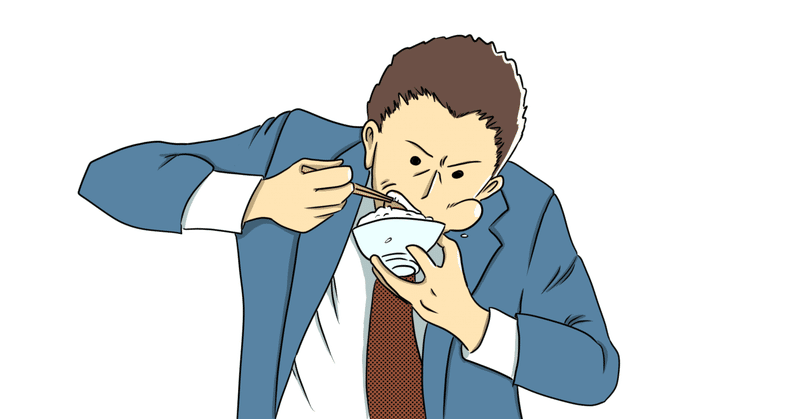
【ソシガヤ格闘記・第8週】食のコモンズから新たな自治を作ることはできるのか。
こんにちは。初めまして。
慶應義塾大学メディアデザイン研究科修士2年、
休学中の吉田凌太(よしだりょうた)といいます。
今回もいつも通り、アイデアとして結晶化する前の、なりかけの思考をそのまま吐き出します。完璧な文章として加工することで削がれ落ちてしまう何かがあることを嫌い、鮮度高く書いてみます。
今、自分は祖師谷にて、新たな「自治」のあり方を実践しようと試みています。そういうとなんか意識高い系になってしまいますね。ただ自治のあり方を模索するために活動を始めたのではなく、「結果としてそうなっている」、といった方が語弊がないかもしれません。
自治という言葉を考え出すと拡張が無限に可能で、正直吐き気がします。気持ち悪くなります。 最終的には生死を彷徨う、人間とは何か、そんな議論にまで拡張せざるを得ません。ゲシュタルト崩壊に陥って、文字が読めなくなることもあります。今の現状や自分の置かれた周りの機会をじっくりと省察した上で、現状に対してどんな意味づけができるのかを考えてみることにしました。
自治というと、しきりにメディアで現れるのが「デジタル化」です。もう聞き飽きました。一つのアプローチとして、住民全体にDIDを発行し、そこに医療情報やその他情報を付与し、データの保守運用獲得をどのように設計するかをトップダウンで検討する。確かに全体のアーキテクチャ設計をどのように進めていくかを考えていくのも大切です。当該分野にはいずれ関与していくだろうし、今のデジタル庁はじめ凄腕の方々を巻き込んでできたらいいなと思うばかりです。適当ですが、きっとすごいことができるでしょう。横展開できる素晴らしいモデルがどこかでポンと生まれて、実証を兼ねて輸入が進んでいくでしょう。全くの無関心ではないですが、今の最終目的として設定してこれを進めるのは、旨みを感じません。
じゃあ自分が最大限できる機会ってなんでしょうか。
いやむしろ、自分たちが一番気分昂る価値ってなんでしょうか。
自分の環境を振り返ってみましょう。大学院はメディアデザイン研究科ということもあり、人間と計算機、もっと拡張するなら、自然全体の中の人間のあり方を省察することに興味があります。行政システム、という人間による鋭意の集合体にシステムが浸透している形態に興味があるのも、その一環なのかもしれません。コミュニケーションや日常生活の中に潜む小さな幸せを、どのように自然の中に定義づけるか、そして過度に高尚化した人間の政治文化をどのように生活に回帰させるか、それが僕のミッションなのかもしれません。人間って大したことないんだよ、でもだから生きてて楽しんだよ、っていう裏返しの感情を楽しめるようにしたいです。
そう思うと一気に肩の力が抜けます。直感的に、街中での食連鎖を新たに萌芽させることに興味が湧いてきます。
大前提、自治とか考える前に、自治ってなぜ必要なのでしょうか。そもそも自治っていう言葉って生きていく上で当たり前というか、これを考えることって人間としてのあり方を考えることに近い気がします。自治会とか、地方自治、自治体とか、人口体については頻繁に言及されますが、これは現実の中の表面にすぎなくて、本質的に「生きる」を考えた時に、食べる、寝る、生きるということは密接になりかねないのかなと。
その上で、街の文脈を重ね合わせると、誰かと時間を重ね合わせること、これが街に住む一番の喜びなのかなと感じます。簡略化すると、共有です。そしてもっとポップにするなら、コモンズの再定義という言葉に置換できます。人間を支配する、心を動かす、それは難しい、そんなことない気もします。みてください、みんなスマホを電車でしてる。でもそれがしたいわけではない。人間と人間をつなぐ物体や機会をみえるようにし、時にそれが重なり合ってたり、時に離れたりを繰り返す中で、相互に繋がりが自然に生まれ、最終的な「自治」に結果的に辿り着いている状況が作りたい。
そのコモンズの一つの表現方法として、食器があるのかなと仮説を立てています。前にもあげたポストマンの話に戻ります。他民族が集まる当初のアメリカで、地域コミューンの架け橋となっていたのが郵便局員でした。掛け合うたびに会話を交わし、その度に関係性が生まれていく。一見郵便に目が行きがちな中で、それを支える器にこそ価値があったという事例です。
この例をそのまま今やってもきっと難しいでしょう。情報の接種手段がSNSで簡単に手に入れられるし、郵便はAmazonでワンクリックで完了。そんな世界で、「繋がりを大切にしましょ!」と綺麗事言っても、振り向きません。ストーリーが完全に文脈から断絶しており、それを設計するのは無茶があります。強制的に振り向かせるものでもなく、理想として直感的に琴線に触るものでありたい。ってなると、やっぱりゲノムレベルで人が反応する何か、生きていることを感じる何かを街に足していくことが一番なのかなと感じてます。
5年前、アルバニアに行った時のことを今でも忘れません。若者たちがニコニコしながら夜に街に集い、一緒に酒を交わしながら、笑顔で話していた姿を。それでいい気がします。まあいいや。
昔から見た時に、食を1人で食べる、そんな光景を想像することはあったんでしょうか。どんな時代も常に誰かと、仕様もない会話をしながら、ご飯を食べる。それが楽しいのに。そう思ってそうです。時代に反逆するけど、自分たちが少しワクワクするような取り組みをスタートできたらなと思ってます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
