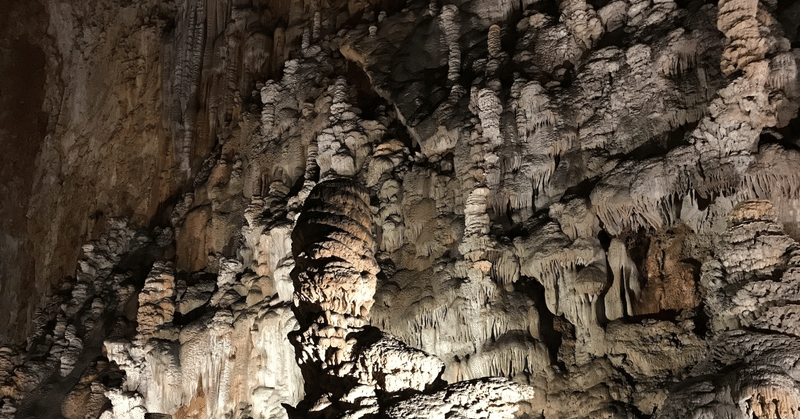
これからダンジョン飯を読もうかと思っている人がうらやましくってたまらない
ダンジョン飯の発行部数1000万部と超売れているけど、日本の人口1億2千万人に比べるとあまりにも少ない。つまり読んだことのある人よりない人の方が圧倒的に多い。これから1巻から14巻の完結までイッキ読みすることができる人がこんなにもたくさんいる。
なんてうらやましいんだ。
私もそうなりたい。
今すぐガーンと頭をぶつけて記憶を失いたい。
私がダンジョン飯を読んだことがない異世界に転生したい。
もちろんリアルタイムでダンジョン飯を追いかけていた私も幸せだったことは間違いない。
それでも「完結後にこの作品をイッキ読みしたい」という絶対に叶わない欲望を持ってしまう。人間の欲って果てしない。でもだからこそ人間なのだと、この作品を読んで思った。
ダンジョン飯は「魔物を食す」ことを描いたファンタジーだが、それは発端であって、読み進めると「人間の欲望」という内容に行き着く。
と、いうわけであたかも「ダンジョン飯」未読者向けの記事のように始まったが、以下思いっきりネタバレフルスロットル完読した同士向けです。ごめんね。
まだ「ダンジョン飯」未読という幸せものは是非とも『ダンジョン飯』全14巻+『ダンジョン飯 ワールドガイド冒険者バイブル』を買え!
テレビアニメ『ダンジョン飯』は本日1月4日スタートです!
食べることは生きること
食べる系グルメ漫画が普及して「食べることは生きること」といういい感じの締め文が陳腐化してしまった感がある。
この作品でも出て来るが、それは「なんかいい感じの締め」というより「世界のルール」として言及されている印象だ。主人公たちが長い旅路の果てに行き着いた答えではあるが、最初から提示されていたごく基礎的なもの。
食は生の特権だ。
「ダンジョン飯」の1話と最終話のラストでこの一文がリフレインすることからもわかる。
疑いなく、徹頭徹尾、これが作品の一貫したテーマだ。そこにダブルミーニングも裏テーマもなく、1話と最終話で同じ意味に使われている。
それなのに1話と最終話では読者の印象はまるで違う。そうでなければ意味がないし、それこそがリフレインの醍醐味だ。
この一文を読んだとき、私は無意識のうち、勝手にこう読み換えていた。
生は欲望の特権だ。
7巻以前でもライオス一行や他パーティー、他の住民たちの「食べたい」「儲けたい」「大切な人を救いたい」「謎を解き明かしたい」という欲望は随所に出てきた。
生理的欲求以外で魔物を食べたがってドン引きされるライオスの描写も前面に出ていた。
だが、まいた種が実るように、「欲望」というテーマが押し出されたのは、ミスルンが登場した8巻からだ。7巻以前も抜群に超絶おもしろいのだが、この作品がバリバリメチャメチャおもしろくなるのは8巻からだと勇気を持って言い切ってしまおう。
生物の原初的な望み「食欲」を入り口にした今作は、欲求を食べる悪魔の存在が明かされることによって、さらなる深層へと進んでいく。
そこには食欲をはじめあらゆる望みを内包する「欲望」がひそんでいた。
生きるから「欲望」があるのか、「欲望」があるから生きるのか?(鶏が先か、卵が先か……)
ただ言えることは、「欲望」と生が同義だということ。しかし「欲望」があるから魂と肉体は縛られているとも言える。
それは理外の存在である悪魔でさえ、逃れられない強い枷だ。
お前は
こんなものに縛られる必要のない
もっと自由な存在だったはずだ……
欲望という魔力、生きるという魔術
人間の面白いところは、「欲望」が生まれ続けるところだと、作品はいう。
人間は生理的欲求のみで生きるのではない。だから一方が叶ったらもう一方が叶わなくなる矛盾した「欲望」をいっぱい持つし、「欲望」を叶えたことで不具合が生まれ、それを正したいという思いがけない「欲望」がどんどん生まれたりする。
作中でもこの人間の性質が悪魔に食料を供給し続けているが、しかし最終巻では希望として扱われている。ほんとうのほんとうに大切な核となる欲求が失われていない限り、「欲望」は生まれ続ける場面が描かれている。
食われた欲求は戻らなくとも
欲求が尽きることはないと思うんですよ
作中において異次元から取り出した無限のエネルギーが「魔力」、それをコントロールする方法が「魔術」とされる。作中でライオスたちのいる次元は有限の世界だが(現実世界も)、ひとつだけ存在する無限のエネルギーこそが「欲望」である。
残念ながら、現実にも作中にもこのエネルギーをコントロールする術はない。ライオスたちも私たちも、その「欲望」に振り回されつつ、おののきつつ、それでもどうにかこうにか、あっちを立たせこっちを立たせ、えっちらおっちら頑張るしかない。
ただ唯一、人間が「欲望」から主導権を奪い取れる方法が、イヅツミがたどり着いた結論のように「選ぶこと」なのだ。
本当にやりたいことは絞る必要がある。
今一番やりたいことってなんだ?
「選ぶ」と簡単に言ってしまったが、これがまた難しい。特に成熟し、安定していない社会では。
そんな社会を作るにはどうすればいいのか? そこが「ダンジョン飯」の終着であり、ライオスたちの新しい冒険の出発に繋がるわけだが、この描き方がほんとうに良かった。
「欲望」の核とはなんだったのか
1000年間熟成した欲望を悪魔に食べられてしまったシスル。
同じく大部分の欲求を食べられ、残された悪魔への復讐心も叶って空っぽになったミスルン。
しかし最終巻でシスルはヤアドに抱かれて(おそらく)息を引き取り、ミスルンはカブルーに手を取られて立ち上がった。
この二人の違いはなんなのだろう。シスルは核を悪魔に食べられてしまったからなのか?
完全に私見だが、そうではないだろう。「欲望」の核はその人の中にあるのではなく「他者とのかかわり」なのではないかと思う。
シスルにとって他者はデルガルだけだ。王族と国民はデルガルの所有物でしかない。だからデルガルがもういないとわかってしまって(シスルは自分に話しかけているのがデルガルの姿をした別人だと気づいた、のが私の解釈だ)、核を失ったのだ。
対するミスルンには他者がいる。カナリア隊の仲間、カブルー、キャラブックで描かれた兄。核があるので欲求は生まれるし、他者の役に立つことに喜びを見出すこともできる。
これはライオスも同様だ。かつてのライオスにとっても他者はいなかった。ファリンのことも自己と分離できているかあやしい(なんたって似たもの兄妹なので)。他人に興味のないライオスは繊細なコミュニケーションができないから、彼の心に爪痕を残せるのは剥き出しの悪意しかない。シュローやカブルーからの言外のコミュニケーションがまったく刺さっていないのも、やんわり優しく遠回りだから。
よって、物語が始まった当初ライオスの世界にいたのは二種類の人間だけだった。自分(と同一視した仲間)か、酷い悪意をぶつけてくる敵(学校や兵隊時代のいじめ加害者、無理解な両親)だ。敵と認識した時点で理解をシャットアウトするため、なぜ相手が悪意を持つのか考えるのにも至らない。
こういうライオスたち、世の中にいっぱいいますね。
まあ私がそうなんですけど。ほんとうにライオスのコミュ障っぷりは全コミュ障大共感だ。
自分語りだが私も「言ってくれなきゃわからない」タイプで、暗黙の了解とか言外に匂わせるとか空気とかほんとうにもう全然何にもわからない。わかる人が魔法使いに思える。ちなみに、敵以外の他人=自分なので、自分については言ってないことも相手は理解してくれると思っているんですよ、マジで。困ったね。
そんなライオスだが、逃げることのできない迷宮の中で、色々な冒険をし、パーティーの仲間たちと色々なものを共に食べ、自分が食べたいものと他人が食べたいものは違うと学び、助けたり助けられたり、殴ったり殴られたり(これはシュローだけか)、ピンチになったりさせたり死にかけたりして、ようやく自分とは異なるけれど尊重したい「他者」を発見するのだ。
よく作劇の本に「主人公の成長を描こう」とか「成長とはラストが冒頭とはまったく違う状態になること」とか書いてあるけど、あれだけ読んでもよくわからない。実際に本で具体例を読んでこういうことかと納得しないとだめ。私にとって「ダンジョン飯」のライオスほど「主人公の成長」の具体例を見せてくれる存在はない。
実のところライオスの成長はそれほど劇的なものではない。相変わらずコミュ障だろうしサイコパスだろうし、どう逆立ちしても王様に向いてない。でも最終巻ラストそして巻末の「モンスターよもやま話」で描かれたライオスには「他者」がいて、しかも彼らを大切に思っている。「ステータス:なし」「ステータス:0」はまったく違う。コミュニケーションにとってその最初の一歩が最も難しく、大切なのだ。
耳が痛いです、はい。
ついライオスの話ばかりしてしまったけど、「ダンジョン飯」では「食」と同じくらい、「ディスコミュニケーション」や「理解しあってなさ」や「価値観の違い」が描かれている。これは今作だけでなく九井諒子さんの作品全てに、だ。
あなたと私が見ているものは違う。「違いの名手」九井諒子
「ダンジョン飯」連載以前から九井諒子さんの作品が好きだった。
三冊の短編集は紙と電子の両方を持っている。
作品集を見てわかるのは、九井諒子さんという作家さんはほんとうに「真実はたったひとつ」なんてまったくこれっぽっちも信じていないんだな、ということだ。
世の中のありとあらゆるものが、それを捉える目の数だけ存在している。同じものを見ていても、見ているものは違う。
それが如実にわかる短編は、「狼は嘘をつかない」(「竜のかわいい七つの子」収録)と「えぐちみ代このスットコ訪問記 トーワ国編」(「ひきだしにテラリウム」収録)だろう。
どちらも可愛らしくてのんきな画風のエッセイパート(観察する側)と、リアルな画風の漫画パート(観察される側)で構成されていて、観察する側される側、それぞれの視点から描いている。
この二つの作品は、どちらかといえばコミックエッセイ画風とリアル画風のギャップを狙ったものかもしれない。
あるいはエッセイパートは「狼は〜」が子育て体験記、「スットコ訪問記」が海外旅行記で、「親/観光客」という上から目線で「子供/現地」を一方的に観察するというグロテスクを風刺したという意図の方が大きいかもしれない。
かもしれないが、二つの作品はともにコミックエッセイ部分も書き手にとって真実なのが伺える。もちろんリアル画風の漫画パートで描かれた観察される側からの嫌悪や反発もまた真実だろう。同じ事柄について相反する感想が提示されたとき、ついネットに毒された私たちは「どちらかが嘘をついている」と考えがちだが、往々にして「どちらも嘘ついていない(少なくとも本人とっては)」というのは現実にたくさんある。むしろ、意図的な嘘よりそっちのケースの方が多いだろう。
九井諒子さんは、作品の中でこういった「視点の違い」「価値観の違い」をずっと描いている作家さんだ。
もちろん「ダンジョン飯」もガッツリ描かれている。
「ダンジョン飯」にはさまざまな人種が登場する。それぞれの人種は同じ古代人を祖とする人間であるが、相互理解が困難なほどにあらゆるものが違う。その原因は魔法や地域差もあるが、最も大きいのは「寿命」だろう。平均400年生きるエルフと平均50年生きるハーフフットで同じ価値観を共有しろという方が無理だ。
そして私はこういう「見ているものが違う」ことを創作物の中で見せられるのが大好物なのだ。
みんなには生きてて欲しい!!
ついでに私と同じくらい(1千年)
寿命も長くなって欲しい!!
追い詰められて迷宮の主人になることを選ぶマルシルの願い。
いや笑った。めちゃくちゃ面白い。こういう緩急のつけかた、ギャグが九井節だなあと思う。
それはともかくここはすごく九井諒子さんの「『価値観』観」が出ているなと感じる部分だ。
人間は自分本位の価値観しか持てない、ということである。
当たり前だ。他人本位の価値観なんて、持っていないと同じことだ。
私の場合だと、他人に興味があって他人の気持ちを慮れて空気が読める人間は魔法使いだ。逆に向こうからすればこっちは悪意があって人の気持ちを無視しているようにしか思えないだろう。小学生の時に教えられた「ひとの気持ちになって考えましょう」がおそろしく難しいのは、その「考える」原点である価値観は自分のものだけだからだ。
だからすれ違う。だから見ているものが違う。
そして興味深いのは、「ダンジョン飯」の中でこの人種間の不理解は、人間の「欲望」と違ってまったく解決していないということだ。
私は人種による寿命の差をなくしたいの
(略)
人種間には見えない溝があって
お互い同じ人間だと思ってない
マルシルは悪魔にこう語るが、実際のところは寿命差によって大切な人間たちに先立たれ置いていかれることを恐れていたので、死を受け入れたことで納得する。人種間の断絶にそれほど興味があるとは思えない。
勝手に拝察するのだが、九井諒子さんにとって「価値観の違い」は作品を描く上で重要な題材だが、決して解決するものではないのだろう。
ただ「ダンジョン飯」の中でこの価値観の不一致への緩和策として出てくるものが、「料理をつくり、食卓を囲むこと」だ。
「同じ釜の飯を食う」という常套句の通り、一緒に食事をすることは一体感を生む。連帯感が出てくる。
仕事以外で話をしなかったライオスパーティーが本当の仲間になったのは、食卓を共有したからだ。
寿命も文化も居住域も倫理観も違う人間同士わかりあうことは多分ない。それでも一緒に食事をすること、美味しいものや不味いものを共有することで「意外といい奴らじゃん」と思うくらいのことはできる。根本は解決していないが、しょうがないのだ。神が解決するものじゃないと思っているのだから。
なお余談だが、「ダンジョン飯」の中ではメインストーリーで人種間の断絶が描かれているが、おまけ的にちらっと描かれている異人種間恋愛も気になるところ(マルシルの両親の話、『ワールドガイド』のオッタの漫画、思いっきし同人種間だけどシュローとファリンの話)
九井さんの他作品の恋愛描写を見ても、九井さんが「恋愛に相互理解なんか全然いらーん」と考えてそうで潔くて良い。むしろ理解していない、相手に勝手に幻想を重ねてときめいている状態が「恋愛」なのかも。九井さんの長編恋愛漫画があったらめちゃくちゃ読みたい。
ライオスたちのこれからはどうなる?
オタクなので「ライオスたちのこれからの人生」に思いを馳せてしまう。
二次創作を描くには作品が完成され過ぎているので、馳せるだけだけど。
ライオスの対外的なサポートはカブルー、公人としてのサポートはヤアドがいる。私的なサポートは、14巻の巻末漫画見る限りではマルシルだよね?いいよね?ね? …ということでマルシルがいる。死ぬほど苦労しつつもなんとかなることも明言されている。
マルシルはどうするんだろう。
死ぬほど苦労して作った国の行く末を1千年、孤独に見守るのだろうか。
果たして見守れるのか。シスルのように執着し過保護にならずにいられるか。
国も、おそらく多大な貢献をしたであろう彼女に依存せずにいられるか。
第二黄金郷の後継はどうなるんだろう? ファリンの子? 彼女は子どもが産めるのか?
とかなんとか、まあ色々妄想たくましくなってしまう。大好きな作品なのでしょうがない。
彼らの人生がどうなるかはわからないが、最終巻の「モンスターよもやま話14」でライオスの王としての自覚の芽生え方はとても良かった。自然だし、1巻からするとあまりにもライオスらしくなくて、成長と変化がとても良くわかる。
ライオスは絶対王様には向いていないが、そもそも王様というのは向いているからなるものではなく、なるからなるのだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
