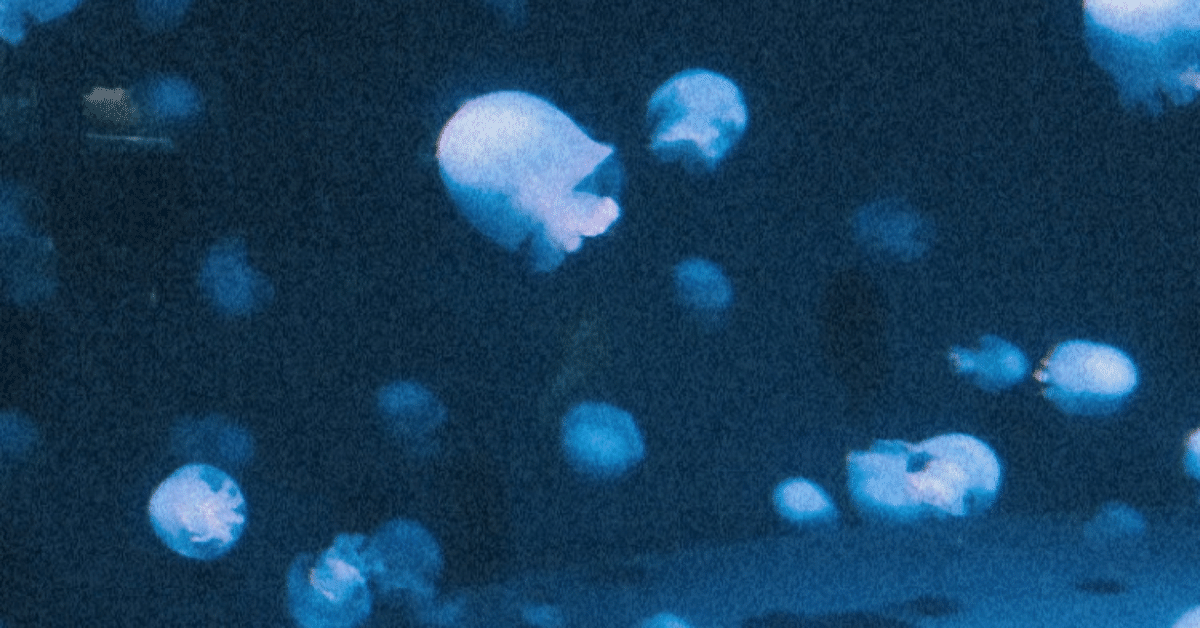
透明少女
わたしの記憶の中にどうしても頭から離れない少女がいる。わたし自身幼かった頃の記憶だから、彼女のことは少女、と呼ぶのが自然なのだけれど、どうしてもしっくり来ない。数個しか歳も離れないはずの彼女は、頭の中ではまだ小学生なのに、いつまで経っても、今のわたしよりもずっと大人びているように思う。
いつも夏の匂いがする公園に新しい匂いがした。懐かしいような気がしたけれど、それが何か分からなかった。白い絵の具で薄めて作った水色とピンクみたいな色の空が優しくてほっとする。
少女の名前は思い出せない、元よりあの頃から知らなかったのかもしれない。交わした言葉も記憶にある限り一つ二つしか無い。なんだかんだわたしは彼女のことが好きで、それは憧れのようなものだったのかもしれないけれど、気がつけばそばに寄っていた。なにか話すでもなく、彼女もそばに置いてくれた。
ある日彼女が履く短めの白い靴下に自分のと同じワンポイントを見た。嬉しくなって話しかけた、靴下同じのだね、彼女が振り返って笑った、その顔が優しくてほっとした。ふっと力を抜くような笑い方が本当に大好きだったのに、今になっては顔つきもよく思い出せないのだ。
靴下の話をしたのは、校舎の運動場にでる玄関から伸びた少し長めの階段の下。わたしは一輪車に乗っていて、彼女は多分あまり得意ではなかったから、右手を手すりに捕まって、左手で一輪車を支えていた、靴下に気づいてするすると近づいたわたしの言葉に、彼女は笑いかけたあと上手だね、と言った。それがすごく嬉しかった。
柔らかい風が吹いて、わたしたちふたり以外の全てが目の前から無くなったみたいだった。
一度だけ、一緒に下校した日が確かあった。彼女の家は同じ方向ではなくて、その日はおばさん家に行くんだと、わたしのいつもの通学路に彼女は居た。なにか話すわけでもなく、ただただ並んで歩くだけ、季節はよく覚えていないけれど夏服のブラウスから伸びた彼女の細い腕が、すごく白くて好きだった。あの頃のわたしの中の、素敵な女の子の全てが彼女だったのだ。
長くて黒い綺麗な髪を真似てみたかった、いつもしゃんとして綺麗なブラウスと伸びた背筋が眩しかった、彼女の履いていた靴下のワンポイントの花の名前はなんだったんだろう、欠片みたいな記憶だけでわたしの頭に棲みついているのだ、本当に顔も声も思い出せない、だけど確かに彼女は居て、今日もどこかで呼吸をして、わたしもおなじ世界にいて、それだけでいいと思ってしまう、数少ない小学生の頃の記憶に彼女だけが鮮明で、それでいて一番曖昧なのだ。
彼女がわたしの透明少女
わたしの世界で一番綺麗な人
どうかこれからも忘れませんように
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
