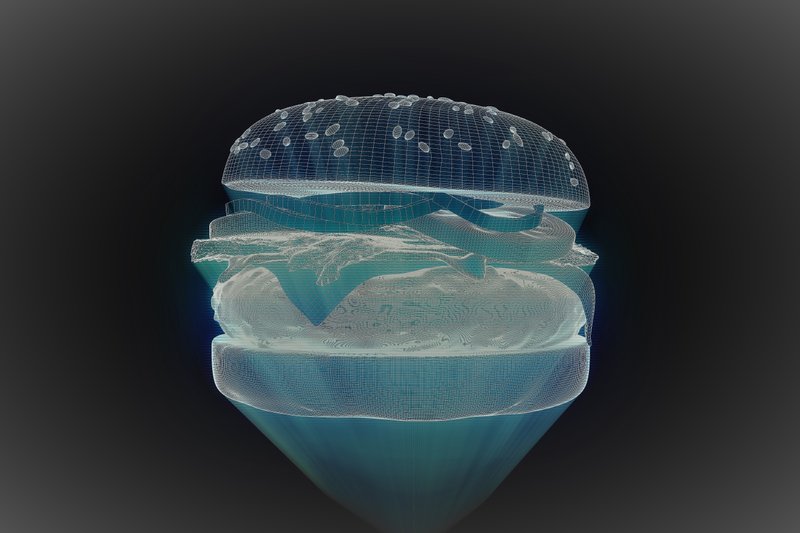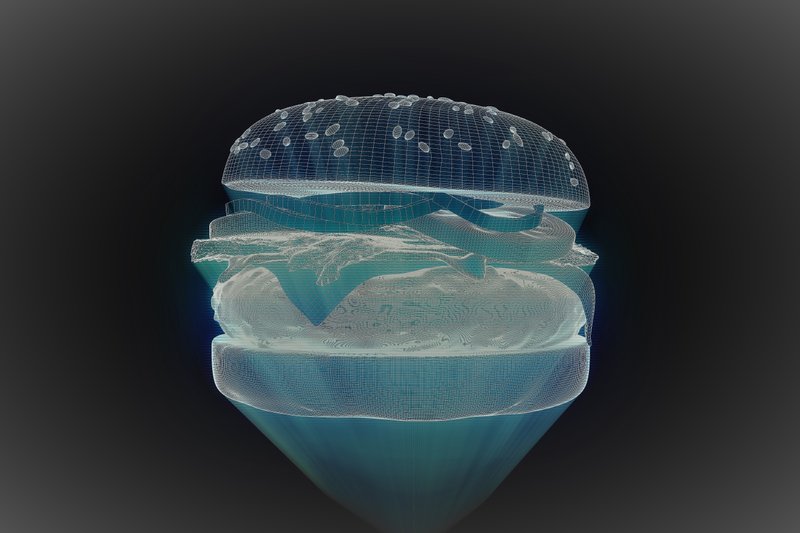「お菓子の家(Edible House)」には、未来がある。
「お菓子の家」と言えば、グリム童話「ヘンゼルとグレーテル※」に出てくる、魔女が住む家。子どもの、女子の、いやヘタをすれば、全人類にとっての"ドリームハウス"に違いない。
(※原文を読むとけっこう残酷なのだが、この際忘れよう。)
"お菓子の家"をググると、「家の形をしたお祝い用ケーキ」として、数多のメーカーやパティシエさんの手で商品化されているのが分かる。某有名レシピサイトでも、子どもと一緒に作って楽しむスイーツの題材として、沢山の投稿がある人気テーマだ……って、ちょっと待