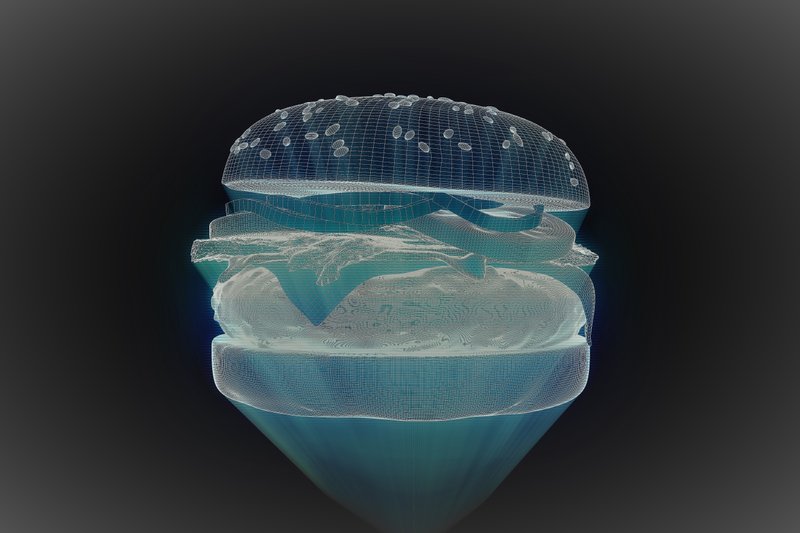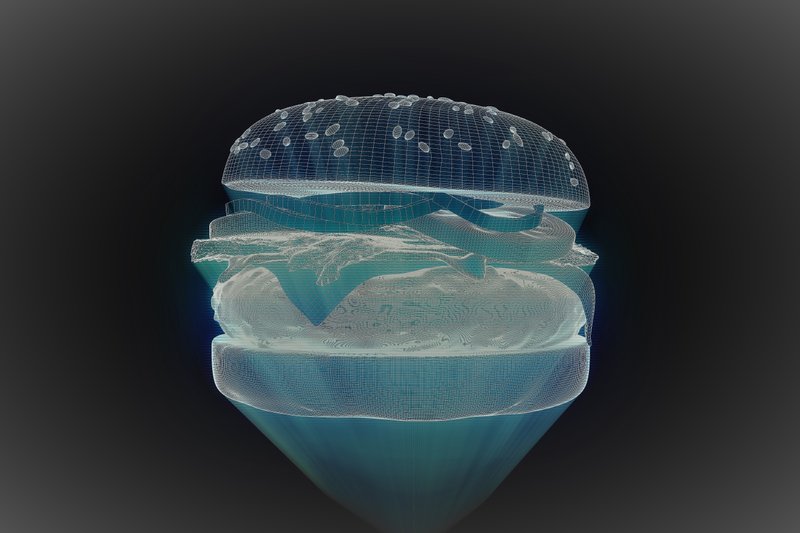フードロスに取り組む人が増えても、フードロスが解決しない理由。
最近、フードロスに取り組んでます!余った食材や規格外野菜を食べるイベントやります!という人が増えた。特に若い世代の取り組みとしては、気候変動マーチ(行進)、脱プラスチックに次いで、多いのではないだろうか。
日本に限って言えば、この動きは昨年くらいから急加速した。フードロスに取り組むベンチャーにVCの資金がつくくらい、まるで「成長分野」のような空気がある(成長しちゃイカンだろw)。
しかし、僕としては「なんで今ごろになって急に?」という感覚が拭えないのだ。
農水省が、ロス