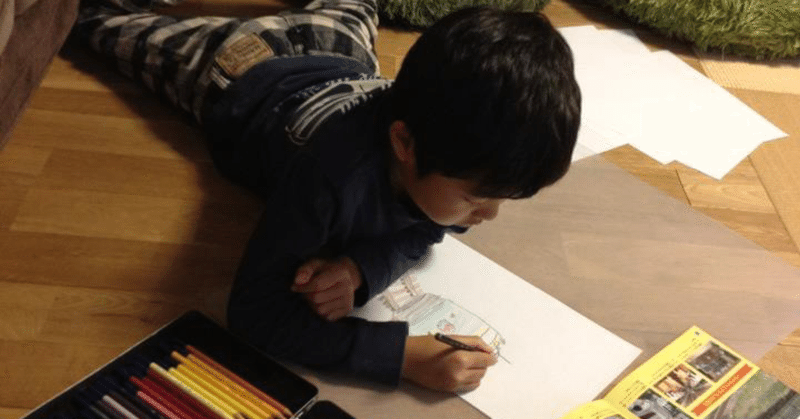
どんな子育てをしていましたか?
まだ私も16歳男子の母親なので
「していましたか?」と過去形で質問されると
いや、まだまだ現役やしなーと思うわけですが
私に「子育て」について質問してくれるのは
まだ「幼い」と言われる年齢から
小学生くらいの子の保護者(主にママ)なので
そのママたちがイメージしやすいように
具体的に「例」をあげて
話します
♦︎♦︎♦︎♦︎♦︎♦︎
先日、私が仕事から帰宅したら
その16歳息子がお寿司を握っていました。

鯛を漬けタレで味つけたもの。
鯛は柵で購入したそう。
漬けタレはもちろん自分で合わせたもの。
他には

昆布で締めた鯛もありました。
昆布締めをするのは久しぶりで
昆布も購入してきたそう。
この16歳息子
小学4年から6年くらいに
ものすごく料理、特に魚料理にのめり込み
ある時期は、連日、魚を捌いてお刺身を作っていました。
お時間ある方はこちらのブログも
ご覧ください。その息子が当時書いていた
ブログです。
小学生料理人マサトの料理日記
学校から戻って
近くのスーパーの鮮魚売り場に魚を見にいきます。
その頃、その魚売り場は魚の種類も多く、
鮮魚売り場の人たちも親切で、毎日魚を見にくる小学生に「オススメの魚」や料理法などを詳しく話してくれていたようです。
私はその頃、フルタイムの会社勤めをしていたので、息子の買い物に付き合うことは皆無でした。
スーパーで店員さんと話している様子は同級生のお母さんが目撃して私に知らせてくれていました。
息子自身からも「今日は、おまけに小さい魚をトレイに入れてラップし直してくれたんだよ」など、随分良くしてもらっていることがわかる話を聞いていました。
この頃は、毎日毎日、魚を捌いたり、柵を買ってきて刺身をしたり、貝の刺身に挑戦したりと、
私が帰宅すると、刺身やお寿司が出来上がっていました。
私の帰宅はだいたい夜の8時頃でしたので、下校後
5時間くらいは自由な時間のあった息子は、1人で魚料理に勤しんでいました。
リュックを背負って、魚を買いに
電車で小田原の魚屋に遠征したりも
してました。
その魚屋では「神経締め」を実際に
見せてもらったことも。
うちの息子、魚料理が好きで
刺身を作って私の帰宅を待っている。
という話をすると
「お手伝いしてくれるのーえらーい」
と良く言われました。
うちの息子は
脳みそキレッキレで手先も器用で
料理は技術だけでなくセンスもあり、
行動力もありました。
探究心があり、観察も得意。
すごく大人しい子で口数は少なかったですが
必要なことを感じ良く端的に伝えることができ
どこに行っても働く人の邪魔をしないわきまえがあり、
一方で、子どもらしい好奇心いっぱいの
つぶらな目をした
かわいらしい子でしたが
別に偉くはないです
単に好きなことを時間たっぷり使って
楽しんで極めていただけです。
あと
良く言われました。
「うちの子とは全然違う」
(うちの子は料理なんて全然しないとか手伝いをしないという意味の発言)
(または、手先の器用さなどの比較)
(うちはゲームばっかりしている、という発言も多い)
そりゃそーやろ。
今
うちの息子のハナシしてんねん。
なぜ私が嬉々と
息子が料理して楽しそうで、すごくて
天才で、ってハナシに
「うちの子は‥」って自分ちの子批判が
展開されるのか、私の思考回路では
起こり得ない現象です。
これを、ここまで読んで
「きっと私も、その人みたいに
わが子と比べた発言したりおちこんだり
しそう。下手したら嫉妬したり、さなえさんの
自慢話みたいに思えてしんどくなりそう。」
そんな風に感じている人も
いるでしょう。
私が、なぜ
絵本を使った「子育て」
子育てについて話す仕事を
しているか?
それは
私は、「ある部分」において
どうやら、人よりだいぶ得意な母親だと
気がついたからです。
「ある部分」とは
子どもはそもそも
自分で自分を成長させる力を持って
生まれてくる。
そう信じる能力が
人より優れていたようです。
私が良く使う言葉に
「ガチ」
というものがありますが
ガチ、マジ、ホンキ
で
子どもは自らを成長させる力がある。
と信じています。
みんな、だいたい
「信じてる」って言いますよね。
そりゃ。
でも、ガチ度には大きな違いがあります。
私は
この、親の
ガチ度
が、子どもの生きる力を
育てることに、大きく影響するという
自論(私の考え)を持ってます。
ガチ度が強くなればなるだけ
子育ては幸せです。
子育ての悩みは解決しませんし、問題も
なんだかんだ起こります。
個々対応は必要だし、人の手を借りたり
お世話になることもあります。
だけど、心の底から
「信じるもの」がある人間は
強いです。
強さを持ってこそ、優しさは生まれると
私は思っています。
だから、ガチ度の高い私は
自分の得意なことを活かす仕事を
したくて、今の仕事をしています。
ダンスが得意な人がダンスの勉強して、その得意を
活かして人に教える仕事したりしますよね?
それと一緒です。
子どもは自らを成長させる力を持っているということを信じるのが得意な人が、子育てについて勉強して
人に伝える仕事をしています。
信じることが得意でなく、それが子育ての苦悩になっている人がいれば、私の話を聞いてもらいたい。
聞いてみたら、何か気づきがあるでしょう。
親も子どもも唯一無二の存在なので、お教えすることは
ありませんが、学びの一つとして伝えることは
できます。
私に、私の「得意」を気づかせてくれたのは
私の息子です。
生まれてから、息子と共に過ごしている中で
その「得意」に気がつきました。
もう一つ
これまた、ガチで思っていたことがあります。
それは、
子どもは可愛がっていればいい。
可愛がりさえすればいい。
と思っていたことです。
でも別に、始終機嫌の良い母親でいる気など
さらさらありませんでした。
機嫌の良し悪しは
子どもにわかりやすいようにオモテに出していました。
叱らない子育てには魅力を感じませんでした。
だから、しっかりドスのきいた声で子どもには
叱ってきました。
ただ私が「叱る」必要がある、と感じる基準みたいなものは、人と比べると変わっていたかもしれません。
例を出すと、
テープやのりを使うときに
「もったいない!」と使い方に制限をする
よその人を初めて見たときに
「もったいないのは、そっちちゃうやろ」
と感じたことをハッキリと覚えています。
子どもは自らを成長させるために
今したいことをするので、
したいことができるだけできるように
親は子どもの望みを叶えていればいい。
あとは、やたらとわかりやすく
可愛がればいい。
自分の親としての能力を過信してないので
できるだけやればいい。と思っていたので
望みを叶えることを言いなりになっていると
感じたことはありません。
無理なら無理と子どもに言えば済むハナシです。
無理が通じなくて、号泣されたり暴れたり
したこともたくさんあります。
そんな子育てをしてきました。
私も息子も社会の一員ですから
生きていれば、自然と様々な制約や規制
制限があり、
しがらみの中にいます。
それらを打破してやろう!みたいな気負いはなく
生きているだけで我慢してることがあるのだから
それ以上に、親が子どもに
無用な我慢をさせる必要などないと考えていました。
感覚過敏で(3歳直前まで療育に通っていました)
疲れることが多いだろうと理解してたので
「頑張る」という概念は親の側から
子育てに持ち込みませんでした。
※「頑張る」も、子どもが自ら育てます。
魚料理の話に戻すと
料理するのに力を使い果たして
洗い物までできない息子に変わって
私がせっせと片付けをしました。
「料理したら片付けまで全部させないと!」
と鼻息荒く話してる人を見たことありますが
誰がそんなルール作ったんや?
と疑問でした。
料理した人
片付ける人
家族の中に誰かいれば良くないか?
もしくは食べたあと、誰も動く気にならなければ
洗い物すらしなくていい。
と私は思います。
私はそう思うので、私の子育ても
自然とそうなります。
私が息子のために身体を張ってやったことは
どれだけ連日、刺身が続いても
毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日
食べることです。
魚を買うお金はケチケチしませんでした。
魚を絵に描くことも好きだったので
絵を描くことができる紙類、画材、ケチりませんでした。
したいことに、親の出せるだけはお金を使いました。
うちは習い事や通信教材に出るお金がなかったので
「使い道」がどこか?だけの話だと思ってます。
料理に夢中になっていた小学生時代から
4年ほど経ち、
先日久しぶりにお寿司を握った息子が
食べさせたかった相手は
かわいい彼女ちゃん。
子どもは、成長するのです。
今になって思うのは
「可愛がる」ことに不足を感じない子育てをしていると
子どもが親から自力していく過程を
恐れることなく見守れる、ということです。
思春期以降
子どもの自立に、余計な不安を持ち
子どもに執着する親は、いつまでも子どもがかわいいから離れられないのではなく、
幼少期に可愛がることが足りていないから
足りてない分を親のエゴで不適切な時期に満たそうとしているのではないか?と私は分析しています。
話がわかりやすいように
息子の近況と、小学生時代の話を例にあげましたが
総じて私の子育てはこんな感じです。
・子どもは自らを成長させる力がある
・親は子どもをひたすら可愛がるだけでいい
・子どもの望むことをする
以上です。
2021.11.9
待ちよみ絵本講師 内田早苗
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
