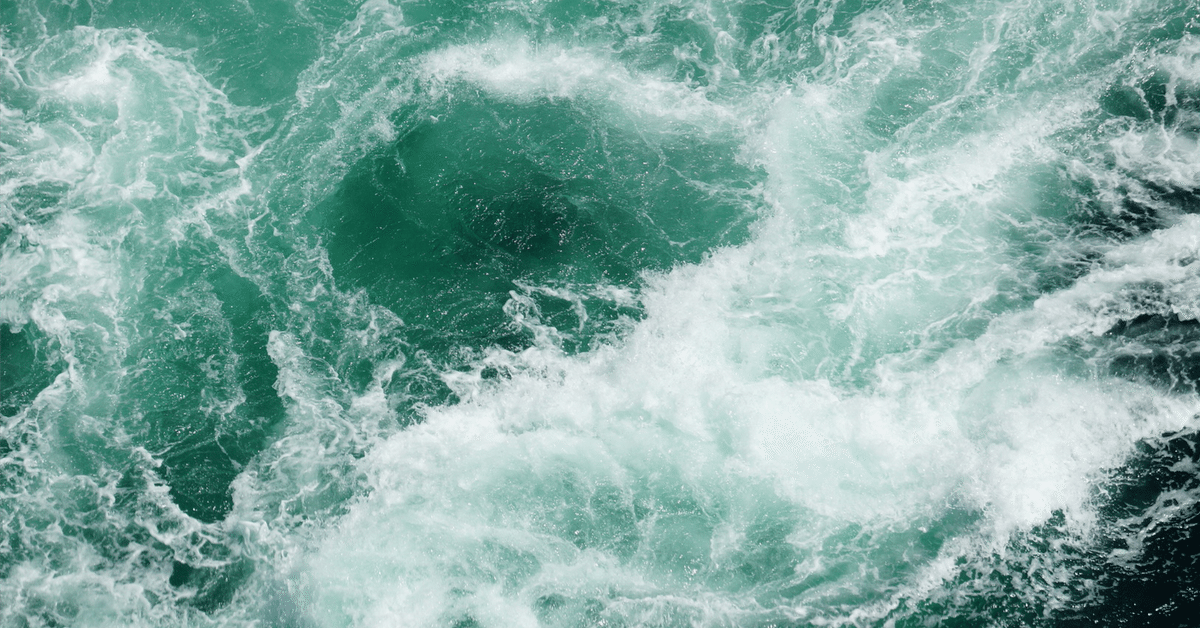
『義経記』におけ義経と鬼一法眼
近世以前の日本には、「剣術流派の開祖が天狗から兵法(剣術)を習った」という伝承が複数ありました。しかし、そうした伝承は江戸時代の知識人によって嫌悪され、それらの伝承が捏造であることを証明しようとする言説がしばしばありました。そうした江戸時代知識人の意見が本当に妥当なものなのかを確かめるために、義経の天狗伝説を中心に取り上げ、天狗伝説の生成と拡大の過程を検討したいと思います。
義経にまつわる伝説が広まった経緯については、古典文学研究の世界で成果が積み重ねられています。そこで、それらの成果を利用しつつ、古典文学において義経がどのように描かれてきたのかを検討し、それらが義経の天狗伝および剣術流派の開祖伝説にどのように影響を与えたのかを考えてみたいと思います。
前回は『義経記』における義経の僧正が谷詣での説話を取り上げました。今回は鬼一法眼説話を取り上げます。
日本の剣術の歴史を調べてみると、「京八流」という伝承が散見されます。京八流とは『本朝武芸小伝』巻六「吉岡拳法」に
或曰、吉岡者、鬼一法眼流、而京八流之末也。京八流者、鬼一門人鞍馬僧八人矣、謂之京八流也云云。
(或ひと曰く、吉岡は、鬼一法眼流にして、京八流の末なり。京八流は、鬼一が門人鞍馬僧八人あり、之を京八流と謂なりと云々。)
とあるように、「鬼一法眼」という人物の流れをくむ流派とされています。
そして、『兵術文稿』巻下「倭邦陳法伝来説」に
源義経住鞍馬寺之日、従鬼一之門人鞍馬寺僧、而習剣術於僧正谷、
(源義経鞍馬寺に住むの日、鬼一の門人鞍馬寺僧に従いて、剣術を僧正谷に習う)
とあるように、江戸時代初期において、義経は僧正が谷で鬼一法眼流の剣術を習ったという説が唱えられていました。
こうした「鬼一法眼伝説」の現存する最古の作品が『義経記』巻二「義経鬼一法眼が所へ御出の事」です。
自身が源氏の御曹司であることを知った義経は、奥州に下り藤原秀衡を頼ります。しかし奥州では特にすることもなく、無聊をかこっていました。そこで、「都にだにもあるならば、学問をもし、見たき事をも見るべきに、かくても叶ふまじ、都へ上らばや」(巻一「義経秀衡にはじめて対面の事」)と思い立ち、京に舞い戻りました。
当時、京の一条堀河に「鬼一法眼」という陰陽師法師が住んでいました。彼はある不思議な書を所持していました。
爰に代々の御門の御宝、天下に秘蔵せられたる十六巻の書有(り)。異朝にも我朝にも伝へし人一人として愚かなる事なり。異朝には大(太)公望これを読みて、八尺の壁に上り、天に上る徳を得たり。張良は一巻の書と名付(け)、是を読みて、三尺の竹にのぼりて、虚空を翔ける。樊噲是を伝へて甲冑をよろひ、弓箭を取つて、敵に向ひて怒れば、頭のかぶとの鉢を通す。本朝の武士には、坂上田村丸、これを読み伝へて、あくじ(悪事)の高丸を取り、藤原利仁これを読みて、赤頭の四郎将軍を取る。それより後は絶えて久しかりけるを、下野の住人相馬の小次郎将門これを読み伝へて、わが身のせいたんむしやなるによつて朝敵となる。されども天命をそむく者の、やゝもすれば世を保つ者すくなし。当国の住人田原藤太秀鄕は勅宣を先として将門を追討のために東国に下る。相馬の小二郎防ぎ戦ふといへ共(ども)、四年に味方滅びにけり。最後の時威力を修してこそ一張の弓に八の矢を矧げて、一度に是を放つに八人の敵をば射たりけり。それより後は又絶えて久しく読む人もなし。たゞいたづらに代々の帝の宝蔵に籠め置かれたりけるを、その比(ころ)一条堀河に陰陽師法師に鬼一法眼とて文武に道の達者あり。天下の御祈禱して有(り)けるが、これを給(賜)はりて秘蔵してぞ持ちたりける。
鬼一法眼が所持した書とは、「天下に秘蔵」された「十六巻の書」です。この書は本来「異朝」すなわち中国に所在していました。周の武王を助けた太公望や、漢の高祖劉邦の功業を支えた張良・樊噲は、この書を読むことで「八尺の壁に上り、天に上る」「三尺の竹にのぼりて、虚空を翔ける」「甲冑をよろひ、弓箭を取つて、敵に向ひて怒れば、頭のかぶとの鉢を通す」といった超人的な能力を身に着けました。後に、この書は「本朝」日本に伝わり、桓武天皇の忠臣として蝦夷討伐に活躍した坂上田村麻呂、盗賊退治等の逸話が伝わる藤原利仁、関東で「新皇」を称した平将門、そして平将門追討で功績を上げた藤原秀郷に読まれ、彼らの偉業の糧となりました。ここで挙げられている人名は、過去の代表的な英雄として中世の文学作品にしばしば登場する人々です。『義経記』「義経鬼一法眼が所へ御出の事」では、彼ら全員が「十六巻の書」を読み、この書を読んだことで類稀な能力を身に着けた、という設定になっています。
さて、この不思議な力を秘めた書は、秀郷以後読む者もなく、帝の宝蔵に代々秘蔵されていました。鬼一法眼は文武の道に通じており、「天下(殿下)」と称される為政者のために祈祷をし、その対価としてこの書を賜りました。
義経はこの書の話を聞きつけると、それを見ようと鬼一法眼の屋敷を訪問しました。義経と対面した鬼一法眼が用向きを問うと、義経は次のように回答しました。
誠が御坊は異朝の書、将門が伝へし六韜兵法といふ文、天上より給(賜)はりて秘蔵して持ち給ふとな。その文私ならぬものぞ。御坊持ちたればとて読知らずは、教へ伝へべき事もあるまじ。理を抂げてそれがしにその文見せ給へ。一日のうちに読みて、御辺にも知らせ教へて返さんぞ。
義経の回答から、鬼一法眼が所持する「十六巻の書」の名前が「六韜兵法」であると判明します。六韜兵法は私物化してよいものではないため、自分に貸してほしい、と義経が申し出ました。しかし、この申し出は鬼一法眼によって言下に拒否されてしまいます。そこで、義経は鬼一法眼の娘である幸寿と男女の仲になり、幸寿に六韜兵法を盗み出すよう頼み込みます。
幸寿を具して、父の秘蔵しける宝蔵に入(り)て、重々の巻物の中に鉄巻したる唐櫃に入(り)たる六韜兵法一巻の書を取出して奉る。御曹司悦び給ひて、引擴げて御覧じて、昼は終日に書き給ふ。夜は夜もすがらこれを服し給ひ、七月上旬の頃より是を読み始めて、十一月十日頃になりければ、十六巻を一字も残さず、覚えさせ給ひて
鬼一法眼の宝蔵から盗み出した六韜兵法を幸寿から受け取った義経は、昼間はそれを筆写し、夜はそれを学習しました。そうして七月上旬から学び始め、十一月十日頃に学び終えました。
以上が、義経の武芸の師とされる鬼一法眼が初めて登場する物語です。
『義経記』の描写を『平治物語』と比較すると、「義経が築地を飛び越える」という描写は古態本『平治物語』にも
追もはやく逃もはやく、築地・端板を躍越るも相違なし。
という風に語られています。しかし、古態本『平治物語』では義経がどのようにして人並み外れた身体能力を身に着けたのか語られていません。流布本『平治物語』では
夜は夜もすがら武芸を稽古せられたり。僧正が谷にて、天狗と夜な〳〵兵法を習ふと云々。されば早足、飛越、人間の業とは思へず。
と語られ、僧正が谷で天狗から兵法を習った結果とされています。
これらに対して、『義経記』では巻三「弁慶洛中にて人の太刀を奪ひ取る事」で
大国の穆王は六韜を読み、八尺の壁を踏んで天に上りしをこそ上古の不思議と思ひしに、末代といへ共(ども)九郎御曹子は六韜を読みて、九尺の築地を一飛びの中に宙より飛び返り給ふ。
と語るように、鬼一法眼が秘蔵する六韜兵法を読んだ結果であるとします。
この義経の超人的な武芸の由来を鬼一法眼に求める『義経記』の語りは、江戸時代に語られていた伝承と共通しています。しかし、その語られ方には後世のものとやや異なる点があります。
例えば、『本朝武芸小伝』巻六「吉岡拳法」には
或曰、吉岡者、鬼一法眼流、而京八流之末也。京八流者、鬼一門人鞍馬僧八人矣、
とあり、鬼一法眼の門人である八人の鞍馬寺の僧侶が京八流の源流であると語りますが、『義経記』では鬼一法眼と鞍馬寺の僧侶との間に何らの交流もありません。
また、『兵術文稿』で「鬼一」が会得したのは『三略』を中核とする「八陣法」であるのに対し、『義経記』で鬼一法眼が所持する秘伝の兵法書の書名は「六韜兵法」です。
さらに、武道・軍学に限らず、何らかの技芸を伝授する際には、一般的に「師弟の礼」というものが求められます。『新当流兵法書』「新当流手継の序次第」(『日本武道大系』第一巻「剣術(一)」所収)では、新当流の伝授に関して
縦雖荷千金、莫真実志、人努々不可授之
(たとえ千金を背負って来たとしても、真実の志が無ければ、絶対に授けてはならない)
という条件を付けており、「真実の志」は「千金」にも代えがたい貴重なものであるという価値観を示しています。
それに対して、『義経記』の義経は策を弄して鬼一法眼から兵法書を盗み取り、義経と鬼一法眼の仲は険悪なものになります。二人の関係性はお世辞にも師弟と呼べるようなものではなく、『新当流兵法書』が理想とするものとは大きく隔たっています。
以上の点から、『義経記』巻二「義経鬼一法眼が所へ御出の事」が「鬼一法眼伝説」を主題とする現存最古の作品であるものの、『義経記』における「陰陽師法師」鬼一法眼から武道伝書における「武道家」鬼一法眼に変化するためには、なおいくつかの段階を踏まなければならないと言えます。
参考文献
島津基久『義経伝説と文学』第一部「義経伝説」第二章「義経に関する諸伝説」第二節「牛若丸時代に属する伝説」
岡見正雄『義経記』日本古典文学大系、一九五九年、岩波書店。
栃木孝惟等校注『保元物語 平治物語 承久記』新日本古典文学体系、岩波書店、一九九二年。
八木直子「鬼一法眼譚の構造:「義経記」を中心に 」『甲南女子大学大学院論集』創刊号、甲南女子大学、二〇〇三年。
小井土守敏・滝沢みか『流布本平治物語 保元物語』武蔵野書院、二〇一九年。
