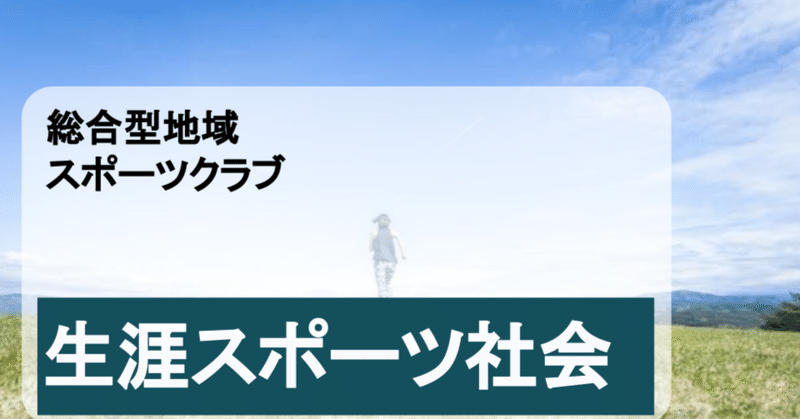
私が目指している生涯スポーツ社会の姿
どこまでいっても一番大事なのは、「スポーツは遊び」が本質だということ。
どうも、ふじみスポーツクラブの上杉健太(@kenta_u2)です。埼玉県富士見市で、誰もがいつまでも、自分に合ったスポーツを続けられる地域社会の実現を目指して、総合型地域スポーツクラブの運営をしています。
今日は、『私が目指している生涯スポーツ社会』というテーマでお話したいと思います。人生をかけてやっていく永遠のテーマ的なお話です。ここがブレると「あれ?俺は何を目指してたんだっけ?」となってしまうので、定期的に自分でも確認作業をしておくといいやつです。
1.引退がないスポーツ社会
では一つ目です。まずは『引退がないスポーツ社会』を挙げておきます。とにかく日本のスポーツライフには引退の文字が結構強めのポジションをとってしまっています。
学校スポーツの限界
まず私たちが出会う最初の『引退』は部活動からの引退ですよね。中学3年生、高校3年生、大学4年生などが、それぞれの学校を卒業して、部活を引退する。そして次の代が部の中心となっていく。みたいなやつですね。私も高校時代に経験しました。上級生が引退し、私が部長になりました。あの瞬間ですね。
この『引退』の何が嫌いかと言うと、その瞬間に引退した人から強制的にスポーツの場を奪ってしまうということです。もう試合に出られないからと言って、練習すらさせてもらえなくなる。もちろんそこには、受験勉強という大義名分が引退した側にもあったりするので、あまり文句が出ないような社会的仕組みになってしまっているのですが、中には受験勉強をしない引退者もいるわけで、彼らのスポーツをする場は明らかに不当に奪われ続けてきたわけです。私はこれを絶対になくしていきたい。
この問題の本質は何かというと、『試合に出られないのなら練習をする意味がない』という勝利至上主義あるいは競技志向優勢主義だと思います。多くの学生引退者は、大会出場資格を失うことで引退していきますから。その学校の生徒・学生である内は、本来的には部に所属する権利を有しているにも関わらず、です。
とすると、社会的に変えていかなければならないのは、エンジョイ志向や健康志向、コミュニティ志向といった、スポーツが本来持っている多様な志向・目的を認めていくことです。認めるというのは、競技志向と同レベルで扱うということです。試合に出られる”レギュラー”が有するスポーツをする権利と、試合には出ないメンバーが有するスポーツをする権利を、同等に扱うということです。これは人権の問題でもあります。
また、学校をステージにスポーツをやる以上、どうしても”引退的な瞬間”は現れてきてしまいます。そう、卒業というタイミングです。学校の所属が変われば、部活も変えなければならないというのが現実的。とすると、学校でスポーツをやる以上、卒業と同時に部活動を”引退する”というのはどうしても避けがたい。これこそが、学校スポーツの限界だと思っています。
私が「学校から地域へ」と言って、地域スポーツの振興に力を入れたいのは、こういう事情があるからなんです。地域をスポーツの中心にすれば、学校を卒業して新しい学校や会社に入ったからといって、その地域に住んでさえいれば変わらずにスポーツ活動を続けられるんです。これは、実際に私が大学生の頃に地域に立ち上げたフットサルクラブで実証済みです。地域でやっていれば、学校の卒業というイベントは、引退なんてものに直結しないんです。
プロスポーツの誤解
もう一つ、目立つ『引退』がスポーツ社会にはありますよね。それがプロスポーツ選手の引退だと思います。彼らの引退の意味は、「一線を退く」というもので、決してスポーツをやめるという意味ではないのですが、何となく野球選手が「引退する」というと、もう野球はやらないという意味に聞こえてしまったりしますよね。
でも本当は、ただただ「プロ野球選手をやめる」というだけであり、コーチとして野球をやったり、趣味で草野球をやったりするわけですよね。でもそんなところにいちいち世間は注目したりしませんから、プロスポーツ選手はまるでスポーツ自体をやめてしまったかのように見えるわけです。それが世間一般の『引退』のイメージとなり、「引退=スパッとやめる」みたいな誤解となっている側面も否定できないと思います。
本当は、そんなスパッとした線引きをする必要はなく、世界で戦う技術・体力がなくなったのなら、国内で戦えばいいし、国内のトップレベルで戦えなくなったなら地方で活躍すればいいし、それもできなくなったらエンジョイ志向や健康志向、コミュニティ志向に移行してもいい。とにかく、自分に合ったステージでスポーツ活動を続ければいいんです。最近のサッカー選手はそうなってきていますよね。すぐに引退せずに、レベルを落として活躍するステージを変えていって長く選手を続けています。
(※その背景に三浦知良選手の存在がいることはもう間違いないことです。モデルって大事ですね。)
たまに、『プロは勝たなければ意味がない』という主張に出会うことがありますが、それは完全に間違った認識だと私は思っています。『勝利』は、スポーツで人を楽しませる手段の一つでしかありません。ていうか、一人の選手・チームの勝利によって喜ぶ人もいれば、逆に悲しんだり憤ったり、実際的な損害を被る人もいるわけですから、社会的に見れば一人の選手や一つのチームの勝利と言うものには実はあまり価値はないんです。あなたが勝たなくても誰かは勝つ、という世界なので。
プロスポーツの本質はエンターテイメントであり、人を楽しませるということです。高い競技レベルはそれを実現しやすいということであり、それは勝敗を競うことで生まれやすいということです。ここを誤解すると、簡単に勝利至上主義に陥ります。人を楽しませるのがプロスポーツの本質なのだとしたら、難しい顔をしてプレーしていてはいけないんです。プレーヤーこそが最も楽しい顔をしなければ。
(※真剣さと楽しさは両立できる)
ちょっと話がぶれた気がしますが、要するに競技レベルが落ちたからって引退なんてしなくてもいいということです。それぞれのステージで続けるスポーツがあると言うことですね。プロ選手においても。
2.選択の自由があるスポーツ社会
次に挙げておきたい生涯スポーツ社会像は、『選択の自由がある』ということです。これはもう本当に大事で、結局はこれがないとどれだけそれぞれの団体などが頑張っても、生涯スポーツには繋がらないと思っています。一度選んだ道をずっと歩むか、それをやめる(引退する)か、みたいな選択しかできない人生なんて、苦しすぎるでしょう(;^_^A 苦しいものは基本的には続けられません。これは原則として受け止めなければなりません。
(※苦しみを乗り越えられる人はもちろんいますが、大半がそうではない。大半がそうではないものを、社会として採用するわけにはいかない)
種目の選択の自由
スポーツにおける選択といえば、まずは種目の選択が挙げられると思います。まずはここが豊富にあることが重要です。自分がやりたいと思える種目や、十分な環境が整った種目。とにかく身近にその種目を続けていける環境があることが必要ですね。
そして、そういう種目がいくつかあり、それを選択できる。いくらずっと続けていける種目があるといっても、それが例えばバレーボールの一択だとしたら、バレーボールが嫌になったり怪我などによって続けられなくなったら、もうスポーツを続けられなくなってしまいます。なので、いくつかの種目があり、それをいつでもどちらでも選べるという状況こそが重要です。
この問題を考える時に、種目間の対立構造がどうしても顔を覗かせてきます。各種目団体が、自分たちの種目の競技人口ばかりを考えると、プレーヤーの奪い合いという醜い(何とも醜い!)争いが勃発します。それは表面的には見えるものではないかもしれませんが、プレーヤーはそういうのを敏感に感じ取ります。例えば私が小学生の頃、野球をやっていた私は、同時にサッカーもやりたかった。ところが野球のコーチはサッカーをかなり敵視していました。同時にサッカーと野球をやっていた子が、明らかに不当に試合に出してもらえない状況を見た時に、私はサッカーをやることを諦める判断をしました。
こういうことが起こらないようにしたいわけです。私は。
どうしても組織は、その組織の利益を最大化しようとします。よそのクラブの利益の為に、自分のクラブの利益を削る判断なんて、なかなかできません。だからこそ私は、総合型地域スポーツクラブなのだと思っています。なるべく同じ組織として活動していく。そうすることで、同じ利益を共有できますし、コミュニケーション不足(誤解)による余計な対立構造なども生まれなくなります。
志向・競技レベルの選択の自由
さて、スポーツの選択においては、種目さえ自分の好きなものが選べればいいというわけではありません。それではまだまだ解像度が荒すぎます。この社会の多くの人が、自分に合っていない志向やレベルでのプレーを余儀なくされ、苦しんでいると思います。”レギュラー”になれずに試合に出られず、なんなら練習すらもまともに参加させてもらえないのに、その種目をやるにはそこに所属するしかない人が一体どれほどいるでしょう。これはもう悲劇でしかないですよね。その人のスポーツをする権利は一体どこへ行ってしまったのでしょう?
クラブに一つのチームにしかない場合に、このようなミスマッチを受け入れざるを得ない状況が生まれます。本当はそれほど勝ちにこだわっているわけではないのに、チームに才能あふれるたった一人のプレーヤーがいる為に、大人がそちらに引っ張られてしまって勝利を過剰に求めるようになってしまい、結果としてエンジョイ志向の人はそっちに合わせる羽目になる。このような状況はたくさんあると思います。そして20歳くらいまでの私は、完全にエンジョイ志向の人を競技志向に無理矢理引っ張り上げるような人間でした。ここの反省は猛烈に今でも持っています。
重要なのは自分に合った種目が選択できるだけでなく、志向・目的や技術や体力のレベルも合った環境でスポーツができることだと思います。その為にも、単一種目や単一志向だけで組織を作ってしまうと、どうしても組織の利益の最大化を図った結果、無理やりにでも組織に合わせさせるというやり方になりがち。強引に、「君は才能がある!今からやればプロにもなれるかもしれない!」と全員に言って強引に加入させる、みたいな(;^_^A
こういう無理矢理のミスマッチを生み出さない為にも、クラブ内に志向別・レベル別のチームなどの活動があることが大事なんです。競技志向をすすめるのも、エンジョイ志向をすすめるのも、どちらもクラブの利益の為になるのなら、普通はプレーヤーに合った方を提案できますよね。これぞWIN-WINだと、私はそう考えています。生涯スポーツ社会の実現には、この発想が絶対に必要です。無理矢理にでも3年間やらせればいいとかじゃないんです。ミスマッチの数年間によって、その後、一生スポーツをやらなくなる人が一体どれほどいることか。
(※燃え尽き症候群を含めて)
3.強制力のないスポーツ社会
さて、3つ目に挙げたいのが、『強制力がない』という社会像です。誤解を恐れずに言うと、「別にスポーツをやらなくてもいい」ということです。
私はスポーツの本質は『遊び』だと思っていて、『遊び』とはつまり、余白のこと。それがなくても生きていくのには困らないもの。でも、あったら楽しいもの。人生を豊かにさせてくれるもの。遊びとはそういうものだと思います。なくても別にいいもの。強制されないものだからこそ、スポーツは楽しい。私はそう思っています。
スポーツで遊び続ける
「スポーツは遊びだ」と言うと、たまに怒られます(;^_^A 「スポーツは真剣にやるものだ!遊びじゃない!」と主張されるかたが怒ってしまうことがあるんです。これはもう悲劇でしかないです。なぜなら私は何も、「スポーツは真剣にやるものではない」と言っているわけではないからです。むしろ、私はスポーツは真剣にやりたいです。真剣にやってこそ、本当の楽しさが現れてくると思っています。ただし、遊びです。そこはもう本質なので。問題は、一部の人が『遊び』というものを、『真剣』と対照的なものと捉えてしまっていることでしょう。きっと社会がそういう教育を私たちに行ってきたのだと思います。「遊んでないで勉強しなさい!」と言われたことが誰でもあるでしょうが、これが象徴的な言葉でしょう。
真剣さと遊びは両立します。プロスポーツ選手にとっては、ある意味ではスポーツはなくてはならないもので、仕事であり遊びではないということも言えますが、彼らはめちゃくちゃ真剣に遊んだことでスポーツをエンターテイメントに昇華させた存在です。自分が楽しいだけでなく、周りの人も楽しませるレベルに到達した。それがプロスポーツ選手というものの見方だと思います。やっていることはあくまでも遊びです。
(※実際に、世界中の人々が飢餓で苦しむ時代が来たとしたら、スポーツ選手だってスポーツどころではなくなるでしょう。畑を耕し、動物を狩り、食料の確保に必死になるでしょう。それがつまり、スポーツがあくまでも『遊び』の領域にいるということです)
スポーツは遊び。これが本質なのですから、競技志向もエンジョイ志向も健康志向もコミュニティ志向も、全て遊びです。遊びとしてのスポーツの範疇です。プロスポーツも遊びです。めちゃくちゃ高レベルで真剣に遊んでいる人たちのエンターテイメントを見せてくれています。ありがとうございます。
同じように、子どものスポーツもお年寄りのスポーツも、やはり本質は遊びです。それが結果的に心身の成長や健康維持などをもたらしますが、それはスポーツの持つ『運動』という一側面の話でしかありません。『運動』はスポーツが持つ大事な要素の一つですが、あくまでも一つの側面です。スポーツのどの側面を重視するかは、ライフステージで大きく変わっていくものでしょう。だから、そんなものはどうでもいいんです。どうでもいいというのは、どの側面を大事してもいいという意味です。とにかくコアな部分。スポーツは遊びというところだけ守っていれば、あとは何でもいいんです。とにかく人々が、死ぬまでずっとスポーツ遊び続けられる社会。私はそれを作りたいのです。遊びは強制されるべきでない。スポーツも同様です。
ということで今回は、私が目指している生涯スポーツ社会像についてお話ししました。言語化するたびに言い方は少しずつ変わっているかもしれませんが、基本的にはこれを総合型地域スポーツクラブの普及・発展によって体現しようとしているのが今の私です。もっと違う最適解が見つかったら、そちらに取り組む可能性だってあります。誰かの何かの参考にもなれば幸いです。
今回もお読みいただきありがとうございました!
ではまた!
ここから先は

総合型地域スポーツクラブ研究所
総合型地域スポーツクラブのマネジメントをしている著者が、東京から長野県喬木村(人口6000人)へ移住して悪戦苦闘した軌跡や、総合型地域スポ…
総合型地域スポーツのマネジメントを仕事としています。定期購読マガジンでは、総合型地域スポーツのマネジメントに関して突っ込んだ内容を毎日配信しています。ぜひご覧ください!https://note.com/kenta_manager/m/mf43d909efdb5
