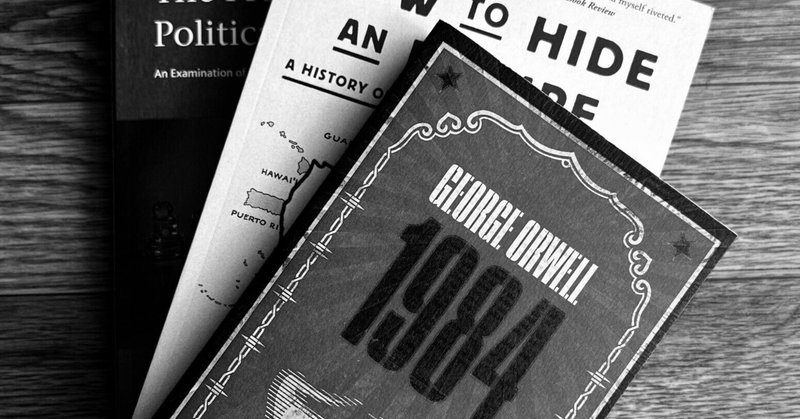
英文和訳って難しい:NYTの記事から
アメリカ音楽の歴史に残る偉大なシンガーである、サラ・ヴォーンについて、識者がお勧めの曲を紹介するというニューヨークタイムズの記事を読みました。
どうやら、ヴォーンにかぎらず、伝説級のミュージシャンについて、「5分でわかる」的なシリーズをNYTはやっているようです。ヴォーンの記事のなかに、以下のような文がありました。
Forget five minutes, all it might take is a second and a half of hearing her sing to make your spine tingle or your heart drop.
5分という縛りは忘れよう。彼女の歌を1秒半も聞けば、背筋がゾクゾクしたり、ドキッとしたりするでしょう。
私の日本語訳はかなり下手です。文法的にいえば、高校で学習する文法事項が複数入っています。まず、助動詞might(仮定法)を使うことによって断定を避けています。hearing以下の動名詞句はいわゆる知覚動詞ですので、VOCの形になりCには原形不定詞singがおかれています。さらに、to makeの不定詞句も、makeが使役動詞ですので、同様にVOCになっており、tingleもdropも原形不定詞です。さらに、このto不定詞は広義には結果用法の不定詞と解されます。文意をふまえた上で日本語の表現力を問うならば、大学受験のよい問題になりそうな一文です。
一方、単語的にはあまり難しくありません。ちょっといやなのがspineとtingleくらいでしょうか。spineは、ニール・セダカの記事でも話題にしました。「背骨・脊柱」の意味の名詞です。
tingleという動詞は、「(耳や手が)ちくちく痛む・(体が)ゾクゾクする」という意味です。drop one's heartは驚きを表す表現のようですが、調べたかぎりでは、わかりやすく確定した日本語訳が存在しないようなので、文脈をくんで訳すしかありません。ヴォーンの歌に心を動かされるという文脈ですが、これを日本語の母語話者にわかりやすく伝えるために、オノマトペを使いました。英文和訳の難しさを強く感じさせる英文です。
今読んでいる、今井むつみ・秋田喜美「言語の本質」が、まさにこのオノマトペを扱った本です。特設ページが作られるほど話題になっている本です。
この本の感想はまた後日書きたいと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
