
間合いがわからない
また不合格か・・・
40人が受信して30人が合格という結果だった。
合格率は75%。
4人の内3人が合格しているのだ。世間一般で言えばかなり緩い試験に属するだろう。今日は県内の四段審査だった。不合格となったのはたった10人だけ。残念ながら、私はその不合格だった10人に含まれている。
今回が初めてではない。
恥ずかしながら、2回目だ。
40年振りの昇段審査

私はアラカンの剣道愛好家。
とは言っても、ずっと剣道を続けているわけではない。小学生の時に始めた剣道は、大学卒業までウナギのように細く長く、ときには曲がりくねりながら続けてきた。
しかし、社会人になると思うように時間も取れず、なかなか稽古ができない状況が続く。また、就職と同時に地元を離れたこともあり、剣道のつながりも一切なくなってしまった。
剣道をやめたつもりはない。
しかし、仕事の都合もあったので、どこかの会や道場に所属ということもできなかった。たまに学生時代の友人に誘われて、稽古や大会に出る程度だ。年に1回、いや、2年に1回防具と竹刀を引っ張り出してくる。
気が付けば、そんな生活を40年近くも繰り返していた。
転機を迎えたのは約3年前。
コロナ禍の2020年だった。
地元にUターン就職したのを機に、剣道を再開した。と言っても、仕事の都合でなかなか稽古はできない。参加できるのは日曜日の夜、六段・七段のシニア世代が集まる稽古会だけだ。稽古は約1時間。その内の40分を基本稽古に充てている。
そんな中、先輩方に勧められて四段に挑戦することになった。実に40年振りの昇段審査だ。申し込み用紙も間違ってはいけないと思い、書く手が震えた。
四段がどの程度なのかわからない。しかし、
「まぁ、受かるだろう」
とは思っていた。周りの人はみんな六段・七段なのだ。四段なんてものは通過点に過ぎない。そんな風に考えていたが、それでも審査当日は極度の緊張から吐きそうになった。実際は前日の夜に吐いた。
ちょっと呑みすぎたみたいだ。
納得できない

残念ながら、初めての四段審査は不合格だった。それ程実力差を感じることはなかったので、たまたま落ちただけだろう。緊張しすぎたのが原因に違いない。いや、前日の体調管理が問題だったか。次に受ければ余裕で受かる。四段なんて、赤子の手をひねるくらいのものだ。
そんな風に楽観視していた。
しかし、2回目の挑戦となった今回も不合格だった。私は納得できなかった。何が悪いのかさっぱりわからない。
75%の合格率だ。年長者の私を合格させるべきではないのか。もしかすると、合格者は私の知らないところで金銭の授受をしてるのではないか!?などと本気で勘ぐってしまう。審査員一人10万円くらいずつ包めば合格できるのだろうか…
10万はちょっと高いな。1万円で何とか手を打ってもらおう。
折しも登録しているメルマガから四段不合格の話が流れてきた。居ても立っても居られないとはこのことか。気が付けば、私はそのメールに返信していた。「納得できません」と。
相談ではなく、ただの愚痴だ。わかったようなことを言うなと言ってやった。思いがけず、すぐに返信が届く。この人、暇なのか?と思いつつもちょっとワクワクしながらメールを開いた。
しかし、残念ながら期待していたような内容ではなかった。私は慰めの言葉が欲しかったのかもしれない。しかし、そんな雰囲気は微塵も感じられなかった。寧ろ逆だった。血も涙もない。いやもしかすると血は緑色なのではないかとさえ思えてくる。
返信の内容はこうだった。
四段の審査で合格率75%という点がそもそも納得できません。こちらの四段審査は合格率が40%程度です。少ないときには20%程度の時もあります。75%はユルユルです。
四段はそんなに甘いものではありません。
そういうものなのか!?
全国的に80%前後が当たり前だと思っていた。英検4級くらいの、誰でも合格できるレベルだと思っていただけに、衝撃を受けた。
自分が納得できないと思っていた部分が完全にズレていたのだ。この時の私は、できることなら、ドラえもんの四次元ポケットにこっそり逃げ込みたい気分だった。
剣道と向き合おう
ここで腐るのは簡単だ。腐ったミカンの中にこっそり紛れ込んでおけば良い。今こそ「俺たちは腐ったミカンじゃね~!」と叫ぶのだ。昇段審査なんて面白くないから受けるのをやめると言えば、それでラクになれる。
しかし、それでいいのか?
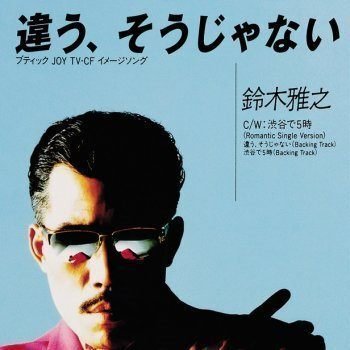
私は剣道が好きなのだ。
できることならミカンは熟した状態で収穫したい。
私はもう一度剣道と真剣に向き合うべきなのだ。
そもそも稽古時間が足りないのかもしれない。
稽古時間が圧倒的に少ない

愚痴メールに「週に1回しか稽古ができない」と書いたところ、丁寧な返信があった。それによると…
週3回以上の稽古:技術が向上する
週2回の稽古:現状維持
週1回の稽古:技術は下降傾向
ということだった。週1回しかできない私は完全にアウトだ。

しかも、貴重な1時間の稽古の内、40分が基本稽古に割かれている。もちろん基本稽古は重要だ。朝食に味噌汁をつけることと同じくらい重要なことだ。しかし、今は基本稽古よりも昇段審査につながる実践的な稽古がしたい。
地稽古も一般的な地稽古ではない。毎回、2分間の回り稽古を4回するだけで終わってしまうのだ。
相手の方は六段・七段で全員が60歳以上のシニアばかり。あなた方はそれで充分かもしれない。六段・七段でほぼ完成されている剣風だからだ。
しかし、私自身は稽古内容に物足りなさを感じていた。稽古1回1回に対する集中力が足りないと言われてしまえばそれまでだ。立合いを意識した稽古をすれば良いだけだとかもしれない。
でも、どうすることもできないのだ。周りは高段者ばかり。手も足も出ないことが多い。実際、ほとんどの稽古では何もできずに2分間が終わってしまうのだ。
やはり一人稽古で補うしかないのか……
しかし、一人稽古では相手との間合いや攻めを体得することは難しいだろう。だから、それ以外の部分だ。
一人稽古では基礎固めのつもりで取り組もう。ダイヤモンド以上にに固く。
間合いがわからない

現時点で、いくつか課題があるのは確かだ。まず、「間合い」。間合いがわからない。「間合いもわからないのに四段を受けるのか?」と言われそうだが、その通り。ぐうの音も出ない。
それでも合格できると思っていた自分の甘さにほとほと嫌気が差した。甘かった。甘すぎた。小岩井のカフェオレを3倍に濃縮したような甘さだった。
しかし、明確な課題が分かっていても、それを解決する方法がわからない。どうしたものか。
どうしても遠くから打ってしまう
間合いについて、何が良くないのか自分なりに分析してみた。
その結果、遠くから打ってしまうことが問題ではないかと考えた。特に昇段審査の立合いとなると、緊張しているのもあって、つい遠いところから無理に打ってしまうのだ。相手が怖いというのも多少ある。
一事が万事だ。
遠い間合いから打ったら出端を打たれ、精神的に凹む。その後は何とか挽回しなければと思って更に焦って遠いところから打つ。また応じられる。そうして、1回目の立合いは時間切れとなってしまった。
運命とは時に無慈悲である。2回目の立合いは相手が悪かった。何だか噛み合わないのだ。お互いに良いところなし。絶望的な気持ちになりながら立合いを終えた。還暦前になって初めて、人生は思い通りにいかないということを思い知らされるとは……
遠い間合いから焦って打つことによって、全く攻めというものも表現できていないのかもしれない。ということは、「間合い」と「攻め」は裏社会と表社会のように密接な関係があるということか。政治家とヤ〇ザを描いたサンクチュアリを思い出す。
攻めと打突はバラバラになってはいけない
間合いと攻めには関係があるところまでは何となく理解できた。つまり、遠い間合いから勢いよく竹刀を振りかぶっちゃ駄目ということだろう。幼稚園児にもわかるように言うならそういうことだと思う。
そう言えば、前に見た香田先生の動画で
「攻めて、打つのではなくて、攻めながら打たなければならない」
と解説されていた。遠くから打つということは、攻めと打突がバラバラになることなのか。何となくつながって来たかもしれない。
間合いを詰めてみるも…
次の稽古の時に、とにかく間合いを詰めることにしてみた。馬鹿正直に遠くから打つのはもうヤメだ。「正直者の頭に神宿る」らしいが、神宿るどころか髪も薄くなってきた。面を打たれ過ぎたのかもしれない。いや、打たれ過ぎるほど稽古はしていないような気もするが……
しかし、上手く行かない。間合いを詰めたところまでは良かったが、結局何もできずに打たれてしまった。
この前は「間合いに入って我慢しろ」って言われたからそうしたのに、今度は「待つな」って言われてしまった。真逆だよ、真逆。

サンド富澤さんもびっくりだろう。一見矛盾しているアドバイスだ。上手く両立できれば良いのかもしれないが、そんな簡単なことではない。『間合いに入り、攻めつつ打つ』である。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
