四教論:なぜ合気道の技法には「教」の字が使われているのか?
私が一般的にいわれる「合気系武術」なるものに出会ったのはちょうど30歳の今から9年ほど前、書店にてある大東流合気柔術のビデオを何の気なしに購入したのが最初である。

初めて見た「合気」の世界はまったく自分にとっては未知の世界で、それまでの空手等の武道経験にはなかった異質の武術に、これは事実なのかいわゆるただのヤラセなのか、まったく判断がつかなかった。
その大いなる疑問は、様々な情報を集めまわるという行動を私自身にうながすこととなった。
その結果、どうやら単なるヤラセでもないようだと判断した私は、まずは体験をということでいろんな道場を訪ねて歩き、最終的に関西の合気会系の道場に通うことにした。
しかし、道場に通ったからといって、最初から達人技のようなものにお目に掛かれるわけでもなく、まずは基本のようなものから老若男女に混じっての稽古からはじまった。
以前から私は宗教や思想の世界にも興味があり、特に古神道のものの考え方こそが新しい世界を作るのではないかと漠然と考えていた。
つまりこの世界の「終息的現状」を変えるためには何か別の考え方が必要であり、そしてそれは古神道(の考え方)なのではないか、と。
ちょうどその時期に開祖植芝盛平翁の合気道の理念と出会ったのである。
まさに私の探し求めていたものに巡り会った嬉しさから、より一層稽古と研究にのめり込んでいった。
しかし頭ばかりの知識は増えても、実際に身体でわかるなどということができるものではない。
そこで、勤めていた会社を辞め、時間の融通がきくアルバイトをしながらの稽古に明け暮れていたある日、突然に何かが開けた。
合気道に流れる法則性を肌で感じた
それからのことである。
それまで難しいと思っていた開祖のお言葉が次々に理解できるようになり、力ばかり必要だと感じていた合気道の技の数々も、全て一つの法則の上に成り立っているとの実感を抱くにいたったのは。
法則とは、つまり、宇宙は「陰陽」の二気により生じ、陰の中にも陰陽があり、陽の中にもまたさらに陰陽がある。この四つのものが基本になって互いに循環し、結び合いながら宇宙のあらゆる事象が生じている、ということである。

これは即ち、開祖のおっしゃられた「気流柔剛」であり「天火水地」ということであり、「知勇親愛」である。
この四つの調和をもって、宇宙の心である「愛」の、生成化育の営みは実現されているものである。

生を成し育て化する。プラスの面として創造と発展、マイナスの面として衰退と滅亡を表す。
生と死は一体である。ただし、通常はプラス面のみを意図することが多い。
そしてこの四つの陰陽の中心に立って調和を取ることが、「あめのうきはし」に立つべき人間の、宇宙の心と一体になった生き方であり、合気道とはその鍛錬の道ではないか。
従って、大宇宙の循環、生成化育の大法則(私はこれこそが合気道でいう「呼吸」だと思うのだが)に則して、合気道は行うべきではないか、と思い至るようになったのである。
この突然の「気づき」に、最初のうちはあれこれと疑いもし、いろいろな実験を試みて、理論を一つひとつ検証しながら慎重に進んできた。
そうして、どうやらこの方向性に間違いはないとの確信に至ったのであるが、それと同時に、私はそれまで住んでいた都会を離れることにした。
熱心に通っていた道場からも少し身を遠ざけ、合気道というものを自由なやり方でより深く研究しようと決意したのである。
そして4年半前に奈良県は吉野の地に移り住み、地元の基幹産業である山仕事に従事しながら、合気道研鑚の日々を過ごしてきた。
そしてようやく日々の暮らしも落ち着いた昨年より、合気道の私塾を開いて、地元の方々や友人、稽古仲間等を相手に私独自の合気道の指導を開始し、さらなる理論の整理を行いながら現在にいたっている。
何を重視して指導を行うか
合気道の指導にあたる者として、私はこれまで様々な道場を訪れ、いろんな指導者の方々にもお会いしてきた。また多くの技術指導書も研究してきた。
しかし常に感じてきたのは、修行者の多くに、本当の合気道というものがほとんど伝わっていないのではないかということである。
そしてそれは外見上の技術(型)を重視して、その中身をあまりにも疎かに、いや後回しにし過ぎているからではないかと思うのである。
どの道場でも基本技を中心に稽古を行っていることであろう。
しかしその基本技というものでさえ、各道場各指導者によってまちまちである。
道場によっては型の伝承を大切に考えているところ、型よりも流れを大切にしているところ、固い稽古を大事にするところもあれば柔らかい稽古を重要視して行うところもある。
時には道場に複数の指導者がいて、それぞれ違ったことを教えているようなところもある。
合気道の型とは何であるか?
植芝開祖は「合気道は型を守り型を破り、型を創造しなくてはならない」とおっしゃられたと聞いている。
型の稽古というものは外見上のかたちを真似るだけではなく、その中に流れる理を考えることであると私は理解している。
理を学ばない限り、かたちをいくら覚えても意味はないのである。
ものごとは何ごとも「最初が肝腎」である。
最初の段階で型の意味と合気道の「根本」たるものをしっかりと教えておかないから、多くの修行者が迷ってしまうのではないだろうか。
合気道というい「生き方」の実現
私は、合気道はある程度の段階までは、理合さえ学べば簡単だと常々言っているが、世間一般には、合気道の理合はむずかしいものとされている。
しかし理屈も判らないで稽古するのでは無駄も多く、むずかしいと思うのも当たり前ではないか。
また、やたら気や愛、和合といった単語を持ち出してきては、さらにわかりにくい、摩訶不思議なものにする傾向もある。
まずは目に見える形、感じられる形、物理的に当たり前な常識の形で学ぶべきである。そういうことを頭でしっかり理解しないで、いくら肉体の習練を行っても成果はなかなか上がらない。
指導者自身も「むずかしい」と言う(あるいは本人も理解できていないことを教えようとしている)ものだから、いつまでたっても「勘違い」が続く。
まずは簡単なように考え、簡単なレベルから始める、というのが教育というものの正しい順序であり、そうするのが指導者の務めである。
一教、二教の「教」の字の意味
この度、私の合気道研究の一端をここに紹介するが、これは私の全くの私論であることを先にお断りしておく。
合気道の技は数限りなく存在する。いくつかの基本技の名が広く知られてはいるが、自由技になると名もないようなものはいくらでもある。
しかしそうした技も、実は一教から四教の応用に過ぎない。
先代の吉祥丸道主も「合気道は一教から四教で十分」と何かに書いておられたし、開祖盛平翁は「三教までは準備運動、合気道はそれから」とおっしゃったと聞いたこともある。(1)
こうしたことを考えあわせると、一教~四教について、一教は「腕抑え」、二教が「小手回し」、三教は「小手捻り」、四教は「手首抑え」と説明するのは、初心者に形を教えるために便宜上行われてきたもの過ぎず、(一教~四教それぞれの技の)形の中から、そこに含まれる「教え=理合」を学んでいく、というのが合気道本来のあり方ではないか、と私は思うのである。(2)

つまり、一教から四教というのは単なる技の名称ではなく、読んで字のごとく、「(1~4の)教え」であるというのが私の考え(「四教論」)である。
四教の概論
四教論に至るまでに、私はまず一教と二教とは相反する関係、表と裏の関係にあると考えた(これは四教をよりよく理解することにも繋がってゆく)。
この世の中というのは、すべて表と裏というような相反する事物が、実は密接につながり絡み合い、ひとつになって成り立っている。
そして現実には、それらは表裏一体となって、あるいは絶え間なく入れ替わりながら、その姿を現わすものである。
だとするならば合気道の「技」について、同じように考えてみたらどうなるであろう。
このように考えて私は、一教と二教は同時に働いて初めて効力を持つものであり、それが三教という状態であるという考えに至ったのである。
しかし、最初から相反することを同時に認識することは困難である。
だから、初めはそれぞれ分けて考え、双方をよく理解した上で初めて同時に使えるようになる。
また、そのようなひとつひとつの理屈を理解していくためには、「型」による稽古という形態をとる必要がある。
合気道が型稽古の形態を守るのはそういう理由であると私は考えている。
一教とは自分を中心とした「円の確立」
それでは、これから具体的な説明に入っていきたい。
まず一教について。
一教とは自分を中心とした「円の確立」ということ。
自分の力の範囲を認識する。そしてその中に相手を入れないという形で学ぶ稽古である。
剣で言えば「正面打ち」。

捕りは相手の攻撃を防ぎつつ振り上げ、前に出ながら相手の中に食い込もうとする。
交差取り一教押さえ

受けは自分を守りつつ相手の中に入ろうと受けを取る。捕りはそれを防ぎつつさらに食い込む。

この攻防によって自己の中心からの力、また相手の中心からの力を認識し合う。
(象徴的な腕の形といえるのだが)円相を保ちながら掌(てのひら)は相手の方に向けて、相手を「制する」。

私の一教の稽古では、単に押さえ込みだけではなく、入身投げや四方投げ、小手返しなど、あらゆる技において一教の理合ということを学ぶので、形そのものよりもその意味ということを感じていただきたい。
これは二教以下も同様である。
二教とは「相手との融合を図る」稽古
次に二教。
一教で互いに認識し合うことを学んだら、次は「相手との融合を図る」稽古となる。
これが二教だ。
一教で相手とのつながりを知って、二教で相手と一体になるのである。
二教とは自己の中心と相手の中心を重ね合わせ、互いの力の円が重なり合っている形である。
そこにはすでに力の衝突はなくなっている。
剣で言えば「横面打ち」。
自分の横面打ちは単に相手のこめかみあたりを打つのではなく、相手の斜め後方死角に食い込んで密着し、相手の首を掻き斬るところまで入る動きである。

相手と一体となり、自他の区別がなくなるということは、どちらかが死んでいるということとも言える。
実戦を考えるのであれば、そういうふうに考えるほうがよい。
交差取り二教押さえ

腕の形としては一教と同じく円相ではあるが、掌の向きは自分のほうを向いている。
ものを「抱える」形である。
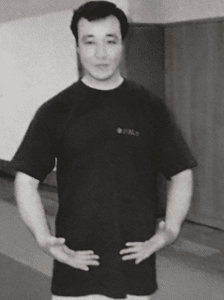
一般的に行われる一教、二教は体術による抑え込みで、特に二教は相手の手を鉤型に極めての技として知られている。

しかし別にそうして痛みでもって技を行うことなしに、一瞬にして相手を地に這わせることができる人はたくさんいる。
正しく二教の流れに入ったならば、簡単にできるということなのである。

一教と二教についてもう少しわかりやすい例をあげるとすれば、一教は相手の首筋に後ろから、二教は首筋に前から剣を当てている状態といえる。
一教

二教

つまり一教は表、二教は裏、あるいは一教が活、二教が殺という言い方もできよう。
三教とは、「一教と二教を同時に行う」稽古
このような一教と二教の違いをしっかり踏まえた上で、三教を学ぶ。
三教とは、いわば「一教と二教を同時に行う」ものである。
一方で相手の侵入を防ぎ、一方で相手が逃げるのを防ぐ。
生かしながら殺すということでもある。

また、「遠心力」と「求心力」の関係とも言える。
遠心力は一教、つなぎ留めておく力である求心力は二教、このふたつの力が同時に働くから、ものは中心の周りを回り続けることができる。

右側: 二教の理合による小手返し。相手の身体が力の範囲内に取り込まれている。
技においても三教の力がなければ実際は有効でない。
前述の通り世の中は本来、表裏活殺一体であるから、(三教とは)相手の中心に深く突き刺すように当てにいく、剣でいえば「突き」に相当するものと私はとらえている。
交差取り三教押さえ

腕の形は円相であり、掌は片方が相手を向きもう片方が自分の方を向く。
相手を「制しながら」と「抱えながら」が同時である。

一教の稽古は相手がやる気にならなければ成り立たないし、二教の稽古は相手が無理な抵抗をすると正しい理は学べない。
だからこそ、(合気道特有の)捕りと受けが協力しての型稽古が必要とされているのではないかと考えている。
四教とは「力のほとばしり」
さて、最後の四教についてだが、三教で相手とつながり一体となってはじめて、力というものは相手にストレートに伝わる。
その「力のほとばしり」が四教であると考えている。
剣における本当の斬り、本当の突きであり、「トドメ」の一撃、相手の息の根を止めるものである。
三教までは、ただ相手に当てているだけ。
ただいつでもやれる状態にもっていくだけのもの。
本当の力は、四教ではじめて伝わるのである。

ただし、ある程度のレベルの方は一教や二教をするにしても、三教あるいは四教を使った技を掛けている。
それはそれでよいのであるが、それを自覚してやっている人は非常に少ない。
だから初心者や下級のものに対しても、わかるかたちでそれを教えることがない。
だから合気道はむずかしいと言われるのである。
まずは、一教から四教の教えをきっちりと認識しなければならない。
三教の結びの状態からの技が本物の合気道の技である。
もう一度開祖の「三教までは準備運動、合気道はそれから」という言葉を、深く考える必要があるのではないだろうか。
文・元 龍貴
参考文献
斉藤守弘『新装版 武産合気道 第1巻 基本技術編』
「三教までは準備運動である。合気道はそれからである」という開祖の言葉が紹介されている。
(2)植芝吉祥丸『合気道』復刻版
合気道の基本技の紹介として一教「腕抑え」、二教「小手回し」、三教「小手捻り」、四教「手首抑え」の記述がある。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
