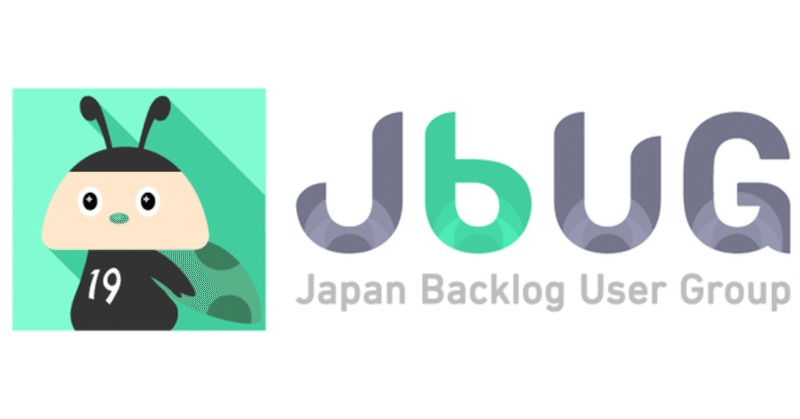
JBUG静岡 #1「プロジェクト管理を学ぼう!」イベントレポート
さすらいのコミュニティ用務員のおじさん、フクイです。
2020年9月17日(土)19時からオンラインで開催されたJBUG静岡さんの勉強会「プロジェクト管理を学ぼう!」に参加させていただいたので、思い切って巷で最近はやっているイラレコ・グラレコ風味でイベント・レポートを書かせていただきました。
1.JBUG静岡について
JBUG(Japan Backlog User Group)とは福岡の会社ヌーラボさんがSaaSとして提供しているプロジェクト管理サービス「Backlog」のユーザーコミュニティです。このコミュニティで取り扱うテーマはサービスとしてのBacklogだけではなく、あまり扱われることが少ないプロジェクト管理も範囲にしています。そのため参加者もBacklogユーザー以外の方もたくさん参加しておりConnpassの登録者も2000人に迫るほどのオープンなコミュニティです。支部も札幌から沖縄まで数多くありイベントもすでに70回近く行われております。
JBUG静岡は昨年末に準備会#0が開催された新しい支部で、今回が正式な第一回となるイベントでした。昨年12月日の土曜日昼に浜松市のはままつトライアルオフィスにて予備開催#0が実施され、さあ第一回!といったところで多くのコミュニティがそうであったように今年に入ってからのコロナウィルス流行の影響でなかなか開催ずることができなかったようですが、ついにオンラインという形で実施されることになりました。コロナウィルスは怖いですが、こういった地方のイベントに気軽に参加できるようになったというのは、いいことですね。実際に50人を超える今回の参加者の中にはたくさんの静岡以外の地区から参加された方がたくさんいた事と思います。そういう私もその一人ですが・・・・

当日の参加はグラレコに挑戦しようと少し早めに接続して準備することにしました。
2.オープニング
いよいよ19時になり、イベント開催になりました。オープニングのスピーチはJBUG静岡運営の栗原さんです。

オープニングの説明では、JBUGについての説明から、JBUGはBacklogを使用した仕事のやり方、プロジェクト管理について。そして実体験の共有を目的として活動をしているという話からはじまり、今年残念ながら2月のリアルイベントがコロナの影響で中止になりましたがオンラインで開催され600人以上が参加したBacklogWorld2020の紹介などがされていました。そして昨年誕生し、今回の第一回開催までにまつわるお話などを説明されていました。こういった丁寧なコミュニティの説明ははじめて参加する人にとっては大事ですよね。
3.中西さん:Backlogに自動翻訳機能を付けてみた!

最初のLT登壇は中西さん。仕事ではWindowsアプリの開発をされていて、最近はKintoneのお仕事も多いようです。趣味ではNoCodeに取り組んでいるとのことです。JBUGへの登壇は昨年のJBUG静岡#0とオンライン開催のJBUG大阪#4に続いて三回目とのことです。
今回の発表テーマはなんと「自動翻訳」です。昨年のJBUG静岡#0の時の栗原さんの発表にあったオフショア開発対策に関するLTからヒントを受けて、個人で開発されたとのことです。仕組み的にはGoogle TranslateをIntegromatで自動化しBacklog上で動かすというもの。Backlog上で行われる会話を自動で言語判定し、対する言語2つに翻訳してBotが表示するというもの。たとえば日本語で書きこめば中国語と英語に、中国語で書き込めば日本語と英語に翻訳されます。なんか最初からプロジェクト管理を飛び越してAIとか自動化とかという世界に突入しています!しかもこれをNoCodeで実現し、しかも運用コストが月1000円以下というから、世の中すごくなったもんだとオジサンとしてはおどろく限りです。今回使用したIntegromatという自動化ツールはフローチャートを理解できればNoCodeでも使えるとのことです。
3.nさん:数千人からの問い合わせを15人で捌くために出来ること

二番手はnさん。浜松生まれ浜松育ち、今は新宿にある会社に勤めてますがコロナ禍のリモートワークで今は浜松で働かれているということです。インフラエンジニアとサービスデスクを経験し今はRPAとかDXのコンサルを仕事にしている方です。この方も趣味はNoCodeでPlay(No)Codeというコミュニティをされているそうです。
今日の発表はそのサービスデスク時代の経験をもとにしたお話です。当時は社内ヘルプデスクで4500人のユーザに対して15人で対応していたそうで1人・1日当たり70件くらい対応したようです。数を聞いただけで疲れそうです。サービスデスクだからいろんな辛いこともあったようで、お願い事は「人にやさしく」です。みなさんもサービスデスクに電話するときには敬意と感謝をもって対応してくださいね。
本題です。もともとこの沢山の問い合わせをこなすためにはアサインのスキルとか状態の把握とかが人用なのですが、これを何とかするためにはEXCELでは無理でやはりBackLogのようなチケットツールの活用が大事という事です。この時はサービスデスクを1つのプロジェクトとして扱ってBackぉgを利用したようです。ツールを使う事で状況や情報が共有されるようになり効率よく対応できるようになるのですが、やはり新しいツールになかなか手を出さない人もいて、そういった人に丁寧に対応して定着されたお話なんかが印象的でした。
4.Shimizuさん:スモールチームの或る一個人のプロジェクト管理(仮)

三番手のShimizuさんは埼玉の会社にリモートワークで働いているデザイナーとマークアップエンジニアの方、デザイナーだけあってプレゼン資料がかっこいいですね。会社は8人という小規模なのですが90近くのプロジェクトがあり、それそれのメンバーが数多くのプロジェクトを同志にこなしているというのが仕事の特徴です。様々なビジネスをディレクターとデザイナー、そしてエンジニアやライターが協働で進めていくからプロジェクトの管理も大変そうです。
発表で一番勉強になったのは、プロジェクトの細分化が必ずしも効率化につながらないこと。Shimizuさんの会社ではたくさんのプロジェクトをそれぞれ1プロジェクトとして管理していたのですが、それではたくさんのプロジェクトを抱えているため検索性がものすごく悪くなってしまい、対策として登録ルールを定めたうえで一本化したそうです。登録ルールは「接頭辞をつける」「件名を簡潔にする」「重要度の明確化」です。実際の画面も見せていただきましたがすっきりとうまく纏まっていて必要な情報が探しさすそうでした。
5.大石さん:とある会社のBacklog使用砲(初級編)

最後は大石さん。登壇テーマに「砲」という文字があるのは「とある科学の超電磁砲」がらみだそうです。30年越えの大ベテランですがこのへんに人柄がにじんでいます。
大石さんの会社ではとにかくBacklogを使い倒していて、プロジェクト管理ツールやインシデント管理ツールとしてだけでなく、ワークフローや社内の様々な情報を取り扱うプラットフォームとしてBacklogを活用しています。まるでKintoneとかSalesforceとかみたいな使われ方です。登録されているプロジェクト数もすでに1500を超えているとのことです。たしかにここまで徹底的に使えば情報も一元化され、いろんな仕事がスムーズに進みそうな感じです。ただここまで情報が多くなると放置されたりする情報も増え情報漏洩など様々な問題も発生します。それをAPIを使用してマスタ連携したり、プログラムを使って自動チェックをしたりして工夫しているとのことでした。
6.クロージング

クロージングは最後のLTを発表した大石さんが続けて
今日の総括はとにかくバラエティに富んだ発表だったこと、たしかに4つのLTでしたが、自動化とか、利用方法の工夫とかいろいろな内容だったので10回くらいのLTを聞いた感じでした。登壇したみなさん、運営の皆さんお疲れさまでした、そしてありがとうございました。
JBUG静岡では第2回、第3回も続けていくとのことなので次回も楽しみです。
ちなみに以下も開催されます
10月8日(木)JBUG東京#18
10月11日(土)JBUG広島#6
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
