
【イベントメモ】配信実践者が語るオンラインコミュニケーションで双方向性を高める極意〜DevRel/Japan CONFERENCE 2022から
2022年8月5日(金)〜6(土)にDevRel/Japan CONFERENCE 2022がオンライン/オフライン並行で開催されました。昨年もコミュニティやマーケティングに関する多くの知見をを与えていただいたこのイベント。今年もまた個人的に気になったセッションについて紹介してみたいと思います。
DevRelとは?
本題に入る前に少しDevRelというものについて説明します。
DevRelとはDeveloper Relations(デベロッパーリレーションズ)の略で、IT製品やサービスのマーケティング活動の一環として、製品やサービスの情報をそれらを使用する開発者に届けるための活動で、ブログやSNSの発信やコミュニティの形成など様々な活動を行っていくことです。
これらDevRelに関わるマーケター、エバンジェリスト、エンジニアなどのコミュニティのひとつがDevRel Japanであり、その大規模なカンファレンスがDevRel/Japan CONFERENCEです。
<カンファレンスの動画です>
パネリストの紹介
新藤洋介さん(モデレーター)
・天神放送局、
・8月からアトラシアンのコミュニティ・マーケティングマネージャー
ざっきーさん
・野良Hack、IoTLT放送部
・普段は通信会社のインフラエンジニア
・配信活動はプライベートで行っている
・コミュニティ活動に参加したのは2017年くらいから
・2018年にLTは一回限りなのでもったいないと配信に取り組む
<「いいね!」の見える化>

・Node-REDのダッシュボード機能を利用して作成
・ボタンを押すという非常にハードルが低いアクションで共有できる
・Twitterのように見えなくならない、イベント中は残る
<参加者の共感を効果音で再生>
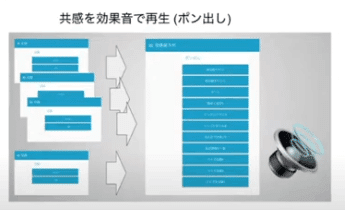
・共感を音声で表現する。拍手や賑やかしで場の雰囲気を音で共感する
・ポン出し(TVなどで行われる効果音)
清水優吾さん
・PowerBIのレクチャーやコンサル(Microsoft MVP for Data Platform)
・Youtyubeのチャンネル「PowerBI勉強会」
・仕事でのビデオ共有、配信双方ともの知見
<2拠点生活>

・横浜の自宅(1年間くらいをかけて構築)
・山口県の自宅(2つの環境を容易、マイクによって使い分ける)
ツールとマイクの相性がある
宮原徹さん
・株式会社びぎねっと社長兼CEO
・「オープンソースカンファレンス」をフルオンライン化
Zoom+YoutubeLIVEの組み合わせ
・OSCをほぼ毎月、各地域が順にホストを担当する
リアル開催にいつでも戻れるようにする
・申込みはシンプルにConnpassに集約
・YoutubeはLIVE+アーカイブ
・Slidoを使って質疑応答の双方向感を演出
最初は質問でないがフィーバー状態になることも
それをどう越させるか?主催側で呼び水的な質問をすることもある

ディスカッション

フィーバー状態になるのに地域性があるか?
宮原さん:地域性はすごくある。コミュニティの参加者や、コアの人たちの性質で雰囲気が決まる。例えば北海道はイベントが少ない地域なのかイベントがお祭という意識が高く、双方向を求めるZoom参加者が半分近くいる。集まりやオーディエンスの雰囲気次第で双方向性が大きく変わるのでそこの見極めが大事、温まらない人を煽っても無駄な努力。乾杯からスタート 雰囲気をつくる。
ざっきーさん:OSCに参加させてもらいましたが、ご当地の名物を用意するなど始まる前から下ごしらえが始まっている事を感じた
2拠点の使い分けは?
清水さん:2拠点作っている理由はごく家族的な理由です。移住ではなくて2拠点生活。月の75%は山口、月初めは横浜と決めている。
新藤さん:自分がどこに居てもやることは変わらないということですね
清水さん:そうです、最近言ういわゆるロケーションフリーです。どこに居ても同じクオリティを保てるようにほぼほぼ同じ構成を作っている。相手に自分がどこにいるかを意識させない。
双方向性のコミュニケーションで気をつけていること
清水さん:会話していない聞いているお二方(ざっきーさん、みやはらさん)が頷いているのが素晴らしいと思いました。カメラをを切ってしまうのは参加していないのと同じ。自分は必ずカメラにしてリアクションをしているが、参加者の皆さんにカメラオンにしてもらうようにするのはけっこう難しい。
リアクションしてもらうために質問を最初にやるようにしている。例えば「お昼食べた人はGoodボタン」のようにするとリアクションをとってくれる。そのあとは「この場はリアクション取っていいんだ」と認知される。
雰囲気作りが大事だと思う。絶対「返さないといけない」と思ってくれる聞き方を考えている。
新藤さん:参加する側にも意識改革が必要ということですかね?
清水さん:強要はできないので、なんとなくそういう雰囲気に持っていくとか、「参加したほうが楽しいよ」「リアクションするということが参加するということだよ」みたいなのをどう持っていこうかというのを毎回考える。
新藤さん:リアクションをお願いするというのは世代とかパーソナリティの問題があるので主催者側もそこに気をつけるし、参加する側も気をつけていくという話。
さっきーさんのツールについて
ざっきーさん:5秒間隔に「いいね!」の数をグラフ表示しています。リアクションのハードルをめちゃくちゃ下げることを目指しています。Tweet出来ないという人は匿名性というかアカウントすら持っていないという人がそれなりに参加していますが、これであればWebにアクセスしてボタンを押すだけで参加している気になれる。
コミュニティの文化を共有する
新藤さん:「このコミュニティはこういう文化で運営している」というのを最初に共有するしてもらえるといいなぁ・・・というコメントが参加者有りましたがホントにそうだと思います
Slidoをつかいこなす

宮原さん:Slidoは使いこなしがすごく難しいツール。まずページにアクセスしてもらうのを冒頭でしてもらって、最初に択一のアンケートに答えてもらう。そこで参加者のレベルを理解する。とにかくページを開いてもらう。次にQ&A画面のテストとして「テスト」と入れてもらう。それから「ここに質問書き込んでくださいね」とアナウンス。アイスブレイクを兼ねて質問ツールの使い方をご案内する。ウォーミングアップする。コメントや感想でもいいから書いてください・・と掲示板のように使う。
Twitterやチャットと分かれると大変なのでSlidoにまとめる。全員が何の質問について離しているのかを共有できるようにする。そこからフィーバー状態に持っていく。
使いこなしがとにかく難しいのでなれるしかない。時間がない、時間配分も双方向性では大事
時間配分のところで気をつけているところは?
ざっきーさん:私自身がコミュニティを主催するのは少ないのですが、開催される時間帯や時期・・・体のリズムとして「そろそろだな」というのには心がけています。あとは時間通りに終わらすということです。LT時間をコントロールしてさくさく進めて時間通りにきっちり終わるというのを心がけています。
新藤さん:時間というのも大事なインフラだと思いますね
清水さん:コミュニティだと僕はゆるいのでオーバーランすることも多いですが、時間を守らないといけない場合は、自分の中でスイッチが入って「欲張らない」というスイッチが入ります。最低限伝えないといけないことをピックアップして、飛ばすものも自分の中で決めています。
ただ、生放送なので「頑張っちゃいけない」できなかったら「来週やりましょう」「別に予定をたてましょう」とする。時間にとらわれすぎなので、本当に必要なら朝一にやるとか・・・ 本当にやらなくちゃいけないならアジェンダをキッチリしましょうとか・・・聞きたいことがあるなら事前に投げておけばよいし・・・質問えお事前に出しておいて解についてのみディスカッションするとか・・・その匙加減とか準備の仕方とか・・・かなと思います。
経験したイベントでのフィーバー状態は?
清水さん:人数が多かったと意味では2020の夏のJapan Power Platform カンファレンス(参加者400人)のときのオープニングのMCをしたときです。聞きながら進行しながら、時間が来たらぴったり次に渡すのをどうしようかな・・と考えて・・・なんとなくやりましたね。雰囲気の話はありましたがイベントの初回の挨拶で8割方決まると思いますね。ラジオなんかでもそうですよね。
新藤さん:最初のムード作りが必要っていうのはありますよね
画面に動悸させてTweetを合成させたりとかはありますか
新藤さん:みなさんのなかで配信されているものと別のものを拾っていく・・・たとえばTweerとかを・・・これをやった事による記憶にノコrったというような事はありますか?
ざっきーさん:配信者の立場で聞いている方が聞こえ方の良し悪しを気にしますが・・・私は参加者に聞いちゃいますね。教えてもらえればユーザー体験を改善できますのでなるべく腰を低くして望んでいます。
宮原さん:ぜんぜん違う話ししていいですか?OSCもミートアップもそうなんですがZoomとYoutubeを使っているときには裏側を見えるようにしています。リアルのときのコミュニティだとあるザワザワ感を出すようにしています。音声テストや雑談は流しっぱなしです。
没入感はコンテンツでやるということで、話す側のコンテンツ力がすごく出ると思います。
僕は双方向性という意味で参加者がカメラオフでも構いません。場数を踏んでくると慣れで反応が見えてくるようになります。双方向性を求められることも多いのですが、まず講師の人が参加する気分になっていないからです。
「参加している感がない」とよくアンケートに書かれますが、まずはそれぞれの参加者がどうやったら主体的に参加出来るのかを考えたらいいと思います。
このイベントも裏側でスピーカー側のプライベートチャットが流れていて聞いてる人と双方向のようになっていますが、それをやる側と参加している側がどんどん書いてくれることによって相乗効果が出てきて「整ったぁ」となりますね。
新藤さん:さっき、渋谷の会場のもりあがっている様子が見えましたが、そういうのを見ると全員オンラインでやっているこちら側も盛り上がりますよね。
オクロック理論
昨日、宮原さんとオンタイムの話をしたら「そんなテレビじゃないんだから」と笑われましたが・・・・・「オクロック理論」と呼んでいるんですが仕事で配信しているとき、本当にちょうどの時刻になるとガクーンと参加者が離脱してしまいます。これはテレビで育っているからなんじゃないかなと思います
クロージング
新藤さん:OSCでもカルチャーをわかってもらおうというのはいい知見だなぁと思ったのですが、ざっきーさんはなにか前提のお作法はこうですよというようなものはありますか?
ざっきーさん:コロナが落ち着いてハイブリッド開催になってきたので、リアルにもっと戻ってきてくれるのかなと思っていたのですがIoTLTでは1/3くらいでした。オンライン参加は物理的な移動が伴わないし、時間的にも物理的にも参加しやすい・・・というのは良いことなのですが、オフラインとオンラインの比率が常に変わっていくので、その時時のベストなインタラクションを考えています。
清水さん:タイトルをきちんと決めていくのが大事。話すことと期待値がずれるとアンケートの結果も全然悪くなってしまいます。「これに興味ある人きてね!」といって来てもらって、始まっちゃったらあとは最大限反応を見てやる感じですね。僕の口から「つまんなかったですかね」と出たら、それは僕が不安になっているときですね。直接聞いてしまうくらいフランクでいいかなと思います。
新藤さん:感情表現は大切かもしれませんね。宮原さんはどこの会場に行っても温まっているというのはかなりのノウハウですよね。
宮原さん:すごく感じるのが参加してくれている人の当事者意識の差なんだとおもいます。コミュニケーションをしたい人はグイグイ来るじゃないですか?お客さんで居ると当事者意識が生まれないから、話聞いても身につかなかったりしますね。どうやって当事者意識を持ってもらって自分でもやってみようと思えるようにするのが中心にあるし、DevRel・・・開発者とのリレーションズってそこのところで今日のテーマはかなりコアに近い話だと思います。
新藤さん:当事者意識ですね、受身の姿勢で教育を受けて「答えがひとつです」というのではなかなかフラットにつながれません、だから運営側が参加者に当事者意識を持ってもらうのをうまく工夫することで双方向性を確保できると思うので、我々主催側や配信側だけでなく、参加する方々もそういう意識を持っていって持たうというのが今日のキーワードかなと思います。
とはいえ我々の知見も有り余るほどあるので、このテーマは何回車っても楽しく話せるテーマだと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
