
【試し読み】『言葉はいかに人を欺くか』 本当に「言われていること」を読み解く
ジェニファー・M・ソールの本邦初となる翻訳書『言葉はいかに人を欺くか』を刊行しました。付録には「犬笛、政治操作、言語哲学」を収録。現代の社会や政治を分析する論点として今、注目されている「犬笛」を理論化するものです。訳者である小野純一さんのコンパクトで明快な解題も収録。哲学者の國分功一郎さん推薦の一冊です。
↓ 目次などの詳細はこちら
ジェニファー・M・ソールとは❓
1968年生まれ。専門は言語哲学や心理学の哲学。とくに政治言説における人種差別・性差別の言葉に関心があり、言語哲学的なアプローチで分析する著作を発表しています。2011年には優れた女性哲学者に贈られる英国女性哲学者協会の賞を受賞するなど、現在、最も注目される哲学者の一人。その活動はアカデミズムの世界に留まらず、BBCニュースやハフィントンポストなどの一般メディアで時事的な社会問題を論じており、「犬笛政治」について解説した2019年のBBCニュースの動画は話題になりました。
なぜいまこの一冊なのか❓
近年、トランプ政権の誕生やポピュリズムの世界的な台頭を背景に、「ポスト・トゥルース」と呼ばれる現象が起こりました。それは、客観的事実を主張するよりも、情緒や個人的信条に訴えかけることの方が、世論に強い影響を与える状況のことです。
大きな発言力のある個人や政治家が、メディアやSNS上で特定の聞き手を扇情・操作し、対立する立場をとるグループや個人を攻撃させる。そんな有害な言語行為に対し、当の発言者は巧妙にも「そんなことは言っていない」と責任すら認めないような欺瞞が世界中にはびこりました。ソールのこの本は、まさにこの現代社会の抱える有害な言語行為やありふれた日常的な言語行為を読み解き、それにどう立ち向かうべきかヒントを与えてくれます。
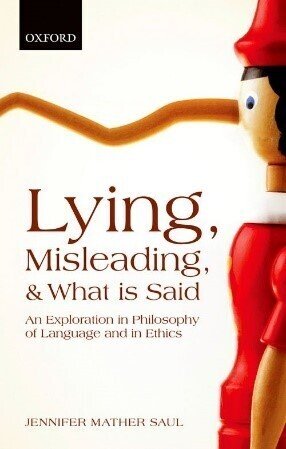
原著 Lying, Misleading, & What is Said: An Exploration in Philosophy of Language and in Ethicsはオックスフォード大学出版局から刊行されている。
ソールは、長年、言語哲学を研究しながら(とくにアメリカ・イギリスの)政治家の欺瞞に着目してきたと言います。言語哲学者(いわば人間の本質である「言葉」のプロ)が、そのアプローチを応用して社会問題を論じるのは珍しいことではありません。普遍文法仮説で有名なノーム・チョムスキーのメディア論や、最近ではソールもこの本で多く参照するジェイソン・スタンリーの『ファシズムはどこからやってくるか』が話題になりました。こういった系譜にこの本も位置づけられると言えます。そんな言語哲学のもつ現代的意義や専門的な議論を分かりやすく説明する「訳者解題」を抜粋して掲載します。*記事向けに微修正しています。
***
訳者解題(抜粋)
本書の詳細な概要はソールによる序文を参照していただくとして、ここでは簡単な紹介をしよう。通常、私たちは噓をつくことに罪悪感を抱くだろう。冗談と違って、噓をつくには能動的、積極的に相手を騙す必要がある。それに対して、ただのミスリードでは道徳的に悪と言える欺瞞を自ら積極的に行わず、誤解を生じさせるだけに思える。できるだけ他人を騙さないよう努力するので、噓に比べて好ましいと感じるかもしれない。だがソールはこの倫理的な価値判断は再考すべきだと論じる。
噓もミスリードも、人を裏切るという意味とその効果においては変わらない。ただしミスリードでは、ミスリードする側にのみ非があるのではなく、聞き手が自分自身で間違った解答にたどり着く点で部分的に責任を担うという考え方もある。ミスリードする人は自分の手を汚さずに、つまり噓をつかずに、噓と同じ成果を得ることができる。それどころかミスリードする人は、自分が相手を欺いたのではなく、相手が勝手に誤解したのだから、自分は悪くないと安心感を得るかもしれない。自分の行いを正当化する自己欺瞞であるなら、噓と比べより反道徳的だとも言える。
だがもし、もうすぐ臨終を迎える心優しい老人が、前日に息子が事故死したことを知らず、自分の息子が元気かあなたに尋ねたら、どうするだろう。「あなたの息子は昨日死にました」と事実を告げるべきか。それとも(不慮の事故の前に会った時は)「元気でしたよ」と答え、穏やかな最期を迎えさせるべきか。この議論は、日常生活でどの言語行為を選ぶかで発話者の人格や道徳性が露呈する点で重要だとソールは指摘する。
ソールの関心は日常会話だけでなく政治にもわたる。1998年、アメリカ元大統領ビル・クリントンが、当時、ホワイトハウス実習生だったモニカ・ルウィンスキーとの不倫スキャンダルの際に「不適切な関係はありません」と述べたのを、覚えておられる読者もいるかもしれない。ソールはたびたびこの例文を引いて、この発話が噓であるかミスリードであるかを考察し、その区別にこそ倫理的な重要性があると述べる。さらにソールは、このような政治に関わる発言では、それを聞き手がどう考えるかで、その人が元から有する政治的姿勢そのものが露呈することを示す。すなわち、クリントンは噓を避けミスリードすることで、法的・公的にできるかぎり誠実であろうとしたと考えるか、その反対に狡猾で卑劣な態度をとったと考えるか、聞き手のその判断が彼らの政治信条に対応することをソールは示した。
このようにソールは数々の事例を挙げ、噓とミスリードの間にある道徳的な区別をあぶり出し、ミスリードの方が善いという常識を疑い、倫理学に新しい議論と知見を提供する。両者の区別には、言語哲学の中心概念である「言われていること」や、言葉通りの意味、言外の意味が関わる。哲学だけでなく、ありふれた会話や政治の中で「言われていること」とは何かという問題は、自明のようでいて、実は共通した理解がない。
ソールの出発点
日常言語をめぐる考察において、言語行為論の創始者オースティンの跡を継ぎ、「会話の含意(推意)」ど、現在盛んに議論される概念を導入したのは、ポール・グライスである。彼が一九六七年にハーヴァード大学で行ったウィリアム・ジェイムズ記念講演は、その後の意味論、語用論、コミュニケーション論の基礎になった(『論理と会話』清塚邦彦訳、勁草書房)。ソールは自ら述べるように、グライス理論に依拠しながら、本書の見解を形成する。本書の主題である「言われていること」のソールの理解に大きく関わるのでごく簡単に説明しよう。
グライスが体系的な説明を与えた含意は、会話において字義通りの意味以上の何かが伝えられる現象だ。彼の理論によれば、その前提には「協調の原理」と「会話の格率」がある。協調の原理とは、自分が参加する会話の中で合意される目的や方向性に従うことである。少なくともこれが守られていると想定されるときに聞き手が意味を推論し、また話し手も聞き手にその能力があると仮定している場合に、会話の含意が成り立つ。本書の特に第4章で協調という言葉が特徴的に用いられているのはこのためである。グライスによれば、会話の参加者が「会話の格率」――量、質、関係、様態――に従うことで「会話の含意」が成り立つ。
「量の格率」は、① 会話に必要とされるだけの情報を全て与えること、② 必要以上の情報を与えないこと、である。「質の格率」は真である情報を与えること、すなわち① 真でないと知っていることを言わないこと、② 十分な根拠のないことを言わないことである。「関係の格率」は会話の主題に関係することを言うことである。「様態の格率」は明瞭でなければならない、すなわち① 把握できない表現を避けること、② 多義性(曖昧さ)を避けること、③ 簡潔である(不要な冗長さを避ける)こと、④ 順序立っていることである。
グライスはこのように「原理」と「格率」を示したが、その説明が簡潔で抽象的な特徴づけであったため、グライス理論をめぐり、後継者たちは修正を試みていく。本書はそういった議論を参照しながら進むので、それらのうち主要なものに触れておく。
「言われていること」から含意、関連性理論へ
第2章で記されるとおり、フランソワ・レカナティは、含意に関してグライスの図式を採用するには、「言われていること」をより広く捉える必要があることを主張する。すなわち、「言われていること」とは表現された命題であり、その際の含意は文脈に依存する命題である、という主張である。このように、レカナティは「言われていること」には発話のあらゆる段階で語用論的なプロセスが関わるという文脈主義の立場をとり、「言われていること」の字義通りの意味、つまり意味内容(意味論的内容)という概念に批判的である。レカナティとは異なり、ケント・バックは「言われていること」の意味内容を認める極小主義に立つ。
しかし、これに加えて語用論的内容として「含み(隠意)」を提案する。バックはグライス理論が明確に区別しない推論を指摘し、含意(推意)を引き出すのとは異なる含みのプロセスを主張する。
グライス理論を受けて語用論では関連性理論が展開した。本書でも参照される代表的な論者に、スペルベルやウィルソン、カーストンなどがいる(第2章、第3章)。語用論は認知的な方向に考察を発展させ、グライス理論の修正を図った。彼らは人間の認知システムが推論だけでなく、知覚や記憶のほか、明言されないが理解にとって必須の情報を把えることも含めて、全体的に解釈するという観点から論じる。なかでも関連性理論は、解釈を論理的な問題よりも心理的な問題として扱う点で、グライスの語用論やその後の意味論とは大きく異なる。グライスをはじめとする言語哲学者・分析哲学者の立場は、話し手の意味は確定できる命題であるという前提に立ち、関連性理論の立場はそれをより緩やかに捉える。
通常、「言われていること」は、真偽判定できるという観点から論じられる。だがソールは、噓やミスリードのように人を欺くことを目的とする言語行為も同じように理解しなければ、真の発話の理解にはならないと考える。そこで「言われていること」の概念を検証するために、噓という特定の目的に限定して、概念を作る。すなわち、彼女は「言われていること」が噓である場合の必要十分条件を見つけ、噓とミスリードを明確に分ける。
人を欺く言語行為は噓以外にもさまざまに存在する。その一つが、民主主義にとって危険な政治戦略としての「犬笛」である。これも含意によって人心操作するという特定の目的をもった「言うこと」である。犬笛は本性上、示唆や指示や含みよりも広い文脈や情報に関わり、真偽判定を前提とする問題とは異なる領域を成す。その点で「犬笛」の意味論には独自性がある。ソールは噓やミスリードの言語行為の論理的な解明から、倫理に接続するのと同じように、噓とは異なる欺き方で人心を操作する犬笛の仕組みを分析することで、差別と偏見を助長する犬笛への対抗策を探る。本書に収録した「犬笛、政治操作、言語哲学」によって、私たちはソールがいかに理論と関心を一貫して展開しているのかを知るだけでなく、その現代社会における意義を窺うことができる。
犬笛という人心操作
元来、犬笛は犬が人間よりも広い範囲の周波数を聴きとれることを利用し、犬に合図することを目的に使われる。この意味を転じて、特定の集団にだけ分かる合図でメッセージを送り、人心を操作する政治手法を犬笛と呼ぶ。犬笛による発話は、誰もが言葉通り理解できる表現から成るが、その隠れた意味は一部の聞き手だけが把握でき、他の人は気づかない。特に政治家は犬笛を用いて、人種差別的な態度を隠しながら、自分の人種差別主義に賛同する相手にだけ合図を送り、支持を募ることができる。その真意を公言すれば支持を失うことが確実でも、犬笛を巧みに利用すれば、差別に反対する人たちさえ支持者にできるかもしれない。
差別主義者の真意を読み取れずに、もし私たちが、その政治家に投票してしまったら、どうなるだろうか。私たちは意に反して、人種差別的な政策や発話に加担したことになるかもしれない。政治家に巧妙に騙されたと感じた有権者に対し当人は、自分はそんなことは言っていないとか、自分は人種差別主義者ではないと否定するだろう。このように犬笛は練られた戦術なのだ。そこでソールは犬笛政治への有効な対抗措置を提案する。論文が立脚する実証研究が示すように、どんなに巧妙な犬笛でも、それが人種差別である可能性が指摘されると、被験者への効果が弱まることが分かっている。確かに犬笛は知らずに拡散されることから、意見を声に出して言うという民主主義の根幹を蝕む。この脅威に対する強力な対策を言語哲学者の見地から示唆するからこそ、ソールの考察は重要なのだ。
世界的にポピュリズムが台頭するなか、2016年にトランプ政権が誕生し、ソールの犬笛の議論は注目された。2019年1月28日のBBCニュースが犬笛政治を取り上げ、その中でソールにインタヴューしたことで、彼女や犬笛について知った人も多いだろう。この短いインタヴューは犬笛政治の危険性を簡潔に力強く伝える。本書の附録論文とあわせて参照されたい。ソールはまた別の論文でトランプ元大統領が差別主義を巧妙に隠す話法を利用することを分析する。彼女はそれを「人種のイチジクの葉」と名づけた(“Racial Figleaves, the Shifting Boundaries of the Permissible, and the Rise of Donald Trump”)。イチジクの葉は成人の彫像などで性器を隠す用途から、「不都合な事実や不正の隠蔽」を意味する。
ソール自身、本書で政治家の策謀に昔から関心があったと言うように、言語哲学的なアプローチで、人種差別や性差別の問題に迫るのが彼女の哲学的スタンスだ。その一つが彼女が主導する「暗黙のバイアス」をめぐる大規模な国際プロジェクトであり、研究成果が出版されている(Implicit Bias and Philosophy, 2 Volumes, Oxford University Press, 2016)。バイアスとは特定の人種や性別の人々に対する無意識の偏見であり、差別主義者だけでなく平等主義者や偏見の対象となる人も暗黙のバイアスをもつことが同書で実証されている。このような問題に対し心理学など他の分野では議論の蓄積があったが、哲学は遅れて注目し始めた。ナショナリズムの世界的な台頭、コロナ禍における特定の人種への差別の悪化などを考えると、学際的アプローチによる彼女のプロジェクトの意義は大きい。
↓Amazonで購入する
↓ 目次などの詳細はこちら
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?




