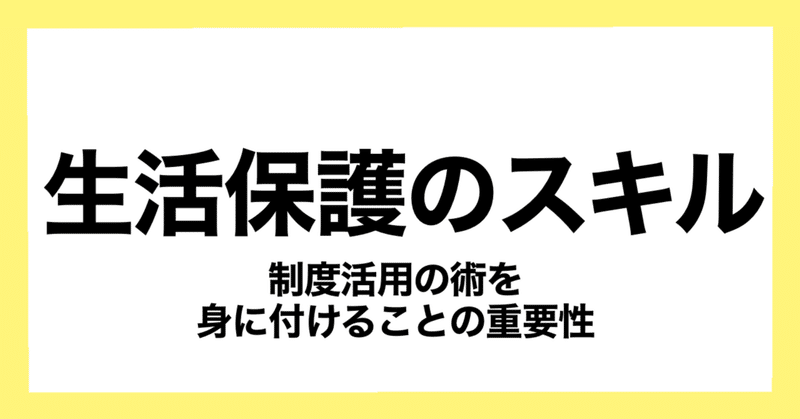
生活保護制度を学ぶ機会の重要性
こんにちは、KEIです。
私のnoteにたどり着いたみなさんは、生活保護制度をどのくらいご存知でしょうか?相談窓口を担当したことがありますが、よく質問されるのが、、、
これだけしかお金が貰えないのですか?
自立を目指すって何?お金が貰えるだけの制度じゃないの?
自動車や家を売却しなければならないと聞いたのですが本当ですか?
医療費や家賃がタダになると聞いたのですが本当ですか?
結局、私は保護申請できるのですか? などなど…
さらに、保護受給中の方からも
就労指導なんて聞いていない
転居指導なんて聞いていない
収入認定なんて聞いていない
返還金なんて聞いていない
通院費が出るなんて教えてもらっていない
障害者加算なんて教えてもらっていない などなど…
様々な苦情を耳にすることもありました。
生活保護制度の大枠はとてもシンプル
憲法第25条に定められた「健康で文化的な最低限の生活」の保障が根底にあり、日本国民のセーフティーネットとしての役割があります。
最低限度の生活水準維持に必要な基準額があり、これに対してご自身の収入で不足する部分が生活保護費として補われます。
【例①】最低生活基準10万円-ご自身の収入3万円=生活保護費7万円
【例②】最低生活水準15万円-ご自身の収入14万円=生活保護費1万円
考え方はとても簡単なんです。
しかし、実際の運用は複雑…ケースワーカーによって異なることも?!
同じマニュアルを見ながら生活保護制度を運用していても、福祉事務所によって取り扱いが異なることが当然のようにあります。なんと、場合によっては同じ福祉事務所内のケースワーカーによっても違うこともしばしば…
ケースワーカーも公務員ですから人事異動がありますし、担当変更もあります。そんなときに急に就労指導や転居指導をされ「前の担当と言っていることが違う!」なんてことがあるくらいです。
自動車を保有容認すべきか?
収入申告が遅れたのは不正受給か?
働いているけどその給料の金額は妥当か?
アパート家賃が高ければ転居が必要か?
昔の借金の返済はどうすべきか?
勝手に病院通院したときは自費か?
福祉事務所の中でも日々、様々なことを協議して決定しています。だからこそ、経験年数の浅いケースワーカーはどうしたら良いのか悩むことも。本来はあってはならないことですが、間違った取り扱いをしてしまうケースワーカーも少なくはありません。
「間違った取り扱いをするCWをもつと生活保護を受けている当人はあまりに不幸ですよね!」
少なくとも僕はそう思います。
だからこそ、生活保護を受けている方自信が、自分事として生活保護制度を学ぶ機会が必要なのではないでしょうか。もしかしたら、生涯に渡って保護を受け続ける人もいるかもしれません(近年の傾向としてハナから仕事を諦めて生活保護で生きていくことを希望する方もいらっしゃいます)。それならなおさら、知らないでは損をすることが何度も訪れます。
私のnoteが生活保護制度を少しでも深く知っていただける、きっかけになれば幸いです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
