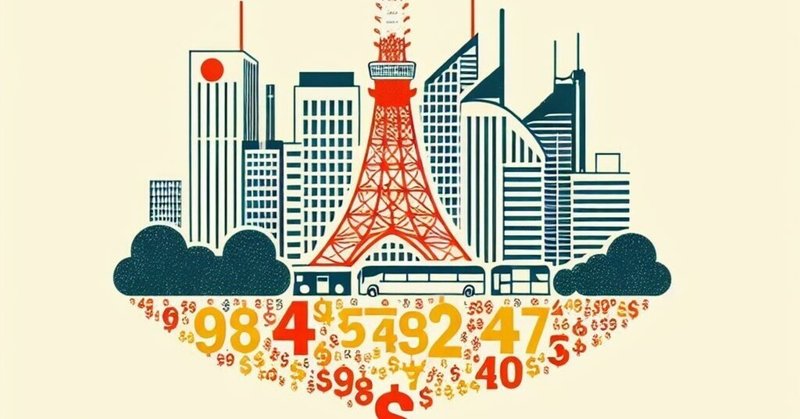
349 東京都消費者物価のポイント
消費者物価のメインの対象にしている生鮮食品を除く総合の前年比(2.3%)は急速に低下してきた。植田日銀総裁の指摘していた通りだ。
しかし、植田総裁のホンネのターゲットである食料及びエネルギーを除く消費者物価上昇率(2.7%)は高いまま。

海外のエネルギーと食品の前年比上昇率が低下し、輸入物価の前年比上昇率が低下しているからだ。
うれしいことに、サービス価格が堅調だ。
注)海外のエネルギーと食品価格の上昇で潤うのは海外業者。サービス価格の上昇で潤うのは主に国内業者。

但し、今の前年比上昇率はパンデミック後物価が低下していた反動上昇的なところがあり、3年前と比べると、食料及びエネルギーを除く総合物価指数の年率上昇率は1.1%と目標の2%より大きく下回っている。


もう一つ注意する点は、
生鮮食品を除く消費者物価前年比上昇率は低下しているが、3か月前比では再び上昇していることである。
これは、原油価格が一度下げてから反騰したのを反映している。しかし、原油価格は再び下げている。
こんなにフラフラする物価目標の対象では困るので、植田総裁のホンネのターゲットは食料及びエネルギーを除く総合物価指数なのである。


結論
食料及びエネルギーを除く総合物価指数の3年前上昇率(年率)は1.1%と目標の2%を大きく下回っており、日銀は金融緩和を継続する。
但し、異常な金融政策であるマイナス金利の修正(0%へ)はするだろう。物価抑制が目的ではなく、異常な金融政策の修正である。消費者物価は昨年からトレンドが上向きに転じていることからも、決断はしやすい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
