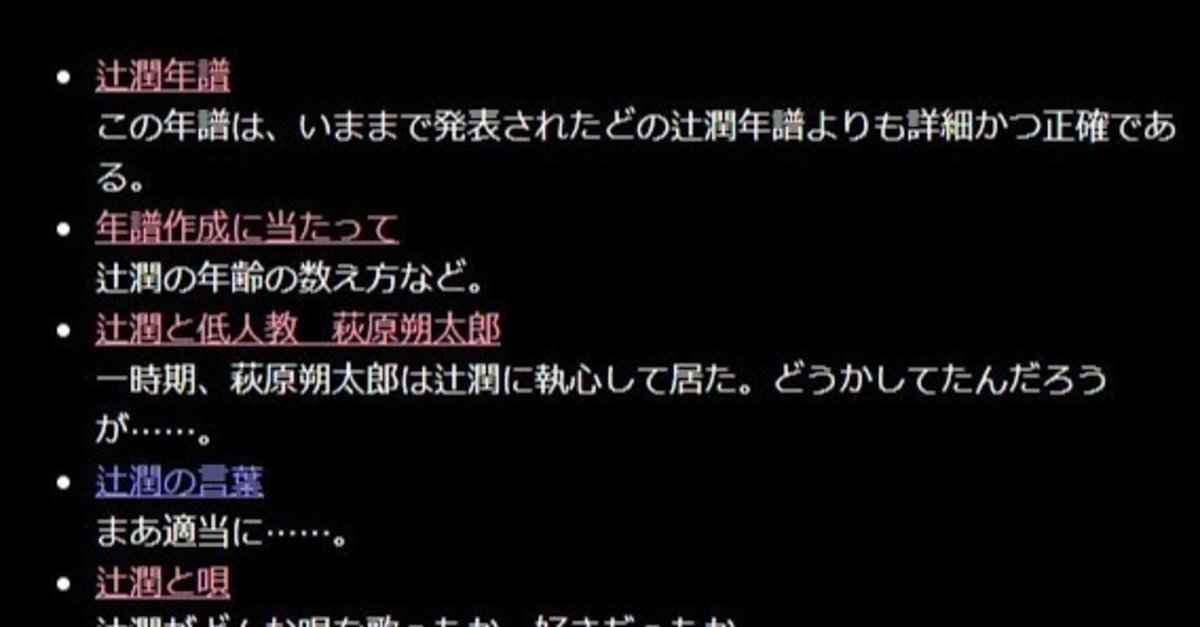
辻潤のひびき「辻潤年譜」
辻潤のひびき>辻潤年譜

辻潤年譜
(Oct.22, 1999) updated
--------------------------------------------------------------------------------------
この年譜は、辻潤の生活(流浪)史が見えるように編集してみたもの。
この年譜は、いままで発表されたどの辻潤年譜よりも詳細かつ正確である。
辻潤の年譜や記事は諸書により多々食い違いが見られ、いささか頭に来たので自分で作成してみた。おそらく、どこかの暇人か暇でない人が同様のものを作成していることだろうと思う。この年譜作成にあたっては諸書を参考にしたが、読み間違い、読み抜けも多くやらかした。この年譜が完璧だとかは言えないが、今までの年譜よりは確かであろうと思う。典拠を示しているので、疑わしい箇所はそれをまず調べてほしい。
作成にあたっては辻潤全集別巻の年譜(高木護 作成)を基本にし、この年譜と異なる箇所或は加えた箇所に、典拠を記した。また辻潤の作品が典拠と思われる箇所に、作品名を加えたりしている。辻潤の雑誌への発表などは原則として省略。別に作品リストを作成したので合せてみてほしい。年譜中の年齢はその年の誕生日以降における満年齢。括弧内は数え年齢。辻潤に振り回されている様子が面白いので、周囲の人間についても少し加えてある。
典拠は、記載のあるものの他は以下の通り、年譜中に"*" に数字を付して示した。書簡については『選集』の書簡番号を付した。
1.玉川信明 『ダダイスト辻潤』
2.倉橋健一 『辻潤への愛 小島キヨの生涯』
この本は、小島キヨの日記に基づいているので日付に信憑性がある。
3.佐々木靖章 「辻潤の著作活動」(辻潤全集別巻)
4.平塚らいてう 『元始女性は太陽であった』
5.書簡 『辻潤選集』
6.宮嶋資夫 「遍歴」
7.高橋新吉 「ダガバジジンギヂ物語」
尚、年譜中には矛盾する記載もあるが、まだ整理できないことによる。
辻潤の年譜というのは、特に晩年はどこそこに居候したとか、どこに行ったとかばかりだから、放浪前の時代についても辻潤がどこで何をしたのかを入れないと釣り合いが悪いことになる。また何をしたかということを入れると、全くキリがない。しかし、本を漁ってみてもおのずと得られるものには限界があることだし、自分にできることも限られたものだから、できるだけ入れてみることにした。それでかなりゴタゴタしたものになった。
辻潤が何を考えていたかまでは当然入れるわけにはいかない。それは辻潤の書いたものを読むか、辻潤について書かれたものを読んでもらうより仕方がない。ここにあるのは、辻潤の外形の流浪だけである。
--------------------------------------------------------------------------------------
一八八四(明治一七)満0歳(数え1歳)
十月四日明け方(*1 菅野青顔年譜によるらしい)(戸籍は一年遅れの明治十八年に入籍)、東京市浅草区向柳原町一丁目の祖父辻四郎三の隠居所(この家は「医学館」といって江戸の医者たちの集会所だったものを買い取り、雑作手入れして住まいとしたなかなか凝ったものであったが、のちに隣地の柳北女学校の拡張のために立ち退いた(辻美津「実話蔵前夜話」))でうまれる。
母美津(みつ、光津ともいった)は、会津藩の江戸詰め家老田口重義と、その妾某女とのなかにうまれたが、重義と別れた某女が美津を連れ子として四郎三の後添いに入って養女となる。
(辻美津「実話蔵前夜話」によると、田口重義は会津藩の江戸家老でお留守居役兼勘定奉行。美津の母は幸と言い、四谷信濃町お留守居与力、加藤市左衛門の三女で、十八歳の時田口家へ後妻として入った。明治三年十一月田口重義が亡くなり、幸の姉の嫁いで居た二千石の旗下、深尾の縁故で、辻家の四郎三の嫁として美津諸共入った、とある。美津がいつ生れたのかははっきりしないが、明治前の生まれのようである。)
父六次郎は姓は茂木、埼玉の豪農に生まれ、茂木家は維新前は幕臣だったらしい。六次郎は養子婿であった。(*1)
祖父の四郎三は明治維新までは浅草蔵前で札差をしていたので、費沢な暮らし向き(このころの記録としては『文芸春秋』昭和三年十二月号に、辻美津述―桑原国治編「実話蔵前夜話」として掲載されている)だった。
この祖父は、辻潤が五,六歳以降に死亡したらしい。(「少年時代の読書」)
辻潤の親戚については、蔵前にいた時十銭婆あという婆さんがいて、四谷から歩いて来て来るたび小遣い十銭をくれたという。この人は大岡雲法という画描きの姪で、おふくろのオヤジの兄キ位にあたるその画描きは四ツ谷の天王様の合天井へ六歌仙をベタベタと描いたことで有名だとある。(「幻燈屋のふみちゃん」)
まもなく同区蔵前片町に移る。また向柳原の祖父の隠居所に移り住む。
一八八五(明治一八)満1歳(2歳)
一八八六(明治一九)2歳(3歳)
一八八七(明治二〇)3歳(4歳)
父母に手を引かれて浅草の仲見世や観音様などをよく歩いた。このころ熱を出、よくヒキツケを起こした。
この頃、浅草の観音様にお参りに行った時、易者が頼みもしないのに天眼鏡で覗いて、「このお子さんは僧侶になされば必ず出世なさいます」と告げる。(「自分はどのくらい宗教的か?」など、四、五歳とある。「あさくさ・ふらぐまんたる」には三四歳の頃、とある。)
四、五歳位の時から「幻燈屋のふみちゃん」と毎日雨が降っても風が吹いても遊ぶ。(「幻燈屋のふみちゃん」)
一八八八(明治二一)4歳(5歳)
浅草区向柳原の柳北女学校付属の柳北幼稚園に入る。このころまでは四、五人のお手伝いさんにかしずかれて育ったが、賛沢なくらし向きのために、祖父の蓄財も底をついてきた。
一八八九(明治二二)5歳(6歳)
母方の曾祖母に連れられて浅草の新堀端付近にあった自性院や西福寺に行って、曾祖母から色々な話をきく。自性院のご開帳のおりに、「地獄極楽」の掛軸を見て、その後ずっと地獄極楽殊に地獄にひどく興味を持った。(「自分はどのくらい宗教的か?」、「あやかしのことども」)
尚、辻潤の書いたものには、祖母については、「のんしゃらんす」に、「未だ存命の頃、「世が世なら――」という繰り言をきかせてくれた」とある他には出てこないようである。
この年、腸チブスに罹病。(「あやかしのことども」)
『西遊記』を愛読し、赤本から、馬琴? の訳したものや、唐本など色々な本を集める。(六ツか七ツ頃とある。(「お化けに凝った」)
母に連れられて毎月欠かさず芝居を見て歩いた。(「昔見た芝居」少年の頃とあり、年代は不明。蔵前に住んでいたとある)
一八九〇(明治二三)6歳(7歳)
浅草区猿尾町の育英小学校尋常科に入学。(*1) 成績は上の部だったが、目立たないおとなしい子供であった。
一八九一(明治二四)7歳(8歳)
辻美津「実話蔵前夜話」によると、この年、蔵前にあった伊勢屋の馬鹿蔵と呼ばれた大きな蔵も、また家屋敷も、みんな日下という人に譲った、とあり、蔵前の財産を処分したらしい。
一八九二(明治二五)8歳(9歳)
父六次郎が親類の知事の縁で三重県の官吏となり、父母に伴われて伊勢の津へ行く。
(「自分はどの位宗教的か?」などによると、八歳から伊勢の津に住む、とある。従ってこの年津に行ったというのは疑問が残る。辻潤の記憶も不確かと思われるので、全集年譜に従っておく。)
三重県知事のN氏とかなり深い縁辺であった、とある。(「最初の自然」)
辻美津「実話蔵前夜話」には、三重県知事になった人物として成川常義の名があり、成川常義は、美津の父田口重義が会津藩の重役だったため官から狙われて入牢した時の牢名主で、入獄中兄弟の契りを結んだ、とある。
大林日出英、西川洋『三重県の百年』山川出版社 1993 付属の年表によると、 一八八九(明治二二)年十二月二十六日、成川尚義が三重県知事になっているから、成川の名は尚義が正しいと思われる。三重県知事は、その後一八九六(明治二九)年八月十二日、田辺輝実に代わって居る。
辻美津「実話蔵前夜話」によると、成川は明治三十五年に逝くなり、それまでは美津は繁々往復していた、とあるから、成川尚義は三重県知事を辞めてから東京に住んだのかもしれない。
しばらく知事の官舎にいたが、やがてトウセイ川という河の岸辺に移り住む。(「最初の自然」)
地図を見ると津にはトウセイ川という名の川は見当たらない。塔世橋という橋があるから、トウセイ川というのは、安濃川のことなのだろう。
キリスト教講義所の讃美歌に惹かれキリスト教会の日曜学校に通う。日清戦争の愛国熱が高まるとともに中止。(「自分はどの位い宗教的か?」「ふりぼらす・りてらりあ」)
隣に尺八の名人が居て、尺八に興味を持つ。(「エイ・シャク・バイ」)
「一番辛いイヤなことは毎日学校へ行かなければならないということでした。私はまったく異国人扱いにされたからです。」とある。慰めてくれる友達がないので、父母に頼んで東京から三公という男を呼んでもらい、生れかわったように快活になった。三公というのは家に始終出入りして、なにくれとなく用事をたしてくれる下男のような食客のような男とある。多分初秋の頃、三公と一緒にハセ山に登る。初めての山らしい山。その後たびたび登った。(「最初の自然」)
探偵小説というものの味をおやじから教えられた。夜、夕餉がすむと辻と母と女中などを集めて、おやじは毎晩探偵小説を読んできかせた。父六次郎は役所で書記のようなことをやっていたらしい。字がすこしばかりうまかったので辞令などを書かされていた。六次郎は江川近情という書家の門弟となって習字の稽古をしていた。(「ふりぼらす・りてらりあ」 明治二五、六年頃とある)
弟義郎生まれる。
義郎は後、洋服仕立て職人となる。十代から奉公に出ていたという。(*1)
一八九三(明治二六)9歳(10歳)
滝沢馬琴の『椿説弓張月』、『日本外史』などを読む。
一八九四(明治二七)10歳(11歳)
東京に戻る。神田佐久間町の叔父(父の弟、かつて質屋)の借家を借りて住まう。(「エイ・シャク・バイ」)
(「昔見た芝居」に日清戦争の済んだ時分に戻ったとある。とすれば、翌一八九五(明治二八)年四月頃ということになる。三月三十一日休戦条約調印、四月十七日講和条約調印である。しかし、そうすると、八歳から十一歳まで伊勢の津に居たという辻自身が述べて居ることと食い違う。人は、年号や歳などより、事柄を覚えているものであろうし、日清戦争の愛国熱が高まるとともに教会行きを中止したということも考え合わせると、一八九五年に戻ったとする方がよいように思うが、はっきりしない。全集年譜に従って置く。)
浅草区猿尾町の育英小学校高等科二年に入る。
このころ、尺八を吹きはじめ、銀笛(ぎんてき)や手風琴もこなした。(「エイ・シャク・バイ」)
一八九五(明治二八)11歳(12歳)
一八九六(明治二九)12歳(13歳)
神田区淡路町の府立開成尋常中学校に入学。
同級生に、斎藤茂吉、村岡典嗣(つねつぐ)がいた。(斎藤茂吉「友を語る」には他の多くの同級生が挙げられて居るが、そこには辻潤の名は見えない。)
吹田順助は、翌年の同級生。(『回想の吹田順助先生』年譜)
(全集年譜には前年入学とあるが、これは以下の理由によって間違いである。
斎藤茂吉全集(昭和二十九年および昭和五十一年刊)の年譜や斎藤茂吉「私の困った学科」によると、斎藤茂吉は一八九六(明治二九)年九月十一日第五級に二学期から入学。また斎藤茂吉「瘋癲と文学」によると、辻とは明治二十九、三十年の交わりで、同級生だとある。辻が英語がよく出来たと述べていて一緒の教室で学んで居るから、クラスメートであったことが分る。斎藤茂吉全集中の書簡などによっても、斎藤茂吉のこの入学年は疑いようがなく、辻の入学はこの年であることが分る。
辻が前年入学して一年留年したなどは、辻程の聡明な男に対しては考えられない。
さらに、『回想の吹田順助先生』(同学社 1965)中の吹田順助の年譜には、一八九七(明治三〇)年、開成中学二年級に編入とあり、同級生として辻潤の名が挙げられて居る。
斎藤茂吉「私の困った学科」には、この頃は一年生を五級生と云って居たとある。また田邊元(はじめ)らの父である田邊新之助が新たに校長になって英語を教えたとあるが、時期は明らかではない。開成中学は、五年生の時に私立になったが、それまでは府立で、ニコライの寺院が近かったとある。)
通学のかたわら小さな体のハンデを克服するために、神田お玉ケ池の天心真揚流磯又右衛門の道場に通う。しかし長つづきはしなかった。
妹、恒(つね。のち、評論家津田光造夫人うまれる。
(津田光造の名は諸文章に光三とも書かれて居て、以下混在)
一時かなり刀剣に凝る。(「らんどむ・くりちこすDADA」十三、四の頃とある) 「少年の癖に遊戯や運動がきらいで、陰気なことが好きで、玩具を持って遊ぶことにもさしてキョーミを感じなかった幼年の頃、私がややキョーミを持ったものは刀剣の類であった。」(「ものろぎあ」)
一八九七(明治三〇)13歳(14歳)
九月 尺八に夢中になり、学業の怠惰と家庭の経済状態の悪化により中学校中退。(「エイ・シャク・バイ」)
家計の悪化は母美津の乱費にもよるか。(*1)
(開成中学の入学年を改めたことにより、退学年をずらした。月は全集そのまま)
辻潤は毎日尺八を吹いて暮らす。父は小言を言ったが、母は黙認。(「エイ・シャク・バイ」)
W.H.Sharp、上田学訳 『ある英国人のみた明治後期の日本の教育』1993 行路社 によると、一九〇〇年頃の中学校は在籍者の内半数が退学という状況であった。最も多い理由が一身上の理由で、これは経済上の問題だとあるが、安易に退学する風潮があったことは否めないだろう。開成中学の状況は分らないが、辻潤もこの風潮に影響されたことは有り得ることである。
一八九八(明治三一)14歳(15歳)
『文章倶楽部』に載った泉鏡花の「髯題目」など二、三の作品を読む。
『徒然草』に親しむ。以来辻の愛読書となる。
母の奨めもあって、初代荒木古童の門に入り尺八を習う。尺八で身を立てることを考えるが荒木古童に反対され断念する。(「エイ・シャク・バイ」)
一八九九(明治三二)15歳(16歳)
神田区錦町三丁目の正則国民英学会に入る(夜学か?)。磯辺弥一郎、豊橋善之助、高橋五郎、岡村愛蔵、ドクトル.ウッドらに学ぶ。同級に福島県須賀川出身の小倉清三郎、宮城県白石出身の一条勇吾(のち仙台市で写真館を開く)、同県角田出身の星嘉十郎らがいた。「ユニオンリーダー・巻四」からの感化でキリスト教を信じ、内村鑑三の著作に親しむ。
内村鑑三の『求安録』を手にしてキリスト教に帰依し始める。内村鑑三の著作は殆ど片端から読む。(「自分はどの位宗教的か?」)
昼間は某会社の給仕をしていたらしい。(*1、「三ちゃん」)
一九〇〇(明治三三)16歳(17歳)
英語の独習のかたわら江戸時代の稗史、小説を乱読。また内村鑑三のいくつかの著作を読む。
一九〇一(明治三四)17歳(18歳)
神田佐久間町の小学校の臨時訓導を勤める。(*1)
この頃聖書や英書ばかりを読む。
辻の書いたものによれば、父六次郎はこの年六月二十一日、星亨東京市会議長(市長とあるが市会議長が正しい)が伊庭想太郎に刺殺された時、東京市教育科に勤めている。(「あまちゃ放言」)
父六次郎は、時代は不明だが原敬の秘書をしたともいう。(松尾季子「思い出」)
父親は、「無能で淘汰をされてからは、士族の商法のような骨董屋を始めたがそれも一向商売にはならず、息子の教育は碌に出来ず、始終生活に脅かされ、揚句の果てには気が狂って死んでしまった」とある。(「文学以外」)。
また父親は意気地のないために財産どころか借金を残したとある。(「文学以外」)
辻は少年の頃から内心父を「小人」として軽蔑していたとも書いている。(「あまちゃ放言」)
この年、父六次郎は働いていたわけだが、十八九の頃から自活をしなければならない境遇に置かれた、とある。(「にひるのあわ」) 詳細不明。
一九〇二(明治三五)18歳(19歳)
日本橋区呉服町にあった私塾会文学校で教鞭をとる。
午後2時頃から5時頃まで教え、月給3円。後夜学でも教えるようになり、月給9円。(「幻燈屋のふみちゃん」)
そのかたわら同区一ツ橋の自由英学舎に通う。
国民英学会の英文科を出ていたから、英語は習う必要はなかったのだが、巖本善治、青柳有美が一緒にやっていた『女学雑誌』の愛読者だった関係から、先生達がその頃一ツ橋の教育会で始められた「自由英学」に早速馳せ参じた。(「連環」)
「自由英学」は、巖本善治、青柳有美が巣鴨でやっていた明治女学校とかけもちでやっていたので、毎日時間が一定していなかった。辻も呉服町の私塾に雇われていたので毎日は出席できなかった。女学校の特別に熱心な連中が自由英学にもやって来て、その中に、相馬黒光や野上弥生子がいた。(「連環」)
「自由英学」の運命はまことに短いものであったという。(「天狗だより」)
この年の夏に宮城県白石の山奥の一軒家である友人の一条勇吾をたずねる。うまれてはじめての一人旅。
鳥峠という山の半腹にある一条勇吾の家は郵便局でもあり、四五家族が共棲する古びた大きな家であった。この家に一週間程くらし、地図なしの見当で角田まで歩き、H(星嘉十郎?)の家を訪ねる。一条勇吾をそこで待ち合わせ、彼と共に徒歩で塩釜に出、船で松島に行く。このひとり旅は、藤村操の死から受けた衝撃もその理由の一つで、家人や友達に自殺の危惧を懐かせたが、そんな意志はなかった、と書いている。(「天狗だより」)
仙台や松島を見物。
(藤村操の自殺は、翌一九〇三(明治三六)年五月であるから、この旅行も翌年かと思われるが、他に確証がないので、そのままにしておく)
宮崎滔天の不忍庵主の名で『二六新報』連載の「狂人譚」や、『三十三年の夢』を読む。また『万朝報』(明治二十五年創刊)の読者となる。
霜月、日暮里の花見寺に数町の茅葺きの家に移る。当時は田圃があり、野川が流れる自然の多い処であった。それまでは神田の四畳半に暮らしていた。この後(年月不明)佐久間町の二階を借り、そこにふみちゃんが愛人とともに訪ねて来たという。(時期不鮮明)(「幻燈屋のふみちゃん」)
十二月 正則国民英学会英文学科卒業の証明書を出してもらう。
一九〇三(明治三六)19歳(20歳)
一月二十七日 「終日雨降る何処にも行かず透谷全集読みくらす。」(「幻燈屋のふみちゃん」)
この頃神田佐久間町の狭い横町のとある家の二階を借りていた。廃残のオヤジは失業して気が変になり、おふくろは死ぬばかりの大病にかかり、辻は夜学と家庭教師の内職をやっていた。(「幻燈屋のふみちゃん」 年月は推定)
夜遅くまでの仕事に閉口してこの頃本郷の叔母のところに寄寓。(「幻燈屋のふみちゃん」)
日本橋千代田尋常高等小学校の代用教員(助教員)となる。月給15円。
この頃六畳一間に間借りして居る。(「書斎」)
十一月 幸徳秋水『平民新聞』創刊、読者となる。
この年、アンデルセンらの作品をいくつか試訳する。
この頃、キリスト教から社会主義の思想に影響され始める。(「鏡花礼讃」)
木村荘八(木村荘太の異母弟)に英語を教える。(「連環」)
一九〇四(明治三七)20歳(21歳)
この年から二、三年、平穏な日がつづいた。小文や小説などの習作をする。このころ意中の人がいた。
六月三十日 検定試験を受け、東京府管内における小学校専科正教員の免許をとる。
十月二十日 千代田尋常高等小学校の専科正教員となり、五級上俸給与を受ける。
四、五年やめていた尺八をふたたび吹くようになり、竹翁門下の可童に習う。(「エイ・シャク・バイ」二十一二歳とある)
一九〇五(明治三八)21歳(22歳)
小学校で教鞭のかたわら、もっぱら洋書を漁り読む。
一九〇六(明治三九)22歳(23歳)
七月二十四日 四級下俸を受ける。
九月 宮崎滔天が月刊新聞『革命評論』創刊、読者となる。
少年時代から知合ったNという友人に連れられて宮崎滔天の評論社をたずねる。(「宮崎滔天を憶う」)
このNが誰かは不明だが、高橋新吉「ダガバジジンギヂ物語」には、「辻潤の少年時代からの友人に、沼田という人物があった。沼田は、秦国で、成功した貿易商だった。」とある。沼田かもしれない。Nという人物については「ものろぎや・そりてえる」に「そのNという友達は二十年もまえから、幾度かビルマと東京の間を往復していながら、未だかつて京都へ下車したことのない変物なのだ。彼は僕の少年時代に、陽明の『伝習録』を愛読していたら、しきりに僕に英語の勉強をすることを勧めてくれた。僕が英語を習う気になったのはまったく彼の煽動の賜物であるのだ。」とある。
十月 佐藤政治郎編集、発行の『実験教育指針』(この月から月刊となる。それまでは半月刊)に、翻訳や創作を発表し始める。
この年あるいは翌年、九段下のユニヴァーサリスト教会での『芸苑』の文芸講演会の講演を聴きに行く。辻は『芸苑』の愛読者であった。講演者は、上田敏、平田禿木、島崎藤村、馬場孤蝶、生田長江など。(「生田長江氏のことなど」)
平田禿木が洋行帰りだとあるから、おそらくこの年である。『明治文学全集 32』の平田禿木の年譜によると、一九〇三年二月に英国に留学し、一九〇六年六月に帰国して居る。
第一次『芸苑』は一九〇二(明治三五)年二月の一冊、第二次が一九〇六(明治三九)年一月から一九〇七(明治四〇)年五月までの十七冊。毎月同所で講演会を開いていたという。(『近代文学大辞典』)
この頃(前年か)一時期神田の私立音楽学校に夜間通って洋楽を学ぶ。(「De Trop」 一九一八(大正七)年の十二、三年前。「やがて夜間をもパンのために働らかなければならないように余儀なくされた。」とある。)
「天狗だより」には、自由英学が席(ママ)を置いた最後の学校であると書かれているが、「天狗だより」を書いた当時は、この音楽学校のことは忘れて居るのだろう。
学校は、他に、アテネ・フランセで仏語を学んだと書いてある本がある。(岩崎呉夫『炎の女』、および『炎の女』を引用したと思われる三島寛『辻潤 その芸術と病理』、玉川新明『ダダイスト辻潤』) アテネ・フランセ創立は、一九一三年(アテネ・フランセホームページ)。しかし、根拠が不明である。
一九〇七(明治四〇)23歳(24歳)
五月 日本橋区の市立第三実業補夜学校の訓導となる。月給七円二十銭。
(昼間の千代田尋常高等小学校と兼ねてということか)
八月六日 新宿角筈十二社にての「社会主義夏期講習会」に参加する。大杉栄、堺利彦、幸徳秋水、山川均、片山潜らの顔ぶれであった。他に田添鉄二、福田英子、新村忠雄、筑比地仲助、西川光二郎、森近運平らが出席。
この頃(24,5歳)から酒を飲み始める。(弟義郎による。(*1))
一九〇八(明治四一)24歳(25歳)
浅草区の精華高等小学校に教鞭をとる。
月給24、5円。他に夜学と家庭教師の内職をやっていたという。(「古風な涙」)
この学校での勤務表が残っているが、一九一一年二月に、父の一周忌で休んだ他は皆勤の精勤ぶりであった。(*1)
小石川区大原町の亀井という華族の屋敷の近所で、小さい植木屋の庭の中の隠居所に建てた四畳半と三畳の二間の家に住む。父母と妹の四人で暮らす。(「古風な涙」二十四、五歳頃で、小学校教師に雇われていた、とある)
この頃、父は四年越しに心臓を患い、完全な廃人でおかしくなっていた。辻はこの頃はキリスト教の信者だったとある。(「古風な涙」)
一九〇九(明治四二)25歳(26歳)
五月 巣鴨区上駒込八四〇の染井の借家に移る。
六畳、四畳半と三畳三間の家、奥の三畳を書斎にし、念願の書斎もありお気に入りの家であった。この家に母と妹と三人で暮らした時代が最も平穏で幸福な時代であったと辻は後に回顧している。(「書斎」)
このころ吉原の酒屋の娘の御簾納(みその)キンとおたがいに好意を持ち合い、文通をする。また岩野泡鳴の著作を読む。
この年、「音楽界」主宰者の小松玉巌(耕輔)を知り、同誌の二月号から七月号まで、九月号から十二月号で「音のかがみ」を連載。
一九一〇(明治四三)26歳(27歳)
二月 父親死す(井戸にて自殺したとも伝えられている)。
父の墓は染井にあるという。染井墓地か。(「ふもれすく」)
伊藤野枝が上野高等女学校四年に編入。(*1)
野枝は福岡今宿村に生まれ。野枝は自分の望みのためには家族さえ省みなかったというが、勉強がしたくて、この頃東京の叔父代準介の家に寄宿していた。何日も徹夜して勉強し、いとこの代千代子と同じ学年に編入した。(瀬戸内晴美「美は乱調にあり」など)
ロンブロオゾオの『天才論』(L'homo di Genio の英訳、一九〇五年版の The Man of Genius)を本郷の古本屋で入手する。(*3)
この頃、日曜はTという友人と二人で風呂に出かけ、半日は無駄話をして暮らした。「福島にいるTまでも、わざわざ浅草からあの森の中へ引っ張りこんで」とある。Tとは誰か不明。後、辻が染井を離れることになり、Tも東京を離れた、とある。(「のんしゃらんす」六七年の昔染井の森の奥の方にいる時分、とある。)
六月 大逆事件起こる。
一九一一(明治四四)27歳(28歳)
一月 大逆事件の徳秋水ら十二名処刑される。
四月 神経衰弱を理由に精華高等小学校を退職、ただちに下谷区桜木町の上野高等女学校の英語教師となる。月給、4、50円。
国語教師をしていた哲学館出の友人西原和治の世話による。(「ふもれすく」)
または、教頭佐藤正次郎の世話もあるか。(*3)
西原和治は後に宗教色の強い雑誌『地上』(一九一六年二月創刊)を出したりした。(小松隆二『大正自由人物語 望月桂とその周辺』) 後の『天才論』出版の際にも出版社を探してもらったりしたようである。(「おもうこと」)
バーナード・リーチの夫人が上野高女の会話の教師をしていた関係から、バーナード・リーチと知りあう。バーナード・リーチが桜木町にいた時分、時々尋ねたり、演奏会に一緒に行ったりした。(「連環」)
教え子の野枝と知りあう。
かつての教え子であった御簾納(みすの)キンと交際するが、プラトニックなものであった。(「ふもれすく」)
一方で野枝とは朝と帰りを共にし(『東京朝日新聞』一九一六(大正五)年十一月二十一日号の投書記事)、野枝の住む叔父の家にも訪ねたり親しくしていた。(*1)
八月 野枝は夏休みに帰郷し、アメリカに連れて行くという条件で承諾し末松福太郎と(仮)祝言をあげるが、すぐに上京、辻の家を訪ねる。(*1)
野枝の上野高女の授業料はこの婚家から出ていた。(*1)
夏に『天才論』の初めの部分を訳す。((*3)および「おもうまま」)
九月 平塚らいてうら『青鞜』創刊。
一九一二(明治四五/大正元)28歳(29歳)
三月二十七日 前日卒業式を済ませ故郷に帰ることになった野枝と辻は、二人で上野の展覧会に行く。その帰り辻は野枝を抱擁する。野枝はその夜従姉とともに故郷に帰る。(伊藤野枝の手紙「動揺」など)
四月 九州に帰った野枝が婚家に入って九日目に家を飛び出し、上野高女の懇意にしていた教師の援助で上京(この教師に事情は知らせなかった)、辻の家を訪ねる。(伊藤野枝の手紙「動揺」など)
伊藤野枝「出奔」には、野枝が婚家を飛び出し友人の下に匿って貰っている間に、辻と文通し、辻から、汝と痛切な相愛の生活を送ってみたい、という手紙を受け取っていることになっている。
扱いに困った辻は上野高女側と相談するが、野枝との中を学校側から疑われ、教師が嫌になっていたこともあって四月末上野高女を辞職する。(*1、「ふもれすく」、伊藤野枝「動揺」)
六月 巣鴨区上駒込四一一番地にて、野枝と同棲(婚姻届けは大正四年七月)、母光津、妹恒も同居する。生活のために陸軍参謀本部の英語関係の書類を翻訳する。
辻は生活のため翻訳仕事を始め、ロンブローゾ『天才論』は六月から三か月半余りで訳し終わり、秋頃出版予定の筈が、佐藤政治郎に紹介された本屋がつぶれ、その後出版社がなかなか見つからなかった。(「おもうまま」)
野枝は辻に勧められて平塚らいてうに手紙を出し、また訪問する。(「ふもれすく」および(*4))
七月末 野枝は末松家との問題を解決するため郷里に戻ったが、結局らいてうの援助で上京。(*4)
十月ころから野枝は『青鞜』の雑用を手伝うようになり、『青鞜』に文章も書き出す。((*4)、『青鞜』十月号に入社の記事が、十一月号から文章(詩)が出ている。)
十二月 大杉栄が『近代思想』の第一巻第三号に「マクス・スティルナー論」を発表。
辻がこの年または翌年に『唯一者とその所有』を読み始めるようになった(「自分だけの世界」)のは、大杉の記事が契機か。(*3) また木村荘太のところに行った時この本を熱心に読んでいたという。(木村艸太「魔の宴」)
一九一三(大正二)29歳(30歳)
二月十五日 青鞜の第一回公開講演会が神田青年会館で開かれ、野枝も壇上に立つ。(『東京日日』十六日号)
六月八日 『青鞜』紙上の野枝の文章を読み興味を抱いた木村荘太(本名しょうた)が野枝に面会を求める手紙を書く。
六月十三日 野枝は木村の手紙を受け取る。野枝は手紙を辻に見せる。辻は返事を書かなきゃいけないとすすめる。
六月十四日 野枝は返事を書き、辻に見せて投函。
六月十七日夜 木村荘太は、野枝からの返事を受けて、六月二十六日、印刷所文祥堂を訪ねると書き、木村の拠る雑誌「フェーザン」と共に送る。
六月二十三日 朝、野枝は今月は校正を早く切り上げるから二十六日まで掛からないかもしれないという木村宛ての葉書を辻に頼んで、文祥堂に行く。昼過ぎ、木村から電話があり、これから行くと告げられる。午後三時頃、木村が印刷所で校正作業中の野枝を訪れる。野枝と男との同棲は新聞などでも噂になっていたが(『中央新聞』、辻ではなくGとの噂)、野枝はこの時それを否定。木村荘太は、その後野枝に手紙をだし、さらにもう一通の手紙を書く。二十五日まで五通の手紙を送る。
六月二十四日 朝、野枝は辻が出かけた後、木村荘太からの手紙を受け取り、辻と同棲していること、それにいたった事情を書いた手紙を書く。木村からの手紙が来る。家を出て帰ると、辻が野枝の手紙を読んでいて、何ともいえない険しい、苦しそうな表情を見せる。紙と鉛筆をもって、「怒ってるんですか」と野枝が訊くと「僕はなにも別に怒ってはいない。木村氏の手紙は皆気持がいい。ただおまえの昨日の態度の明瞭でなかったのが遺憾だ」と書かれていた。
六月二十五日 朝、野枝に木村からの手紙が来る。帰宅してさらに手紙を受け取る。野枝は、先に書いた文章とは別にとり乱した心情を表わす手紙を書く。
六月二十六日 野枝は二つの手紙を投函。校正から帰ってさらに木村からの手紙を受ける。木村は、野枝からの返事を受けてこの恋愛からしりぞくという返事を送り、その夜さらに野枝と辻宛に自分の気持を述べた手紙を書いて投函。
六月二十七日 朝野枝、木村からの返事を受け取る。その後、もう一度お目にかかることができれば、気持ちがしずまるかもしれないという手紙を書いて出す。
六月二十八日 朝、辻は夕方から南盟倶楽部にある音楽会に来るようにと切符をおいて出かける。野枝、木村からの手紙を受け取る。
木村は野枝からの手紙を受け取り、二十九日か三十日に来てくれるよう返事を書き送るが、この手紙は野枝には届かなかった。
辻は、木村の手紙を読んだ後、自分に見せない手紙を木村に出したかと問うが、野枝は返事をごまかす。
六月三十日 辻と野枝で書いた手紙を入れた袋を野枝が持ち出すと、いやがって片附けろ片附けろといった辻が、今度の事件が起こると持ち出してきては拾い読みしたりしているのを、野枝は勝ちほこったような気持でながめる。
午前に、人が来て、それとなく母がその人のうちに行っている事をほのめかしながら、野枝たちが追い出しでもしたような、すべて、老人の旧いコンヴェンショナルな頭で判断したことをそのまま並べたてて帰っていったのに、辻の妹恒と今夜迎えに行くことを約束。
木村は、昼まで待って野枝が来ないので、来てくれるよう電報を打ち、野枝が来た場合の留守を宿の女中に頼んで、辻の家に赴く。窓越しに辻に会うが、辻はギクッとして苦痛と嫌悪の表情を示す。野枝がいないので、宿に戻った木村荘太は待っていた野枝に対して、自分に来るほうがよいのではないか、といった風に話す。帰って考えると言って午後十時頃野枝は去る。
辻と恒が母を迎えに行く。
辻は、野枝が戻ると紙に書いたものを見せて野枝を責める。黙ってまま横になっている野枝に辻は、お前の心が動いているなら静かに別れようと囁くが、野枝はそれを拒否。
七月一日 その日帰った辻は野枝に「昨夜から苦しくてたまらないのだ。」と話し、自分の心境を書いたものを野枝に見せる。さらに二人で紙に書いて会話し、木村をハッキリ拒絶する勇気があるかとの問いに、ありますと野枝は答える。翌日午前に来てくれと木村が言っていたので、二人で行くことを決める。
七月二日 勝ち誇ったような顔の辻を伴い、野枝は木村荘太を訪問。辻は、昨夜の様子を書いたものを木村荘太に見せる。野枝も辻と離れることはできないと告げる。木村荘太は自分の知らない二通の手紙を知りたがった辻に手紙を見せ、「その手紙に書いたのがほんとうの気持でいながら、こんな行動をとっているあなたなら、僕は軽蔑して捨てます!」と野枝にいい放つ。木村荘太はこのことで文章を書いていたが、へんな噂になるのを避けるために、小説にして発表すると告げる。野枝もまた書くと話す。
(以上、木村艸太「魔の宴」、伊藤野枝「動揺」)
野枝が『青鞜』第三巻八号に「動揺」を、木村荘太が『生活』に「牽引」を発表。
木村荘太は野枝の妊娠に気づかなかったようである。そして随分と長くこの事件の後遺症を引きずっている様子が「魔の宴」には見える。
「魔の宴」によると、この事件が辻が公にその存在を示した最初であった。伊藤野枝の名が有名になるにつれて、辻の方は無能の役立たずというような評判が広がって行ったようである。伊藤野枝の「偶感二三」には「私が私の良人よりも多く名を知られているということのために私達の関係についてしばしば侮辱が加えられる。」「良人にはいつも軽い侮辱の影が投げられている。」とある。
九月二十日 野枝は郷里の福岡県糸島郡今宿村に帰って、長男一(まこと)を生む。
近所に住んでいた福田英子によってアナーキスト渡辺政太郎と知り合う(「ふもれすく」)。
渡辺政太郎は、寺島珠雄『南天堂』によると、一九一七(大正六)年後半、指ケ谷町九二(かつて辻一家がいた隣か)に移り、翌年亡くなっている。
サンジカリスム研究会に顔を出す。
この頃の辻潤をすぐ近所に住んでいた野上弥生子が小説の中で次のように描写している。(「彼女」)
「たゞ一つ彼は決して悪型の人聞ではなさそうだと云ふことだけは思はれました、けれども江戸文明の頽壊した血を受けて、その多くの特徴を備へてゐる上に、彼の私淑してゐると云ふスチルネルあたりの自由主義が悪く影響して、自堕落な、安易な、一種のデカダンであるらしく見えました。彼女との恋愛事件に関して職を失つてからの生活難が、彼のその傾向を著しくさせたのでありませう。且つ精神病者であつたと云ふ父方の遺伝は、彼の容貌にも幾らか現はれてさへゐました。若いのだか年寄りだか分らないやうな、不思議な表情の昏迷、暗い額、長い青い顔をした小柄な身体は、一と目見て彼が陰性の弱い人聞であり、激しい生存競争に飛び込む勇気のない、懼れた厭世家であるやうに思はれました。同時にその厭世的傾向は、都会人本来の素質たる反対の色々な傾向に裏付けられてゐるために、それは真摯な強い執着となる代りに、極めて不徹底な、卑怯な、胡魔化しに変ずる事を免かれなかつたのであります。彼の吹く尺八はいつも悠々と響いてゐました。家賃が滞って家を立ち退かなければならなくなつた時でも。明日のパンを心配しなければならない夕方でも。」
一九一四(大正三)30歳(31歳)
三月 野枝は無政府主義者のエマ・ゴオルドマンの著作に親しみ、ゴオルドマンやエレン・ケイの論文を潤に手伝ってもらって訳し、東雲堂から『婦人解放の悲劇』として出版する。
五月 大杉栄が『近代思想』第二巻八号で、野枝の『婦人解放の悲劇』を取り上げ、賞賛。(伊藤野枝全集年譜)
この頃は、辻夫婦と息子だけで暮らしていたらしい。以前は、母と妹夫婦が一緒に暮らしていたという。(*4) これは、らいてうの証言だが、らいてうが奥村博と駒込の家に引き移ったのはこの年の六月十七日頃。(『読売新聞』六月十七日号)
妹恒の夫は小学校教師で後に死別。(*1) 後の津田光三との結婚は、雑誌『民衆』(大正九・一〇)「消息」欄に「津田光三氏、此程辻潤氏の令妹恒子氏と結婚して、東京府下上落合五〇三に居を構えた。」とある。(*3)
九月 野枝に興味を抱いた大杉栄が渡辺政太郎に伴われて、小石川区竹早町の辻の家を訪問する。(*1、大杉栄「死灰の中から」)
大杉栄と交際がはじまり、野枝は思想上の変化を来たしてくる。
九月ころ小石川区指ヶ谷町九一番地に転居。
(全集年譜のこの転居は疑問である。岩崎呉夫『炎の女』には、婚姻届が、大正四年七月(日欠)とあり、何らかの形で婚姻届を調べたものと思われるが、この時の住所が小石川区指ヶ谷町九一番地となっている。この月に小石川区指ヶ谷町九一番地に転居だと伊藤野枝が『青鞜』第四巻十一号に書いた住所と食い違う。しかし確定できないのでそのままにしておく)
『青鞜』の編集さらに翌年より野枝の要求を入れて、発行がらいてうから野枝に委ねられる。(*4) 『青鞜』の第四巻十号(十一月一日発行)の「編集室より」の目次の署名が、前月のらいてうから野枝に変わっている。
『青鞜』第四巻十一号(十二月一日)には野枝の住所が小石川区竹早町八二とある。(伊藤野枝「編集室より」)
十二月 佐藤政治郎、生田長江、岩野泡鳴、小倉清三郎らの紹介を経て、神田区佐久間町四丁目二三番地の植竹書院から、植竹文庫第二篇としてロンブロオゾオの『天才論』が出版され、反響を呼ぶ。(「おもうこと」)
この年、江渡狄嶺(幸三郎)を知る。
一九一五(大正四)31歳(32歳)
一月 野枝は『青鞜』に「"青鞜"を引継ぐに就いて」を書き、同誌の経営および編集・発行人となる。
宮嶋資夫夫妻が訪れ、谷中村についての話をする。野枝は谷中村に残り、今また水没の危機にある人達の話に興味を抱き興奮するが、辻は、子供の世話もろくにできない野枝の興奮ぶりを冷ややかに見る。(「ふもれすく」など) 野枝は、宮嶋資夫から谷中村関係の本など借りて読んだり講義を受けたりするが、このことが、野枝が辻との思想の違いを認め、やがて大杉に走る契機となる。(伊藤野枝「転機」、大杉栄「死灰の中から」)
月末、野枝はこのことについて意見を述べた手紙を大杉に出す。後大杉は月に一回位辻の家を訪れ、辻とマックス・スティルナーの「唯一者と其の所有」の話などをする。辻は、この本を自分のバイブルだと言って尊崇し愛読していた。(大杉栄「死灰の中から」)
二月 小石川指ケ谷町九一番地の借家に移ったか。(*1)
三月ころ 『阿片溺愛者の告白』を訳し始める。翌年半ばに訳了。(*3)
三月ころ 奥村博(らいてうの愛人)を伴い、サンジカリズム研究会に現われ、会終了後、奥村博の絵の出品されている障子社という展覧会を見るように呼びかける。(宮嶋資夫「人間随筆」及び『青鞜』三月号の「編集室より」に、三日から七日まで、京橋区柳町東中通り画博堂で開かれ、真田久吉、埴原桑喜代、清水太助、奥村博が出品、とある。)
七月末(大杉栄「死灰の中から」) 野枝、出産のため、辻、一を伴い、実家に戻る。半年近く留まる。この長い帰郷は『青鞜』の行き詰まりと、上京費用捻出の困難のせいらしい。(*4)
辻も野枝とともに留まったらしい。「陀々羅行脚」に、今宿の海岸で半年近く暮らした、とある。
八月十日 次男流二生まれる。
夏頃、野枝のいとこと浮気したらしい。野枝は別居を申し入れるがこれは実現しなかった。(伊藤野枝「別居について」)。このいとこは、叔父代準介の娘、千代子ではなく、別のいとこだという。(瀬戸内晴美「青鞜」)
時期は不明だが、母に一時だけ子供をつれて田舎にひとりで行かして貰いたい、辻に自分の生活をもっと正しくするために少し考えたいからしばらく別れてみたい、と話し、双方から承諾を受け、その準備のため働いていたとある。(伊藤野枝「成長が生んだ私の恋愛破綻」)
十二月初め 野枝帰京。(『読売新聞』十二月二十二日号)
十二月 スティルナー「万物は俺にとつて無だ」を訳し、土岐善麿主宰の雑誌「生活と芸術」に発表。
この年(或いは翌年)、岩野泡鳴の妻で青鞜社員の清子の世話で、泡鳴の「プルターク英雄伝」の下訳をする。((*4)および岩野泡鳴の年譜)
アーサー・シモンズの「表象派の文学運動」の下訳をする。
一九一六(大正五)32歳(33歳)
一月 このころ大杉は神近市子とも関係していたが、野枝と会って火が点き、接吻を交わす。(宮嶋資夫「予の観たる大杉事件の真相」)
三月 『青鞜』は以後発行できず、この月で終刊。(*4)
四月末(宮嶋資夫「予の観たる大杉事件の真相」) 野枝は、辻に大杉と暮らす決心を話す。(伊藤野枝「別居について」) 宮嶋資夫が訪ねると「辻は私の顔を見ると、もう駄目だよ、と言つた。野枝の左の目のふちが黒くはれていた。一体どうしたんだい、と訊くと、どうもこうもないさ、もう別れることにきめたんだ。キッスしただけだと言ふがどうだか判るもんか、と言つた。野枝は二児の母だつた。そして下の子は乳呑子だつた。母親は困つたことになりましてね、と言つた。野枝は、私は決して辻が嫌ひぢやありません。けれども仕方がありませんわ、と言つた。」(*6) 翌日、野枝は次男流二を連れ、小石川区指ケ谷町の家を出、大杉の下宿していた番町の福四万館に行く。(宮嶋資夫「予の観たる大杉事件の真相」(*6)) 「ふもれすく」によると辻が野枝をなぐったのは、野枝が家を出た一週間ほど前であるから、宮嶋資夫が訪ねたのは野枝が出ていく一週間ほど前の可能性がある。
四月二十九日 野枝は千葉県御宿村の上野屋旅館に移り、その後流二を千葉県夷隅郡大原町根方の網屋の若松家に里子にやる。(野枝および大杉の書簡、『伊藤野枝全集』小伝)
辻は、上野寛永寺の一室、大西克礼がギョイヨーの翻訳をしていたあとの部屋を借りて移ったが、当分誰も来てくれるなと語った。(*6)
野枝が家を出たことについて、宮嶋資夫に「忘却が何より強い復讐だ」と話している。また、宮嶋資夫と一緒に岩野泡鳴を訪れ、泡鳴が訴訟を起こせというのにも、宮嶋の決闘しろというのにも、ただにやにや笑っていた。(宮嶋資夫「人間随筆」)
野枝が福四万館にいた頃、「一日その頃下谷の寺にゐた辻君を尋ねて、
「あなたと私とだつて何も他人でなくたつて好いぢやありませんか」と云つた。其の時辻君は、
「貴様と○○位なら淫売を買いに行か」と云つてから、
「お前は大杉君の方へ行く時分には一人でなければいやだと云つてゐたぢやないか。それなのに今になつてそんなことを云ふのは大杉君に負けたんだろ」と云つたら、
「いえ私は初めからかうなんです」と強情を張つてゐた。」とある。(宮嶋資夫「予の観たる大杉事件の真相」)
野枝と別れてから、段々遊蕩を覚えはじめた。(宮嶋資夫「人間随筆」)
その後、下谷区北稲荷町三四番地に住む。(*1)
本籍地もここに移す。この家に「英語、尺八、ヴァイオリン教授」の看板を掛け、いわゆる浅草時代が始まる。彼はここを根城にして、「パンタライ社」と称する。
パンタライは「万物は流転する」の意味という。
ヴァイオリンは佐藤謙三の教授、ヴァイオリン、尺八には生徒が集まらず、英語は数人生徒が集まった程度のようである。(*1) 「生徒に五十里、田戸、茂木などが英語を習ひに行った位のものだつた。」彼らはサンジカリズム研究会の仲間。(*6) 生徒の中に、尾崎士郎、矢部周、荒木久平、木蘇穀(毅?)、宮崎丈二らがいた。彼らは前後して高畠の門下となったという。(「連環」)
三島寛『辻潤 その芸術と病理』には、ここで英語を習った河合勇(元朝日新聞印刷局長、日刊スポーツ印刷社副社長)が三島寛に寄せた手紙が載って居る。「わたし(明治三十二年生)が、早大英文科在学中、友人渡平民氏(早死)の紹介で、下谷坂本二丁目の電車通りの裏横町の二階屋へ、英語を教わりに半年ほど夜分に通いました。当時上根岸にあった上野高女の教師をやめた後と思います。ワイルドの〈ドリアングレーの画像〉を教えてもらいました。辻氏の訳読は明快で英語の出来る人だと思いました。当時階下に老母がいて、伊藤野枝のおいて行った赤児の子守をしておりました。...」
辻潤は「いつも孤独を養うことのできる二階のある家をえらんでいた」(辻一「おやじについて」)が、この家も二階家だったことになる。また、辻自身また他の者が書いたものによると、辻潤は夜間にしか書けず、また人前では絶対に書かなかった。これらの傾向は晩年まで見られるようだ。
五月十四日 浅草観音劇場で芝居「どん底」に男爵役で出演、他に監督も兼ねた佐藤大魚(惣之助)、木蘇毅など。(~二十三日 (*1))
この年あるいは翌年、夏の昼下がり、五十里幸太郎が望月桂のやっていた一膳飯屋「へちま」に辻を連れて来て、それからちょいちょい遊びに来たという。(望月桂「忘れがたい人」『ニヒリスト 辻潤の思想と生涯』) 「へちま」については、東京お茶の水下、猿楽町で氷水屋をはじめてから四カ月たった一九一六年九月、望月桂夫妻はその店をたたんで、谷中の善光寺坂に同じ店名で今度は一膳飯屋、つまり簡易食堂を開業した。この店は一九一七年七月頃閉店、とある。(小松隆二『大正自由人物語 望月桂とその周辺』)
十一月九日 大杉栄をめぐる野枝、内縁の妻堀保子、神近市子の四角関係から、大杉が市子に刺され、相州「葉山の日蔭の茶屋事件」として各新聞、雑誌紙上をにぎわす。
この頃、浅草浅草雷門わきの貸席東橋亭で黒瀬春吉主宰の未来派講演会が開かれ、赤ん坊を抱いた辻も話をする。(添田知道「辻潤・めぐる杯」ただし年代ははっきりしない)
この年、武林無想庵、大泉黒石らと知りあう。
この年または翌年、高橋誠一の父と殆ど毎晩のように酒を飲む時期があったが、一を連れて来たという。一を連れてさまよっていたのだろうか。(高橋誠一「辻おじさんとおやじ」『ニヒリスト 辻潤の思想と生涯』)
一九一七(大正六)33歳(34歳)
この年の行動はほとんど明らかでない。辻潤の空白の一年。作品発表もほとんどなく、各年譜がこの年頭は比叡山に上っていることになっているので、記事が抜け落ちている。特に春以降が不明である。
『浮浪漫語』に「浅草漂泊時代(March,1917)」と説明を附けて、一と一緒に撮った写真が掲載されている。また「ふもれすく」に「千束町流浪時代」という別の言葉が出て来るので、千束町近辺を放浪していたか。「シェフトフに就いて」には、一九一七、八年頃は友人の下宿を転々として歩いていた、とある。「あさくさ・ふらぐめんたる」(一九二五年作)には、「六七年前下谷の稲荷町にいた時分は毎晩のように浅草へ出かけた」「経年、千束町辺にゴロゴロしていたときには二十銭あると、私は幸福になれたものだ。なぜなら山二バアに行けば酒二合に肴二品にありつけたから。」とあるが、この年が千束町流浪時代である根拠も薄い。
木村幹に連れられて、佐藤春夫の家を訪れる。(「勉めよや春夫!」)
木村と二人で神田あたりをぶらついた揚句、木村が気まぐれに引っ張って行った。辻に稲荷町に家らしきものがあり、佐藤春夫が麹町の幽霊坂に遠藤幸子と暮らしていた頃で、早春の頃だったろうか、とある。(「勉めよや春夫!」)
佐藤春夫の年譜によると、神奈川県中里村に住んでいた佐藤春夫は、一九一六年十二月に上京して幽霊坂に住み、一九一七年六月に遠藤幸子と別れている。
他には、『天才論』の訂正第六版が四月一日出ている位しか情報がない。(*3)
オスカア・ワイルドの「ドリアングレイ」、アマジュウス・ホフマンの「セラピョン兄弟」を訳したが出版にいたらなかった。(関東大震災で原稿消失(*5 2))気なぐさめに酒を呑み、つれづれなるままに尺八を吹く日がつづいた。
一九一八(大正七)34歳(35歳)
三月 下谷区北稲荷町六番地に移る。(*1)
五月 『阿片溺愛者の告白』を三陽堂書店から刊行。
序の中で、自分は以後一切自分から好んで英文学の本は訳さないだろう、と書いている。(*3)
九月頃 佐藤春夫に二度目に会う。佐藤春夫が『中外』に「田園の憂鬱」を発表した前後とある。時期不明だが、その家で谷崎潤一郎を紹介される。佐藤春夫の動坂と神明町時代によく彼を訪問した。一ツにはあまり遠くない追分の下宿にいたからだ、とある。(「勉めよや春夫!」)
十一月 『響影――狂楽人日記』を三陽堂書店から刊行。
この年、早稲田大学裏の片岡厚(のちの神近市子の夫)の下宿に、しばらく居候する。毎晩のように片岡厚をつれ出しては、あちこちとカフェやバアを歩き回る。片岡厚から紹介されて、はじめてシェストフを知る。片岡厚は気前よく『虚無からの創造』の英訳本を辻に与えた。(「シェフトフに就いて」一九一七、八年頃とある。年代は全集年譜に従った。)
「あさくさ・ふらぐめんたる」(一九二五(大正一四)年十月発表)には、「六、七年前下谷の稲荷町にいた時分は毎晩のように浅草に出かけた。」とある。
一九一九(大正八)35歳(36歳)
春頃、本郷追分、栄林館に下宿。夏下宿料滞納で追い出され、菊坂上の友人木蘇毅の下宿に転がり込む。(*1)
「その頃、私は下谷の稲荷町のお寺の中の一軒家に住んでいた。(略)私のその頃の生活は――今でもかなりだらしがないが――まったくお話にならぬメチャなもので、浅草のグリル・チャメーという酒場を倶楽部のようにして飲酒に耽けり、揚句の果てに役者の真似などやって、とうとう本郷の友達の下宿にころがり込んだ。
その友達というのが奥栄一君なので――(略)その下宿にはその後木蘇君とやってくる。前からいた布施延雄君が帰ってくる」とある。(「仲介役として」)
この頃、一を連れて、石井漠の家を訪れ、母美津が病気で寝込んだため、しばらく一を預かってもらう。一は、幾日もしないうちに「おばちゃん、おばちゃん」と石井漠の妻八重子に懐くようになり、十二階や花屋敷へ連れていって遊ばせた、とある。
「辻は一を八重子に預けて、伝法院のそばのカフェー・パウリスタに入りびたっていた。パウリスタには六区の舞台に出ている役者、音楽家、ペラゴロ、社会主義者、その社会主義者を見張っている象潟署の刑事などがたむろし、一杯五銭のコーヒーで半目ねばる連中もいた。五銭のコーヒー代が払えなければ、伝票をテーブルの脇の釘にさして帰る。後から来た売れっ子のとが役者がその分を払ってくれるから、店でも咎めなかった。
辻は時どき一のようすを見に来たが、昼間から酒を呑んでいるようで、いつも酒の臭いがした。辻に金はなくても、凡俗な生活に反逆して世捨人のように生きている彼には、何人も信奉者がいて、行げば呑ませてくれるのである。
漠も辻があらわれると、十二階の裏手にある「グリル茶目」に連れて行って一緒に酒を呑む、グリル茶目は、評論家であり歌人でもある黒瀬春吉が経営していた店で、入口のわきに「労働同盟会」という看板をかけたおかしな飲み屋だった。伊庭孝、佐々紅華、ピアノの沢田柳吉、杉寛や漠などのたまり場になっていた。...
一ヵ月余りして、健康を回復した辻の母ミツが一を引き取りに来た。」 また、辻は漠の部屋で酔っ払って、押し入れで泊まることもあった、とある。大正七年頃は、日本館の楽屋や漠の自宅まで押しかけるペラゴロだった、という。
(石井歡『舞踏詩人 石井漠』 著者は石井漠の子息だから、父母から直接聞いた話と思われる。この本は辻潤に関する部分に少し不正確なところがある。)
九月 『獄中記』を越山堂より刊行。
十月 下宿料を払わないので下宿を追い出され(*1)、麹町九丁目の武林無想庵の家に居候。
無想庵は二階に居て、辻は階下の一室に暮らす。無想庵とは顔も見なけりゃ口もきかない日が何日もあるという生活。(*6)
十一月 無想庵が借家を出て放浪に身を任せることにしたので、無想庵の紹介で比叡山に上り、宿院にてスティルナーの『唯一者とその所有』の訳業を続ける。(*3) 十一月の半ばごろだと記憶するとある。比叡山に一年あまりいたという。(「妄人のことば」)
十二月中旬 無想庵、来山。宿院からさらに善光院に住む。((*3) 、宮嶋資夫「山上より」(『東京日日新聞』一九二〇年三月一日~五日号))
一九二〇(大正九)36歳(37歳)
一月十日 宮嶋資夫が、下見に来山。十日位留まる。(宮嶋資夫「山上より」および (*6))
二月五日 宮嶋資夫が家族を伴い来山、正覚院に住む。この間に無想庵は山を下りる。(宮嶋資夫「比叡の雪」および (*6))
(宮嶋資夫「遍歴」によると、十二月下見に来山、一月に家族づれで住んだことになっているが、発表が早い「山上より」「比叡の雪」の日付を採った。)
二月十五日頃 辻は、「翻訳したステイルナーの校正をする為めに山を下つて東京に帰つてしまつた。辻の外にもう一人宿院に泊つてゐたKといふ京都大学の学生も、辻と一緒に帰つてしまつた。」(宮嶋資夫「比叡の雪」)
『読売新聞』三月十日の「よみうり抄」に「辻潤氏 両三日前上京目下市内本郷台正修館に投宿中」とある(*3)。
辻は、『唯一者とその所有』の校正は書店側がやって、校正させてもらえなかったと書いているから、辻が何をしていたのかは不明である。(「」)
五月 『唯一者とその所有』「人間篇」を日本評論社より刊行。
この月に伊藤野枝、大杉栄共著『乞食の名誉』出版される。中に大杉の「死灰の中から」等を収める。
この頃から宮嶋資夫を慕って、絶えず色々な人が叡山を訪れる。(*6)
六月七日 神近市子を訪問。
「秋田雨雀日記」六月七日に「午後四時ごろ、神近君を訪問した。辻潤君がいて、三人で八時ころまで快談した。」とある。神近市子の居所については一月一日に「神近君は出獄後、宇井家に寄宿していた」とある。
六月 上旬再び比叡山に上る。(*1)
比叡山で、後に「永遠の女性」「白蛇姫」「ランテンデライン」(ランテンデラインはハウプトマンの「沈鐘」に出てくる妖精(『架空人物辞典』欧米編))と呼んだ、当時同志社の学生だった野溝七生子と知り合う。辻は一見して恋に落ちたとある。(*6) 辻は命懸けで惚れたという。(「陀々羅行脚」) 野溝七生子は「ボーイフレンドの好みだっていってしまえば面食いで、ですから辻潤氏のようなタイプには尊敬こそすれ食指を動かさ」なかった。(矢川澄子『野溝七生子という人』) 一方、宮嶋資夫「遍歴」には、二、三年して、とうとう思いを達したぞ、と叫びながら辻がやってきたとある。辻自身は、「『永遠の女性』ときたらなんとも手の出しようがない。」と書いている。(「陀々羅行脚」)
宮嶋の「ところへ京都や神戸から、多数人が集まるようになつて山の上も騒がわしくなつた。自由人聯盟以来警察の注意もだんだんきびしく、ここにも常尾行がつくようになつたので、延暦寺でも警戒しはじめて、宿院との間もだんだんぎこちなくなってきた。」(*6)
八月 宮嶋資夫は日日新聞の小説連載が決まって、東京へ帰ってからの家を定めるため一度帰京。(*6)
九月 宮嶋資夫は比叡山を下りる。八月末に家族は既に下っていた。(*6)
十月七日 神近市子、片岡(鈴木)厚の結婚披露会に出席。(秋田雨雀「秋田雨雀日記」)
神近市子に片岡厚を紹介したのは、辻という。(*1) 「秋田雨雀日記」には、午後五時から、神楽坂の倉田家で、宮嶋夫妻、遠藤夫妻、大泉、伊沢、尾崎、辻の諸君出席とある。
一九二一(大正一〇)37歳(38歳)
この年執筆意欲盛ん。
『英語文学』の英文和訳の選者となる。
五月二十八日 エロシェンコが上落合の辻の家に遊びに来る。エロシェンコがレコードをききたいと言ったので、居合わせた高橋勝也が近所の犬養健のところに連れて行った。エロシェンコに対し内務省から危険思想を抱いているということで退去命令が出され、この夜淀橋署に検束された。(「連環」および『東京朝日新聞』五月二十九日号など)
十一月 佐藤惣之助の紹介で川崎砂子一八七番地の路次の突き当りの二階建ての家に、母と息子を引き連れて住む。(「文学以外」) それまでは母と一は、新宿区上落合の妹の家で暮らしていたらしい。(*1)
前は落合村にいて毎日火葬場の煙を見て暮らしていた、さらにその前は友人知人の家に寄宿していた。これで、薄汚ない風呂敷包みに原稿紙と二三冊のノートと三省堂発行の古ボケタ英和辞典と尺八とを包んでブラブラと歩きまわる必要がなくなった、とある。地上げをしたボロ長屋で土台がシッカリしていないためか、電車や汽車の通るたびにグラグラ揺れる、とある。朝と昼と晩のケジメがつかなくなり、「寝床はどうかすると、三日も四日も敷きっぱなしで、原稿書きがイヤになると、その上に仰向けにひっきりかえって欠伸をしたり、バットを吹かしたり、天井の節穴を眺めたり、古本を乱読したりする。」(「文学以外」)
この月、川崎に越してまもなく高橋新吉来訪。(『ダダイスト新吉の詩』跋及び高橋新吉「師友」)
高橋新吉の八幡浜商業の先輩、坂本石創が高橋新吉のことを辻に話していた。(*7) 「辻潤の友人の小倉清三郎の妻に、坂本の姉がなったりした関係で、私のことをあらかじめ、辻潤に吹き込んでいた」(高橋新吉「平戸廉吉」)
「綿だけのふとんを被て、辻潤は、ねていたが、鼻下に髭を蓄えていて、ドテラを着て、応対した。家の入口から、奥まで見通しの狭い家だった。鮭の切り身をおふくろに買って来させて、めしを一緒にたべさせられた。」(*7)
ダダを新吉より知り、ダダイストと名乗り始める。(*7)
十二月 『自我経』(『唯一者とその所有』の全訳)改造社より刊行。
この頃、ジョウジ・ムウアの「一青年の告白」を訳し始める。(『一青年の告白』自序、*3)
この頃、稲垣足穂を知る。(稲垣足穂「唯美主義の思い出」)
はたちを過ぎた頃、佐藤春夫と歩いていて、辻潤に出会ったという。稲垣足穂の生まれたのは、一九〇〇(明治三三)年十二月二十六日、佐藤春夫の知遇を得たのが、一九二一(大正一〇)年であること(『新潮日本文学辞典』)から推定。
「さて、はたちを過ぎた頃だった。佐藤先生と、相馬屋紙店の前を神楽坂下に向って歩いていた時に擦れ違ったとんびを着た人物があった。瞬間の印象は「貧乏恵比寿」に見えた。先方の門歯には金冠が光っていたようだが、ともかく、この数日間、歯刷子を当てた歯並びではなかった。」とある。(稲垣足穂「唯美主義の思い出」)
一九二二(大正一一)38歳(39歳)
一月三十一日 この夜、神田の仏教会館における久板卯之助の告別式に出席。久板卯之助は、一月二十二日伊豆山中に写生に出かけて凍死したアナーキスト。出席者は他に、望月桂、岩佐作太郎、堺利彦、伊藤証信、宮嶋資夫、谷口伝次郎ら。告別式後の追悼懇談会は八時半にいたり、臨監の西神田署が解散命令を出した。(小松隆二『大正自由人物語』)
四月 加藤一夫、津田光造らの「シムーン」(第二号から「熱風」と改名。第八号で廃刊)に高橋新吉のダダの詩を紹介する。
六月 『浮浪漫語』を下出書店より刊行。
六月三十日から朝日新聞に発表された「「犬の死」その他」を見ると、この頃は妹夫妻が一階で暮らしていたようである。
七月一日 「労働運動組合」主催の月島での社会主義思想講習会の講師となって、「ダダイズム」についてしゃべる。(*2)
一週間ほどのち、この時知り合った広島の十日市町の洋服屋の娘小島清(きよ)を同伴して、房州の白浜に宮嶋資夫をたずね、同家に滞在する。(*2)
小島清とは、後同棲。
しかし、辻の気持は「白蛇姫」に残っており、辻は肉体関係以外には小島清に興味を示してはいない。婚姻届けは清に一任し結局は法的には結婚するが(辻の渡欧中)、辻に自分の心情を理解されないことは清には最後まで苦悩の源となる。小島清は、うわばみのおキヨ、女高橋、pomme de terre(じゃがいも)とも呼ばれ酒好きの女性であった。(*2) 高橋新吉は「日本のダダ」で小島清をダダイストに数えているが、理由がよく分らない。
小島清の前に「一寸四ケ月程一緒にくらした女があるが――これはその女の里の方で無理に連れ戻ったのだが――やっぱり死んでも僕と暮らす程惚れていなかったとみえてそのまま泣き寝入りになってしまった」とあるが、詳細不明。この女のことは公に書いていない、とある。(「里親」)
九月 浅草区馬道一丁目九番地の黒瀬春吉経営の「パンタライ社」がお座敷ダンス営業のかたわら、「ジプシイ喜歌劇団・享楽座」をつくったので、潤もそこの一員となる。そして春吉作「元始」と歌舞劇「享楽主義者の死」に主演することになり、舞台稽古をしてプログラムまで刷ったのに、その旗上げ公演はお流れになった。
この年、谷崎潤一郎としばしば会う。また岡山のエイスケ・ヨシユキ(吉行淳之介の父)と文通する。
一九二三(大正一二)39歳(40歳)
一月 古賀光二が『駄々』という雑誌を出し、辻のところへ三百ほど送って東京で売ってくれと言って来た。(「陀々羅行脚」)(この雑誌は二号でつぶれたとある。(「錯覚したダダ」)) 前年十一月末に手紙が来て、三度に一度位は返事を出して、手紙の交換をしていた。(「陀々羅行脚」)
一月の末か二月の初め二三日東京に泊まって遅く帰ってみると古賀が来ていた。彼は一カ月余りブラブラなすこともなく金が入ると、酒を飲んで女を買いに行った。(「陀々羅行脚」)
二月十五日(『高橋新吉全集』年譜) 辻の編集で『ダダイスト新吉の詩』中央美術社より刊行。
八幡浜の警察の留置所にいた高橋新吉は、この詩集を受け取って破り捨てたという。(*7) 書名も辻が決め、杜撰な編集でノートの書きさしや未定稿の詩が混じっていて誤植が滅法に多いという。(高橋新吉「ダガバジ断言」)
この頃 吉行エイスケがオリーブ色の鉢巻きをして『ダダイズム』をふりまわして乗り込んで来たらしい。(「陀々羅行脚」)
三月 古賀が三月初めに帰ってから凡そ二十日程後に旅行に出かける。野溝七生子の母親に会うこと、清の実家を訪ねて勘当されていた清の帰参を懇願に及ぶこと、愛媛にいる病気中の高橋新吉を見舞う目的であった。古賀が来いと言っているし、大泉黒石も九州に行く用事があるというので、辻が先に行って黒石を待ち、講演をすることになった。(「陀々羅行脚」)
大阪で辻は降り、清はそのまま広島へ。難波から南海に乗り粉浜で下車し井崎を訪ねる。広島に行き清の実家に泊まる。二日滞在にして清と袂を分かつ。(「陀々羅行脚」)
箱崎神社の傍らの馬出(まいげん)松原添というところの古賀光二の下宿に滞在。(「陀々羅行脚」)
四月四、五日に黒石から九日に東京を発つという電報が来たので、十三日に講演を行うことにし、辻も切符を売り歩く。結局黒石は講演には来なかった。(「陀々羅行脚」)
長崎に行き、黒石の泊まっている本博多町の坂本旅館に押しかける。長崎から天草に渡る。(「陀々羅行脚」)
博多や大分で「ダダ」について単独で講演する。(「陀々羅行脚」「「錯覚したダダ」)
丸善の博多支店でシェストフの英訳本 All things are possible を買う。後に「無根拠礼讃」と題して訳したもの。(「シェストフに就いて」震災前の年とある、震災の年の震災前という意味か。)
日付が不明だが、小島清と古賀光二を伴い高橋新吉を訪ねている。(高橋新吉「師友」)
「土なくもがな」に(三月二十九日博多の松原で)、「脱線語」に(一九二三年四月別府にて)とあるから、別府に行ったらしい。
武者小路実篤に「直接には震災前の年に日向の宮崎で一度お目にかかった。」(「連環」)とあるので、宮崎まで行ったらしい。
「遊びに来た新聞社の人が一緒に訪ねてみないかというので、先生が会ってもいいというなら一緒に行こうといった。二、三日して、その人が来て先生が会うというからというので出かけた。」紅茶を飲んで話した。とうとう「新しい村」へは行かなかった、とある。(「連環」)
帰途、呉に立ち寄り、ダダ展覧会に「面接」。(「錯覚したダダ」)
帰途、松江普門院の住職をしていた中西悟堂を訪ねて、姫路から播但線で松江に行く。見送りの中西悟堂と米子で降り、悟堂の友人の清水寺に一泊、京都を経て帰る。(「浮生随縁行」)
但しこれらの帰途とは、関東大震災後の旅行の帰途かも知れずはっきりしない。
九月一日 関東大震災。
関東大震災で住む家を失い、十日あまり野天生活。母と子供を蒲田の妹に預けて、身重の清を実家の広島に送るための旅に出る。(「ふもれすく」)
九月十六日 伊藤野枝、大杉栄、甥の宗一少年、甘粕憲兵大尉らによって虐殺される。
芝浦から船で名古屋へ赴く。春山行夫、佐藤一英らの若い詩人たちの歓迎を受ける。
辻は名古屋で清を汽車に乗せ、それから二、三日して大阪へ下車し、そこでとりあえず金策にとりかかって一週間程くらし、新聞の号外により甘粕事件を知る。(「ふもれすく」)
軍からの事件の発表が二十四日、記事解禁の二十五日から号外などの形で事件が報道されたという。(時事新聞二十五日号、中島陽一郎『関東大震災』)。
甘粕大尉は後に満州国における重要人物となるが、翌年この事件の報復を企てたアナーキストの試みはことごとく失敗、多くの検挙者を出し、冬の時代を迎えることになる。(小松隆二『大正自由人物語』など)
清は、大阪の辻を追いかけて大阪に行く。昼間なのに清の体を求める。谷崎に会い、清を広島の実家に届け、四国に渡る。(高木護『辻潤 「個」に生きる』)または、辻はその後広島の清の実家に立ち寄ったが、普段とは異なる様子で身重の清の体を求めたという。二日あまり清の実家に滞在の後、伊予八幡浜の辻のファン酒井家に滞在。(*2)
一人で高橋新吉を訪ねる。(高橋新吉「師友」)
十一月一日 三男秋生生まれる(昭和二十年、ルソン島イサベラ州イラガンで戦死(*2))。
十二月六日
小島清の日記(*2)
「浅ましい。実際自分でもはづかしい。ほとんど毎晩続けてのドリーム、何故だろう、生理の関係がしら? 自分では気持の上ではかなり超俗的な、老人、若い老人の気でゐるのだが――
少し頭を使ふとすぐ鼻へいく、近頃又鼻が少しわるい。強いて自分の気持を殺そうとも思はぬが、ツクヅク人間がイヤだ浅間しい。潤からハガキ。本年中に広島へ帰るとの事、そして東京へ帰るのかしら、あまり帰京したくもない
別府の消印、黒蛇と心中でもして了ったら、――かへってサッパリするかもしれぬ。八木から手紙 蒲田は相変らずの生活らしい。
どれも頭が散文的になって困る」
十二月十七日
小島清の日記(*2)
「瓢然と潤がやってくる。東京へ金策に出かけて又暫くは宮崎に落ちてくつもりだと、三月末頃上海へ行く予定だ相な」
十二月十八日
小島清の日記(*2)
「夜一緒に日進会に活動写真をみる、かなり面白かった。今日は家で酒を一合半ほど、活動の帰りにカフェーでホットウイスキーをやる。秋生の頭に悪いだろうとあとで苦しむ。
東京歌劇団の黒川澄子の亭主で潤の従弟にあたる茂木君も貝原旅館に訪(ママ)ふ 五六才頃逢ったきりで茂木君は潤を記臆(ママ)にない。寂し相な顔をした人可成り頭もいいらしい。ずいぶん苦しんできたとの事だ。生きる事の苦しさを潤と話してゐた。ニヒリスティックな色彩をかなり帯びた思想を持ってゐた」
十二月二十日
小島清の日記(*2)
「三時廿分の急行で潤は東京へいく。又正月の始め頃くるのだ。茂木君も見送りに現れる。 出血は三四日前に止った。月経だったのかも知れたい。潤とは一回も をしなかった。若し又すぐにあとでもできられると閉口だから。赤坊はもう一人で沢山だ。十八目に宮崎の湯浅君から私に手紙がきた。赤坊と潤の世話で返事も書くひまもなかった。明日でも出そう。
君子のオヤヂさんが脳溢血でなくなったそうな。近頃はノーイッケツが流行るとみえる」
とあるが、辻潤が四国で正月を迎えたとすると、年内に東京から戻ったことになる。小島清の日記にはそういう記述がないようであるから、小島清には知らせないで戻ったのだろう。
大震災後、よけいに自分の心の落ち着きを失ったせいか、いよいよ放浪癖が激しくなったように感じるとある。(「苦熱の窓」)
一九二四(大正一三)40歳(41歳)
別府の「紅葉館」という旅館の娘辛島キミコや、宮崎県の都城の菊村雪子と懇ろになる。
(倉橋健一『辻潤への愛』には、「九州で仲よくなったお雪ちゃんとは、別府の菊村君子の妹である。」とあるが、高橋新吉の「ダガバジジンギヂ物語」には、辛島キミ、菊村雪子の名が出て来るので、『辻潤への愛』が間違っているのだろう。『野溝七生子作品集』年譜にも、友人辛島キミ(大正十一年東洋大学第一科印哲卒業)、とある。)
一月 四国で正月を迎える。(「こんとら・ちくとら」7)
二月 日向の宮崎に滞在。九州を一巡して宮崎に帰った。高橋新吉が来ていて、四、五日一緒に暮らした。龍潜館という旅館に滞在か。(「ぐりんぷす・DADA」) 但し高橋新吉の「ダガバジジンギヂ物語」には、「辻潤は、私よりも早く、宮崎市を訪れて、遊んで帰ったあとであった」とある。辻潤の記述の方が詳細なのでおそらく辻潤の方が正しいのだろう。「ダガバジジンギヂ物語」には、「湯浅浩という味噌屋の息子が、ダダイズムに共鳴して、手紙を度々よこしていた。」「「辻さんは、僕の恋人を盗ろうとするんだからな」と、湯浅は言った。」とある。
日向で七十何歳かのおすみ婆さんとしばらく一緒に暮らす。(「きゃぷりす・ぷらんたん」)
日向の宮崎から別府の「紅葉館」へ。別府の「紅葉館」の君子は、野溝七生子を通して知り合った。ペルシャの哲学に凝り固まって気がおかしくなった。別府に来ると必ずクンシを訪れて、酒と寝床にありつく、とある。(「きゃぷりす・ぷらんたん」)
「きゃぷりす・ぷらんたん」の日付が四月二十九日で「紅葉館」で書かれてあるようである。
五月 帰京、住処を転々とする。小石川の白山上のアナやダダ系の詩人や文士の溜り場になっていた松岡虎王麿経営の南天堂書店二階のレストランに、しばしば顔を出す。
四月頃 東京市外蒲田新宿三一五番地、松竹撮影所の近所の長屋の橋の津田光造(妹恒の夫)の長屋に落ち着く。二階一間、一階二間の二階を占領。ここには既に母と一が住んでいた。(小島清の未定稿「酒の匂ふ人生図絵」(*2))
以後蒲田で四年あまり暮らし、昼夜顛倒の生活。(「ひとりの殉難者」)
五月 清、秋生と共に上京。(小島清「酒の匂ふ人生図絵」(*2))
この家には、林芙美子が友谷静江と訪問、菊村雪子、野溝七生子、「幻燈屋のふみちゃん」、吉行エイスケらが訪問、高漢容が無銭旅行の途路立ち寄ったという。蒲田撮影所の見物を兼ねて多くのファンが訪れ、津田光造はたまりかねて出家し池上の寺に住み込んだ。清がいるので押しかけて来るわけにもゆかず菊村雪子は、恒と共に佐藤惣之助が二号に出させていた川崎のカフェー、オリオンの女給になった。辻がノイローゼ気味で原稿が書けず、清も麻布のシルバーベルと云うカフェーの女給になった。(小島清「酒の匂ふ人生図絵」(*2))
卜部哲次郎、荒川畔村(関根喜太郎)、木庭孝、室伏高信、百瀬二郎(エリゼ二郎)、宮嶋資夫、大津澗(日→月)山、長谷川修二、市橋善之助、飯森正芳(非職の海軍中佐)、村松正俊、鴇田英太郎、宮川曼魚、尾崎士郎、平林たい子らが出入りする。
この家は戸締まりもせず来客の深夜訪問も許したので、「カマタホテル」とよばれていた。
階下の三畳では、昼間は義郎が八木という弟子と洋服を縫い、この仕立場が夜にはバクチ場となった。(*2)
七月 『ですぺら』を新作社より刊行。
八月 吉行エイスケ、津田光造と共に、信州穂高町の清沢清志家に数日寄寓。
夏、信州のあちこちを歩き回る。清沢清志を訪ね、エリゼ二郎の仮寓しているM市のM家で懇ろな待遇を受ける。源地というところでエリゼ二郎は待っていたとある。(「苦熱の窓」この時、安成貞男が死去したとある。『日本近代文学大辞典』によると、安成貞男の死亡年月日は、一九二四年七月二十三日)
M市は松本市。百瀬二郎は松本市近郊の生まれであった。M家は百瀬家と思われる。百瀬二郎の父は県会議員になって松本市に滞在することが多くなり、市内の源地にりっぱな邸宅を建て後に妻となる女性と同居したとある。ただ百瀬二郎はこの頃までに勘当されているようでもあるが。(小松隆二『大正自由人物語』)
十一月 『一青年の告白』を新作社より刊行。
序に、震災がなかったら去年の暮れあたりに出ていたかもしれない、とある。この原稿は震災では無事だったのだが、イザ印刷にかかろうとした時に原稿百枚あまりなくなっていた。その百枚足らずのホンヤクをするために、この夏を二月あまりも費やした。そのお陰で他になんにもすることさえ出来なかった。とあるから、信州ではこの翻訳をしていたようである。
清は本郷区富士前町の磯辺館に下宿する。同町の詩人岡本潤のおでん屋「ゴロニャ」の手伝いが名目であったが、清はさかんに飲み歩く。(*2 寺島珠雄『南天堂』には、「ゴロニャ」の手伝いを頼んだことはない、とある。)
アナーキスト達の絶望の影響もあってか、辻も同様であり、この頃、女と見れば手を出す。少年を犯すこともしている。(*1) 時代ははっきりしないが、山本正一談として、人の女房でも平気、私の母も押さえつけられたとある。(高木護『辻潤 「個」に生きる』)
十一月二十八日
小島清の日記(*2)
「カフェーオリオン、村松正俊、潤、酔ばらい、なぐられ、おつねさん、秋生、品川よあかしバー、」
十二月六日
小島清の日記(*2)
「朝から呑む。遂に夕方まで呑み続ける 牧野君もくる。のみかつ歌い 夜にいり 又々出かけ 大斉堂とかいうカフェで呑み又、南天堂、大勢ゐる。
誰か辻潤がごろにゃにゐた事を報告する。一寸胸がおどる、逢ひたくもある。今にくるだらうとみんな云ふ、まもなくやってくる。秋生が却って達者になった由をきく 日に五合位牛乳を呑む相だ。案外お互ひに平和なしっくりした気持で話ができた 酔ひもかなり醒めて了った。労連の川口君が送ってくれる。下宿がしまってゐるので、ごろにゃへ泊る。」
十二月七日
小島清の日記(*2)
「潤が昨晩、大久保へ手紙を出しておいた由を話したので大久保へとりに行く。」
十二月十日
小島清の日記(*2)
「朝芋を二つたべた丈で空腹で仕様がないので金はないけどごろにゃに飯を食べるぺく出かける。山内君がゐた 一緒に一杯呑み始める。ほろよいになった頃、辻潤がやってくる 昨晩手紙を書いて出したがみたかと云ふ まだみない。
偶然と云へ 私も昨晩涙のテンテンとした手紙を出したのだ。潤もまだそれをみない。困ってゐるからすぐに荷物を送ってくれる様たのむ。きたらすぐに質屋へいれて金をこしらへねぱならぬから。
明目、ツキヂの小劇場へ行く事を約す。十六日の宮嶋資夫君の弟の總見の切符を買ってくれる。
明日カフェーロシアで待ち合はす事を約す。電車賃がないのでその由を云ふと五円くれる。一文なしの時なのでとてもどきんと胸にきて涙がでる。酔ってゐたので、潤ののった電車の出だしたのを追っかけて泣き乍ら戸を(電車の)たゝいたが遂に打っちゃった。」
十二月十一目
小島清の日記(*2)
「カフェーロシアで五時半まで待ったが来ないので、劇場の前で一時問余り待つ七時頃やってくる。
朝から夜中までをみる。幕なしたので八時半頃すむ。黙々と銀座を歩く 遂に蒲田までついていく。百番のおでん部でのみ、カフェー松竹でのんで、二人とも酔っぱらって帰る。 久振で潤と一緒にねる。」
十二月十二日
小島清の日記(*2)
「秋生がよく肥えた。もう私の事は忘れたらしい。親はなくとも子は育つか 行李がもうチャンと縄がかけてある。
本を二冊かりて私はまた帰る。
潤はこの二三日のうちに旅行するがそれまでにもう一度ゴロニャで逢ふ事を約束。刑事がくる。下宿から、下宿届を出したのに無職とあったのでその為にきゝにきたのだ。
巡査とか刑事とか云ふのはどうしてこう無智もうマイでふ快な奴ばかりなのだろう。明朝 九時までに駒込署へ出頭せよといふ。」
十二月十三目
小島清の日記(*2)
「荷物がくる。駒込署で一時間ばかり冗まんな注意をきかされて帰る。
よる、ごろにゃへ飯を食べに行くと五十里君がゐないので勝盛君が一人で困ってゐるので手伝ってゐる。と宮嶋君が加藤一夫をつれてやってくる。まもなく辻潤がまたやってくる。みんなかたり飲んでシギリに議論し歌ふ 私は呑まないのでつまらない。一緒でみんなで南天堂へ行き、例の如く潤と宮嶋でケンカをやる。
川口が潤を殺すと云ふ。岡本潤が裸になる。面倒臭いので、潤をひっぱって外へ出る.友谷静栄がきてゐた。カフェーとすし屋へよって一時すぎに下宿へ潤と一緒に帰る。」
十二月十四日
小島清の日記(*2)
「朝、顔も洗はづに潤とごろにゃへ行く、宮嶋が昨夜ごろにゃへ泊ったのである。又酒がはじまる。南天堂へ行く。伊藤君がくる。みっちゃんがくる。その他いつもの連中大勢。可なり酔っぱらって、夕方、潤と一緒に川崎へ着物を質にいれに行く。かめさんの処へよる 留守なので前の酒屋で一杯呑み、酒肴持参で市場のおばさんの家へ行く。酔っぱらって潤が私を殴るける。
蒲田へ帰る電車でおつねさんに逢ふ カフェー松竹へよる。」
十二月十五日
小島清の日記(*2)
「秋生がだんだん私を想い出し相なので急いで帰る。潤も出かけるので一緒に出て池上の古谷栄一君を訪ねる。留守。それから九段の北欧新興美術展をみ、呉服橋へ出て、北辰クラフに山口と云ふ人を訪ねる。夕方一緒になだやで一杯のむ、あんこう鍋が素的にうまい。出て銀座をぶらつくと、中村貫一夫妻と宮城君に逢い一緒にカフェーライオンにはいる。トマトとチーズがばかにうまい。室伏高信、鳥山君などに逢ふ。潤はそこに残り、私は帰る。
腹が空いたのでごろにゃへよると、又宮島君や伊藤君がゐる。例の如く南天堂へ行く、酔っぱらってけんかが始まる。血が流れる。電車がなくなる。ごろにゃへ押しかけてみんな泊る。宮嶋、伊藤、山内、中井。」
「十二月十九日、辻潤は京都にいた。キヨにハガキを書いた。二十一日、酔っぱらって下宿に帰って寝ていると、山内画乱洞が預っていた荷物をとりにやってきて、明日、宮嶋資夫らと大阪へたったことを知らせた。一緒に行きたいたあ、と思うと、矢もたてもたまらなくなった。夜中に胃がひどく痛んだ。いろいろ思案したが、出かけることにした。九時四十五分の神戸行急行に乗った。宮嶋、伊藤、山内、しげちゃん、川口。もし、大阪に辻潤が居なかったらどうしようという不安があった。かなり、寂しい気持で出かけた。」(*2)
十二月二十二日
小島清の日記(*2)
「潤公がめつからないので弱る。大阪にゐるにゐるのだが。――昨日富田屋へ宮嶋を訪ねてきた相だから。
加藤氏を訪ねたがまだ来ない相だ。谷崎氏は奈良へ出かけた由、或は一緒かも知れぬ。加藤氏の処に御厄介になる。しきりに寂しさにせめられて困る。こんな弱い事でどうなる。」
十二月二十四目
小島清の日記(*2)
「一日中潤がくるかと心待ちに待っていたが遂に来ない。谷崎さんの処へ行ってみ様と思ったけど処がわからないので行けない。どうする事もできない。どうすればよいのだ。
潤に対する妄執を断たなくてはいけない。もっと大きく、高く、強くならねぱならぬ。
ガスストーブのガスがしきりに私を誘惑する。あの栓をねぢって眠りさえすれば明目の朝までに私は幸福な眠りにはいれるのだ。だが栓をねぢった事を意識してゐてはとても眠れない。
ガスの匂ひがシキリに鼻につく、もれてゐるのではないだろうか?
死 死を決して私は恐れはしない。
岡山のユイスケの処へ潤の事をたのんで子紙をだしておく。」
十二月二十五日
小島清の日記(*2)
「加藤氏と一緒に岡本の谷崎さんの処へ行ってみる。谷崎さんはルス、奥さんに逢ふ。エイスケをつれて一度きたとか。
夜、約束通り、宮嶋氏くる。
宮、みっちやん、川口、久保、富田砕花なと一緒に呑み例の通り。
宮嶋君になぐられる。潤からデンポー
岡山から、――アスコイ、直に返電。」
十二月二十六日、小島清は、翌日正午、岡山に着いて吉行エイスケの家に行った。一泊して広島に帰った。(*2)
十二月二十八日 汽車で朝鮮へたつ。(*2)(*1)
朝鮮の高漢容という青年に招かれて渡鮮、京城に遊ぶ。ある夜誘われて共産党の秘密会合に出席したら、拳銃の乱射騒ぎに遭い、警察隊の出勤となり、一週間穴倉に匿われる。高漢容はアナーキストの一派であった。
高橋新吉が、この年の夏、高漢容の元を訪れている。名が金漢容(キンハンニョン)になっているが、おそらく同一人。(*7)
この秋、上野の戸田正春経営の貸席「三宣亭」に潤を中心に、宮嶋資夫、ト部哲次郎、五十里幸太らダダ系、アナ系の文人たちが集まる「三宣亭」は彼らの溜り場となった。
一九二五(大正一四)41歳(42歳)
小島清は一月四日広島をたち、途中京都をぶらついて、六日朝東京に帰った。(*2)
一月の末に朝鮮から帰る。(「こんとら・ちくとら」)
二月三日
小島清の日記(*2)
「潤はなか/\帰らないし、下宿の払ひはできないので、いよいよごろにゃに厄介になる事にする。カムチャッカ君と荷物を持って、ごろにゃにはいると潤がにこにこ顔で座ってゐる。
南天堂、ブラザーと呑み廻って、ごろにゃのベッドで潤とねる。五十里君は岡本君の処へ行く。
ごろにゃは金がないので、この四五日休業」
三月二十一日
小島清の日記(*2)
「宮嶋さんが三里塚から帰ったので五十里君は戸川町へ行く。勝盛君は四国へ帰る。辻潤がみんなが出かけたあと行きちがいにやってくる。かなり酔っぱらって、ふ快相な顔をしてゐる。私が「横暴だ」と書いた事について、怒る。だが私の生活については可なり心配してゐてくれるらしい。
一時間余りゐて帰る 苦しかった。
だがこの場合、今更もうどうにもならない。手紙を整理して万感こもごも。」
四月 「ゴロニャ」解散後、清は百瀬晋、牧野四子吉、五十里幸太郎の四人で池袋に家を借りて住む。(*2)
六月七日 清は、中野の吉行エイスケの家に移る。(*2)
六月二十三目
小島清の日記(*2)
「廿一、廿二ともモーゼキと幸ベェの処へ泊る。今日中野へ帰宅。
完全に半月ぶら/\遊んで了った。
少し酒をやめて静かに落ちついて、何か書いて売りたいものだ。
私にはつとめなどでき相もない。あれの方も少しやりたいけど中々とりかかれない。
酒をのんでは駄目だ、せめて今年一杯禁酒をし様。
久し振りに机に向って何か書こうと思ってもとんと頭の統一がとれなくてメチャメチャだ。酒をやめ様。酒をやめ様。
幸ベェと一緒にゐればイラ/\して、ケンカをするし、こうしてみんなと離れて一人ゐるとたまらなく孤独にせまられるし、こんな事では何にも仕事なんかできはしないのではないか。
孤独にたへ様、そして何か書こう。みんな誰だって、独り、一人なのだ。サンチメンタルな寂寥などにまけてはならない。
夜中に潤公がやってくる。相変らづ酔っぱらって。どうも酔っぱらひはウルサクてやりきれない。」
六月二十四日
小島清の日記(*2)
「ひるすぎに潤公と一緒に小山さんの処へ行く、ルス、それから萩原さんの処で酒を御馳走になって、みんなで村山知義、川路柳虹をオソッタがみんなルス
あざみでのんで蒲田行 百番にちょっとよる。」
七月 卜部哲次郎、荒川畔村らと『虚無思想研究』を創刊、編集・発行人は日本橋区下槙十二番地、関野喜太郎(荒川畔村)となっている(~八号)。
「ウラ哲や荒川畔村がいなかったら、あの雑誌も出なかったかもしれない。」とある。(「ものろぎや」)
夏、一を連れて、流二のいる千葉県大原に行く。震災前はたいてい毎年行っていたという。(「こんとら・ちくとら」3 「こないだ」のこととある。今朝の新聞に細井和喜蔵の訃が報じられているとあり、細井和喜蔵の死は、一九二五年八月十八日(『新潮日本文学辞典』)。)
九月 激しい喘息に襲われたが、病院に行く金もなく、辻潤の窮乏を救うための「辻潤後援会」が生まれる。(*1)
新居格、大泉黒石、加藤一夫、内藤辰雄、室伏高信、村松正俊、宮嶋資夫、市橋善之助、卜部哲次郎、荒川畔村ら賛成・発起人十人によって、「辻潤後援会」ができ、一口、一カ月一円。期間は十月より翌年の三月までの半年で、佐藤惣之助(一口)、吉行エイスケ(五口)、徳田秋声(一口)、小川未明(一口)、古谷栄一(五口)、萩原朔太郎(一口)、白井喬二(一口)、細田源吉(一口)、生田春月(十口)、加藤一夫(一口)、谷崎潤一郎(十口)、豊島与志雄(一口)、斎藤与里(一口)らがこれに賛成、後援してくれた。
十月から、後援会の醵金により、静岡県藤枝の志太温泉にて静養。
十二月十八日 清、秋生を伴い広島に帰る。(*2)
大正十四年十二月六月の日付の林芙美子の『蒼馬を見たり』の序文に、この三十一日に旅に出ます、とある。
一九二六(大正一五/昭和元年)42歳(43歳)
一月 広島の寿座で、エリアイ・パブロバ一行中のヴァイオリンの演奏を聴く。(「閲覧聴聞月録」 この年『改造』四月号で幸田露伴の「活死人」を読んだ、とあることにより年を確定)
二月二十七日 清、蒲田の家に戻る。清、三月四日から転々。(*2)
三月十五日
小島清の日記(*2)
「蒲田へ報告がてら、着物をとりに行く。飯森さんが上京してゐらして潤と一緒に加藤一夫の処へ行った由。
かきおきして帰宅。」
三月十六日
小島清の日記(*2)
「夕方から、静江さんがみやこのおたけさんを見たいと云ふので一緒に浅草へ出かける。みやこで二合呑むと久しぶりなのでかなり陶然とする。おたけさん!矢張り別嬪だ。だけど肴の「かに」は美味かった。例のまた「中屋」による。三本のむ。そろそろ酔が廻って、先(まず)、うら哲をヲソウ、ルスだ、遂にかまたまで遠出だ
おでん屋のおばさんの処に寄らふと思ったら閉ってゐた。
潤、飯森、ウラ哲がもうねてゐた。綿をシイてねる。夜中にエリゼ二郎がやってきたが、びっくりして帰って行く。」
三月十七日
小島清の日記(*2)
「うら哲はイヤ/\相に店へ出勤する。午後から、潤、飯森さん、静江さん、私の四人で原村の梅林に出かける。四、五年前に行った時は、かなり落ちつきのある古雅な処だったが、ヂシンにやられた故とみえて、すっかり荒廃してコーリョウたる姿に変ってゐる。
ピールを三四本のんで、潤の発議でオンタケヘと出懸ける。古色蒼然、静寂としたおみやだ。傍の妙な家で精進料理を食べる。お酒を四本ほど呑む。ずいぶん大きな徳利だ。潤にあんまをしてもらっていい気持だ。飯森さんは今夜帰ると云ふ。静江さんは弟さんに蓬はねばならないと云ふので、蒲田で別れる。
飯森さんと蒲田駅の前の変なカフェーで別盃をくむ。飯森さんを送ってまたおでん屋のオバさんの処で呑む。潤、シキリに七生公に逢ひたがる。七生公かまだにゐるのだ相だ。腹が空いてゐたので、そばを食って帰る。」
この年、一は静岡県立静岡工業学校入学。(矢内原伊作「辻まことの芸術」年譜)
五月頃(「空々漠々」から推測) 知人の紹介により東京府下荏原郡大岡山に移り住む。それから洋行までの間に四度引越しをしている。(「え゛りと・え゛りたす」) 大岡山に移り住むことになったのは、それまでの家の一年余りの家賃滞納のせいらしい。(「空々漠々」) 六月十五日の住所は、宮嶋資夫宛て書簡によると大岡山一二七(宮嶋資夫著作集月報による)で、パスポートの住所も同所だとすると、いつ四度引越ししたのかよく分からない。大岡山に移り住む以前のことか。
十月二十四日頃 高畠素之の資本論翻訳完成祝賀会に出席。出席者は他に、石川三四郎、小川未明、江口渙、宮嶋資夫、木蘇毅、中根駒十郎。(『読売新聞』十月二十五日号)
一九二七(昭和二年)43歳(44歳)
九月十一日 中原中也に訪問され、高橋新吉に会うよう勧める。((*2)及び『中原中也全集』日記)
十二月 『世界大思想全集』の印税により渡欧を決める。(『万朝報』昭和二年十二月二十一日号、パスポート発行十二月十四日)
「ものろぎや・そりてえる」には、なぜフランスへ行くのか一向ハッキリした理由は発見できない、とある。宮嶋資夫には、「今更外国へ行ったって仕方がないのだが、日本にいたって矢張り仕方がないからな」と話している。(宮嶋資夫「人間随筆」)
一九二八(昭和三)44歳(45歳)
一月一日 「アナーキストの塩長五郎が、作家の吉田金重と訪ねていくと、座敷では津田光造・恒夫妻が居て、酒宴たけなわであった。辻潤は丹前の上に羽織を着て、長火鉢の前に泰然として座っていた。」(*2)
一月十日 銀座尾張町の東側角の「ライオン」にて渡欧歓送会。(*1)
「ダダ」を盗られたと言って、高橋新吉が辻を刺そうと会にやって来る。(*1) 辻は、新吉がその提唱者であるとその場でスピーチした。(「ひぐりでいや・ぴぐりでいや」)
出航の四日ほど前、伊勢の津を経て奈良のH館に泊まる。それから大阪に行ったか。伊勢の津に行ったのは「白蛇」に会う目的もあったらしい。Y市の姉の家に往復の電報を打ったが、旅行中との返事が来た。(「ものろぎや・そりてえる」)
大阪駅前の角屋に泊まる。国鉄の「鉄道アナ」というファン、M、Sなどが、運賃がタダなので集まるなど、二十人以上が泊まった。宿屋の勘定は、長谷川修二にたのむといって船にのった。(玉生清「辻潤の思い出」) 玉生清は、それで辻潤をケチのケチだったと書いている。宮嶋資夫の書くところでは、辻は「俺は猶太だ」とよくいっていたという。「彼は僕等と一緒にどんなに飲み、使ひ(?)あるいても、最後は必ず嚢中に若干の予備金を残してゐるのを常とした。」とある。(宮嶋資夫「人間随筆」)(ケチというよりケチくさいのか。)
出発前日(または前々日)、大阪郊外岡本住まいの谷崎潤一郎から招きを受け、同家で送別の宴をひらいてもらう。美津、一、清、秋生、長谷川修二とともに谷崎家に一泊。(玉生清「辻潤の思い出」その他)
パスポートによると、この時の住所は、東京市外在原郡碑衾大岡山一二七番地。(*2)によると、大岡山三九に住んでいる。
読売新聞第一回巴里特置員として息子一を伴い、神戸港から「榛名丸」にて渡仏。
一を伴ったのは、画家志望の一の希望を容れたもの。(「え゛りと・え゛りたす」)
上海、香港、新嘉披、彼南(べなん)、みんな上陸して見物した。(「榛名丸の三等船室より」)
新嘉披(シンガポール)では、未知のMという人が待って居て、おそろしく歓待してくれた。(「シンガポールの夢」)
四十日あまりの航海でマルセーユに到着。(「ものろぎや・そりてえる」「此処が巴里」)
パリ十四区モンスリ公園街四番地のホテル「デュ・ミイディ」に投宿する。
パリ到着後、ほとんど外出せず部屋の中で読書に過ごす。(辻一「父親辻潤について」など)
最初の一ヶ月位は手紙を書くほかは「大菩薩峠」を読むことに費やす。(「巴里の十日間」「此処が巴里」)
米国のニューヨーク在住のベンジャミン・カッサアスと文通、著作の「きやめれおん」などを贈られる。(「Benjamin De Cassers」)
その後トンプイソアール街一三八番地の横丁の角にある安ホテル「ブェファロオ」の五階(「子供のいない巴里」には四階とある)二十九号室に転宿。(「ものろぎや・そりてえる」「子供のいない巴里」) 禁酒しながらさまざまの妄想に耽ったり、異人の本や中国人の本をヒマにまかせて読み散らかしていた。そうして時々ムダ書きばかりしてくらしていた。(「「ものろぎや・そりてえる」)
パリではトリスタン・ツァラや先に渡仏していた武林無想庵、村松正俊や、少し遅れて渡仏した林倭衛らと会う。また松尾邦之助を知る。
六月 ステイルネルの「唯一者とその所有」、同じく「芸術と宗教」、プレカアノワの「無政府主義と社会主義」(これは辻潤訳となって.いるが、百瀬二郎の訳である)の三訳が『世界大思想全集』二九として、春秋社から出版される。全集は当時の円本ブームにのって版を重ねる。
七月十四日 ソルボンヌ大学に接した広場、オーギュスト・コントの銅像の前で、パリの群集の前でに日本人仲間と大声を張りあげて、「月は無情と言うけれど――」という新ストトン節をうたい、異人たちが目を丸くして驚いているのを尻目に、「奴らにァこの歌の意味がてんで分らんじゃないか。ざまあみろ」といって啖呵をきった。(三島寛『辻潤 その芸術と病理』)
大正十三年の流行歌として、添田さつき作詞および調曲の「ストトン節」、添田さつき作曲の「月は無情」という歌があり、「月は無情」が「月は無情と言うけれど」と始まる。新ストトン節というのは間違いだろう。(『新版日本流行歌史』 社会思想社 1994)
この間に清は辻の家に出た。(*2)
予定の金がなくなり、これ以上ムリをして半年や一年ヨーロッパにいたところで、たいしたこともないと考え帰国を決める。(「西洋から帰って」)
十二月半ばパリを発つ。(「ものろぎや・そりてえる」)
一九二九(昭和四)45歳(46歳)
一月一日 村松正俊と共にシベリヤ鉄道の三等に十数日ゆられ、京城の汽車の中で正月を迎える。(「帰朝漫談」)
一月三日 午前九時何分かに品川駅に着く。(「ものろぎや・そりてえる」)
東京市外荏原郡碑衾町大岡山三九番地に落ち着く。大津澗山をはじめ、相変わらず人の出入りが多く、酒盛りの日々がつづく。
帰国後、ほとんど仕事をしない。(「ものろぎあ・そりてえる」)
洋行してかえってから、ひどく疲れが出て、この年の前半は殆ど毎日ねてくらす。(「ひとりの殉難者」)
二月ころ 大岡山のたった一軒の若い古本屋「無有奇庵」(児玉明人)と知り合い、親しくなりしばしば出入りする。近所住まいの木庭孝、木蘇毅、鴇田英太郎、鈴木義広らと無有奇庵の二階を溜り場にして酒盛りをひらいたり、泊り込んだりする。上司小剣、相田隆太郎、宮前一彦らとも知り合う。
四月 『どうすればいいのか?』を昭光堂文芸部より刊行。
六月 辻の帰国と共に蒲田の家に戻っていた清は、富士前町の磯辺館に移る。(*2)
清は辻の家に出たり入ったりを繰り返すが、松尾が辻と同棲することで決定的に別れる。一方でこの頃から、画家(志望)の玉生(たまにゅう)謙太郎と交際し始めたらしい。(*2)
秋(九月二十九日以降(*5 3))、大家から立ち退きを求められ、母と一は荏原中延一〇八九の義郎の下に身を寄せたらしい。(*1)
十一月 このころ赤坂桧町の乃木倶楽部に萩原朔太郎をたずね、交遊をなお深くし、マンドリンやもしくはギターと尺八の合奏をしたりする。
二、三度たずねたことがある。(「癡人の独語」)
十二月 訳文集『螺旋道』を新時代社より刊行。(ヒュネカア「螺旋道」を除いた訳文は、すべて『浮浪漫語』にも収録)
(この年、マックス.スチルネルの草間平作訳が「岩波文庫」上下二巻<上八月刊、下十二月刊>として出版される。訳者序に「翻訳に当っては、常にバイイングトンの英訳を参照し、二、三この訳本に従った個所もある。また邦訳には辻潤氏のバイイングトンからの訳書があるが、これは、訳者も間々参照して訳語等の上でなお助けられたにも拘らず、決して良訳として推奨しがたいのが遺憾である。本訳書としても、決して自負するに足るものではないが、同氏訳に比べれば、原語訳というだけでも幾分解りよいであろう。もし著者に対して何らかの興味をいだきながら、同訳本によって愈々スチルネル難解の嘆を深からめられた読者があるならば、あらためて本訳書を手にとって頂きたいと思う。訳者などよりも遥かに多く、原著書を愛し、本書の広く読まれることを希望せられるであろう辻氏は、かく申したからとて、恐らく不快のみは感じられないことと信ずる……」とある。)
一九三〇(昭和五)46歳(47歳)
一月二日 卜部哲次郎を伴い旅行に出る。関西を歩きまわる。(「ひぐりでいや・ぴぐりでいや」)
一月二十二日頃、旅行から帰る。(*5 6)
二月 雑誌『ニヒル』創刊(~三号)。
創刊号の発行人は、竹下綾之介。二、三号は辻。
辻は雑誌創刊等のために半年あまり一日16時間働いたと書いている。(「うんざりする労働」)
同月 「辻潤短冊色紙頒布会」がひらかれる。「爐邊の酒を暖む客なきを嘆ずる勿れ 窓外に竹あり数竿 松あり数株」――というものもあった。
五月頃 静岡方面の旅行の帰途沼津に飯森正芳を訪ねて、宮嶋資夫の天龍寺入りを知る。(「Mの出家とIの死」及び宮嶋資夫著作集年譜)
この頃、生田春月の告別式をすませた帰りに牛込の「飯塚」で始めて児玉花外に会って、痛飲する。(「」生田春月は、この年五月十九日自殺して居る。)
十一月 『絶望の書』を万里閣書房より刊行。
お酉様の晩(七日または十九日)オリエントの楼上での石角君の出版記念会に出席。小野好業に誘われたもので石角とは初対面。その帰りに小野好業と観音様に御詣りし、観音経を買う。(「あさくさ・ふらぐまんたる」)
十二月二十日過ぎに東京を離れる。(「迷羊言」)
十二月暮れ 京都で京都女子高等専門学校在学中の松尾とし(季子)を知る。(*1)
松尾とは少し前から文通していた。松尾は佐賀県の武雄出身。松尾は一に「あなたに魂を抜かれた」と言わせた女性である。(*1)
この年、下村海南の娘とも知り合う。
一九三一(昭和六)47歳(48歳)
一月 帰京。机の上に数百通の年賀状が堆積していた。(「迷羊言」)
四月 松尾とし上京し、辻の家を訪れる。(*1) 六月四日までに帰省。(*5 120)
やがて松尾は同棲。(*1)(年月不明)。
六月一日 妹夫婦も同居。(*5 120、ウラ部もまだいると書いている)
八月 このころ銀座尾張町の東側角の「ライオン」に通いつめる。ときの常連に川口K介、室伏高信、宮川曼魚、村松正俊、長谷川修二、岡田竜夫、安藤更生、長岡義夫、小林キン一郎らがいた。店に居合わせた永井荷風にいやがらせをしたりした。
十二月 芝の白金町の山本正一方に寄寓、新年を迎える。
この頃の一家の収入は図案会社に勤めていた一の給料位(月15円程)であった。(後に松尾としは三鷹で教師となる。)(*1)
一九三二(昭和七)48歳(49歳)
荏原郡中延や、目黒区洗足辺りを転々する。
一月 淀橋の画家高橋白日方での「素面」句会に出席、「夜は更けてとうとうたらり鱈ちりや」などの句をひねる。
「とうとうたらりたらりら」は地歌の「翁」の歌い出し。(『邦楽曲名事典』)
二月 荏原中延から洗足に引っ越し母子、義郎と住んでいたが(*1)(二月十日の『やまと新聞』によると津田光造夫妻も同居している)、二、三日眠らずに呑みつづけ、精神に異常を来たし、天狗様になったぞ、羽が生えてきたぞといって屋根から飛び降りたり、町中をおらび歩いたりして、新聞のゴシップ記事になる。青山脳病院の斎藤茂吉博士の診察を受け、しばらく入院する。
この狂気は、『読売新聞』の四月十一日号の記事、山本夏彦『無想庵物語』では脳梅毒によるものとあるが、後に慈雲堂病院の精神科医三島寛(あきら、無想庵の弟)が判断したところでは、常習性酒癖による一過性精神病である。(三島寛『辻潤 その芸術と病理』)
羊狂(狂気のまね)説、コカイン説もある。(*1)
狂気の印象も人により異なっている。辻一は、「辻潤はときどき気が狂った。その度数は次第に重なり正気の期間はだんだん短くなり、しまいに衰耗して狂気と正気の境界が朦朧としてきた。」(「父親辻潤について」)と書いているが、松尾としは、発作はいつも帰省中で、自分には終生狂人ではなかった。強いて言えば羊狂だったでしょう、と書いている。(「辻潤の知人のことなど」)
三月末 東京市代々幡 井村病院に入院。(*5 13 四月二十六日書簡住所が井村病院、「かばねやみ」など)
二月十日の『やまと新聞』に辻潤発狂の記事が出ているので、二月に発狂したのは確実であるが、どうも状況がはっきりしない。
三月末に慈雲堂病院に入院か。慈雲堂病院患者名簿に三月末入院とあるという。(*1) 辻まことの「父親と息子」にも慈雲堂とある。
三島寛『辻潤 その芸術と病理』には、青山脳病院に一ヶ月入院ともある。井村病院に入院する前のこの入院はありそうだが、確実な証拠は見つからない。
小島清の日記(*2)
「四月四日
辻潤、遂に脳病院に入院
卅一日面会に行く 先頃の饒舌にひきかへ非常なカ黙 全く妙に狂人らしくなった(大人しくなった事) 付添人がらんぼうするんじゃないかしら。
もはや再起はむつかしいだろう
四月二九日
二十七目に貞ちゃんと辻を見舞ひに行く。殆んど常人と変りない。これで、もう一ヶ月もはいってゐれぱなほるかも知れぬが、たゞ出てきて、また不セッセイな生活をやれば再発のをそれがある故出てきてからの生き方が問題なり」
『読売新聞』の四月十一日号の「辻潤氏『天狗』になる」という見出しの記事では青山脳病院で診察を受けた後、井村病院に入院して静養していたが、発狂したとある。
辻潤の書いたものから拾うと次のように内容はほぼ一致している。
「まんごりあな」 I病院に入院して四か月。
四か月というのは、月の数を数えたものと思われる。数え年と同じ数え方で、辻潤は月日を数えるのにこの種の数え方をしているようである。
「かばねやみ」 三月末頃発病。I病院に四か月ばかり入っていた。
「自分はどのくらい宗教的か?」 三月瘋癲病院に入院。
病院では暇潰しに少しばかり習字の稽古。患者や看護人に頼まれ、毎日のように画仙に字を書く。(「かばねやみ」)
四月二十三日 谷崎潤一郎、佐藤春夫、田中貢太郎、北原白秋、萩原朔太郎、加藤一夫、佐藤朝山、宮川曼魚、新居格、武者小路実篤、西谷勢之介、中山忠道(中山啓)、安藤更生、古谷栄一、宮嶋資夫、室伏高信、井沢弘、村松正俊、山本正一、ト部哲次郎、津田光造らの世話人で「辻潤後援会」ができ、銀座の伊東屋六階で文壇画壇らの名家揮毫小品即売展がひらかれ、その売り上げ金を静養費の一部として贈られる。
六月初め 井村病院退院。(「変なあたま」)
後大島で二十日ほど静養。(「だだをこねる」)
(この年の斎藤茂吉の日記より辻潤の名が出てくる記事の抜粋(『斎藤茂吉全集』)
五月二十日 辻潤後援會ニ10圓ヲ寄附ス。
六月三日 辻潤ノコトニテ津田氏来ル。
六月十一日 午食后ニ朝日新聞ノタメ、辻潤ノタメニ「瘋癲と文学」十枚ヲ書ク
六月十四日 辻潤君ノ處ノ津田君、(略)来ル。
六月十六日 午前中、辻潤ガ来ル筈ノ處、スデニ大島ニ出発セシ由ニテ来ラズ。眞心ナシ。
七月八日 来客(略)津田光造(辻潤ノタメニ40圓渡ス)
辻潤の狂気については「瘋癲と文学」には次のようにある。
「今年になると、天狗に成りすまし長髪を垂れ長髯を撫して足に草リ(くさかんむり+鞋)を穿いた辻君を見たときには私の如き者でもしばらく言語なくして驚かざるを得なかつたのである。」)
八月五日 松尾とし上京。(*2)
八月十日 小島清自殺未遂。(*2)
この夏を伊勢の津でくらし、名古屋、八月末に能登を放浪する。(「だだをこねる」) また虚無僧姿となって尺八の門付けをする。
九月二日ころ大島から帰る。(*5 126 翌年に分類されて居るがこの年のものだろう)
九月 東京に帰り、中延の津田光造方や、その他の家を転々とする。このころ目黒区洗足一三一二番地に転居。まもなく同一二八五番地に転居。
「かえってから義弟の家にいそってやっぱり毎日ゴロゴロ寝てばかりいた。それから義弟にていよくにげられた」(「だだをこねる」)
十二月二十四日には東京市目黒区碑文谷原町一三一二に居る。(*5 15 書簡住所)弟辻義郎方か。翌年、二月十一日、目黒区洗足一三一二、三月三日、目黒区洗足一二八五から書簡。(*5 16,17)
一九三三(昭和八)49歳(50歳)
能登から帰京してから体の調子が悪く寝てばかりいたが、三月頃より外出して歩き回るようになった。(「まんごりあな」)
五月 このころ目黒区原町の弟辻義郎方にしばらく同居。
七月十四日ころ 名古屋放浪中警察に保護され東山寮精神病室に収容。義郎、一が引き取りに出向く。
八月九日 目黒区原町の大通りを猿又一つで、「日本の農村を建設しろ!」とわめいて歩いているところを目黒署に保護される。
市外豊島郡石神井(現、練馬区関町南四丁目)の慈雲堂病院に入院する。
病院では、男女合せて数百人が一堂に会して、毎朝夕一時間、南無法蓮華経を読誦。(「瘋癲病院の一隅より」)
見舞いに来た知り合いの女を廊下に連れ出し、「おい、いいだろう」「やらせろ」と言ったそうである。(高木護『辻潤「個」に生きる』)
高橋新吉が夏に見舞いに来る。(高橋新吉「師友」)
としの着物全てが勝手に質に入れられたり、共産主義の友人が頼って来たりして、辻の家にいられないと思ったとしは、精神錯乱を疑った一に勧められ慈雲堂病院に四、五日いて、迎えに来た父と共に九州に帰る。としは静養後、教師となる。一九三五年に再上京。(*1)
十一月 清、辻に玉生謙太郎と同棲することを告げる。(*2) 離婚届は、昭和九年九月二十日。(*1)
一九三四(昭和九)50歳(51歳)
四月三日 慈雲堂病院退院。
退院してすぐ、若い友人だった鴇田英太郎(この時故人)の親友の宮城県石巻の松巌寺住職松山巌王に招かれて、上野から常磐線に乗り、夕方小牛田で迎えた石巻の松巌寺の和尚と鳴子の姥の湯に一週間居て、その後石巻の松巌寺に行く。(「天狗だより――又は奇仙洞通信」) 東北方面は縁が薄く、震災後、勿来関から二里ばかり入った「湯の網」で一夏過ごしたことがあるという。この旅についての詳細は不明。湯ノ網鉱泉は、北茨城だから厳密に言うと東北とは言えない。(「かばねやみ」「天狗だより」) 四月半ばより(*5 131)松巌寺で静養。 和尚の書斎を占領し、毎日本を読んだり、手紙を書いたり、タバコをふかしたり、ゴロゴロねたりする。(「かばねやみ」)
四月二十四日 清、辻の母美津と秋生を小田原の津田光造の家に連れて行く。(*2)
六月二十二日ころ 石巻から気仙沼のファン菅野青顔を頼って、同町の観音寺に一週間滞在。
六月二十八日 気仙沼からいったん石巻に帰る。(*5 134)
四,五日して、松岩村尾崎の海光館に二十日ほど滞在。
毎日酒びたりの生活。(菅野青顔の手紙(三島寛『辻潤 その芸術と病理』))
七月二十一日 帰京。豊島区池袋町五丁目二五二番地の向井(山崎)玄宙子方に寄寓。
八月一日 清、玉生謙太郎の長女出産。(*2)
八月 向井方を追い出され、読者の小野庵(保蔵)、傘哲(内田庄作)、我乱洞(山内直孝)らを頼って静岡県藤枝、神奈川県湯河原、小田原辺りを流寓。
八月二十四日(*5 35) 世田谷の太子堂町二三四(三二四か、*5 35)番地槙義衛方に寄寓。
九月十二日 中野区文園町四八 文園アパート。(*5 37)
九月十七日 太子堂。(*5 101)
九月二十日 谷崎潤一郎、佐藤春夫、萩原原朔太郎、新居格、竹林無想庵らを発起人として、新宿角筈の「セノウ」にて「辻潤君全快祝う会」が催される。発起人の他に上山草人ら多数が出席。
十月六日 母美津丹毒により死亡。辻潤、一、流二、秋生、恒、清で通夜。(*2)
十一月六日 小田原を出て、しばしば馬込の玉生夫妻の家に居候をする。高橋新吉や佐藤朝山などが訪れ、貧しいながらも一つの桃源郷であったという。(*2)
一九三五(昭和一〇)51歳(52歳)
一月三日 九州佐賀の松尾の下へ旅立つ。(*2)
どこからか尾行が付いて来て、松尾の家に入るや早速干渉がはじまり、早々に引き上げる。(*1)(キチガイ病院に入ったものは一年とか監視される、と書簡にある(*5 133))
一月十四日 小田原に戻る。(*2)
一月十九日 玉生夫妻の家に居候。(*2)
二月二日 小田原に戻る。(*2)
二月から四月まで、山内我乱洞(または画乱洞)の世話で小田原在中島四一番地に転居した津田光造方に同居。
四月頃 書物展望社の斎藤昌三を訪れ、天狗になった前後から最近までの文稿を一括したから、何処かで出版して呉れるように奔走してくれと頼む。引き請けるものもあるまいし持ち回るのも面倒なので、書物展望社で少部数を出すことになった。(斎藤昌三「陀仙辻潤君」)
五月頃 東京に帰り大森区馬込東二の一〇七一番地の霜田アパートに一と同居。上京した松尾としと同棲。このアパートは一名義で借りたもの。(*1)
ただし、一はやがて行き先も告げず荷物をまとめて出て行った。(「松尾季子「思い出」)
このころ大森警察署に保護され、同区新井宿の竹久不二彦がもらい受けに行く。
五月 玉生夫妻が長女と共に居候(~八月)。(*2)
夏、『癡人の独語』の校正に毎日通う。(斎藤昌三「陀仙人辻潤君」)
八月 『癡人の独語』を 700部限定で書物展望社より刊行。
八月十七日、十八日 神奈川県茅ヶ崎の斎藤昌三の少雨荘で「素面の会」の一泊句会に出席。
九月二十一日 浅草の「三州屋」で『癡人の独語』の出版記念会が開かれ、佐藤惣之助、木村幹、荒木郁子、大津賀八郎、古谷栄一、倉持忠助、曽根彩花、酒井真人、斎藤昌三、石井漠、井伏鱒二、村松正俊、添田知道、ト部哲次郎、矢橋丈吉、尾形亀之助、片柳忠男、山本正一、宮前一彦、山内我乱洞ら六十数名が出席。
十月 飲酒の日々を送るうちに、大森の家は電気、ガス、水道を止められる。(*1)
十一月 松尾と共にファンを頼って塩原甘湯温泉へ行く途中、松尾は駅で辻を見失い、一泊して先に甘湯温泉へ行く。ソルボンヌ大卒というファンの手紙は偽りであり、旅館「霞上館」に宿泊。辻は挙動不審で(錯乱状態か)王子の滝之川警察署に監禁される。一が辻を松尾のいる甘湯温泉に連れて行く。(「松尾季子「辻潤の思い出」)
一と辻は、午前三時何十分に西那須に到着。乗合バスがないので、五、六里の道を歩く。(「ぼうふら以前」)
松尾が甘湯温泉に来て、数日後一と辻に会う。(「松尾季子「辻潤の思い出」)
辻は夜中に旅館をさ迷い出て凍死寸前となる。自殺というわけでもなかったらしいが、何のためにさ迷い出たのか不明。松尾が抱いて暖めて回復。心中されては困るので立ち退きを求めた旅館主から戻り銭を請求して帰京。薄紅梅という銘の尺八をかたに置いて行く。((*1)「松尾季子「思い出」)
半月ほど甘湯温泉に滞在。(「孑孑以前」)
矢橋丈吉などの友人の元を転々とした後、馬込東三丁目五八五(五二五か)の東(あずま)館の四畳半(六畳とも)の部屋に転がり込む。(「松尾季子「思い出」)
十二月末 松尾としは上智大学で英文学を教えていた明石譲寿に頼んで両親に詫び状を出し、父と兄が上京し、高輪病院に入院、二週間ほど昏睡状態となる。この十二月末が松尾が辻潤を見た最後であった。(「松尾季子「思い出」)
一九三六(昭和一一)52歳(53歳)
一月 堕胎同意書を求められたのに辻は「胎児却下願い」を書き、松尾人工中絶(二回目)。((*1)、「松尾季子「辻潤の思い出」)
一月三十日 昨年から風邪をひいていた辻は急性肺炎で倒れ、危篤状態となる。(*5 55) 半月ばかり、生まれてはじめてのような苦痛を味わった。(「消息」)
息子の若松流二は、一から肺炎で寝ている父の面倒を頼まれ、勤めたばかりの図案会社を辞め、同月末より四月末まで、辻潤と二人で東館に暮らす。(若松流二「虚空鈴慕」)
二月十日 松尾九州へ帰る。(*1)
松尾としとは死にいたるまで文通を続け、松尾は最後まで辻の理解者であった。
五月 『孑孑以前』(ぼうふらいぜん)を昭森社より刊行。
六月はじめ 東館を下宿料滞納で追い出される。(*5 138、「妄人のことば」)
六月 伊勢の津市極楽町の今井俊三方に寄寓。(「妄人のことば」「浮生随縁行」)
一月あまり寝てばかりで過ごす。九月末に津を出る。(「妄人のことば」)
九月二十五日 津を出て、大阪に旧友のFを訪ね、三日ばかり滞在。(「妄人の秋」「妄人のことば」)
九月二十七日(「妄人の秋」) そこから比叡山に上り、そこの法然堂に堂宿中の無想庵をたずね、一月ほど同宿。
山に迎えにきた京都の機屋の息子で画家である伊藤健造(三)と山をおりる。
(「妄人の秋」によると、十月二十一日頃、無想庵と二人で下山となっている。)
京都では上京区千本通り一条北入ル、バー「織縁樽」を溜り場となして、やはり機屋の息子の中西倪太郎、村田某、伊藤某、本屋のワキヤ、洋画家伊谷賢蔵、京都大学の田辺某らと盛んに交流する。遊びの軍資金はもっぱら伊藤が算段した。
十二月 一日から八日まで大徳寺で参禅する。上京区猪の熊通り一条下ル中西方に寄寓。中西方から左京区浄土寺石橋町九一番地の伊藤方に移り、そこで年を越す。
十二月二十二日 松ヶ崎のY書房の二階の一室に納まって、日々三度の飯にありつき尺八などを吹き鳴らし、至極太平楽をきめこむ。(「妄人のことば」)
一九三七(昭和一二)53歳(54歳)
二月初め 午前十時過ぎの汽車で二条駅を出て鳥取で降り、I家に一泊。「鳥取にはかねてNを通じて知己になったやはり洋画家のI君の兄さんがいるので、是非立ち寄るようにということで私は下車したのである。」 翌日砂丘見物の後、夕刻上井駅に到着、極楽寺に行く。極楽寺は、暮れにY紙に辻の消息が出ていたというので、未見の詩人のYが久しぶりに葉書を寄越し、この寺に行くことをすすめたもの。(「浮生随縁行」)
二月 七日ころから四月八日まで、鳥取県東伯郡西郷村の前田洞禅(朝陽)住職の日照山極楽寺に滞在。
極楽寺を立ち神戸、須磨、岡山、呉、広島、岩国辺りを転々流寓。
四月の末から大阪の布施延雄方や岩崎鼎方に寄寓。
六月四日 京都市内を菅笠、垢だらけの洋服、女日和下駄姿でうろついているところを西陣讐察署に一日保護される。萱笠に「迷故三界域悟家十方空本無東西何処有南北」と墨字してあった。
六月七日 同市内の松ケ崎京都高工前で暴れているところを下鴨警察署に再び保護される。
六月八日 同市々外の岩倉病院に強制的に収容される。
八月 帰京。淀橋区淀橋七一九番地の木村鉄工所内の西山勇太郎方に寄寓。西山と雑誌「万物流転(パンタライ)」の創刊を計画するも、発行にいたらなかった。
九月 淀橋区柏木一丁目一四二番地のアダチ・ハウス内の一方に同居。
(このころ酒びたりの父親にあきれ果て、まことはそんな父親から逃げ出すことばかり考えたという。)
この頃より、牛込横寺町の路地奥の稲垣足穂をちょくちょく訪れる。飯塚縄暖簾の近所だったからだとある。(稲垣足穂「唯美主義の思い出」 日華戦争が始まった頃とある。蘆溝橋事件が七月七日。)
「彼には然し、私の顔を憶えることなんかどうでもよかったらしい。日華戦争が始まった頃、筑土八幡うらの或る家でひょっくり顔を合わせたが、「このエトランゼは誰かね」と彼は傍への家人にたずねたからだ。でも、これをきっかけとして、彼はちょくちょく横寺町の露路奥に私を訪れるようになった。飯塚縄暖簾の近所であったからだ。」(稲垣足穂「唯美主義の思い出」)
一九三八(昭和一三)54歳(55歳)
一管の尺八、菅笠、頭陀袋、腰に手拭い、下駄――姿の放浪の旅がつづく。
一月 小田原で半月ねこむ。(*1 菅野青顔宛書簡、別の手紙の中で前年末から二十日ねこんだとある(*5 67))
一月二十八日 蒲田区南南郷一の二八 (*5 114)の玉生一家のところ(六畳一間)に居候。(*2)
三月二十五日 玉生方から、鶴見へ行ってもらう(妹、恒のところか)。(*2)
四月五日~十八日 蒲田の玉生方に居候。(*2)
四月十九日から月末ころまで、横浜市外生麦町一七〇七番地の津田光造方に寄寓。一時休息の後、また放浪くらしに徹する。
七月某日 鶴見の恒のところにいた、とある。(*2)
一九三九(昭和一四)55歳(56歳)
二月 小田原を経て、静岡県地方を流寓。同県庵原郡松野村南松野の東光寺に、坊主になったト部鉄心(哲次郎)をたずねる。
五月ころ 大森の一方に同居。一は同居をいやがっていたという。(「癡人の手帖――その二」)
八月 大森区新井宿二丁目一六四七番地の一方に同居する。
同区馬込の添田知道方にしばしば顔を出す。
秋から淀橋の西山勇太郎方に寄寓。(*5 72)
京都、大阪、鳥取、岡山、広島を流寓。
十二月二十五日 東京から京都へ。(書簡の中で二十五日こちらに来たとある(*5 69))
京都では嵯峨野在住の岡本潤をたずね、「生きてたって、ちっともおもしろくもねえな、天皇ヘイカバンザイでも唱えて、高いビルの尾上からで飛びおりて見せてやろうか…」とこんな話をする。
岡本潤のところで二、三泊。数日後、西陣讐察署に保護され、ファンの織本糸遊が貰い下げに行く。(岡本潤「よみがえる辻潤の魂」ただし年代不明となっている、昭和一二か。)
京都の伊谷賢蔵方や文房具店の脇屋方に寄寓。大阪の岩崎鼎方に寄寓。
一九四〇(昭和一五)56歳(57歳)
京都で新年を迎える。京都市外大原村の小松均方に寄寓。
三月末 帰京。(「癡人の手帖――その二」) 荻窪署員付きで淀橋の西山勇太郎方に。この荻窪署員は落ち着き先確認の送り届け。警察署員付きの方が訪ねやすいという意味もあったか。(寺島珠雄「辻潤 晩年の一断面」)
杉並区上荻窪のサラマンダー荘に寄寓。(「癡人の手帖――その二」) 「交友観」によると飯森正芳方か。
小田原小田原の山内直孝(我乱洞)方に寄寓後、伊勢の津の夾竹桃荘に滞在。(「癡人の手帖――その二」)
また藤枝の志太温泉元湯に遊ぶ。
五月 「オール女性」No,74号に「大原だより――ふらぐめんた」を発表、それに「自分は一道の光明に浴することが出来、登るべき道を発見することが出来たのだ。私は今や最後の高峰?に辿りついて、ホッと一息ついているところである」と書いている。
八月はじめ、ふたたび京都を流寓、大徳寺聚光院に二、三日寄寓。
九月一日ころ津の今井俊三方に寄寓。(*5 78)
九月末に帰京。豊島区駒込三丁目三六二番地の五月堂の食客。
(この九月、寄寓先の我乱洞の手引きで、小田原のうなぎ屋「川治」で三好達治、坂口安吾らと会食する。)
十月 小田原の山内直孝(我乱洞)方に寄寓(二階の一部屋を占拠、直孝夫人に上げ膳、下げ膳をさせた上に、酒がついていないと文句をつけ、反対に「ろくでもなしの居候は居候らしくしとれ!」と、こっびどく叱りつけられる)。
我乱洞の家は子供が六、七人に両親がいる家であった。(松尾季子「思い出」)
二階でごろごろして、大の男なら働かんかいと婆さんに毒づかれていたという。一方で、我乱洞の家の前に乞食みたいな母子連れが通るのを見て、我乱洞に幾らか出させ自分でも出して、僕は坊さんです、これであったかいものでも食べなさいよと、一銭銅貨を二、三枚与えたそうである。(高木護『辻潤「個」に生きる』 但し年月の明記はない)
また東京の五月堂にしばらく寄寓。
十一月 横浜市鶴見の津田光造方に寄寓。
十月から十二月にかけて、淀橋の木村鉄工所内の西山勇太郎方にしばしば顔を見せる。
この年、稲垣足穂と交際。(*1)
稲垣足穂の辻潤評価は、『一青年の告白』と『阿片溺愛者の告白』の訳者としてしか認めないであるという。(『稲垣足穂読本』)
「その晩年には、二ケ月にわたって、新宿から夜更けの一時二時頃に、歩いて、私の三畳まで泊りにやってきた。そして決ったように、毎晩古本の英書を二、三冊仕入れてきては、そうでなくとも狭苦しい畳の上につみ上げるのだった。どれもこれも、片隅の、無気力な、ひねくれた蕈(きのこ)のような文学書で、さすがの私も、「なぜもっと堂々としたものに目をつけないのか」と歯がゆく思った。それに彼が聞かせることと云えば、やれ茶碗蒸で一杯やりたいとか、板ワサがどうだとか、いったい鮨というものは……というような講釈ばかりである。「音楽家はめくらで、画家は唖で、文学者はつんぼだと云ってよいならば、革命家には横着者が多い。あなたも一種のぐれ者だから、温泉旅館で、風呂から上ってきて、手拭を欄干にかけて、畳の上に置かれているお膳とお銚子に向うような所が多分にある。あなたの先生が青柳有美だということは先日初めてきいたが、成程と思った。抽象的なこと以外に熱中するのは病気乃至薄志弱行の兆候だと云うことがあるよ。Shame on you!」とやると、辻潤は、「アイフイールシェーム……」何とか洩した。私は、エーセスィートの末路を眼前に見せられたような気がして、自分もこんなことになったら大変だと、今さら反省しないわけに行かない。彼は明方、小鳥が啼き出すのを合図に、愛玩の尺八を腰に差して出かけて万世橋辺りまで流して、得たところの金銭のうちから、二円なり三円なりを私の飲代としてくれるのであった。ちなみに、私の三畳には夜具がなかったことを知って貰いたい。(私は、日華戦争が始まった頃から、京都住いをするようになる迄、即ち一九三七年から一九五〇年まで、夜具無しで過した)
明けて正月二目、彼がまたもや、「祝おうじゃないか」と云って、外から三畳の磨硝子の戸に手をかけた時、それは開かなかった。私は返事しなかった。鍵がかけてあった。辻潤とはそれっ切りである。――でも、貧乏エビスは本物であった、と私は思っている。」貧乏エビスとは辻のこと。(稲垣足穂「唯美主義の思い出」)
一九四一(昭和一六)57歳(58歳)
四月 淀橋の木村鉄工所内の西山勇太郎方にしばらく寄寓。同月二十、二十一日ころは杉並区辺りを転々する。
六月 東京のあちこちを転々とする。大田区馬込の添田知道、尾崎士郎、室生犀星ら方にもしばしばあらわれる。また木挽町五丁目の片柳忠男、戸田達雄、矢橋丈吉らのオリオン社や、その出版部をたずね、尺八を吹いて聴かせる代わりに昼飯をおごらせる。
七月 大阪を転々する。
八月 七日から津市極楽町の今井方に寄寓。
十一月 小田原の我乱洞方に寄寓。
十二月五日 小田原を出て気仙沼の菅野青顔方に、手足にヒビをきらし、汚れきった十徳姿で訪れる。(菅野青顔の手紙(三島寛『辻潤 その芸術と病理』))
青顔の家は、家族が十人で、一階は六畳の茶の間に八畳の店(青顔の妻がミシンを踏んだ)、二階は八畳間で、辻は昼間は二階の部屋にこもって読書の生活を送る。夜は青願ら妻子と雑魚寝同然の明け暮れを送った。(菅野青願「我が人生の教師よ」及び三島寛『辻潤 その芸術と病理』)
十二月八日 英米への参戦を聞き、青顔の勤務先の図書館を訪れ、日本の敗戦を予言する。(菅野青顔の手紙(三島寛『辻潤 その芸術と病理』))
(辻は戦争反対を公言したらしいが、取るに足らない人物として警察の追求を免れたらしい。(*1))
十二月三十日 同地の河原田の画家広野重雄方に寄寓。
一九四二(昭和一七)58歳(59歳)
一月十五日まで広野重雄方、十六日から菅野青顔方、三十日から二月三日までふたたび広野方に寄寓。
二月四日 気仙沼を離れる。
二月五日 一まず横浜市御見北寺尾一五〇九番地の津田光造方に寄寓。(*5 80)
東京の新婚早々の風間光作方に泊り込んだりもする。
四月 淀橋の西山勇太郎方に寄寓。また蒲田区南六郷一丁目二八番地の玉生清方に寄寓。
大田区新井宿二丁目一六四七番地の竹久不二彦(竹久夢二次男)方に孫の野生(ノブ)(一と無想庵の娘イボンヌの間に生まれた娘、子のいない不二彦夫婦が養女として育てていた)に会いにきて泊り込む。
七月 ふらりと放浪の旅に出る。京都、大阪を経て、十月の初めごろから奈良県添上郡柳生村の橋本定芳住職の芳徳寺に滞在。
十二月 中旬ごろ京都を四、五日ぶらつき、また芳徳寺に帰る。
一九四三(昭和一八)59歳(60歳)
昨年の十月から柳生の里の芳徳寺に在って、『唯一者とその所有』以来に翻訳意欲をそそられたというA・キャノブィッチ『美への意志』を完訳し、昭森社で出版されることになったが未刊(原稿は戦災で焼失)。同寺には七月六日まで滞在。
七月 七日ころから、定芳住職の好意と松尾とし子の仕送りで但馬の城崎温泉の地蔵湯に遊ぶ。宿は同温泉の「つばき屋」。
七月十五日ころから横浜市鶴見区北寺尾一五〇九の津田光造方に寄寓。
津田光造は辻を貧乏神と呼んでおそれ、辻を避けて台湾に行ったという。(玉生清「辻潤の思い出」)
八月 淀橋の西山勇太郎方に寄寓。また新宿旭町のドヤ街の冨田屋別館をしばらく宿にする。
門付けの道すがら、中西悟堂をたずね、ご馳走になる。
九月 このころしばしば松尾とし子の縁つづきの目黒区自由ケ丘の石井漠方に出入りする。漠夫人にユダヤ人とジプシーに関する原稿や、伊藤野枝の形見の品などが入っているという、小さな柳行李をあずける。大森の矢橋丈吉方にも寄寓。
十月 小田原の我乱洞方に寄寓。
十一月 西山勇太郎方に寄寓。同月の中旬ごろから奈良県の柳生の里の芳徳寺、広島を流寓。
十一月 京都の大徳寺を寄寓。(*5 105 十五日書簡)
この年、金子光晴と交際。
金子光晴「江戸っ子潤さん」に次のようにある。
「洗いざらしのひとえものに、尺八一本もってあてもなくふらついていたとしても、辻潤が、身一つをもてあましていると考えるのは早合点だ。(略)死ぬ一年前まで、僕は、毎週のように彼とあっていたが、どうして彼は、応分に生きる張りあいある人生をおくっていた。
としよりになったが、彼は、むかしの俤を失わずに、なかなかいろ男だった。彼もよくやって来て、一ねむりしてかえったり、のろけをきかされたりしたが、僕のほうからも、彼のいた自由ヶ丘のアパートヘでかけていった。
あの部墨はひどい焼けだたみで、ケバ立って、西日のつよくあたる部屋で、夏のことで二人ははだかになるよりしかたがなかった。(略)はだかで寝ながら話をきいていると、江戸のお店の旦那衆とかわりがなかった。それからもっと、江戸っ子の矛盾、江戸っ子のおやじ気質――彼は、むかっぱらを立つ。いたって条理は立っているのだが、ときどき、キイッと、曲り角の自転車の急ブレーキのようなきしみを立てる。よっぱらいの妻君のなれ初め話を、十度もきいた。いまでもときどきゆくらしい。むかしの好人の話がでるとき、彼は少なくとも三十台になる。自由ヶ丘のアパートのへやは、悴と悴の嫁のイボンヌが支那へたったあとのへやで、乱暴ローゼキのままの上に異様な臭気がつよい。どこかすえたそのにおいは、屍臭に似ている。(略)もう、なにも食べもののない時代で、配給もなにもない彼はどうしているのかときくと、ファンがいると言った。松島へゆくと、寺で彼を待っててくれるのだが将軍様のお膝元はなかなかはなれられないと言う。自由ヶ丘はまだ、田園らしい空気があった。パリヘ行っても、見物もせずに、そのままかえってきたくらいで、彼は、放浪や異国とは縁が遠い。白い木の橋のかかった川のふちをあるきながら彼は黒石の話をした。オンマー・ハイアムと、北氷洋のほら穴の話をした。それがまた、いつかしおらしい愛人の話になった。辻の女性は、どれがどの女なのか、それこそ分裂症状的に話がごたついて、現在と過去のけじめがつかない。ぶなの木の下の木椅子に腰をかけると彼は、ふとい息をついて言う。
「死ぬときはね。死ぬときはうなきを食って死にてえ」
(略)
そんなことがあってから二度程合っただけで僕は疎開してしまった。終戦後に彼が死んだときいた。(以下略)」
金子光晴「詩人」にこの年の疎開について次のようにある。
「「この戦争では犠牲になりたくない。他の理由で死ぬならかまわないが……」
そんな意地っ張りから、あわただしく荷作りして、トラックで送りつけ、十二月はじめ頃に、すでに雪にとざされた平野村の家に辿りついた。」
この年、高校生の吉行淳之介に自作の詩一編を五〇銭で売りつける。後で再び訪れあまり安い、もっとくれと言ったそうである。(吉行淳之介「窮死した詩人との出会い」)
この四行の詩は「かばねやみ」中にあるナンセンス詩(しりとりうた)の一部を少々変えたもの。昔作ったものを思い出して書いたのだろう。
吉行淳之介「辻潤から買った詩」には、和紙に枯れた見事な字で詩が書いてあった、とある。
みなとは暮れてルンペンの
のぼせ上がったたくらみは
藁でしばった乾しがれい
犬に食わせて酒を呑み
(辻潤の代表作だな)
吉行淳之介全集年譜によると、吉行淳之介は、一九四二(昭和一七)年、静岡高校に入学。翌一九四三年四月心臓脚気と偽って休学、帰京、とあるから、四月以降の話なのだろう。
一九四四(昭和一九)60歳(61歳)
この年のはじめ萩原朔太郎の手紙を西山勇太郎に三円で売りつける。「顔面に、むくみがあり、あの清純な聡明を思わす眼ににごりが現われていた。」(「辻潤氏から金参円で買った萩原朔太郎の手紙」西山勇太郎)
一月 浅草の木賃宿に泊まる。しばしば野宿。(*1 一月二十六日 松尾とし宛書簡)
一月末 淀橋区上落合一丁目三〇八番地の静怡(せいたい)寮に住む。(このアパートの管理を友人の小田原の桑原国治がやっていた)(*5 154)
二月十五、六日、千葉県大原町根方の若松方に寄寓。九州の久留米市在の松尾とし子に再々無心する。
二月十八日まではいたらしい。(*5 161)
三月末から六月まで宮城県石巻港新町の松山巌王住職の松巌寺に滞在。ジェムス・ハネカアを訳したり、気仙沼の菅野青顔から借用したバイイングトンの英訳本によって『自我経』の誤訳訂正などをする。
寺の物置小屋にくっついている三畳の部屋に起臥。(「続水鳥流吉の覚書」)
七月 帰京。空き家同然の静怡寮に住みつく。
松尾とし子や我乱洞らに食い物などを送ってもらったり、届けてもらったりする。
十一月二十四日 静怡寮で虱にまみれて死んでいるのが桑原夫人により発見される。警察医は狭心症として処理したが餓死とも言われる。(*1)
十一月二十七日(*2) 弟義郎、流二、桑原夫人により火葬。(若松流二「虚空鈴慕」)
染井(現豊島区駒込六の十一)の西福寺に葬られる。
--------------------------------------------------------------------------------------
[ホームページに戻る]
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
