男が手を出す時 『それから』夏目漱石
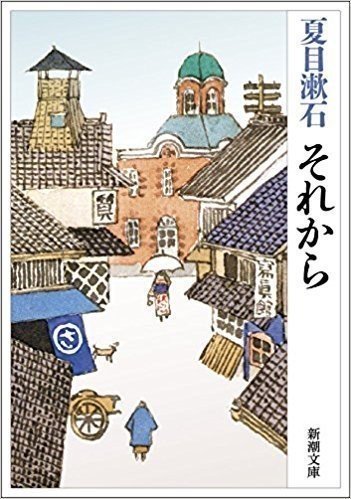
「それから」は、漱石の三部作の真ん中に位置する。新潮文庫版の解説によれば、「三四郎」のそれからが、「それから」であり、「それから」のそれからが、「門」ということになる。1908年の9月から1910年の6月までの2年間に、それぞれ半年間のブランクを空けつつも、通底する主題をもった作品を三作も連載し続けたのだから、漱石の生産性はたいたものだと思う。
個人的な読書体験でいうと、「三四郎」は高校時代に読み、「それから」は20代に映画(松田優作が代助、藤谷美和子が三千代)を観た後に読んだ。「門」を読んだのは40代になってからであった。期せずして、それぞれの主人公の年齢とほぼ同じ頃に読んだことになる。
今回は、「それから」をしっかりと再読した後に、「三四郎」と「門」もパラパラと斜め読みした。せっかくなので三部作を比較するレポートを書いてみたい。題して、“男が手を出す時”である。
お読みになった方はおわかりだと思うが、「三四郎」は “手を出せなかった(出さなかった)男”の物語である。
熊本から上京した三四郎は、その道中で、ひょんなことから妙齢の女性と同じ部屋に泊まることになる。女性は、思わせぶりな態度を三四郎にみせるが、実直な田舎青年である三四郎は、「手を出すこと」なく朝を迎える。出発に際して、女性は三四郎に「あなたはよっぽど度胸のない人ですね」と言い残して別れていく。
物語の冒頭で展開されるこのくだりは、、肝心なところでもう一歩踏み込めない三四郎の性分を象徴しており、この本を通して貫かれる主題とも言える。
当時にあっては現代的で魅力的な女性美穪子に対しても、互いの好意をなんとなく感じ取り合いながらも、最後のひと押しが出来ぬままに終末を迎え、美穪子は別の男性のもとに嫁いでしまう。三四郎はあっけないような形でふられ、物語は終わる。美穪子との恋愛が始まるのかと期待をさせつつ、恋愛が始まる前に終わってしまう。
かなり乱暴にいえば、三四郎は「手を出すべき時に手をだせなかった男」であり、「三四郎」という小説は「何かが起きそうでいて、何も起こらない物語」である。
「それから」は、かつて好きだった女性に「手を出せなかった」男が、親友の妻となった女性と再会することからはじまる。代助は三千代が幸せな夫婦生活を送っていないことを知るほどに思いが募り、ついにはそれまでの彼の人生とは不似合いな略奪愛を繰り広げる。
親友も、家族も失ってしまうこと、自分がもっとも忌み嫌っていた“食うために生きる”という俗世間に身を投げ出さねばならないこと、に逡巡し、悩みながらも、すべてを承知したうえで、代助は三千代に「手を出してしまう」。それが、彼の選んだ道であった。
代助は三千代にどうやって告白するのか、父親とどう決別するのか、平岡には何をもって対峙するのか、物語の終盤に向けて、いくつかのクライマックス場面が期待され、その期待通りの場面が描かれていく。漱石の本で、小説のクライマックス的な場面がちゃんと描かれているのは珍しいのではないだろうか。
それが、「それから」の小説yとしての面白さかもしれない。
いわば、代助は「手を出してはいけない時に手を出してしまった」男であり、「それから」という小説は、「何か起こりそうで、しっかりと何かが起きた物語」といえるかもしれない。
ただ、個人的な感想を言えば、三千代は、代助が、そこまで大きな代償を背負って自分のものにするほど魅力的な女性にはみえない。ただ思わせぶりに待つだけの女性のように思える。
大きな代償を引き受けてまで愛を貫いたといえば男らしいのかもしれないが、私には、代助が背負った負債の大きさが気になって仕方ない。
そんな私の心配を漱石も抱いていたようで、いうならば、「門」は、「手を出してしまった」代償によって、主人公がじわじわと追い詰められる,物語である。
追い詰められる主人公は宗助といい、親友から奪った妻は御米である。二人は崖の下の家に、ひっそりと暮らしている。人妻を、しかも親友の妻を奪ったという事実は、明治にあってはとてつもない禁忌で、越えてはならない一線を越えてしまった二人は、精神的負債という見えない責任を背負い続けて生きている。
崖の下の家という環境設定が、負債の大きさを感じさせる。
夫婦で静かに生きていた二人の前に、ひょんなことから、かつての親友安井の影がちらつきはじめる。その影が大きくなるほどに、宗助は少しずつ自分自身に苦しめられる。挙げ句の果てに、円覚寺の門をたたき、禅の教えにすがろうとするが、それもかなわない。
安井は、どういう人間になって宗助の眼前に現れるのか、宗助は彼にどう向き合うのか、「それから」と同様に終末に向けてクライマックスを期待させるが、安井は登場しないまま、物語は唐突に終わる。
一節には、胃潰瘍に苦しんだ漱石が、これ以上書き続ける体力をなくしてしまったと言われるが、尻切れトンボ感は拭えない。小説としては山場にかけた失敗作といわれても仕方ないであろう。
いうならば、宗助は、「手を出してしまったつけを生涯背負い続ける男」であり、「門」という小説は、「起こるはずであった何かを、はぐらかしてしまった物語」である。
「手を出すべき時に手をだせなかった三四郎」
「手を出してはいけない時に手を出してしまった代助」
「手を出してしまったつけを生涯背負い続ける宗助」
いずれにしろ、男が手を出すタイミングというのは、難しいものである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
