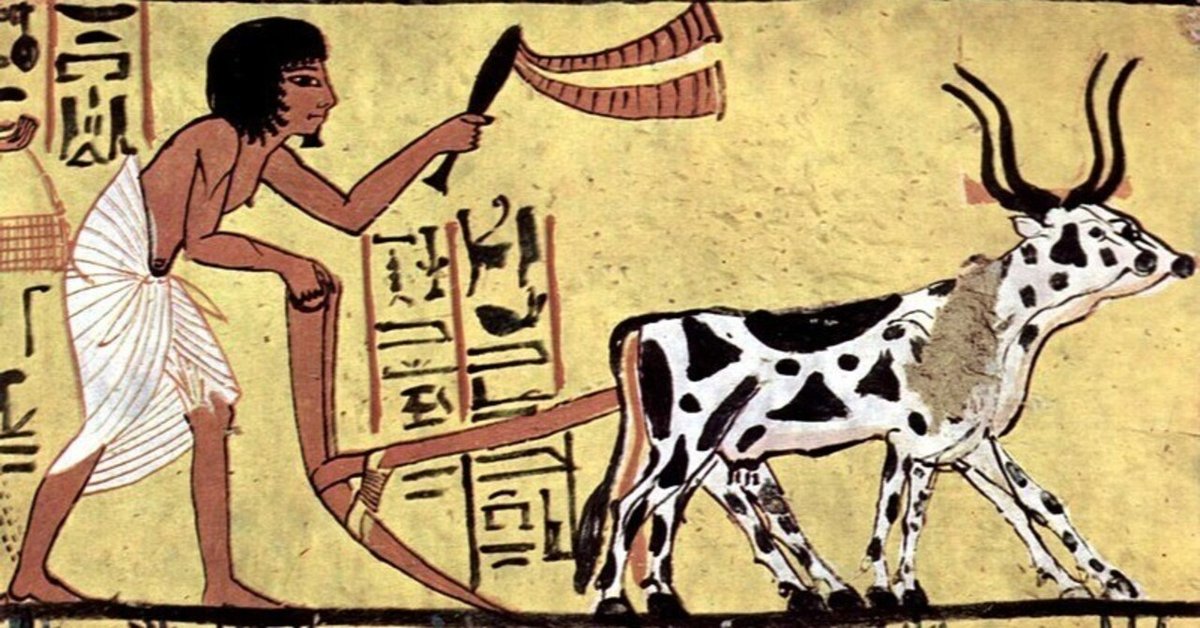
健康と文明病 ⑧(投石による狩猟)
投石と狩猟
では、武器としてのハンドアックスはどの様に使われたのでしょうか。謎の多いハンドアックスですが、使用方法に関して一つの興味深い仮説が有ります。それはハンドアックスを、フリスビーの様に獲物に向かって投付ける石弾として使ったと言うのです。この投石仮説は、それほど突飛なものでは有りません。実際に、獣皮を張った標的に投げ付けて実験すると、相当の威力が有ると言います。
実は、人類は文明以後にも投石を戦争の武器として、長らく使って来た歴史を持っています。古代ギリシア・ローマ時代には投石を専門とする投石兵が存在し、弓兵と並んで重要な兵力を構成していたと言われます。ただ、当時は素手で投げたのではなく、投石器と呼ばれる中央に石を置く幅広の部分の有る長さ1~3mのひも状の道具を使い、ひもの両端を持って頭上で振り回し、遠心力を利用して目標に投付けたのです。旧約聖書にも、イスラエル軍とペリシテ軍との闘いで、サウル王の代わりに一騎打ちを受けて立った羊飼いの少年ダビデが、ペリシテ軍の身長3m近い巨人兵ゴリアテを投石器で倒し、剣を奪って首を刎ねた話が出ています。ミケランジェロの有名なダビデ像が、左肩に垂らしているベルト状のものがその投石器です。
図58)ダビデとゴリアテの一騎打ち

図59)ミケランジェロのダビデ像(アカデミア美術館、フィレンツェ)

この投石器の威力は想像以上に強力で、重装歩兵中心の戦いだった古代には弓矢よりも有効ではるかに破壊力があり、前後を円錐形に加工された弾丸は皮革製の鎧の上からでも内臓に致命傷をおわせ、鎧を着けていない場合は人体を貫通したとされます。また、射程距離でも弓の180m程度に対して、投石器は400mを越えたとも言われ大きく上回っていたのです。共和制ローマを苦しめたケルト人は、戦闘では手の他にも首と胴に掛けた3つの投石器を使い、巨大な石を猛烈な勢いで投げ付けて、ローマ兵の盾・兜などの防御武具を打ち砕いたと言われます。子供の頃から投石器の訓練にはげんでいた彼らの狙いは非常に正確で、的を外す事はほとんど無かったと言います。
図60)トラヤヌス記念柱の投石兵

さらに時代が下った16世紀にも、黄金を求めて新大陸の征服に乗り出した侵略者のスペイン人に対して、投石器は抵抗の武器として使われています。アステカやインカの先住民は、弓矢・投げ槍と共に投石器を使って、馬に乗り銃と鉄製武器で武装した貪欲なコンキスタドールに立ち向かったのです。現在でも南米アンデスでは、オンダと呼ばれるリャマの毛で編んだ投石器が、羊の群れの誘導や害獣を追い払うのに使われています。また、パプアニューギニアでは、投石器による狩猟も行われていると言います。
図61)アルパカの毛糸で編んだ投石器(ペルー南部)

日本でも約2000年前の弥生時代、北部九州から土弾と呼ばれるラグビー・ボールに似た形状の小石ぐらいの大きさの土器が出土していますが、これも石の代わりに敵に投げ付ける武器であったと考えられています。
狩猟用の武器として初めて投石を使ったであろうホモ・エレクトスは、投石器は使わず素手で投げていた事でしょう。しかしプロ野球では、時速160kmもの剛速球を素晴らしいコントロールで投げるピッチャーがいます。ヘルメットの上からボールが当たっても脳震盪を起こす程の打撃がある訳ですから、素手での投石でも獲物に致命傷を与える事は充分可能だったはずです。実際、オーストラリア先住民のアボリジニは、飛んでいる鳥の群れやワラビーを投石で狩りしており、かって狩猟採集と遊牧で生活していた南西アフリカのコイコイ(ホッテントット)は、100歩離れた所からコイン大の標的に石を命中させる事ができたと言われます。
図62)ホッテントットと皮で覆われた小屋

ヒトの投擲能力
ピッチャーがコントロール良くボールを投げるというのは、我々から見るとなんでもない普通の事の様に思えますが、実は目標に向かって強く正確に石を投げ付けるという技能は、類人猿には出来ないヒトに固有の特殊な能力なのです。チンパンジーなどの類人猿は、地上では手指の背を地面に着けて歩く、ナックル・ウォーキング(指背歩行)と呼ばれる特殊な四足歩行をしています。これはチンパンジーの主食である果実の稔る熱帯雨林の樹冠部への適応による手の特殊化の結果です。熱帯雨林では、木性のツルが樹冠を覆う様に繁茂しています。このツルや枝先に稔る果実を取るのに、チンパンジーはツルや枝に手の4本指を引っ掛けてぶら下がり、腕渡り(ブラキエーション)で移動します。この腕渡りへの適応によって、チンパンジーは長く曲がった4本の指と、極端に短い親指を持つ手を進化させたのです。この熱帯雨林の樹冠に適応した長く曲がった指を獲得した結果、チンパンジーは地上ではナックル・ウォーキングという特殊な四足歩行をせざるを得なくなったのです。
図63)チンパンジーのナックル・ウォーキング

しかしナックル・ウォーキングへの適応は、今度は手首が硬くなり後ろに曲げられなくなるという結果をもたらしました。それによってチンパンジーは、手首を痛める事無く長時間手指に体重を掛けて歩く事が可能になった訳ですが、同時にヒトの様に手首のスナップを効かせて物を遠くへ投げるといった事も出来なくなってしまったのです。また、こうしたスナップを効かせた投擲能力が、石器作りにも不可欠なのは先にも触れた通りです。
図64)チンパンジーの手

チンパンジーなども、ヒョウなどの敵を威嚇するのに樹上から木の枝などを投げ付ける事が有ります。彼等よりもはるかに正確で強力な投擲能力を持っていたホモ・エレクトスが、狩猟の為にこの能力を使い始めたというのはごく自然な事と言えます。恐らく、最初は地面に転がっている丸い自然石を使ったのでしょうが、剥片石器を発明しその刃の有効性も知っていた彼等が、投擲用の石弾にも剥片のような鋭い刃を付けて威力を高める事を思い付くのは難しく無かったはずです。そして、既に習得していた石核から剥片を剥がす技術に磨きを掛け、巨大な原石から大型の剥片を剥がして整形し、投擲弾としてのハンドアックスを完成させたのです。この様に考えれば、ハンドアックスというそれまでの原始的なオルドワン石器と比べると、明らかに異質で不連続の飛躍的な進歩を遂げた、この革新的な石器の誕生を無理なく説明できると思います。
ハンドアックスの謎と投石
また先に述べた、ハンドアックスにまつわる様々な謎にも容易に説明が付きます。石器の全周に鋭い刃が付けられていたのも、獲物に投げ付ける武器で有れば当然です。大型の素晴らしいハンドアックスと共に、小型で貧弱な作りのものが多数見付かるのは、獲物の大きさに合わせて使い分けていた事が考えられます。また、大型で優美なハンドアックスには生活の糧を得る道具への愛着やこだわりが感じられますし、大きな獲物を仕留めた時の見返りを考えれば、その制作に時間と手間を掛けても充分に見合うものだった事でしょう。1つの遺跡から、数百にも及ぶ多数のハンドアックスが発見される場合があるのも、弓矢と同様に狩りに使う予備が必要であった可能性も考えられます。
さらに、ハンドアックスを投石による狩猟に使ったと考えると、人類の石器文化の発展を、狩猟用の武器の進化として一貫して捉える事が可能となります。現在、狩猟に使われた武器として確認されている最古のものは、約40万年前のイギリス・エセックス州クラクトンから出土した長さ30cmの木製の槍の穂先や、ドイツ北西部シェーニンゲンの炭鉱から発見された3本の木槍で、後者はトウヒ(マツ科の針葉樹)を削った長さ1.8~2.3mのもので投げ槍として使ったようです。近くからは、石器のカットマークの付いた野生馬10頭分ほどの骨が見付かっています。また、イギリス・サセックス州ボックスクローヴ遺跡からは50万年前の丸い穴の開いた馬の肩甲骨が出土していますが、この穴は投げ槍による可能性が高いと言われます。
このように、50~40万年前頃には槍を使った狩猟が行われていた事がほぼ間違い無い訳ですが、槍という洗練された狩猟具が発明される以前には、もっと原始的な道具が使われていた時代が有ったと考えるのが自然でしょう。そこで、最もありそうなのが投石なのです。獲物の草食獣よりもずっと足が遅い人類が狩猟をするには、何らかの飛び道具が不可欠です。実際、オーストラリア先住民のアボリジニは投石で鳥やワラビーを狩猟している訳で、何処でも手に入る石を使う投石は、最初の狩猟用武器として最も相応しい様に思うのです。
図65)ムスティリアン尖頭器とスクレイパー

また以前にも触れましたが、ハンドアックスは160万年間という驚くほど長期に渡って作り続けられて来ました。ところが約30~20万年前、中期旧石器時代に入り槍の穂先に使ったと思われるムスティリアン尖頭器が出現すると、それと入れ替わる様に姿を消して行きます。つまり新たな武器の出現と共に、ハンドアックスは作られなくなって行ったのです。この時代にも、優美で薄いハンドアックスが作られていましたが、徐々に槍先に使ったと思われる両面加工された木の葉形尖頭器へ移行して行き、両者の境界を区別するのは困難だと言います。もしかすると、薄身のハンドアックスの中には同様に槍先として使われたものもあったかも知れません。
アシュール文化からムスティエ文化へ
図66)ムスティエ洞窟(フランス)

中期旧石器時代(30万年~3万年前)はネアンデルタール人に代表される旧人の活躍した時代ですが、それまでのハンドアックスの様な大型で重い石核石器を特徴とするアシュール文化から、ムスティエ文化(フランスのムスティエ洞窟に由来)として知られる小型の剥片石器を中心とする石器文化へと大転換した時でもあります。石槍の製作には木の柄の先端を2つに割り、そこに先の尖った石器を挟んで固定する必要が有ります。つまり、槍の穂先となる尖頭器は薄く作らなければならず、それに適した薄く小型の剥片石器を量産する技術として開発されたのがルヴァロワ技法だったのです。一方、投擲用の石弾だったハンドアックスにはある程度の重量が必要で、薄くする理由はそれほどなかったでしょう。つまり、石器文化の前期旧石器のアシュール文化から中期旧石器のムスティエ文化への移行は、狩猟の武器が石弾の投石から槍に変化した事が背景に有ったと考えられるのです。
図67)ルヴァロワ技法

ルヴァロワ技法では、予め石核を亀甲形に調整加工・整形してから、最後に一個または数個の剥片石器を剥離します。これによって、1つの石核から複数の剥片石器をつくる事が可能になり、石器の量産化に道を開くと同時に、石器製作の効率も劇的に向上する事になりました。アシュール文化では、0.45 kg のフリント(火打石)から5.1~20.3 cmの刃が作られましたが、ムスティエ文化では同じ材料から10.2mもの刃が剥離されたのです。つまり、石器の刃を得るという点では、一挙に50倍以上に効率が上がった訳です。さらに、ホモ・サピエンスが活躍する後期旧石器時代(5万年~1.2万年前)になると、石刃技法によって同じ0.45 kg のフリントから12mの刃を作り出す事が可能になったと言われます。こうして中期旧石器時代以降、剥片石器の定形化・薄型化・大量生産が一気に進行して行ったのです。
石刃技法とは、縦長の石核の上面を打ち欠いて水平の打面をつくり、その周囲に打撃を加えて連続的に細長い剥片(石刃)を剥がしていく石器製作方法です。これにより、1つの石核から30~40点もの石刃が製作できたと言われます。
図68)復元された石核と石刃(4万年前、イスラエル)

(つづく)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
