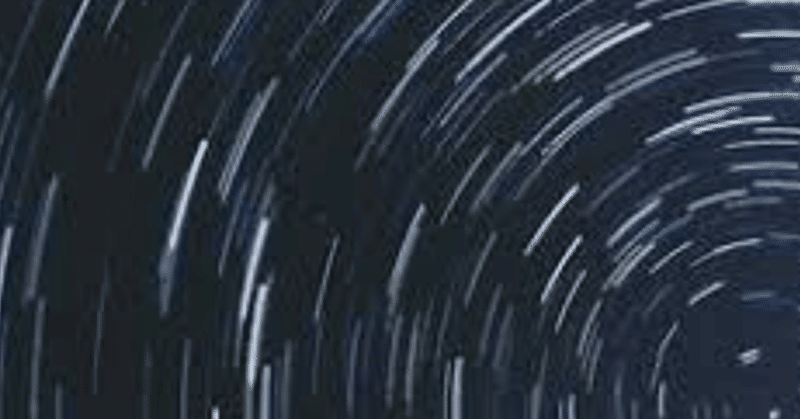
混沌の落胤は水とともに地に満ちて(3)
□□□□□□■
『狩人』の意識は現在の時間軸には無い。
目映い光の元で、一組の男女が永久の愛を誓い合っていた。
──兄貴!
──お義兄さん。
二人が笑いかける。手にした両親の遺影が、微笑んだ気がした。
賃貸に運び込まれる荷物。幸せで膨らんだ重み。荷物を運び込み、不快ではない汗を拭う。
弟夫婦との昼食。将来を語り合う二人。
弟が屈託のない笑顔を向ける。
──兄貴も名前つけるの手伝ってよ。
"渋谷に行く"というライン。頭では行くなと叫びながら、手を介して放たれたのは、"早めに帰ってくるんだぞ"という、無責任さを未来に託した、くだらない一言。
自宅の時計が、破滅までの時を律儀に刻み続ける。
生中継から伝わる恐怖と絶望。
何千、何万と繰り返し見ながら──無駄だと知りながら、覆される結末を妄想し……結局は、徒労に終わる。
渋谷の風景。磨り減って割れた靴底から、水が入って朽ちた靴下を容赦なく揺らす。錆びたショベルを支えに俯いて、水面には脂で汚れた長髪と、エナメル状に固く延びきったたわしのような無精髭。目の隈は土気色を濃く帯びて、怒りと悲しみでこわばる口許は、よだれと呼気を垂れ流す。
水の中だろうと瓦礫の底だろうと関係ない。必ず見つけ出してやる。最早頭の中だけで呟いたのか──己を鼓舞するために口からまろびでたのか、『狩人』には区別がつかなかった。
痛み、身を焼くような熱さと、骨に染みる寒気が交互に肉体を支配する。『狩人』は視界を巡らせる。ひび割れたアスファルトを濡らす自分の血に、タールのような血を撒き散らす、ぬめぬめした肉塊と触手に覆われた獣。
己の寿命を磨り減らしながら、また視界を巡らせる。曇り空。崩れたビル。卵の殻のように砕け、空中を漂うそれらは、渋谷の中心にある『何か』の揺り篭みたいに見えた。
それを見つめていたのは自分だけではない。
皮の鎧に長靴、古びた外套に帽子を目深に被り、斧槍や細剣を携えた誰か。
──まだ生きていたか。
向けられる視線は感情を排しているかのようだ。瞳に浮かぶ紋様は、蒼く光り、揺らめく。
『狩人』は言葉を返そうとし、口内にたまった血を泡立たせた。ごぽっ、と音が響き、軌道に流れ込み、湿った咳が響き渡る。
──長くはなさそうだ。楽にしてやれるが、どうする?
僅かな寿命を磨り減らし、拒絶の意思を示すように視界を何度も巡らせる。
──苦しむが、命だけは助けてやれるぞ。
僅かな寿命を引き換えに、肯定を示すように顔を起こした。
顔を掴まれた。目の前の人物は、懐から焼き印を取り出す。奇妙な紋様と、蒼く光る炎。
──ようこそ『狩人(ハンツマン)』。この印が、お前に力を、技を、そして『うみ』が『海』ではないことを教えてくれる。
段々と近づく印。光彩は目映い蒼に萎縮し、水晶体を保護する水分は炎の熱で干からびてゆく。
そして、体を貫く激痛。血液を燃料として燃え盛るような苦痛と、印に刻まれた情報が脳を食いつくし、再編してゆく。肉の繊維が千切れては再生し、肥大化と縮小を繰り返す。骨は肉の収縮で砕け、体内の鉄分と硫黄を含み、印から流れる炎で鍛造されてゆく。
脳は熱を帯び、融解と凝固の合間に印からもたらされる知恵を取り込む。
そして限界を越えた意識は、過去の水面から飛び立ち、現世に揺蕩う『狩人』の意識と結びつき、走馬灯の境界から現実へと引き起こす。
□□□□□■■
『狩人』は身を起こし、ぼやけた焦点を合わせる。
腹の傷は塞がり、僅かな瘡蓋を残すのみになった。皮鎧も外套も、目立った損傷はない。
自身が横たわるカビだらけのマットレスの真横に、得物とカンテラが安置されている。炎は消えることなく、ただ揺らめく。
辺りを見回すと、埃と汚れにまみれた家財と湿気で腐り始めたフローリング、カビたカーテンに黄ばんだ壁が見えた。もとは賃貸部屋なのだろうと、『狩人』は結論づける。
そして、視線。
殺気を帯びぬそれを緩慢な動作で辿ると、部屋の入り口に襤褸を纏う人影を見つけた。
骨張った足にひび割れた爪、腕には鱗と水掻き、もう片方の腕は細く延び、風切り羽根が生えつつある。
痩せこけた少女だった。
左目からは蛸の足が生え、犬歯は鋭く伸び、右目は爬虫類のごとく、瞳孔が縦に割れていた。
【つづく】
アナタのサポート行為により、和刃は健全な生活を送れます。
