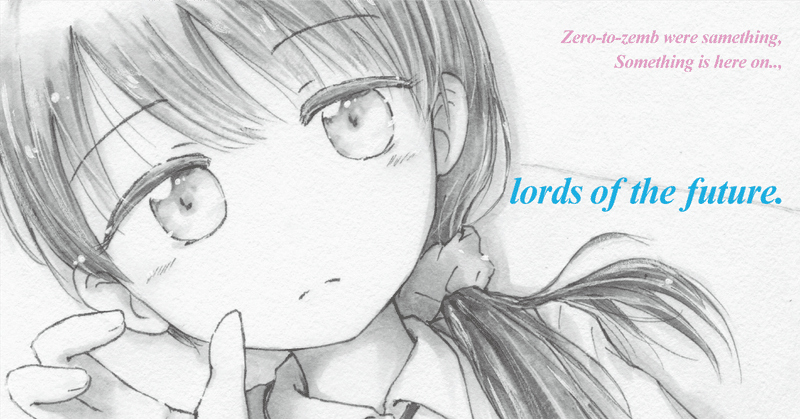
理知を継ぐ者(8) 「あれってなんだったんだろう」
【ここまでのまとめ】
受講生Dによる、署名運動/抗議活動が行われたのは去年の春頃でした。それから1年くらい経っています。時間はひとを理性的にします。状況の経緯も明確にします。あの行動/事件から、何が変わり、何が変わらなかったのか。理性的になったひとはそれを、理知的に捉える/捉え直すことが出来ます。
なんらかの「事件」が起こった時、人はえてして、その話題について感じ、考え、話そうとします。自然にそうしています。でも「事件」が起こった/起こっている時とは、やはりえてして、混乱しているものです。
高橋源一郎はよくエドワード・サイードを引用しています。おれが最初に読んだのはサイード『イスラム報道』からの引用でしたが、おれの理解では、サイードを通して高橋が言いたいのはこういうことです。
「なんらかの事件の渦中にいるとき、当事者も、周囲も、たいてい興奮してるし混乱してる。彼らは興奮し混乱し、一方的になったり、過敏になったりしている。そういう中で平静を保てるひとこそ知的なのだ(なのでサイードを見習いましょうね)」
まったくその通りです。あまりにその通りなので「やっぱそれが理知的な人間の態度だよな! 高源師匠、分かってるう!」と反射的に思ってしまいますが、でも実際、これはとても難しいことです。
実際おれなんか、「なになに、なにがあったの!? 企業Bの講師Cがなんだって? うわ、まじ! やばいじゃん!」と興奮するばかりで、とうてい「混乱の中でこそ知的であるべき」はやれません。時間を置いて、やっとそれがなんだったか分かる。「あー、あれってこういうことだったのかもなあ」、そればっかです。
だから当事者のDさんにしても、部外者のおれにしても、
「あのとき、自分に落ち度はなかっただろうか? 考えるべきことをちゃんと考えられてただろうか? 話すべきことを、ちゃんと話せていただろうか?」
「あれから何がどうなっただろう? 今現在という時間は、ちゃんとあの事件の『その後』として続いてるのだろうか?」
そういうことを考えていい気がしています。
この連載のタイトルは、元々は『そういえば、あれってなんだったの?』でした。思うところあって今のに変えましたが、話そうと思ってることは前者のままです。
この連載は、「あー、あったあった。そういえば、あれってなんだったんだろう?」と振り返ってみる連載です。
*
そうして振り返って、「あれは間違っちゃったなあ」でもいいと思うんですよね。「間違ってはなかったけど、けどちょっと、あすこらへんは言葉が足りてなかったなあ」とかでも。
それで「ごめんなさい」になっても。
トライセラ和田も同じですが、興奮や混乱の中で「正解」を出すのって、ものすごく難しいことだと思います。初期衝動の直感的理知はあるにしても、せめてあってその程度だろうとおれは思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
