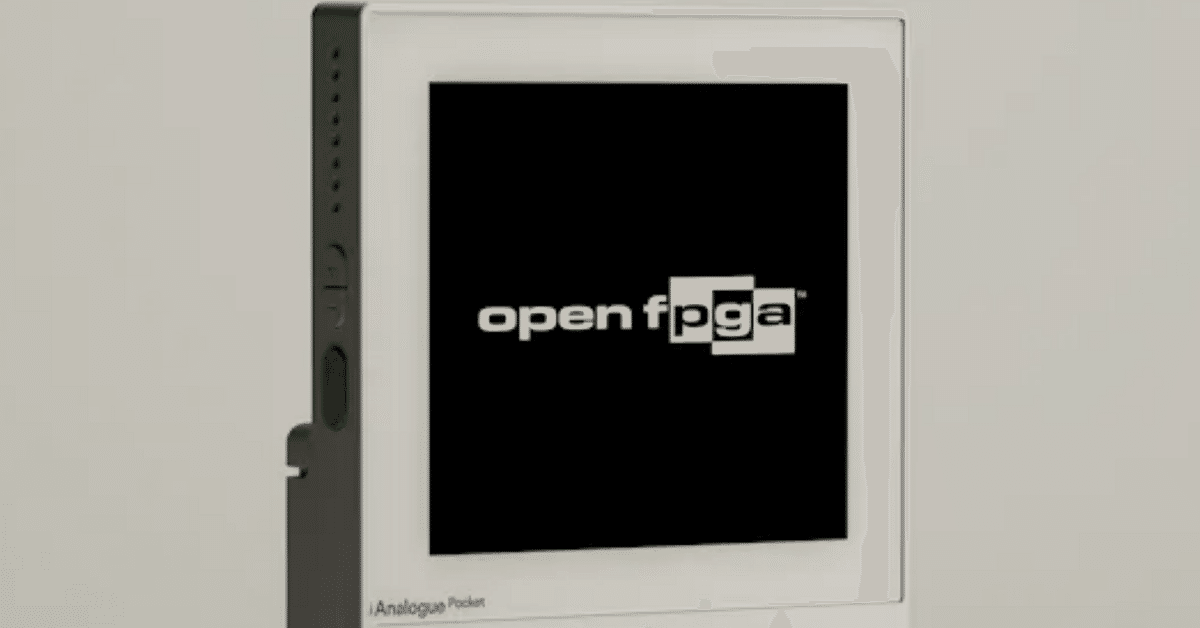
Analogue PocketのOpenFPGA
複数のハードを遊べるマルチレトロゲーム互換機が最近増えてます。
そんな中、Analogue Pocketは基本的にはFPGAを利用したGB、GBC、GBAのレトロゲーム互換機です。
ですか、OpenFPGAといったものでコアと呼ばれるものを導入することでFCやSFCなどのゲームも遊ぶことが可能です。
そもそもFPGAとはなんぞやというとこなんですが、FPGAはField Programmable Gate Arrayの略です。
私も正確に理解している訳では無いのですが、こちらを利用することで過去のレトロゲームハードをICチップ上に再現できる、みたいな感じです。
Analogue PocketはGBシリーズを動かすためのFPGAとは別にOpenFPGAで利用するためのFPGAがもう1つ搭載されてます。
なので、そちらを利用してFCなどの別ハードのゲームを遊ぶことができるようになってます。
Analogue Pocketで遊べるレトロゲームハード
OpenFPGAを利用せずにAnalogue Pocketが遊べるレトロゲームハードは次の7つです。
ゲームボーイ
ゲームボーイカラー
ゲームボーイアドバンス
ゲームギア(変換アダプタが必要)
ATARI LYNX(変換アダプタが必要)
NEOGEO Pocket/NEOGEO Pocket Color(変換アダプタが必要)
PCEngine Huカード(変換アダプタが必要)
こちらはゲームソフトを使用して遊ぶ形になります。
なのでゲームソフト吸い出す必要はありません。
次にOpenFPGAを利用して遊べるレトロゲームハードはと行きたいのですが数が多すぎるのでコアを公開しているサイトのリンクを張っておきます。
こちらのコアを使用することで遊ぶことができるレトロゲームハードを増やすことができます。
OpenFPGAを使用して遊ぶ際にはゲームソフトを吸い出しを行う必要があります。
こういったことからAnalogue Pocketはかなりたくさんのレトロゲームハードを遊べます。
OpenFPGAで利用するゲームソフトは必ず自分で所有しているものを吸い出して使用してください。
遊べるハードは増える?
Analogue Pocketはコアを追加すれば遊べるレトロゲームハードが増えます。
ではAnalogue Pocketで遊べるレトロゲームハードは今後増えていくのか、といったところですが、私はしばらくの間はこれ以上増えないんじゃないかなと考えています。
根拠としてはAnalogue Pocketが携帯ゲーム機だから、ということです。
Analogue Pocketの本体内蔵のコントローラーボタンは十字キーとスタート、セレクト、ホームにABXYとLRです。
PS、SSを遊ぶにはL2、R2など足りないボタンが出てきます。
64もアナログスティックが無いので厳しいです。
Dockに繋げば外部コントローラーが使えますが、携帯ゲーム機のメリットが無くなります。
Analogue Pocketは持ち運んで遊べるというのが、いい所だと思うので、本体内蔵のコントローラーでは遊びにくいレトロゲームハードに関しては追加されないんじゃないかと考えています。
最後に
Analogue Pocketは携帯レトロゲーム互換機としてはかなり満足度の高いゲームハードだなと思います。
遊べるレトロゲームハードの数が多いので所持しているレトロゲームソフトが多い方は購入検討してもいいんじゃないかと思います。
とはいえ国内販売が無く、個人輸入する必要があるので入手ハードルは若干高いです。
興味を持った方はAnalogueのウェブサイトのリンクを載せておきますのでご覧いただければと思います。
今回の記事が何かの参考になれば幸いです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
