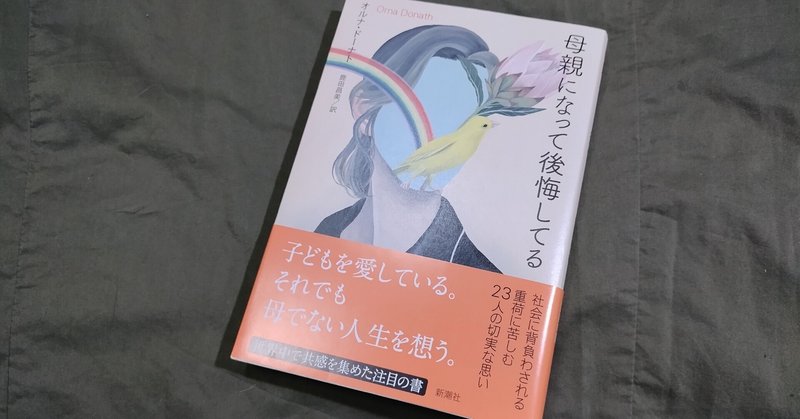
「母親になって後悔してる」を読む前に考えていること
「怖いなあ」と思う本
Amazonの購入履歴を遡ってみた。「2022年5月16日」あらま。この本を買ってからこんなに経っているんだ…現在2023年8月のお盆。最近ちびちびとつまみ読みを始めた。
日本語訳の発刊が同じ年の3月。多分、Twitterで見かけて2ヶ月迷って、それでも「読むべきだ」と思って購入した記憶。第一、タイトルが衝撃的だ。
「母親」という言葉を「後悔」という言葉につなげて、ドキッとしない人はいるのだろうか。ドキッとしない母はいるのだろうか。ドキッとしない女性はいるのだろうか。
即日で本が届いて封を開け、「怖い」と感じたのをよく覚えている。
「パンドラの箱を開けるような」とはよく言ったもので、この本を読んだらどうしようもない後悔が溢れてくるのではないか、とも思ったし、頑なに「母でよかった」という思いにしがみつくのではないか、とも思った。
どちらも経験したくない。
この本を読みたい、読めるタイミング
「この本、読んだ?」と読書好きの友人に尋ねてみた。「読んでない」と答えが返ってくる。「ダークサイド堕ち確定な本って気がする」とのこと。わかるわかる。私もそう思ったから読まなかったのだ。
じゃあ、なぜ今、読み始めようとしている?…「読める」と感じたから。
どうして読めると思えたの?…「後悔しない確信が持てたから」
子どもの年齢もあるだろうか。私の子どもたちは10代後半から20代に入った。もしも後悔してしまって、手を離してしまっても、少なくとも新生児期のように即座に命の危機がある年齢ではない。そんな余裕もあるだろうか。
1年間本棚の背表紙を眺めながら、時々手に取りながら、「私は子どもたちの母になったことを後悔しているのだろうか」と問い直してきた。この問い直しはなかなか勇気が要ることだったし、闇の深淵を覗いている気分にもなった。
ぞわっとする思いを繰り返しながら、私はずっと問い直してきた。「私は母親になったことを後悔しているだろうか」…そうではない、後悔していないのだ、柔らかい気持ちでそうわかって、私はこの本を手に取っている。
「後悔すること」と「違う人生を考えること」は違う
後悔はしていない、私の元に子どもたちが来てくれたことに心の底から感謝している。ただし、「もしも子どもがいなかったら?」「もしも子どもたちが私の元に来なかったなら?」という想像はする。
そしてもうひとつ、「違う時期や間隔に生んでいたら、もっと良い育ち方ができたのではないか」という子どもたちへの反省も。
母親になって後悔しているか?と問われ、母親でドキッとしない人がいるのか、と思ってしまうのは、「後悔」と「反省」と「別の人生への想像」をごっちゃにしてしまうからではないか。
それほどに、母親という役割は不可逆だ。そして重たい。
分けて考えよう。後悔はしていない。しかし、反省したい、すべき点はある。それは後悔とは異なる。そして、子どもがいない人生を想像したっていいはずだ。想像することは今の人生を否定することとは違う。
FIFA Women's World Cupを観ていて思ったこと
時を同じくして、女子サッカーのW杯が開催されている。なでしこジャパンは素敵に心躍る活躍を見せてくれた。私はグループステージからなでしこの試合に張り付いたし、対戦可能性のある相手の試合も予習観戦していた。
ノックアウトステージ2戦目で敗退した時、サッカーの試合で推しチームが負けると始まる、いつもの自問自答が繰り返された。
負けたというのに、この後悔のなさはなんだろう?この感謝はなんだろう?手に入れられなかったのに、この充実感はなんだろう?手に入れられなかったという事実に得られたものはないだろうか?…ある、と私は思う。
社会において、進学しないこと、恋愛しないこと、結婚しないこと、子どもを産まないこと、母親にならないことと言った「得なかったことへの損失」は大きく語られるけれど、「得なかったことによって得られるもの」について語られることは少ない。
得なかったことから得られるもの、それについてこの1年ずっと考えてきた。得なかったこと、手の内にないものについての損失ではなくて価値、ないことによって得たもの。母親にである私が、母親でなかったら得られたもの。
経済学をかじっている我が子と、人生経験の機会費用の話になることがある、経験の機会損失について語られることは多いが、得たことによって損失した利益(なんて言うんだ?)については語られないこと多いよね、と。
経験したことから得られるものと、経験しなかったことから得られるものに、差はないのではないか?したこととしなかったこと、得たことと得なかったことは対等なのではないか。そんな話を我が子としている。
自分が得なかったものへの怖さ、そんなものを手放して、私はこの本を開いている。なでしこのみんなが、私の恐怖を蹴飛ばしてくれたのかもしれない。読んでみて、また考えたことを書けたら書こうと思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
