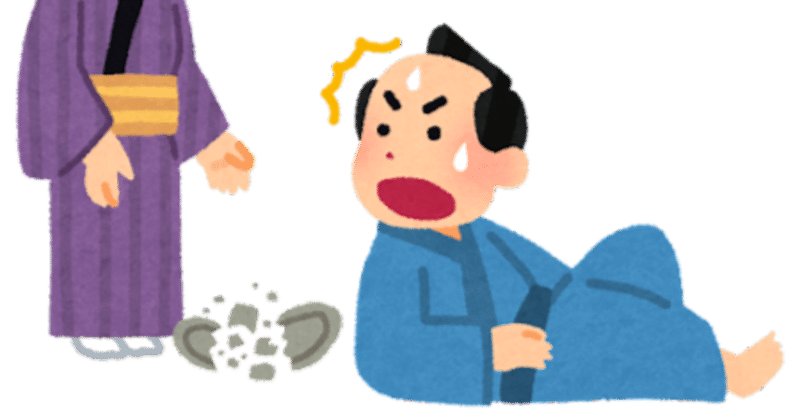
落語のはなし
私のラジオネームは、落語の「厩火事(うまやかじ)」をもじっている。
厠と厩は意外に遠目で見るとわからんもんで。
たまにTwitterでエゴサなんぞしてみると、落語の演目を綴ったツイートが引っかかり、「書いて間違うならまだしも、打って間違うのは、そりゃ『かわやかじ』と覚えちゃってるんじゃないの?」と思ってしまう。
というくらいだから、まだまだ名前も出されないペーペーという事で、投稿の気合いを入れ直すのだ。
閑話休題。
私は落語が好きなのだけれども、所謂マニアでは無く、ごくごく普通にエンタメとして楽しむ程度である。
そして、周りに落語好きがいない故に、これが一般的なのかわからないのだけれども、私は落語の「噺」そのものが好きなのだ。
よく、「○○の△△は聴いておいた方が良い」みたいに、噺家と、その方を代表する噺というのがワンセットで定着しているようだが、そこらへんはあまり意識はしていない。
純粋に話の構成が素晴らしく、スッキリとまとまって、なんとも痛快なショートショートのような噺が特に好きだ。
なので、私はよく、落語の入門編として「猫の皿」を推薦している。自分もこれでハマったので。
よく、寿限無なんかの前座噺を推奨する人がいるのだけれども、それはあくまで「やる側」の入門編で、「観る側」としては、何とも退屈で面白みもなかったりする事が多いと思う。
勿論、噺家によって見え方が変わって大化けした爆笑をかっさらう事もあるが、そういった「演者で観る」という視点は、初めての人にとっては勝手がわからない事なんだろうなとも思う訳で。
そしてそして、よく言う名人上手な古の噺家の喋り方も、あまり好きでは無い。
フニャフニャと滑舌も悪く、演じ分けも出来てるんだかどうなんだか。
あれを「味」とか「粋」で擁護する落語ファンは、多分、ブランディングに弱いんだろうなと思ってしまう。
リアルタイムならまだしも、現代において志ん生が凄いと言う落語ファンはちょっと信用ならない。
なので、私は「誰が演る」ではなく、「何を演る」かで判断している。そして、自分が好きな噺を、自分が一番好きな状態で演ってくれる人が、私にとってのお気に入りなのだ。
とはいえ、やはりそんな事を良いつつも落語ファン推薦の痺れる代表演目も見過ごせないのです。
話し方で言うなれば「三代目 春風亭柳好」(※五代目という説も有)が自分としてはピカイチで、「野ざらしの柳好」という通り名となった由来の「野ざらし」は、立て板に水のような歯切れの良い口調でチャンカチャンカとコミカルに進んでいく様は、現代でも大いに通じると思っている。
初めて聴いた時は音質の悪いテープ録音のような音源だったのだが、見事に呑まれてしまった。
当時は、サゲ部分で「野ざらしでございました」もしくは「野ざらしというお噺」と言ってたと思うのだが、「野ざら…」くらいで会場の大拍手によってかき消され、あたかも「野ざらし!」といって去っていったのだと勘違いし、「カッコいいなぁ~」とバカみたいに思ってたのだけど、今でも「誰かこういうふうにパシっと終わってくれないかなぁ~」と淡い期待をしている。
もうひとつは、これは気迫という点で立川談志の「らくだ」である。
もう伝説となっているので多くは語らないが、正直、私は談志フォロワーではない。
あまりにもムラがありすぎて、調子の良い時の演目以外は、くだを巻いてるようにしか聞こえないし嫌いだ。
しかし、「らくだ」は別格だった。
いつも通りのくだ巻きか…と思っていたが、徐々にエンジンがかかり、最後の最後まで息が止まるほど魅入ってしまった。
噺自体は大して面白くもないのに、あたかもドラマを観ている感覚に襲われる程、この噺には似つかわしくない熱量なのだ。
これを観てからというもの、立川談志への見方が少し変わったと思う。
最後に、どの噺でも安心感を持って見られるフェイバリットな噺家さんを2名。
一人目は柳家小三治。
非常にゆったりとしていながらも、耳馴染みが良く、噺が入ってきやすい。
まさに演舞のような優雅さを体現している。
二人目は立川志の輔。
柳家小三治で書いた事にプラスして、しっかり笑わせるという事も忘れない。
現時点で、私の中ではパーフェクトな噺家さんだと思います。
是非、興味があるけど何から聴けばいいのか…と悩んでいる方は、とりあえず上記の2名を聴いてみる事をオススメします。
特に、古風な喋りでも無く、しっかり笑えて、新作・古典も柔軟にこなす技術、落語へのハードルを下げながらも品格はしっかりと維持させているという点で、立川志の輔の「猫の皿」は聴いておいて損はないと思います。
という事でしたが、皆さん、ガッテンいただけましたでしょうか?
お後がよろしいようで。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
