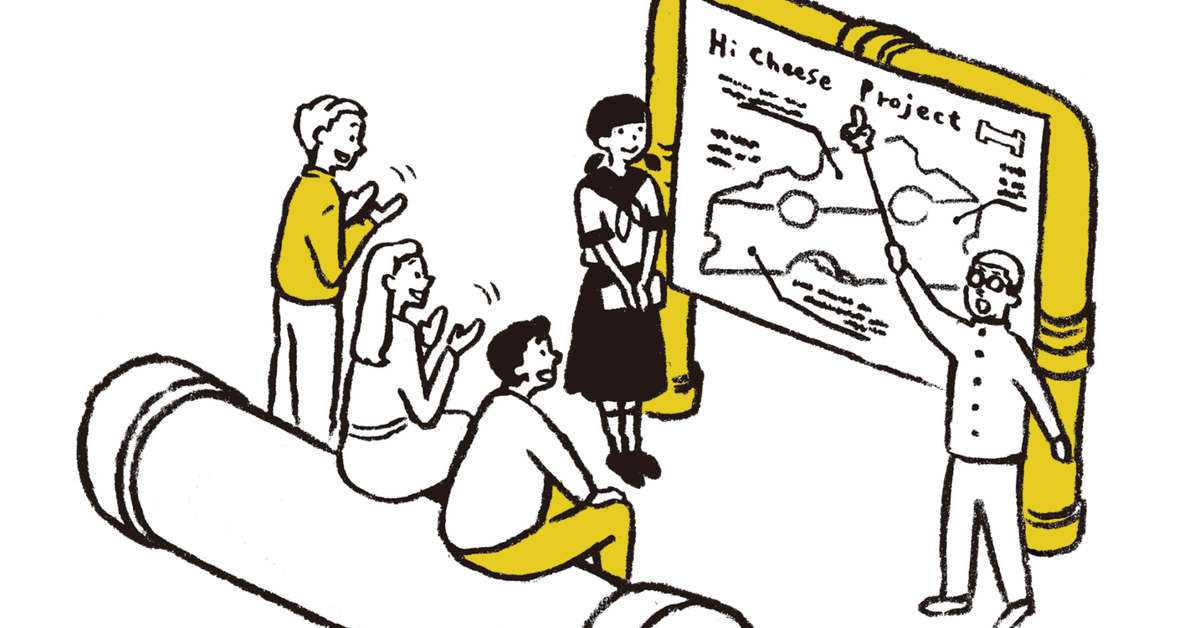
河原部社ができるまでの話
この5年半で、行政、大学関係、教育関係、まちづくり団体などなど150回を超える視察対応をしてきました。その中で、圧倒的に多かった質問の一つ「河原部社はどのようにして生まれたか」を書いてみたいと思います。(理事長:西田遙)
これまでのざっくりとした流れ
2015年4月 ひと・まち・しごと創生総合戦略が行われる
2015年10月 地元の有志が集まって中高生ランドの構想開始
2015年11月 構想が固まる/市長にプレゼン/団体設立準備
2016年4月 NPO法人河原部社設立/行政から事業受託
2016年10月 中高生の拠点事業「Miacis」スタート
2017年4月 キャリア教育プログラム「韮崎版職場体験」スタート
2018年4月 新成人ブックレット「アダルトニューニラサキ」スタート
2018年9月 韮崎ローカルメディア事業「にらレバ」スタート
2020年4月 社会に開かれた教育開発事業「シラカンパ」スタート
2021年4月 週3正社員制度導入
2021年4月 休眠預金等活用事業「ニラサキサラニ」スタート
2022年1月 第12回地域再生大賞「大賞」受賞
チーム韮崎スタイルのまちづくり
河原部社の活動している韮崎市は、「チーム韮崎」をスローガンに掲げ、まちづくりのあらゆるシーンに市民を巻き込んでみんなでチームとしてやっていくスタイルをとっています。なので、外部のコンサル等にまちづくり計画を丸投げするのではなく、市民と有識者からなる分科会チームを構成して、その中でこれからの政策を話し合っているという特徴があります。
そしてその中の、チーム3「教育・子育て」に後に河原部社を立ち上げることとなるメンバーが偶然にも集っていたのがことのはじまり。
設立理事となる4人
チーム3では、「韮崎市は0歳~13歳までの子育て支援は充実しているけれど、その先が足りない」「13歳~18歳が家庭と学校に任せきりになっている。もっと地域でなにかできないか」「0歳~18歳まで切れ目のない支援をしていくまちにしたい…!」といった意見が出されていました。
そして実際に長野県の茅野市にある「CHUKOらんどチノチノ」という中高生の拠点施設を見学に行ったことから、韮崎でも実際に中高生のための拠点づくりをしようという流れになっていきます。
ただ、市内に中高生向けに活動をするような団体が無かったため、それならばと、チーム3の中で特に強い意欲を持っていた4人が立ち上がり、独自に構想づくりをはじめました。

▼最初の4人
県内で30年以上子育て支援の活動をしていた50代の女性2人、市内で自動車整備工場を営みながら教育委員もしていた50代の女性、市内でパン屋を営んでいた40代の女性
市長プレゼン前夜の出会い
4人で構想を固め、いよいよ市長プレゼンとなった前夜。
メンバーの1人が経営しているパン屋に当時24歳の私が、たまたまパンを買いに行きました。
▼その時の私(西田遙)
大学卒業後プロジェクトデザインを生業に起業しつつ、地元でも子どもたち向けになにかやりたいな~と思っていた。
そしてパン屋で雑談をしていたら、お互い地元の子たちのために何かしたいという共通の想いを持っていることに気づき、そこからはとんとん拍子で、その日の夜翌日の市長プレゼン練習の見学に行って、その場で「僕も一緒にやりたいです!」と声を上げ、少しプレゼンの修正をして、翌日5人で市長プレゼンに行き、さらにやる気になって、市に通るかわからなかったけれど、通らなくても自分たちでやろうとNPOを立ち上げ、その後結果的に市から事業の委託を受けることができ、本格的に活動をはじめることとなります。
仕事を辞める決断
この話をすると「タイミングがすごいですね」とか「自分たちの地域にもそういう人がいれば…」ということをよく言われます。
でも、私が一番キーポイントだったなと思うのは、もちろんタイミングもありますが、有志で集まったメンバーがすぐに活動をはじめたことと、その中の2人(初代の理事長と私)が仕事を辞めてフルコミットしたことです。
これは普通に考えれば当たり前のことかもしれませんが、よくまちづくりの現場では意見やアイデアは出すけど、実際にはやらない(やりたくても自分の既存の仕事や活動があってやれない)という人がいます。
これだといいアイデアや構想ができたとして、いざはじめようとした時に「やる人がいない」状態となってしまいます。
やると決めて、自分たちで考えて、自分たちで実際にやる。
私はまだ20代でもあり、決断するのは比較的簡単だったけれど、初代の理事長は自分がいままで30年以上続けていた仕事をスパッと辞めて、またゼロからプレイヤーとなって活動をはじめたわけで、その決断力と行動力なくしては河原部社は現実のものにならなかったはずです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
