
オール讀物新人賞最終候補作Ⅰ
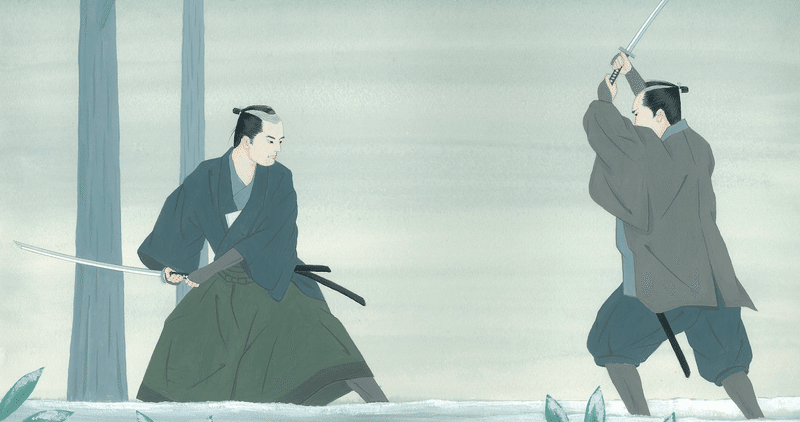
私の書いた時代小説を読んでください。
オール讀物新人賞は、藤沢周平、石田衣良(「池袋ウェストゲートパーク」)等々、多くのそうそうたる作家を生み出してきた由緒ある新人賞です。
そのオール讀物新人賞に、ぼくの応募作が4回、最終選考に残りましたが、いずれも受賞ならず。
このままぼくの書いた小説が誰の目にも触れず終わってしまうのはあまりにも忍びなく、皆さんに読んで頂こうと、ここに投稿することにしました。
noteにはほかに「オール讀物新人賞最終候補作Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ」もあります。
読んでいただけたら嬉しいです。
まずはこちらから。

「りんという女」(第95回オール讀物新人賞最終候補作)
1
「銀次さんはおいでですか。もし、頼まれ屋さん」
考え事をしていて、おもての声にはすぐには気づかなかった。
あわてて戸口に行き腰高障子を開けると、春のまぶしい陽に包まれて女が立っていた。
細身で背は高め。瓜実顔に一重の目。化粧は薄目で、松皮の小紋の紺鼠色(こんねずいろ)の小袖に藍白(あいじろ)の無地の帯を締めている。齢は二十六、七だろうか。大年増とはいえ、その輝く美しさに銀次は思わず身が固まった。
「手前が銀次でございますが」
かろうじて言って、女の持っている物に目がいった。
手に朱塗りの角樽(つのだる)を提げている。
祝い物を受け取る覚えはない。そうか、ここに届けに来たのではないと気づくのにしばらく間がかかった。
「御頼み事でしょうか」
「はい」
「どうぞ中へ」
間口二間の手狭な長屋に招き入れた。女は、上がりがまちに置かれた座布団をはずして腰をおろした。
「いまお茶を淹れます」
「いえ。すぐに失礼いたしますから」女はそう言って、角樽を銀次のまえに置いた。「これを届けていただきたいのです」
朱塗りの角樽には「剣菱」と書いてある。名の知られた上等の下り酒である。
「これをどちらさんに?」
「松井雪之丞さんに」
松井雪之丞? 町家の者の名ではないようだが、何者なのだろう。
「お住まいにお届けするんですね?」
「当人にじかに渡してくださいな」
「雪之丞さんというのは?」
「当代きっての花形役者。豊楽座の役者さんですよ。中村歌右衛門の愛弟子だそうです。ご存じありませんか?」
「不調法なことで相済みません」
もちろん歌右衛門は知っているが、雪之丞という名ははじめて聞いた。
女は、つづけた。
「宮芝居の役者さんですよ。いま、湯島天神でやっています」
江戸の芝居小屋は、中村座、市村座、森田座の江戸三座だけではない。
それら官許の大芝居より格は落ちるが、木戸銭も安く手軽に見物できる小芝居というものが数多くある。小屋がけの小規模な芝居小屋である。大芝居のように櫓を上げることも回り舞台や引幕を使うことも許されず、かわりに緞帳(どんちょう)を用いたので緞帳芝居ともいった。小芝居のなかでも神社や寺院の境内に小屋を出しているものを宮地芝居とか宮芝居とかいう。
「あの……あなた様は?」
銀次の前に座った美しい女は、深川三十三間堂町の材木問屋伊勢屋の内儀、りんと名乗った。たしかに大店の内儀らしく、着ているものも見るからに上等で風格さえ感じられる。この貧乏長屋にはそぐわない輝きを放っていた。
「湯島天神の境内で小屋を張っている豊楽座の松井雪之丞さんにお届けするのですね?」
「そうです。芝居小屋のどなたかに頼むのではなく、じかにご当人に手渡していただきたいんです」
「ご贔屓(ひいき)にしている役者さんですか」
「はい」
「ご用命はわかりましたが……」
腑に落ちないことがあって、言いよどんだ。
銀次は「頼まれ屋」である。ここ鳥越明神裏、元鳥越町甚平店に移り住み、表の腰高障子に「たのまれ屋銀次」と屋号を出して、もう一年にもなるだろうか。町々に客寄せの引き札(ちらし)も配っている。
伊勢屋の内儀が町で見たという銀次の引き札にも、「探し人、家移り手伝い、草刈、草引、家作修繕、家掃除、留守番、家事手伝い、荷物運び、病人やお年寄りの介添え、そのほか、よろずなんでも請け負い〼(ます)」としている。
その文言どおり、頼まれれば何でも請け負う。これまで、老人の茶飲み友だち捜し、身の上相談、恋文や付け文の届け、墓参りの代行など、一風変わった頼み事も数々あったが、すべて応じてきた。それにくらべれば、これは風変わりな注文というわけでもなかった。
「でしたら、あなた様が行かれたほうがよろしいのではありませんか? そのほうがお気持ちも伝わりますし」
「……そうもいかないのです」
「それはまた、どうして」
おりんは急に目を伏せ、黙り込んだ。
なにやら事情がありそうだった。
「お客様の内証は、決して外には漏らしません。それを鉄の掟としております」
「お話ししなければ、届けていただけないのでしょうか」
「『なんでも頼まれます』と看板も出しておりますし、引き札にもあるとおり、お頼みごとは何でもありがたく承ります。ただ、これはお相手のある用向きでございますから、おりんさんがご自身で届けられない訳を教えておいていただきませんと、何か聞かれたとき困りますので」
実は、その裏には、この用件が御定法に触れたり、犯科の手伝いとなるようなことではないか確認しておく意図があった。
おりんは唇をかむように固く口をつぐんだが、やがて伏し目がちに話し出した。
「実はわたし、雪之丞さんとはわりない仲だったのです。お恥ずかしい話ですが、夫のある身でありながら、本気で懸想してしまったのですよ。逢瀬を重ねるたびにどんどん好きになって、離れられなくなってしまいました。
ですが、雪之丞さんは人気役者です。女の人はよりどりみどり、夜ごと相手を替えて遊んでいました。そんなこと、はじめからわかっていたことです。でも、雪之丞さんと逢瀬を重ねるうちに、自分がひどい焼き餅焼きだとはじめて思い知ったのです。それで、ほかの女の人を抱いてくれるなと頼みました。もちろん、そうはいきません。口争いになり、とうとう、わたし、言ってはならない言葉を吐いてしまったんです。河原者風情が、って」
銀次はどことなく違和感を覚える。金持ちの内儀や大店の娘、身分のある御女中が役者にはまり、淫らな関係にのめり込むなど、よくある話だが、目の前の品のある楚々とした婦人とは、どうしても結びつかないのだ。河原者風情などという汚い言葉も似合わない。感情を抑えた物静かな表情の裏には、うかがい知れない燃えたぎるものが秘められているのかも知れない。女はわからない、と銀次は思った。
「だから、もう会うことは叶わないのです。ただ、最後に、一時でも女の仕合わせを教えてくれたあの人に、お礼を言いたいのです。ささやかながら、これがそのしるしです」
銀次はあらためて言った。
「お話は伺いました。お届けいたします」
「よろしくお願いします」
「言づては?」
「いいえ。何も言わなくても、あの人にはわかるはずです」
「伊勢屋のお内儀からということでよろしいですね?」
「名前も無用です」
「名前もいわない?」
「この伊丹の銘酒は、赤穂浪士が討ち入り前夜に酌み交わしたお酒だそうです。いつだか雪之丞さんがこのお酒を飲みながら、『仮名手本忠臣蔵』の大星由良之助を演じるのが夢なんだと打ち明けてくれたことがあります。だから、名前など出さなくてもわかります」
「名前を出さなくてよろしいのですね?」
「はい」
「承知いたしました」
おりんが話を打ち切るように言った。
「手間は先にお払いいたします。いかほど?」
「お届けだけですから、二百いただきましょうか」
銀次は、中身によってひと仕事の料金を二百文から五百文くらいにしている。手当の高い大工や左官の日当が五百文くらいだから、二百文の手間はまあ妥当といえるだろう。
「ではこれで」
と、おりんは紙の包みを出して銀次のまえに置いた。
中身をのぞいてみると、なんと、小粒が四枚も入っている。
小粒金四枚といえば一両で、大工の日当の十日分にもあたる破格の報酬である。
「お使い物を届けるだけでこんなには……」
「いまお話ししたこと、だれにも言わないという約束料もふくめての代金ということでどうでしょう」
「承知いたしました」
と銀次は頭を下げた。
おりんは立ち上がり、戸を開けかけたところで振り返って、
「今の話、他人様にはくれぐれも内密に」
念を押した。
「ご心配なく」
「お使い物、まちがいなくお届けねがいますよ」
「はい」
「まちがいなくご当人の手に渡してくださいね」
「承知いたしました」
女が帰るとすぐに、出かける用意をはじめた。
庭仕事や家の掃除など、たいていの仕事は、御納戸色に紺縞の着物と紺の股引きと決めている。着物の尻をからげ、柿色の長半纏を羽織る。半纏(はんてん)の背には大きな丸のなかに銀の一文字。
しかし、花形役者に届け物となるとそうもいくまい。黒足袋から白足袋に履き替え、着物の裾を下ろし、羽織を羽織った。これで、材木問屋の手代くらいには見えるかも知れない。
角樽を提げて家を出た。湯島天神までは、小半刻(三十分)ほどだろう。
明るい日差しが町にあふれ、行き交う人々の表情も心なしか和やかである。梅雨にはまだ間がある心地よい風が頬をなでる。
これを届けたら、ひさしぶりにやえの顔でも見に行くか、と銀次は思った。
一年ほどまえになるだろうか、頼まれ屋の注文で家移りの手伝いを頼まれ、家財道具を運んでの帰り、御蔵前通りを元鳥越町に向かって歩いているときだった。元旅篭町にさしかかったあたりで、突然雨が激しく降り出した。
あわてて目の前の両替屋の軒下に飛び込んだ。雨足はますます激しくなり、いくら待ってもやみそうになかった。濡れて帰ろうかと思いはじめたころ、
「銀ちゃん?」
となりで声がした。
振り向くと、さきに雨宿りしていた女が長身の銀次をのぞき込むように見上げていた。一重の目が切れ上がった、さっぱりした顔立ちの美人である。
知らない顔だし、親しげに呼びかけてくる美人にも心当たりはなかった。
「銀ちゃんでしょう? やっぱり銀ちゃんだ」
笑うと端正な顔立ちに温かさがひろがった。齢は二十三、四だろうか、桜色の鮫小紋の小袖に黒地の帯を締め、紫色の長袋を抱えている。中身は三味線のようである。
「あの……どちらさんで?」
「やえよ、富岡橋のそばの五右衛門店の」
銀次は子供の頃、深川の佐賀町代地に住んでいた。女はそのときおなじ町内に住んでいたやえだった。
「おやえか?」
「思い出した?」
「見違えた。あのころのしょんべん臭いおやえとは大違いだ」
目元や微笑んだ口元に子供の頃の面影が見えた。
「やだ。あれからもう何年たったと思っているの」
「そりゃそうだな。稽古の帰りか?」
三味線を見て聞いた。
「そう」
数軒先に傘屋があるのを見つけて、雨の中に飛び出し、傘を買ってすぐに戻った。
「家はどこだ」
「諏訪町よ。吾妻橋のそばの」
「送って行こう。大事な三味を濡らしちゃいけねえ」
「悪いからいいわよ。やむまで待ってるから」
「遠慮するな。おれは今日の仕事はしまいだ」
二人は傘を差して雨の中を歩き出した。
道々話すうちに、やえは清元の師匠であることがわかった。今日は稽古をつけてもらってきたのではなく、弟子の家に出稽古に行った帰りだったのだ。
三味線とやえを濡らさないように傘を差し出していたので、大川端にある一軒家に着いたときには、左半身がずぶ濡れになっていた。
それに気づいたやえが、雨が上がるまで休んで、着物を乾かしていけといった。勧められるまま家に上がり込み、出された酒をちびりちびりとやるうちに話がはずみ、気が付けば夜も遅くなって、そのまま泊まって行くことになってしまった。
その三刻(六時間)ほどのあいだに、二十年の空白はたちまち縮んだ。幼なじみはたがいにうち解けあい、男と女の関係になるのに間はいらなかった。
その夜、雨は朝までやまなかった。
その日をきっかけに、ひと廻り(七日)に一度は諏訪町の家を訪ね、泊まるようになった。
惚れ合っているし、いっしょになってもいいと今は思っているが、たがいに口に出すことはなかった。やえのところには、美人の師匠目当てにせっせと通ってくる男弟子が大勢いる。その御月並み(月謝)で暮らしは潤っている。銀次の存在で男弟子が減り、やえの暮らしを脅かすことになるのは望むところではなかった。
だから、やえの家を訪ねるときは弟子たちが帰った時分を見計らって行くし、朝は早めに出るようにしている。まるで間男だ、と自嘲することもあるが、これもやえのためだった。
2
湯島天神には東側から入ったほうが早いと思い、下谷広小路から天神裏門坂通りへと折れたのだが、それがまちがいだった。坂道がえんえんと続き、やっと登り切ったと思ったら、さらに長い石段が待ち受けていた。湯島天神の男坂と呼ばれる急な石段である。やっと上までたどり着いたときには、すっかりくたびれていた。
しばらくたたずんで境内を見回すと、たくさんの人で賑わっていた。
参拝者だけではない。鳥居のわきには水茶屋があり、おもてに並んだ腰掛け台は満席である。
参道に沿って売薬香具売りや土産物屋の床見世が連なっていて、人々はそのまえで立ち止まり、覗き込み、買い物をしている。右手の奥のほうには楊弓場の小屋も見える。神社は手軽に行ける行楽の場でもあった。
そんな床見世と背中合わせに建っている大きな建家が目にとまった。裏手に回ると、芝居小屋だった。役者たちの大きな絵看板が掲げられ、周囲には、役者の名や演し物の「白波五人男」と書いたたくさんの幟が小屋を囲むように立ち並んでいる。
宮芝居の認可は晴天の百日に限って許されたので百日芝居ともいうが、規制が緩むのに乗じて百日の興行を繰り返し、ほとんど常打ちと変わらない小屋も多かった。
木戸口で雑談をしている若い衆と親爺を見つけ、声をかけた。
「もし、豊楽座の方でしょうか」
「はいよ。お客さん、すまねえが、もう札留めだ。明日また出直してくだせえ」
若い衆が言った。
若いのが呼び込みで、親爺のほうは木戸番らしい。
二人のすぐ後ろの札売り場には満員御礼の札がかかっている。だから一息ついているのだろう。
「いえ、雪之丞さんにお届け物で」
「ほお、剣菱か」呼び込みの若い衆が角樽を見て言った。「上物だ。預かりますからそこに置いていっておくんなさい」
「いえ、じかにご当人にお渡しするようにということなので」
「無理を言っちゃ困るよ、いま舞台の真っ最中だ」
二人に酒手を渡して、もう一度聞いた。
「待たせて頂くわけには参りませんか」
木戸番の親爺が酒手を袂(たもと)に滑り込ませながら言った。
「そろそろ芝居がはねる時分じゃねえか?」
「そうか」若い衆が言う。「あと小半刻(三十分)ほどで終わる」
宮芝居は夕刻七つ半(午後五時頃)までと定められている。
「それでは待たせて頂いても?」
「太夫に伝えますから、裏でお待ちくだせえ」
若い衆が裏口へと案内にたった。
裏木戸を入った土間で待っていると、呼び込みの若い衆が雪之丞を案内して出てきた。
弁天小僧そのままの衣装と白塗である。三十少し前だろうか、おりんとさほど齢は変わらないように見える。さすが当代きっての花形役者だけあって、細面の男前で色気があり、花もある。
雪之丞は、辞儀をし、いささか困惑したように銀次を見た。
「お届け物でございます。どうぞお納めを」
角樽を差しだした。
「あの、どちらさまの」
「名はいわずともおわかりになると」
「はて、そう申されましても……」
「深川の伊勢屋さんのお内儀です」
しかたなく名前を出した。
「はて、存じやせんが」
「おりんさんという方です」
「存じません」
困ったように重ねる。
おりんとのことをおおっぴらにされたくないのかも知れないと察して、言った。
「ご贔屓筋も大勢いらっしゃるから、覚えておいででないかも知れません。お礼のしるしとおっしゃっていました。どうぞお納めください」
「なんのことかわかりませんが、縁も所縁もない方から頂くわけにはまいりやせん」
銀次は戸惑う。人気商売だから、見ず知らずの者から献物を受けることもないことではないだろう。それを断るとはどういうことだ。
しかし、どうしても受け取ってもらわないと困る。それが頼み主の注文だ。
銀次は機転をきかして言った。
「剣菱は、浪士が討ち入り前夜に飲んだ出陣の酒だそうでございます。太夫は、大芝居で『仮名手本忠臣蔵』の大星由良之助を演じるのが夢だそうで。これはそれに掛けた験担ぎ(げんかつぎ)の御酒でございます」
「大星由良之助? わちきはべつに由良之助を演じてみたいと言った覚えはござんせんよ」
嘘ではなく、まったく心当たりがないような口ぶりである。あるいは役者だけに、よほど芝居が上手いのか。
銀次は困り果てる。どこの誰とわからずとも、適当に礼を言って、受け取ればいいことではないか。それを、どうしてここまで頑なに拒むのか。
「わざわざご足労いただいて申し訳ありやせんが、これは」
持って帰れという。
そこまで言われては、押しつけて帰るわけにもいかなかった。
「……さようですか。お騒がせいたしました」
銀次は角樽を取り、すごすごと裏木戸を出た。
頼まれごとが不首尾に終わったことを頼み主に伝え、受け取った金を返さなければならない。どうやら、雪之丞は伊勢屋にもおりんという女にもほんとうに心当たりがないように見えた。その真偽も訊ねてみたい。いったいどうなっているのだ。しかし、このことは亭主にばれると都合が悪いようだし、会って話すにはどうしたらいいのだろう。思わず眉間に皺が寄った。
浅草御門にさしかかったときには、日が傾きはじめていた。
元気にはしゃぐ声がして、振り返ると、神田川の川縁で子供たちが釣りをしているのが目に入った。男の子が三人、女の子も一人いて、川面に釣り糸を投げている。
見ると、水面が無数の魚影で埋め尽くされ、波立っている。ボラだ。ときおり河口などに湧いたように大群が現れることがあるが、大人は見向きもしない。とくに温かい時季のボラは、身が臭くて、猫も食べないほど不味く、「猫またぎ」といわれるほどである。
そんな食べられない魚でも、子供にとっては格好の遊び相手なのかも知れない。
「釣れた!」
「だれか、網をもってこいよ。網なら何十匹でもひとすくいだ」
「きゃあ、ぬるぬるしてる」
悲鳴と歓声と嬌声が川縁を飛び交う。
銀次は思わず橋の途中で足を止め、楽しそうな光景をしばらく眺めていた。
一人の男の子が釣り上げたボラを、水を張った桶に入れた。それを見たとき、銀次はあることを思いつき、土手を下りていった。
「坊や、その魚、売ってくれねえか」
「……いいけど」
男の子に小銭を渡した。
ほかの子たちも、何事かと集まってきた。
「この桶も貸してもらうぜ」
「いいよ」
銀次は角樽の栓を抜き、栓を鼻につけて嗅いだ。特段、変なにおいはしない。それから、樽の酒を桶の中に少し注いで見守った。
豊楽座を出たあと、ずっと気持ちの奥にわだかまっているものがあった。おりんが、雪之丞本人に間違いなく手渡ししてほしいとしつこいほど念を押したことが気になっている。雪之丞があれほどまで頑なに拒んだこともひっかかる。
それで、酒になにかあるのではないかという疑念がわいてきた。思い過ごしかもしれないが、確かめてみないと気が済まなくなっていた。
桶のなかをゆったりと泳いでいたボラが、しばらくすると、すさまじいいきおいで廻りはじめた。そして、突然全身を痙攣させて苦しみ、まもなく動かなくなってしまった。
ボラは、腹を上にしてぷかりと浮かんだ。
桶を覗き込んでいた子供たちから悲鳴が起こった。
3
このまま家に帰るわけにもいかなくなり、桶と角樽を抱えて八丁堀に足を向けた。北町奉行の定町廻り同心、平井文史郎の屋敷である。
団扇片手に縁先に出てきた文史郎は、すでに部屋着になっていたが、布団にはまだ入っていなかったようだった。
「夜分、申し訳ありません」
「よお、久しぶりじゃねえか」
「へい」
「とんと顔を見せやしねえ。つれねえ野郎だぜ」
銀次はたのまれ屋を口過ぎとしているが、じつはもう一つの稼業を持っている。岡っ引きである。文史郎から手札と十手を受けたが、岡っ引きを専業とすることも、子分や手先を抱えることも嫌って、探索を命じられたときはいつも一人で動くから、実態は下っ引きと変わらなかった。
銀次が岡っ引きであることはおおぴらにしていないので、家主以外は、近所の者もおなじ裏店の住民も知らない。
「じつは、厄介ごとがありまして」
銀次は無沙汰を詫びて、角樽と桶を差し出し、おりんの一件を伝えた。
「これがその酒か」
「へい。魚が死んだ桶も危ないので坊主に桶代を渡して引き取ってきました」
「物はなんだ。砒霜(ひそう)か斑猫(はんみょう)か鴆毒(ちんどく)か附子(ぶし)か」
「そいつはわかりませんが、手に入れやすいのは、砒霜か附子でしょうか」
「猫いらずの石見銀山てのもあるぞ」
「石見銀山は苦みがあるので、酒に混ぜても気づかれてしまうおそれがあります。それに、飲んだ量が少なかったときは確実に死なすことができません」
「それにしても毒飼い(毒殺)とは穏やかじゃねえな」
「へい」
「りんという女、どうやって毒を手に入れた」
「さあ……」
「そもそも、その女はどこのどいつだ」
「明日にでも、三十三間堂町の伊勢屋を当たってみようと思っています」
「その女が頭取(主犯)とは限らねえぞ。誰かの指図で、毒入りとは知らされず、おまえの所に持ち込んだだけかも知れねえ」
「さようですね」
「ところで、その役者は歌右衛門の弟子といったな?」
「へい」
「歌右衛門は大芝居の役者だ。その弟子がどうして宮芝居に出てる」
「さあ……どういういきさつなんでしょうかね」
「いずれにせよ、伊勢屋に当たってみてからのことだな」
「へい」
八丁堀の組屋敷を出て暗い道を歩き出したとき、どこかで五つ(午後九時)を告げる時の鐘が鳴った。
遅くなってしまった。今夜は、やえのところに行くのはあきらめよう。
「ない?」銀次は当惑して、聞き直した。「ご町内に伊勢屋という材木屋さんはないんですか?」
「ないよ」
表口まで出てきた町役人らしき初老の男がぶっきらぼうに言った。
三十三間堂町の自身番屋である。
「伊勢屋の内儀という方に用を言いつかったんですが」
町役人が番屋の狭い座敷のほうを振り返り、調べ物でもをしているのか、眼鏡をかけ、帳面を繰っている老人に声をかけた。
「瀬利屋さん、伊勢屋という材木問屋を知っているかい? 聞いたことないよねえ?」
瀬利屋と呼ばれた眼鏡の老人が気むずかしそうな顔を上げ、戸口のほうにちらりと視線をよこして言った。
「ないね。わたしの知っているかぎり、三十三間堂町どころか、木場の問屋仲間に、伊勢屋という材木屋はない」
町役人の男があとを継ぐ。
「この人は深川で古くからやってる材木問屋さんだ。この人がないというんだからないよ」
眼鏡の老人が帳面に目をもどし、すこしばかり嫌みっぽくつぶやいた。
「私が知ってる伊勢屋は、料理屋と菓子屋とそば屋と駕籠屋と早物屋(葬儀屋)くらいのもんだ」
ずいぶんとある。
町役人が銀次に言う。
「伊勢屋というのは出まかせだったんじゃないのかね。火事喧嘩、伊勢屋稲荷に犬の糞というくらい、どこにでもある屋号だ」
「木場の材木問屋のお内儀でおりんさんという方はご存じ……」
言い終わらないうちに、眼鏡の老人は無言で首を振った。
りんという女が、この世から消えてしまった。
銀次は番屋のまえで茫然と立ちつくした。おりんが内儀でないにしろ、その店と何らかの関わりがある者だとおぼろげに見当をつけていたのだ。ところが、そもそも、伊勢屋という材木問屋はないという。
そういえば、と銀次はすぐに腑に落ちる。
どうして自分で届けないのかと訊いたとき、女は思いのほかあっさりと打ち明けた。ふたりは理(わり)ない仲だったが喧嘩別れしたと。今ならわかる。理由を聞かれたときのために、もっともらしい口実をあらかじめ用意していたのだ。まんまと騙された。
あの女、いったいどこのだれだ。
「おう」
小者を従えてやってきた平井文史郎が、三十三間堂町の番屋のまえで待っていた銀次を認めて近づいてきた。このあたりは、文史郎の町廻りの廻り筋である。
「なにかわかったか」
「それが……伊勢屋という材木屋はないというんで」
文史郎はふんと鼻を鳴らし、ふて腐った笑みに口元をゆがめた。
「敵もやってくれるじゃねえか」
「酒のほうは……」
「酒に浸しておいた銀簪(ぎんぐし)が真っ黒になったとよ。やっぱり毒入りだった。いま、酒の入手先を探らせているが、まあ、わからずじまいだろうな」
下り酒を扱う酒屋は少なくないし、料理屋などからも手に入れられる。買った客までたどり着くのは至難の業だろう。そもそも、こうなると、中身がほんとうに剣菱だったかどうかも怪しくなってくる。
「旦那、雪之丞を洗ってみるというのはどうでしょう」
「役者のほうを?」
「へい。こうなると、とっかかりはそこしか残っていません」
「んー」文史郎は腕組みをして考え込んだ。「そうだな、ちょっと突っついてみるか」
「おめえ、人を殺したいと思ったことはあるか」
「……なんだね、藪から棒に」
酌をしていたやえが顔をしかめて銀次を見た。
ひさしぶりに諏訪町の家を訪ね、二階に上がって飲み始めて半刻(一時間)ほどたつ。
「あるか」
「そうだねえ、死んじまえって思ったことはあるけど、殺したいとまではねえ」
「殺すほど怨んだことはねえか」
「殺したいほど怨んでも憎くても、ほんとうに殺すのとは大違いだ。そんな恐ろしいこと、できるもんか」
「そうか」
「……なにか、御用の筋とかかわりがあるのかえ?」
銀次にはたのまれ屋のほかにもう一つの稼業があることを、やえは知っている。
「まあな」
おりんという女は、銀次を利用して人を殺そうとした。ひとつ間違えば、銀次が下手人にされ獄門となることもあったのだ。それなのに、さほど怒りが沸いてこないのが不思議だった。それはたぶん、あの女が醸し出す凛とした空気だ。毒婦や犯罪者なら隠そうとしても隠しきれない、身にまとわりついた胡散臭さや鋭利な刃物のようなものが感じられなかった。手口は悪辣で陰険だが、そこにはなにか毅然としたものがあった。雪之丞を殺そうとしたのには抜き差しならないわけがあったのではなかろうか。そう思えてならず、やえに聞いてみたのだ。女ならわかる気持ちがあるかもしれない。
「どんな野郎だ」
「え?」
「おめえが殺したいと思った相手さ」
しばらく考えていたが、「忘れた」と投げやりにいい、顔を近づけてきて耳元で囁いた。
「ここに来たときは、御用のことは忘れておしまい」
そういって唇を吸い、銀次の盃に酒を注いだ。
その柔らかな声に、心の中にわだかまっていた悲しみ、やり切れなさ、切なさ、痛み、すべての黒い澱みが嘘のようにかき消える。いい女だ、と銀次は感慨してやえを見る。
開けた窓の向こうに明るい月が見えている。雨も風もない静かな夜だった。
開いたふすまの向こうの部屋にはすでに夜具が延べられ、有明行灯の明かりにぼんやりと浮かんでいる。枕が二つ。
「今夜は泊まって行けるんだろう?」
背中を押しつけるようにしなだれかかってきた。
やえは、そんなことをする女ではなかった。その美貌とは裏腹に色気に欠け、男に媚びることもない。それがかえって気に入ってもいたのだが、今夜はいつもとちがっていた。めずらしく酔ったのかもしれない。
柔肌の甘い匂いが銀次をつつみ、奥に潜んでいた欲情をかき乱した。
後ろから抱きすくめ八口(やつくち)から手を滑り込ませると、んっと小さな声がこぼれでた。
奉行所から出てきた文史郎は、空を見上げて誰に言うともなく言った。
「すっきりしねえなあ」
空はどんよりと曇り、湿気が肌にまとわりつく嫌な陽気だった。
「おはようございます」
門前で待っていた銀次が歩み寄って挨拶すると、文史郎は前置きなしに言った。
「雪之丞に会ってきたぞ」
「え? 本人にですか?」
「そうだ」
銀次は驚いて文史郎を見た。本人に気付かれないように、ひそかに周辺を探ってみるつもりだったのだ。まさか、本人に直接聞きに行ってしまうとは。
しかし考えてみれば、雪之丞に嫌疑がかかっているのではなく殺されそうになったほうなのだから、直接たしかめてみるのも手かも知れないと思いなおした。
歩き出した文史郎を追いかけて、銀次が言った。
「それで何かわかりましたか」
「殺そうとした野郎に心当たりはねえと言いやがる」
「そうでしょう? あっしにもそう言ってました」
「どうなってるんだ。女は、雪之丞も覚えていないほど些細なことで逆恨みしたか、それともはなから人まちがいか」
なにもかもしっくりこない。銀次は歯がゆさを覚える。
「そういえばよ」文史郎は思い出してふっと笑った。「角樽を持ってきた男は、そんな恐ろしいことをするような人には見えませんでしたよ、と言ってた」
「雪之丞は、あっしが毒を入れたと思っているんですか?」
「だから、違うといっておいたよ。まっとうな、信の置ける男だとな」
「ところで旦那、雪之丞があそこまで頑固に献物を断ったのは、なにか思い当たる節があったからじゃねえでしょうか」
「というと?」
「たとえば、命を狙われている前触れがあったとか」
「ふん」文史郎は雪之丞の顔を思いうかべたらしく、鼻で嗤った。「あの色男、どんな悪さをしやがった」
「へ?」
「中村座の座元に会ってきたんだ」
定町廻りの同心は、お役目で、狂言替わりごとに演し物の検閲を行う。当代の御公儀に関わるような事件を扱っていないか、江戸府内で起こった事件を題材にしていないかなどを検閲するためである。
江戸三座にはお役桟敷(さじき)という専用の場席があって、そこで新しい演目を観て検閲する。それが縁で文史郎は小屋主の座元とも親しくなり、今では気易く言葉をかわす仲になっていた。
「雪之丞は歌右衛門の愛弟子といってたらしいが、そうじゃねえ。真名(本名)は豊作といって、ただの付き人だ。歌右衛門にくっついて上方からこっちに下ってきたんだ」
中村歌右衛門は大坂の歌舞伎役者である。江戸に招かれてしばらく中村座の舞台に立ち、絶大な人気を博したが、今は大坂にもどっている。
「すると、雪之丞も上方者で?」
「いや、もともとはこっちのほうの出らしい」
「江戸から上方にのぼって、そこで歌右衛門の付き人になったということですか?」
「そうだ。しかし、こっちにもどって来てすぐにお払い箱になった」
「どういうことです?」
「使い物にならなかったのさ。歌右衛門が舞台に上がるときの小道具を忘れる、間違える、早替わりの介添えも邪魔になるだけ、おまけに師匠の財布から金を抜いたり、楽屋荒らしなんかもやってたらしい」
「それじゃ馘(くび)にもなりますね」
「物静かで穏和な歌右衛門が、めずらしく声を荒らげて怒鳴りつけたそうだ」
「よほど腹に据えかねたんでしょうね」
「それでしばらくしたら、野郎、小芝居の人気役者になっていた。歌右衛門の愛弟子とかなんとかいって、うまくもぐりこみやがったか」
銀次はいった。
「たいそうな人気で、毎晩のようにお座敷に声がかかるそうです。贔屓筋は雪之丞の取り合いで大変だそうですよ」
「付き人のできそこないが、大したご出世だ」
「そこで、湯島あたりを聞いて廻ってみようかと思うんです。やつの身上の手がかりでも掴めねえかと」
「そいつはいいところに目をつけたな。銀次、やっぱり、おれの見込みどおりだった」
「どういうことで?」
「おめえは、岡っ引きとして勝れ者だということさ」
日本橋の高札場のあたりまで来たとき、ぽつりときた。
「降って来やがった。こいつは本降りになりそうだな。どこかの番屋で傘を借りるか」
二人はそこで北と南に別れ、足を速めた。
雨はすぐに激しく降り出したが、一刻もたったころ霧雨にかわった。
今日は湯島天神の切通坂を上っていったので、前ほどたいへんな思いをしなくて済んだ。
上がりきったところで振り返ると、そぼ降る雨の中に江戸の町がひろがっていた。
足下に不忍池が見え、むこうには大川がゆったりと流れている。晴れていれば、右手には江戸城も望めるはずだった。
左に折れて門前町に入ってゆくと、花街の色合いが濃くなる。両側に料理茶屋や巾着屋、菓子屋、煙草屋、酒屋、銭両替屋などさまざまな見世が立ち並ぶ。江戸三座の芝居町ほどではないが、芝居茶屋も何軒かある。芝居見物の客の案内や食事などの世話をする見世である。客はここに役者や芸者を呼んで遊宴もする。
湯島は陰間(かげま)の町でもあり、芝居茶屋よりも陰間茶屋のほうが目に付く。男色がもてはやされた昔とちがって、今は陰間茶屋も影をひそめたが、日本橋芳町、湯島天神前、芝神明門前の三所だけは今も健在である。
銀次は芝居茶屋をしらみつぶしに当たってみるつもりだった。
手はじめに入った一軒目で、こちらに雪之丞が来たことがあるかと聞いた。
「どちらさんで?」と訝しそうに聞き返す若い衆に、
「いま人気絶頂の雪之丞さんのことを読売に載せたいので」
と、矢立を手にして言った。
十手を見せれば気構えて、かえって口が重くなるかもしれないと考えたからである。
若い衆は読売屋と聞いて気を許したらしく言った。
「うちで遊んだことはねえが、よく見るぜ。雪之丞が通ると、通りがどよめく」
よほどの人気のようである。
若い衆は、舞台に出てきたときの雪之丞の美しさや艶っぽさを褒めちぎり、女たちが群がり取り合うのも無理はないと、人気の凄さを並べたが、身上が知れる手がかりは出てこなかった。
そのあと回った三軒の芝居茶屋も似たようなもので、手がかりは出てこなかった。
四軒目の茶屋を後にしようとしたとき、手代らしき男が銀次の背に声を投げてきた。
「雪之丞は鶴屋さんを贔屓にしている。そっちで聞いてみな」
教えられた芝居茶屋を訪ね、応対に出た女主人に役者の道に入る前の仕事やどこの生まれか訊ねてみたが、なにも知らなかった。
落胆して話を切り上げようとしたとき、女主人が言った。
「そういえば、おまえさんとおなじようなことを聞いた人がいたねえ」
「どんな人です?」
「齢は二十六、七に見えたがね、年増だけどきれいな人だった。座敷に上がって御酒と料理を召し上がったんだが、ご婦人がこういう見世に一人で見えるのはめずらしいことだから覚えているんですよ。その人が、雪之丞が大好きだとか言って、根掘り葉掘り聞いていった」
「……」
「そんなにお好きなら、一度お座敷にお呼びになってみたらいかがですかと言ったら、恥ずかしくてそんなことはできないって。変わったご贔屓さんだ」
愛想のいい鶴屋の女主人は丸い顔を崩して笑った。
「名前は……?」」
「さあ、なんといったかねえ。二度目もひとりでお見えになって、わたしを酒の相手に話をしていったんだけど」
「ひょっとして……」そう言いながら、銀次の胸は波打っていた。「三十三間堂町の材木問屋のお内儀で、おりんさんといいませんでしたか」
「ああ、そうだ、その人だ。お知り合いかえ?」
「いえ、ちくとお名を耳にしたことがあるだけで」
肌がざわっと粟立った。あの女だ。消えたと思ったあの女が、この町に来ていた。おりんという名の女が。
「二度いらしたんですか?」
おりんは、雪之丞の真名はなんというのか、在所は八王子村ではなかったかと訊ねたという。
「八王子村?」
「ええ。たしかに雪之丞さんはお得意さんだけど、そんな立ち入ったことまではねえ。てっきり上方の人だと思っていたし」
4
朝から雨が降りつづいていた。
まだ明けやらぬ六つ頃に元鳥越町を出てきたのだが、八王子村に入ったときには昼を過ぎていた。
銀次はぬかるむ田舎道に足を取られながら、やっと目指す屋敷にたどり着いた。八王子村の名主の田子久右衛門で、その屋敷も豪壮である。
出てきた久右衛門は五十二、三の、品のある男だった。
「江戸元鳥越町の銀次と申します。御用の筋でお話を伺いに参りました」
と銀次は書状を取り出した。文史郎が、関東取締出役、通称八州廻りを務める友人に書いてもらった添え状である。
関東には、関東取締出役と直結した御改革組合村という治安取締を行う組織がある。寄場組合とも称し、八王子では十五宿を親村寄場とし、それぞれ組合村を組織して、小組合に小総代、その上に大総代を置いている。
田子久右衛門はその大総代で、取締組合の中核である寄場役人でもある。だから、土地のことにも精通している。
久右衛門は軒先で雨に濡れてたたずむ銀次を招じ入れ、上がりがまちに座を勧めた。添え状を読むと小女を呼んで茶を出すよう命じ、言った。
「さて、なにをお話しすればよろしいかな?」
「偽名なのでお聞きしても詮のないことかも知れませんが、おりんという女を知りませんか。齢のころは二十六、七。とびきりの美人です」
「さて、心当たりはありませんなあ」
「では、豊作という男は? これも美形です。齢は三十少し前。今は宮芝居の役者になって、たいそう人気を呼んでおります」
「豊作……はて、聞いたような……」困ったように首をかしげていたが、「そうだ、人別帳を調べてみましょう」
と言って席を立った。名主は、村の住人の人別帳を管理している。
十数年分なのだろう、風呂敷包みを抱えてもどってきた。
手分けしてそこから豊作の名を探す。小半刻(三十分)もたったころ、
「ああ」
久右衛門が声を上げた。見つけたのだ。
「いましたよ、豊作だ」思い出したらしく、人別帳の記述を指先でとんとんと叩いて言った。「百姓がいかにもの名前なので思い出しました。戸吹村の小作人の伜です。十三年前にいなくなっていますな」
「いなくなっている?」
「いきなり、ふっといなくなったんです」
「なにか事件に巻き込まれたとか、悪いことをしてばれそうになったとかして、逃げ出したとか」
「そんなことはないと思いますよ。家族にもだれにも思い当たる節がない。理由がわからんのです。神隠しと騒ぐ者もいたが、そうですか、江戸におりましたか」
「いなくなったとき、豊作はいくつでした?」
「十五です」
今の雪之丞は三十少し前。齢の数は合う。
「どんな伜でしたか」
「さて、取り立ててなにかあったとは……」
「さようですか……」
なんの手がかりも見つけられず、銀次は落胆していた。わざわざ八王子くんだりまでやって来たのに、無駄骨に終わった。
銀次の気持ちを察してか、役に立てずに申し訳ないと久右衛門は謝った。
雨のなかをまた江戸までもどると思うと気が重かった。
それを囃すように、どこかで烏がやかましく啼きはじめた。
「おや、こんなに遅く、どうしたえ?」
夜の四つ(十時)をすでに過ぎていた。
戸板を開けたやえはすでに寝間着姿だったが、機嫌を悪くするでもなく迎えいれた。
無造作に渡された包みを開けて、いぶかしそうに見た。中身は黒地に薄鼠色の縞が入った縞物の着尺である。
「これは?」
「反物だ。おめえに似合いそうだから買ってきた」
「あたしに?」
「八王子織物だ。なにか誂(あつら)えるといい」
「渋くてなかなかいいじゃないか」嬉しそうに見入っていたが、ふと目を上げた。「八王子? 八王子村まで行ったのかえ?」
「御用の筋でな」
「そりゃご苦労だったね。くたびれたろう」
「くたくただ」
「寝る前に一本つけよう。ねっ?」
やえはいそいそと梯子段を下りていった。
疲れていたのは身体だけではなかった。気付かぬうちに、心の中から柔らかさまで消えてしまっていた。
「おめえが殺したいと思ったのは誰なんだ」
二階の座敷で酒を飲みかわすうち、ふと口をついて出てしまったのだ。
やえは飲んでいた猪口を盆にもどし、銀次を見た。
「どうしてそんなこと聞くのさ」
踏み込んではいけない過去の記憶を、こじ開けようとしていた。
先日聞いたとき、答えをはぐらかされた。辛く悲しい過去を掘り返すことになるのだと気づいて、深追いするのをやめた。あのとき、聞いたことを後悔したのに、今夜また、蒸し返してしまった。
「知りてえんだ。おめえのことをぜんぶ」
やえがぽつりと言った。
「父親だよ」
「おめえの?」
やえは小さく頷き、観念したように重い口を開いた。
父の伝三は貸本屋の奉公人で、貸本を背負って外回りをしていたのだが、不始末を起こし、暇を出されてしまった。商品である貸本や売上げの金を何度もなくし、使い込みを疑われたのである。
それからは、羅宇屋(らうや=煙管売り)、眼鏡売り、青物売り、青竹売り、冷水売りとさまざまな振り売りをやったが、どれもうまくいかず、しまいには働きに出ることをやめてしまった。
母親のトキは家計の助けにと、永代寺門前町の料理屋に女中に出たが、伝三が仕事をやめてからは、その給金が家族四人の暮らしを支える唯一の便となった。
伝三は昼日中から酒を飲むようになった。女房がもらってきたわずかな給金を当てにして酒屋に走らせるのである。
トキが、暮らしの費えが苦しいと訴えれば、「金のことをおれに言うな」と怒りだし、髪を掴んで引きずり回し、殴る蹴るした。
だから、やえと幼い弟にとって伝三はひたすら恐ろしい存在だった。濁った酔眼で睨みつけられると身がすくんだ。
母親のトキが、料理屋の仕事が長引き帰りが遅くなると、家の者が腹を空かせて待っているのに飯もつくらず余所で油を売りやがって、それでも女房かと怒鳴りつけ、いつものように頬を張り、髪を掴んで引きずりまわした。いつまでもやめない伝三に弟がしがみついて「やめて」と泣き叫んだ。やえも、「やめて」と泣いて懇願し、突き飛ばされて竈(かまど)に顔をぶつけうずくまっているトキに抱きついて庇う。それでも、伝三は疲れて眠り込むまでやめなかった。毎日のように繰り返される修羅場だった。
兄妹で相談して、別れたほうがいいとトキに言ったことがある。しかし、女の側から離縁を申し出るなど道義にはずれたことはできないと言う。
離縁ができないなら、三人で逃げようと言ったのだが、そうもいかないと母は力なくうなだれるだけだった。そのときのトキの気持ちがやえは今も理解できない。誰の目から見ても伝三はろくでなしだったし、女房に逃げられても当然の男だった。
だからといって、父親への恐怖心や嫌悪感が殺意に変わることはなかった。どんなろくでなしだろうと父は父であり、敬うべき家長だから、殺すなどは思いもよらないことだった。母もおなじだったのかも知れない。どんなに虐待されようと、女というものは男に仕え尽くすものだという考えに囚われていたのだ。
「おめえは、いつも明るくてよく笑う子だった」銀次はしみじみと言った。「まさか心中にそんな辛い思いを抱えていたとはなあ」
「そりゃそうだよ。父親が荒れはじめたのは、銀ちゃんがよその町に移ったあとだからね」
やえが十四のとき、トキは苦労がたたったのか、風邪をこじらせてあっけなく死んだ。二つ下の弟は大工に弟子奉公していたし、やえは清元の師匠宅の通いの女中をしていたが、かねてから勧められていたこともあって住み込みになった。
兄妹は佐賀町代地の裏店に寄りつかなくなり、ときどき無心に来る父親を追い返した。つまり二人の子は、母の死をきっかけに伝三を捨てたのだった。
伝三は物乞いと変わらぬまでに堕ちた。道行く人に酒代をねだり町を徘徊するようになったのだ。そして、ある雨の日、足を滑らせ油堀川に落ちて死んだ。
やえが伝三を殺したいとはじめて思ったのは、つい先だってのことである。母の墓前に手を合わせていたとき、トキの憐れな生涯が思い返されて、あらたな悲しみに心が震えた。それとつながって、伝三の数え切れないほどの無法がつぎつぎとよみがえった。
子供のころは父の専横ぶりにひたすら怯えているだけだったが、今なら真の姿をはっきりと見定めることができる。そこには、父としての自負も威厳の欠片もなかった。
あの男は、生きる力をどこかにおいてきてしまったのだ。生きる力がないことを嫌と言うほど思い知らされ、前に進むことをやめてしまったから、あんな生き方しかできなかった。本人も辛かっただろうと思う。しかし、それがどうしたというのだ。同情する筋合いなどどこにもない。わたしたちはそのせいでさんざん苦しめられたのだ。
突然殺意が突き上げてきたのは、そのときだった。母を殴り、髪を掴んで引きずり回す伝三を殺したいと思った。
その父親は、五年まえに死んでいた。
「だけど、あいつはもういないんだ。この気持ちをどうしたらいいのさ」
やえはため息混じりに独り言ちた。
「聞いて悪かったな」
銀次は素直に謝った。
「父親を殺したいと思ったんだよ? 実の父親を。なんて女だろうねえ。親を殺したいだなんて、あたしゃ人でなしだ」
あふれた涙が頬を伝い落ちる。その透き通った涙が、銀次の胸にしみる。
やえが愛おしかった。
抱き寄せて、命を絞り出すように言った。
「おめえはなにがあってもやえだ。優しくて、心ばえのある、いい女だ」
美しい女は、細い肩をふるわせ、銀次の胸の中でいつまでも泣いた。
底の見えない深い夜だった。
朝いちばんで文史郎に八王子の聞き込みの結果を報告し、その足で浅草茅町の老人宅へ行って庭の草引きをすませた。こちらは頼まれ屋の仕事である。
つぎの日も朝から障子紙の張り替え、家移りの手伝いと頼まれ屋の仕事をこなした。そうしているあいだも、探索のほうに気が行って落ち着かなかった。
おりんが、雪之丞がいつまでたっても死なないのでたしかに酒を届けたのか文句を言いに来ないか、あるいは、業を煮やしたおりんが、ふたたび雪之丞殺しを試み、やってきたところを押さえられるのではないか、などと思いをめぐらしたが、事がこちらの思惑通りに都合よく運ぶはずもなかった。何事も起きず、時だけがいたずらに過ぎていった。
つぎの日、布団から這い出して遅めの昼飯をとっていると、開け放した戸口から声がした。
「銀次さんはこちらで?」
戸口から中を覗いているのは、飛脚だった。
「へい」
「早便り(速達)でございます」
八王子村の田子久右衛門からだった。銀次が帰ったあとさらに調べて、取り急ぎ書き送ってくれたのだ。
部屋に戻るのももどかしく、軒先で手紙を開いて文字を追いはじめた銀次の顔が、見る見るうちにこわばった。
5
「八王子村の田子久右衛門さんから手紙です」
文史郎は銀次から手紙は受け取ったが開いて読むこともなく、訊いた。
「なんと書いてある」
「読んで肌が粟立ちました」
銀次が帰ったあと、久右衛門が、戸吹村の益田徳之助という名主に、真名を豊作という男のことをたしかめてくれたのだった。手紙はその報告である。
今から十四年前、名主の徳之助の家で盗難事件があった。屋敷の奥の間に置いてあった二つの金箱のうち、村入費の一時金五十数両が入った金箱が盗まれたのである。
なくなっていると気づく半刻ほどまえ、小作人の仙吉が来て、不在にしていた徳之助の帰りを待っていたが、しばらくして帰った。仙吉が疑われたが、そんなことをする男ではなかったので、疑いはすぐに消えた。しかし、その夜、豊作が徳之助のところに来て、仙吉が重そうな物を抱えて歩いているのを見たと告げた。
金箱かと聞くと、それはわからないが、調べてみたほうがいいかもしれませんと言って帰っていった。
徳之助が寄場役人を伴って仙吉の家を調べると、家裏の雑木林から金箱が見つかった。箱はばらばらに壊されて土に埋められており、中身はなくなっていた。盗んだのは仙吉だということになった。
しかし、徳之助は仙吉がやったとはどうしても思えず、不問にして、盗まれた金は徳之助自身が穴埋めし、事件は犯人がわからぬまま終結とした。
しかし村人たちの疑いは解けず、村八分にされた。それから一年もしない秋の終わりのある日、仙吉は一家心中を計った。その年は未曾有の大凶作で、口にできる米が一粒もなくなったので、それもあったのかもしれない。
仙吉夫婦と幼い息子は死んだが、娘が一人生き残った。父親に首を絞められたのだが、徳之助たちが駆けつけたとき、息を吹き返したのである。
豊作が村から姿を消したのは、その直後のことだった。
生き残った娘は、日本橋横山同朋町の遠戚に養女として引き取られた。遠戚は蕎麦屋で、屋号は「武蔵屋」という。
そのとき娘は十四歳で、名は志乃といった。
話を聞き終わった文史郎は、睨みつけるように銀次を見た。
「銀次、しかと頼むぜ」
「へい」
すぐさま同朋町に向かった。
武蔵屋という蕎麦屋はまもなく見つかった。奥で蕎麦を打っていた初老の主人に、こちらに志乃という方はおいでですかと訊ねると、たしかにうちの娘だが、ずいぶんまえに嫁入ったという。
嫁ぎ先は有田屋。日本橋今川橋跡の瀬戸物屋である。
有田屋は、間口十間もある立派な店構えの、伊万里焼を中心に品揃えしている陶器屋だった。
志乃は家を留守にしていた。御用の筋と聞いて応対に出てきた主人の七兵衛は、女房は病み上がりでなかなか元気がもどらないので、気散じをかねて熱海の温泉に湯治に行かせたといった。
戻りはと訊くと、いつになるかわからないと答える。
「病み上がりといいますと、お内儀はなにか病でも?」
「……ええ」
怪しいと銀次は感じる。七兵衛はいかにも誠実そうで嘘をつくような男には見えない。その正直者が必死に嘘をついている。
「ところで、なにをお調べなので?」
銀次は答えに迷ったが、ここで思い切って揺さぶりをかけてみることにした。
「雪之丞殺しの件で」
「えっ……」
七兵衛の顔からたちまち血の気が引いていった。
「あの宮地芝居の人気役者の雪之丞ですか?」
「左様で」
「それと志乃がどういう関わりがあるとおっしゃるのです」
「さあ、そいつをいま調べているところで」
おれは、雪之丞と名前を言っただけだ。七兵衛は、雪之丞が何者かを知っていた。志乃が絡んでいるとは一言も言っていないのに、あっちから言い出した。
「お帰り下さい」七兵衛は唇をわなわなふるわせながら言った。「うちの女房が人殺しなんて、とんでもない言いがかりです」
「さようですか。それじゃひとまずお暇するといたしましょう」
立ち上がり、帰りかけたが、思い出したように振り向いて言った。
「てめえの女房が人殺しだなんて、考えただけでもゾッとしますやねえ」
店を出るとすぐに裏に回り、見張りについた。
志乃が家から出てくるか、どこかからもどってくるかもしれない。
別れ際、吐いた嫌味な台詞は、七兵衛の気持ちをさらに追いつめるためだった。
いくら探索のためとはいえ、おれも嫌な男だぜ。
その日の見張りは徒労に終わった。志乃は家の奥に身を隠しているのか、七兵衛のいうとおり湯治に行っているのか、姿を見せることはなかった。
元鳥越町の裏店にもどり、疲れた身体を横たえて、枕元の行灯の火を落とそうとしているところに、表戸を叩く者がいた。
「銀次さんはおいでですか」
戸を開けると、そこに男が立っていた。昼間話した有田屋の七兵衛だった。
「お話ししなければならないことがございます」
と七兵衛は言った。
招じ入れて戸を閉め、上がりがまちに座をすすめた。
銀次は、無言で、話し出すのを待った。
やがて七兵衛は苦しそうに口を開いた。
武蔵屋の娘志乃は、十五のとき薬研堀の水茶屋で茶汲み女として働くようになった。その美貌が評判を呼び、人気絵師によって美人画にも描かれてたちまち人気に火がつき、店に客が押し寄せることとなった。
ある日、七兵衛は休息を取りにその店に入った。日本橋室町の瀬戸物問屋の手代をしていた七兵衛は、出商いでその界隈を回っており、たまたまその店に入ったのだ。江戸で評判の看板娘がいることなど露ほども知らなかった。
そのとき、茶を飲み終わった七兵衛のもとに桜湯を持ってきた娘を見て、雷に撃たれたような衝撃に襲われた。一目惚れだった。この人が、わたしの妻になる人だと思った。
それからというもの、店に通い詰め、ある日、勇気を振り絞って、もうすぐ神田祭だがいっしょに行かないかと誘った。
それをきっかけに二人の仲は深まり、志乃が十七になった春、めでたく祝言を挙げた。
七兵衛は夫婦になって一念発起し、独立して精励し、とうとう店を構え、奉公人を使うまでになった。
志乃は美しいだけでなく、気が細やかで、そのうえ、大事には冷静に対処する度量もそなえ、頼りになる女房でもあった。七兵衛にとって志乃は、かけがいのない人となった。
「その志乃が近頃元気がなく、夜ごと忍び泣いているのを見て、なにがあったのかと問いました。志乃はすべてを打ち明けてくれました。
知り合いの大店のおかみに誘われて湯島の宮芝居を見物に行った帰り、門前町の通りで親の仇に出くわしたと。今をときめく人気役者、雪之丞が、両親と弟を死に追いやった張本人、豊作だったと。しかし、わたしには親の無念を晴らすことができない、とんだ親不孝者ですと志乃は泣くのです」
七兵衛の話はつづく。
「この齢になって女房の惚気(のろけ)などみっともない話ですが、夫婦になってますます、日をかさねるごとに志乃のことが好きになって参ります」
その表情に笑みはなく、恋する者の思い詰めた切なささえ見える。
「だからどうしても許せなかったのです。大金を盗み、その罪を志乃の父親になすりつけ、一家心中にまで追い込んだ男が。
仇を討とうじゃないか、とわたしは申しました。それじゃおまえ様や二人の子供、店の使用人にまで迷惑が、と志乃がいうので、かまうものか、そんな奴は生かしておいちゃいけないと申しました」
銀次は訊いた。
「それでは、七兵衛さんが……」
「はい。豊作を殺そうと決心し、毒入りの酒を用意したのはわたくしです。志乃に罪はいっさいありません。身元がばれないように偽名を使い、よその者に頼んで持って行かせるようにと言い含めたのもわたしでございます。志乃は、毒入りとは知りませんでした」
「それであっしに白羽の矢が立ったというわけで」
「お詫びの言葉もございません。ですが、ほかに手だてはなかったのです」
「罪悪人の身勝手な申し立てですね」
「おわかりください。可愛い女房を死罪獄門にかけるわけにはいかないのです」
「ところで、志乃さんは毒入りとは知らなかったとおっしゃいましたが」
「はい」
「それでは志乃さんは、毒入りでもないただの酒を豊作に届けるだけだと思っていた?」
「はい」
「それが親の敵討ちになるんですか?」
そう言われて、人の善さそうな志乃の亭主は言葉を詰まらせた。自分の弁明にほころびがあることに気づいたのだ。
七兵衛の言うことのなかにどれくらい真実が含まれているのだろうか、と銀次は探っている。
七兵衛一人でやったというくだりは嘘だ。この男は、自分一人で罪をかぶるつもりなのだ。そこまで女房に惚れているか。
「ところで七兵衛さん、雪之丞はまだ死んじゃいませんぜ」
「え?」
「そんな話は聞こえてこないでしょう」
「はい、そういえば……」
「献物の剣菱を持っていったんですがね、突き返されました」
「じゃあ、あの酒は……」
「今もわからないのですが、豊作は、なぜ献物を受け取るのを嫌がったんでしょう」
「………」
「酒を持って行くまえに、脅し文でも投げ込んだんじゃないですか? 村の五十両を盗んだのはおまえだとか、仙吉が一家心中したのはおまえのせいだとか。そうでもなきゃ、あそこまで用心するはずがねえ」
「………」
「結句、それが豊作の命を救うことになったんですよ。皮肉としかいいようがありませんね。ところで、これからどうします?」
相手は意味が飲み込めず、いぶかしげに銀次を見る。
「自訴に参ったのです。お縄を掛けて御番所にお連れねがいます。お縄を掛けられるなら、ぜひとも銀次さんにと」
「もう遅い。今夜はひとまずお引き取り願いましょうか」
「それは……どいうことでしょう?」
「七兵衛さんはどこにも逃げやしないでしょう? ま、逃げてもかまいませんがね」
「何をおっしゃっているのか……」
「眠くて、頭がうまく働かねえ。失礼しますよ」
答えを待たず、行灯の火を消し夜具にもぐり込んだ。
暗い部屋にしばらく静寂があったが、やがて黒い影が立ち上がり、表に出た気配がして、障子戸が音もなく閉まった。
おもてで飛び交う長屋の女房たちのやかましい声で目が覚めた。
そろそろ布団を出るかとぐずぐずしていると、女房たちの騒々しい話し声がふととぎれ、同時に表戸が静かに開いて、女が入ってきた。
こんどは女房の志乃だった。
戸惑いを隠して銀次は言った。
「これはおりんさん、やっとお目もじ叶いましたね」
「今日はお礼にうかがいました。あなたさまがいなければ、大きな過ちを犯すところでした。それをとめてくださったこと、心からお礼を申し上げます」
「礼なんぞ……」
「心ばかりですが」
志乃が手に提げていた角樽を上がり框に置いた。
「いえ、お心遣いは無用です。どうぞこれはお持ち帰りを」
「毒など入っておりませんよ」
志乃は小さく笑い、お世話をおかけしましたと頭をたれてきびすを返した。
嫌な予感がして、思わず呼び止めた。
「お志乃さん、今からどちらへ?」
「呉服橋御門内の御番所へ」
「どんな用向きで?」
「毒飼いをたくらみましたと自訴しに参ります」
「雪之丞はぴんぴんしておりますぜ」
「ですが、殺そうとしたのは紛れのないことで」
「お志乃さんが殺したのは、ボラ一尾です」
「……ボラ?」
「夫婦になって十年、ご亭主は今もお志乃さんにぞっこんのようで」
「……七兵衛と話したのですか?」
「夕べこちらに見えられましてね、さんざんお惚気を」
「えっ……」
「今の仕合わせをわざわざ台無しにすることはねえと思います」
「………」
「さあ、家にお帰りなさい。ご亭主がお待ちですよ」
志乃は無言で立ちつくしていたが、やがて顔がゆがみ、目に光るものがあふれて、固く閉じた口元がこまかく震えた。
お志乃が立ち去ったあと、銀次はそのまま座り込んでぼんやり空を見ていた。何も解決してはいない。それでもなぜか、澱んでいた黒いものが消え、心に光がさし込んだようだった。
気がつくと、昼どきになっていた。飯でも炊くか、と立ち上がり、布団を片づけて、米を研ぎはじめた。
竈の前にかがみ込んで火吹き竹を吹いていると、腰高障子がいきなり開いて、侍が飛び込んできた。文史郎だった。
「銀次、いるか」
「おや、八丁堀」
「行くぞ」
「でも、いま飯を炊いて……」
「あとにしろ。雪之丞が刺された」
「ええっ?」
6
番屋の土間に置かれた戸板の上に雪之丞の亡骸が横たわっていた。
胸と喉を刺され、藍白の派手な単衣が血で真っ赤に濡れている。
「下手人は?」
「お縄をかけられて今は大番屋だ」
「まさか……」
お志乃か七兵衛かと胸が騒いだ。
「おりんじゃねえよ」文史郎はにっと皮肉っぽい笑みを銀次に向けて言った。「どこかの大店のお嬢様だとよ。ほかに女をつくったとかなんとか、悋気昂じてかっときてやっちまった。お座敷に飛び込んできて、大勢の目のまえで包丁でぶすりとやったんだから、下手人ははなからわかってる。これで一件落着だ」
銀次はほっと胸をなで下ろす。
「これで、毒入り下り酒の件も仕舞いだ。そういうことでいいな?」
「いいんですか?」
「それしかねえだろう。五十両盗んだ当人が死んじまったんだ。それとも、死人をお白州に引っ張り出すか?」
旦那もとぼけたお人だ、と銀次は苦笑する。話をすり替えて、毒入り酒の一件も幕引きにしてしまおうと言っている。
「ありがとうございます」
「礼を言われる筋合いじゃねえ」
雪之丞の死を知って世間は騒然とし、女たちは取り乱し、日々泣き暮れることだろう。しかし銀次は、とてもそんな気持ちにはなれない。いつしか志乃夫婦に親近感を抱くようになっていたし、同情心も湧いていたのだが、文史郎もきっとおなじ気持ちなのだろう。雪之丞の死は自業自得だし、みずからが招いた運命だったのだ。
五十両を盗んだ罪ではなく、それとはまったく関わりない色恋沙汰で死罪という裁きを下したのは、お天道様の悪戯心かも知れない。
それにしても、あっけない、拍子抜けするような幕切れだった。
銀次は人気役者の亡骸を見下ろし、気の抜けたような吐息をふうともらした。
「銀さん」
やえが梯子段を上がってきて、二階の座敷で先に一杯やっている銀次のまえに立った。黒地の縞物の着物に着替えていた。
「お」
思わず声をあげた。先日、土産に持ってきた八王子織物で誂えた小袖である。
「どうだえ? 知り合いの縫子さんに無理を言って、急いでやってもらったんだ」
なかなかいい。女っぷりがますます上がったと思うが、照れくさいからそうは言わない。
「ま、いいんじゃねえか」
「なんだよ、素直じゃないねえ」
笑いながら近づいてきて、となりに座った。
「おめえも一杯やりな。上物の下り酒だ」
「美味しい」
やえが酌を受けた剣菱を一口味わって、声を漏らす。
「実はね」やえがいきなり切り出した。「昨日、志乃さんという人と話をしたんだ」
「え?」
「おまえさんの家に行ったのさ。ちょいと野暮用でね。そしたら、薄暗い上がりがまちに知らない人がいるじゃないか。あたしゃ、びっくりして腰が抜けるかと思った。それがお志乃さんだったんだ」
「そうか、来たのか」
「あまりにもしょんぼりしてるし、訳ありのようだったから、ここに連れてきたんだ」
「ここに連れてきたのか……?」
「ああ。話はぜんぶ聞いたよ。たいへんだったんだねえ」
「なにを聞いた」
「なにもかもさ。生まれ在所から金箱盗みの濡れ衣を着せられて村八分になったとか、今日までのいきさつまで。雪之丞はまだ死んでいないらしいけど、まもなく毒入り酒を飲んで死ぬだろう。わたしは人殺しですって」
「そうか」
「わたしも父親を殺したいと思ったって打ち明けた。殺すことは叶わなかったけど、罪深さに変わりはない。生きるってことは、そういう因果を背負うことなんだってあたしは言った。ね? まちがってないだろう?」
「ああ、おめえの言う通りだ」
銀次も自分の背中に負った因果の数々を思い起こす。
辛く悲しいものだったが、人はその重さに堪えて生きていかなければならないのだ。生きているかぎり贖罪を望むなど許されない。
「ところで、おれんところに来た野暮用ってな、何だったんだ」
にこりとしてやえは席を立ち、すぐに戻ってきた。
「これ、おまえさんに」
目の前に広げられたのは、古渡り胡麻柄の唐桟の着物だった。
「帯も買った。どうだい、粋だろう? 銀さんにお似合いだ」
「こいつは、持参金のかわりかえ?」
「……え?」
振り向いたやえの表情が固まった。
「おやえ、おたがい、そろそろ年貢の納め時とは思わねえか」
「……ちょ、ちょっと待っておくれ。確かめておきたいんだけど、それは祝言の申し出かえ」
銀次が気恥ずかしそうに頷く。
やえは顔を輝かし、手を差し伸べる銀次の胸に飛び込んでいった。
了
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
