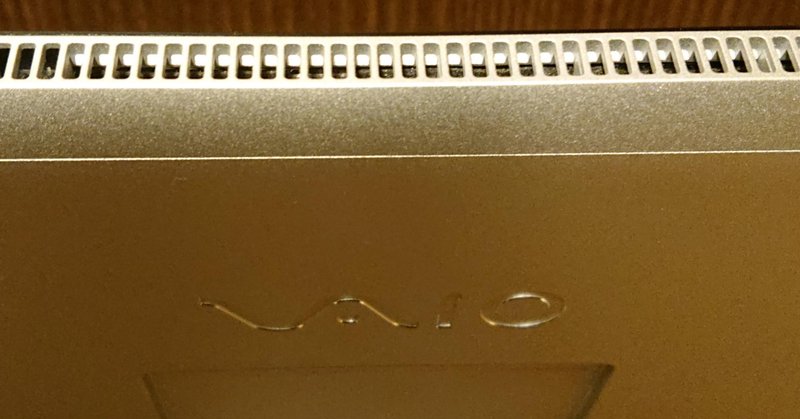
XPS13を手放したワケ、スペック表に出てこない性能
以前、僕のノートPC遍歴ということで、XPS13を早々に手放したことを書きました。その理由について書こうと思います。
DELLのXPS13は、とてもコストパフォーマンスの高いPCでした。画面解像度も高く、Core-i7、16GB RAM、SSD(容量は忘れてしまいました。)と、ノートPCとしては十二分なスペックで、しかも、値段もリーズナブルでした。
満足して仕事に使っていたのですが、ある日事件が。
XPS13にとあるCAEソフトをインストールして、シミュレーションをしました。時間のかかる計算だったので、CPUの使用率はほぼ100%のまま数十分放置していました。
なんと、勝手に電源が落ちてしまい、シミュレーション結果は得られず。
キーボードや底面がムチャクチャ熱くなっていました。熱で落ちたのです。
XPS13で、CAEなんかやるなよ、って話もありますけれど、そのシミュレーションをXPS13でやるため、構造を観察。
XPS13は、底面から空気を取り入れ、本体奥から温まった空気を排出する構造でした。ゴム足で底面は浮いてますが、机表面とPC底面までの空間の厚さは数mmです。
これでは熱い空気を吸い続けどんどん熱がたまるのは火を見るよりも明らかです。
そこで、雑誌などで、底面の吸気口をふさがないように数センチ持ち上げてあげると、熱がこもらず、シミュレーションが無事に終了しました。
と、いうことがあって、XPS13は手放すことにしました。
そして、仕事用のPCは中古のVAIO Z Canvasになったのです。VAIOはタブレット部分の背中から吸気し、上面のスリットから温まった空気を排出します。熱暴走で落ちることはなくなりました。
こういう、熱設計のことはスペック表には出てこないですよね。
XPS13を責めるつもりはありません。同じような熱設計のノートPCはたくさんあります。とんでもない負荷をかけない限り、十分な働きをしてくれます。
熱設計というと、最近のVAIOは、VAIO True Performanceと呼ぶ技術を使って、CPUの高速化を図っています。うまくCPUの熱を逃がしてやることで、より高速にCPUを動かすという技術です。ざっくり説明すると、CPUは熱くなると動作周波数を落とすようにできていますので、なるべく熱くしないという手法で高速化を図るというものです。
これがあるので、僕は、WindowsモバイルPCとしてはVAIOのSXシリーズをお勧めします。
熱設計って、スペック表には出てこないので、分かりにくいです。ヘビーな作業をされる方は、熱設計がどうなっているかというのは重要なポイントになるという話でした。
最後までお読みいただきありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
