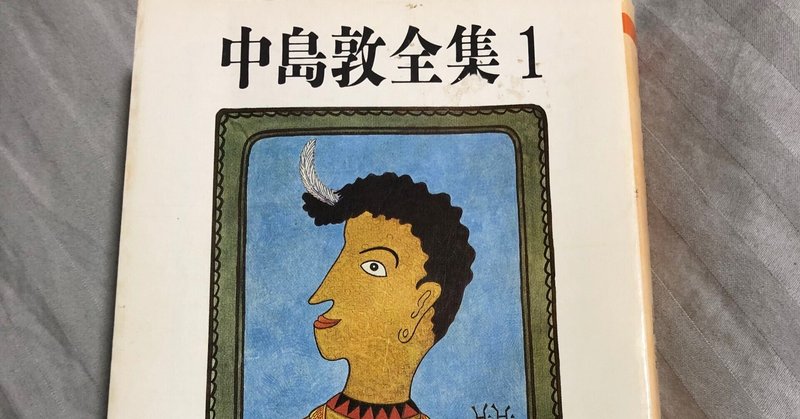
中島敦「光と風と夢」
奇数章が、小説「宝島」や「ジキル博士とハイド氏」などを著したロバート・ルイス・スティーブンソンと彼にまつわる叙述であり、偶数章がサモア在中のスティーブンソンによる日記となっている。趣向を凝らした構成である。
僕には読み進めるまで、この構成に気が付かなかった。あまつさえ、話が行ったり止まったりするので読みにくいとすら感じでいた、
読む前にはこの作品が、中島敦の南洋時代の生活を素材にした「爽やかな青春物語」を期待していたのだけど、全然違っていた。
おまけに、何を描こうとしているのか全くわからない。長いばかりで分かりにくく、途中で一旦挫折してしまった。
でも、読まないままというのも癪なので、また読み始めたら、半ばあたりで漸くこの構成の狙いみたいなものが分かるようになり、面白くなってきた。
読み進めていくうちに主人公スティーブンソンの姿がくっきりし始めてきたのである。
七章では、代々スコットランドの灯台技師であったスティーブンソン家の歴史が記され、また九章では、スティーブンソンの小説家としての生き様が記されている。
この辺で作調が締まってきた気がした。
五章のサモア政治情勢(偶数章はこれについて描いている日記)を読んだ時には、爽やかさへの期待は裏切られ、疲れてしまったのだが。
スティーブンソンの「宝島」は(retold版だが原語で)読んだことがある。
その内容もそうだったけど、そこの挿画の荒々しさからから、スティーブンソン自体かなりマッチョな人間なのだろうと思っていたが、マッチョなのはメンタリティだけであり、フィジカルには肺結核、胃痛、神経痛を持病とする虚弱体質であったようだ。少し驚きである。
サモアを愛し、サモア人を利用しようとする帝国主義国家である英仏独に対抗するスティーブンソンではあるが、やはり一外国人によるペンによる戦いには限界があり、傀儡の王ラウペパに対して、スティーブンソンが応援する高潔で英邁マターファとその一統は負けてしまうのである。
サモアの政治情勢が一旦落ち着いた後、ストーリーはスティーブンソンの内省的な動向を描くものに発展してゆく。
スティーブンソンによる人生論、文学論へと話が飛翔するのであるが、これはおそらく同じように体を壊して南洋で健康を取り戻そうと過ごした作者中島敦の思い出もあるのだろう。
ラストシーン近く、南洋の美しい夜明けの風景が描かれ、そして、スティーブンソンの死へと至る。
とても快い作品だった。
この作品は「文学界」昭和17年5月号に一挙全文掲載され、その年の芥川賞候補となった。
しかし、この時は「該当作なし」ということで惜しくも受賞できなかった。
解説によると、選考委員であった川端康成は強く推しており、「芥川賞に価ひしないとは、私には信じられない」と書いている。
また、「文学界」編集者の深田久弥曰く、「戦争騒ぎで詮衡委員たちの頭がどうかしていたのだろう」とのことであり、評論家の吉田健一はこの形式に日本の文壇が受け入れられなかったのかもしれない、と述べている。
確かに名作と言っても過言ではない作品だった。
20240112
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
