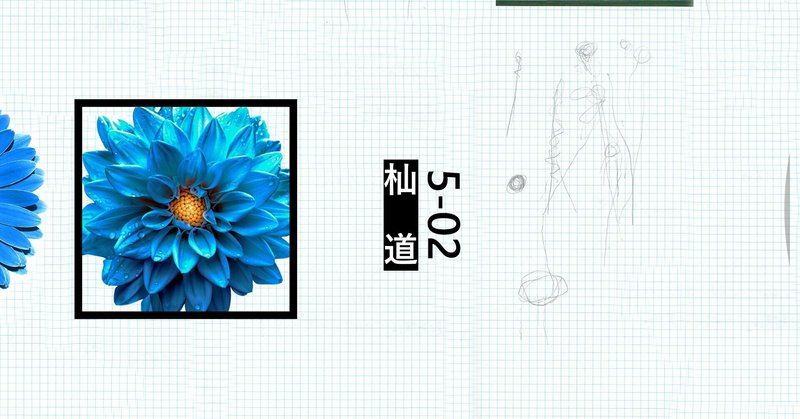
パルマコンとしてのノスタルジア
9人の読書好きによる、連想ゲームふう作文企画「杣道(そまみち)」。 週替わりのリレー形式で文章を執筆します。前回はRen Homma「記憶の縦パス」でした。
【杣道に関して】https://note.com/somamichi_center
【前回までの杣道】
5-01 「記憶の縦パス」Ren Homma
https://note.com/nulaff/n/nc0088a7b0906?nt=magazine_mailer-2021-05-24
4-07 「龍ちゃん」屋上屋稔
https://note.com/qkomainu/n/n6c5035f11334
__________________________________
ノスタルジアは劇薬だ。劇薬とは毒性の強い医薬品、つまり摂取量を誤ると生命に危険を及ぼす薬ということだ。ところで、薬局のことを英語でファーマーシー(pharcy)、あるいは薬理学のことをファーマコロジー(pharmacology)というが、その語源はギリシア語パルマコンあるいはファルマコン(pharmakon)からきている。ギリシア語のパルマコンにはもともと、毒と薬という両義的な意味があったそうだ。
プラトン『パイドロス』の冒頭で、ソクラテスはパイドロスに対して、パルマコンという言葉の由来となったパルマケイアーの神話を語っている。パルマケイアーは治療のための泉を意味し、その泉のほとりでポレアス(北風)にさらわれた若き乙女オーレイテュイアがパルマケイアーの辺で遊んでいた際に、ポレアスに押されて奈落の底に落とされてしまう。治療のための泉と若き乙女の死。治療薬であると同時に毒薬でもあるパルマコン。
ジャック・デリダは「プラトンのパルマケイアー」という論考のなかで、なぜ、ソクラテスは『パイドロス』の冒頭で、パルマケイアーの神話を語ったのかと問うている。対話の先でソクラテスはパイドロスが携えてきたテクストを薬物に喩えている。つまり、ソクラテスはテクスト(エクリチュール/書かれたもの)の両義性(治療薬と毒薬)を問うために、パルマケイアーの神話を持ち出したというわけである。では、ソクラテスにとってのテクストの持つ両義性とはどういうことか。テクスト(書くこと)は記憶を助けるための薬ではあるが、それは記憶したことを思い出す助けになるにすぎず、むしろ想起(アナムネーシス)の妨げ(毒)になる。ソクラテスはここでエクリチュール批判(弁論家批判でもある)をしているわけである。そういえば、文献学者ニーチェも、プラトンのテクスト(対話篇)は、教育のための想起手段であって、文字テクストととらえてはならないと語っていた。
閑話休題。ここまでの話は、なぜか、古代ギリシア時代以来、記憶と薬(パルマコン)の相性がいいという話にすぎない。ここからが本題なのだが、ではノスタルジアとはどのような記憶の状態のことか。一般的な辞書によれば、遠く離れた故郷や過去の事象について、懐かしみ、しみじみと思いを馳せる心境とある。空間的にも時間的にもあまりに遠くに来てしまったが、「できれば戻りたい、でも戻れない」という意味合いもある。
またまたギリシア語を持ち出して恐縮だが、ノスタルジアの語源はギリシア語のnostos(家に帰る)にあるらしい。nostosにalgia(苦しい状態)を結びつけて、17世紀後半頃にノスタルジアを造語したのがスイスの医師ヨハネス・ホーファーだそうだ。ホーファーはスイス人の傭兵が極度のホームシックにかかった状態を見て、この言葉をつくったという(ちなみに、ノストフォビアという言葉もあるらしい。こちらは帰郷嫌悪、故郷や家郷に対する恐怖や嫌悪をいうそうだ)。したがって、確かに、ノスタルジアには戻りたいけど、戻れないという苦しい意味合いもあるわけだ。しかし、言うまでもなく、ノスタルジアには甘美さが伴う。苦しさと甘美さ。おっ、またまたパルマコン(両義性)だ。
ところで、ノスタルジアは突然、喚起されることがある。ある風景や物を見たり、触れたり、いや、プルーストのマドレーヌ菓子のように、匂いや音によっても喚起される。この「突然に」というのが厄介だ。覚えたもの、学習したものを思い出すわけではない。あくまでも受動的に、現在の知覚が刺激されたとき、沸き起こる。脈絡を欠いた記憶。そこではどのような知覚の回路が形成されているのか。さらに厄介なことには、刺激のもととなった事物が自分のこれまでの経験とはまったく無関係に思える時だ。例えば、外国の風景や家屋の写真や絵を見た時。明らかに自分の故郷でないどころか、過去の経験にさえもない。
そういえば、映画『ノスタルジア』を撮ったタルコフスキーが「ノスタルジアとは、ロシア人がソ連国内を旅行した時には感じないが、ひとたび外国に旅行すると必ず強く襲いかかる感情で、死に至る病いに近いとさえ言える独特のものだ」と語っていたのをどこかで読んだ気がする。つまり、ノスタルジアという感情は必ずしも、自分の過去や実際の故郷につながるとは限らないということだ。とするならば、ノスタルジアはかつてあったものやいまは失われてしまったものを懐かしみ、思いを馳せるだけではない。むしろ、あり得たかもしれないもの、あり得るべきであったものが失われてしまったからではないか。だからこそ、苦しさと甘美さがあるのだ。
デジャビュ(déjà vu 既視感)という現象がある。はじめての経験なはずなのに、以前経験したことのあるような錯覚をもたらす現象だ。デジャビュに関しては、現在の経験と過去の経験の類似性が高いほど、既視感が高まると言われている。ベルグソン的にいえば、想起としての記憶力が現在の知覚に混入し、どれが現在の知覚でどれが記憶か識別できない現象と言えようか。
あったものとあり得たもの(あるいはあり得るべきもの)。後者の場合のノスタルジアは、デジャビュのようなものではないか。構想力(想像力)について、カントは『人間学』のなかで「過去のものをわざわざ現前化する能力は想起能力であり、何かを未来のものとして表象する能力は予見能力である」と語っているが、あったものとあり得たものへのノスタルジアは、デジャビュのような二つの能力の交差といえないか。ノスタルジアは現実逃避のための感情にすぎないとしばしば言われるが、後者の場合にはむしろノスタルジアに積極的な面があるのではないか。実際、タルコフスキーが描いた『ノスタルジア』のなかで、主人公の詩人アンドレイ・ゴルチャコフが夢見る故郷は、主人公の故郷ではないだろう。世界が救済されるために、あり得た世界、あり得るべき世界だったのではないか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
