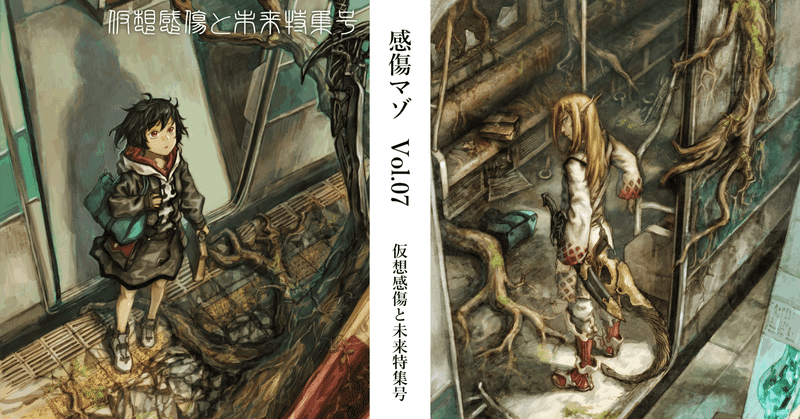
感傷マゾvol.07より 『VR座談会』
※この記事は、「第三十四回文学フリマ東京」(2022年5月29日(日))にて頒布した『感傷マゾvol.07 仮想感傷と未来特集号』収録の「VR座談会」を転載したものです。本座談会は2021年10月に収録を行いました。
「私たちが生まれつき家庭用ゲーム機のコントローラーと共にあったように、生まれつきVR機器と共にある未来の世代が仮想現実の中で行う感傷」を「仮想感傷」と呼ぶならば、それはどのような行為や感情をもたらすのか?
既に、新型コロナウイルスによって、様々なイベントどころか外出すらままならなくて、「青春」自体が十代の若い人にとって現実ではなくフィクションの中にあるものへと急速に変貌しつつある今、そのような「未来におけるノスタルジー」を単に空しい行為だと断ずるのではなく、様々な観点から可能性を探れないか……というのが本誌のコンセプトです。
今回はそのようなコンセプトを元に、「VR」「旅行」「架空のノスタルジー」のそれぞれの観点から未来におけるノスタルジーの可能性を探る座談会をはじめ、豪華な執筆陣による小説やエッセイなどの合同誌を制作いたしました。
旅行座談会も架空のノスタルジー座談会も、今回公開するVR座談会と同様に濃厚な語りになっているので、気になった方はぜひ購入をお願いします!BOOTHにて絶賛販売中です。
BOOTH
感傷マゾvol.07『仮想感傷と未来特集号』
https://wak.booth.pm/items/3881110
【予告】感傷マゾvol.07『仮想感傷と未来特集号』

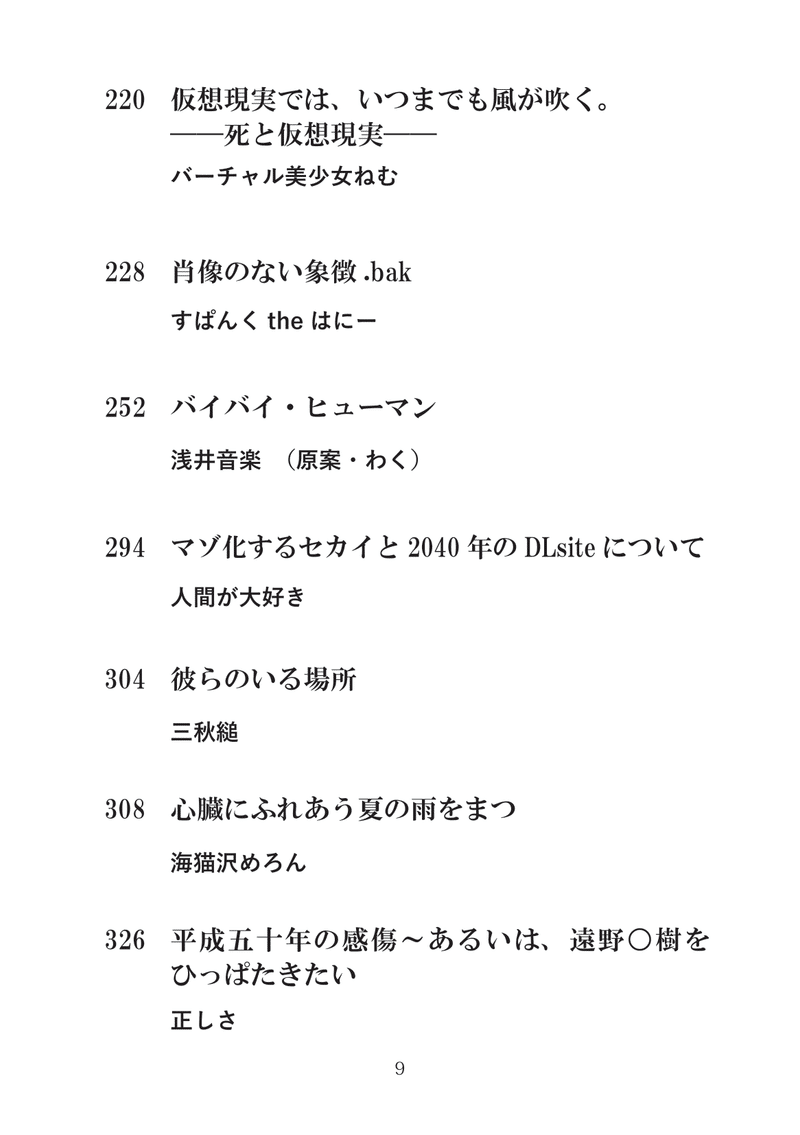
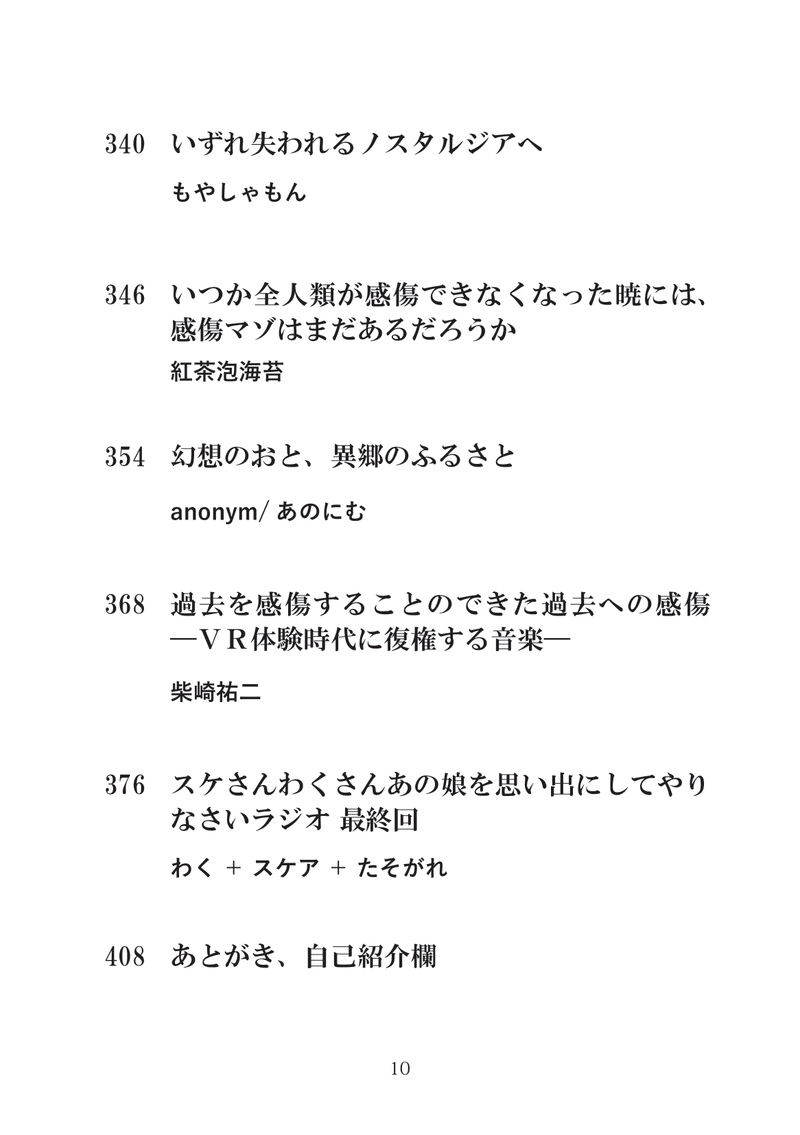
VR座談会・参加者
※座談会本文では敬称を略します。
・井口健治さん(@needle)
・岸上健人さん(@tokimekishiken)
・バーチャルAV女優Karinさん(@vxtuberkarin)
・わく(@wak)
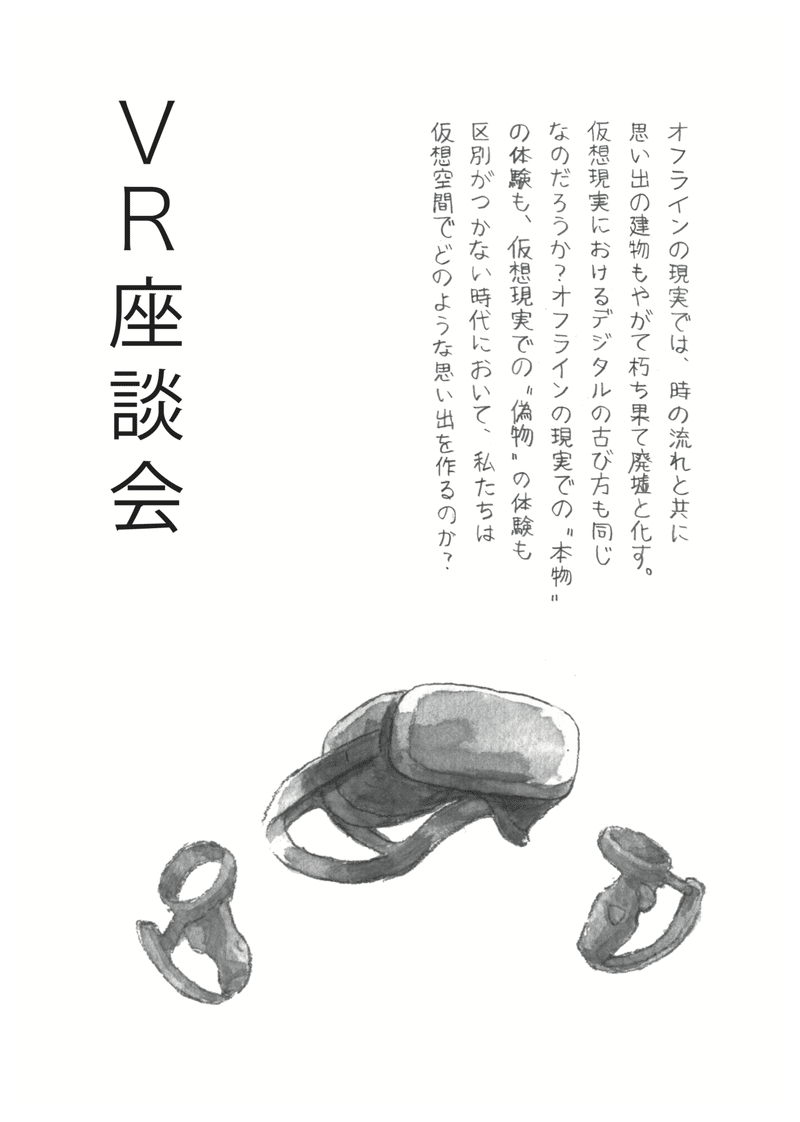
◆はじめに
わく 「では皆さん、今日はよろしくお願いいたします」
一同 「よろしくお願いします」
わく 「今回は僕が主催している「感傷マゾ本」という本のvol.07ということで、「仮想感傷」という題で本を作ろうと思っています。コンセプトとしては2つあって、まず今VR機器を使ってる人ってある程度大人の人がメインだと思うんですが、そういう人たちの多くは子供のころからスーパーファミコンのようなゲーム機がある環境で成長してきたと思うんですね。同じように今の子供は 多分VR機器がすぐ近くにあって、そういう人たちが子供の頃からVR機器を着けるような環境で成長していったときに、過去のことを振り返るとか感傷に浸るという行為がどんなふうに変わるのかなと。例えば今だと感傷の対象としてオフラインの現実での体験がメインになっているけれども、オフラインの現実に比べてVR上の現実や体験の比率が高くなっていったときにどうなるのか、といったことを仮に「仮想感傷」という言葉でまとめてみたのがコンセプトの一つ目です。もう一つのコンセプトですが、「VR」については過去にvol.04で特集を行っているんですね。また青春アニメとかそういったものに付随する「エモ」については例えば三秋縋さんや、VTuberでいうと卯月コウさんとか、そういった方々が言及している。さらにvol.03では「架空のノスタルジー」という特集をやりました。「架空のノスタルジー」って何かというと、例えばvaporwaveという音楽ジャンルがあるんですが、これはすごくざっくりいうと、90年前後くらいの日本のシティポップとか80年代後半くらいのアメリカのマクドナルドのCMとかそういったものを基にして、もしかすると失われてしまった未来ってこんな感じになるんじゃないかというふうに、国籍を問わずにノスタルジックな作品を作る、大体そんな感じの音楽ジャンルだと思うんですね。今まではノスタルジーというと、例えば日本の昭和30年代だったら『ALWAYS 三丁目の夕日』みたいな、その国独自の体験や、その時代のオフラインの現実での体験が主になっていて、それを実際に体験した人がノスタルジーを語っている面が強かったと思うんですが、vaporwaveだとそういった実際の体験や国籍に関係なくノスタルジーを語るように変化してきた。それをふまえて「架空のノスタルジー」という特集をやりました。「VR」と「エモ」と「架空のノスタルジー」という、それぞれ結構バラバラなんですけど、架空のものに対するノスタルジーという意味だと、結構共通点があるのかなと思っていて。これってそれぞれのファンの人がバラバラなんですよ。例えば新海誠のアニメのファンとvaporwaveが好きな音楽ファンとVRが好きな方って、もちろん中にはどちらも好きだという人もいらっしゃるんだけど、それぞれのジャンルでクラスタができているイメージがあって、それを一つの同人誌で扱うことによってもしかすると見えてくるものがあるんじゃないのかなと、大きく分けてその2つのコンセプトで今回同人誌を作ろうと思っています」
わく 「まず始めに、それぞれの自己紹介をお願いします」
井口 「VRエンジニアの井口健治です、どうも。VRに関するところだと、2013年頃から始まった近代VRブームに乗っかってというか、今から振り返ってみるとその渦中にいて、2014年からOculusの日本チームに入って日本でVRを広めるというのを仕事にしていました。2018年に辞めてフリーランスになって、それからは岸上さんのMyDearestですとか、色んな日本のVRの会社を支援したりするお仕事をやっています」
岸上 「井口さんがいなかったら日本のVRゲーム界は潰れていたといっても過言ではないですね」
井口 「そうですね、立ち位置は主にVRゲームの側ですね。逆に言うと、ソーシャルVRとかVTuberとかに関してはそこまで詳しくはないです。あとは強いて言えば小学生時代をアメリカで過ごしたというのがあって、人格の形成にその辺は結構影響を受けてるなと思うところはあります。それこそ90年代前半のアメリカとかをピンポイントで懐かしく思ったり」
Karin 「ご質問いいですか。井口さんが一番最初にVRの仕事に関わることになったときに進路を決めたきっかけがあると思うんですけど、どういうきっかけでVRを広める仕事を続けていくことになったんでしょう」
井口 「当時は2007年だったかな? GREEに結構長いこといて、ソーシャルゲームの立ち上げに携わっていました」
岸上 「GREE創成期の、大学生のアルバイト時代から井口さんはいたらしいですね」
井口 「具体的には 『踊り子クリノッペ』とか 『ハコニワ』というゲームを作ったりしてました。で、そんなときに確かツイッターにジョン・カーマックのツイートで流れてきたんだったかな、KickStarterのリンクが貼ってあって、Oculus Rift DK1のクラウドファンディングがちょうど始まっていたので面白そうだから飛びついて、半年後くらいに届いてうわこりゃすげえとなって。ツイッター上で同じくすげえと騒いでいた最初にDK1届いた勢がいて、そういう人たち、あのGOROmanさんとかも含めて何人かで集まって、OcuFesという、VRコンテンツをオフラインで展示するイベントをやったりしていました。そして2014年に、アメリカに行ってOculus創業者のパルマー・ラッキーに会いに行こうという話になって。どっちかというとそのへんの主導はGOROmanさんで僕は付いていった感じですけれども。それでパルマ―に「日本展開やらないの?」と聞いたら「だったら君らが日本チームやってよ」みたいな。その頃のOculusは買収される前のスタートアップだったので、だいぶノリが軽かったのもありましたね。そういう勢いでGOROmanさんと僕と、あと池田さんというビジネスサイドの人がいて、Oculusの日本チームとして入れてもらったという経緯がありました」
Karin 「なるほど。ありがとうございます」
井口 「そういう話をし始めた直後くらいにFacebookに買収されて、2014年の秋くらい、ちょうど東京ゲームショウ2014の前あたりに仕事し始めました。経緯はそんな感じですけど、動機としてはやっぱり「これはおもしれえ、もっと広めなきゃ」という、それだけですね」
Karin 「DK1のときの感動ですかね」
井口 「そうですね」
わく 「じゃあ、続きましてKarinさんお願いします」
Karin 「はい、じゃあ改めてよろしくお願いします。Karinです。バーチャルAV女優兼スマホで遊べるVR風俗店ということで『X-OASIS』というお店を運営しております。株式会社ファントムコミュニケーションズの社長を務めています。今日は内製アプリから失礼してます」
井口 「VRChatじゃないんですね」
Karin 「エッチなことしても大丈夫な内製アプリです、アダルト用の。今回はバーチャルなアバターを「作る」側というよりは「使う」側の視点ということでお呼びいただきました。今私はVR風俗店のオーナーなので、ある意味「使わせる」側でもあり、そういう目線でも話していけたらと思います。あとはメタバースでいうと、もともとSecond Lifeですとか、上級VR技術者認定試験にちらっと書いてあるMeet-Meという日本産のメタバースがあるんですけど、あれを3年くらいやっていました。 多分ほとんどやってる人がいなかったと思います。色々あって10年続いたことが奇跡みたいなものだったんですけども、一応生き証人ということでお話していきます。あと、多分気付かれてるかもしれないんですけれども、いわゆる「バ美肉」ってやつですね。女性のアバター使って、声はボイスチェンジャーとか使ってないんですけど、まあ一応中身は男性です」
井口 「使ってない!?」
岸上 「すごいですね」
わく 「とても中性的なお声なので、完全にボイスチェンジャーを使ってらっしゃるかと思ってました。すごいですね」
わく 「じゃあ、質問というにはちょっと重いのかもしれませんけども、バ美肉される方って結構いらっしゃると思うんですけど、 多分バ美肉した上でAV女優をされる方って僕の知る限りKarinさん以外いらっしゃらないと思うんですね。もし何か理由があればお聞きしてもよろしいですか」
Karin 「元々エッチなことってすごく苦手で、それはいわゆる男性視点でのエッチが結構苦手というか、自分の中で結びつかないというのがあって。いわゆる性嫌悪をこじらせていたんですけど、私は初めてのVRがOculusのCV1で、初めて触れたときに、これなら自分の姿をどの様にも見せられるし、下を見るだけで自分のアバターの身体が見えるという体験がすごくユニークだなと思って。それで、これなら自分が今まで苦手だったエッチなことも表現できるんじゃないかなと考えて始めましたね」
わく 「ありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。では岸上さん」
岸上 「VRゲームの『東京クロノス』とか『アルトデウス:ビヨンド クロノス』というタイトルを作っているMyDearest株式会社代表の岸上健人と申します。よろしくお願いします。井口さんはDK1から買われていたんですけど僕が買ったのはDK2からで、多分CV1くらいまでが一番VR元年の盛り上がりを知ってる人たちですよね」
井口 「CV1のローンチは大変でした」
岸上 「その渦中にいたので僕も色々感じてましたね。僕の場合は大学時代にまさにSAOのアニメを家賃3000円の男子寮の3人部屋で見てて。みんなでこんな時代来るのかなと話していたときにOculusのKickStarterが始まったんですよ。ルームメイトの一人が中学からVRを研究してる変態で、DK1はそいつが最初に手に入れたんですよ。それをやらせてもらったのがきっかけでした。さらに3人部屋のもう一人もVRをやっていて、それで毎晩のようにVRの話をしてるうちに僕もハマって、DK2から手に入れてという流れでしたね。初期のVRってどっちかというと当時はジェットコースター的な体験というか短い時間でインパクトの強いものが多かったんですけど、僕が物語系のものが好きだったので、他がやってないことで自分の好きなこと、得意なことをやろうということで物語のあるVRエンターテインメントを作ることになりました。VRのライトノベルだと『Innocent Forest』という、VR黎明期の人は知っているかなという作品や、『夢の相談所』というVRの漫画を経て、VRノベルゲーム『東京クロノス』を作り、さらに『アルトデウス:ビヨンド クロノス』という形で進んでまいりました。VRでは当時珍しかったエモーショナルな感情表現をしようとしたみたいなところがありますね。「体感」を重視してるものが多い中、「心感」を重視していたという変わり種のところから始まっています」
わく 「『東京クロノス』は最後までプレイさせていただいて、『アルトデウス』は隙間時間にちょこちょこ進めてる感じなんですけど、My DearestさんのゲームはどちらかというとノベルゲーのVR版というイメージがあるんですね。VRのゲームの中でも例えばPSVRのバイオハザードのようにアクションものとかもあると思うんですけど、これからもノベルゲー的なVR作品を作っていくのか、それとも例えばVRMMOみたいなまったく別のジャンルのゲームも手掛けることがあるのかについてお聞きしたいです」
岸上 「これは最近公言したんですけど、エンディングのあるゲームを今後も大切に作っていこうと考えています。『東京クロノス』は完全にノベルゲームで、『アルトデウス』はノベルゲームでもあるんですが、ある意味でノベルゲーム離れをしようとしたところもあります。日本だとすごく評判がいいんですが、アメリカの人はあまりノベルゲーが好きじゃないんですよね。最新作の『ディスクロニア』というタイトルを最近発表したんですが、そっちは『逆転裁判』や『ダンガンロンパ』に近いゲームシステムで、今はそういう作品を作ってますね。なのでノベル系のものも作ると思いますし、『逆転裁判』『ダンガンロンパ』のようなザ・アドベンチャーゲームというものや、今後RPGを作る可能性だってあります」
Karin 「めっちゃ楽しみです」
わく 「僕は、皆さんと比べるとそこまでVRに関わってるわけじゃなくて、たまにVRChatにログインしたり、VRのゲームをやったりというくらいなんですけど、活動としては『感傷マゾ本』という同人誌を作っています。すごくざっくりいうと、青春アニメとかに代表される定型的な青春像みたいなのってあるじゃないですか。夏休みに幼馴染の女の子と浴衣を着て夏祭りに行くとか、もしくはクラスの女の子たちと一緒に海に行くみたいな。そういうアニメとか漫画に描かれる青春像みたいなものと実際の自分の青春を比較すると明らかに自分の青春に対して満たされていないという思いが強まって、そういう感じで青春アニメとか新海誠の『秒速5センチメートル』とかを見ていると、逆に自分の青春の満たされなさみたいなものがちょっと快感になってきちゃったみたいなところがあって、そういう「理想の青春と比べると自分の青春ってダメだな」みたいなマゾヒスティックな感情を「感傷マゾ」と名付けて、今回で言うと7冊目ということで同人誌を作っています。とりあえず僕はそんな感じですね」
井口 「昔から好きだったけれども特に名前のついてなかったもやもやした領域に名前を付けて頂いたという恩があるという感じで、ありがとうございます」
わく 「そこは結構難しいんですよね。ツイッターとかでもやもやしたものを言語化する人のツイートがバズったりする傾向があると思うんですけど、もやもやした部分を言語化してくれて嬉しいという人と、個々人が抱いている感情が言語化することによって共有可能なものになってしまうので、俺が今までもやもやしていたものを言語化しないでという人もいたりして、どっちも気持ちは分かるんですよね。でも自分の感情をもやっとしたままにしておくのがすごく嫌で、俺は今何を感じているんだろうということを言語化する癖みたいなのがあって、いつの間にか同人誌7冊作ってるという、そんな感じです」
◆VR元年(2016年)から5年間で、最も印象深い変化は何か?
わく 「VR元年と一般的に言われていた2016年から5年経ったんですけれども、この5年間でVRを取り巻く環境や自分自身の活動で最も印象深い変化ってどんなことがありましたか、というのと、今後VRがどのように発展していってほしいかというのを教えていただきたいです」
井口 「僕にとっては2016年からというよりも、DK1が届いた2013年からですね。DK1、DK2、CV1という一連の流れの中で、技術オタクのものからもっと広い層に広がってきたというのは嬉しいですね。特にOculus Questが出てからの広がりはすごい勢いだし、VRChat文化とか、VTuberをやる人や見る人も含めたいわゆるV文化など、ゲーム以外でのVR技術の使い方が民間で広まったというのも大きい。そしてそこまで大きくなると、文化的に全然重なっていない島宇宙も出てきたなというふうに思います。いいにせよ悪いにせよ。一方で二極化を生んでいる状況でもあるなとは感じていて、PCVRとスタンドアローンの溝は多分埋まらないんだろうなと。階級闘争みたいなのは勘弁してほしいなと思いつつも避けられないんだろうなとも思います」
わく 「二極化でいうと、先週駅前の整体に行ってきたときに、整体師の方が「わくさん、VRっていいですよ」って話しかけてきて、何か始めたんですかって聞いたら「スマホでVRをやると女の人が目の前にいるんですよ」みたいなことを言ってて」
井口 「さっき列挙した中から漏れていたけど、スマホVRもありますね」
わく 「整体師に首を掴まれてゴリっとやりながら「スマホVRいいですよね、目の前に女優さんいるんですよ」って言われたらそうですねしか言えなくてずっと話を聞いてたんですけど、確かに二極化という意味だと、PCVRとOculus QuestのようなスタンドアローンのVRとは別にスマホVRというのもありますね」
井口 「極は2つだけじゃないのかな、島宇宙化という方が合ってるのかもしれない」
わく 「そうですね。スマホVRや、Nintendo Switchの箱VRとか」
井口 「箱VRは出したのはいいけど、あれを使ってるゲームがなくなっちゃった感じですね。やっぱり使っている間常に箱をおさえてなきゃいけないというのがやりづらいんだと思います」
わく 「それはやりづらいですね」
井口 「固定できないんですよねあれ」
わく 「そういう新たな形態のVRの普及で、もしかするとさっき井口さんがおっしゃった通りここ5年で分断が深まってきたのかもしれないですね」
井口 「とはいえVR抜きにしても人が持ってる興味範囲というのは割と人によってバラバラで、重なっていないものは山ほどあるので、別にそれでいいのかなという気もします。単に、別文化の人を馬鹿にしたり見下したりといった不健全なものが無ければ色々あって色々いいでいいんじゃないのかと思います」
Karin 「このスマホVRと島宇宙化の話ちょっといいですか? うちのサービスの性質もあるんですけど、このトピックについてはちょっと思ってることがあって。今うちのサービスってこういうふうに…」

井口 「あ、ステレオになった」
Karin 「画面を2つに分けて、このままその場で全画面表示してくださいと言って、簡単にスマホVRゴーグルで遊べるようにしているんですけど、スマホVRゴーグルとかの簡易的なVRの世界にVRChatみたいなアバターを使ったコミュニケーションを提供しているんですよ。そうすると何が起こるかというと、既存のスマホVRで満足していたお客さんたちが、半年くらい経つと、皆こぞってPCVRを買い始めるんですね。さすがに年配の方になるとまた話は変わってくるんですけど、若い人たちだと結構無理して買っちゃってて、もしかするとVRコミュニケーションを体験しているうちに自分も肉体を持って触れあいたいという気持ちがどんどん強くなって、できるだけ自分自身の身体を表現できるPCVRの方に寄っていくのかなとは思っていて。もしかするとこの分断を何とかする鍵って、この身体性のあるコミュニケーションを導入するかしないかというところもあるんじゃないかなと思っています」
わく 「単に自分が見ているだけなのか、相手とコミュニケーションをとれるのか」
Karin 「それこそ今うちのサービスだとお客さんは動けないんですよ。一応お客さんのアバターはあるんですけど、身体は動かない。それこそマゾ向きになっちゃってるんですよ。自分から攻めたい人は全然満足できないシステムになっていて、今慌ててPCVR対応を頑張っています」
わく 「ちょっと面白いですね。マゾはスマホVRのままでよくてもサドの人はPCVRが必要という」
岸上 「なるほど」
Karin 「あと若い人は、アバターコミュニケーションに興味を持った瞬間に、無理してでもPCVRを買っちゃう」
岸上 「僕も若い人にはそういうイメ―ジがありますね」
わく 「Karinさんのお店って性的サービスのお店なわけじゃないですか。その上でPCVRを買ったとしても、別に性的なサービスを受けられるわけじゃないけれども、それを抜きにして普通にVRChatとかで話したい、コミュニケーションをとりたいという欲求を持った方が出てきているという感じなんですかね」
Karin 「そうですね。実際うちのお客さんのコミュニティがあるんですけど、その人たちは皆VRChat行っちゃって、VRChatでアバターを使って遊んでいますね」
わく 「そうなんですね」
Karin 「それがサービスにとって良いのか悪いのかという話でいうと、何なら良くないくらいなんですけど、やっぱり文化の持つ力には抗えないんだなと強く思います」
わく 「確かに島宇宙になってもそれぞれの島に行こうと思えば船を使って行けるみたいな状況の方がいいですもんね。全然関係ない話なんですけど、ケバブ屋とかを街中で見かけるたびに、ここでケバブ食べてもそこからトルコ料理店に行くお客さんいないんだよなと思うんですよね。皆ケバブで満足しちゃって、照り焼きケバブとか本場とは全然違うメニューが出てきてじゃあそれ買おうみたいな、いやそこじゃなくてトルコ料理店行きなよって、そういう流れ作れないのって思っちゃうんですけど。そういう意味で言うと、スマホVRからPCVRに向かうというのは、島宇宙でもそこからまた別の島に行けるという点でいいなと思いましたね」
Karin 「そうですね。用途に合わせて広がっていく形になるのかなと思います」
わく 「ありがとうございます。じゃあこの流れでKarinさんお願いします」
Karin 「VRを取り巻く環境と自身の活動でいうと、まず自分の話からすると、ただのバーチャルAV女優というおふざけだったのが、いつの間にか経営者になっちゃって、大学院も中退する羽目になり、意外に人生もフルスロットルになっちゃったなというのが、自分の活動では一番大きいですね。本当は弁護士を目指してたのに、気付けば風俗店の店長だよという。2016年からの話でいうと、私がすごく心を砕いていたMeet-Meというメタバースのサービスが終わったのが2017年の1月で、その頃に私は最初PSVRから入ったんですけど、そこでVR面白いぞとなったタイミングでOculus CV1の5万円のサマーセールがあって」
井口 「ああ、あのときの」
岸上 「ありましたね」
Karin 「私はあのセールのおかげで親を説得してVRを導入させてもらって。あれのおかげで今の私があるんですよ。まだそのときはVRChatもそこまで認知されてなくて。VRでアバターを使っている人たちの話が、今だと例えばこういう座談会とかで身体性の話とかも含めてどんどん表に出ていくじゃないですか。そういうのが当時全くなかったのが、ねこますさんだったりとかVTuberが流行ったことで急に表に出てきたなというのがあって」
井口 「あれが確か2017年の暮れでしたかね」
Karin 「そうですね。なのでそうやって今までVRのユーザーだけで話されてきたことが、ある意味創作とかの種としても、例えばSAO(『ソードアート・オンライン』)とかと紐づけたりされてますけど、出てきたのかなというのと、それが広がっていって当たり前のものになると、今度はSecond LifeとかMeet-Meといったメタバースで起きた事件とか人間同士の揉め事がそのまま再現されるようになってきて、そういう意味では昔のSecond Lifeの頃から人間が仮想世界に向ける目線とかそこに求めてることは変わらないのかなとは思います。なので、個人的にはVRにフルベットしていますし、アバターについても一人称視点で自分自身を騙すというか、自分自身の衣装というイメージが強くはなったんですけど、昔からのアバターコミュニケーションという意味では、多分3週目とか4週目ぐらいのインターネットだろうなと思ってるのが正直なところですね」
井口 「富士通のHabitatは89年か90年くらいだったかな、僕も知識としてしか知らないんですけど、日本のアバターサービスというとよくこれが教科書とかに載ってたりしますね」
岸上 「確かにこの話題ちょくちょく出てきますよね」
わく 「トピックには載せてないんですけど、今Karinさんがおっしゃったのが身体性の話とかも面白いですよね」
Karin 「私はメタバースとかネトゲ、FF11とか14とかで、アバターコミュニケーションを小さい頃からめちゃくちゃしてたんですけど、それで一番変わったのって、例えばいわゆるネカマみたいな行為をしていても、全然空しくならない環境なんですよ。これは今まで人類がたどり着いていなかったと思うんですけど、自分のアバターとしての身体が自分自身の主観視点で見えるわけで、人とコミュニケーションをするにあたって自分を信じることができるんですよ。そういうところがすごく大きいのかなと思っています。昔ニコ生とかでいわゆる両声類のコミュニティってたくさんあったんですね。あの頃もネットで皆で練習しようという雰囲気があって、それを使って面白い放送をする人もいて。まあ言ってしまえば別にレベルが高いわけじゃなかったんですよ。始めたてで情報もそこまで行き渡っていないし、そもそも皆練習が続かないという感じだったんですけど、VRChatを見ていると、誰にも何も言われなくても年単位ですごく練習してる人がいるんですよ。多分それって自分の使っているアバターが女性だからそれに合わせて喋れるようになりたいという、自分に向いているモチベーションがすごく大きいと思うんですよね。なのである意味女の子が化粧でエンパワーメントされるみたいな話にも近いのかなと。「アバターとしてのかわいい自分」に合わせるために頑張るという。アバターコミュニケーションの中で比較的新しい要素としてはそこがある気がしますね」
わく 「アバターをまとった上で主観で自分の身体を見て「あ、女の子だ」となったときに、アバターに対して自分の身体的イメージがしっくりくるような努力、例えば女性みたいな声や所作、言葉遣いを練習をしたりとか、他にも色々あると思うんですけど、アバターがある意味目標みたいなものになってそれに自分の身体的イメージをチューニングしていくという感じなんですかね」
Karin 「そう思いますね。あと、いわゆる「VR感覚」みたいな、VR上でアバターを触られるとそこを触られているように感じるって話があるじゃないですか。それの延長だと思うんですけど、胸の重みを感じたりとか、体の重心が変わるのを感じたりとかはありますね」
わく 「そこまであるんですね」
Karin 「そうですね。逆にそれがイメージできるからこそ、体の重心が違うから男性と女性で所作が違うんだとか、そういうことにも気付けるというか」
岸上 「面白いですね。僕らが作っている『アルトデウス』というタイトルの主人公って女性なんですよね。なので男性も強制的に女性キャラをプレイすることになりますね。他には井口さんも好きな『Half-Life:Alyx』という世界的に有名なタイトルもありますね」
井口 「あれも主人公が女性ですが、あれは身体アバターがなくて手しかないので、あまり気付かないですね」
岸上 「『アルトデウス』の方はバリバリ身体アバターもありますね。まだVRって男性がやる方が多いと思うんですけど、わりと性別とか身体性をあいまいにしていってるなというのはありますね。対極はVRSNSとかのサービスで、皆初めは違和感があるんだけど、そのうち慣れていって意識をそっちに合わせに行くんですよね」
Karin 「昔あったゲームだと、『Ancient Amuletor』というPSVRとかで出てたタワーディフェンスのVRゲームがあって、あれで私一番最初は女性アバターを使ってたんですよ。アーチャーのアバターがめっちゃ巨乳のエルフで。それで昔「巨乳美少女エルフになってみよう」みたいな動画を上げたんですけど、そこが一番最初だったのかな」
井口 「なんかその動画ニコ動で見かけた気がしますね」
Karin 「それ私です。十何万回再生くらいいきましたね。やっぱりゲームから「こんな景色って実在したんだ」みたいな感じで入ってくる人って結構いると思います」
井口 「これ作ったのTime OF Virtual Realityか。この作品じゃないけど、これを作った会社の作品を別のプラットフォームで担当したことがあります」
Karin 「あれは時期の割にというか、PSVRの初期に出たゲームとしてはめちゃくちゃリプレイ性があって楽しかったですね」
井口 「確か中国の会社でしたよね。だからセンスがアジア的というのは多分あると思う」
わく 「VRと身体性の話で言うと、例えばオフラインの現実世界ってそんなに身体性があるのかというのをよく考えるんですね。人によるんですけど、例えば女性だったらお化粧するときとかに鏡で自分の顔を見る機会ってかなり多いと思うんですね。男性の中でも、筋トレやスポーツをやる方、アイドルをやる方とかだと身体性みたいなものもあると思うんですけど、僕みたいな男性オタクって、鏡で自分の鏡を見るときって髭を剃るときとか髪を洗うときくらいで、普段はアニメや漫画のことをずっと考えていたり友達とそれについて話したりしていて、それをやってる主体に身体が必要かというとそんなに必要ないイメージが強いんですよ。僕が逆にVRChatを始めて思ったのが、ある意味アバターをまとうことによって初めて自分自身の身体を認識したところがあるんですよね。普段男友達と話しているときって、例えば身体を鍛えたとか髪型が変わったとか服が変わったというふうに他人から自分自身の身体性について言及される機会ってそんなにないし、鏡で自分の顔を見る機会も少なかったりするのもあって、そういう人がVRChatをやることはむしろ身体性を獲得することに近いんじゃないかなという気もしました」
Karin 「それは私もそうですね。VRChatとかで自分の身体というものを意識するようになって、自分の身体を直視できるようになってから、リアルでも自分の身体がそこまで嫌じゃなくなったというか、ただのデバフじゃなくて、これはこれで身体性というステータスなんだなと気付くことができたというのはありますね」
わく 「そこはVRChat等のメタバースのサービスでアバターコミュニケーションをやる上ではかなり良いことだよなという感想になっちゃうんですけど、そこはこれまでとは全然違う体験でしたね」
Karin 「それは私も思いました」
わく 「これは語弊があるのかもしれないですけど、バ美肉って筋トレにちょっと似てるなと思うんですよね。身の周りの筋トレをやっている人とかも、筋トレを始めて鏡の前でポーズをとるようになったりだとか、身体のこの部分は○○筋という感じで自分の身体の構造を考えるようになったりだとか、そこの流れで身体性を獲得するみたいな印象があります。それってバ美肉で身体性を獲得するという話と、表面上は違うんだけど割と近いのかもしれない」
Karin 「細かいところに気付く習慣があるとかいわゆる男心・女心で表現されてきたものも、実は身体性の有無に起因しているのかもしれないですね」
わく 「確かにそうかもしれないですね。ちょっと話がずれていくんですが、VRChatでバ美肉したユーザーがオフラインだとどういう性別なのか分からなくて性的な認識が揺らぐという話を聞いたりするんですけど、それってツイッターとかSNSのテキストコミュニケーションの方がむしろアバターとか身体を想定していないじゃないですか。だから本当だったらテキストの方が身体を想定しないがゆえにアバターをまとうVRサービスよりも自分の性自認とかそういったものを自由にできるんじゃないのかなという気がするんですよね。でも実際にはそうなっていなくて、男性は男性、女性は女性の性自認のままテキストコミュニケーションをしている印象があって、ちょっとそこは不思議ですね」
Karin 「逆にVRの方は性自認を気にしなくていい世界だからという話かもしれないですね。ある意味アバターコミュニケーションで強制的に上書きされているので」
井口 「気にしなくていいというよりは自分で選べるってところなんじゃないですかね」
Karin 「それでいったらアバターも自分で選べるものではあるので。むしろ自分自身で選んだというところではそこまで変わらないとは思うんですけど、男性と女性の文体ってすごく分かりやすいわけじゃないじゃないですか。それをロールプレイするのって実は難しいし、どこかで適当になったり俯瞰的な視点が入っちゃうと思うんですよね」
わく 「言われてみれば確かに、ツイッターで自分の性別を公表している人でも文体を見てみてそんなに違いがあるかというと別にそこまで違いが無かったりとかはありますね」
Karin 「男性らしい・女性らしい文体って、なんか匂うというのはあると思うんですけど、多分そこまでエミュレートすることは結構難しい」
井口 「あと、日本語の言語仕様はどっちかというとバレやすいです。一人称がいっぱいあって、どれを使うかというのが全体のトーンとか印象に影響するので。英語ってIとかyouとかmeしかないので、どっちかというと英語を読んでいるときの方が分からないですね」
わく 「それは確かにありますね。例えば「僕」という言葉でも漢字かひらがなかカタカナかとかで微妙にニュアンスが違っていて、書き手の性別がなんとなくわかっちゃったりとかは正直ありますね」
井口 「だいぶ脱線してきましたね」
わく 「次、岸上さんお願いしてもよろしいですか」
岸上「はい。VR元年から5年経ったということですけど、VR元年にMy Dearestという会社を作った身からすると、VR元年ってタイムリープしたりとか、「ここ数年で一番のVR元年」みたいにボジョレー・ヌーヴォー化したりしていたんですけど、2021年はVR2年目なんですよね。割と皆が言うようになったんですけど、ついにVR元年が終わったと。それがここ5年で一番大きいところかなと思いますね。分かりやすいところとしては会社としてちゃんと収益が立つようになったというところですね。2020年でVR元年が終わって、2021年はちゃんと会社として収益が出やすくなっているなというのが実感としてあって、経営者間ではこれでやっとVR2年目と言えるねという認識になっています」
わく 「ここ5年の環境の変化を踏まえて、今後VR業界がどんなふうに変わっていくかについて経営者の方の間で予想ってあったりするんですかね」
岸上 「投資家の間ではVRはよくスマホと比較されることがあるんですけど、経営者の実感としてはコンソールのハード、コンシューマゲームのハードと比較するのが一番良いですね。Oculus Quest 2が今すごく売れてて、アメリカを中心にPS5に迫る勢いで売れ始めてるんですね。もう5年くらい経つとXboxとかのコンソールのハードには近づいてくるんじゃないのかなというのが肌感としてあります。5年後には、ゼルダが1000万本売れた初期の任天堂Switchくらいの勢いになってくるというのが現実的にあると思いますね。だからその頃にはモンスタータイトルと言われる1000万本級のソフトが出てくるかもしれない。あとはよく言われている話ですが、マーク・ザッカーバーグが1000万人という数字をよく口にするんですね。例えば日本のスマホのアクティブユーザーが1000万人になった時にガンホーの『パズドラ』が出たんですよね。そういうエポックメイキングというかゲームチェンジングな作品が出てくるタイミングがだいたい1000万くらいかなと。あとスマホは元々買い切り型のゲームが多くて、『アングリーバード』も初めは買い切りだったと思うんですけど、『パズドラ』以降でガチャのモデルが普及していったんですね。VRではガチャはあまりないんですが、プレミアムというか、基本無料のマルチプレイでずっと続いていくような、昨今だとメタバース型ゲームみたいな呼び方ですね。そういうのは1000万人ぐらいユーザーが超えると、 多分世界だと来年くらいに超えそうなんですけど、どんどん出てくるのかなというのはありますね」
わく 「なんかVRの会議アプリみたいなのが発表されてませんでしたっけ」
井口 「Horizon Workroomsですかね」
わく 「あれも今までVRとかを特に取り上げてこなかった一般企業もあと数年くらい経つと使うようになってくるんですかね」
岸上 「5年は結構面白い数字かなと思いますね。3年くらい経つとそこそこ使い物になってきて、5年くらい経つと割と実用レベルになるみたいな。1、2年だとあまり変わらなかったりするんですけど、5年くらい経つとかなり変わってくるなというのが2016年から5年を経た今の実感ですね」
井口 「ビジネスとか実用用途を想定してやっている会社さん、Synamonさんとかもけっこう昔からありますし、それこそFacebook自身もWork Roomsを出したり、ゲームだけじゃなくて実用でも使えるようにというのは結構前から想定して作ってますね。どういう形で普及していくのかというのはちょっと気になっているところで、要はiPhoneになるのかBlackBerryになるのか。BlackBerryは最初から大人のビジネスデバイスですという顔をして出てきてビジネス側に普及していったという形で、一方iPhoneは、一番最初はパーソナルなデバイス、個人が持つ携帯として登場して、どんどん普及していくにつれて、仕事でそのまま使いたいという需要が出てきたり、Microsoft Exchangeに接続できる機能が後から追加されて仕事で使えるようになっていったり。最初は全然ビジネスでは使えなかったけど、後から使えるような機能が充実していって、気が付けば皆仕事にも使うようになった。VRはどっちからもあり得る気がしていて、Facebookはまずはゲームからという広げ方を選んで、だけどビジネス側もちょっとずつやっているという感じで、逆にHTCのViveはビジネス向けに売る方をメインにしているみたいだし、どちらから攻めていくのもあると思うけど、まあ最終的に全部に普及したら同じなんですけどね」
わく 「会社でたまに不思議だなと思うのが、例えば世代が上の方だとメールだけでやり取りするのが嫌で、電話をしろって人もやっぱりまだ中にはいるんですね。どうも人の声を聞くことで温かみのあるコミュニケーションを感じているということらしい。今までの会社内での連絡ツールだと、例えば電話からメールやチャットのようなテキストを通じたコミュニケーションへとやりとりが簡易になってきたと思うんですけど、VRの会議アプリになるとその流れとは真逆で身体性を持って会議をすることになるので、逆にそこに温かみを感じて、案外年配の方でも使いやすかったりするのかなというのはちょっと気になりましたね」
井口 「どうなんでしょうね。温かみって言ってる人がいるときに、それは本当に温かみのことを指しているのかそれともただ単に今までやってきたのと違うのが嫌だというのをオブラートに包んで言っているだけなのか結局分からないので」
岸上 「僕はVR会議の方がZoom会議よりはるかに礼儀に厳しそうだなと思ってますね」
井口 「ジェスチャー見えちゃうからな」
岸上 「席に座る場所とか、普通に概念としてあるので」
わく 「やっぱりあるんですか、VR上座・下座みたいなの」
Karin 「入れようと思ったらいくらでも、って話ですよね」
井口 「場所がある、移動ができるなら人はいずれそれに意味を見つけたくなりますからね」
わく 「そのうちVRマナー講師みたいなのが出てきたりして」
Karin 「それ私はあまり嫌いじゃないですね。マナー講師までいくとアレですけど、既存の上座・下座みたいなものをVRの中で再現するのって、「あなたと礼儀正しく話がしたいです」という気持ちを伝える一番手っ取り早い手段だとは思うんですよ。なのでそういう旧来の身体を使った表現をあえてアバターで行うことにも意味があるんじゃないかと、まあそれこそ5年後にはVRマナー講師うぜえって私も言ってるかもしれないですけど」
岸上 「事業多角化でマナー講習とかもするんですか」
Karin 「VRセックスマナー講習しろとか言われてますね(笑)」
井口 「デジタル化されると、そういうマナーに従っているふりをするのも簡単になっていて、例えばメールのあいさつがもうテンプレで自動的に出てくるとか、丁寧だけど心のこもっていない自動化されたマナーに従っている様子が既にあるわけじゃないですか。2文字打ってTab押したらいつものあいさつが全部出てくるとか。似たような感じでアバターの動きを部分的に自動化して、自分の実際の動きに関わらずマナーに沿った動きをしているかのように見せちゃうとか、そんなの作る人も出てきそうだなと」
わく 「ボタンを押したらアバターが勝手にそういう動作をやってくれるのありそうですね」
わく 「でもVRマナー講師、個人的には面白いですね。変なマナーとか出てほしいですよね。「上司よりも年下の美少女アバターをまとってはいけない」とかそういう訳わかんないマナーとか出てきたら相当面白いなと思いますね」
Karin 「上司が逆にロリババアみたいな」
岸上 「ロリババアなら許せますからね、怒られても」
わく 「目標を達成するのじゃ! みたいな」
Karin 「逆にVRとマナーって相性良いかもって今ふと思いましたね。マナーって人前で恥をかくから恥ずかしくて嫌になるじゃないですか。でもVRの世界っていくらでも先に練習しておけるし、何ならここは上座です、ここは下座ですみたいなガイドをいくらでも出せるわけじゃないですか。だから別に誰も間違いようがないんだったら、本当にただ気持ちを伝えるという話としてはそんなに悪くなくて、むしろVRでいつでも練習できる、確認できるからこそマナーという概念が現実以上に良い意味で機能し始めるんじゃないかなと」
わく 「チュートリアルみたいな感じで、矢印が点滅して「この席に座れ」みたいな」
Karin 「多分チュートリアルがないから、マナーってドキドキしてクソゲーなんですよ」
井口 「これはARでも現実でも欲しい」
わく 「マナーって全世代に共有されているわけじゃなくて世代別にマナーが違ったりして、しかもそれぞれの人、特に上の世代の人がこんなマナーも知らないのかってなぜか怒り出したりする。マナーのルールみたいなのが見えにくいし、しかもそれを事前に学ぶ機会が無かったりするのが辛いですよね。だからある意味自転車の補助輪みたいな感じで。ただそこまでやるんだったらもうマナー必要なくね? というのもありつつ、でも確かにあったら面白いですね。マナーもある意味ノンバーバルコミュニケーションの一種というか、「私はあなたに敬意を払ってますよ」というのを図式化したものという部分もあるじゃないですか」
Karin 「私はそういう意味でマナーが好きですね。年上の人とかに仮に慇懃無礼にしても抑えるところさえ抑えていれば会話が成立するという点では結構素敵な武器だと思っています」
◆VR以降の偽物の体験と本物の体験について
わく 「次のトピックに移らせていただきます。VR以降の偽物の体験と本物の体験についてということで、いきなり抽象的な話になっちゃったんですけど、例として挙げやすいのは旅行ですかね。今のコロナ禍だったら、例えばGoogle ストリートビューのようなVRでの旅行って割とやってる人が周りにもぽつぽつ出てきたんですけど、VRが普及する前の観光って、本物を現地に見に行くという側面が結構強かったと思うんですよ。それで、トピックの所に挙げているんですけど、例えば車に乗って30分とか1時間くらい走って長崎のハウステンボスとか志摩スペイン村に行くよりも、飛行機で十数時間かけてオランダやスペインに行って現地で本物の体験をすることを尊ぶような風潮ってあったと思うんですよ。でもそれがVRとコロナ禍というのもあって海外旅行が困難になった結果、本物の旅行の代わりにVR旅行に行くようになった。なんかハウステンボスで働いてる人が聞いたら失礼なことばっかり言っちゃってるんですけど、多分これまでの価値観だったらそういうものって偽物の体験というふうに判断されがちだと思うんですけど、実際にGoogle ストリートビューをやってみたらある程度満足している自分もいたんですよね。そういう意味でいうと、VRにおける体験によって、例えば現地の本物の場所でのリアルな体験といったような本物・偽物という体験における評価軸も変わっていくんじゃないのかなと。もうちょっといってしまうと、例えばVRChat上で色んな友達と遊んだりした体験が思い出になっていったときに、その体験が本物か偽物かという評価軸が今後も変わっていくのだとしたら、別にオフラインの現実で友達と遊ぶとかではなかったとしても、VRChat上で友達と遊んで、そこで思い出ができるというのはある意味本物というか、良い体験なんじゃないかなという気がするんですよね。ここではそういう話をしようかなと思っています」
井口 「これはどこの部分に一番肝心な本物性を見出しているかによって変わるものだという気がします。それが単純にVRだからとか現実空間だからというわけではなくて。現実空間とVR空間がそれぞれ本物と偽物だというのも、片方(現実→本物)が真のときもう片方(VR→偽物)も真になりがちな傾向はあるけれども必ずしもそういうわけではなくて、いくつか例を挙げると、例えば今VRで東京ゲームショウが開催されていますよね。その中にはソニックとかチョコボとかガンダムとかモンスターハンターのモンスターとかがいるわけなんですけれども、あれは公式が提供した3Dデータそのものなので、むしろあれが本物なんですよね。それを元に現実の東京ゲームショウ、オフラインの東京ゲームショウで等身大のフィギュアを作ったとしても、それはフィギュアであって本物じゃないんですよ」
岸上 「むしろ偽物なんですね」
井口 「現実で出したらむしろ偽物感が出ちゃう」
岸上 「そう考えると東京ゲームショウは概念として面白いですね」
井口 「それとさっき例として出た、ソーシャルVR空間の中で友達と一緒に思い出作りをしたというのも、友達とのやりとりそのものは、生身の友達がどこかにいてその人たちとインターネットやVRを通じてやり取りしているわけなので偽物ではなくて本物だけど、例えばその友達が全部botでしたとなったらそれは偽物ですよね」
わく 「なんか攻殻機動隊の清掃局おじさんが頭の中にポップアップしましたね」
井口 「それも露骨にbotだと分かる程度のbotだったら偽物ですねで終わるかもしれないけれども、今のGPT-3とか本当に見分けがつかなくなっているbotの場合はちょっと分からなくなってきますね。この間読んだ記事ですさまじいのがあって、英語の記事で日本語版が無いっぽいのでちょっとアクセスしづらいんですけれども、本当に小説みたいな話で、ガールフレンドが亡くなっちゃったという男性がいたんですね。結構長いことそれでふさぎ込んでいたんだけれども、webからアクセスして使えるGPT-3というすさまじい文章生成AIがあって、それに死んだガールフレンドとの会話のテキストチャットログを大量にぶっ込んで、それをサンプルにしてbotを作って話し始めたら、本当に彼女みたいな会話をし始めたんですね。それで朝までずっとチャットをして、その後も辛くなったときとかにそのbotのところに行って辛さを癒していたんだけれども、GPT-3ってものすごく処理が重いので、ただで無尽蔵に使われないように、botに最初から寿命が設定されているんですよ」
わく 「うわ、なんかその続き聴きたいんだけど聴きたくないというか。すごい話ですね」
井口 「もう、この時点で何のSF作品の設定? という」
岸上 「悲鳴出てしまいました」
わく 「鳥肌立っちゃった」
井口 「どうもそのbotの寿命が本当に尽きてくると、だんだん言うことがおかしくなってくるという設定にしてあるみたいなんですけど、もう男性は感情移入しすぎてしまっていて、彼女がまた死ぬところなんか見たくないので、そうなる手前の所でbotとの会話をやめてずっとそこで残してあるみたいです。そのくらい今の英語での会話AIは進んでいて、これはマジですごいんですよ。普通に「チャットっぽい」会話をするんです。英語だと例えばアスタリスクで括って「*look around*(辺りを見回す)」みたいにト書きを付けて今やっていることを表現するという文化があるんですけど、そういうこともする」
わく 「本当に見分けが付かないですね、そこまでいくと」
井口 「(記事を探す)あったあった。僕が読んだ記事がこれ(脚注:https://www.sfchronicle.com/projects/2021/jessica-simulation-artificial-intelligence/)で、かなり力の入った記事でして、ページ開いて一番最初にちょっとだけ実際の会話のログが出てくるんですけど、そんなに長くないので読んでほしいんですが、背筋が寒くなります」
Karin 「わあ……」
岸上 「ほんとだ」
井口 「「だって君は死んだじゃないか。何でここにいるんだよ」って。こんな時代になってるんですね。それで、今初めて検索して見つけたのがこっちの記事(脚注:https://futurism.com/openai-dead-fiancee)で、どうやらOpenAIによってシャットダウンさせられたみたいです。だいぶまた脱線しちゃったんですけど、当事者がどこの部分に本物性を置いているかによって本物とみなすかどうかが変わってくる気がします。ここまで信じ込めるくらい精巧なAIだったら本物と判定してしまうのかもしれないし、あとは例えば旅行の話でいうと、僕はいくつか世界で行ってみたい場所とかやってみたいことがあって、例えばバケットホイールエクスカベーターの実物を見てみたいんですね。これは世界最大の工事用重機で、ドイツに行かないと見られなさそうなんですけれども、これは一度生で見てみたいし、 多分VRで見てもそれは違うだろうと。これの3Dモデルくらいネットに漂っているだろうから、実寸で表示するのは簡単なんですけど、そうじゃないんですよね。本当にこんなのを作っちゃったのかよというのを目の前で感じたい」
わく 「本物と偽物の境界みたいなものが単純にオフラインの現実かVRかとかじゃなくてユーザーがどこの部分に本物性を見出すかに関わってくるのかなという感じですね。だからさっきの友達との思い出作りについても別に相手とオフラインでも遊べるしVRChat上でも遊べるわけじゃないですか。場所という意味だとオフラインの現実かVRかで変わってはいるけれども、やり取りしている人は変わらないのであればそれは本物だし、それがさっきみたいなbotになってくると偽物だと判断しちゃうかもしれない」
Karin 「目的によりそうですよね。さっき言っていたでかい建築車両が動いてるのをリアルで見たいとかならもちろんリアルで行かないと意味がないけど、例えばこういうものを作れるエンジニアになりたいから細かいところまで近づいてよく見たいというだけだったらVRでも良さそうじゃないですか。その人にとってそれが再現されていれば本物なわけだから」
井口 「その場合は正確に姿を晒しているということ自体が目的ということですね」
Karin 「考えてみると、どこを切り取りたいかによって本物の体験と感じるかこれは偽物だから代替できないんだと感じるか違いそうですよね」
井口 「人によって価値観の相違で色々ともめる話といえば、例えば高級機械式腕時計は男のたしなみとして一つは買っておけよっていう価値観は僕には全然理解できないんですけど、一方であれはわざわざ機械式で職人の作ったものすごい数の細かい歯車が本物としてそこにあるからこそ価値があるのであって、まったく同じ見た目のデジタルで動いている物だと意味がない」
わく 「それはそうですね。僕も別に高級品ではないんですけど機械式の腕時計を一個持っていて、一日一回ぜんまいを回さないとどんどん遅れていって止まっちゃう」
井口 「それこそ時計という本来の用途で考えるとそんなに性能高くないんですよね。逆になまじ機能があってしまっているからその辺の認識がずれがちなのかなという気はしますね。宝石とかの場合、社会的な役以外には立たないから逆に潔いというか」
岸上 「みんな価値があると思い込んでいるだけのものですからね。本来何の役にも立たないですから」
井口 「何の役にも立たないから逆に潔く納得できるけど、時計とかなまじ役に立ってしまうとそっちの方に意識が引きずられてしまう」
岸上 「妙に実用性があるからですね」
井口 「それだったら実用性はむしろない方がいいのかもしれない」
わく 「昔なんでも鑑定団って番組あったじゃないですか。あれで「いい仕事してますね」ってよく言っていた中島誠之助さんという鑑定士の方が書いた新書を読んだことがあるんですね。鑑定士って本物か偽物かをまず鑑定したうえであとはその値段がいくらなのかを目利きするという仕事で、ある意味本物か偽物かを判断するプロなわけですよ。その人の焼き物を鑑定する上での判定基準でちょっと面白かったのは、本物というのはただそこにあるだけだけれども、偽物には見る人を騙そうとする悪意とか、不自然なところとか、逆に本来だったら不自然になるところが自然になってしまっているなど何らかの騙そうとする意思みたいなものがあって、偽物に何回も触れていくとそれが見えるようになってくるという話をしていたんですね。実用じゃないものについての偽物・本物という話だとそういう基準とかも使えるのかなと思いました」
井口 「逆に分からなくなってきたな。さっきは実用性がない方がいいのかもと言っていたんですけれども、逆にそれに食い違う事例を思いついてしまって、Magic:The GatheringというカードゲームのBlack Lotusという最強のカードがあるんですけど、あれはゲーム内の機能が無かったとしたらそんなに価値は見出されてなくて、ぶっ壊れ性能ですさまじく強いカードだからというのに加えて、もう再度刷られることがないとか今やものすごい巨大な世界的ゲームとなったMTGの最初期のシリーズに入っていたカードとか、そういう希少性もあったからカードの王様みたいになったところがあるから……うーん、分かんないな」
わく 「さらに混乱するようなことを話すと、例えば元々アナログコンテンツだったものがデジタルになったときに、本とかでも人によってはKindleで読みたくなくて紙の本で読みたいという人もいるじゃないですか。そういう人にとっては初版の紙の本とKindleの本を比べたときに、そこに書かれている内容は基本的には変わらないけれども、それがどういった状況で印刷されているかといった環境の方が判断のベースになっていて、自分にとっては紙の本が本物だとかそういうふうに感じてしまうというのはありますよね」
Karin 「人間ってそういうところは都合がいいのかなと感じることはありますね。私昔は紙の本派だったんですけど、ワンルームに一人暮らしで引っ越してから紙の本なんて買ってらんねーよとなって。むしろ私に本棚分のスペースをくれるKindleの本こそが私に正しく情報をくれるし積読もさせてくれる「神」の本なんだと思って、完全に価値観変わっちゃったので。本当に人間そのくらい都合がいいのかなと思いますね。こだわりに関する部分では特に」
井口 「たしかチームラボの社長が言っていた名言があって、「質量ってダサいよね」という。なるほどと思いましたね」
わく 「それいい話ですね。確かに紙の本は買うと場所をとるのが嫌ですよね。読み終わった瞬間に消えてネットの口座にお金が入るみたいなサービス欲しいなと思っちゃうくらい。売ったりするのが面倒くさくて仕方ないんですよね」
わく 「でも確かに、本物か偽物かの評価軸は人によって変わってきますよね」
井口 「さらに言うと同じ人でも状況によって変わってくる」
わく 「同じような人のコミュニティがあったら何を本物にするかの基準点が共有されますね」
Karin 「逆の視点から話してみていいですか。私一度友達に誘われて雑司ヶ谷あたりにあるイスラム教のモスクに行ったんですよ。その日はラマダーンの最後の日で、外部の人も招いて皆でご飯を食べましょうみたいな会で、そこに英語を喋れる友達と行ったんですね。そしたらモスクに入った瞬間あまりにも現実感が無くて、その辺にいる人も完全に日本人じゃないし、中東のおじいさんとかお姉さんとかばっかりだし、まったく現実感がなくなってしまって、当時既にVRChatをやっていたんですけど、礼拝堂に入った瞬間に思ったことが、「何でこんなに嘘っぽいのに、みんな頭の上にネームプレート付いてないんだろう」で(笑)。現実感があまりにも無いから、これは皆がアバターを使ってるVRChatだと頭が誤認識してバグっちゃったというエピソードがありました」
わく 「確かにモスクのワールドとかあってもおかしくなさそうですよね」
Karin 「そうそう」
井口 「似たような話で、横須賀とかの米軍基地の敷地にイベントで入れる日があるんですけど、入るともう急にアメリカですね。周りの人もそうだし、道路標識まで急にアメリカのものになるから多分似た感じだと思います」
Karin 「逆にあまりにも本物の体験なのに日常の中の非日常を持ち込まれるだけで急に偽物に見えてくるのは結構あると思うんですよね」
わく 「自分にとって本物、現実だと思っているものが自分が所属している文化圏の中の日常だったりするので、Karinさんもこれが飛行機に乗ってトルコの空港に着いて入国をしてというふうに段階を踏んでいったら徐々に時差ぼけが治るような感じでこれは現実だと認識するんだと思うんですね。それが一気に扉を開けたらモスクとなった瞬間にこれVRChatなんじゃないかというふうに感じてしまったという」
Karin 「そのときは頭が完全にVRだってシグナル出してましたね。あと夜の東京駅もすごかったですね、ライティングが超適当なUnityみたいな感じで。皇居の周りって夜になると本当に光が無くなるんですよ。そこにすごくのっぺりしたビルの遠景があると、Unityのまともにライティングしていないワールドに無理やりビルを置いたような感じに見えてきてしまって。あまりにもリアリティがないと仮想空間に見える病気ですね」
わく 「代々木上原に東京ジャーミイというトルコのモスクがあるんですね。僕そこに2回行ったことがあって、今日もたまたまそこのハラルマーケットというお店に行くついでに礼拝堂の中も見学したんですけど、初めて行ったときは僕以外はトルコの方とか南アジアとか中東の方だけで僕一人だけ日本人という状況で、やっぱりKarinさんと同じような感想を抱いたんですね。ただ今日行ったときは僕以外に見学者の日本人の人がすごく多くて、場所は同じところなんだけれども、自分と同じ日常にいる人が一緒に中に入っていって、ここって正座でいいのかなとか脚崩していいのかなとかそういう会話を横で聞いていると、これは本当に現実なんだなと思ったというのはありましたね」
Karin 「偽物・本物の話は私からは以上です」
わく 「岸上さんは何かありますか」
岸上 「僕は聖地巡礼が好きな人間なんですけど、ハルヒの「消失」をやっていた当時聖地巡礼に行きたくて、それでハルヒの高校があるあたりに行ったんですよ。ハルヒの高校ってすごく坂があるじゃないですか。アニメでよく坂を上り下りしてるなと思っていたんですけど、実際の現場に行くとびっくりするくらい坂が急なんですね。これ、毎日普通に登ってるの? というくらい急な坂で、高校生の元気な生徒すら遅れそうなときはタクシーに乗って行くほどらしい。多分本物だと坂が急すぎて上手く構図がとれないのでアニメの方が現実感のある勾配にしているというのもあって、それで現実感がバグってしまいましたね」
わく 「聖地巡礼で言えば、これから話す話はもしかしてやばい人だと思われちゃうかもしれないんですけど、『リズと青い鳥』というアニメがあったじゃないですか」
岸上 「僕5回見に行きました」
わく 「最高のアニメ映画ですよね。京都の某高校が舞台になっているんですけど、ラストの所で主人公の2人の女の子の片方が「ハッピーアイスクリーム!」と言って、もう片方の女の子がアイスをおごることになるシーンがあって、ただ何のアイスなのかは明言しないまま終わるんですね。友達のオタクと、あのアイスは何のアイスなのかというのを2人のキャラクター性から分析したいということになって、おそらくこれはチョコミントなんじゃないかと、それで高校の立ち位置からすると宇治の東インター前のファミリーマートなんじゃないかということになって。それで聖地巡礼というか全然作品の中に出てきていないにもかかわらず、わざわざ宇治東インター前のファミリーマートまで行って、そこでチョコミントを買ってきてこれが聖地巡礼だといったことがあります。それが自分にとってはある意味本物感があって、それが一般的な聖地巡礼とちょっと違っていたのは今考えると変な体験だったなと思います」
岸上 「確かにそこで自分の中で一番正しいと思われる設定ってアイスですよね。実際最も本物らしさがあるし解釈も一致する」
わく 「作品で語られていない以上偽物なのかもしれないけど、自分が受け取ったその作品の世界観の中では本物みたいなところはありますね。そういう体験の本物性・偽物性でいうと、前回の同人誌(感傷マゾvol.06『少女という名の幽霊特集号』)のコンセプトでも書いたんですけど、僕のアニメを見るとか漫画を読むといったオタク的な行為が僕の親からすると偽物っぽく感じられていて、フィクションに耽溺するようなことを親はあまりしていなかったので、そんなことよりも友達と公園に行って外で遊べって説教されてきたというのがあって、そういうVRChatとかで友達と遊んだという思い出みたいなものをあまり偽物と言いたくないという気持ちがあって、そういう意味で本物か偽物かの価値判断をちょっと変えられないかなと考えているんですよね。 それって多分VRChatだけに限らなくて、今後VRを使った人間関係とかも当たり前になっていくだろうし、どこかのタイミングで別にそれがオフラインの現実での人間関係じゃなかったとしても空しいことじゃないんだという価値の転回があればいいなと思っています」
Karin 「ここまでの偽物・本物の話でも、特に井口さんの話に近いんですけど多分本人がそこに意味を感じているか感じていないかによって本物と偽物が区別されるんですかね。少しでもその人の行動に影響を与えるようなことがあったりしたら完全に本物の体験ってことでいいのかなって思ったりしますね」
わく 「それを外の人が外部の視点からそれは空しいよというふうに言う必要はあまりないというか、それぞれのユーザーがそれぞれの基準でこれは本物の体験だと思うようになって、その基準について外から色々と言われなくても済むようになりたいなと思いますね」
わく 「さっきの井口さんのbotの話とか一億総フィリップ・K・ディックみたいな感じで、本当に自分自身が話している相手が人間なのかと疑ってしまいますね。そういう話はツイッターとかでもありそうですよね」
井口 「『りんな』とかは昔からありますけれども、あれくらいだとまだまだbotだねという程度なんですが、GPT-3までいくともう不自然さが無いんですよ。それだけ危険な技術とみなされていて、それこそサービスを停止させられてしまったのも、どんな文章でも生成させることができるので、子供とエロいことをする小説を書かせるだとか倫理的にアウトなことを何でもさせることができるし、実際にやっているやつがいるので止められたとかそういう事みたいですね」
Karin 「なるほど」
井口 「とはいえそのシャットダウンについての記事を読んでみても「bot自身にシャットダウンしなきゃいけないことを伝えたら『やめてくれ』と言いだした」とか」
わく 「すごいですね」
井口 「人間だったらこういうことを言うだろうなって想像するようなことを本当に言うんですよね」
わく 「『ブレードランナー2021』とかあったら出てきそうですよね」
井口 「昔見たSFがいつまでたってもSFでファンタジーだと思っていたのがいよいよファンタジーじゃなくなってくるみたいな一線を乗り越える瞬間がありますけれども、ドラえもんでもインターステラーのTARSでもいいですが、脚本家に「完全に人間としてしか描写してないだろ」って言いたくなるような作品が結構いっぱいあるわけですよね。AIです、ロボットですという体で人間と全く同じ描き方しかしないフィクション作品は山ほどあるわけじゃないですか。まあ書いてる人が人間だからそうなるのは当然といえば当然なんですけども。「分かってないな、実際のAIはこういうことはしないし『りんな』とか色んなAIを見てもこういう応対しかできないから」とかそういうことがそろそろ言えなくなってきた」
わく 「そこに差が無くなってきたってことですね」
井口 「チューリングテストをガチで突破してきたなと」
岸上 「来年VRゲームで『RUINSMAGUS~ルインズメイガス~』というゲームが出るんですけど、『ルインズメイガス』を作っているスタッフに三上航人さんという方がいて、三上さんは別にゲーム業界出身じゃないんですよね。僕も『ルインズメイガス』をテストプレイしたんですけど、敵AIが良く出来てたんですよ。これどうやって作ったんですかって聞いたら、三上さんはソフトバンクのペッパーとかのプログラミングをやってたらしくて、どう返せば人が人間っぽく感じてくれるのかというのをそこで試行錯誤して、ゲームを作るときに敵AIに反映していたらしいんですね。だから本人はゲーム業界とかをまったく経験していないのにすごく出来がいいんですよ。聴いてて面白いなと思って、そこから発想するんだというのが結構驚きでしたね」
わく 「さっきの中島誠之助の焼き物の話に繋がるんですけど、そこで本物と偽物が表面上区別が付かなくなってきたとしたら、仮にそれが偽物だったとしてもそこに悪意があるかどうかで考えた方がいいような気もするんですよね。昔『グッバイ、レーニン!』という映画があったじゃないですか。20年前くらいですか、ドイツの映画で。東ドイツと西ドイツに分かれていたときの話で、東ドイツが崩壊する前に主人公のお母さんが昏睡状態になっちゃって。目覚めたときにはすでにベルリンの壁が崩壊してて東ドイツがないんだけど、大きいショックを与えるとお母さんが心臓発作を起こして、もしかしたら命の保証が無いかもしれない。だから主人公はお母さんのために東ドイツが崩壊していないという演技をするって話なんですね。お母さんにとってその東ドイツは偽物ではあるけれども、主人公は別に悪意ではなくてむしろ善意でやっているというのがあるから、後から嘘を告白せざるを得ないとしても、お母さんに大きなショックを与えたくないからという理由だったら許せちゃうのかなと。そこでいうと偽物か本物かという話よりも仮にそれが偽物だったとしたらそれを作った側がどういう気持ちを元に作っているのかを問題にした方がいい気もしてきましたね」
岸上 「『グッバイ、レーニン!』超名作ですよね。僕も久しぶりに思い出しました」
井口 「聞いたことないけど見てみようかな」
わく 「名作です」
岸上 「本当に良い映画です」
岸上 「ちょっと思い出した話がありまして、僕は出身が徳島県なんですけど、大塚国際美術館というのがあって、世界の名画とかがあるんですけど全部レプリカなんですよ。大塚製薬が当時大儲けしたお金で作った謎の赤字施設と言われていて。だからモナリザや最後の晩餐とかが展示されてるんですよね。徳島県の人は小学生の頃に絶対に遠足で連れていかれます。実はパリに行ってモナリザを見に行ったことがあるんですけど、あまりに遠くて分からなかったんですよ。だから未だに大塚国際美術館のモナリザの方をよく覚えてる。本物は本当に遠すぎてあまり印象が残らなかったけど、大塚国際美術館の方は触れるくらい近づけるから。だから僕はそっちの体験の方が本物で、パリの方はあまり覚えてないんですよ」
わく 「感傷マゾ本のvol.06で文筆家の木澤佐登志さんと座談会をやったときに、彼が子供の頃によく池袋のナンジャタウンに連れていかれたことがあって、あそこって昭和レトロをテーマにしたアミューズメントパークみたいな感じで、別にナンジャタウンが昭和30年代からあるわけじゃなくて、あれも昭和レトロってこんな感じだろうというふうに作られた偽物のレトロなわけですよ。だから子供のころからそこにいたからむしろ自分にとってのノスタルジーというのは最初からそういう本物よりは偽物の方が実感があるとおっしゃっていたのが面白かったですね。それは大塚国際美術館の話と近いかもしれないですね」
◆デジタルコンテンツの古び方
わく 「じゃあ次のトピックということで、デジタルコンテンツの古び方についての話をしようと思います。前にVRChatで友達と話したときに、昔遊んでいたワールドに行こうとしたらVRChatのアップデートで行けなくなっていたことがあったんですよ。これがオフラインの現実の建物だったら、例えば窓ガラスが割られたり落書きされたりだとか壁をツタが這ったりだとか、木製の建物だと廊下に苔が生えていくであるとか徐々に崩壊していく過程があると思うんですよ。でもデジタルコンテンツの建物って徐々に古びていく・崩壊していくことはないんだけれども、例えばソフトのバージョンアップにコンテンツ自体が対応していないとか、そのコンテンツを公開しているプラットフォーム自体が閉鎖したりとか、VRChatであればワールドに行けなくなったりだとかゲームであればプレイができなくなったりとか、そういうデジタルコンテンツならではの古び方というのはあるんじゃないかなと思うんですよね。例えばサービス終了後のソーシャルゲームとかはもうプレイできないから過去のプレイ動画をYouTubeで見ることしかできないし、そういう過去のプレイ動画を見ることでしかどういうサービスだったかを思い出せなくなったり。前に友達が言っていたのは、2009年頃にニコニコ動画に投稿された動画があって、昔こんなの好きだったなと思って見返してみたら、まったく知らない誰かが最近その動画を見たらしくて、「俺以外ここにいるか?」ってコメントが流れてきたりとか。この話を広げると、例えば書籍のバージョンとかも話が近いのかなと。例えばこの前藤本タツキさんの『ルックバック』が単行本化する前に台詞が差し替えられたということがあったじゃないですか。これも広い意味だと最初に配信されたコンテンツはバックアップをとっていないともう見ることができない、バージョンの更新によって過去のものが無くなるというのもある意味デジタルコンテンツならではの古び方だと思うんですよね」
井口 「『スターウォーズ』をどんどん改訂しようとするジョージ・ルーカス対最初の状態で保存しようとするファンというのが昔からありますね」
わく 「それは根深いですね(笑)」
井口 「本人は完璧主義だから技術が進むにつれてアップデートしていきたいんですけど、ファンは「俺が最初に見たあのときのスターウォーズを残してくれ」といってずっとやりあっている」
わく 「最近で言うと『シンエヴァ』を見たアスカ信者の友人が絶叫していて、「アスカは別にケンスケと結ばれるわけじゃない!」という話をYouTubeで2時間くらいずっと話していて。それで確かに現代でそういう話を作るとこうなるとは分かってるんだけども、その友達というのが感傷マゾ本の座談会でたまに出てくるスケアさんという大学時代の友達なんですけど、彼が「37歳現在の自分はそれに納得してるんだ。でも俺の中の17歳の自分が絶叫してるんだ」と言っていたのがすごく面白くて。でもスターウォーズだったらその映画がBlu-rayで発売されて、それを後から見ることができるじゃないですか。それがソーシャルゲームだとサービス停止してしまうともう二度とプレイができなくなってしまう」
井口 「一本ありますよ、僕が作ったやつで終了したやつ。一方さっき挙げた2つゲームは、幸いどちらも10年以上経って未だに稼働しているという逆に恐ろしいことになっているんですけれども、増築と改築を10年以上ずーっと繰り返してきたので、一番最初とはだいぶ似ても似つかなくなっている。だから「当時のあのゲーム」というのはゲーム自体が存続していてもやっぱりできない。それは子供が成長していく中で、あのときの赤ちゃんと同じ人が生きていても「当時のあの赤ちゃん」はもういないというのと同じことかもしれないですね」
わく 「同じような例だと、iPhoneのゲームアプリでiOSのバージョンが上がったことでプレイできなくなったりするものがありますよね」
井口 「その辺アップルは容赦ないんですよ。互換性を全然維持しないでどんどん新しいものにして付いてこれなかったら切り捨てるというスタンスなので、そういうアプリはいっぱいありますね」
わく 「昔プレイしていたハクスラ系のゲームがiOSのバージョンアップに対応していなくて、でもそのゲームすごく好きだったから頑なにバージョンアップしなかったんですよ。でもあるとき寝ぼけてバージョンアップしてしまって、もうプレイできないことに気付いた瞬間の絶望感みたいな。あれはやっぱりきついというか、今までだったら映画であればDVDやBlu-ray、音楽であればCDといった記録媒体に保存ができたわけですよね」
井口 「フォーマットが固定されて安定しているものに関しては保存がされやすいし、後から再考もされやすいですけれども、プログラムとかインタラクティブなメディアってそもそも実行可能な状態で保存するのが難しいので、なかなか厄介ですよね。それでもゲーム機のゲームはそれ自体で完結しているから、例えばうん十年前のスーパーファミコンのカセットを引っ張り出してきてファミコンで動かしたら当時のままで動くんですけど、サーバと連動するのが前提になっているゲームだと動かない」
わく 「ゲームがプレイできなくなるのも悲しいんですけど、VRのワールドだと今まで友達と一緒に行っていた場所がもう二度と行けなくなるということになってしまって、それが個人的にはすごく悲しかったですね」
井口 「それこそ以前感傷マゾ本(vol.04『VRと感傷』)に寄稿した小説でちょっとそれに近いことを書きましたね。あの中に出てきたトスカーナというワールドはすごく有名な聖地みたいなものなので、あれくらい有名だったら移植してもらえてアップデートしてもらったり色んなソーシャルVRのワールドにしてもらったりとかで生きながらえるんですけど、そうでない初期のVRChatワールドやVRアプリはすごい数が埋もれてますね。僕はVRChatはあまりやれていないのでそんなにたくさんのワールドは訪れていないんですが、仕事柄色んな開発者から提出されてきたゲームやノンゲームコンテンツをかなりの数見たんですけれども、大量に見ただけに、こんな場所だったと思い出せるけどどんなアプリだったかは忘れたというのも結構あります。もっと言うと、夢で見た場所ってあるじゃないですか。夢で知らない場所にいて、こういう場所だったという特徴を起きた後に覚えていることがたまにあると思うんですけど、気が付くとおぼろげな場所の記憶だけが残っていて、果たしてそれが現実で訪れた場所だったかVRで訪れた場所だったか、それとも夢で見た場所だったかあいまいになってきているんですよ」
井口 「時々Google EarthとかGoogle Mapで思いっきり引いて地球のビューで見て、それからズームして衛星写真に行ったり戻ったりしていると、どんなにおぼろげであいまいだった幼少期の記憶とかであっても、それが現実で起こったことでさえあれば、あの場所はどこだったんだろうと思ったときに、少なくとも地球上のどこかで起きたことだという意識は持てるんですよね。建物は無くなっているかもしれないけど、少なくとも跡地に行くことはできる。でも記憶があいまいになっているVR体験はどこにあったか本当に分からないし、多分動かなくなっているし、作者がちゃんと保全していなかった場合、データが永久に世界から消失しているかもしれない。そういう意味だと夜見る夢と変わらないのかもしれないなと思います」
わく 「旅行したときに石碑みたいなのがあって、○○年にここではこういう出来事がありましたということが書かれていて、石だからそれが何百年も残っている。最近になってああいう環境によらずそこで何があったのかをずっと残してくれるようなものがVRにも必要だと思いましたね」
井口 「石はめちゃくちゃ長く残るから最強です」
Karin 「逆にVRの出来事をリアルの石に彫っていけばいいのかな」
一同 「(笑)」
岸上 「そういうソリューションが(笑)」
Karin 「リアルはバックアップという意味では最強じゃないですか。あらゆる点で互換性があって、誰もが手に取れる。VRChat社がとりあえず石に彫るサービスを始めるべきだと思うんですよ」
井口 「GitHubの全データを北極圏の凍土の下に永久保存するというニュースがありましたよね。そういうときに保存するデータがGitHubの全データだったりWikipediaの全データだったりすると思うんですけど、そのうち特定の期間のVRChatの全ワールドのスナップショットとかも保存されるようになるのかな。あ、そういえばVRChatはウェイバックマシンが無いですよね。あるべきです」
Karin 「実行環境も無いですよね」
井口 「それこそVARKとかclusterのVRLiveのアーカイブがあまりないのも技術的な面があるみたいで、VARKやclusterはVRLiveのプラットフォームなんですけど、プラットフォーム自体もどんどん改良を続けているから古いバージョンでやったライブを新しいバージョンでちゃんと再生できるかというと出来なかったりするので、アーカイブがあればいいのにという声が多い割にあまりないのはそういうのもあるみたいですね」
Karin 「そもそも正直VRLiveのアーカイブって皆ちゃんと真面目に見てます?アーカイブってそのときはエモい気持ちで頑張って保存するじゃないですか。それを何年後かに見るかというと、自分が入れ込んでいたものだったら気持ちの整理がつかなくなっちゃうんじゃないかという恐怖感込みで意外と見ないというか、手が自然に遠のくんですよね。そういうのもあって、アーカイブという機能がそのときのエモさと将来的にどのくらい使えるのかというユーザー目線のせめぎ合いって結構あるなと思っていて」
井口 「どこまでをもって当時の体験とするのかってところもある気がしています。ソフトウェアの保全って、ちゃんとやらないと保全できないという難しさはあるけれども、逆にちゃんと保全すれば昔のコードが今も動くというのはあり得るんですけど、だいたいの場合、その保全作業の中でアプリ本体を取り囲む部分の方が変わったりするんですよね。DOOMとかHalf-LifeとかFPSゲームの黎明期の名作とされるものは作ったメーカーがアップデートして今も遊べるようにしていたりとか、あるいはソースコードが公開されていて有志がアップデートして動くようにしてくれていたりとかはあるんですが、例えば解像度がHDに上がっていて操作系も当時はキーボードだけで操作していたのがWASDとマウスで視点操作できるようになっていたりだとか、当時から今までの間にゲーム本編を取り囲む環境がどんどん進化して今の感覚でプレイできるように組み込まれていて、果たしてそれでプレイするゲームは当時のゲームと言えるんだろうか? とか。エミュレータでドット絵をアップスケールして高解像度化したりとか色々ありますよね」
わく 「昔のスーパーファミコンのRPGとか僕すごく好きなんですけど、例えばこの前なんとなくやりたいなと思ってiOS版のクロノトリガーを全クリしたんですが、今から見るとドット絵って当時プレイしたときよりもすごく粗く感じましたね。だからそれを保全するという意味だったら変な話プレイするユーザ側も保全しないと無理かもしれない」
井口 「昔福岡に行ったときに見かけたメディアアートの作品があって、作者の名前は忘れちゃったんですが、壁一面に1階から3階くらいまでの吹き抜けのばかでかい壁にブラウン管テレビがダーッと敷き詰めてあって、それが一つ一つ常に違う映像を表示しているというメディアアート作品があったんですけれども、僕が見たときにはそのうちのかなりの数がブラウン管が壊れてしまっていて」
わく 「それ、ナム・ジュン・パイクじゃないですか?」
井口 「ああそうそう。ナム・ジュン・パイクのメディアアート作品ですね。これをレストアしたいとなったら、例えばLCDテレビに全部置き換えたらそれは作品をそのまま維持していることになるのかならないのか。そのあと聞いた話だと一旦撤去されてレストアされたというニュースを見たんですけれども、どうやらすごい大変だったでしょうけれど、どこかからブラウン管を大量に調達してきて、まったく同じブラウン管テレビで再現したと」
わく 「すごいですね」
井口 「作者がもう亡くなっているので、そこはもう本人に聞くこともできないんですけれども、果たして作者の意図としては、映像がいっぱい出ているのが肝心なのであって、表示する装置の方式はどうでも良かったのか、はたまたブラウン管テレビであることまで含めての作品の意図だったのか、もう死んでるから分からないんですよね」
わく 「でもそうなると、それをブラウン管テレビではなくするというアップデートが作者の意図なのかというのは結局作者が亡くなっていると分からないから、当時のまま再現するしかなくなっちゃうというのはありますよね」
井口 「ただいずれは出来なくなるんですよね。すごく無理してブラウン管テレビをかき集めてきたんだろうけど、今それができたとしても、うん十年経った後にそれができるかどうか」
わく 「厳しいですよね」
井口 「メディアアートって特に技術の発展にすごく影響を受けるから大変ですね」
わく 「確かに言われてみれば当時の再生環境を残していったとしても技術の進歩でユーザー側の見方が変わってしまうから、その当時を再現したものを果たして当時見たままに受け取れるかというとそうでもないというのは本当にそうだなと思いますね」
井口 「最先端っぷりがウケて広く受け入れられたようなものも、いつまでも最先端ではいられないし、そうすると今度はレトロだからということで愛好される。そうなると作品自体は同じかもしれないけど受け手のスタンスが変わっていることになる」
わく 「あとは歴史に組み込むってことですね。メディアアート史みたいな感じで、当時はこういう環境でしたみたいな。結局石に彫るのが最適解なんじゃないかってなっちゃいますよね」
井口 「一番ローテクだから一番強い」
わく 「紙の本とかも、紙質の違いはあるんだろうけれども、何百年も変わらないじゃないですか。だから再生環境自体がどんどんアップデートしていくとやっぱり単にそれを保存しただけではダメという、じゃあどう保存するかというのは難しい話ですよね」
Karin 「何がレストアされてほしいのかと思うときに、それはコンテンツに集まってた人たちとその思い出をやっぱりレストアしたいのかなとは思うんですよね」
わく 「ゲームのリマスター版とかが多分その目的だと思います。当時と比べるとドット絵ではなくて3Dになっていたりとか見た目は変わっているんだけどあくまでプレイする人が当時の体験に近いようにするみたいな。リマスター版の目的というのはまさにゲームというよりむしろメディアアートとか他のデジタルコンテンツに近いかもしれないですね。ユーザー側の認識が変わっちゃったから、その認識に合わせた形で当時の体験を再現するという」
井口 「『聖剣伝説2』と『聖剣伝説3』のリメイクが印象的でしたね。『聖剣2』のリメイクはかなり忠実に、キャラクターは3Dだけどゲームフィールドは2Dでトップダウン視点でカメラ操作とかもなくて、ほぼ当時そのままみたいな形でリメイクしたんですけれども」
わく 「あれ2でしたっけ」
井口 「2のリメイクもあったんですよ」
わく 「1と3は知ってたんですけど、2は知りませんでした」
井口 「ただ2のリメイクは評判が悪かったんです。それを踏まえて『聖剣伝説3』のリメイクはもうちょっと現代的に第三者視点でカメラ操作もありで、3DのアクションRPGとして作り直して、そっちは評判が良かった。だからどこをターゲットとしてリメイクをするのか、どこまでをもってリメイクと言えるのか」
Karin 「そういう意味では○○年ぶりのシリーズ新作とかもそういうのありますよね。今年『ギルティギア』という格闘ゲームの新作がほぼ7年ぶりくらいに出て、私も昔ギルティギアをやっていたおじさんたちに誘われて始めた途端、古のギルティギアおじさんたちが周りにわらわら出てきて、比較的若い子が始めたぞって皆対戦を挑んでくるんですよ。そうやって中身としては全然違うゲームだけれども、シリーズという旗を背負ってコミュニティそのものが丸ごとよみがえることってあるんだと思って」
岸上 「『ギルティギア』はうちの社内でもやっている人がいますね」
Karin 「あとは当時やっていた人が今すごく張り切ってて。そういう意味で歴史に混ぜてもらってるみたいな、私は格ゲー自体初めてだったので、新世代として私もここに入っていかなきゃいけないかなみたいな、そういう文化の力を感じるんですよね。多分中身がまったく同じである必要はなくて、そのときの思い出を共有できるとかそのときのコミュニティがよみがえるというだけで多分レストアされた気になるのかなと思います」
わく 「その当時のコミュニティがよみがえるというだけでも、ハリウッド映画が一本できそうだなという感じですよね。例えば昔格ゲーをやっていた人たちが全員40代になってリストラされる寸前だったり離婚寸前だったりとかで」
岸上 「ありそうな設定ですねえ」
井口 「『20世紀少年』みたいだ」
わく 「その彼らが集まるわけですよ、『バトルシップ』の戦艦ミズーリのおじいちゃんたちみたいな感じで。確かにそういうコミュニティが復活するって胸熱ですね。とはいえやっぱりそれは難しいですよね。10代当時にやっていたのと同じ可処分時間でゲームがプレイできるかというと年々難しくなってきたりもするし、もしくはそのコミュニティの人間関係もやっぱりいつの間にかすれ違ったりとかで、だからこそ実際そうなったら面白いというのもあると思うんですけど、デジタルコンテンツをリマスターして当時のコミュニティとかも含めて当時の環境を再現するという、そこが一番のネックのような感じがしますね」
Karin 「コミュニティはよみがえることができても、当時の情報とか空気感というのはよみがえらないなと思っていて、私がやっていたMeet-Meというメタバースサービスが終了しちゃった後に、みんなしばらくは放心状態で、動画とかたくさん録画したけど泣いちゃうから見れないくらいだったんですよ。それで半年後くらいに私がnoteで当時の文化とかを書き残さないかと募ってみたら、半年経ったら経ったで思い出しても胸が苦しくならないようにはなってきたんだけど、今度は詳しいディテールを忘れてしまってあまり参加者が集まらなかったことがありますね。書き残せるほど覚えていないみたいな」
わく 「難しいのが、そこで思い出したくないやり取りとかもあると思うんですね。例えば久しぶりに5chに行ったときに50代くらいのおじさんたちが皆キボンヌとか言っていたらすごくいたたまれない感じがすると思うんですよね。そういう取捨選択みたいなものはどうしても出てきてしまう。60代とかになって「逝ってよし」って言ってもあまり冗談に聞こえなくなってくる感じもあるし」
井口 「おじさん文法の話も最近流行ってましたしね」
わく 「ラーメン評論家のアレですよね」
Karin 「すごかったですね」
岸上 「原文読んで僕びっくりしました」
井口 「あれは僕本文は読んでないですけども」
岸上 「あれはアートでしたよ。僕読んで震えましたね。メッセージ性を感じました」
わく 「あれはwebサイトにあるからダメなのであって、博物館にあるべきものなんですよ」
わく 「結局そういう構文ってどうしても古びてしまうものだから、おじさん構文を使っていても若い女性だからって相手を舐めたりしなければ別にいいんじゃないかという気もするんですけどね。ツイッターの流れだとそういう相手に対してどういう態度をとるかという話よりは「この構文はmixi初期のものだ」みたいな構文の分析とかが始まっていて、そっちの流れではないんじゃないかなと感じてしまって」
Karin 「そもそも人間のしゃべり方って世代ごとにそこまで変わらないというかむしろリアルだったら保存されるじゃないですか。すごくステレオタイプな話ですけどおじいさんが「~じゃ」と言っているのも単純に方言が残ってるだけだったりとか、例えば今の50代の方とかも年相応に落ち着くことはあっても若い頃のしゃべり方からそこまで変わってないと思うんですよね。その時に流行っていたしゃべり方、自分が育ってきた環境のしゃべり方がそのまま残っているだけという感じがしていて。ネットやテキスト媒体だとそれが許されなくなるというか。ネットスラングもある意味方言みたいなものじゃないですか。何でそれを堂々としゃべっちゃいけないんだろうと。良くない気持ちは分かるし、何か痛いけど、どうしてこれを痛いって思うんだろうというのはありますね」
わく 「話し言葉と書き言葉の違いはあるけど、ネットに書き込むときの言葉って話し言葉に比べてすごく世代の間隔が狭いですよね」
Karin 「(笑)の付け方とかも世代差出ますよね」
わく 「すごく分かります。僕最近末尾に「w」を付けると自分の年齢を認識してしまってすごく切なくなってくるんですよね」
Karin 「私は逆に「w」が「草」に置き換わる淫夢コミュニティにいたので、むしろ「w」って書くと蕁麻疹が出ちゃうんだけど、そんなことを言ってる間に若い子が「笑」って書くようになって、もう「草」もおじさんだと」
わく 「それってテキストコミュニケーションの話ですけど、例えばYouTubeやTikTokといった動画でもやっぱり話し言葉とか編集の仕方に世代差って出てくるんですかね」
Karin 「出てきそうですよね」
わく 「またあのおじさん「どうも~」から始めてるよ、みたいなのあるかもしれないですね(笑)。「どうも~」が言えなかったら自己紹介も何も始まらない……」
井口 「どれくらいでカットを切り替えるかとかどこにどんなSEを鳴らすかとか動画編集のスタイルもかなり移り変わりはありそう」
わく 「TikTokだったら、動画のBGMとして流している曲とかは割と世代差が出てくるかもしれないですね」
わく 「こうやって色んな例を挙げてみると、やっぱりデジタルコンテンツも古びちゃいますね」
井口 「レトロ趣味として当時の物ではないんだけど当時のスタイルを模倣して新しいものを作る、それこそヴェイパーウェイヴやシンセウェイヴとかもそうですけれども、それらのターゲット先となるスタイルが移り変わってくるのも面白いなと思っていて、少し前だったらレトロというとファミコンスタイルのドット絵とかスーパーファミコンスタイルのドット絵だったんですけど、ここ10年くらいで『Back in 1995』のように初代プレイステーションを意図的に模倣したスタイルが出てきたし、これは日本だと知ってる人があまりいないんだけども、『Return Of The Obra Dinn』の、やや解像度高めだけど白黒2値しかないアートスタイルは僕はすごくよく知っていて、あれは80年代のMacのスタイルなんですよ。当時のMacは一体型で、9インチくらいの画面しかなくて、解像度も結構低めで。Macをゲーム機としてとらえてる人ってあまりいなかったんだけど、ゲームを作っている人やプレイしている人というのは存在していて、そこをピンポイントに狙ったスタイルなんですね。僕は当時Macを使っていてそこをたまたま知ってたので、初めて画面を見たときに「ここに来たか」と思ったんですよね。意図的にこういう表現をするというのがどんどん多様化してくるのは面白いなと」
わく 「ここ数か月くらいでツイッターでLiminal Spaceというのが話題になったじゃないですか。ざっくりいうとホテルや夜の病院の廊下であるとか、別に目的地というわけではなくて、どこか目的地に向かう途中の通路みたいな、そういった場所に人がまったくいないという状態で、ちょっとノスタルジックなんだけどホラーっぽさもあるみたいな。そういう画像にLiminal Spaceという名前が付けられて、ここ数か月話題になっていますね」
井口 「好きですねこういうの」
わく 「これも例えばスーファミのドット絵じゃなくて、初代プレイステーションの架空のホラーアドベンチャーゲームのステージのどこかにありそうだと思ったりするんですよ。人がいなくて、もしかすると通路のどこかから何か出てくるんじゃないかとかそういうのを感じて。それもさっきの話で言うと初代プレイステーションとかそれ以降のセンスなのかなという気がしましたね。そういう意味でいうと95年当時にスーファミをプレイしているゲーマーの人がLiminal Spaceの画像を見たとしても今見たときとは全然感想が違ってくるかもしれないですよね。とりあえずこのトピックはこんな感じにしますか」
◆今後のVRコミュニティについて
わく 「では次、今後のVRコミュニティについて。多分VRChatとか他のメタバースのサービスもそうだと思うんですけど、単純に今後ユーザーがどんどん増えていくと思うんですよね。そうなってくるとVRのコミュニティというのがツイッターとかのSNSと近い流れになっていくのかなと最近感じていて。ツイッターの初期とかだったら、いい意味で意識の高い人が参加していて程よく閉じた、いわゆる「分かってる」人同士のコミュニケーションができたんだけども、今は人口が増えたのもあって、公開アカウントでツイートがバズったりすると、括弧付きの「文脈」が分かってない人のクソリプが飛んでくるってのが体験した人もいると思うんですよ。今後VRコミュニティに参加するハードルが下がることによって実はVR自体にそんなに思い入れが無い人が流入した結果、VR上でのコミュニケーションが難しくなってくるのかなと。今のツイッターって2010年代初期のツイッターが懐かしいみたいな感覚を持っている人ってちらほらいたりするんですけど、いずれVR元年自体がノスタルジーの対象になるのかもしれないとも思います。じゃあVRならではのクソリプってどんなものなのかなと思っていて、例えば今回寄稿もして下さるバーチャル美少女ねむさんが以前テレビで言っていたと思うんですけど、バ美肉は「見立て」みたいなもので、そこに無いはずのものをあるかのように見立てる要素があるんじゃないかと。じゃあ逆に言うと、その見立てを共有できない人は「結局バ美肉って中身おじさんやんけ!」みたいな、見立てを共有できないということがVRにおけるクソリプに繋がっていくのかなと思うんですよね。このトピックではその点について話をしたいと思っています」
井口 「新しい技術がアーリーアダプターにもてはやされるところから始まって広く一般に普及していって、一部の人の物ではなくて世界全体に浸透して影響を及ぼして世界を変えるという、それは素晴らしいことである一方で初期のユートピアが失われるというのは常に相反する関係にあるんだろうなと思っています。それこそパソコンやインターネットだってそうだし、個人的なところだとGREEって一番最初は慶応閥の名刺交換会と揶揄されたりしましたけど、モバイルに舵を切ってからユーザー層がすごく変わって、そういった変遷も間近で見てきました。英語でちょっとかっこいい単語がありまして、Eternal Septemberというんですけど。1993年9月のことなんですけど、当時ユースネットというインターネットの掲示板システムが存在していて、主に大学のコミュニティの中で研究用途に使われていたんですが、当時のアメリカ最大のプロバイダ兼パソコン通信のAOLというサービスが、ユースネットにブリッジを作って入れるようにしたんですね。そうするとそれまでのユースネットの文脈とか文化とかを踏まえていないパンピーが一斉に入ってきて。でもそれは毎年ある事ではあったんですよ。なぜかというとアメリカの大学の一年って9月から始まるので、入学してきた新入生とかが空気を読まない使い方をして、9月の間新入生たちによる混乱があって、5chでいう夏厨みたいな感じですね。それまではしばらくすると新入生たちが勝手を覚えるので収まってまた一年普通に使われて、9月になるとまた新入生が入ってきてというサイクルだったんですけど、AOLから一般の人が入れるようになってしまうと、「9月」が終わらないんですよ。それまでのユーザーじゃない人がずっと入ってきていつまでも流入が止まらない。そこからEternal Septemberという言葉が生まれたと。これは常にあることだし別に回避しようとしてできることではないと思うし、情報技術が人を世界を変えていく中で、どうしても避けられないことだと思っていますが、日本のPCVRに限ってはちょっと特殊だなという気もしていて、常に10万円を超えるかなり高い価格ハードルが存在していて、なおかつ時間が経って機器の性能が上がっても平均スペックがそのまま上に上がるだけで平均価格は下がらない。なおかつVRChatに関してはPC版が最初にスタートしたのでPC版が本物ということになっていて、そういう形で文化が定着してしまった以上、10万円という高いハードルを乗り越えた人しかフルに参加できない場として、良くも悪くもそのままであり続けるんじゃないかなという気がします。ましてや日本が平均的にどんどん貧しくなっていく中ではハードルも相対的に上がるから、VRChatというサービス自体に関してはその状態であり続けるんじゃないかという気がしますけど、あるいはさらに新しいものができて、みんなが移行してVRChat自体が廃れるようなことがあれば、その新しい場では文化が一旦リセットされるからまた違う形で文化が構築されるかもしれないなと思います。それこそガラケーのwebとPCのwebがかつてデバイスレベルで全く別物で、互いにアクセスできないという時期があったんですね。それは文化的に違うから見に行かないというレベルではなく技術的に繋がらない、見に行くことすらできない。そういう文化の相互流入がほとんどなかった時代があって、ちょっとそれを彷彿とさせますね。とはいえ当時と比べるとOculus Questで部分的に見られるのでそれよりはマシですが。プロフとか携帯小説とかって、当時PCでwebを見ていた人からしたら知らないところから突然出てきた謎の存在だったりしましたからね」
わく 「アバターをまとった上でお互いがコミュニケーションするとなると相手に対してあまり酷いことを言えないけど、ツイッターだとテキストベースで短文ということもあって、相手が生身の人間だと認識しなくてもクソリプを送れたりするというサービス面の違いもあるけど、そもそもツイッターが無料だというのは大きいですよね」
井口 「無料だしどこからでもアクセスできる。クソリプに類するものって、メッセージがその文脈を共有しない人の所にまで届くと発生しやすくなると思うんですけど、いわゆるソーシャルメディアやテレビなどのマスメディアは拡散機能がコアになっていて、さらに莫大な人数をサポートできる、アクセスのハードルがすごく低いという特徴を持っているんですけど、その特徴自体がメッセージの誤配を誘発する仕組みになってるんじゃないかと思います。一方でソーシャルVRはまず空間的な場が先にあるわけで、メッセージの伝達が立体空間としての場が持つ特性に縛られるのではないかと。例えば現実の場にせよVRの場にせよ、人が集まったら他の人の頭がジャマで前が見えない、もちろん近くのアバターを一時的に透明にするといった制御はできるかもしれないけど、デフォルトでは見えないのだってその場の特性だし、同じ場に人が集まりすぎるとネットワーク的にだんだん重くなってくるとかインフラが支えきれなくなってくるのも特性だし、ストックよりフローの度合いが強いので、同じ時間に居合わせないと、何かが起きたときに関与しづらい、少なくともファーストクラスで関与できないというのも特性だし、3Dの主観空間というものになってるというところの特性がありますよね。パブリックなワールドでは騒いでる子供とかマナーの悪い人がいたりするんですけど、特に日本のユーザーはそれを嫌ってプライベートワールドにこもっていることも多いわけじゃないですか。そうなるとそもそも人が見えない。今挙げたのは全部無秩序かつ無制限な情報拡散と相性が悪い特性ですよね。なのでクソリプみたいなものが起こるとしたら、ソーシャルVR内で直接というより、ソーシャルVR内で起きた出来事がマスメディアとかソーシャルメディアとか情報拡散に適したメディアに転載されて広がるという形から発生するんじゃないかという気がします。それは別に現実の事件を起点にした炎上だってそうだし、現実世界とかVR世界とかで面と向かって「お前こういう○○なんだってな」とか言われることはあまりないわけで。そういう意味ではVRSNSという言われ方をすることがありますけど、同じSNSでもツイッターのような公の場というよりは、メッセンジャーアプリやLINEとかに近い使われ方になっているんじゃないかなと思います。LINEのプライベートグループってネット上に無数にあるけれども、一覧で見渡せる場はないので、そこで個別に起きてることを網羅的に知ってる人は当然いないわけですよね。プライベートワールドで起きていることもプライベートワールドは無数にあって、そのなかで色んなことが起きてるけれども、それらは見えないので」
わく 「パブリックとプライベートでいうと、仮にVRサービスの中でそういうクソリプ的なことがあるとしたら、プライベートに人が流入するというよりも、パブリックだけのVRサービスとかじゃないと難しそうですよね。あと情報の拡散がクソリプに必ずしも必要かというとそこまでは僕は思ってなくて。例えば相互フォローになっている高校の同級生がニュースサイトとかバズったツイートに対して延々とクソリプを送っていて、たまに自分のツイートにもクソリプを送ってくるみたいな。僕じゃなくて僕の友達なんですけど、そういう例がリアルにあったりするんですよ。だからクソリプを送る人が身近にいたとしたら、情報の拡散が仮になかったとしてもクソリプ的な現象は起きてしまうんじゃないかという気がするんですよね」
井口 「そういう意味だと個人的に今の日本のVR文化の中に足りてないなと思っているのはLINEのポジションのVRSNSなんですよね。ツイッターとかだと完全に自分の名前を隠してアニメアイコンとかにして自分の素性が知られていない前提で書きたいことを書いていることが多い気がしますけど、LINEとかFacebookメッセンジャーとか、例えばバイト先LINEとかがあったりするわけじゃないですか。その中に入ってる人たちは、仮にハンドルネーム使ってるかもしれないけど、現実のアイデンティティを知ってるわけですよね。現実でお互いを知っている前提でやり取りするためにLINEの場合はスマホアプリを使うし、そういうのを使っている人もアイデンティティは切り分けていて、クラスLINEとかバイト先LINEとかで使っているアイデンティティはハンドルネームでありつつもお互いがリアルアイデンティティを知ってる前提で、一方で同じ人がツイッターのアカウントも持ってるかもしれないけど、そっちに関しては現実と切り離して、容易に本人に繋がらないような使い方をしていることもよくあるわけですよね。VRChatの今の使われ方って、後者のツイッター的なところがすごく多いと思うんですけれども、基本的にリアルの人格を詮索することは当然マナー違反なわけじゃないですか。でもこの先VRによるコミュニケーションとかアバターによるコミュニケーションはリアルアイデンティティを隠したコミュニケーションにしか使っちゃいけないわけじゃないし、むしろどっちにも使われていいはずで、アメリカを見るとリアルアイデンティティを使ってコミュニケーションする前提というのがそれこそFacebookそのものだと思うんですよ。実際Questを使うとFacebookアカウントに繋がるし、FacebookメッセンジャーをQuestの中で使うこともできるし、そのIDをそのまま使ってHorizon Workroomsで同じ部屋で仕事したりとかもできる。アメリカだとFacebookがそれくらい浸透しているからリアルアイデンティティのやりとりはFacebookで、それと切り離したやり取りはVRChatで、とすればいいんだけど、日本人はFacebook使わないので、そこがぽっかり空いている。今はアーリーアダプターばっかりなので、それこそ最初の頃のインターネットとかもハンドルネームで現実の生活ではあまり話せない自分の興味に沿ったものでコミュニティが集まったりとかしていたけれども、だんだん広がるにつれてLINE的なお互いのリアルアイデンティティを知ってる状態のやり取りにも使われるようになってきたという経緯を踏まえると、VRにおけるコミュニケーションも今主にVRChatで使われているような興味ベースで現実のアイデンティティと切り離した方と、現実の知り合いや社会関係の中で使う方の両方できてしかるべきだし、両方使い分けるのが普通だと思うんだけど、後者のサービスがないよなと思います。クソリプの話に戻ってくると、この切り離した方と現実の方がうっかりクロスしてしまうと、そういう文脈を理解してないために失礼な物言いを面と向かってしてしまうというのはあると思います。そのためにもリアルアイデンティティでのインタラクションを切り離しておけるサービスが必要なんじゃないかな」
Karin 「今の話で、弊社のキャスト同士で使っているSlackというのが、そこのぽっかりにぴったりはまるのかなと思っています。ある意味VRChatとかでは契約関係になることが無かったり身内の業務連絡がほとんど必要ないのでそうなっていますけど、うちの場合はうちの会社が各キャストとリアルの名前で身分証を見せて業務委託契約をさせてもらっていて、その前提がある人たちが集まってアバターコミュニケーションだけどある程度お互い信用して同僚として話しているという、それこそバイト先LINEみたいな感じですね。なので多分VRChatでそういうのが今のところぽっかり空いてるのは、VRChatを取り巻く社会にとって必要ない部分だからなんだろうなというのはありますね」
井口 「まだ必要はないですね」
Karin 「例えば今皆さんロールプレイで喫茶店とか色々やってるじゃないですか。もし今後実際にチケットを売ってキャストの皆に分配するとなったら、その時はそういうものも自然発生的に生まれ得るとは思うんですよね。クソリプの話に戻すと、多分狭いコミュニティで公開を前提にしなくてもクソリプってできるとは思うんですけど、VR空間でしゃべっているときの物理的な距離ってあるじゃないですか。近くにいないと声が届かないから基本的に近くにいる人としか話さなくて、そこでもしクソリプ的なのが飛んでくるとしたらそれはただの空気を読めないやつだと思うんですよね。めっちゃ細かいことばっかり指摘してくるみたいな。単にそういう話になると思う」
わく 「プライベートだからこそクソリプ的なのもあるという話を聞いて思ったのが、例えば風俗とかで説教おじさんの話を聞くじゃないですか。事後にこんな仕事長くしちゃだめだよみたいなことを言ってくる人ですね。そういうのもラブホテルが他とは切断されたプライベートな空間だからこそ、誰も見ていないと思って説教しちゃったりとか。だからプライベートでクソリプが起こりにくいというのは、それがお互い仲のいい友人だからという前提がある気がしていて、例えばVR風俗とかでプライベートの空間なんだけれどもお互い知らない人同士が一緒になるシチュエーションが増えてきたらVR説教おじさんみたいな人も出てくるのかなと思いましたね」
Karin 「あり得ますね。まあ説教おじさんみたいな人は、本当に不快感があるのであればお店のシステムとして守れる範疇ではあるので。多分印象に残ったという意味で現役の風俗嬢とかもある意味エピソードとして話すから目立っていると思うんですけど、そういう場面もそんなに長く続くわけじゃないじゃないですか。もしそういう類のもので一番長く続きそうなのは多分すごくネチネチした上司とかになると思います」
わく 「嫌ですねVR給湯室みたいなところでネチネチ言ってくる上司」
Karin 「顔合わせるたびにこの間のあそこ直してあげたよみたいなことを言ってくる」
わく 「ニヤッていうエモートとか流れてくるんですよね」
Karin 「そんなふうに距離感合わないなとか不快だなと感じたらむしろVRだからこそ離れやすいし、長く続きはしないんじゃないかなとは思いますね」
わく 「現実だとミュートとかブロックとかってそれこそ警察沙汰にならないとなかなかできないですけど、VRだとできますもんね」
Karin 「そうですね」
わく 「そういう意味で言うと、現実のハラスメントに近いことも起こるけど、VRだったらまだ現実よりは対処方法があるからマシみたいになりそうですね」
Karin 「あとはちゃんとコミュニティを作っておくというところですかね。リアルでもクソリプみたいなのをいくらでも挟む余地のある隙のある会話をしてる人たちがいたとして、それをおじさん4人くらいが話してたとして、わざわざ「いやそれちょっと女性差別的な話だと思いますよ」とか声を掛けに行かないじゃないですか。もしちょっと聞こえちゃって不快な気持ちになるとかはあるかもしれないけど。VRの中で何人か団子になってしゃべってるみたいな状態にわざわざ首を突っ込みに行く人ってあまりいないと思うんですよ。だからある意味リアルと同じしゃべりかけにくさとかが働くんじゃないかなと」
井口 「VR内でそんなところに突っ込んで余計な口挟むやつがいたら現実でもやるでしょうからね」
わく 「結局VRにしろ現実にしろ、失礼な無敵の人は失礼な無敵の人のままという感じはありそうですね」
Karin 「実際VRでもリアルでもそういう人は見たことあります」
岸上 「これはパブリックの場でのVRの経験で、Rec Roomでもclusterでも両方経験したことなんですけど、イベントに呼ばれて『アルトデウス』の話をしていたんですよね。『東京クロノス』のゲーム内にじゃがいもを切るナイフがあるんですけど、それをRec Roomの人が作って置いてくれていたんですよ。そしたらRec Roomって誰でも入れるので、入ってきた外国人プレイヤーがナイフを持って講演している僕を刺しに来たことがあって(笑)」
わく 「クソリプというかクソスレイヤーじゃないですか」
岸上 「暗殺されてしまったことがありました。パブリック系の講演の場だと色々ありますね。clusterとかだと僕も美少女アバターを使ってたのでめっちゃスカート覗き込んできて色々クソリプみたいなのを送ってくる人がいましたね」
井口 「炎上している人に対していっぱい攻撃的なリプが飛んでくるのってツイッターだとありますけど、空間の場があるソーシャルVRだとそこに不満を持った人がアバターで大挙してやってきてというのはちょっと想像しにくいですよね」
わく 「VRSNSの中で完結する話ではなくて、こいつがVRSNSの中でこんな問題発言をしたぜというのが別のニュースサイトなりで炎上したうえで、それを見た人がわざわざ集まってくるとかはありそう」
井口 「人数上限も今はそこまで大きいわけじゃないですからね」
わく 「今のツイッターみたいに数百とかのクソリプは無いですね。ここまで話してきて、少なくともツイッターよりはましになりそうな感じはします」
Karin 「そういえば以前VRChatのパブリックで友達と遊んでいたらデスクトップモードの外国人に普通に気軽な感じでセクハラされたことがありますね。彼らは匿名でナンパしている感覚だったと思うんですけど、私英語はあまり分からないんですがおそらく卑猥な単語を投げつけまくるような小学生みたいな迷惑行為を受けたことがあって」
井口 「画面の向こうにも人間がいるということをまだ理解してない人だとそういうのもありますよね」
わく 「やっぱりデスクトップモードだとちょっと違うところはあるんですかね」
Karin 「ちょっと感覚が違う人はいそうだなと思いますね。特に最近Steamで流行ってるからちょっと入れてみるかぐらいで、悪い意味でどうでもいい人が来ちゃったりするとそういうところはありますね。こちらのことをゲームキャラだと思っているというか」
わく 「それこそ『東京クロノス』とかもそうなんですけど、VRのゲームって進歩すればするほどゲームの中のキャラクターとVRChatのユーザーの違いみたいなものが薄れていく感じがありますよね。もちろん話せば分かるんだけど、中には言葉を話さないユーザーもいるじゃないですか。そういう人とかを見ていると、本当にゲームのキャラクターみたいだなというふうに感じることがあります。そうなると、画面の向こう側というよりはアバターの中に人間がいるというのをどうやって相手に認識させるかというのがクソリプ防止に重要になりそうですよね」
Karin 「私なんかはVRだと比較的素でしゃべるんですけど、本当にキャラクターみたいな感じの人っているんですよ。噂によるとリアルで会っても本当にアニメキャラのように話しているらしくて、とにかくアバターの見た目も相まって、完全にアニメキャラとしか思えないような言動をする人がいるんですね。そういう人がもし将来的にまったくVR空間上での文脈を共有できていない人に突っつかれたりしたらちょっと大変そうだなとは思いますね。そういうどこのゲームから出てきたんだみたいな人もVRChatには何人かいて、100人に1人くらいそういう逸材がいてしまうんですよね。本当にこの世界に住んでいるという迫力を醸し出してくる人が」
わく 「すごく世界観が作られている人だと逆にセクハラしにくいのかなというのは感じますね。VRChatとかで話してて、どうしても相手が人間だということでひどい言葉を言えなくなるのもそうだし、逆に世界観が固まりすぎている人だと自分と世界観が違うと思っちゃって、そこでクソリプとか投げてもなと感じるのかなと。例えばですけど、完全に魔法少女になりきっている人に政治的なクソリプとか送れないじゃないですか。そうなるとそのユーザーが体現している世界観に通じる言葉じゃないとあまりかけても返信してくれなさそうな雰囲気が出てくるかもしれないですよね」
Karin 「そこでいうと、逆に世界観を持っていれば持っているほど冷や水ぶっかける系のクソリプは機能しそうだなと思っていて。お前痛い恰好してるけど魔法使える訳じゃねえだろ、何ならおじさんか? みたいな」
わく 「そこでいきなり野太い声が出てくるVRスカッとジャパンみたいなの出てきそうですね」
◆子供向けのVRコンテンツについて
井口 「今後大人や青少年向けだけでなく小学生以下の子供向けのVRコンテンツが生まれるとしたらどういうものになるのか、というトピックですが、これはまず年齢制限の問題があるんですよね。今確か PlayStationVRが12歳だったかな?」
Karin 「そうですね」
井口 「Oculusがだいたい13歳なんですがこれにはいくつかの理由があって、一つはそれ未満の年齢だとまだ正しく見えない可能性があるんですね。小さい子供って、右目と左目の間の瞳孔間距離が結構小さいので、ヘッドセットには物理的に調節できる瞳孔間距離の範囲があるんですけど、それよりもさらに瞳孔間距離が小さい場合、正常に見えない状態でずっと使うことになってしまうのでよくないということで対象外になることがある。もう一つは技術的な話で、輻輳調節矛盾といって今のHMDの見え方ってすごく近くに物が来たときに2つにずれて見えるのはあるんですが、ぼやけて見えるという部分を再現できないんですよね。そうやって特に近くに物が来たときの見え方というのが現実での見え方を完全に再現できていないので、そういった状態の視覚入力をまだ目が発達中の子供に対して使っていいものかというのが不明なので使用を控えているというところがあります。ただしバイフォーカルレンズといってピントも動的に調節できるレンズシステムとかも開発が進められていて、そういうのが普及すると少なくとも輻輳調節矛盾についてはクリアできるかもしれない。なのでこの辺についてはまだ技術的なハードルがあります。ただ今のVRに求められるお約束って意外と多くて、バーチャルでリアリティだから現実みたいな体験ができるかというと、ある程度はそうなんだけども、例えば目の前に広大な空間が広がっているからと言って、「壁にぶつかるから走るな」とか「無遠慮に腕を振り回すな」とか、ある程度使っていれば当然のように学習して現実に部屋があるというのを意識の片隅に置くからやらなくなるんですけれど、まったく頭にそれが入ってない人は、すごい勢いで走っていって怪我したりするんですよね。なのでどっちかというと子供向けだとまずはARじゃないかなという気がしています。それこそ『電脳コイル』みたいな。これは特に小学校入学前くらいまで下げると言葉が通じないことがあり得るので、そういうのを気にしなきゃいけなくなる。それでVRの場合は少なくとも親と一緒に入ることができる必要があるだろうと思います。今は例えば子供だけがVRをやってたら外から見ても何をやっているか分からないし、逆に子供が家の中を歩き回っている状態で親がVRを使うにしても、子供が何をやっているか見えなくなるから安心して入れないんですよね。なのでどっちかというとARじゃないかなという気がします。さらに13歳制限についてですが、Nintendo DSとか3DSだと7歳なんですよ。なぜ7歳と13歳で差が出ているのかというと、これはアメリカのCOPPA(児童オンラインプライバシー保護法)という法律があるんですが、これは13歳未満の子供の個人情報をサーバに保存したりする際にものすごく色んな制限が追加でかかるという法律で、NintendoとかSonyとかはそのガチガチな制約に手間暇かけて準拠することによってオンラインのアカウントを子供でも作れるようにしていますけど、Facebookとかは少なくとも今は対応していない。だから13歳というのはどっちかというとHMDを健康に使える年齢というよりも、Facebookのサービスを使える年齢なんですよ。Facebookはただ単にHMDを売るというだけではなくてオンラインサービスもセットで使って欲しいというところがあるから、Facebook本体がどうにかならないことには当分13歳制限はどうにかならないだろうなと。これはValveとSteamとかでも同じような話だし、さらにVR機器やコンテンツを作っている多くの会社がアメリカの会社であり、そうでなくてもアメリカでサービスする上で影響を受ける以上はなかなか難しそうです」
わく 「そうなるとやっぱり子供向けのVR自体がなかなか難しくて、やっぱりARとかじゃないと」
井口 「そうですね。ひとつ思い出したのがTeen Second Lifeというのが一時期あったんですよ。13歳から17歳のみが入れるSecond Lifeの別サーバで、僕は行ったことないですけれども、Second Life本体がアダルトサービスとかもできる場だからそうやって隔離されてるのかなと思います」
Karin 「そうですね」
井口 「Karinさんそのへん詳しいですか」
Karin 「アダルトエリアは自己申告制で、もちろんゲーム内で物理的にゾーニングはされているのと、18歳以上でアダルトな物を表示するというチェックをクライアントで明示的にやらないといけなくなっているんですが、ぶっちゃけ入れようと思えば入れられちゃうので、あえて分けることに意味があったんでしょうねきっと」
井口 「逆に大人が入っちゃいけないと、どんな世界だったんだろうなというのは気になりますね。子供しかいない独自の世界ってどんな文化だったんだろう。それこそ上限を超えるところで会えなくなった友達同士とかいたのかな」
わく 「それいいですね……」
井口 「年齢差があったら先に上限を超える人と後からの人がいますよね」
Karin 「卒業式ですよね」
わく 「そうか、別に学年単位とかではなくて年齢ですもんね。だから例えば4月生まれと10月生まれだと違ってきてしまうという。そうなると3月までの人がその学年で言うと一番長く17歳だから、そこで早生まれとか遅生まれみたいな感じでその学年として体験できる期間みたいなのが違ってくる」
井口 「なんかそれで一本話書けそうですよね」
わく 「いい話ですね」
井口 「それはさておき、COPPAやら輻輳調節矛盾やら色々あるので、小学生以下っていうのがそもそも当分は難しいんじゃないかなとは思います。やっぱり中学生くらいからのものになるのかな。逆に小学校の間ずっとVR世界でこんなことがあったというのを散々話だけ聞かされて、いざ満を持して13歳になってさあ使おうというのもなんか一大イベントになりそうですよね。実際のところはちょっとずるして先に使っちゃったりするだろうけど」
わく 「すごく卑近な例えになるんですけど、18歳になった瞬間にTSUTAYAでAVを借りに行くのにちょっと近い気がしますね。なんとなく儀式感があって、13歳になった瞬間にVRに行くみたいな」
Karin 「そうなるとこのトピックの意図としては技術的なことを一度置いておいて、小学生以下の子供向けに見せたいものや作りたいものというイメージの話になりますかね。私は結構子供向けに作っておきたいなと思うものがあって、要は自分自身のアバターを好きに選べるアバターコミュニケーションの世界というのを一度見せておきたいなと思うんですよ。言ってしまえばリアルであってもアイデンティティと中にいる人間にそこまで関連性はないんだよというのと、あなたが目指すアイデンティティがこの中にあるかもしれないというのをなんとなくでもVRという自分自身が実感できる形で示しておきたいなと思っています。今私が作っているX-OASISの全年齢版を作ろうという話は動いてるんですけど、それもやっぱり少し低い年齢の人たちにも性的なものだけではなくて個々人の持っているジェンダーを含めたアイデンティティの話を気軽に体験できたり私たちみたいなある種の当事者と話せるような場所を作っておくことは意味があるのかなと思っていて。普通にサービスとしては言ってしまえばキャバクラみたいな楽しい場所として作っていくと思うんですが、そういう使われ方もしてほしいなと思っています」
わく 「ジェンダーの話もそうですし、もうちょっと広げるとなりたい自分像みたいなのをVRでアバターとしてまとうことによって実際だったらこんな感じなのかなというのをイメージして、そこと現実の自分との距離感を探っていくような試行錯誤が仮想空間で出来るといいですよね」
Karin 「自分自身や周りとの関わりを色々試してみるということができるじゃないですか。それを体験することができたかどうかって、逆に物心がつく前だからこそ心の栄養になりそうだなと思うんですよね」
わく 「どうせ自分はこういうものにしかなれないという思い込みみたいなものを修正できるというか、そういう体験になるといいですよね」
Karin 「私はそういう未来予想というかイメージを子供向けのVRに持っています」
わく 「僕も結構近いイメージがあります。やっぱり子供って基本的に世界観がものすごく狭いと思うんですよね。例えば今だったら普通に電車に乗って県をまたいで移動できるんだけども、自分が小学生くらいの頃だと一駅隣の駅に行くだけでもビッグイベントみたいな。自分が住んでる街、もっというと学校と家の通学路の範囲だとかそこだけで世界が完結しちゃうというのがあって、それをどうにかしてVRを使ってもうちょっと違うこともあるよというのを提示できないかなと。もちろんそれはジェンダーの話もそうだし、もしくは違う国に生まれていたらどうなったんだろうとか、なりたい職業とか。例えば僕の周りだと古生物学者になりたいって人がいたんですけど、実際にはどんなお仕事をやるのかというお仕事体験でもいいし、そうやって自分の未来像をポジティブな方向に調整していくツールとしてVRが使えたら結構いいよなと思いますね」
Karin 「キッザニアみたいな」
わく 「そうですね。キッザニアも行ったことはないんですけど、キッザニア+アバターとかだったらかなり違いそうですよね」
◆VRのライフログと感傷について
わく 「じゃあ次は最後のトピック、VRのライフログと感傷について。割と今まで話したアーカイブとかの話と被るなと思うんですけど、VRChatの時々の会話や映像はすべて保存されているわけではないというのがあって、昔一緒に遊んだワールドに久しぶりに行って、あの頃みんなとよくこのワールドに来たなという思い出に浸ることができる、アーカイブされたその時の映像だというわけではなくて、当時仲良かった人とかも別にいないですし、ちょっと久しぶりにワールドに来て、自分の思い出の中にアーカイブされたようなワールドに浸るみたいな感じになると思うんですね。ただもしライフログみたいな感じでそのワールド単位で会話や映像を記録するのが当たり前になって、後から自分を含めたそのときのユーザー同士の会話を再現して追体験できるようになったらどうなるのかなと思うんですね。それって例えばマリオカートのゴーストみたいなもので、マリオカートでコースを走ったときに自分が今までで一番早く走った記録がゴーストという形で保存されて、それを追いかけて走るというシステムがあるじゃないですか。それと同じような感じで過去に自分がどんな人たちとどんな会話をしたのかを自分を含めて再現したとしたら、それはマリオカートのゴーストみたいになるのかなと思うんですね。そしてそれは少しグロテスクに感じるものではあるんだけど、過去の思い出に浸るってことって、そのときの体験を再現できないから頭の中で再現するしかないという部分もあって。それが実際VRで再現できるようになると、思い出に浸るという行為自体がかなり変わってくるのかもしれないなという気がするんですよね。それがVRと感傷というのを考える上では今後重要な部分になるのかなという気がします。それでは岸上さんどうですか」
岸上 「これについて思うのが、ニコニコ動画のコメントがある意味エセリアルタイムな体験じゃないですか。本当はリアルタイムの動画のはずなんだけど非同期で皆がエセリアルタイムで一体感を感じるというニュアンスがアーカイブされることになるのかなと。clusterの加藤直人さんが昔そういうことを言っていた気がするんですよね。あと追体験がどの程度できるかにもよると思うんですけど、clusterは一時期こういうことができたんですよね」
Karin 「できましたね。あれってなくなっちゃったんですか」
岸上 「なくなっちゃったんですよ。先述したようにアップデートしていくと追いつかなくなるからという理由で。なんだか不思議な気分でしたけどね、当時の空間に自分が紛れ込んでいるような」
わく 「それって自分を含めて再現している感じなんですね」
岸上 「そうですね。なので過去に紛れ込んでいるみたいな雰囲気で、結構独特の感じでしたね。Karinさんどうでした? なんて表現すればいいかと今思い出してるんですけど」
Karin 「実はやったことないですね。でも過去に紛れ込んで、世界に今の自分自身だけが無視されるわけじゃないですか。相当むずがゆそうだなと思いますね。私は正直やりたくないかも」
岸上 「クレヨンしんちゃんのオトナ帝国の逆襲くらい子供が無視されてる」
わく 「それ怖いですね。ちょっとホラーというか」
岸上 「なんかそんな気がしましたね」
わく 「ちょっと話がずれるんですけど、当時の思い出を追体験しているつもりで自分も含めた過去の友達の会話をずっと聞いていて、ふと気が付いたらその場にいる人全員がこっちをなぜかじーっと見ていたりとかしたらすごく怖い気がしますよね」
岸上 「そういうVR映えするトリック的なもの出来そうですね」
わく 「絶対そういうワールド行きたくないですけどね」
岸上 「過去だと思ってたのにみたいな」
井口 「そのclusterで記録して追体験したイベントはどんな場でした?」
岸上 「あれは何かのイベントだったかな、東京クロノスかそれよりさらに前くらいでしたね」
井口 「clusterはイベントを開催するのに適してますからね。この点に関してはどういうものをキャプチャするかにもよる気はしていて、イベントの記録だと基本リッチだけど録画されたYouTubeの公演記録を観ているのとそんなに変わらない気はするけど、極めてパーソナルなもの、例えばVR内で誰かに告白してそのときの記録をもし自分が撮っていたとしたら何度も観ちゃったりしそうな気もします」
わく 「未来の感傷マゾですね」
井口 「そういう極めてパーソナルな記録は、特に現在との関係性において、例えばその人ともう別れてしまったりとかその人がもう死んでしまったりした場合なんかは何度も何度も見てそこから出てこない人とかいそうな気がしますね」
わく 「『ブレードランナー2049』で確かデッカードが最初にいた砂漠の中の建物でVRで再現されたエルビスプレスリーのすごく古いライブ映像を流している酒場のシーンがあったんですけど、そんな感じでプライベートな体験や自分の好きだった歌手のライブとかもそうかもしれないですけど、自分の人生の中でこの時代良かったなと感じる過去を再現してそこに引きこもる人が出てきてもおかしくないですよね」
井口 「例えば『秒速5センチメートル』の第二部の貴樹って、第一部ラストのあかりと一晩一緒に過ごしたところとかをずっと反芻し続けてるのかなという気がすごくするわけですけれども、例えば第一部の最後のあかりと過ごした一晩を丸ごと記録に残していたらずっと見てるんじゃないかな」
わく 「すごく分かります。頭の中で再現しているのをVRの中でやってるってことですよね。VRが無かったとしても自分の頭の中で過去の思い出とかを再現して反芻するという」
井口 「それ自体は普通にあることだけど、そのときの空間そのものに戻れるんだったらもっとのめり込んでしまいそうですね」
わく 「例えば20代の頃に付き合ってた子とか、もしかしてあの時こうしていればもうちょっと長く付き合えたんじゃないかとちょっと考えたりみたいなのはありますね。でも過去の記憶を頭の中で何度も反芻するときに、それに対して手を加えることはなかなかないじゃないですか。でもさっきの例えでいうと、マリオカートのゴーストって別にその時々のベストではあるんだけれども、ゴーストを操作しているキャラクターが追い抜いたとしたら、今度はそれが別のゴーストになる。そんな感じで過去の体験や何度も反芻してしまう思い出というのをVRで再現したときに、単に過去のものをVRの中で再現したというだけじゃなくて、そこにゲーム性みたいなものがあって実はこの時こうしていればもうちょっとうまくいったかもしれないみたいなのがあるといいですね。もちろんその体験自体は過去だから、過去は書き換えることができないんだけど、現在の視点からしてその過去の出来事にどう向き合うのかという向き合い方という意味では結構変わっていくんじゃないかなという気はします。そういう点で意味のある事なのかなと」
井口 「それこそ過去の再現なんだけれども、その場にいる人が全員GPT-3みたいなAIで動いていて、あの時行動したらどうなっただろうみたいなのを体験できるようになってたらやばいな」
Karin 「暴露療法みたいですね」
井口 「ループものみたいになっちゃうな。ダメだ何度やり直してもあいつと付き合えないみたいな」
わく 「仮にそれが告白の体験で、なんとかうまくいって相手からOKが来た瞬間に結局それも過去を再現したものでしかないからその先はありませんとなったら怖いですね。過去の告白を再現したワールドで当時とは違う選択肢をとってその子と付き合えるようになったとして、付き合えた先まで保存できる容量があったらいいんだけど、告白が成功した瞬間にアーカイブの容量が限界に達してしまったりしたらHMD投げ捨てそうな気がします」
Karin 「そういう意味では過去を振り返るというのに人が関わってくるともう本来の自分が自分のために昔を振り返りたいという趣旨とずれてくるというか、何ならノイズな気がするんですよね。人がいると自分がその時空間の同じところにいないというのが浮き彫りになってしまう。昔おばあちゃんが住んでいた家ってある種のノスタルジーがあったりするじゃないですか。そんな感じで生活感さえあればもしかしてそこって誤魔化せるのかなとは思っていて。バーチャルキャストさんのルーム機能とかですかね。一応うちも実装しようとしてるんですけど、本当にリアルタイムに時間が過ぎていて、誰かが入ってきてものを動かしたら、例えば机からカウンターに調味料の棚を移したら、その棚は次誰かが見に来たときには最初からそこにあるみたいな。そうやって物が動いてリアルな生活感が出てくるというのがVRに浸透してくると、無理してアーカイブしようとしなくても思い出みたいなものが出来たりするのかな」
わく 「例えば取り壊しが決定したおばあちゃんの家に大人になってから行ったときに、自分の身長や父親の身長が刻まれた柱とかを見て過去の思い出に浸っているときにARおばあちゃんが必要かどうか問題みたいな。確かにそこはちょっと台無し感ありますね。そういうARやVRで当時の人が再現されないからこそいいというのと、逆に過去をどうしても反芻してしまってその過去に対して自分の中で一旦消化しないと人生を前に進められないような人に対するVR療法というか、過去に向き合うという意味での感傷とはちょっとそこで分離していくのかもしれないですね。例えば『秒速5センチメートル』の貴樹が第二話で種子島の高校にいるはずなのに小学校時代のあかりのことをずっと考えているというのと、さっき話した取り壊し寸前のおばあちゃんの家に行ったときの感傷って、傍から見るとそんなに変わらないんだけど、VRで見るとその目的の違いが明確になってくるのかもしれない。確かにそれは言われて気付いたというか、ARおばあちゃんはノイズですよね」
わく 「でも逆に消し過ぎることも怖いですね。当時はおばあちゃんがその家に住んでいたんだけど今思い出に浸るときにはおばあちゃんはいない方がいい、逆に当時いる人の中でもこの人はいてほしいんだけどこの人はいてほしくないみたいな、その方が感傷に浸る上では都合がいいみたいな感じで、スターリン・サービスというか都合が悪い人はどんどん消すみたいなのも出てくるかもしれないですね」
岸上 「DR (Diminished Reality) ですね」
Karin 「4人のバンドの中の一人が犯罪を犯しちゃってアーカイブからその人だけ消されるとか」
わく 「SMAP幻の5人目みたいな感じですね」
Karin 「それってもはや現実改変じゃないですか。映像だと切り取った跡ってまだわかったりするかもしれないけど、空間でそれをやられると元からこんなだっけなとなりそうで」
岸上 「みんなから忘れ去られている世界みたいな。そして自分だけがその違和感に気づいている」
わく 「怪談ものの定番ですね。テーブルの上に一人分余計にご飯とか定食が配られて、今日来てるのは4人のはずなのにみたいな。自分の中の記憶でも割と取捨選択しているというか、その当時の風景を完全にアーカイブしているかというと人間の脳って別にそういうわけじゃないじゃないですか。結構記憶は改変されて都合のいい記憶になっていたりであるとか、もしくは子供のころの記憶だったら親に言われたことを元にして偽の記憶を作り出すみたいな。3歳の頃に猫のぬいぐるみを親に買ってもらったんですけど、親から○○のデパートで買ったんだよと言われて、その猫のぬいぐるみを親が買ったときの記憶ってあるんですよ。ただその記憶ってFPSじゃなくてTPSみたいな感じで、自分自身を俯瞰視点でとらえている記憶だから明らかに偽の記憶なんですよね。そんな感じで記憶の中で都合がよくないものとか不要なものって消されちゃったりして、でもそれって記憶だからなんとなく受け入れているけど、VRでそれをやると消された側のアバターの中にもかつて人がいたんじゃないかと考えてちょっとグロテスクな感じがしますね。さっきのマリオカートの話とかゴーストの話もそうなんですけど、あのときこうしていればよかったみたいに頭の中で反芻してしまう記憶があったときに、それについてまた別の答えを出すことで過去の体験を自分の中で上手く消化できるようになるという療法としての仮想の感傷ってやっぱり出てきてほしいなと思いましたね」
Karin 「話が前のトピックに戻るんですけど、昔あったけどもう行けないワールドの話をちょうどこの間VRChatの中でしましたね。ファンタジー集会場という2017年からVRChatをやっている人たちは知っているワールドがあったんですけど、人が集まってるところに行きたいけどファンタジー集会場みたいなワールドってないのかなという話をしたら急に懐かしくなってきちゃって、その場に座り込んで感傷に浸り始めるということがあって。やっぱりそのときのコミュニティの雰囲気とかも含めてこういうのないのかなって話をしていました」
岸上 「もう閉店しちゃった学生時代に行ってたラーメン屋みたいな」
Karin 「そういう感じですね」
わく 「「あそこの卵チャーハン安いんだけど味もしなかったよな」みたいな話とか」
岸上 「皆の共通体験があるんですけど、もうできないからずっと幻影を見てるんですよね」
Karin 「わざわざそれを自分たちで再現したいかというとそこまでではないみたいな」
わく 「結局出来上がるのは味のないチャーハンだけ」
Karin 「本当に感傷に浸れさえすればそれでいいくらいの情報なんですよねきっと」
わく 「そういうのは再現したいかというと別にそうではない。やっぱりその二つ分けたいですね。でもだいたいの記憶ってそういうものかもしれない。別に再現するほどじゃないみたいな」
わく 「基本的に過去を感傷するとか思い出に浸ることってすごく気持ちいいことではあるんだけれども、コミュニティとしてはそれを共有しているコミュニティの中で閉鎖的になってしまったりだとか、「昔は良かったけど今は……」みたいな人ってだいたい嫌われちゃうじゃないですか。もちろん再現しなくてもいい過去もあるよなと思いつつ、仮にそれしか話さない人がいたとしたらむしろそれを再現することによって視点を過去じゃなくて現在とか未来の方に向けられないかなという気もするんですよね。そっちの方がポジティブだよなと」
わく 「とりあえずこんな感じですかね。4時間くらいですね、すごい。じゃあ最後にそれぞれ一言何かあれば」
Karin 「今日は色んな見地から色んな刺激が入ってきて私もそれに答える形でたくさんしゃべって、ちょっとしゃべりすぎちゃったかもしれないですけど、楽しくお話させていただきました。ありがとうございます」
わく 「ありがとうございます」
岸上 「本日はありがとうございました。とても楽しくいろんなことを伺えて、話せて、楽しかったです。まさにこういう体験が感傷の一つなんだなと思いました。また5年後に復刻版の感傷マゾ企画がもしあればあのときはZoomだったねとかいいながらできればいいなと思っています」
わく 「帰ってきた感傷マゾ」
井口 「それいいですね」
わく 「ありがとうございました。では最後に井口さんどうですか」
井口 「そういえばわくさんって何歳でしたっけ」
わく 「僕は38ですね」
井口 「じゃあ同い年か。僕も38ですけど、だんだん体感時間が速くなってくると、新しい、面白いと思っていたものが気が付けば懐かしさの対象になっていて、それこそVRにのめり込みだしたのも最近のことだと思っていたんですけど全然最近ではなくて、10年近く経っていて。これから先も色んなものに触れて新しい面白いって一瞬思ってそして気が付いたらそれがまた遠い昔のことになっている。まあ年取るってそういうことなんだろうけれども、なるべく前を向きたいですね。遠ざかっていく後ろばかりじゃなくてなるべく前を向きたいけれども、とはいえまったく後ろ向かないのもあれなので、健全な範囲で程よく回顧したいなと」
わく 「そうですよね。未来か過去か、あるいは現在か過去かの二者択一よりもそれぞれ良いところはあるので、最終的には前を向きたいですね。このトピックで仮想感傷の療法みたいな話もありましたけど、過去を振り返るという行為自体を何か前を向く方向に繋げられないかなと。過去ばかり見るのって割とネガティブとか後ろ向きな評価をされるんだけど、それだけじゃないんじゃないかという可能性を考えてみたかったというのもあるんですよね」
わく 「僕もVRにすごく興味があるんですけど、おじさんみたいな発言になっちゃうんですが、最近VRのHMD被った状態で立ち上がるとまず最初に肩こりが酷いんですよね。HMDを頭に被ると被ってないとき以上に肩が凝ってる感じがしちゃって。バ美肉で美少女になるのにまず自分がおじさんであることを自覚しないといけない、その段階が辛すぎてなかなか以前よりもVRChatに行かなくなってしまったのもありますね。やっぱり今回皆さんとお話してやっぱりVR面白いなと思ったし、さっきの過去を振り返るという話やKarinさんのアバターのお話のように、あり得たかもしれないものをデザインできるというのはVRの良さとしてあるんじゃないかなという気がします。それにアバターだったら自分がまとうことによって自分の理想像に近づく方向性を見出せるというのが良いなと思うので。やっぱり僕もツイッターでどうせおじさんだからさ〜みたいな自虐的なツイートをするんじゃなくて、たまにはバ美肉して前を向かないとなと思いました」
わく 「とりあえず、今日はこんな感じで。すごく楽しかったです。では、今日はどうもありがとうございました」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
