
【試し読み】高柳聡子「チェルビナ・デ・ガブリアック 二つの魂を生きた詩人」(『埃だらけのすももを売ればよい ロシア銀の時代の女性詩人たち』より)

『埃だらけのすももを売ればよい ロシア銀の時代の女性詩人たち』
高柳聡子
四六判、上製、184ページ 定価:本体2,000円+税
ISBN978-4-86385-604-2 C0095 装幀 名久井直子 2024年2月下旬発売
詩集とはある世界観の具現であった
ロシア文学におとずれた興隆期「銀の時代」(1890~1920年代)。ペテルブルクの古書店で偶然見つけた詩集を手がかりに、100年前の忘れられた15人の女性詩人たちのことばを拾い上げる。『女の子たちと公的機関』が増刷を重ねる著者による「web侃づめ」の好評連載が書き下ろしを加えて書籍化!
チェルビナ・デ・ガブリアック 二つの魂を生きた詩人
今回は同時期に生きた二人の女性詩人を紹介してみようと思う。
まず一人目は、チェルビナ・デ・ガブリアック(1877-?)。20世紀初頭のロシア文学界で大センセーションを巻き起こした著名な詩人。ぺテルブルクでヴァチェスラフ・イワーノフが主催するシンボリストたちのサークル「塔」へ参加し(ここはイワーノフのお眼鏡に適った者しか出入りできなかった)、アンナ・アフマートワの夫で詩人のニコライ・グミリョフが率いていた雑誌『アポロン』で紹介されるやいなや、そのエキゾチックな名と不遇な境遇、真の姿がわからぬがゆえの神秘性、さらに、深い悲しみのヴェールをまとったような深淵な詩で読者を瞬く間に魅了した。
もう一人は、エリザヴェータ・ドミートリエワ(1887-1927)。ぺテルブルクの貧しい貴族の家に生まれ、幼くして父を肺病で亡くし、自身も肺や骨の結核に苦しみながら子供時代を過ごした人。大人になってからも病の後遺症が残り、いつも足を引き摺って歩いていたという。それでも、女子教育大で学び、ロシア文学の教師として働きながら詩作を行った人。ドミートリエワは、チェルビナ・デ・ガブリアックよりも早くから『アポロン』に詩を送っていたが、編集担当だったセルゲイ・マコフスキイは、足を引き摺って歩く、この冴えない女性詩人の作品に目もくれなかった。

1781年に死んだ女へ チェルビナ・デ・ガブリアック
私のなかには他人の夢が棲んでいる
死んだ若い女の夢が
そして磔にされた者の貌が 狂気で脅しながら
十字架の上から見つめている
黒ずんだ唇は憤怒している
彼は忘れてはいない、似たような顔だちに
鉛よりも重き欲情の痕と
ナザレの男の子(おのこ)への
果てなき怖れと衝動を
どこかで見たことがあることを
私の声は 彼女の愛の残り火を隠しつつも
炎のごとく歌っている
私の眼のなかで 彼女は燃え盛り
狂気の旗を受けとるのを待っている
その罪の最後の賜物を
(1909)
チェルビナ・デ・ガブリアックの詩「1781年に死んだ女へ」は、1909年の『アポロン』第2号に、他の詩作品とはやや異なる形で掲載された。クリミア在住の詩人・批評家のマクシミリアン・ヴォローシンによる「チェルビナ・デ・ガブリアックのホロスコープ」という小論のなかで引用のように彼女のいくつかの詩が紹介されたのである。異国の名をもつこの無名の詩人は、ヴォローシンの言葉に優しく抱かれた、生まれたばかりの赤ん坊のようにペテルブルクの文壇にお目見えしたのだった。
いまわれわれは新しい詩人の揺りかごのそばにいる。これはロシア詩における捨て子だ。誰の仕業かわからないが、柳行李がアポロンのポーチに置かれていたのだ。赤ん坊は、「Sin miedo(恐れずに)」(*スペイン語)というトレドの銘が書かれた繻子の刺繍の紋章入りの薄いバチストの産着にくるまれていた。枕元にはサトゥルヌス(*ローマ神話の農耕の神)に捧げるヒースの枝と、「ヴィーナスの涙」と呼ばれているシダの束が置いてあった。黒い断裁面のあるメモには、急いで書かれたとおぼしき細い女性の筆跡で、「Cherubina de Gabriack. 1877. Catholique(チェルビナ・デ・ガブリアック、1877. カトリック)」と書かれていた。
アポロンは新しい詩人を養子に迎えようとしている。

ヴォローシンのほかに、この異国の詩人を知る者はなかった。古代ギリシャのアポロンの神殿のポーチに捨て置かれていた赤ん坊とは、いうまでもなく『アポロン』誌に拾われた新しい詩人の比喩である。さらにヴォローシンは、この子の揺りかごの上の空では、美と愛を物語る金星(ヴィーナス)と、宿命的な悲しみを示す土星(サトゥルヌス)がひとつになり、魅惑的な情熱と悲劇をあわせもつ星の下に生まれた子であると言い添えている。編集人のマコフスキイのもとに届く手紙には差出人の住所は記されてなく、その存在すら疑わしかったのだが、一度電話で会話する機会を経て、ようやく実在の人物だと信用されるにいたった。
この時すでに32歳だったはずのチェルビナは、非常に敬虔なカトリック教徒の家に生まれた。父はスペイン人で、母はロシア人。修道院で教育を受け、厳格な父は毎日欠かさずその日の出来事を娘に報告させていたのだという。その不自由な生活のなかでチェルビナが外の世界と交流する手立ては文通しかなかった。
新しい詩人をめぐるこうした神話性に満ちた紹介は大いに功を奏し、チェルビナ・デ・ガブリアックはたちまち時の人となる。『アポロン』のその後の号には、チェルビナの詩が13篇も掲載されている。彼女の詩は、まるで傲慢な古代の女の魂が詩人の身体を乗っ取り、人知れず潰えた自分の宿命を代筆させようとしているかのようにもみえる。ギッピウスの詩行と同じく、ここでもまた、「ナザレの男の子(おのこ)」への冒涜的、かつ犯罪的な愛が大胆に告白されている。けれども、修道女のように育てられたチェルビナの内には、ギッピウスとは異質の神への激しい愛が燃えていた。
しかしその後、詩人のミハイル・クズミンが、チェルビナの電話番号が、自分たちの仲間のひとりであるエリザヴェータ・ドミートリエワのものと同じであることを突き止める。すでにチェルビナを(会ったこともないというのに)真剣に愛していたマコフスキイは、なかなか信じようとせず、しかし、やがてそれが真実であることを認めざるをえなくなった。その際のドミートリエワに対する彼の落胆の言葉は罵倒にひとしく、あまりにもひどく身勝手で、ここで繰り返す気にもならないほど悪意に満ちたものだった(彼はただ美しい詩人の幻影を愛していたというだけではないか)。
チェルビナ・デ・ガブリアックという詩人は、ドミートリエワがクリミアのコクテベリにあるヴォローシンの家を訪ねた際に二人で考案した架空の詩人だった。ドミートリエワは大学で中世史や中世フランス文学を学び、フランス語とスペイン語ができたため、彼女の教養と詩才にエキゾチックな西洋の女性の仮面をつけて文壇へ送り出そうということになったのだった(そうしなければ、これらの詩はマコフスキイに受け入れられなかっただろう)。二人によるこのミスティフィケーションの試みは、詩人を世に出すという意味では大成功を収めたが、結果として周囲の大きな失望を生むことになった。
こうして、アポロンの捨て子として拾われた魅惑に満ちた女性は、偽りの名を奪われ、エリザヴェータ・ドミートリエワというロシアの詩人に戻っていく。いったい、詩人とは誰のことなのか? 詩人の身体や名や生い立ちは、確かに、その創作と分かちがたくある。けれどもそれは、誰のためのものなのか? 読者や編集人の熱情のためなのか? 作品の雰囲気に「見合った」魅力をもたぬと責められる女性詩人の才能は、いかにして発揮すればよいというのか?
正体が明かされると、ドミートリエワにはありとあらゆる批判が降り注ぎ、彼女の心はぼろぼろに傷ついてしまった。さらに、ヴォローシンと、かつての恋人ニコライ・グミリョフがドミートリエワをめぐって決闘するというスキャンダルまで起き、以後、彼女は長く口をつぐむことになる。
そうした雰囲気のなかでドミートリエワの日々が心穏やかであったとは想像しがたい。常に消えぬ彼女の魂の懊悩は、その創作のなかにはっきりと見てとれる。ここでは彼女の鏡詩篇(と私が勝手に呼んでいるもの)の一篇をご紹介しよう(ドミートリエワの詩には〈鏡〉がよく登場する)。この詩は創作年がはっきりしないのだが、チェルビナ・デ・ガブリアックの誕生直前に書かれたものではないかと思われる。
・・・
鏡のなかを見よ
見るのだ、目をそらさずに
そこに おまえの顔はなく
そこには、鏡のなかには 生きた
もうひとりのおまえがいる
……黙っていろ、喋るな……
見ろ、見るのだ、悪意と恐怖のかけらが
きらめく嘘が
おまえの姿を塵から創り出したのだ
そうしておまえは生きているのだ
そうしておまえは生きている、動かずに聴け
あちらがわ、鏡のなかの、その底には
水中庭園、真珠の花たち……
ああ、うしろを見るのじゃない
ここでは おまえの日々は虚しく
ここでは おまえのものはすべて壊されるだろう
おまえは 鏡のなかで生きてゆけ
ここにあるのは嘘ばかり、ここにあるのは
肉体の幻影ばかり
束の間 噴水のダイヤモンドに火をつけるのは
偶然の光の条……
愛 ――ここには 愛などない
自分を苛むのじゃない、苛むな
目をそらさずに 見るのだ
おまえは鏡のなかで 生きているのだ
ここではなく……
ドミートリエワは、わずか一年足らずのガブリアック時代にも、それ以降にも〈鏡〉をモチーフにした詩をたびたび執筆しているが、どの作品においても、〈おまえ〉(時には〈彼女〉)と〈私〉が鏡のあちら側とこちら側にいて互いを見つめている。一人の人物の実体と鏡像による視線の交差の様子は複雑に表現されているが、一貫しているのは、こちら側にいる実在の自分ではなく、〈鏡〉のなかの〈きらめく嘘〉が〈塵〉から創りだした〈おまえ〉に存在の権利を与えんとする意思である。
彼女の詩に通底している、別の誰かの魂が生きていること、そして、自分は流浪の身であり定住先などないという意識は、〈鏡〉のこちら側=いま・ここにいる自分の生を真の存在としない。それは、あくまでも魂の生を希求するという詩人の自分自身への態度のせいかもしれない。だとすれば、囚われの身にありながら魂だけで神を激しく愛し、その深い精神的な深淵を詩に綴ったチェルビナ・デ・ガブリアックという女性を、エリザヴェータ・ドミートリエワといかにして分かつことができるのかという疑問に答えられる者が果たしているのだろうか。
1911年、ドミートリエワは、土地改良技術者のフセヴォロド・ヴァシーリエフと結婚し、夫の姓に変更した。エリザヴェータ・ヴァシーリエワとなった詩人はカザフスタンに移り、そこで神智学に没頭するようになる。数年後には詩作も再開するのだが、より宗教的で、詩人自身の精神の求道を反映する作品となっている。そもそもその創作の初期から見られた、生と死、身体と精神、存在といった問題をめぐる思索の継続でもあり、彼女の詩が哲学的と言われる所以でもある。
ロシア革命後の1921年、貴族の出自をもつ彼女は夫とともに逮捕され、ペトログラード(現在のペテルブルク)から追放される。その後、自由の身となるも、1926年頃からは神智学に対する弾圧も始まって、1927年には再び逮捕され、ウズベキスタンの首都タシケントへ三年間の流刑となった。
そうした慌ただしい移動の中で、エリザヴェータの生活はあまり安定したものではなかっただろうと思われるが、どこにいようとも常になにかしら文学に携わっていた。地方都市で子ども向けの芝居を書いたり、スペイン語やフランス語の翻訳を手掛けたり。はたまたタシケントでは、Ли Сян Цзы(勝手に想像で李湘子という漢字をあててみた)という中国人の筆名を用いて詩を書いてもいる。
このエピソードには、チェルビナ・デ・ガブリアックのときと同じく「共犯者」がいる、エリザヴェータが晩年親しくしていた東洋学者のユリアン・シチュツキイだ。エリザヴェータの身を護るためでもあっただろうが、二人は、「人間の魂の不死を信じたがゆえに異国へ流刑となった中国の思想家」という人物像を創りだし、この東洋の詩人に「梨木の下」という七行詩シリーズを書かせている。クリミアでヴォローシンとたくらんだミスティフィケーションといい、エリザヴェータという人は、自分の中のもうひとりの詩人を具現化することによほどの愛着があるようだ。だが具現化といっても、その姿は詩という形式におさまる言葉だけの存在である。しかし、実体が鏡像に存在の権利を譲渡するかのような彼女の鏡詩篇を思いだせば、詩となって姿を見せる中国の詩人もまた、エリザヴェータと分かつことのできぬ人だ。
(ガブリアック、ヴァシーリエワ時代含め)ドミートリエワの詩をすべて収集し、彼女の書簡から、この詩人の伝記を執筆したのは伝記作家のエヴゲーニイ・アルヒッポフだ。1926年秋に彼に宛てた私信のなかでエリザヴェータは、「『告白』は、私が生きているうちは誰にも見せないください、死後はどうでもかまいません」と前置きしてから、自分の人生を振り返っている。この手紙には、彼女のとても素直でシンプルな思いが告白されている。
私にとってこの世界では常に二つのものがいちばん聖なるものでした。それは、詩と愛です。
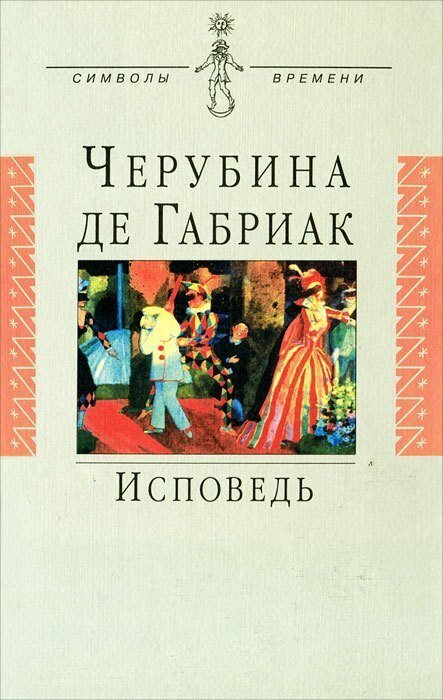
この手紙の一年後、流刑先のタシケントでエリザヴェータは41歳で病死した。ボトキン墓地にあった彼女の墓は、現在その場所に見あたらないのだという。チェルビナの真相が綴られた『告白』が出版されたのは、それから70年以上も後の1999年のことだ。一人の詩人のなかに二つの魂が息づき、互いを深く愛している、それがひしひしと伝わってくる大切な一冊である。
(※こちらは連載時の原稿です。書籍『埃だらけのすももを売ればよい ロシア銀の時代の女性詩人たち』とは一部ちがいがあります)
プロフィール
高柳聡子(たかやなぎ・さとこ)
1967年福岡県生まれ。ロシア文学者、翻訳者。早稲田大学大学院文学研究科博士課程修了。おもにロシア語圏の女性文学とフェミニズム史を研究中。著書に『ロシアの女性誌━━時代を映す女たち』(群像社、2018年)、訳書にイリヤ・チラーキ『集中治療室の手紙』(群像社、 2019年)、ローラ・ベロイワン「濃縮闇━━コンデンス」(『現代ロシア文学入門』垣内出版、2022年所収)など。2023年にロシアのフェミニスト詩人で反戦活動家のダリア・セレンコ『女の子たちと公的機関 ロシアのフェミニストが目覚めるとき』(エトセトラブックス)の翻訳を刊行。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
