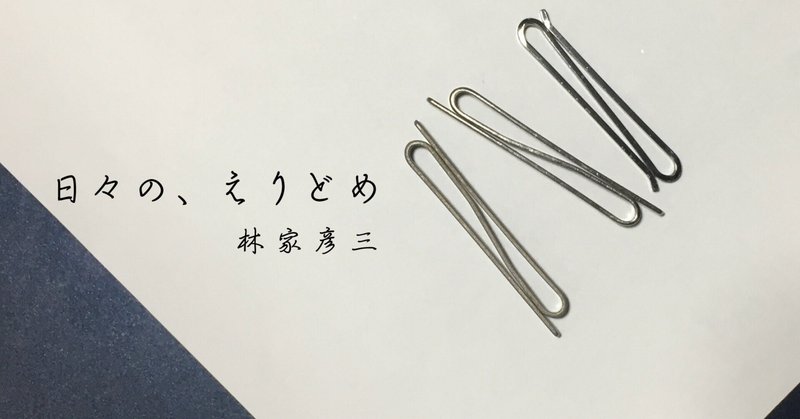
【日々の、えりどめ】第20回 ここに留める
前略、渋柿とジン
どういうわけか、わたしはその日、『若きウェルテルの悩み』の文庫本を持ち歩いていた。急に懐かしくなったのである。そして鎌倉の某喫茶店の隅で読み始めたのであった。
その喫茶店には、ほとんど照明がなかった。全体が、薄暗がりであった。夜も更けていたので、常連らしい店の客人は皆お酒を飲んでいた。わたしも珈琲ではなくて、ドライジンを注文した。
そもそも読書をするような場所と時間ではないので、訝しいような目線を常に感じていた。しかし、そうしているうちに、店のお姉さんが、「さ、ウェルテルさん、これでお読みよ」と、いかにも小説風のすてきな振る舞いで、わたしに小さな手持ち明かりを差し出してくれたのであった。その古い電灯の笠は銀色で、しかもところどころ剥げていたので、わたしはなお嬉しかった。
それからしばらくして、いま一度この喫茶店から親切を受けた。いかにも苦味走った良い男というような様子の店のマスターが、「さ、食べ」と、ぶっきらぼうなセリフで、わたしに向けて手を伸ばしたのであった。それは爪楊枝に刺さった、一切れの柿であった。しかもその柿はまだ固く、ほのかな渋味さえあった。――妙な取り合わせであるが、それは非常にジンと相性が良かった。
これは去年の秋の出来事である。ちょうど、この連載がはじまろうという頃である。それからわたしはこの喫茶店と懇意になり、常連客ともすっかり打ち解けた。はじめは「ウェルテル君」という恥ずかしいあだ名がついていたが、いまではそれも忘れられて久しい。
あれからおよそ一年。いろいろあったようにも思う。もちろん、変化もあった。
結論、渋柿とジンは、合う。縁は異なもの味なもの。独活が刺身のつまとなる。ひとりのはなしかも、作家のようなことをするように至る。
ヘッセと夏
毎年この季節になると、手ばなしに、透明でうつくしいものがたりを、なんの理屈もなんの解釈もなく、読みたくなる。そしてわたしはその背表紙に手を伸ばす。まるで夏草を踏むような思いで――という、そんな比喩さえも恥ずかしくないほどに正直に。
ヘルマン・ヘッセの『青春は美し』(Schöen ist die Jugend)――わたしは毎年夏になると、この小説を読む。
ひと昔前の新潮文庫の氷菓子のような薄水色の装丁で馴染んできたけれども、他の訳も味わいが変わって面白い。いつか辞書を片手に、原文も読んでみたいと思っている。
以上である。この小文に関しては、なんの理屈も解釈もない。ただ、それだけの噺。
チュウ死す
この年月において、忘れられない出来事のひとつが、実家の猫の死であった。
名はチュウ。もともとビニール袋に入れられて雨の降る道端に捨てられていた猫である。目が悪く、すぐに獣医者に治療してもらったのだが、そういうわけもあっていつもおどおどとして、小心者であった。人が来ると目をしばつかせながらそそくさと部屋の奥に逃げた。たまに甘えたがるような素振りもみせるのだが、それもどことなく申し訳なさそうにすり寄ってはまた離れてしまうのであった。
鳴き声は妙に甲高く、音程も間抜けであった。白猫とは言えないくらいに、茶や黒の毛がところどころに混じっていて、毛質はいつも湿っぽくて、それは例えば宮沢賢治の描いた夜鷹の風体を思わせるところがあった。
しかし、それもこれも含めて、わたしはチュウの事がほんとうに好きであった。このような最中で帰省もできなかったので、とうとう会うことはできなかった。ごろごろと喉を鳴らしながらときに遠慮がちに甘えた声を出すチュウの頭を撫でてやることができなかった。それは悔しいことであった。
ある時から、チュウが弱ってきた。動けないくらいだったという。母親も心配していたが、ある朝、そのチュウの姿がない。玄関を見ると、ちょうど猫一匹が通れる隙間が空いていた。チュウは、誰の人目にもつかない庭の隅で、冷たくなっていたのである。――これが、電話で母に聞いたチュウの最期である。
わたしはそれから、チュウの最期を何度も頭の中に思い描いた。動かない体をひきずりながら、無理に力をふりぼって実家の重たい玄関をこじあけ、冷たい草の上で丸くなった、一匹の猫。――思い描くたびに、それはチュウの影とも、飼い猫の影とも思えなかった。それはまさしく、命そのものの勇敢な影だった。賢さなどには縁もなく、強さなど微塵もなく、見習いたいくらいに毎日毎日申し訳なさそうに生き抜いた。
ここで多くは書かないが、いつか追悼のためにもチュウのことをしっかりと書き留めておきたいと思っている。あのうつくしいまなざしを、忘れぬうちに。
わたしはいま、あるお方からのご紹介でスペインの作家J・R・ヒメネスの『プラテーロとわたし』を読んでいる。愛する驢馬のプラテーロを失った〈わたし〉の物語。その作者曰く――「プラテーロ、きみはわたしたちを見てるよ、そうだね?」(長南実訳、岩波書店)
ノラや
百鬼園先生の『ノラや』を久しぶりに読んだ。中公文庫。ここに忘れぬうちに、感想。
深い繁みに分け入ったまま帰らない猫の話。探している。いまでも。あるいは、失われた近代文学史の中で。近代文学愛好者は、探している。もしくは飼い馴らした愛猫のような親しさで、やはりその喪失に対してひそかにも真剣であるような方々には、それは執着すべき重要な日々の問題のひとつ。それがなくては心許ないので、喪失から産出されるものを自らと世界を支えるための杖にしながら。後ろ向きだが、積極的に。
しかし落語界にいると、その近代文学のしっぽのようなものに、ふと出くわすこともある。――けれども、それはよくよく追っていくと、探し求めている迷い猫ではないことがわかる。それは非常によく似た、まったく別の猫である、
それでも追いかけることで、しっかりと経験されているものがある。あるいはノラはいまも近代文学に成り代わって、至る所にその尾を見せる。それら目撃情報こそ、時代遅れの物書きの頼りというもの。それがいかに短い尾であろうとも。
ここからは蛇足になるが、高円寺に「ノラや」という箱があり、落語会が開催されている。わたしもお世話になっている。その会のあとで、ささやかな打ち上げをする酒場がある。そのバーの名は、「クルツ」。
ケルンの水
ある方から、ルートヴィヒ美術館展の招待券をいただいた。場所は六本木。
わたしは人生でたった一度の海外旅行において、このケルンの美術館に行ったことがある。しかし、その記憶が全くない。メモ書きも残っていない。この展覧会に足を運んでカンディンスキーやエルンストの絵を見れば、何か思い出すこともあるかもしれない。
それよりもわたしがいま気にかけていることが、ケルンの水(オーデコロン)のことである。ケルン土産として買ってはきたのだが、使うこともなく保管していたのを、この出来事を機会にふと思い出したのである。
数年ぶりに開封してみると、その柑橘系の晴れやかな香りは、案外良いものであった。わたしはふと忘れていた異国の風を感じるような心地がした。
落語家というのは、おまじないだとか決まり事というものを、わりと好む種族である。いわゆる芸人の願掛けというもので、初日の演目や腰ひもの結び方に至るまで、決まったものを通して縁起担ぎをすることが多い。あるいはそれは芸人という根無し草の、根本にある弱さからくるものではないかと思う。
そうだ、使い道がないくらいならば、このケルンの水をまじないにしようか――と、わたしは思った。手ぬぐいや扇子に吹きかけて、爽やかな香りを残し、それを楽屋でひそかに顔に近づけ、あの大聖堂やライン川を脳裏に思い描き、弱い心、少しでも大きく持つために。それは束の間のドイツ紀行の記憶のように、消えやすい香りだけれども。
スクラップ・ブック
格言というものは言葉として整理しやすいから、よって記憶もされやすいものと思う。
留める――という言葉について、わたしは過去に何か格言を持っていたと思ったが、なかなか思い出せなかった。しかしそれは過去のメモ書きを調べてみて、すぐわかった。
その格言は大詩人フリードリヒ・ヘルダーリンの言葉。Wo bleibet aber , stiften die Dichter.(おそらく――しかしまた留まりたるものを建てたるのは詩人たちのわざ――というような意)
わたしは、もちろん詩人とは言えるような人間では到底ない。況や、若手の芸人である。どちらかと言えば――淀みに浮かぶうたかたは、かつ消えかつ結びて、久しくとどまりたるためしなし――というような世界の方が近しい。落語なんてものは聞いてすぐ忘れるようなものであると、師匠方もよく仰る。あるいは世の中にある人とすみかと、またかくのごとし。
しかしまたわたしは、少しでも留まるものをこそ打ち建てなければ、そうしなければ、そのような意志がなければ、おそらく生きていくにも覚束ない人間であろうということも、ここに正直に告白しておきたいとも思う。
拙著の『汀日記』が書肆侃侃房から出版されて、三か月余りが経った。この本は、幾数年も留まる種類のものだろうか。わからない。評価も部数も、おそらくまだまだ浮遊している本である。
それでもわたしはこの本の書評をはじめ、新聞記事の切り抜きや先輩からの感想の葉書を部屋の机の前に貼りつけ、それらを眺めては心に留めて、日々の忘却の流れに流されないためにしがみついているのである。この本は、たしかにわたし自身の身体を助けるためのお材木になっている。
さて、この連載も今回がひとまずの区切りということになる。
よってわたしはその最後に、ここに曲がった虫ピンのようなカタカナの標題による留め金たちを、羅列してみた次第である。この年月の備忘として、ここに留めるために。
ともかく序文でも触れたようなわが空想の『襟留文集』のお披露目は、まだまだ先のことになりそうである。わたしは日々の紙切れを、ここにばっさりと音立てて綴じておく。
連載をお読みいただいた皆様、誠にありがとうございました。
機会をいただきました遠い都市の出版社さまにも、まずはこちらにて御礼申し上げます。
令和四年。残暑の候。
草々。
【プロフィール】
林家彦三(はやしや・ひこざ)
1990年7月7日福島県生まれ。
早稲田大学ドイツ文学科卒業。
2015年林家正雀に入門。現在、二ツ目。
若手の落語家として日々を送りながら、
文筆活動も続けている。本名は齋藤圭介。
著書『汀日記 若手はなしかの思索ノート』(書肆侃侃房)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
