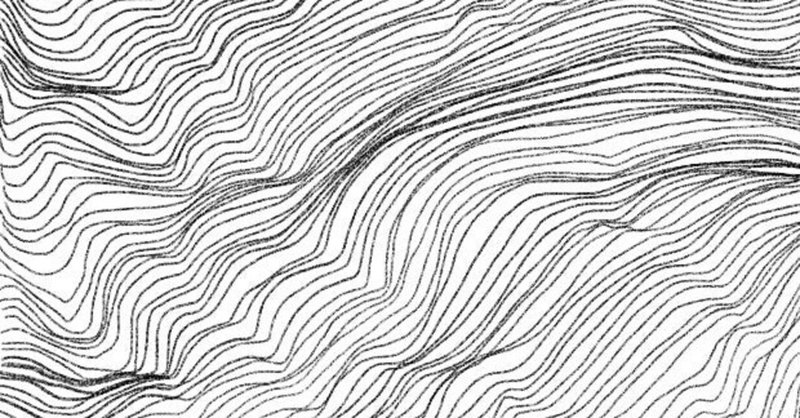
祖父が亡くなった。
祖父が亡くなった。
明るい人だった。
関西人らしくいつも冗談を飛ばしていた。最後に電話したのはいつ頃だったろう。
多分、1ヶ月前くらいだろうか。
俺は都会で暮らしていたから、仕事や日々の雑事に追われる中で連絡も疎かにしがちで、そこに近頃の感染症もあって顔も碌に見せられていなかった。
小さいときベイゴマやらあやとりやら、怪しい手品もよく教えて貰った。本当に楽しかった。何をやらせても、上手だった。
あの時に教えてもらったことは、実はもう覚えていない。楽しかった記憶だけが残っている。
ところで。俺は今何万回と歌われたり書かれたりした後悔を、凡夫らしくやっている。
後悔してももう遅い。
そう思っているところまでが沢山の人と相似形だ。
故人は空にいるのでもなければ、墓にいるのでもない。そんなことはついぞ俺には明かされない。そんなことは分かりきったことだ。成人男性がメルヘンに溺れるわけにはいかない。それでも。
もっとできたんじゃないか。
今はこう思っているし、悩むこともできる。しかし、これから先も悩み続けられるだろうか。
こんなことを今は言っているくせに、日々の雑事におしながされて、気づけばまた同じ後悔に暮れてしまうかもしれない。或いは、気付かぬうちに自分が後悔を「させる側」になるかもしれない。
その人がいたことを胸に抱いて生きていけば、生きていた時にできたであろうことを誤魔化せるなんてことはない。
それは質的に、全く異なる話だ。
どんなに後悔しても、「やるべきであったことをしなかったこと」は、消えては無くならない。
人が亡くなるということは、思った以上に日常に埋没していて、びっくりするほど人はそれに「適応」できる。
死は生の対極としてではなく、その一部として存在している。
あまり好きではない村上春樹のヒット作に出てくる言葉だが、悔しいがこれについては芯を食っていると認めざるを得ない。死は生の直線が伸びる先に唐突に現れる不連続な点で、それでいてその乖離には気づかないような代物なのだろう。メビウスの輪のように、表も裏もなく、それでいて質の異なる領域へのジャンプがそこにはある。
誰しも死にたくはないと思っているから、好きでもない仕事をへいこらしながらやって、酒を飲んでは愚痴を言っている。日々を誤魔化すために、究極の理由=生を「使って」いる(「生きるためには仕方ないじゃないか。つまらないけど辛いけど愚痴でも言って頑張ろう…」)
だからこそ、不意に死が飛び込んでくると僕らは怯える。あれほど避けたいと思っていたはずの死が、極めてフレンドリーに時に呆気なく、日常に浸潤してくるからだ。そして日常の力強さはいとも簡単に、愛しい人の死すら「飲み込む」。
そうすると、必死になって今まで目を背けてきた日常の不甲斐なさに気付かされる。故人への申し訳なさと同じくらい、自分の不甲斐なさをまざまざと見せつけられる。
生を、今をつまらなく生きる理由に使うな。仕方なく生きることはするな。
こんなことを考えたとしても、故人の役には立つまいが、それでも今生きている俺には役に立つ。
こんなことを考えた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
