クラインフォーゲルバッハの運動学について 序
こんばんわ!
生態心理学についてのまとめに続いて、クラインフォーゲルバッハの運動学についてお話ししていけたらと思います。
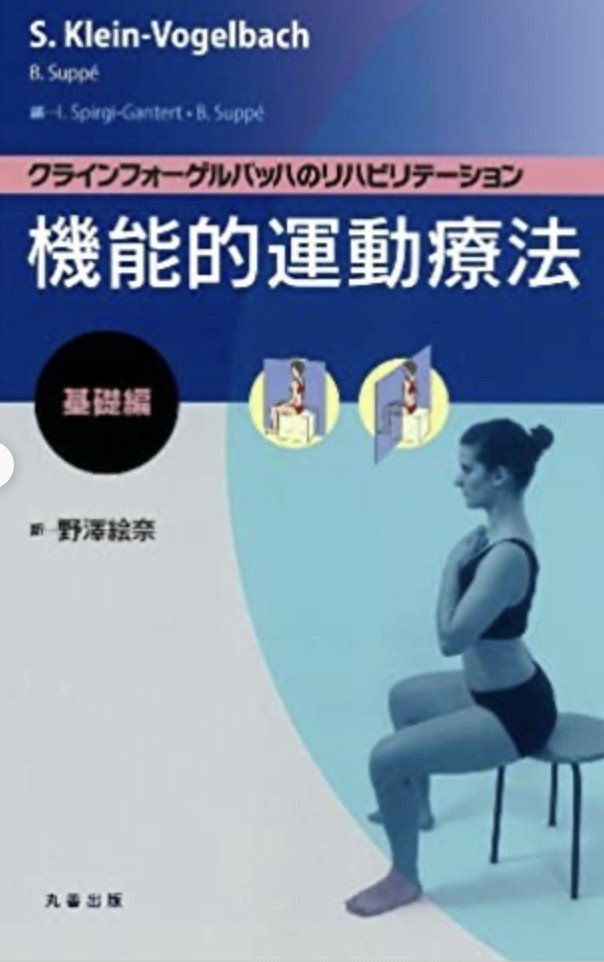
その前に少しだけ!
ぜひ、この自粛期間に読んでいただきたい一冊です。非常に分かりやすくまとまっているのでご一読いただけるとありがたいです。
さて、本題に入らせていただきます。
人は、脊椎動物であり内骨格構造と外側の筋により動いています。
支持する面と接する骨格は、球形や円筒形で非常に傾きやすい構造となっています。
関節は筋や靭帯などの弾力性のある構造で支えられ、柔軟性があり大きな自由度を持っているため骨格だけでは安定性を確保できません。
つまり、人間の身体はかなり不安定な構造をしています。
地上で唯一、直立二足歩行を獲得した人類ですが、機能的な進化では運動性を優先し、動的に動いて対応することで、構造的な不安定性を選択しました。
この不安定性に対して、私たちは生まれてから重力場で自分と環境との関係を探りながら動くことで環境に適応した運動を学習する必要があります。
クラインフォーゲルバッハの運動学では、中枢及び末梢、筋の活動様式を運動学的、運動力学的に分類して説明しています。
次回から分類について深く入っていけたらと思います。
お気軽にご意見、ご指導宜しくお願いします🤲🤲🤲
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
