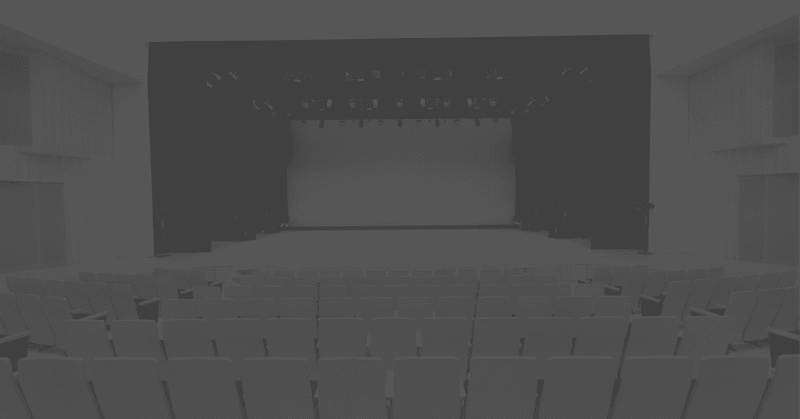
遊川の日誌 vol.2
彼にノートを差し入れて数日すると、「外で話ができないか」との打診が来た。「街」から外へ出たところで、至る所に情報漏洩、監視の糸口はある。どこで何を打ち合わせても無駄だと思いつつ、別の男性職員のIDとダミーの梱包材を調達して、なんとか二人で外に出た。
無駄なのは重々承知の上で、別人名義で予約したシティホテルへ、二人で入った。どうしても目立つ彼の姿を誤魔化すために、外向けの認識阻害機能も有効にしておいた。どうせならもっと広い場所、明るい場所での逢瀬、デートを楽しみたかったが、重大機密の一つと化した彼を連れ出すなら、これでも良い方だと自分に言い聞かせる。
私が狭い部屋でくつろぎ始めると、彼は神妙な面持ちで椅子に腰掛け、私の差し入れたノートをこちらに広げて見せた。そこには数ページにわたって彼の計画が綴られている。一通りパラパラページを捲り、私は顔を上げて首を横に振った。
彼は随分と落胆した様子で、「ダメか」と呟いた。
「ええ、全くもってね。アナタにしては珍しく、落第点ね」
彼は私の言葉に、強いショックを受けていた。その落胆ぶりは、今にも手首をかき切るか、睡眠薬を大量に飲むような素振りにも見える。
「『街』がどんな組織か、アナタもよく知ってるでしょ? 都合よく実験体が手に入ったからって、躊躇なく計画立案者を被験体にする組織に、こんな計画では歯が立たない」
私の指摘に、彼にしては珍しく「ああ、そうだな」と素直に頷いた。永らくベッドの中で苦しみに耐え、辛いリハビリに取り組みながら捻り出した計画を簡単に一蹴されれば、どれだけ能力が高く、それに伴う自尊心があったとしても、こうなるのも無理はないか。
私は彼の近くへ身体を寄せ、その頭を優しく撫でた。
「どうしても、逃げ出したい?」
彼の頭を撫でながら、耳元で囁いた。彼は頷きながら、「今すぐにでも」と付け加える。変わり果てた怪物めいた顔が、より一層苦しそうに歪む。
「あんな杜撰な計画で、どこに逃げるつもり?」
私は彼のノートをサイドテーブルに放り投げた。他の誰にもできない相談を持ちかける癖に、その計画は彼一人が研究施設を脱するまでの話しか記載されておらず、私はその途中で出てくる使い勝手のいいコマの一つに過ぎないらしい。
これまで献身的に身の回りの世話を焼き、どんなに辛いリハビリにも付き添って、心のケアにも尽力してきたつもりだけど、その想いは微塵も汲み取られておらず、未だに「都合のいい女」止まり。多少は役に立つ路傍の石としか見られていない。
それならそれで、構わない。ただ、彼の計画はやはり問題だらけ。私は自分のカバンを探り、ペンを手に取った。
「研究施設を出て、ちょっと距離を取ったぐらいで『街』からは逃れられない。ロケットでも作って、地表から脱出しない限りはね」
私は彼の計画に、自分の名前を書き込んだ。随所に疑問も書き添え、そこにも自分にできることを追記する。「街」から出る際の逃避行にも、パートナーとして名前を付け加える。
計画を実行に移した際、最終的に一人しか逃げられない場合は、私の名前に二重線を引けばいい。実際にそうなるまでは、二人で逃げ出せるように手を尽くす。これで、彼の残りの人生は私のものになる。
私は加筆した計画を彼に突き出した。彼はそれに、熱心に目を通した。
「良いのか? これでは君も」
彼は顔を上げ、私をじっと見て言った。私はまっすぐ彼の目を見つめ返し、ゆっくり頷いた。
「君にここまで協力してもらえるなら、非常に助かる。追記や指摘も、全部ごもっともだ」
彼は再びノートに目を落とす。彼が想像できていなかった部分、事前に必要な道具や準備、逃避行の先やその後の生活、段取りも思いつく限り書き込んだ。あとは、適宜ブラッシュアップしていけばいい。
彼は計画の最後の部分、私が自分の名前を書き添えて丸をつけた部分を指差した。
「本当に、良いんだな?」
「ええ、もちろん」
彼の度重なる質問に、私は即座に返答する。その明快さに彼も色々と汲み取ってくれたらしく、彼はそこで一旦ノートを閉じると、そのまま自分の荷物へ放り投げた。
彼は一連の動作の途中、私のカバンの中に、いつも私が事後に吸っていたメントールのタバコを発見した。以前の彼は見向きもしなかったソレを指差し、「一本くれないか?」と彼は言った。
部屋の中は確か、禁煙だったはず。それ以前に、彼の身体で喫煙などもってのほか。私が「ダメよ」と答えると、彼は「良いじゃないか、一本ぐらい」と勝手にカバンを漁り始めた。私はカバンごと取り上げ、タバコは箱ごと握り潰してゴミ箱へ投げ入れた。
彼は一連の出来事に驚いたらしく、私の顔をジッと見つめている。
「あんまり、勝手なことはしないでちょうだい。外出の偽装も大変なんだから」
私が語気を少し強めて言うと、彼は両手を上げて降参のポーズを取った。
「オレが悪かった。スマン」
彼はスッと頭を下げて謝ると、元の場所へ戻った。
「君と北の方へ逃避行か。かかあ天下になりそうだな」
彼はそう言いながら、優しく微笑んだ。尻に敷かれるようなタイプには思えないが、かかあ天下という響きは、決して悪くない。
「どうせなら、北海道どころか、もっと遠くへ行ってみようか。ロシアどころか、北極点まで」
彼は楽しそうな口調で、妄想をどんどん広げる。国内までなら私レベルの偽装工作でもなんとかなるが、流石に国外脱出、パスポート関連までは心許ない。一旦北の大地で潜伏した後、そこから先は別途考えることになりそうだ。
「駆け落ち、いや新婚旅行みたいなものか」
彼が口にしたフレーズに、私の鼓動は一気に高まる。彼はそこまで考えてくれているとは。なんだか妙にソワソワしてくる。うわついた気持ちで、彼の声に耳を傾ける。
「まさか、君と結婚するとはな。こんな身体になるのも想定外だったが、この展開は完全に予想外だよ」
彼は自分の腕を、もう一方の手で触りながら言った。私は、それを愛おしい気持ちで眺めながら口を開く。
「その身体はどう?」
「どうって言われてもなぁ。気分は最悪だよ」
彼は顔を上げ、向かいにある鏡台の鏡に映った自分の姿を眺めた。自分の顔や容姿が、誰もが一度は目を背けたくなるような、醜いものとなれば最悪な気分になるのも仕方がない。
「手術痕や拒絶の痣、見た目の問題は仕方がない。開発や改善の余地もある。ただ、モルモットにされているという事実、機械の身体に成り下がった境遇は、中々受け入れ難いものがある」
彼は極めて自然な口調で、淀みもなく言った。私はそれを耳にして、しばらく相槌も返事もできずにいた。彼は話題を振ったのに無反応の私を見て、「どうした?」と訊いてきた。私はそれにも答えられず、微かに視線を逸らした。
彼なりの価値観、彼の理想論は理解していたつもりなのに、浮き足立っていたところに冷水を浴びせられれば、答えに窮するのも無理はない。私は彼に見えないよう下唇を軽く噛みながら、彼の方を向いた。
彼は何も変わらない。身体がどれだけ変わろうと、私がどれだけ尽くして、教え諭そうとも。でも、それが彼だ。私が人生を賭して尽くそうと思ったのは、彼がこういう人間だからだ。
彼に切り捨てられていった、見た目だけの女たちとは違う。私は彼を否定しない。彼を手放しもしない。手元にあるものは全て駆使して、どんな手段を使っても彼を振り向かせてみせる。
曖昧な愛も、面倒なだけの愛の結晶も、私は決して求めない。
私は、こちらをジッと見つめる彼をベッドへ押し倒し、自分が着せたものを強引に剥いでいく。何も残らない、何もなし得ない人生で構わない。ただただ酔狂に、狂い尽くしたいーー。
ここから先は
¥ 100
最後までお読みいただき、ありがとうございます。少しでも楽しんでいただけたら幸いです。 ただ、まだまだ面白い作品、役に立つ記事を作る力、経験や取材が足りません。もっといい作品をお届けするためにも、サポートいただけますと助かります。 これからも、よろしくお願いいたします。
