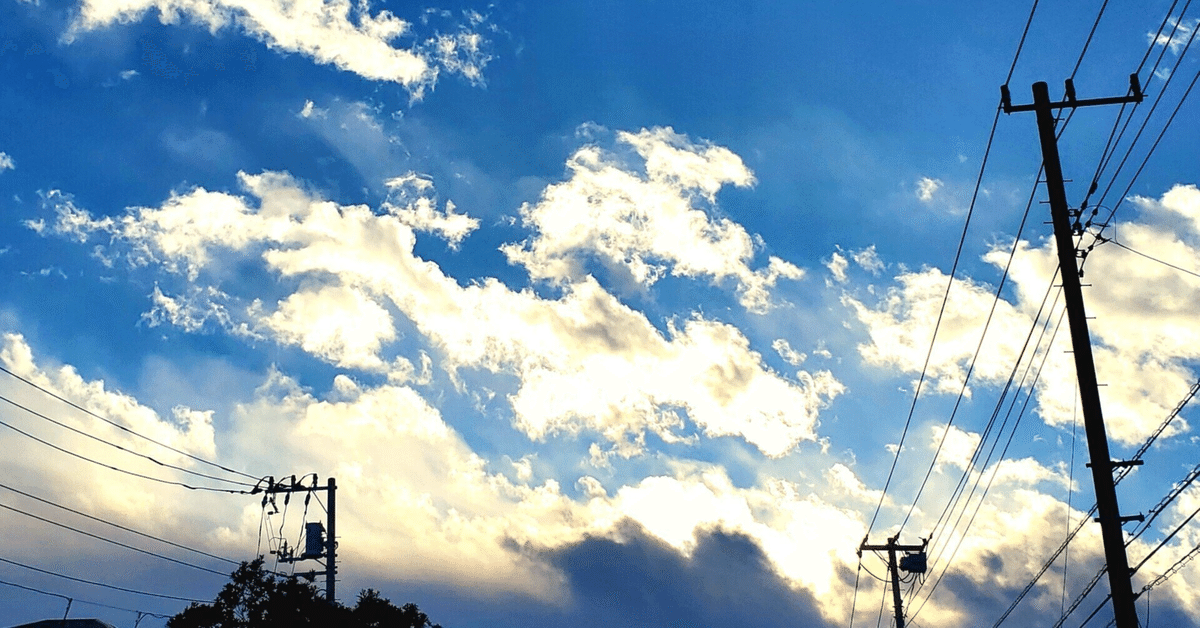
あっぱれ!細川宣伝社 第8話
【第8話】
西中の記念祭のあと、僕はクラスでちょっとした有名人になっていた。記念祭でのパフォーマンスが、新聞に取り上げられたのだ。
見出しは『ちびっ子チンドン 伝統のワザ甦らせる』。
電話取材によるネズミ花火とハッタリに対する僕の拙い喋りが、洗練された文章で綴られていた。
休み時間になるたびクラスメイトが机を囲んでくる。
話している最中、教室の隅から視線を感じた。純也だ。ロッカーに寄りかかって、こっちを見ている。クラス替えで子分の博と離れてから、純也は一人でいることが多くなっていた。
純也も記事を読んでいるのであれば、少なからず思うところはあったはずだ。特に記事を締めくくっていた一文に……。
『ばーか、かーば、チンドン屋。お前の母さん、でべそ。ある年代から上の人であれば、一度は耳にしているだろう。チンドン屋は、一部の人から蔑まれた過去がある。だが、そんなふうに誹謗されるいわれはない。彼らの仕事は、高度経済成長に繋がる日本経済の礎を作ったのだ。もしも非難する者があれば、お門違いも甚だしい。ネット社会の今、チンドン屋は人の温もりや優しさを伝える貴重な職業である』
あれだけチンドン屋をバカにしたのだ。自分のことを言われていることくらい気づくだろう。きっと、胸がチクチク痛んでいるに違いない。読んでいればの話だけれど。
チラリと僕が視線を向けると、それを避けるように純也は廊下に出て行った。
ニュースが梅雨入りを伝えた日の夕方。リビングのソファで漫画を読んでいるところに、父さんが帰ってきた。
「悠太、今度の土曜日、仕事が入った」
きょうは火曜日。土曜といえば四日後だ。
「急だね。どこでやるの?」
「葬儀場」
「葬儀場?」
聞き返したのは、新聞の折り込みチラシをチェックしていた母さんだ。
「そう。お葬式でやる。先方から、是非お願いしますって頼まれたんだ」
「誰が亡くなったのよ。そもそも、葬儀の席でチンドンなんて聞いたことない」
母さんの言う通り。チンドンは、基本的にめでたい場所で披露するものだ。父さんが、首からネクタイを引き剥がしながら説明してくれた。
亡くなったのは、ひいお爺ちゃんと全日本チンドンコンクールに出場した杉さんだった。お正月にジイちゃんが話してくれた、底抜けに明るい、あの杉さんだ。
去年の冬、散歩中に転んで寝たきりになり、結局ベッドから一度も出ることなく旅立ったという。死期を悟っていたのか、杉さんは亡くなる三日前に家族に伝えたそうだ。
死んだら、チンドンで賑やかに送り出してほしい、と。
その遺言を受けた娘さんから、ジイちゃんを経由して、父さんに連絡がきたという。
「それでだ」父さんが、スマホにメモしてあった依頼内容を読み上げる。
「チンドンは出棺の際に十五分ほど。曲はお任せ。オンナ形でお願いしたい」
「おや、まぁ」と目を丸くする母さんの隣で、僕は初めて聞く言葉をオウム返ししていた。
「オンナ形?」
「悠太はオンナ形知らないか」
父さんが、上着を脱ぎながら教えてくれた。
「オンナ形っていうのは、歌舞伎なんかで、男が若い女性の格好をすることだ。簡単に言うと、お姫様のコスプレ。毒舌タレントの桜沢富美男も大衆演劇でオンナ形だったな」
母さんが、冷蔵庫から出してきた缶ビールを父さんの前に置いた。
「でも、わざわざどうしてかしら」
「亡くなった杉さん、若い頃オンナ形でチンドンやってて、それが評判だったらしい」
「なるほどね。だけど誰がやるのよ。まさかパパがやるつもりじゃないでしょうね」
「俺は、ムリムリムリムリ!」
胸の前に両方の手の平を出し、小刻みに振っている。女子高生みたいで、ちょっと気色悪い。
「じゃ、ケン君?」
「ケン君はダメだ。お願いすれば、やってくれるかもしれないけど、あの格好だけは譲らないだろうから」
白塗りでお姫様のカツラをつけて、首から下は黒皮のジャケットとパンツ。想像したら吹き出してしまった。父さんの言う通り、確かにダメだ。
父さんが、ふいに僕を見た。
「そこで悠太、オンナ形をやってくれ」
「嫌だよ。ムリムリムリムリ!」
父さんと同じように、女子高生みたいに手を振っていた。人間、本当に無理なときには、そうやってバリアを張るようだ。
「おや、まぁ。いいじゃない!」
おや、まぁと、やけに落ち着いた言い方をしながら、母さんのテンションは高めだ。僕にオンナ形をやるよう促してくる。
「やってみなさいよ」
「嫌だよ。女になるのなんて」
断固拒否する。女装姿を、万が一友達にでも見られたら……。考えただけでゾッとする。新聞記事をきっかけに、新しいクラスメイトと気軽に話せるようになってきたというのに、前みたいな状況になるのはごめんだ。勘弁してほしい。と、最悪の事態を見越して100%断るつもりでいたのに、父さんの一言で気持ちが揺らいだ。
「最近チンドン頑張ってるから、仁天堂のスニッチを買ってあげようと思ったんだけど」
父さんがズボンのポケットから折り畳まれた家電量販店のチラシ取り出し、ゆっくり広げた。
「なになに、テレビモード、テーブルモード、携帯モード3つのプレイモードで遊ぶことができます、か。へぇ~、悠太これ楽しそうだな」
商品の説明を読み上げながら、横目で僕の様子を窺ってくる。予め仕込んでおいたに違いない。
スニッチは喉から手が出るほど欲しいゲーム機だ。でも我が家は、勉強の妨げになるという理由でゲームはご法度。この機会を逃すと、バイトができる高校生になるまで恐らく手に入らないだろう。まさに千載一遇のチャンス。
女装するか。しないか。
心の天秤が大きく揺れている。ユラユラする天秤の皿を止めたのは、母さんだった。
「きっとお爺ちゃんだったら、やってるわね。チンドン屋は人に喜んでもらってナンボだからって、よく言ってたもの」
人に喜んでもらってナンボ。僕らのチンドンを聴いてくれた人の顔が浮かんできた。
ショッピングモールで涙を流した車椅子のおばあちゃん。
西中の記念祭で大合唱した大勢の卒業生たち。
みんな喜んでくれていた。
お葬式でオンナ形を披露したら、杉さんの家族もきっと喜んでくれるだろう。僕も、チンドン屋のはしくれだ。やる以上は、お客様の要望に精いっぱい応える責任がある。
天秤の『女装する』ほうの皿が、ガクンと下がった。
「やるよ。杉さんのために女になる」
「よく言った。それでこそ男だ。女になれる男の中の男だ!」
父さんが僕の肩を叩いてくる。
「おや、まぁ。やるならママも見に行こうかしら」
母さんも嬉しそうだ。けれど、それが本心なのかはちょっと疑わしい。というのも、さっきから「おや、まぁ」と気のないリアクションばかりで、どこか他人事の感がある。
「母さん、僕のオンナ形、ホントに見たいの? なんか返事がテキトーなんだけど」
「え?」と母さんが、漫画なら頭の上にクエスチョンマークが浮かぶ顔になった。
「だってさ、おやまぁ、って気のない返事ばっかりじゃん」
母さんが固まった。と思ったら、次の瞬間、お腹を抱えて笑い出した。
「悠太ったら勘違いしてる。大勘違いよ、それ」
「おや、まぁ、か。そりゃいいや」と、父さんも手を叩いて笑い出す。
何がそんなにおかしいのか、さっぱりわからない。自分だけ取り残されていることに無性に腹が立ち、二人を交互に睨みつけた。
「ごめんごめん。そうよね、わからないわよね。笑ったりして悪かったわ」
謝ってはいるものの、母さんは、まだお腹を押さえている。
「おやまぁ、って、気のない返事をしてたわけじゃないの。オンナ形のことを『おやま』とも言うのよ」
聞けば、おやまはオンナ形の別の呼び方だという。女の形と書いて「おんながた」「おやま」と二つの読み方があるらしい。
つまり母さんは「おやま、いいじゃない」「おやま、やるならママも見に行こうかしら」と、気がないどころか、息子の晴れ姿を大いに期待していたのだ。
意味を履き違えていた自分が恥ずかしくなってきた。気恥ずかしさから視線を逸らすと、奥義の額縁に目が留まった。
解読できていない四つ目の一文に、僕の目が吸い寄せられる。
『おやまいくたび四丁目』。最初の三文字が、3Dみたいに浮かび上がって見えた。
「あぁ!」てっきり、お山だと思っていたけど「おやまは、オンナ形のことかも!」
僕の指差した先、奥義に目をやった父さんがポンと手を打った。
「そういうことか。四丁目の演奏でオンナ形をやる、と。そうなると、行く度はどう解釈すればいいだろう」
それにだって、ちゃんと意味があるはずだ。
「父さん、四丁目について情報ないの? なんか本に書いてなかった?」
「四丁目か。四丁目は、一日の仕事を締めくくる曲ってことくらいかな。一巡目はゆっくりやって、二巡目、三巡目とフィナーレに向かってテンポアップさせていくらしい」
二巡、三巡ということは、何回もやるというわけか。
何回も。何べんも。何度も。幾度も。幾たびも。うん?
いくたび……。
「行く度じゃなくて幾たびかも! 四丁目を幾たびも演奏するってことじゃないの?」
「幾たび、か。女形で、幾たびも、四丁目を繰り返す。あるかも! やっぱり本を読んでおいて正解だった。四丁目について知らなきゃ、この答えは出てこないからな。どうだ、パパすごいだろ」
本で仕入れた知識が役立ち、父さんは満足げだ。暗号を解いたのは僕なのに、なんだか手柄をとられたようで気分が悪い。もっとも父さんは、そんな息子の気持ちなどお構いなしで、勝手に張り切り出していた。
「そうとわかれば悠太、女形の稽古しなくちゃな」
「うん、やろう」と言いかけて疑問がわいた。女形の立ち振る舞いは、どこで覚えたらいいんだろう。しかし、偶然とは恐ろしい。
首を傾げると、テーブルにあったチラシが目に入った。さっきまで母さんが見ていた折り込みチラシの一枚。健康ランドのイベントを伝えるものだ。
大浴場や宴会場の写真の横に、デカデカと赤字でそれは書いてあった。
『畦道源五郎一座「銀色夜叉」昼夜二回絶賛公演中! 下町の流し目プリンスも出演』
流し目プリンスという文字の横に、お姫様の格好をした人の写真が貼りついている。プリンスというくらいだから男だろう。つまりは、女形……。
これだ!
手にしたチラシには、夜の部は七時からとある。壁の時計を見ると、六時を過ぎたところだ。健康ランドまでは車で十五分ほど。まだ、間に合う!
父さんにチラシを突きつけた。
「父さん、ここに行こう」
「健康ランド? 家の風呂でいいじゃないか」
「お風呂はどうだっていいの。流し目プリンスを見に行くんだよ。女形の参考になるかもしれない」
「そう言われてもなぁ。きょうは外回りで疲れてるんだ。明日じゃダメか」
女形の動きを習得するには、一日でも早いほうがいい。明日なんて遅すぎる。思い立ったが吉日だ。
渋り続ける父さんに、母さんが援護射撃してくれた。
「私も一回、ホンモノをナマで見たかったのよね、流し目プリンス。あの流し目でハートを撃ち抜かれてみたいわ。近いんだから行きましょうよ。ホラ、割引券もついてる。大人三百円引き、子供二百円引きですって。三人で八百円引きよ」
ハートを撃ち抜かれたいというのは正直どうかと思うけど、援軍としては頼もしい。これで二対一だ。健康ランドに行ける確率がグッとあがった。
というのも、三人家族の我が家では、意見が分かれたときには多数決が採用されるからだ。外食で何を食べるかとか、ドライブでどこに行くかとか。ステーションワゴンを購入するときもそうだった。僕と父さんがタッグを組んで、軽自動車のエコカーがいいという母さんの意見を退けた。
そのとき父さんは言っていた。「民主主義において多数決は絶対だ」と。僕と母さんが主張する健康ランド行きを受け入れないのは、父さんの言うミンシュシュギというやつに反することになる。
本人もそれに気づいたようで、溜息を一つついて、僕らの意見を受け入れた。
それと忘れないうちに、さっきの引き換え条件についても念を押しておく。
「スニッチの約束も守ってよね」
父さんが二つ目の溜息をついた。
その横で、母さんが鼻歌を歌いながら、さっき出したばかりの缶ビールを冷蔵庫に戻しに行った。
流し目プリンスの人気を僕は完全に舐めていた。
上演二十分前についたとき、健康ランドの宴会場は、ほぼ満席。なんとか確保できたテーブルも、熟年夫婦と相席だった。
畦道源五郎一座のステージは、想像以上に華やかだった。でも、そう思えたのは、幕が上がってせいぜい五分ほど。流し目プリンスが登場し、客席に流し目を送った途端、おばさんたちが悲鳴にも近い歓声をあげて舞台の前に駆け寄ったのだ。そのせいでステージが見えなくなってしまった。
女形の動きを観察するため、どうにかステージに近づこうとしたけれど、ビクともしない。でかいお尻やぶっとい二の腕に阻まれ、プリンスはおろか芝居の鑑賞もままならなかった。
せっかく来たのに、このままでは無駄足になってしまう。
ステージが終了し、父さんと母さんのいるテーブルに戻ろうとしたとき、帰り支度をするおばさんたちの声が、耳に入ってきた。
「プリンスは、このあと九時からラジオの生出演があって、すぐ出ちゃうからね」
「いい場所とって出待ちに備えないと。急がなくちゃ」
「いつでも写真撮れるように、携帯はカメラモードにしといたほうがいいわよ」
どうやらおばさんたちは、健康ランドを出るプリンスを外で待ち受けるらしい。それを「出待ち」と呼ぶみたいだ。
あっ……おばさんたちのやりとりを聞いて、閃いた。
プリンスを出待ちして、どうやったら女形を上手に演じられるか直接聞いちゃおう。一か八か、当たって砕けろだ。
父さんと母さんに出待ちすることを伝え正面玄関へ向かうと、既におばさん軍団が陣取っていた。二十人近くいる。このままでは、さっきと同じ状況になりかねない。接近できずに終わってしまう。
いったん冷静になって考えよう。
下町の流し目プリンスは、下町をウリにしているだけあって情にあついはず。ファンを無下には扱わないだろう。だとすれば、必ずファンの前を通って車に乗り込むに違いない。じゃあ、どの車だ。見渡すと、車道に一台のタクシーが停まっていた。
あれかな? タクシーのところに行って助手席の窓を軽く叩いた。
窓が静かに下がり、運転手のオジサンが「なんだい」と聞いてくる。
「すみません。プリンスのタクシーは、この車でいいんですか?」
「そうだけど、君は?」
正直に身分を明かしたら、追い払われるに決まってる。なんて説明しよう。そのとき、玄関のほうで、おばさん軍団の黄色い声援があがった。プリンスが出てきたようだ。
時間がない。咄嗟にデマカセが口をついた。
「えっと、僕、源五郎一座の子役で、ラジオ局まで一緒に行くことになりまして」
「それなら、先に乗って待ってればいい」
運転手は疑いもせず、後部座席のドアを開けてくれた。乗り込んで座席の奥に座ったら、心臓がバクバク言い出した。もう、後戻りはできない。
少しして、さっき僕が乗り込んだ後部座席のドアがあいた。半分ほど開いた隙間から、ジーンズのお尻が覗いている。プリンスのお尻だ。
「いつも応援ありがとうございます。明日もやりますので、是非、足をお運び下さい」
色めき立つファンへの挨拶をすませ、プリンスが乗り込んできた。シートベルトをしながら運転手に行き先を告げる。
「赤坂のTVSまでお願いします」
タクシーが滑り出すと、プリンスは「フゥ」と肩で息をしてから、シートに深く体を沈めた。
隣にいる僕の存在には、まだ気づいていないようで、ズボンのポケットからスマホを取り出し、いじり始めた。
緊張もあって、声を掛けるタイミングを逃した僕は、無言でプリンスを見つめることしかできない。
ほどなく、気配を察したのか、プリンスがふいにこっちを向いた。
「うわーーーっ!」
まるで、幽霊でも見たかのようなリアクション。
「なんだ、君はっ!?」
「細川悠太、小学六年生です」
「そうじゃなくて、なんでいるの?」
タクシーが、キーッとブレーキの音を響かせた。車を止めた運転手が、血相を変えて振り返る。
「君、源五郎一座の人じゃなかったのか?」
「ごめんなさい。ごめんなさい。どうしてもプリンスさんと話したくて」
懸命に謝る僕をよそに、運転手が帽子をとってプリンスに頭を下げる。
「ちゃんと確認せずに関係ない子を乗せてしまい申しわけありませんでした。一座の子役だと言ったのを鵜呑みにしてしまいまして。どう致しましょうか」
健康ランドを出て、既に五分ほど走っている。プリンスも困っているようだ。
険しい表情で僕の顔を見てから、チラリと腕時計に目をやった。
「ここで、この子だけ降ろすわけにもいかないし。とにかくラジオの生放送に遅れると困るんで先を急いでください」
思った通り、下町のプリンスは情にあつかった。
落ち着きを取り戻したプリンスが、今度は優しい顔で僕を見る。
「ちょっとビックリしたけど、こんな無茶するってことは、それなりワケがあるんだよね」
さすがプリンスだ。とんでもないハプニングに遭遇しながら、驚いたのは最初だけ。そこからは、慌てた様子などこれっぽっちもみせない。こういうのをタイゼンジジャクというのだろう。子供向け番組『にほんごではしゃご』でやっていた。
コーヒーゼリーに小さい容器のクリームをかけるように優しく促された僕は、チンドン屋をしていて、今度女形をやることを説明した。
「それで、プリンスさんに女形の動きを教えてもらいたいんです。お願いします」
「チンドン屋で女形か。面白そうだね」
口元に笑みを浮かべたプリンスは、手にしていたスマホをポケットにねじ込んだ。
「わかった。局に着くまでの間でよかったら、伝授してあげる」
爽やかな笑顔はイケメンそのもの。女形にしておくのが、惜しいくらいだ。二枚目路線でも十分通用するに違いない。
揺れるタクシーの後部座席で、女形のスペシャルレッスンが始まった。
「女形のポイントは五つ。それさえ押さえておけば大丈夫だから。その五つは、姿勢、歩き方、手の所作、表情、流し目だ。まずは、姿勢からやってみよう」
そう言うと、シートベルトを引っ張り出してゆとりをもたせ、背筋をピンと伸ばした。慌てて僕も、シートベルトをたるませプリンスのほうを向く。
「いいかい。肩甲骨を、背中の真ん中にグーっと寄せて両肩をさげる。こうすると撫で肩になって、女性っぽく見えるんだ」
言われた通りにやってみる。グイッと力いっぱい肩甲骨を合わせた。
「やりすぎ、やりすぎ。胸が前に出ちゃってる。寄せるときは、七割ぐらいの力かな。それで肩をスッと下げる」
もう一回やってみると、なるほど、確かに撫で肩になる。
「OK。次は歩き方。車の中だから手本を見せられないけど、歩くときは基本すり足。膝に習字紙を挟んで歩くと、上手くできるようになるから練習してみるといい」
膝に習字紙を挟んで、すり足の練習。忘れないよう頭の中で復唱する。
「今度は手の所作。大事なのは、手の平を絶対に見せないこと。見せていいのは、手の甲だけ。軽く握るようにして、なるべくなら着物の袖からも出さないように」
僕は、手術を始める外科医みたいに両手の甲を外側に向けた。そうやってみて、ひとつ気になることが。
「太鼓のバチを握らないといけないんですけど」
「太鼓か。そしたらバチを握るときは、フォークとナイフを持つようにしたらどうだろう。ステーキを食べるように、太鼓を打つ」
プリンスが、エアステーキ食べをその場でやってみせてくれた。隣で僕も見よう見まねでやってみる。
これはいい。ナイフとフォークを持つようにすれば、手の甲しか見えないうえ、軽く握った感じになる。
レッスンはどんどん進んでいく。
「表情の作り方は、意外と簡単。口を半開きにするだけで色っぽく見えるから。実はこれ、桜沢富美男さんに教わったんだ」
これは、すぐにできそうだ。口を半分ほどあけて聞いてみた。
「ほうへふか?」
「もうちょっと、閉じてもいいかな」
「ほほふらいへふか?」
「そう、そのくらい。バッチリ!」
口の形が崩れないうちに指先を縦に突っ込み、どのくらい開いているかを確認する。中指一本分だ。
運転手がバックミラー越しにチラチラと様子を窺ってくる。僕らのやりとりが気になるようだ。
女形の特訓は、なおも続く。
「で、流し目。ここぞというときにしかやらないスペシャルなやつを教えてあげる。本来は企業秘密だけど、君、一生懸命だから特別だよ」
プリンスが真っすぐ前を向いた。その姿勢で顔だけゆっくり僕の方に向けたあと、一拍おいて目が合った。
思わずドキッとしてしまう。これが噂の、おばさんたちをイチコロにする流し目か。
だけど、ちょっとおかしい。単刀直入に聞いてみる。
「流し目って、目だけ動かすはずなのに、顔も動かしてましたよね」
「そこに秘密があるんだ。もう一回、ゆっくりやるからよく見てて」
体操のお兄さんが幼い子供を相手にするように、わかりやすくやってくれた。
「目線を前に向けた状態で、こうして首だけを捻る。その間も目線は前。で、捻り切って顔を止めたら、一呼吸おいてスーッと目玉を動かすんだ。最初に顔を動かして、あとから目玉が追いかける感じかな」
もう一回やるよと、プリンスは同じように流し目を見せてくれた。これは教えてもらわないと、わからない。
早速、僕も挑戦する。
前を向いたまま、左にいるプリンスのほうに顔だけ捻って、あとから目玉で追っかける、と。
「ダメダメ。顔の動きに目もついてきちゃってる。そうだなぁ、最初に目標物を捉えておくとやりやすいかも。例えば、料金メーターを見ながらやってみようか」
前にある料金メーターに視線を定める。3420円。しまった。行きはプリンスが払ってくれたとしても、戻るときは自分持ちだ。こんな大金持ってない。
「やってごらん」
プリンスの声で我に返る。
今は料金より流し目だ。帰りのタクシー代なんて心配している場合ではない。
お金の心配を振り払い、料金メーターをジッと見る。そこから目を離さずに首を左に捻ったら、一呼吸おいて目玉をスーー。
「おぉ、できたじゃん! うん、なかなか魅惑的だった」
自分でも、手応えならぬ目応えがあった。イケるかも。
目的地のラジオ局に着くまで、時間の許す限りおさらいする。
加えてプリンスは、女形の心得まで教えてくれた。
「いいかい。女形は演じるのではなく、役に演じられるものだから」
そうアドバイスされたけど、サッパリ意味がわからない。詳しく聞こうとしたら、タクシーがラジオ局に到着してしまった。
運転手が玄関のロータリーに車をつける。料金は4200円。プリンスが、財布から一万円札を取り出した。
「運転手さん、これでお願いします。おつりでこの子を健康ランドまで送り届けてください。足りますよね?」
なんてカッコいいんだ。紳士すぎる。やはり、プリンスと呼ばれるだけのことはある。
運転手が一万円を受け取り、お札の皺を丁寧に伸ばした。
「承知しました。十分足ります」
「助かります。余ったら、運転手さんコーヒーでも買って下さい」
プリンスは「本番、頑張って」と僕に握手してくれ、颯爽と車を降りて行った。
バタンとドアが閉まる。窓越しに、プリンスの背中に深々と頭を下げた。
なんだかここのところ、気持ちを込めてお辞儀をする機会が多い。
ティッシュ配りの名人に。チンドンの長老に。流し目プリンスに。
叫び声が聞こえたのは、車が動き出したときだった。
プリンスが、こっちを見て何か言っている。運転手もそれに気づいたけれど、後続のタクシーに急かされて停まれないようだ。
慌ててシートの左側に移って、窓を開けた。
「……のノリが良くなるから、前の日は豚肉を食べるように。豚バラがおすすめだよ!」
手をメガホンにしたプリンスの姿が、どんどん小さくなっていく。
最初の部分こそ聞き損なったけど、「前の晩に豚バラを食べろ」と言っていたのは聞き取れた。その言葉から想像するに、豚肉でパワーをつければ本番でノリが良くなるということだろう。たぶん、ノリノリで演奏できると伝えたかったんだ。
車から見えなくなったプリンスに、もう一度頭を下げる。
閉館間際の健康ランドに戻ると、案の定、父さんと母さんにメチャクチャ叱られてしまった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
