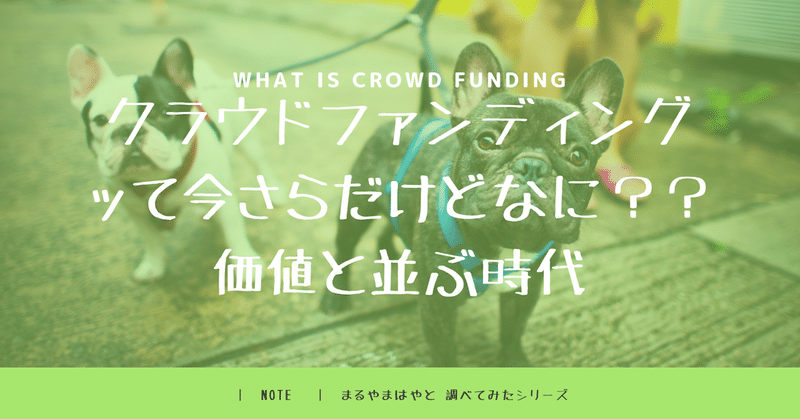
いまさら聞きにくいクラウドファンディングについてちょっと調べてみた
最近クラウドファンディングが浸透し、起業するための資金調達だけでなく、一般の人たちのプロジェクトが気軽にクラファンできるようになってきたとしみじみ実感しています。
自分の周りにもすでにクラファンを企画したことがあるというヒトが数名はいます。クラファンに支援したことがあるヒトはその倍以上います。クラウドファウンディングと間違えて覚えてたヒトも1名います。
そんな人の為にも『そもそもクラウドファンディング』ってなに?にフォーカスをあてて深掘りしてみました。
最近よく目にするクラウドファンディングのプラットフォームが
あッ!!ちなみにクラウドファンディングとは…
Crowd(群衆)×Funding(資金調達)の造語で、一般的には特定のプロジェクトの起案者がインターネット上で不特定多数からお金を集める仕組みのことを指します。2008年に融資型クラウドファンディング(ソーシャルレンディング)としてmaneo、2011年に購入型クラウドファンディングのReadyforが、日本国内で初めて登場し今日に至ります。
クラウドファンディングと一口に言っても融資型や購入型??という表記を見かけませんか。どんな違いがあるのか調べてみました。
クラウドファンディングには主に5つの種類があります。
▶︎寄付型
寄付型クラウドファンディングでは、通常の募金のように特にリターン(見返り)はありません。御礼のお手紙や支援者限定の活動報告などがあるプロジェクトは多く見かけます。
*寄附者は、寄附先より発行される領収書等必要な要件を揃え、確定申告を行うことで、税制優遇を受けることができます。
*プロジェクトの実行団体は、集まった資金を寄附として受け取ることができ、受け取った寄附金は課税の対象外となります。
▶︎購入型
購入型クラウドファンディングの仕組みは、リターンがモノ・サービスであることが大きな特徴です。事前予約型ECサイトに近いイメージだとわかりやすいかと思います。
プロジェクトでしか手に入らない限定品や特別なモノ・サービスを先行割引価格で購入することができることもあります。
購入型クラウドファンディングはさらに「All or Nothing方式」と「All-In方式」の2種類に分かれます。
● All or Nothing方式
募集期間内に目標金額に達しない場合はそれまで集まった金額を1円も受け取れません。
● All-In方式
募集期間内に目標金額に達しなくてもそれまでに集まった金額を受け取ることが出来ます。
どちらの方式もメリットデメリットがあるので、企画する際は担当者と相談しながら決めましょう。
*法人の場合、「法人税」の対象となります。個人の場合は、「所得税」の対象となります。また、出資額が リターンの内容に比べて高額な場合は、寄付金としての扱いとなり「贈与税」の対象となる場合があるので、注意が必要です。
▶︎融資型(ソーシャルレンディング)
融資型クラウドファンディングは、インターネット上で集めた資金をお金を借りたい企業へ事業者が融資を行い、その元本+金利を投資した方々に返済していく仕組みです。
従来融資を受ける選択肢は限られていましたが、2008年に国内初の融資型クラウドファンディングサービスmaeno(マネオ)が登場してから、新しい市場が形成され始めました。
▶︎ファンド投資型
ファンド投資型クラウドファンディングは特定の事業に対して投資を行い、融資ではなく投資に対する分配金という形でリターンが受け取れる仕組みです。
また分配金だけでなく、特典としてその事業で作られたモノ・サービスも受け取れることが多いのも特徴です。
▶︎株式投資型
株式投資といえば、東京証券取引所などに上場している企業の株を売買するようなイメージですが、株式投資型クラウドファンディングは、未上場企業の株に投資できる仕組みをいいます。
従来未上場企業への投資はベンチャーキャピタルや親族や知り合い、エンジェル投資家といった選択肢がありましたが、株式投資型クラウドファンディングの登場で、インターネット上で不特定多数の人から投資を受けることが可能になりました。日本では2017年4月から国内初の株式投資型クラウドファンディングサイトがリリースされています。
融資型やファンド投資型では直接的な金銭的リターンがありましたが、株式投資型では未上場企業の株を取得することになります。この株は将来IPOやM&Aによる買収といったときに初めて大きなリターンを得ることにつながります。
IPO前の場合、流動性はない場合が多く、簡単に他人へ売却することはできません。このことに十分注意して応援したい企業への投資を検討してください。
株式投資型の運営に必要な免許
2015年に金融商品取引法等の一部が改正され、第一種少額電子募集取扱業務が制定されました。これが株式投資型クラウドファンディングサイトを運営するのに必要な免許になります。この免許を持つ企業がまだ少ないので、今後参入する事業者が増えると予想はされます。しかし株を扱うので、参入するハードルは高いと思われます。
後半の融資や投資型になると一気に難しく見える部分が増えたかもしれません。しかし、既存のプラットフォームを利用して10万〜100万円規模のプロジェクトは無数に生まれてきています。それこそ学生でも主婦でも企画さえあれば作ることができます。
そのような手段があると言う選択肢を持っていることが重要ではないでしょうか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

